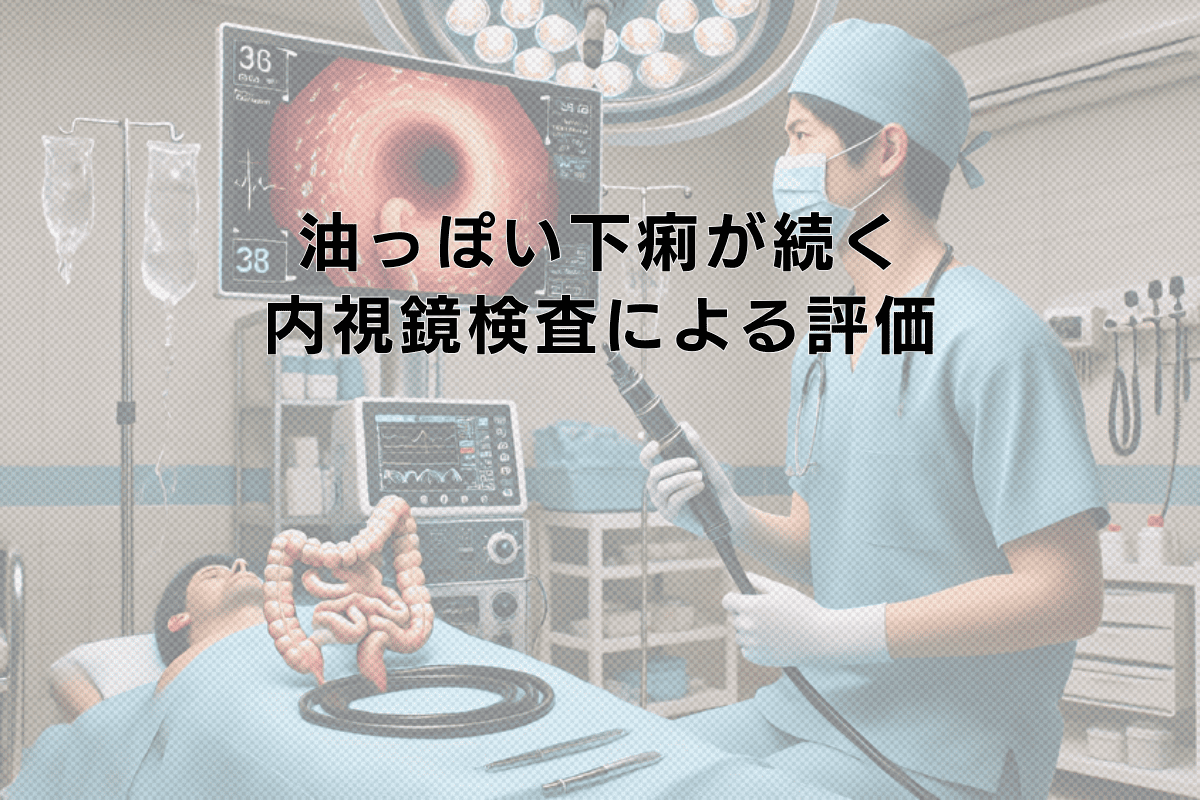便が白っぽく、水に浮き、油のようなものが浮いている、油っぽい下痢(脂肪便)が続く場合、食べたものの影響だけでなく、消化器系の疾患が隠れている可能性があります。
脂肪を消化・吸収する働きを持つ膵臓、肝臓、胆道、小腸などに何らかの問題が生じているサインかもしれません。
この記事では、油っぽい下痢がなぜ起こるのか、どのような場合に医療機関の受診を考えるべきか、そして診断に重要な役割を果たす消化管内視鏡検査について詳しく解説します。
油っぽい下痢とは何か
油っぽい下痢とは、便中に消化しきれなかった脂肪分が過剰に含まれた状態で、医学的には脂肪便と呼ばれ、体の不調を示す重要なサインの一つです。
単なる食べ過ぎとは異なる、特有の見た目や臭いを伴うことが多く、背景にはさまざまな原因が考えられます。
脂肪便の定義と見た目の特徴
脂肪便は、便中の脂肪量が一日あたり7グラムを超えた状態と定義され、健康な状態でも食事由来の脂肪がわずかに便に含まれますが、それを大幅に上回る量です。見た目には、いくつかの分かりやすい特徴が現れます。
まず、便の色が通常よりも白っぽく、淡黄色や銀色に見えることがあり、これは、正常な便の色を作る胆汁がうまく機能していない、あるいは便の通過が速すぎることが関係します。
また、便が水に浮きやすく、便器の水面に油滴が浮かぶこともあり、粘り気が強く、トイレの後に流しても便器にこびりついて取れにくいことも特徴です。臭いに関しても、通常の便とは異なる、酸っぱいような腐敗臭がすることがあります。
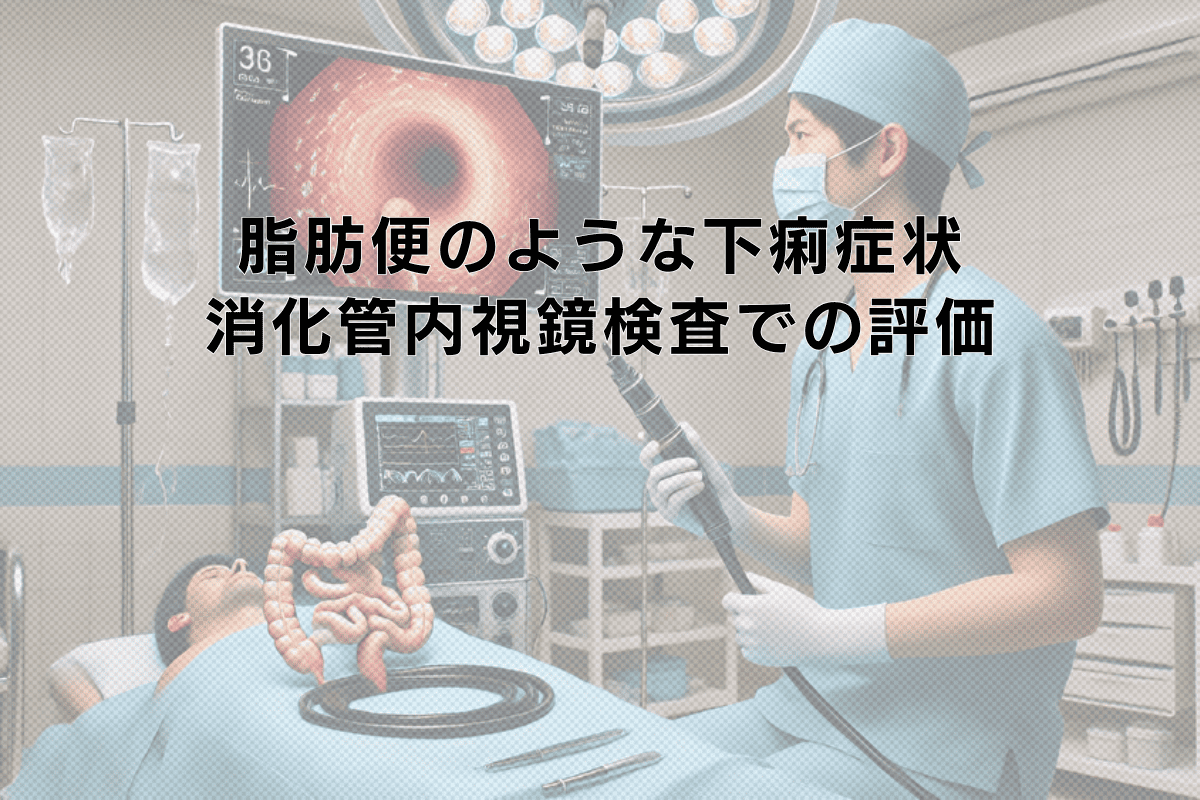
油っぽい下痢を引き起こす食事
特定の食事内容が、一時的に油っぽい下痢を起こすことがあり、脂肪分の多い食事を一度に大量に摂取した場合、消化能力が追いつかずに脂肪便が出ることがあります。
揚げ物、脂身の多い肉類、バターや生クリームをふんだんに使った料理などが該当し、また、一部の健康食品やサプリメント、あるいは特定の医薬品の副作用として、油っぽい便が出現することもあります。
食事性の原因は一過性であることがほとんどで、食事内容を見直すことで改善しますが、通常の食事を続けているにもかかわらず油っぽい下痢が続く場合は、消化器系の疾患を疑うことが必要です。
脂肪分の多い食事の例
| 食品カテゴリ | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 肉類 | 豚バラ肉、牛カルビ、霜降り肉 | 脂身の多い部位は消化に時間がかかります。 |
| 揚げ物 | 天ぷら、とんかつ、フライドポテト | 衣が油を多く吸収するため、脂肪量が多くなります。 |
| 乳製品・菓子類 | 生クリーム、バター、洋菓子 | 動物性脂肪が多く含まれる傾向にあります。 |
考えられる消化器系の疾患
油っぽい下痢が慢性的に続く場合、脂肪の消化や吸収に関わる臓器の疾患が背景にある可能性を考えます。
脂肪の消化には、膵臓から分泌される消化酵素(リパーゼ)と、肝臓で作られ胆嚢に蓄えられる胆汁が重要な役割を担い、分泌がうまくいかないと、脂肪は分解されません。
代表的な疾患として、膵臓の機能が低下する慢性膵炎や膵臓がん、胆汁の流れが悪くなる胆石症や胆管がんなどが挙げられます。さらに、分解された脂肪を吸収する小腸に問題がある場合も脂肪便の原因です。
クローン病やセリアック病といった小腸の粘膜に炎症や萎縮が起こる疾患では、吸収能力が著しく低下します。
疾患以外の原因
消化器系の明らかな疾患以外にも、油っぽい下痢を起こす要因はあり、過度なアルコール摂取は膵臓に負担をかけ、急性あるいは慢性の膵炎を誘発し、脂肪の消化不良を招くことがあります。
また、精神的なストレスが自律神経のバランスを乱し、消化管の運動機能や消化液の分泌に影響を与え、下痢の一因となることもあります。
年齢を重ねることによる消化機能の自然な低下も、下痢を悪化させる原因となることがあります。
生活習慣の見直しやストレス管理によって症状が改善することもありますが、脂肪便そのものの直接の原因ではありません。症状が続けば、生活ストレスへの対処だけで様子を見るのではなく、血液・便検査、腹部画像、内視鏡(必要に応じて生検)で原因をきちんと調べることが大切です。
なぜ油っぽい下痢が続くのか
油っぽい下痢が続く背景には、私たちが食べた脂肪をエネルギーとして体内に取り込むための、精巧な消化吸収の仕組みがうまく機能していない状態です。
この仕組みは、消化酵素、胆汁、小腸の三者が連携して成り立っていて、どれか一つでも働きが鈍ると、脂肪は体内に吸収されず、便として排出されてしまいます。
脂肪の消化吸収の仕組み
食物として摂取された脂肪(主に中性脂肪)は、胃を通過し、十二指腸に達し、消化の重要な段階が始まります。
まず、肝臓で作られた胆汁が脂肪を乳化させ、小さな粒子の集まりに変え、水と油が混ざりにくい性質を解消し、消化酵素が効率よく作用するための準備段階です。
次に、膵臓から分泌される消化酵素であるリパーゼが、乳化された脂肪を脂肪酸とモノグリセリドという、より小さな分子に分解します。
分解された脂肪酸とモノグリセリドが、小腸の粘膜から吸収され、体内でエネルギー源として利用されたり、貯蔵されたりします。
脂肪の消化に関わる主要な要素
| 要素 | 主な働き | 関連する臓器 |
|---|---|---|
| 胆汁(胆汁酸) | 脂肪を乳化させ、消化酵素が働きやすくする | 肝臓、胆嚢 |
| 消化酵素(リパーゼ) | 乳化された脂肪を分解する | 膵臓 |
| 小腸粘膜 | 分解された脂肪を吸収する | 小腸(主に十二指腸・空腸) |
消化酵素の不足
脂肪分解の主役であるリパーゼが不足すると、脂肪は分解されないまま小腸を通過してしまい、リパーゼを分泌する膵臓の機能が低下する疾患、慢性膵炎が代表的です。
慢性膵炎は、長期間にわたる膵臓の炎症により、膵臓の細胞が破壊され、硬くなっていく病気で、アルコールの過剰摂取が主な原因とされますが、原因不明のことも少なくありません。
病状が進行すると、消化酵素を十分に分泌できなくなり、脂肪だけでなくタンパク質の消化不良も起こし、油っぽい下痢や体重減少といった症状が現れます。
膵臓がんによって膵管が閉塞し、消化酵素の流れが妨げられることでも同様の症状が起こり得ます。
胆汁酸の役割と分泌異常
胆汁に含まれる胆汁酸は、脂肪を乳化させる、いわば洗剤のような役割を果たし、乳化作用がなければ、リパーゼは大きな脂肪の塊に効率よく作用することができません。
胆汁は肝臓で生成され、胆嚢で濃縮・貯蔵された後、食事の刺激に応じて十二指腸に放出されます。
胆汁の流れ道である胆道に、胆石が詰まったり、腫瘍ができたりすると、胆汁の分泌が滞ってしまい(胆汁うっ滞)、胆汁が不足すると、脂肪の乳化が不十分となり、消化不良を起こして脂肪便の原因となります。
黄疸(皮膚や白目が黄色くなる症状)を伴う場合は、特に胆道系の疾患を強く疑います。
胆汁分泌の異常をきたす疾患
| 疾患名 | 概要 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 胆石症 | 胆嚢や胆管に石ができる疾患 | 腹痛、発熱、黄疸 |
| 胆管がん・胆嚢がん | 胆道に発生する悪性腫瘍 | 黄疸、体重減少、腹痛 |
| 原発性胆汁性胆管炎 | 自己免疫により胆管が破壊される疾患 | 皮膚のかゆみ、黄疸、倦怠感 |
小腸の吸収能力の低下
消化酵素と胆汁によって脂肪が無事に分解されても、受け取る小腸の側に問題があれば、吸収は行われません。
小腸の粘膜は広大な表面積を持ち、栄養を吸収する役割を担っていますが、粘膜が炎症や萎縮によってダメージを受けると、吸収能力が著しく低下し、これを吸収不良症候群と呼びます。
クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患では、消化管の広範囲にわたる慢性的な炎症が栄養吸収を妨げ、また、セリアック病は、小麦などに含まれるグルテンに対する免疫反応によって小腸粘膜が傷つけられる疾患です。
このような疾患では、脂肪だけでなく、ビタミンやミネラルなど他の栄養素の吸収も障害されるため、栄養失調や貧血、骨粗しょう症などを合併することもあります。
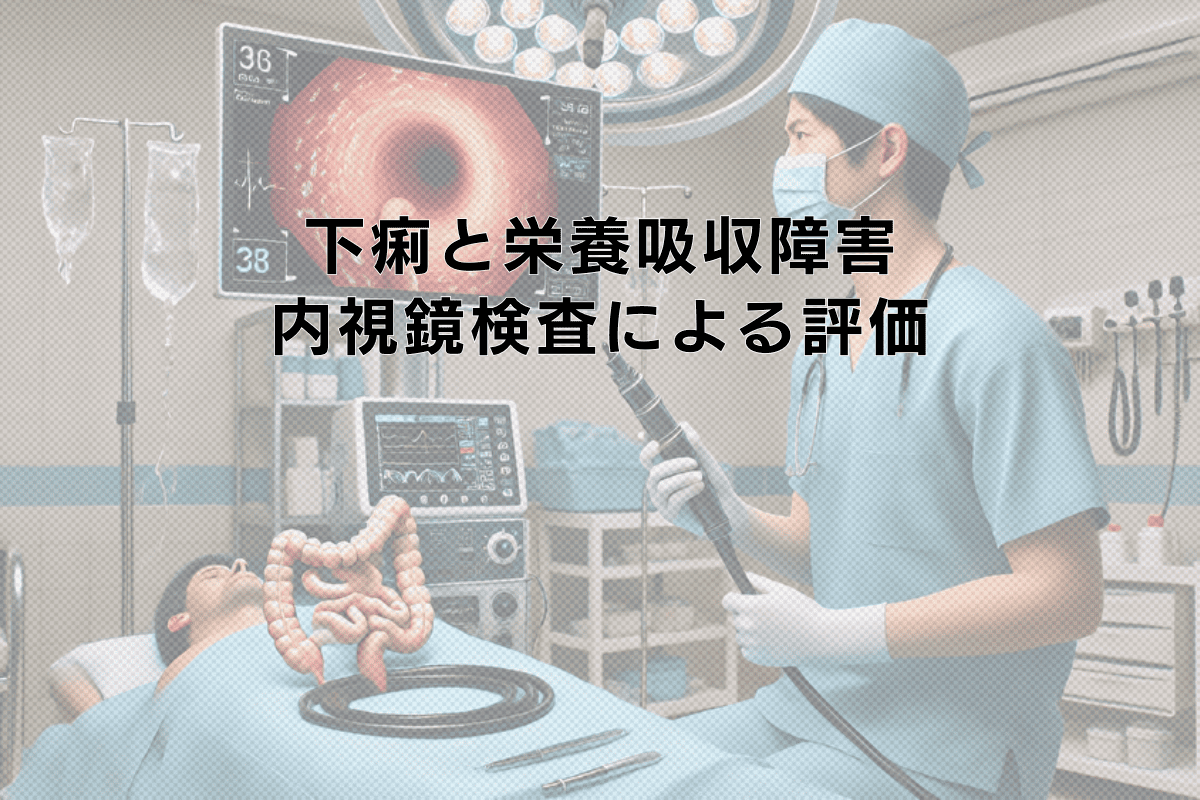
医療機関を受診するタイミング
油っぽい下痢がみられた場合、それが一時的なものなのか、あるいは何らかの疾患のサインなのかを見極めることが重要です。
他の症状を伴う場合や、長期間にわたって症状が続く場合は、自己判断で様子を見るのではなく、消化器内科などの専門医療機関を受診してください。
注意すべき随伴症状
油っぽい下痢に加えて、他の症状が現れている場合は、特に注意が必要です。強い腹痛や背中の痛みを伴う場合は膵炎の可能性を、発熱や悪寒を伴う場合は胆管炎などの感染症を考え、黄疸は、肝臓や胆道系の疾患を示唆する重要なサインです。
また、意図していないにもかかわらず体重が減少している場合は、栄養の吸収がうまくいっていない、あるいは背景に悪性腫瘍などが隠れている可能性も考慮しなくてはなりません。
食欲不振や吐き気、全身の倦怠感が続く場合も、単なる体調不良として片付けずに、専門家へ相談することが大切です。
油っぽい下痢とともに見られる危険なサイン
| 随伴症状 | 考えられる主な疾患 | 緊急性の目安 |
|---|---|---|
| 激しい腹痛・背部痛 | 急性膵炎、胆石発作 | 高い(速やかな受診が必要) |
| 黄疸(皮膚や白目が黄色い) | 胆道閉塞、肝機能障害 | 高い(速やかな受診が必要) |
| 急な体重減少 | 慢性膵炎、悪性腫瘍、吸収不良 | 中程度(早期の受診を推奨) |
| 発熱・悪寒 | 胆管炎、膵炎 | 高い(速やかな受診が必要) |
下痢が続く期間の目安
暴飲暴食など、原因がはっきりしている一過性の下痢であれば、通常は2〜3日で改善に向かいますが、原因に心当たりがないにもかかわらず、油っぽい下痢が1〜2週間以上続く場合は、慢性的な消化吸収不良が起きている可能性があります。
一度改善しても、脂肪分の多い食事を摂るたびに繰り返し症状が現れる場合も同様です。
期間の長さに加え、症状の頻度や程度も考慮に入れる必要があり、日常生活に支障をきたすほどの下痢が続く場合は、期間にかかわらず早めに医療機関に相談しましょう。
市販薬で改善しない場合
下痢止めなどの市販薬を服用しても、症状が全く改善しない、あるいは一時的に良くなってもすぐに再発するというケースは、注意を要します。
一般的な下痢止めは、腸の過剰な動きを抑えたり、腸内の水分バランスを整えたりする作用を持つものが主です。
しかし、油っぽい下痢の原因が消化酵素の不足や胆汁の分泌不全、小腸の吸収障害にある場合、市販薬では根本的な解決にはならず、原因疾患の発見を遅らせてしまう可能性もあります。
市販薬を数日間試しても効果が見られない場合は、使用を中止し、消化器内科を受診して原因を正確に突き止めることが重要です。
消化管内視鏡検査の重要性
油っぽい下痢の原因を調べる上で、消化管内視鏡検査、いわゆる胃カメラや大腸カメラは、非常に重要な役割を果たします。
内視鏡検査は、消化管の内部を直接目で見て観察できるため、他の画像検査では分からない粘膜の微細な変化を捉えることが可能です。
内視鏡検査で何がわかるのか
内視鏡検査では、食道、胃、十二指腸、そして大腸の全域にわたる粘膜の状態を、高解像度の映像でリアルタイムに観察します。
油っぽい下痢の原因として小腸の疾患が疑われる場合、特に十二指腸と終末回腸(大腸カメラで観察できる小腸の最後の部分)の観察が重要です。
得られる情報
- 粘膜の炎症(発赤、むくみ、ただれ)の有無と範囲
- 潰瘍やびらんの存在
- ポリープや腫瘍などの隆起した病変
- 粘膜の萎縮(粘膜が薄くなること)
- 血管の透見パターン(粘膜下の血管の様子)
所見を総合的に評価することで、炎症性腸疾患や吸収不良症候群、腫瘍性疾患などの診断に繋げます。
上部消化管内視鏡(胃カメラ)の役割
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は、口または鼻から細いスコープを挿入し、食道、胃、十二指腸を観察する検査で、油っぽい下痢の原因調査においては、十二指腸の観察が中心です。
十二指腸は、膵臓からの消化酵素と肝臓からの胆汁が流れ込む、脂肪消化の要となる場所で、胃カメラでは、胆汁の出口である十二指腸乳頭部を直接観察し、腫瘍や結石による閉塞がないかを確認できます。
また、セリアック病やクローン病などで見られる十二指腸粘膜の萎縮や炎症、潰瘍といった特徴的な所見を捉えることができ、疾患が疑われる場合、粘膜の一部を採取する組織生検を行います。
胃カメラで観察する主な部位
| 観察部位 | 確認する主なポイント | 関連する疾患 |
|---|---|---|
| 食道 | 炎症、潰瘍、腫瘍の有無 | 逆流性食道炎、食道がん |
| 胃 | 炎症、潰瘍、ポリープ、がんの有無 | 胃炎、胃潰瘍、胃がん |
| 十二指腸 | 粘膜の萎縮、炎症、潰瘍、乳頭部の異常 | セリアック病、クローン病、胆道・膵臓疾患 |
下部消化管内視鏡(大腸カメラ)の役割
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)は、肛門からスコープを挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体と、小腸の末端部分である終末回腸を観察します。油っぽい下痢の原因として、小腸広範囲にわたる疾患が疑われる場合に重要な検査です。
クローン病は、終末回腸に好発するため、大腸カメラによる観察が診断に欠かせず、特徴的な縦走潰瘍や敷石像といった所見を確認します。
また、炎症性腸疾患の一つである潰瘍性大腸炎は、主に大腸に炎症を起こす疾患ですが、下痢や腹痛といった症状が共通してみられるため、鑑別診断のために大腸全体の観察が必要です。
大腸がんやポリープなども下痢の原因となることがあり、これらの病変の有無も同時に確認します。
組織生検による確定診断
内視鏡検査の最大の利点の一つが、疑わしい病変があった場合に、その場で組織の一部を採取(生検)できることです。
採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査に提出され、炎症細胞の種類や配列、細胞の形状などを詳細に評価し、最終的な確定診断を下します。
セリアック病であれば特徴的な絨毛の萎縮とリンパ球の浸潤が、クローン病であれば非乾酪性類上皮細胞肉芽腫という所見が診断の決め手となります。
また、採取した組織が悪性(がん)か良性かを判断するためにも、組織生検は絶対に必要な検査です。見た目だけでは判断が難しい病変も、組織レベルで評価することで、正確な診断が可能になります。
内視鏡検査の準備と流れ
消化管内視鏡検査を安全かつ正確に行うためには、事前の準備がとても大切で、消化管の中を空にして、粘膜をきれいに観察できる状態にすることが必要です。
ここでは、胃カメラと大腸カメラに共通する準備と、それぞれの検査当日の大まかな流れについて解説します。
検査前の食事制限について
検査前日は、消化の良い食事を心がける必要があり、消化管に食物が残っていると、粘膜を詳細に観察することができず、小さな病変を見逃す原因となります。
特に大腸カメラの場合は、数日前から食事内容に注意を払うことが必要です。
検査前に避けるべき食品・推奨される食品
| 分類 | 避けるべき食品の例 | 推奨される食品の例 |
|---|---|---|
| 繊維の多いもの | きのこ類、海藻類、こんにゃく、ごぼう | 白米、うどん、食パン(耳なし)、豆腐 |
| 種のあるもの | いちご、キウイ、ごま、トマト | じゃがいも、バナナ、リンゴジュース |
| 脂肪の多いもの | 肉の脂身、揚げ物、ナッツ類 | 鶏ささみ、白身魚、卵 |
検査前日の夕食は、指定された時間(多くは午後9時頃)までに済ませ、その後は絶食となり、水やお茶などの水分は、指示された時間まで摂取可能です。
下剤の服用(大腸カメラの場合)
大腸カメラ検査では、大腸の中を完全に空にするため、検査当日に多量の下剤(腸管洗浄剤)を服用します。下剤の種類はいくつかありますが、一般的には約1.5リットルから2リットルの液体を、2時間ほどかけてゆっくりと飲みます。
下剤を飲み始めると、30分から1時間ほどで便意をもよおし、その後何度も排便があり、最終的に、便が固形物のない薄い黄色の液体になれば、腸内がきれいになったサインであり、検査の準備が完了です。
自宅で下剤を服用する場合がほとんどですが、不安な方や高齢の方のために、院内で服用できる体制を整えている医療機関もあります。
検査当日の流れ
胃カメラの場合、まず胃の中の泡を取り除く消泡剤を飲み、その後、喉や鼻に局所麻酔を行います。鎮静剤を使用する場合は、点滴のルートを確保し、検査自体は、通常10〜15分程度で終了です。
大腸カメラの場合も、鎮静剤を使用する際は点滴ルートを確保します。検査時間は、個人差がありますが、20〜30分程度が目安で、ポリープを切除するなどの処置を行う場合は、もう少し時間がかかります。
検査中は、医師がモニターで消化管の内部を観察しながら、必要に応じて送気して消化管を広げたり、体の向きを変えてもらったりします。
内視鏡検査で発見される主な疾患
油っぽい下痢を主訴とする患者さんに対して消化管内視鏡検査を行うと、原因となる様々な疾患が発見されることがあります。ここでは、脂肪の消化吸収不良に直結する代表的な疾患について、特徴と内視鏡所見を解説します。
慢性膵炎
慢性膵炎は、膵臓の長期にわたる炎症により、膵臓組織が硬化し、消化酵素を分泌する機能や血糖をコントロールするホルモン(インスリンなど)を分泌する機能が徐々に失われていく疾患です。
主な原因はアルコールの長期多量摂取ですが、胆石や遺伝、自己免疫などが関与することもあります。
初期には腹痛や背部痛を繰り返しますが、進行すると痛みが軽快する代わりに、消化吸収不良による油っぽい下痢や体重減少、さらには糖尿病を発症します。
内視鏡検査(特に超音波内視鏡)では、膵管の拡張や膵石の存在など、慢性膵炎に特徴的な所見を確認することができ、通常の胃カメラでは直接膵臓は見えませんが、膵臓の疾患が十二指腸に影響を及ぼしていないかなどを評価します。
胆道系の疾患
胆道は、肝臓で作られた胆汁を十二指腸まで運ぶ管の総称です。通り道に問題が生じると、脂肪の乳化に必要な胆汁が十分に分泌されず、油っぽい下痢を起こします。
胆石が胆管に詰まる総胆管結石症や、胆道に発生する胆管がん、胆嚢がんなどが原因となり、油っぽい下痢に加えて、黄疸や右上腹部痛、発熱などを伴うことが多いのが特徴です。
上部消化管内視鏡検査では、胆汁の出口である十二指腸乳頭部を観察し、腫れや変形、結石の嵌頓(かんとん)がないかを確認します。
さらに特殊な内視鏡を用いた超音波内視鏡検査(EUS)や内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を行うことで、胆道内部をより詳細に評価し、診断や治療を行います。
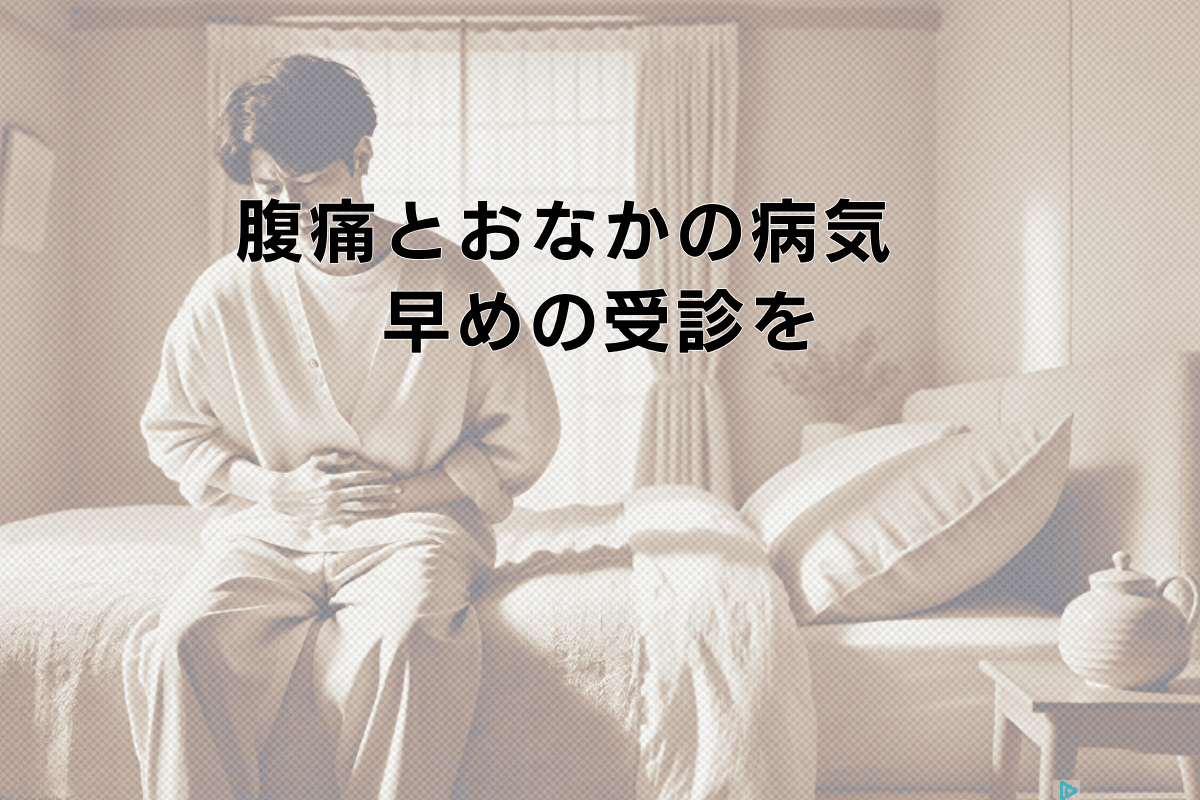
吸収不良症候群(セリアック病など)
吸収不良症候群は、消化された栄養素が小腸から適切に吸収されなくなる状態の総称で、様々な原因疾患を含みます。
その一つであるセリアック病は、小麦や大麦などに含まれるタンパク質であるグルテンに対する免疫系の異常反応が原因で、小腸の粘膜に炎症が起こり、栄養を吸収する絨毛が萎縮してしまう自己免疫疾患です。
油っぽい下痢のほか、腹部膨満感、体重減少、貧血、倦怠感など多彩な症状を呈します。上部消化管内視鏡検査では、十二指腸に見られる特徴的な粘膜の変化(絨毛の萎縮、ひだの消失、モザイク模様など)を観察します。
診断を確定するためには、十二指腸粘膜の一部を採取し、病理組織検査で絨毛の萎縮を確認することが重要です。
セリアック病の主な症状
- 慢性的な下痢(特に脂肪便)
- 体重減少、成長障害(小児)
- 腹部膨満感、腹痛
- 鉄欠乏性貧血
- 骨粗しょう症、骨折
炎症性腸疾患(クローン病など)
炎症性腸疾患(IBD)は、消化管に原因不明の慢性的な炎症を起こす疾患の総称で、主にクローン病と潰瘍性大腸炎に分けられます。
特にクローン病は、口から肛門までの消化管のあらゆる部位に炎症を起こす可能性があり、小腸に病変の主座を置くことが多いです。
小腸の広範囲に炎症が及ぶと、栄養の吸収が著しく障害され、油っぽい下痢や体重減少、発熱、腹痛などの症状が現れます。
大腸内視鏡検査では、クローン病に特徴的な縦走潰瘍(腸の縦方向に走る長い潰瘍)や敷石像(潰瘍に囲まれた粘膜が盛り上がって見える状態)、肛門病変などを確認します。
内視鏡検査以外の評価方法
油っぽい下痢の原因を突き止めるためには、内視鏡検査が中心的な役割を果たしますが、診断の精度を高め、全身の状態を把握するために他の検査も組み合わせて行います。
血液検査
血液検査は、体内の炎症の有無、栄養状態、肝臓や膵臓といった特定の臓器の機能を手軽に評価できる基本的な検査です。白血球数やCRP(C反応性タンパク)の値からは、体内の炎症の程度を知ることができます。
貧血の有無や、タンパク質(アルブミン)、コレステロール、ビタミン、ミネラルの値を調べることで、栄養素の吸収がどの程度障害されているかを評価します。
また、アミラーゼやリパーゼといった膵臓由来の酵素の値を測定することで膵炎の有無を、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ビリルビンなどの値を測定することで肝臓や胆道系の機能障害がないかを調べます。
血液検査で評価する主な項目
| 検査項目 | 何がわかるか | 異常値が示唆する疾患例 |
|---|---|---|
| アミラーゼ、リパーゼ | 膵臓の炎症・障害の程度 | 急性膵炎、慢性膵炎の増悪 |
| AST、ALT、γ-GTP | 肝臓・胆道系の障害の程度 | 肝炎、胆汁うっ滞 |
| アルブミン、総蛋白 | 栄養状態、吸収不良の有無 | 吸収不良症候群、炎症性腸疾患 |
腹部超音波(エコー)検査
腹部超音波検査は、体の表面から超音波を当て反響を画像化し、お腹の中の臓器の状態を観察する検査で、放射線被ばくの心配がなく、患者さんの体への負担が少ないです。
肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓などの実質臓器の観察に優れ、油っぽい下痢の原因検索においては、胆嚢内の胆石やポリープの有無、総胆管の拡張、膵臓の腫れや膵管の拡張、腹水の有無などを評価します。
慢性膵炎でみられる膵臓の萎縮や石灰化なども描出することが可能で、消化管ガスの影響で観察しにくい場合もありますが、多くの情報を得られる有用なスクリーニング検査です。
CTやMRIなどの画像検査
CT(コンピュータ断層撮影)検査やMRI(磁気共鳴画像)検査は、体の断面を詳細に画像化する検査です。
超音波検査よりも客観的で詳細な情報を得ることができ、膵臓や胆道、肝臓などの位置関係や病変の広がりを立体的に把握するのに優れています。
CT検査は短時間で広範囲を撮影でき、急性期の病変の評価に適していて、造影剤を使用することで、血流の状態や腫瘍の性質についてもある程度評価できます。
MRI検査(特にMRCPという胆管・膵管を描出する特殊な撮影法)は、放射線被ばくがなく、胆管や膵管の狭窄や拡張、結石などを非常に鮮明に描出することが可能です。
便検査
便潜血検査は、便に血液が混じっているかどうかを調べる検査で、消化管からの出血の有無を確認し、炎症性腸疾患や大腸がんなどのスクリーニングに用いられます。
また、便中のカルプロテクチンという物質を測定する検査は、腸管の炎症の程度を客観的に評価するのに役立ち、特に炎症性腸疾患の活動性評価に有用です。
油っぽい下痢が主訴の場合、便中の脂肪量を直接測定する検査(便中脂肪染色など)を行うこともあり、脂肪便であることを客観的に証明できます。さらに、細菌やウイルスなどの感染が疑われる場合は、便の培養検査や抗原検査なども行います。
便検査の種類と目的
| 検査名 | 目的 | 対象となる主な疾患 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 消化管出血の有無を確認する | 大腸がん、炎症性腸疾患 |
| 便中カルプロテクチン | 腸管の炎症の程度を評価する | 炎症性腸疾患 |
| 便中脂肪染色 | 便中の脂肪の量を評価する | 脂肪便(吸収不良症候群) |
よくある質問
油っぽい下痢や消化管内視鏡検査について、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 油っぽい下痢は自然に治りますか
-
脂肪分の多い食事による一時的なものであれば、食事内容を見直すことで自然に改善することがほとんどです。
しかし、消化器系の疾患が原因である場合、自然に治ることは難しく、放置することで病状が進行してしまう可能性があります。
腹痛や体重減少などの他の症状を伴う場合や、症状が2週間以上続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。
- 内視鏡検査は痛いですか
-
苦痛を伴う場合がありますが、様々な工夫で軽減できます。胃カメラでは、喉の麻酔をしっかり行うことで嘔吐反射を抑え、また、鼻から挿入する経鼻内視鏡は、舌の付け根に触れにくいため、吐き気が少ないとされています。
大腸カメラでは、お腹の張りを軽減するために炭酸ガスを使用したり、スコープの挿入方法を工夫したりします。
さらに、多くの医療機関では、鎮静剤(静脈麻酔)を使用して、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることが可能です。
- 検査にかかる時間はどのくらいですか
-
検査自体の時間はそれほど長くありません。上部消化管内視鏡(胃カメラ)の検査時間は、観察のみであれば通常10分から15分程度で、下部消化管内視鏡(大腸カメラ)は、個人差がありますが、20分から30分程度が目安です。
ただし、ポリープの切除など、検査中に処置を行った場合は、その分時間が長くなります。
また、検査前の準備や、検査後の休憩(特に鎮静剤を使用した場合)を含めると、院内での滞在時間は2時間から3時間程度を見込むのが一般的です。
- 検査後に気をつけることはありますか
-
いくつか注意点があり、まず、鎮静剤を使用した場合は、検査当日は車やバイク、自転車の運転はできません。ふらつきが残ることがあるため、安全に帰宅できるよう付き添いや公共交通機関の利用を検討してください。
食事については、胃カメラの場合は喉の麻酔が切れるまで1時間程度、大腸カメラの場合はお腹の張りが落ち着いてから摂取可能です。
組織生検やポリープ切除を行った場合は、数日間はアルコールや香辛料などの刺激物を避けるなど、食事制限が必要になることがあります。
次に読むことをお勧めする記事
【脂肪便と下痢が続くときの検査と治療方針】
脂肪便の原因は膵・胆道・小腸など多岐にわたります。『結局どの検査から?』という疑問に、血液・便・画像・内視鏡の流れで具体的に答えています。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
油っぽい下痢の原因を調べる内視鏡検査について理解したら、次は実際の検査準備について知っておくと安心です。特に大腸カメラ検査を予定されている方に役立つ、具体的な準備方法を詳しく解説しています。
以上
参考文献
Nakamura T, Takebe K, Kudoh K, Ishii M, Imamura KI, Kikuchi H, Kasai F, Tandoh Y, Yamada N, Arai Y, Terada A. Steatorrhea in Japanese patients with chronic pancreatitis. Journal of gastroenterology. 1995 Jan;30(1):79-83.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Tazume S, Ozawa A, Yamamoto T, Takahashi Y, Takeshi K, Saidi SM, Ichoroh CG, Waiyaki PG. Ecological study on the intestinal bacterial flora of patients with diarrhea. Clinical infectious diseases. 1993 Mar 1;16(Supplement_2):S77-82.
Corinaldesi R, Stanghellini V, Barbara G, Tomassetti P, De Giorgio R. Clinical approach to diarrhea. Internal and emergency medicine. 2012 Oct;7(Suppl 3):255-62.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.
Binder HJ. Role of colonic short-chain fatty acid transport in diarrhea. Annual review of physiology. 2010 Mar 17;72(1):297-313.
Soong DS, Thompson JB, Poley JR, Hess R. Hydroxy fatty acids in human diarrhea. Gastroenterology. 1972 Nov 1;63(5):748-57.
Fine KD, Fordtran JS. The effect of diarrhea on fecal fat excretion. Gastroenterology. 1992 Jun 1;102(6):1936-9.
Headstrom PD, Surawicz CM. Chronic diarrhea. Clinical Gastroenterology and hepatology. 2005 Aug 1;3(8):734-7.
Kasper H. Faecal fat excretion, diarrhea, and subjective complaints with highly dosed oral fat intake. Digestion. 1970 Jun 1;3(6):321-30.