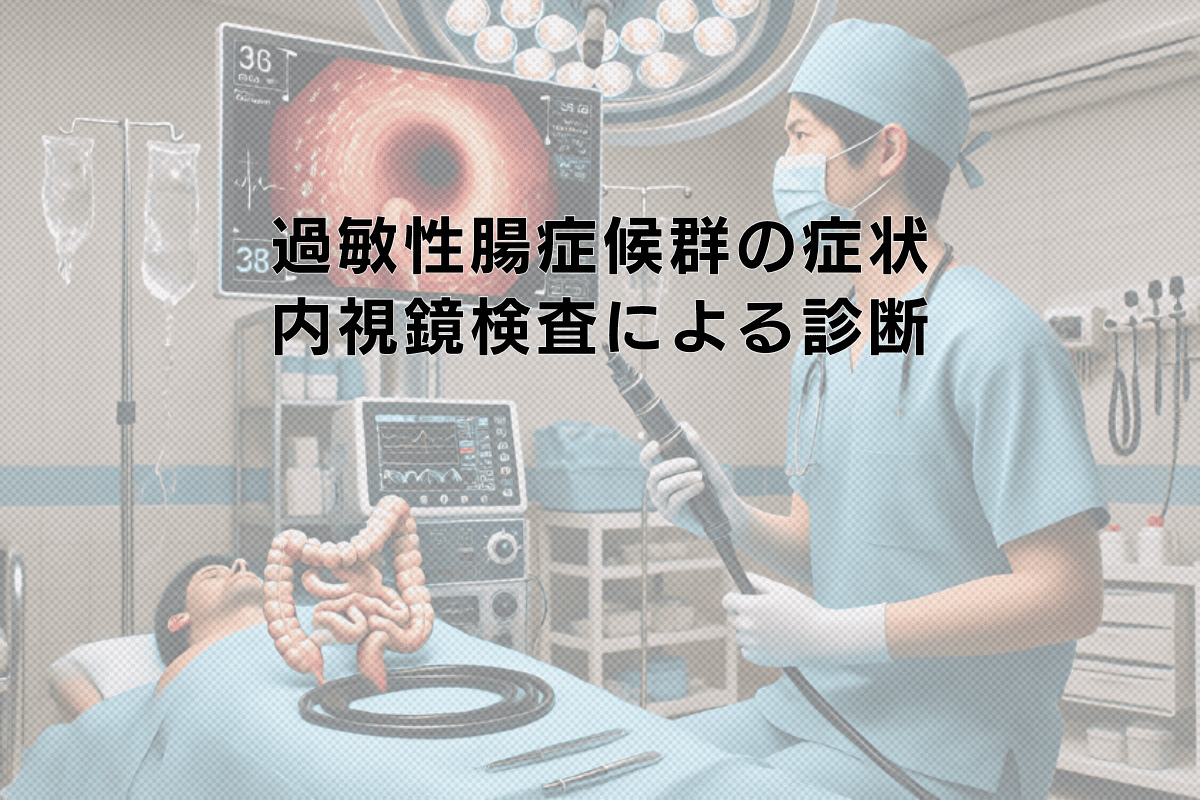いわゆる「過敏性腸症候群」による強い下痢症状をきっかけに、日常生活の質が低下したと感じる方は多いでしょう。出勤や通学などが難しくなり、周囲に相談するのも気が引けるケースも少なくありません。
しかし自己判断のみで対策を続けると、重大な疾患を見逃す可能性があり、大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査による早期の総合的な評価が重要です。
本記事では下痢が中心となる過敏性腸症候群の特徴や、適切な内視鏡検査の受け方、検査後に意識したい日常生活のポイントなどを詳しく解説します。
過敏性腸症候群とは何か
日常的にお腹の調子が悪く、強い痛みや便通異常に悩む方の中には、過敏性腸症候群(IBS)が疑われる場合があり、下痢や便秘の繰り返しが続くことで外出が難しくなり、精神的負担が大きくなることもあります。
IBSが疑われる症状
過敏性腸症候群は腸の機能的な異常が原因とされ、器質的な損傷がないにもかかわらず便通異常が続く点が特徴です。腫瘍や炎症などが見つからないにもかかわらず、以下のような便通の乱れと関連症状が長期化します。
- 下腹部の痛みまたは不快感が続き、排便によって軽減したり、逆に増強したりする
- 慢性的な便秘または下痢が続き、身体的・精神的ストレスに伴って悪化しやすい
- お腹が張る、ガスが溜まったような感覚があり、不規則な食事やストレスで症状が変動する
- トイレの回数や便の性状(固形〜軟便)の変化が顕著で、外出時に強い不安を感じる
下痢が中心となるタイプ
慢性的に緩い便や水様便が続くタイプを指します。過敏性腸症候群の下痢症状が主となる場合、下痢型と呼ばれます。
食事をするとすぐに便意を催したり、ストレスがかかると突発的に腹痛と下痢が生じたりするため、仕事や外出に支障をきたしやすいです。
便秘が中心となるタイプ
排便回数が極端に少なく、硬い便が続く状態です。腸内ガスや膨満感などによる腹部の不快感が強く、便秘からくる下腹部の痛みが慢性化する場合もあります。下痢型と混同されにくいように、しっかりとした診断が必要です。
混合型
下痢と便秘が交互に出現するパターンを指し、排便のタイミングや便の性状が一定しないため、日常生活の予測が難しくなり、心身のストレスが強まる方も多いです。
過敏性腸症候群のタイプと主な症状
| タイプ | 便の特徴 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 下痢が中心 | 水様便や軟便が多い | 食後すぐの便意、急な腹痛と下痢 |
| 便秘が中心 | 硬い便が多く排便回数が少ない | 腹部膨満感、慢性的な便秘による痛み |
| 混合型 | 下痢と便秘が交互に現れる | 症状の予測が難しく、ストレスがかかりやすい |
早期の段階で医学的に評価し、必要に応じて大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査を検討すると安心につながります。
下痢が主症状の背景
過敏性腸症候群の下痢型に当てはまりそうな症状を持つ方は、単に腸が弱いと考えがちですが、実際には様々な要因が複雑に絡み合って下痢症状を起こしています。腸内環境から心理的ストレスまで、幅広い視点で理解することが大切です。
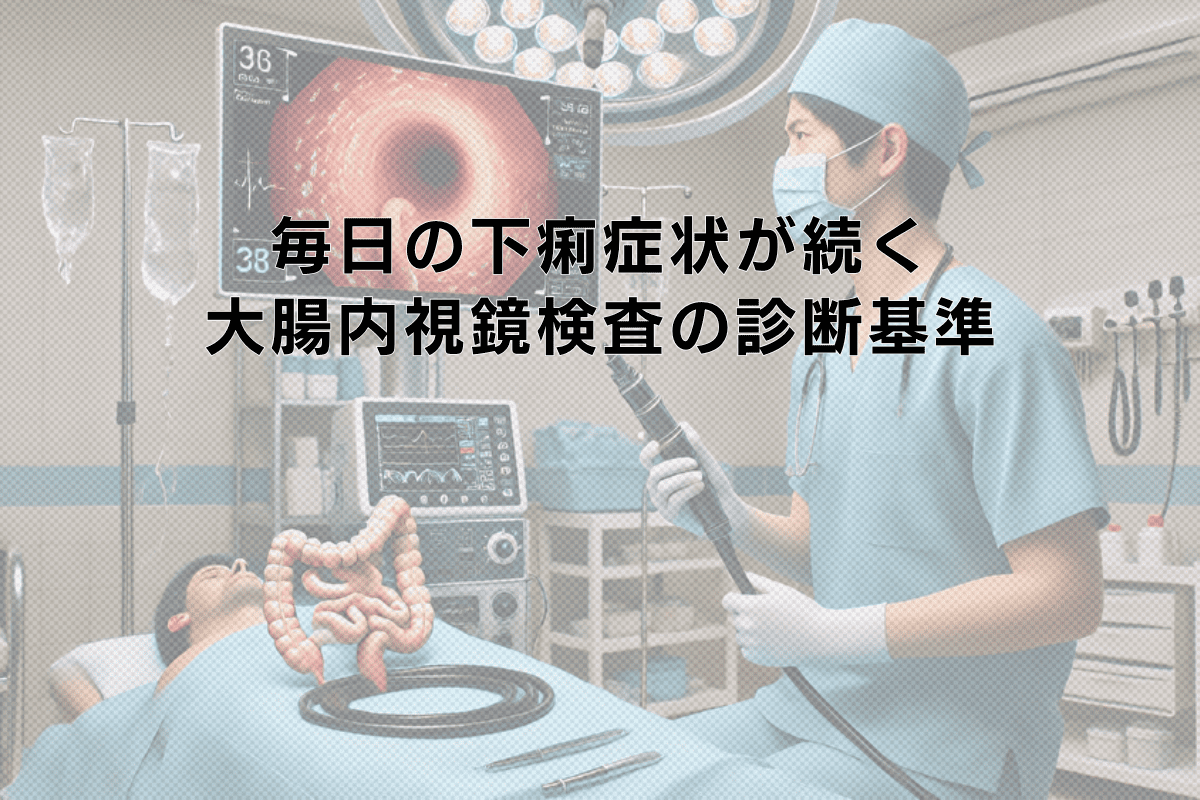
ストレスと自律神経の関係
精神的な緊張状態が続くと、自律神経が乱れやすくなります。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、腸の運動や分泌をコントロールする大切な役割を担っていて、過敏性腸症候群の下痢型では交感神経が過度に優位になり、腸のぜん動運動が過剰に活発になることで下痢が起こりやすくなります。
食生活との関連
刺激物の多い食事や偏りがある食事が腸の状態を不安定にさせることがあり、香辛料やカフェインの過剰摂取、脂っこい食事を頻繁に摂る習慣は、腸に負担をかけて下痢を誘発しやすくします。
また、早食いや不規則な食事時間も腸の負担を増やす原因になりがちです。
細菌バランスと腸内環境
腸内には多数の細菌が存在し、善玉菌と悪玉菌のバランスが健康を左右し、このバランスが乱れると、便がゆるくなる原因となる場合があります。
急性胃腸炎などの病後や抗生物質の服用後に善玉菌が減少し、悪玉菌の割合が増えると下痢型の症状が続くことがあります。
慢性的な下痢が身体に与える影響
慢性的な下痢は栄養吸収を妨げ、体力の低下や貧血につながりやすいです。
頻繁に水分が失われることで脱水状態になり、集中力の低下や疲労感が強まる可能性があり、こうした状態が長く続くと精神的にも悪影響を及ぼしやすく、負のスパイラルに陥ることが考えられます。
下痢の主な原因と関連要素
| 原因・要因 | 具体的な影響 | 見直すポイント |
|---|---|---|
| ストレス | 自律神経の乱れによる腸の過剰運動 | リラックス法、ストレス発散方法 |
| 食生活の偏り | 消化を乱し、腸内に負担をかける | 栄養バランス、調理法 |
| 腸内細菌のバランス | 善玉菌が減少し悪玉菌が優位になる | プロバイオティクスの摂取検討 |
| 脱水・栄養不足 | 長期の下痢で電解質やエネルギーが不足する | 十分な水分補給、補食の工夫 |
無理な我慢や一時的な薬の服用だけに頼らず、下痢が持続する背景を総合的に捉えることが必要です。
- 交感神経と副交感神経のバランスを整える生活習慣を意識する
- 腸内環境を良好に保つ食事(発酵食品・食物繊維など)を取り入れる
- 水分や電解質を意識して補給し、脱水症状を防ぐ
- 下痢が慢性化している場合は医療機関の受診を検討する
下痢症状を生活習慣の乱れや体質だけの問題と判断するのは危険です。大腸カメラなどで腸の状態を直接確認することが必要なケースもあるため、放置せずに適切な検査を視野に入れてください。
内視鏡検査の必要性
過敏性腸症候群の下痢型と思われる症状があるからといって、必ずしもIBSのみが原因とは限らず、腸の病気には多種多様なものがあり、中には大きなリスクを伴う疾患も含まれます。
そこで自覚症状だけで判断せず、内視鏡検査によって正しく評価することが重要です。
大腸カメラ検査の意義
大腸カメラ検査(下部消化管内視鏡検査)は大腸内部を直接観察し、炎症やポリープ、腫瘍などの有無を確認できます。
カメラによるリアルタイムの観察なので、病変があればすぐに把握し、必要に応じて組織検査(生検)も行える点が大きな特徴です。
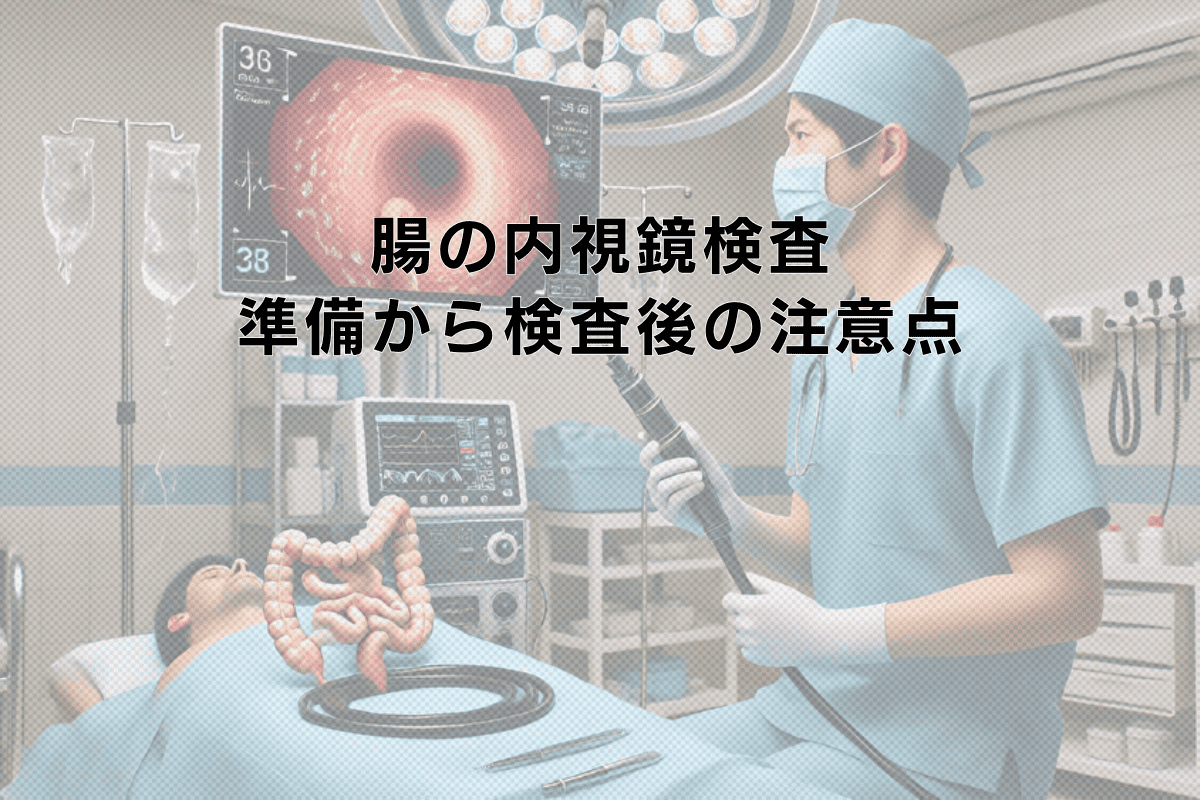
大腸カメラで見つかる主な異常
| 異常の種類 | 内容 | 早期発見の利点 |
|---|---|---|
| ポリープ | 良性から悪性へ移行する可能性がある | 場合によっては検査中に切除が可能 |
| 大腸がん | 進行度に応じて治療法が変わる | 早期治療による生存率向上 |
| 潰瘍性大腸炎 | 大腸粘膜の炎症や潰瘍が特徴 | 適切な薬物療法による症状緩和 |
| クローン病 | 全消化管にわたる炎症を伴うことがある | 病状の把握と合併症の予防 |
過敏性腸症候群の下痢型と思って放置していたら、実はポリープや悪性腫瘍など重大な病気が潜んでいたという例もあり、異常が見つかれば早い段階で対応できるので、大腸カメラ検査には大きな意味があります。
胃カメラとの併用が考えられるケース
下痢症状が中心でも、上部消化管に問題が隠れていることもあり得るため、食道や胃、十二指腸の粘膜異常が原因で、腸の運動に影響を与える場合もあります。
特に胃痛や胸やけなどの症状が同時にある方は、胃カメラ検査との併用を検討すると全消化管の状態を包括的に把握することが可能です。
ポリープや腫瘍の早期発見
大腸カメラは見た目では分かりづらいポリープや初期の腫瘍を見つける最良の方法のひとつで、小さなポリープでも、長い年月をかけて悪性化していく恐れがあるため、発見時点での切除が推奨されるケースもあります。
早期に切除すれば、大きくなる前に取り除ける可能性が高いです。
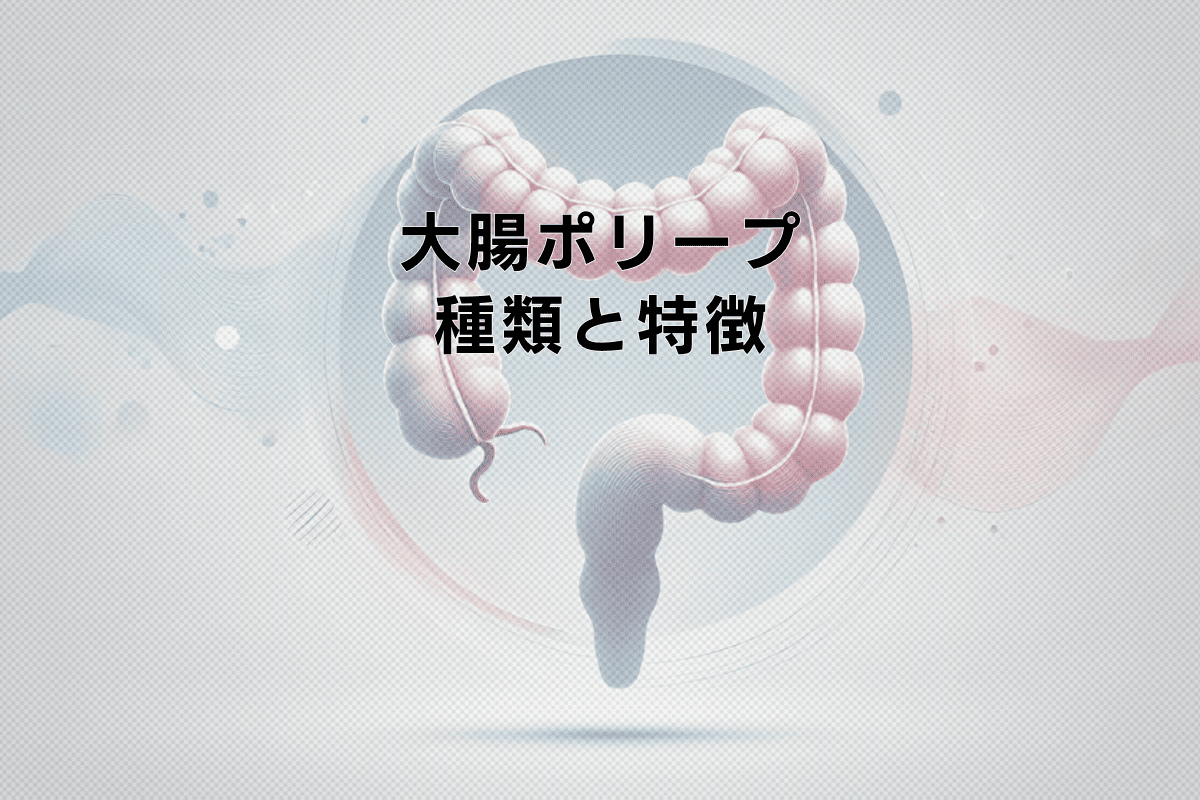
悪性疾患の見落とし防止
下痢や腹痛は、大腸がんやその他の悪性疾患でも起こる症状です。
血便が混じる、体重が急激に減少するなどの特徴的な症状が出る場合もあれば、IBSと似た経過をたどるケースもあるので、内視鏡検査を受けることで、悪性疾患の見落としを防ぎ、安心して治療方針を決めることにつながります。
- 食事やストレスだけで下痢が続くとは限らない
- 便に血が混じる、強い痛みがある場合は特に注意が必要
- 症状を軽視せず、内視鏡検査で大腸内部を直接確認しておく
- 定期的な大腸カメラによるチェックを習慣化すると早期発見の機会が増える
慢性的な下痢がある方ほど、腸内を視覚的に確認して原因を究明する作業が重要です。
内視鏡検査の受診を考えるタイミング
過敏性腸症候群の疑いがある方であっても、どのタイミングで内視鏡検査を受ければ良いのか迷う方は多いかもしれません。症状の種類や持続期間、年齢、家族歴などが判断材料になります。
症状の持続期間
一時的な下痢であれば、腸炎や食あたりの可能性がありますが、数週間〜数か月単位で下痢が続き、改善と悪化を繰り返している場合は内視鏡検査を検討するべきです。特に半年以上にわたって症状が続く場合は見逃せないサインになります。
症状持続期間の目安と受診のヒント
| 持続期間 | 可能性のある状態 | 推奨される対応 |
|---|---|---|
| 数日〜1週間程度 | 単なる腸炎や軽度の感染症などの一過性 | 水分補給や安静で経過観察 |
| 1か月前後 | 過敏性腸症候群の疑い、生活習慣の乱れ | 一度、消化器内科を受診して相談 |
| 半年以上 | 重大な病気の潜在リスクが否定できない | 内視鏡検査など精密検査の検討 |
明確に改善傾向が見えないまま何か月も下痢が続くようであれば、大腸カメラを含む精密検査を受けるタイミングと捉えると良いでしょう。
年齢や家族歴との関係
若い方であっても、遺伝的に大腸がんやその他の消化器系疾患のリスクが高い場合、早期に検査を受けることが望ましいです。
親や兄弟に大腸がん経験者がいる場合、医師に相談した上で内視鏡検査の適切な時期を決めることをおすすめします。年齢とともにリスクが上昇する疾患もあるため、定期的な検査を心がけるのも大切です。
他の病気との併発リスク
過敏性腸症候群と似た症状を起こす疾患として、炎症性腸疾患や大腸がんなどがあり、下痢だけでなく、腹痛や便秘を含めて症状が多岐にわたる方は、併発している可能性も考慮しなければなりません。
血液検査や画像診断で判断がつきにくい場合にも内視鏡検査が有用です。
悪化の兆候があるとき
最初は軽度の下痢だったのが、徐々に回数が増えてきたり、下痢の内容が水様化したりする場合は注意が必要で、加えて発熱や全身倦怠感、食欲不振を伴うようなら早めに消化器内科を受診して原因を突き止めることを推奨します。
原因不明の体重減少も、重篤な疾患を示唆する可能性があります。
- 下痢の回数や質が変化している
- 家族に大腸がんなどの消化器系疾患の既往歴がある
- 半年を超える長期的な便通異常に悩んでいる
- 血便や強い腹痛を自覚した
上記のような場合には、単なる過敏性腸症候群の範囲に留まらない可能性を考え、積極的に内視鏡検査を検討してください。
内視鏡検査に対する不安と準備
内視鏡検査と聞くと、「痛そう」「恥ずかしい」といったイメージを抱く方は多く、検査前の下剤の飲み方や当日の体調管理など、不安要素も様々です。
痛みに関する心配
大腸カメラ検査では肛門から内視鏡を挿入するため、痛みを心配する声がよく聞かれますが、技術や機材の進歩により、できるだけ苦痛を和らげる工夫が行われるケースが増えています。
鎮静剤や麻酔を使用して意識をぼんやりとさせる方法もあり、痛みに弱い方は医師と相談すると良いでしょう。
内視鏡検査で使用される主な鎮静方法
| 方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 鎮静剤(静脈投与) | 意識を軽く低下させ、不安や痛みを感じにくくする | 検査後にしばらく安静が必要、送迎の準備など |
| 鎮痛剤(静脈投与、点滴) | 痛みを和らげる効果があり、局所的な痛みを抑える | 個人差があり、合わない場合がある |
| 局所麻酔 | 挿入部位を麻酔して痛みを軽減する | 内視鏡の操作時に多少の違和感を伴う可能性 |
激しい痛みや苦痛を我慢する必要はなく、適切な鎮静方法を選択することで比較的負担を少なく検査を受けることが期待できます。
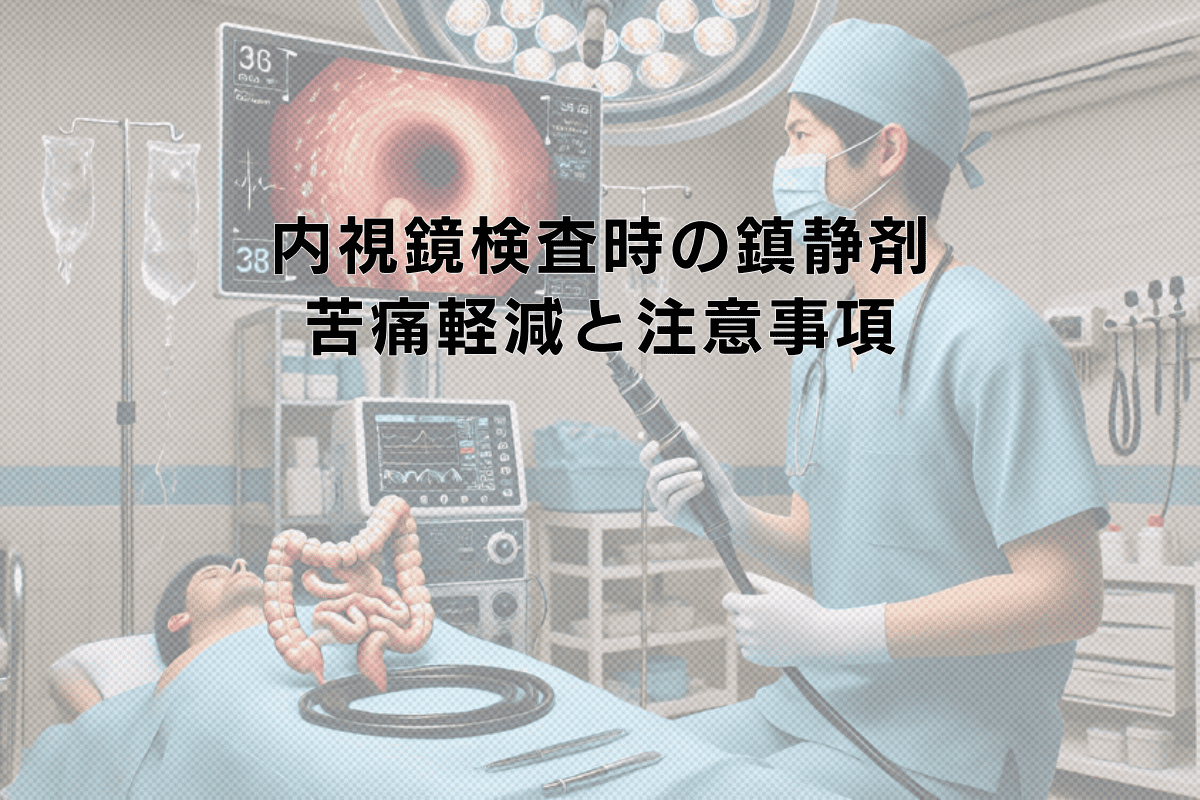
検査前の下剤服用の注意点
大腸カメラ検査では腸内を空にして観察しやすくするために下剤を服用し、大量の水や下剤を短時間で飲む必要があるため、飲み慣れない方には苦痛に感じるかもしれません。
飲み方のペースを一定に保ち、決められた量をきちんと飲み切ることが重要で、飲むスピードを速めすぎると吐き気が起こる可能性があり、遅すぎると検査時間が遅延する原因になります。
食事制限で気をつけること
検査前日は腸内をきれいに保つために消化の良い食事を選ぶよう指示があることが多く、検査当日は食事を控えるか、半日程度絶食にするよう指示を受ける場合もあります。
高繊維のものや種子が含まれる食品は腸に残りやすいので、医師やスタッフの指示に従って控えることが望ましいです。
- 前日は脂質や食物繊維が多いものを控える
- 水分はこまめに摂って脱水を防ぐ
- 指示された時間以降の食事・飲水は避ける
- 検査当日は緊張で脱水気味になりやすいので注意する
正しい事前準備を行うと、検査時間の短縮や観察精度の向上につながります。

リラックスして受けるための工夫
内視鏡検査は緊張しやすい場面ですが、できるだけリラックスして臨み、検査前に医師やスタッフにわからない点を相談し、不安材料を減らすことが大切です。
深呼吸や軽いストレッチなどで体をほぐしておくと、腸の緊張も和らぎやすくなります。睡眠不足は緊張感を高める原因になるため、前日は早めに就寝すると良いでしょう。
不安解消のために意識したい項目
| 懸念・不安 | 対策 | 効果 |
|---|---|---|
| 痛みに対する恐怖 | 鎮静剤を使用するかどうか医師に相談 | 痛みや不安感が軽減される |
| 恥ずかしさ | 検査服やタオルを使用して肌の露出を最小限に | 精神的ストレスを和らげる |
| 時間や費用の問題 | 事前に見積もりや所要時間を確認する | 予定を組みやすくなる |
| 検査後の体調 | 検査後に休憩できるようスケジュールを調整 | 復帰後に無理をしないで済む |
必要に応じて鎮静剤の選択や検査後の休憩時間を確保し、自分に合った形で検査を受けられるように段取りを組むと安心です。
検査後に意識したいケアと日常生活
大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査を受けた後は、当日のケアや今後の生活習慣に注意を払いましょう。検査が終わって安心する一方で、せっかくの検査結果を活かさずに過ごすと同じ悩みを繰り返すことになりかねません。
食事内容の見直し
もし過敏性腸症候群の下痢型と診断された場合、食生活の改善は欠かせません。
脂肪分や刺激物を控え、胃腸に負担をかけにくいメニューを選ぶ工夫が大事で、一度に大量に食べるより、適度な量を回数に分けて摂取するほうが腸への負担が少なく、下痢を起こしにくくなります。
- 高脂肪の肉類や油の多い揚げ物は控えめにする
- 香辛料を多用せず、薄味を心がける
- 食事はよく噛んで、ゆっくり時間をかける
- 発酵食品や食物繊維を適度に取り入れて腸内バランスを整える
暴飲暴食や急激なダイエットなども腸を乱す原因となるため、バランスの良い食習慣を続けることが望ましいです。
ストレスコントロールの方法
下痢の症状には精神的なストレスが深く関係している場合が多く、適度な運動やリラクゼーション法、趣味の時間を持つなど、ストレス源を減らし気分転換を図ることが有効です。
場合によっては精神科や心療内科と連携し、心身両面からアプローチを検討するのも一つの手段になります。
ストレスコントロールに役立つ主な対策
| 方法 | メリット | 継続のポイント |
|---|---|---|
| ウォーキングや軽い運動 | 血行促進とリフレッシュ効果が期待できる | 習慣化するために無理のない距離から |
| 深呼吸・瞑想 | 自律神経を整え、緊張や不安を緩和する | 毎日短時間でも継続すると効果的 |
| 友人や家族との会話 | ストレスの原因や悩みを共有して気持ちが軽くなる | オンラインも活用して気軽にコミュニケーション |
| 気分転換の趣味 | 楽しいと思える活動で精神的疲労を和らげる | 時間を決めて積極的に取り組む |
医療機関での診察やカウンセリングだけでなく、セルフケアでもできることがたくさんあり、下痢が長引いているときほど、精神面の負担を早めに解消しておくことが必要です。
再発予防のためのポイント
過敏性腸症候群の下痢型は、一度症状が治まっても再発する場合があり、生活習慣やストレス対処法を見直さないまま放置すると、同じトラブルが繰り返されることになりかねません。
検査で異常がなかった場合でも、今後の健康管理に活かすことが大切です。
- 定期的に体調や便通を記録して変化に早く気付く
- ストレスに上手に対処する手段を確立する
- 必要に応じて再度内視鏡検査を受ける
- 勝手な自己判断で薬を中断・服用しない
一時的に薬で抑えても、根本的な生活習慣を改めないと症状がぶり返すことがあります。食事や運動など、日常生活の基本を整えることが継続的なケアにつながります。
よくある間違いと正しい認識
過敏性腸症候群の下痢型に関する知識があっても、誤った思い込みや偏った対処で苦しみが長引いてしまうケースもあります。正しい認識を持ち、必要な時期に必要な対策をとることが肝心です。
症状が軽いときの受診
軽度であっても下痢や腹痛が長期間続く場合は、別の重大な病気が潜んでいる可能性を否定できず、下痢が断続的に続く時は、腸の粘膜に小さな炎症やポリープがあり、それが進行するとより大きなリスクへと発展する場合があります。
早めの内視鏡検査で安心を得る方が長期的にはメリットが多いです。
自己判断による薬の服用
下痢止めなどの市販薬を長期間にわたり使い続けると、腸の自然な動きが妨げられて逆効果になることがあります。
原因が特定されていない段階で薬に頼るのは、リスクを伴うので、医師の指示の下で薬を活用するほうが望ましい結果につながりやすいです。
- 下痢止めを服用すると便通を無理に止める可能性がある
- 胃腸薬の成分が根本原因に合わない場合、症状を悪化させるリスクがある
- 長期にわたる服用は医師の判断を仰ぐことが必要
腸の痛みや不快感を一時的に抑えても、根本の原因が解決していなければ再び同じ症状が出る可能性があります。
一度異常なしなら今後も心配ない?
検査時点で異常が見つからなかったからといって、将来的に必ずしも問題が起こらないわけではありません。
ポリープや腫瘍などは後から発生・成長することがあり、年齢や家族歴、生活習慣の変化などを考慮し、数年に一度は再検査を検討することが大切です。
健康診断だけで十分?
健康診断には便潜血検査や腹部超音波などが含まれる場合がありますが、大腸内壁を直接観察できるわけではなく、便潜血検査が陰性でも、早期の腫瘍やポリープが存在することもあります。
大腸カメラや胃カメラのように直接目で見る検査でこそ発見できる異常もあるため、健康診断だけで安心せずに必要に応じて内視鏡検査を追加することが望ましいです。
健康診断と内視鏡検査の比較
| 検査内容 | メリット | 限界 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 簡便に大腸の出血の有無を確認できる | 早期の病変や出血しないポリープは見逃しやすい |
| 腹部超音波 | 臓器の形態異常をある程度把握できる | 大腸内部の細かい変化はわかりにくい |
| 内視鏡検査(大腸) | 直接観察でき、生検やポリープ切除が可能 | 前処置と検査時の負担がある |
| 内視鏡検査(胃) | 胃粘膜の異常や初期のがんを見つける精度が高い | やや侵襲的で検査に時間と準備を要する |
Q&A
- 下痢が続いていても仕事が忙しく、受診する時間がありません。放置するとどうなりますか?
-
長期間下痢症状を放置すると、脱水や栄養不足による疲労感・倦怠感の増大、または重大な疾患の進行を見逃すリスクが高まり、特に数か月以上続く下痢は要注意です。
- 過敏性腸症候群の下痢があるときは、すぐに大腸カメラを受けたほうが良いのでしょうか?
-
すぐにでも受けたほうが良いというわけではありませんが、症状の持続期間や強度によっては早期受診が推奨されます。
症状が数週間以上改善しない、あるいは血便などの異常を感じる場合は、できるだけ早く消化器内科で相談してください。
- 大腸カメラを受けると痛みが強いと聞きましたが、我慢できないくらいなのでしょうか?
-
従来より機器や手技が進歩し、比較的ラクに受けられる方法が増え、鎮静剤を使うことで検査中の痛みや緊張を抑えられます。
痛みに弱い方や不安が大きい方は、予約時に医療機関へ相談すると対策を提案してもらえることが多いです。
次に読むことをお勧めする記事
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
「内視鏡の必要性は分かったけれど“実際の流れ”が気になる」という方へ。準備・当日・後の過ごし方まで一連の体験像をつかめます。検査前の不安軽減に役立つ内容です。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
過敏性腸症候群について理解が深まったところで、さらに腸内環境を整える方法についても知っておくと、より包括的な健康管理ができます。
参考文献
Mitsui K, Tanaka S, Yamamoto H, Kobayashi T, Ehara A, Yano T, Goto H, Nakase H, Tanaka S, Matsui T, Iida M. Role of double-balloon endoscopy in the diagnosis of small-bowel tumors: the first Japanese multicenter study. Gastrointestinal endoscopy. 2009 Sep 1;70(3):498-504.
Fukudo S, Kaneko H, Akiho H, Inamori M, Endo Y, Okumura T, Kanazawa M, Kamiya T, Sato K, Chiba T, Furuta K. Evidence-based clinical practice guidelines for irritable bowel syndrome. Journal of Gastroenterology. 2015 Jan;50(1):11-30.
Yamamoto H, Kita H, Sunada K, Hayashi Y, Sato H, Yano T, Iwamoto M, Sekine Y, Miyata T, Kuno A, Ajibe H. Clinical outcomes of double-balloon endoscopy for the diagnosis and treatment of small-intestinal diseases. Clinical gastroenterology and hepatology. 2004 Nov 1;2(11):1010-6.
Fukumoto A, Tanaka S, Yamamoto H, Yao T, Matsui T, Iida M, Goto H, Sakamoto C, Chiba T, Sugano K. Diagnosis and treatment of small-bowel stricture by double balloon endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2007 Sep 1;66(3):S108-12.
Ohmiya N, Yano T, Yamamoto H, Arakawa D, Nakamura M, Honda W, Itoh A, Hirooka Y, Niwa Y, Maeda O, Ando T. Diagnosis and treatment of obscure GI bleeding at double balloon endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2007 Sep 1;66(3):S72-7.
Fukudo S, Okumura T, Inamori M, Okuyama Y, Kanazawa M, Kamiya T, Sato K, Shiotani A, Naito Y, Fujikawa Y, Hokari R. Evidence-based clinical practice guidelines for irritable bowel syndrome 2020. Journal of gastroenterology. 2021 Mar;56(3):193-217.
Otani K, Watanabe T, Takahashi K, Nadatani Y, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Tanaka F, Nagami Y, Taira K. Upper gastrointestinal endoscopic findings in functional constipation and irritable bowel syndrome diagnosed using the Rome IV criteria: a cross-sectional survey during a medical check-up in Japan. BMC gastroenterology. 2023 May 3;23(1):140.
Kobayashi S, Yamada M, Takamaru H, Sakamoto T, Matsuda T, Sekine S, Igarashi Y, Saito Y. Diagnostic yield of the Japan NBI Expert Team (JNET) classification for endoscopic diagnosis of superficial colorectal neoplasms in a large-scale clinical practice database. United European gastroenterology journal. 2019 Aug;7(7):914-23.
Tanaka S, Kashida H, Saito Y, Yahagi N, Yamano H, Saito S, Hisabe T, Yao T, Watanabe M, Yoshida M, Saitoh Y. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):219-39.
Tabata K, Mihara H, Nanjo S, Motoo I, Ando T, Teramoto A, Fujinami H, Yasuda I. Artificial intelligence model for analyzing colonic endoscopy images to detect changes associated with irritable bowel syndrome. PLOS digital health. 2023 Feb 17;2(2):e0000058.