内視鏡を使って大腸をはじめとする下部消化管を調べることは、ポリープや炎症、腫瘍などの病変を早期に見つけ、必要な治療につなげるために大切な方法です。
下行結腸やS状結腸といった普段あまり意識しない部位に関しても、直接観察することで細かな異常を捉えることが期待できます。
ただし、検査の準備や当日の流れを十分に理解していないと、不安を抱えてしまう方が多いかもしれません。
この記事では、下部消化管を対象とした内視鏡検査の観察範囲や具体的な手順、検査を受ける際のポイントなどを詳しく解説します。
下部消化管内視鏡検査の概要
大腸を含めた下部消化管の状態を詳しく調べるには、内視鏡が有効です。専門的には下部消化管内視鏡検査と呼ばれ、便秘や下痢、血便などの症状がある方に検討されることが多いですが、検診目的でも広く行われています。
大腸内視鏡とは
下部消化管をチェックするための内視鏡は、細長く柔軟性を持ったチューブ状の機器で、先端にカメラや照明がついており、肛門から挿入して大腸の内腔を直接観察します。
画像はモニターに映し出され、小さな病変や異変も見逃しにくいです。
観察する範囲
大腸内視鏡検査では、盲腸から直腸までの大腸全域を基本的に観察し、状況によっては、小腸の末端部(回盲部)までをのぞき見ることもあります。腸の走行は個人差があり、腸が長い方や屈曲が強い方などで検査時間が変わる場合があります。
主な適応となる症状
以下のような症状が続いている場合、大腸内視鏡検査が検討されます。
- 血便や粘液便が認められる
- 腹痛や腹部膨満感が長引く
- 便秘・下痢など便通異常が続く
- 貧血の原因が分からない
- 家族に大腸ポリープや大腸がんの既往がある
いずれも放置すると深刻な病気を見逃すリスクが高まるため、早めに検査を受けると安心です。
診断と治療を同時に行える
内視鏡検査では、発見されたポリープの切除や疑わしい部位の組織採取(生検)を同時に行え、病変を迅速に取り除くことや、がんの有無を確定診断することが可能です。
下部消化管の解剖学的特徴
大腸を中心とした下部消化管は、消化や水分吸収などの重要な役割を担う器官ですが、その構造や走行は複雑です。内視鏡検査で観察する部位の特徴を理解すると、検査の意義をさらに把握しやすくなります。
大腸の区分
大腸は大きく盲腸、結腸、直腸に分けられ、結腸はさらに上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸の4つに区分されます。
大腸の区分と役割
| 部位 | 場所と概要 | 主な働き |
|---|---|---|
| 盲腸 | 小腸(回腸)との接続部分。虫垂が付属している | 消化液の分泌は少ないが病原菌の影響を受けやすい |
| 上行結腸 | 右腹部を上向きに走行 | 水分や電解質の吸収 |
| 横行結腸 | 腹部を横に走行 | 便の形成、腸内細菌による発酵 |
| 下行結腸 | 左腹部を下向きに走行 | 便の水分吸収をさらに進め、固形化を進める |
| S状結腸 | 骨盤付近をS字にカーブしながら走行 | 下行結腸からの便を一時的に貯留し、排便につなげる |
| 直腸 | 便が最終的に貯蔵される部分 | 肛門へ排泄するまでの通路 |
このように、大腸全体をまんべんなく観察することで、多様な病変や異常を早期に見つけられます。
肛門から盲腸までの長さ
成人の大腸はおよそ1.5~2メートル程度とされていますが、個人差がかなり大きく、腸が長い方や屈曲の強い方は内視鏡の操作が難しく、検査に時間がかかったり、不快感が増したりすることがあります。
ただし、最近の機器や手技の進歩によって、患者さんの負担を軽減する工夫がなされています。
大腸の粘膜と腸内細菌
大腸の粘膜は、腸内細菌との共同関係のもとで消化物の発酵や水分吸収に関わっていて、粘膜には多数の絨毛や腺があり、病変の早期発見には粘膜表面を詳細に観察できる内視鏡検査が欠かせません。
ポリープや炎症、腫瘍なども粘膜表面に異常が生じるため、直接的な観察が重要です。
腸内細菌の主な役割
- 消化吸収の補助(炭水化物の分解など)
- ビタミン合成(ビタミンKなど)
- 病原菌の繁殖抑制
- 腸粘膜の免疫機能サポート
このバランスが崩れると、下痢や便秘、炎症性腸疾患などにつながる恐れがあります。
直腸の貯留機能
S状結腸と直腸付近では、便を一時的に留める働きがあり、排便のコントロールをしています。
直腸付近のトラブル(痔や直腸がんなど)は出血や血便、排便困難などの症状が出やすいため、内視鏡検査でダイレクトに観察することで早期発見につながりやすいです。
検査準備の手順と注意点
大腸内視鏡検査を行う際には、前処置を行い腸をきれいにしておくことが極めて重要です。不十分だと検査の精度が落ちたり、見落としが増えたりする恐れがあります。

食事制限と腸内洗浄
検査前日から食事を制限し、消化の良いものを中心に少量ずつ摂取することが一般的で、また、検査当日に腸内を洗浄するための下剤を服用し、大量の水や腸洗浄液を飲んで便や残渣を排出させます。
下剤服用
| タイプ | 服用方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 経口腸管洗浄剤 | 2~3リットルの洗浄液を数時間かけて飲む | 便や内容物を大量の水分で洗い流す |
| 小量下剤 | 小量の薬剤を数回に分けて飲む | 腸管のぜん動を促進し排便をうながす |
| 前日からの下剤併用 | 検査前日夕方や就寝前に下剤を飲む | 検査当日の洗浄剤の使用量を減らす補助 |
医療機関の方針や患者さんの体質によって処方される下剤の種類は異なります。

当日の服装と持ち物
検査当日は、排便しやすいようゆったりした服装で来院することをお勧めします。検査後しばらく安静が必要になるケースもあるため、付き添いがあると安心です。貴重品や必要書類、健康保険証などを忘れずに持参すると良いでしょう。
当日の持ち物
- 健康保険証や診察券
- 検査説明書や同意書
- 前処置用の下剤(自宅で飲む場合を除く)
- タオルやウェットティッシュ
- スマートフォンや書籍(待ち時間対策)
過度な装飾品やきついベルトの衣服は避けるのが無難です。
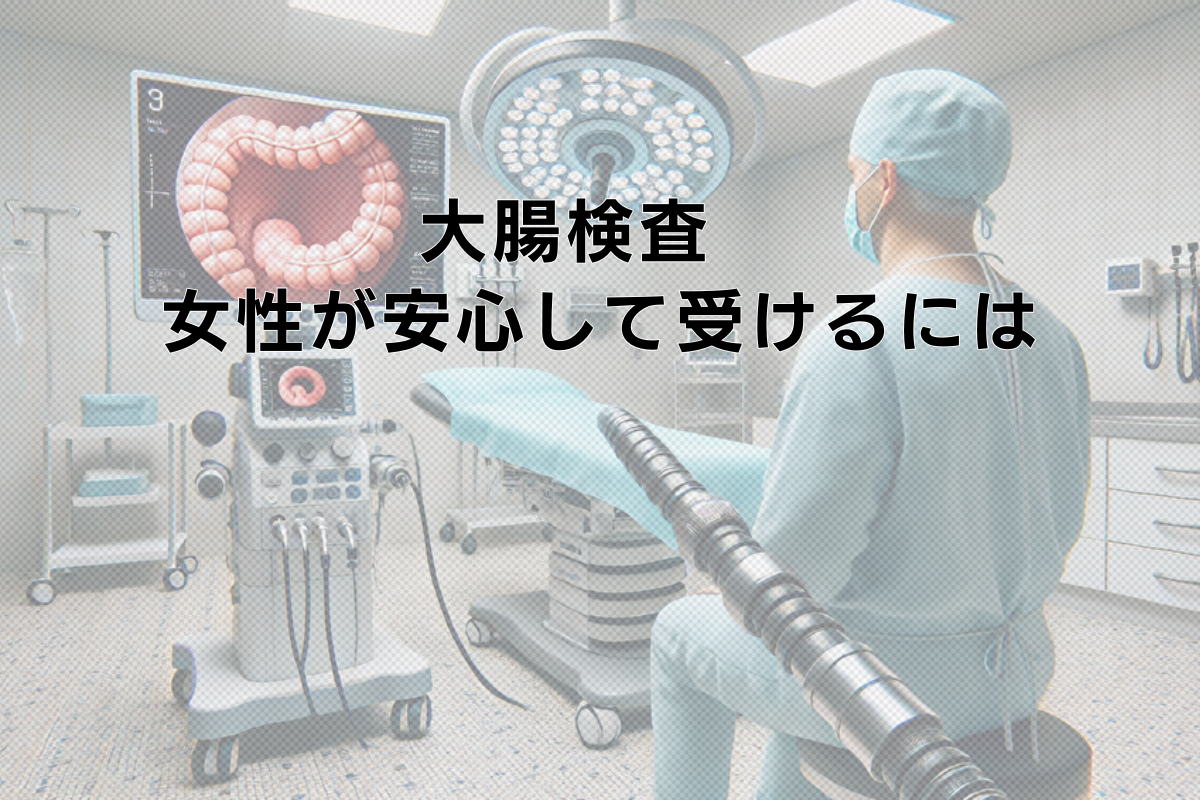
検査直前の注意点
検査直前は、看護師やスタッフから排便の状況を確認されたり、体調を尋ねられたりして、便の状態が十分に透明になっていない場合は、追加の下剤を飲む必要があるかもしれません。
また、血圧や脈拍を計測し、検査中のリスクを事前に評価します。
鎮静剤や鎮痛剤の使用
痛みに弱い方や緊張が強い方は、点滴から鎮静剤を使用する場合があります。
検査中の不快感が軽減し、落ち着いて受けやすくなる一方、検査後は眠気やふらつきが続くこともあるため、当日は車の運転を控えるなどの注意が必要です。

検査の手順と観察範囲
実際に大腸内視鏡検査が始まった後は、内視鏡を肛門から挿入して盲腸付近まで進め、そこからゆっくりと引き抜きながら大腸内部を観察します。挿入時よりも引き抜くときの方が詳細な観察が可能です。
内視鏡の挿入方法
検査ベッドに横向きに寝て、肛門から内視鏡を挿入します。腸の曲がり角などを通過するときに痛みを感じることがあるため、医師やスタッフが慎重に操作します。
大腸は個人差が大きいため、時間がかかる場合もありますが、鎮静剤や丁寧な挿入技術によって負担は軽減されるように配慮されます。
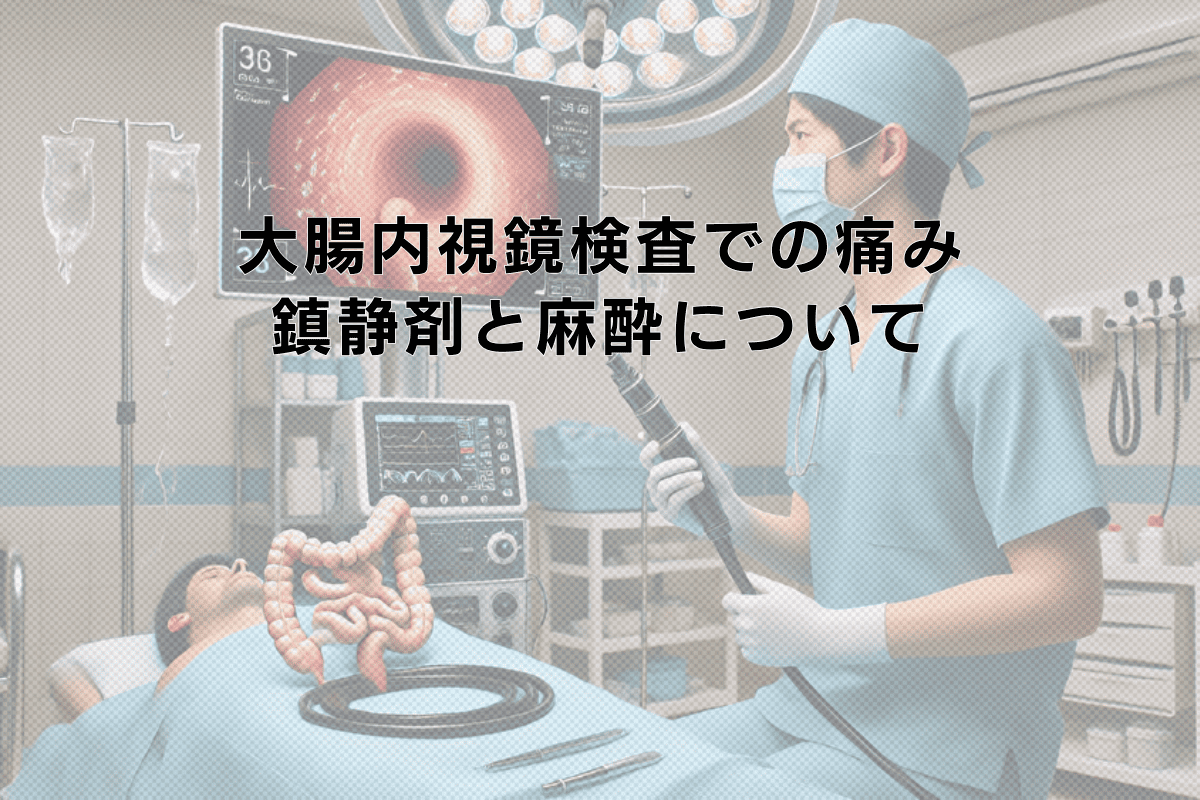
大腸内視鏡検査の主な流れ
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 体勢づくり | 左側を下にして横になる | 膝を軽く曲げ、腹部の緊張を緩める |
| 2. 挿入 | 肛門から内視鏡をゆっくり挿入 | 曲がり角を無理なく越える操作が重要 |
| 3. 盲腸到達 | 内視鏡を盲腸付近まで進める | 大腸全体を観察するための基準点となる |
| 4. 引き抜き | ゆっくりと内視鏡を戻しつつ観察 | 詳細な粘膜確認や病変の発見がしやすい |
| 5. 病変処置 | ポリープや疑わしい部位があれば切除・生検 | 病変を同時に治療し、検査精度を向上 |
挿入と引き抜き、両段階で腸内の観察は行われますが、より詳細な確認は引き抜き時に行うことが一般的です。
空気の送気と二酸化炭素の使用
腸内をよく観察するために、内視鏡から空気や炭酸ガスを送って腸管を膨らませることがあります。
以前は空気が主流でしたが、近年は吸収されやすい炭酸ガスを使用する施設も増えており、検査後の膨満感や不快感が軽減しやすいです。
粘膜観察と画像記録
内視鏡先端に搭載されたカメラからの映像は、モニターに拡大表示され、特殊な光や拡大機能を使用して微細な血管や色調の変化を捉え、ポリープや腫瘍の早期発見を試みます。
また、必要に応じて画像を保存し、後で専門医が再確認する場合もあります。
主な観察ポイント
- 粘膜の色調(赤み、白っぽさなど)
- 表面の凹凸や隆起
- 出血斑や潰瘍の有無
- 血管の走行パターンの異常
- ポリープや腫瘍らしき隆起性病変
それぞれの特徴を総合して判断し、必要があれば組織検査を行います。
病変処置や生検
ポリープが見つかった場合、小さなものであれば内視鏡検査中にポリープ切除を行うことが一般的で、スネアという器具を使って切除し、病理検査に回すことで良性か悪性かを判断します。
疑わしい部位は生検鉗子で一部を採取し、顕微鏡下で詳細に調べられます。
検査後のケアと結果説明
大腸内視鏡検査が終了すると、鎮静剤の影響が残っている場合、しばらくベッドやソファで安静に過ごすことがあります。施設によっては検査当日に結果の概要を説明し、後日正式な検査報告を受け取る流れが取られることもあります。
検査直後の過ごし方
腸内に送られたガスや空気が残っていると、お腹の張りや膨満感を感じることがあり、軽く体を動かしたり、腸内のガスを排出したりしてゆっくり過ごすことが推奨されます。
もしポリープ切除や生検を行った場合には、出血リスクを考えて当日は激しい運動や飲酒を控えましょう。
検査後に気をつけるべきこと
- 強い腹痛や血便がある場合、すぐに医療機関に連絡する
- 食事は医師の指示に従い、消化に優しいものから開始
- 鎮静剤を使用した場合、車の運転や機械操作は避ける
- ポリープ切除後はしばらく飲酒や激しい運動を控える

検査結果の受け取り方
検査後すぐに医師が画像や映像を見ながら説明してくれることが多いですが、生検を行った場合は病理検査に時間がかかるため、結果が出るまで数日~1週間程度要する場合があります。
重大な病変やがんが発見された場合には、専門の医師による追加の説明や治療方針の相談が行われます。
経過観察と再検査のスケジュール
ポリープを切除した場合、大きさや性状によっては一定期間後に再度内視鏡検査を行い、取り残しがないかや新たな病変が生じていないかを確認します。
ポリープが見つからなかった場合でも、年齢や家族歴によっては定期的に受診すると安心です。
経過観察の目安
| 状況 | 再検査の推奨時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 小さな良性ポリープを切除 | 1年後~3年後 | 場合によってはもっと早くチェックすることも |
| 大きめのポリープや多数切除 | 6か月~1年後など短期 | 取り残しや新生ポリープのリスクが高いため |
| 癌の早期発見で切除 | 専門医の指示に従う | 定期的なCT検査や血液検査も併用する場合がある |
| 異常なし | 5年程度を目安に再検査 | 家族歴や基礎疾患がある場合は早めに行うことも |
再検査や検診をうまく組み合わせて、下部消化管の健康を維持していくことが大切です。
大腸内視鏡検査と他の検査の比較
下部消化管を調べる検査としては、大腸内視鏡以外にもCTコロノグラフィーなどが選択されることがあり、目的や状況に応じて複数の検査法があるため、違いを把握しておきましょう。
CTコロノグラフィー
仮想内視鏡とも呼ばれ、CT装置を用いて大腸内部を画像再構成する方法です。
内視鏡を挿入せずに大腸内の形状を確認できる利点がありますが、ポリープの切除や生検ができないため、疑いが強い場合はやはり大腸内視鏡が必要になります。
検査法の特徴
| 検査法 | 侵襲性 | 観察精度 | ポリープ切除や生検 | 痛みや不快感 |
|---|---|---|---|---|
| 大腸内視鏡 | 肛門から挿入 | 高い | 可能 | ややある |
| CTコロノグラフィー | 挿入なし | そこそこ | 不可 | わずかにある |
| 注腸造影 | バリウム注入 | そこそこ | 不可 | ややある |
このように、実際に治療の可能性がある場合や、精度の高い観察が要求される場合は大腸内視鏡が第一選択になりやすいです。
注腸造影
X線透視を使ってバリウムを注入し、大腸の形態を撮影する方法で、以前は主流でしたが、現在では大腸内視鏡に比べると、詳細な観察やポリープ除去ができないという点で使用頻度が減少しています。
超音波内視鏡との違い
超音波内視鏡は、内視鏡に超音波プローブを組み込んだもので、腸管壁の深い層や周囲組織の情報を得やすいことが特徴です。
主に深達度の評価や周辺臓器への浸潤などの確認に使われるため、通常の大腸内視鏡検査とは目的が若干異なります。
よくある質問
- 大腸内視鏡検査は痛いのでしょうか?
-
個人差がありますが、腸のカーブが強い方や腸が長い方は苦痛を感じることがあるようですが、検査技術の進歩や鎮静剤の使用によって、以前よりは快適になったとの声も多いです。
鎮静剤を使うかどうかは相談して決めるましょう。
- 下剤を飲むのがつらいと聞きますが、量を減らす方法はありますか?
-
腸内を十分にきれいにしないと検査の精度が落ちるため、必要量の下剤は基本的に飲む必要があります。
ただし、小量タイプの腸管洗浄液を複数回に分けて飲む方法や、検査前日から弱めの下剤を使い腸を整えておく方法などもあるので、医師やスタッフに相談しましょう。
- どのくらいの頻度で検査を受けるべきでしょうか?
-
ポリープや大腸がんのリスクが高い方は1~3年おき、リスクが低い方でも5年おきなど、状況に応じた提案があります。年齢や家族歴、過去のポリープ切除歴などによって異なるため、一度受診して医師と相談すると確実です。
- 検査の日は仕事を休まなければなりませんか?
-
下剤服用などの準備に時間がかかり、検査後も鎮静剤の影響で意識がはっきりしないことがあり、多くの方が当日は仕事を休むか、翌日以降に予定を組むようにされています。
ポリープ切除などを行った場合は、安静が求められることもあるため注意してください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の前日に必要な準備と食事の注意点】
検査の流れを把握できたら、前日の具体的な過ごし方や下剤の工夫も押さえておくと安心です。準備のつまずきやすい点を実例ベースで確認できます。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
下部内視鏡の役割を学んだ皆さんには、便潜血など他の検査との位置づけも合わせて知ると、受診判断がより納得しやすくなります。
参考文献
Rey JF, Lambert R, null and the ESGE Quality Assurance Committee. ESGE recommendations for quality control in gastrointestinal endoscopy: guidelines for image documentation in upper and lower GI endoscopy. Endoscopy. 2001 Oct;33(10):901-3.
Sewitch MJ, Gong S, Dubé C, Barkun A, Hilsden R, Armstrong D. A literature review of quality in lower gastrointestinal endoscopy from the patient perspective. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2011;25(12):681-5.
Kawada PS, O’Loughlin EV, Stormon MO, Dutt S, Lee CH, Gaskin KJ. Are we overdoing pediatric lower gastrointestinal endoscopy?. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2017 Jun 1;64(6):898-902.
Pasha SF, Shergill A, Acosta RD, Chandrasekhara V, Chathadi KV, Early D, Evans JA, Fisher D, Fonkalsrud L, Hwang JH, Khashab MA. The role of endoscopy in the patient with lower GI bleeding. Gastrointestinal endoscopy. 2014 Jun 1;79(6):875-85.
Moorthy K, Munz Y, Orchard TR, Gould S, Rockall T, Darzi A. An innovative method for the assessment of skills in lower gastrointestinal endoscopy. Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques. 2004 Nov;18:1613-9.
Hardwick RH, Armstrong CP. Synchronous upper and lower gastrointestinal endoscopy is an effective method of investigating iron‐deficiency anaemia. British journal of surgery. 1997 Dec;84(12):1725-8.
Özsoy M, Celep B, Ersen O, Özkececi T, Bal A, Yılmaz S, Arıkan Y. Our results of lower gastrointestinal endoscopy: evaluation of 700 patients. Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi. 2014 Jun 1;30(2):71.
Varadarajulu S, Ramsey WH. Utility of retroflexion in lower gastrointestinal endoscopy. Journal of clinical gastroenterology. 2001 Mar 1;32(3):235-7.
Faigel DO, Eisen GM, Baron TH, Dominitz JA, Goldstein JL, Hirota WK, Jacobson BC, Johanson JF, Leighton JA, Mallery JS, Vargo II JJ. Preparation of patients for GI endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2003 Apr 1;57(4):446-50.
Gorospe EC, Oxentenko AS. Preprocedural considerations in gastrointestinal endoscopy. InMayo Clinic Proceedings 2013 Sep 1 (Vol. 88, No. 9, pp. 1010-1016). Elsevier.










