内視鏡検査は、食道、胃、大腸などの消化管内部を直接観察し、病気の早期発見に貢献する重要な医療技術です。
診断精度を飛躍的に向上させる技術としてNBI(Narrow Band Imaging)システムがあります。
NBIは、特殊な光を用いて粘膜表面の微細な血管の様子を詳細に観察する技術で、通常の内視鏡では見過ごしてしまう可能性のある、ごく初期のがんや前がん病変を発見する能力を高めます。
この記事では、NBIシステムを用いた内視鏡検査がどのような特徴を持ち、いかにして診断精度を高めるのか、仕組みから対象疾患までを、分かりやすく解説します。
NBIシステムとは何か
NBIシステムは、内視鏡検査の分野で広く用いられるようになった画像強調技術の一つです。
がんは増殖するために多くの栄養を必要とし、そのために新しい血管(新生血管)を自ら作り出しますが、新生血管は正常な血管とは形や走り方が異なるため、NBIは特徴を捉えて病変の存在を示唆します。
狭帯域光観察の基本
NBI(狭帯域光観察)は、光源から出る光を特殊なフィルターに通すことで、光の波長を特定の範囲に絞り込んで粘膜に照射し、その反射光から画像を作り出す観察方法です。
通常の内視鏡検査で用いる光(白色光)は、虹の七色のように、さまざまな波長の光が混ざり合っているのに対して、NBIでは青色と緑色の2つの特定の狭い波長帯の光だけを利用します。
この特殊な光が、通常光では得られない粘膜表面の詳細な情報を引き出し、診断に有用な手がかりを提供します。
がんの早期発見を支える技術
消化管のがんは、初期の段階では粘膜の色の変化や凹凸がごくわずかで、発見が難しい場合があり、特に平坦な形のがんは、熟練した医師でも見逃す可能性があります。
NBIシステムは、がん細胞に栄養を供給するために異常に増殖した毛細血管を、黒褐色や濃い緑色などのコントラストの高い画像として映し出すことで、病変の存在を視覚的に認識しやすくなり、がんの早期発見率の向上に大きく貢献しています。
単に表面の色を見るだけでなく、粘膜下の血管の状態という、もう一つの次元の情報を得られることが、この技術の強みです。
NBIの主な役割
| 役割 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 病変の発見(スクリーニング) | 通常光では不明瞭な微小な病変を強調表示する | 見逃しを減らし、発見率を向上させる |
| 病変の質的診断(鑑別) | 血管や表面の模様から良性か悪性かを推定する | 不要な生検を減らし、的確な診断を補助する |
| 治療範囲の決定 | 病変の水平方向への広がりを正確に把握する | より精密な治療計画の立案を助ける |
粘膜表面の微細な血管を可視化
NBIの最大の特徴は、粘膜の表面にある微細な血管のパターンを鮮明に映し出す能力にあります。
血液中のヘモグロビンは、特定の波長の光を強く吸収する性質を持っていて、NBIはこの性質を最大限に利用し、血管が豊富な領域を強調して表示します。
正常な粘膜と病変部では血管の密度や走行パターンが異なるため、違いを明確に捉えることが診断の手がかりです。
炎症では血管が規則正しく並んでいることが多いのに対し、がんでは血管が不規則に曲がりくねったり、太さがバラバラになったりしますが、この違いをNBIは明確に描き出し、病変部と正常部の境界線をくっきりと示してくれます。
通常の内視鏡検査との決定的な違い
NBIシステムを用いた内視鏡検査と、従来の白色光を用いた通常の内視鏡検査には、観察の質において明確な違いがあり、この違いが、診断精度の差となって現れます。
光の波長を利用した観察方法
通常の内視鏡検査では、太陽光に近い自然な白色光を当てて粘膜の色や形を観察し、これは肉眼で見るのと同じような感覚です。
一方、NBI検査では、青色と緑色の2つの狭い帯域の光だけを照射し、この光の波長は、粘膜の表層とやや深い層の血管をそれぞれ観察するのに適しており、病変の血管情報を選択的に取得できます。
観察モードの簡単な切り替え
内視鏡医は、検査中に手元のスコープのボタンを一つ押すだけで、瞬時に通常光とNBI光を切り替えることができ、通常光での全体的な観察中に少しでも気になる部分があれば、即座にNBIモードで詳細な観察へ移行できます。
このシームレスな切り替えが、医師の思考を中断させることなく、効率的で精度の高い検査を実現しています。
通常光とNBI光の比較
| 項目 | 通常光(白色光) | NBI(狭帯域光) |
|---|---|---|
| 使用する光 | 幅広い波長の光 | 特定の2つの波長の光(415nmと540nm) |
| 主な観察対象 | 粘膜の色調、凹凸、形態 | 粘膜表層の血管パターン、表面構造 |
| 画像の見た目 | 自然な色合い | 血管や構造が強調された特殊な色調 |
色調の違いによる病変の強調
NBIで観察すると、粘膜表層の毛細血管は茶色に、少し深い層にある血管は緑色に見えます。
腫瘍性の病変では血管が増生したり、形が不規則になったりするため、NBI画像上では周囲の正常な粘膜とは明らかに異なる濃い茶色の領域として認識されます。この明確な色の違いが、微小な病変を見つけるための強力なサインです。
背景の正常な粘膜は緑がかった色に見えるため、茶色い病変部とのコントラストがより一層際立ち、まるで病変部分だけが浮かび上がってくるように見えます。
生検の必要性を判断する精度
内視鏡検査では、疑わしい部分が見つかると、組織の一部を採取して病理検査で詳しく調べる生検を行います。
NBIを用いると、観察段階で病変が悪性である可能性が高いか、あるいは良性である可能性が高いかを、ある程度高い精度で推定できます。
これは「光学的生検(Optical Biopsy)」とも呼ばれる考え方で、不要な生検を減らし、患者さんの体への負担や医療コストを軽減することにもつながるのです。
本当に生検が必要な病変を的確に選び出し、また生検を行う際にも最も病変を代表する部分を狙って組織を採取できるため、診断の精度向上に貢献します。
NBIシステムの仕組みと光の科学
NBIシステムがなぜ病変の発見に有効なのかを理解するためには、背景にある光の科学的な原理を知ることが助けになります。血液に含まれるヘモグロビンと特定の光の波長との関係が、この技術の核となっています。
血液中のヘモグロビンが吸収する光
血液が赤いのは、赤血球に含まれるヘモグロビンという色素によるものです。ヘモグロビンは、酸素を運搬する重要な役割を担っていますが、光の波長によって吸収の度合いが異なるという物理的な特性も持っています。
特に、415ナノメートル(nm)付近の青い光と、540ナノメートル付近の緑の光を強く吸収します。NBIシステムは、この2つの波長の光を巧みに利用し、ヘモグロビンつまり血管を、粘膜表面から浮かび上がらせるように画像化するのです。
2つの特定の波長の光
NBIで使用する光は、以下の2種類です。
- 415nmの光:粘膜の最も表層にある毛細血管の観察に適しています。
- 540nmの光:表層よりも少し深い部分にある血管の観察に適しています。
光を粘膜に照射すると、血管中のヘモグロビンに吸収され、血管が周囲の組織よりも暗く見え、コンピューターがこの情報を処理し、表層の血管を茶色、深層の血管を緑色としてモニター上に表示します。
NBIで利用する光の特性
| 光の波長 | 主な到達深度 | 強調される血管 |
|---|---|---|
| 415nm(青色光) | 粘膜表層 | 毛細血管(茶色に表示) |
| 540nm(緑色光) | 粘膜下層浅部 | 太い血管(緑色に表示) |
粘膜表層と深層の血管情報の取得
415nmの光は粘膜の浅い部分までしか届きませんが、表層の毛細血管の情報を得るのに優れていて、540nmの光はもう少し深くへ到達し、粘膜下層の太い血管の情報を捉えます。
NBIは、2つの異なる深さの血管情報を合成して一つの画像を構築します。がんなどの病変は、まず粘膜の表層で発生し、異常な毛細血管を伴うことが多いため、特に415nmの光がもたらす情報は早期診断において非常に重要です。
病変が進行すると、より深い部分の太い血管にも変化が現れるため、両方の情報を組み合わせることで病変の深達度(がんがどれくらい深く潜っているか)を推定する手がかりにもなります。
NBIシステムがもたらす診断精度の向上
NBIシステムの導入は、内視鏡診断の精度をさまざまな側面から向上させました。単に病変を見つけやすくなるだけでなく、性質の評価や治療方針の決定においても大きな役割があります。
微小ながんや前がん病変の発見率
NBIの最も大きな貢献は、これまで発見が困難であった平坦な病変や微小な病変の発見率を高めたことです。
食道や咽頭、喉頭領域の早期がん(表在がん)は、通常光ではわずかな発赤としてしか認識できず、見逃されることも少なくありませんでした。
NBIで観察すると、これらの病変は特徴的な褐色の領域として明瞭に浮かび上がるため、発見率が格段に向上します。研究報告によっては、特定のがんの発見率が通常光に比べて数倍高まったというデータもあります。
拡大内視鏡との併用による相乗効果
近年の内視鏡システムは、NBI機能に加えて、画像を最大で100倍程度まで拡大できる拡大機能も搭載しています。NBIで病変を見つけ、次に拡大機能を用いてその表面構造や血管の形を詳細に観察するという流れが一般的です。
これは、例えるなら、生物学者が顕微鏡で標本を観察する際に、まず染色液で目的の細胞を染め(NBI)、次に倍率を上げて細胞の核や構造を詳しく見る(拡大観察)のに似ています。
この組み合わせにより、がんかそうでないかの鑑別精度はさらに高まります。
NBI拡大観察による診断カテゴリー
| 観察項目 | 内容 | 診断への貢献 |
|---|---|---|
| 表面構造パターン | 粘膜の微細な腺管の模様(腺窩上皮)の乱れを観察する | 腫瘍か非腫瘍かの鑑別に重要 |
| 微小血管パターン | 毛細血管の太さ、形、走行の不規則性を評価する | がんの可能性や悪性度を推定する手がかりとなる |
炎症と腫瘍の鑑別
消化管の粘膜は、逆流性食道炎やピロリ菌による胃炎など、炎症によっても赤く見えることがあり、通常の内視鏡検査では、炎症による赤みと、ごく初期のがんによる赤みの区別が難しい場合があります。
NBIを用いて血管のパターンを詳細に観察することで、炎症の場合は規則的な血管パターンが保たれているのに対し、腫瘍の場合は血管の走行が乱れたり、太さが不均一になったりする様子が分かります。
また、がん組織と正常組織の境界が明瞭な線として認識できることも多く、診断の助けとなります。
血管パターンによる鑑別のポイント
| 所見 | 炎症性変化 | 腫瘍性変化(がん) |
|---|---|---|
| 血管の規則性 | 保たれていることが多い | 乱れていることが多い(Demarcation lineの存在) |
| 血管の太さ | 均一 | 不均一(太さや形がバラバラ) |
| 血管の走行 | 整然としている | 蛇行、途絶など不規則 |
治療範囲の正確な特定
がんを内視鏡で切除する治療(内視鏡的切除術、特にESD:内視鏡的粘膜下層剥離術など)を行う際には、病変の広がりを正確に把握し、がん細胞を完全に取りきることが重要です。
通常光では病変の境界が不明瞭な場合でも、NBIを用いることでがんが広がっている範囲(水平進展範囲)を明確に特定しやすくなり、切除範囲を正確に決定でき、不十分な切除によるがんの再発を防ぎます。
NBI検査が特に有効とされる消化器疾患
NBIシステムは、消化管のさまざまな部位の疾患発見に有用ですが、特に威力を発揮する疾患があります。ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。
食道がん(特に表在がん)
食道の表在がんは、粘膜の表面にとどまるごく早期のがんで、この段階で発見できれば、内視鏡治療で治癒を目指せます。NBIは、この食道表在がんの発見に非常に有効です。
アルコールや喫煙と関連の深い扁平上皮がんは、NBIで観察すると明瞭な褐色領域として認識されます。
さらに拡大観察を行うと、乳頭内血管ループ(IPCL)と呼ばれる特徴的な血管の形が不規則に変化している様子を捉えることができ、診断の確信度を高めます。
従来はヨードという色素を散布していましたが、NBIは色素を使わずに同様以上の情報が得られます。
食道におけるNBIの観察所見
| 観察モード | 正常な粘膜 | 表在がん |
|---|---|---|
| 通常光 | 薄いピンク色 | わずかな発赤や色調の変化のみで不明瞭 |
| NBI | 薄い緑色 | 境界明瞭な褐色領域として認識される |
胃がん(特に早期胃がん)
胃がんもまた、早期に発見することが治療成績を大きく左右します。NBIは、胃の微小ながんや、通常光では慢性胃炎の粘膜変化との区別が難しい病変の診断に役立ちます。
NBIに拡大機能を組み合わせることで、がんの表面の微細な構造や血管のパターンを詳しく分析するVS分類(Vessel plus Surface classification)などを用いて、より精度の高い診断が可能になります。
特に、粘膜の下を這うように広がる未分化型胃がんのような発見の難しいがんの診断にも貢献します。
大腸ポリープと大腸がん
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)においても、NBIは重要な役割を果たします。大腸ポリープには、将来がん化する可能性のある腫瘍性のもの(腺腫など)と、その可能性が低い非腫瘍性のもの(過形成性ポリープなど)があります。
NBIでポリープの表面構造や血管のパターンを観察することで、ポリープがどちらのタイプであるかを高い精度で判別できます。
JNET分類などの基準を用いることで、その場でポリープの性質を判断し、小さな非腫瘍性ポリープは切除せずに経過観察とするなど、効率的で患者さんの負担が少ない方針を立てる助けになります。
大腸腫瘍のJNET分類(抜粋)
| 分類 | 血管・表面パターン | 推定される病理組織 |
|---|---|---|
| Type 1 | 見えない、または規則的 | 過形成性ポリープなど |
| Type 2A | 血管・表面ともに規則的 | 低異型度腺腫(早期がん) |
| Type 2B | 血管・表面ともに不規則 | 高異型度腺腫、粘膜下層浅部浸潤がん |
咽頭・喉頭がんのスクリーニング
食道がんの検査を行う際には、リスク因子(喫煙、飲酒)が共通する咽頭や喉頭も同時に観察することが一般的です。
NBIは、食道がんと同様に、咽頭・喉頭の表在がんも褐色の領域として強調するため、スクリーニングの精度を大きく向上させます。
胃カメラ検査の際にこれらの領域をNBIで注意深く観察することで、思いがけない病変の早期発見につながることがあります。
NBIシステムを用いた内視鏡検査の実際
NBIシステムは特殊な技術ですが、検査を受ける患者さん側から見れば、流れや準備は通常の内視鏡検査とほとんど変わりません。ここでは、検査当日の流れや準備について説明します。
検査前の準備と食事制限
正確な検査を行うためには、胃や大腸の中を空にしておく必要があるので、食事制限の内容や時間は、検査を受ける医療機関の指示に必ず従ってください。
大腸検査の場合、準備が不十分だと便の残渣で小さな病変が隠れてしまい、検査の精度が落ちるだけでなく、最悪の場合は検査を中断し後日やり直しになる可能性もあります。
- 上部消化管内視鏡(胃カメラ):通常、検査前日の夕食は消化の良いものを夜9時頃までに済ませ、その後は絶食となります。おかゆ、うどん、白身魚、豆腐などが推奨されます。検査当日は、水やお茶などの水分摂取は可能な場合があります。
- 下部消化管内視鏡(大腸カメラ):検査前日から繊維の多い野菜やきのこ、種のある果物などを避けた消化の良い食事(検査食)に切り替え、検査当日は2リットル前後の下剤を服用して腸内をきれいにします。

検査当日の流れ
検査当日は、まず問診や血圧測定などの体調チェックを行い、その後、喉の麻酔や、腸の動きを抑える薬の注射、そして希望に応じて鎮静剤の注射をします。検査自体は、口や鼻、あるいは肛門から内視鏡を挿入して行います。
医師はモニターを見ながら消化管の内部を隅々まで観察し、特定の領域を詳しく見たいときに、手元のボタン操作で通常光からNBIモードへと切り替えます。切り替えは瞬時に行われ、患者さんが何かを感じることはありません。
検査にかかる時間と体への負担
NBIを用いた観察自体によって、検査時間が大幅に長くなることは通常ありません。観察時間は、胃カメラであれば10分から15分程度、大腸カメラであればポリープがなければ20分から30分程度が目安です。
NBIは光を切り替えるだけなので、患者さんの体に追加の負担がかかることもありません。鎮静剤を使用すれば、うとうとしている間に楽に検査を終えることも可能です。
NBI検査の安全性と留意すべき点
NBIシステムを用いた検査は、非常に安全なものですが、検査後の過ごし方など、いくつか留意すべき点があります。
従来の検査と比較した安全性
NBIは、観察に用いる光の種類を変える技術であり、体に薬剤を投与したり、特殊な放射線を使ったりするものではないため、安全性は従来の白色光による内視鏡検査と全く同等です。使用する光は可視光線の一部であり、人体に害はありません。
アレルギーの心配もなく、妊娠中や授乳中の方でも安心して検査を受けることができます。
検査後の過ごし方
検査後の注意点は、NBIの使用の有無にかかわらず、通常の内視鏡検査と同じです。鎮静剤を使用した場合は、検査後に眠気が残ることがあるため、当日は車やバイク、自転車の運転はできません。
また、生検(組織を採取)を行った場合は、出血のリスクを避けるために、当日の激しい運動や飲酒、長時間の入浴は控えるよう指示されることがあります。食事も、生検当日は刺激の少ない消化の良いものにしてください。
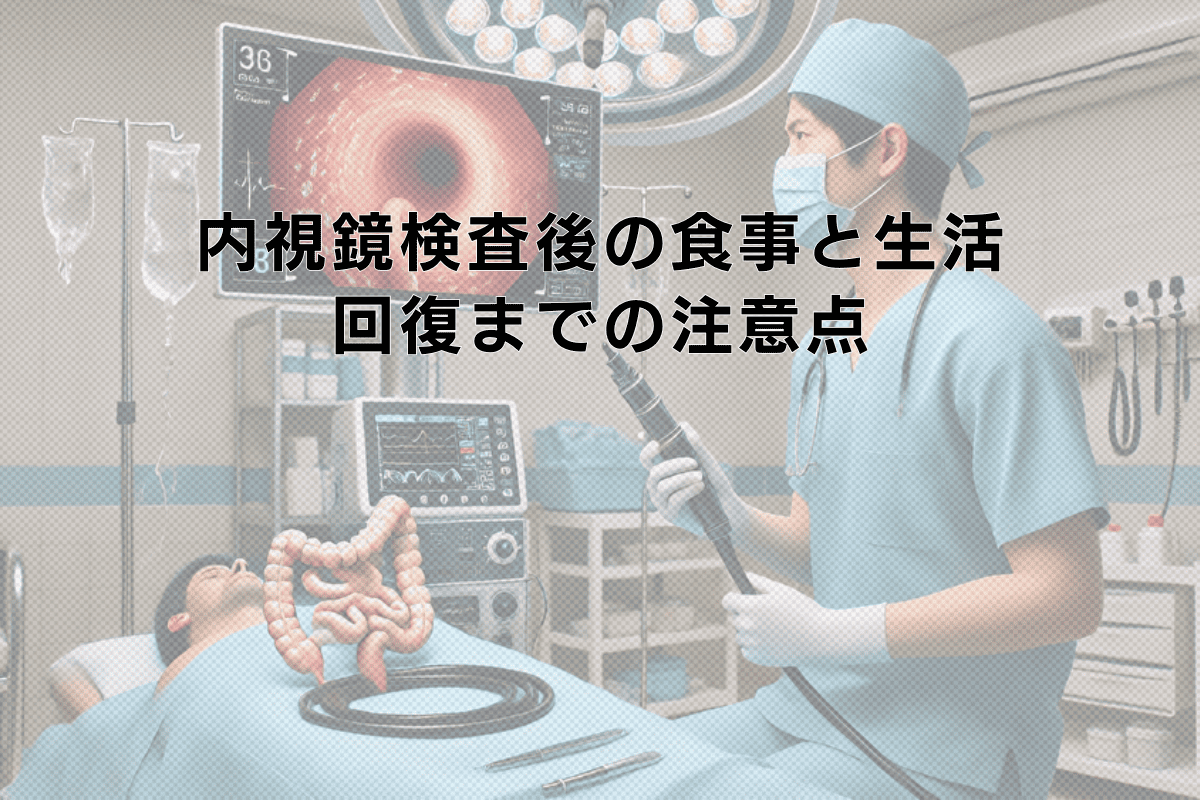
検査後に注意すべき症状
ほとんどの場合は問題なく経過しますが、まれに合併症が起こる可能性があります。
検査終了後、強い腹痛が続いたり、黒い便が出たり(胃や食道からの出血のサイン)、持続する血便が出たり(大腸からの出血のサイン)、熱が出たりした場合は、すぐに検査を受けた医療機関に連絡してください。
検査後の一般的な注意点
| 項目 | 注意内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 食事 | 喉の麻酔が切れるまで(約1時間)は飲食を控える | 誤嚥(むせること)を防ぐため |
| 運転 | 鎮静剤使用時は当日の運転を禁止する | 注意力や判断力が低下するため |
| 生活 | 生検後は激しい運動や飲酒を控える | 出血のリスクを低減するため |
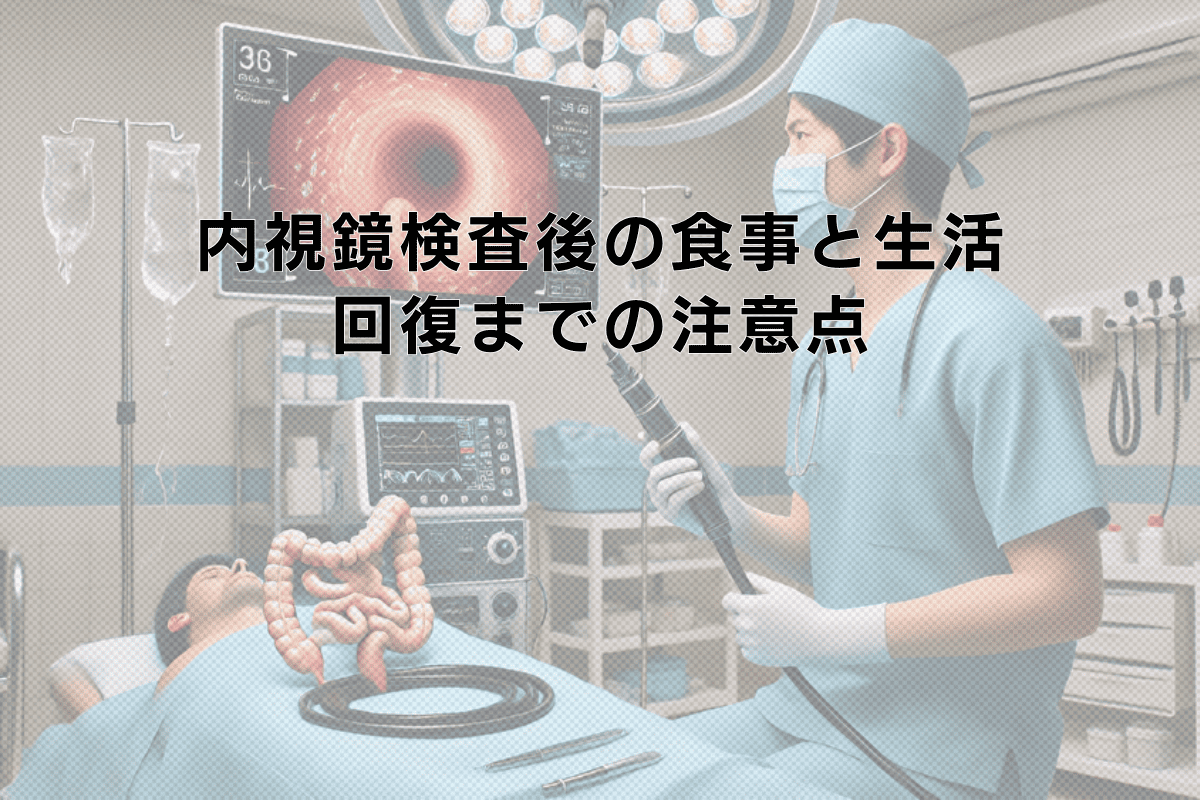
検査結果の説明について
検査で撮影された画像は、その日のうちに医師から説明を受けることが一般的です。NBIで観察した画像も見せながら、どこにどのような所見があったのか、今後の対応はどうするのかといった説明が行われます。
生検を行った場合は、病理組織診断の結果が判明するまでに1週間から2週間程度かかりますので、後日改めて結果を聞きに行くことになります。
NBIシステムに関するよくある質問
- NBI検査を受けると、検査費用は高くなりますか?
-
NBIシステムを用いた観察は、通常の内視鏡検査の一環として行われるもので、保険診療の範囲内です。条件を満たせば狭帯域光強調加算(患者3割負担で約600円)が算定される場合があります。
内視鏡検査の費用については以下の記事も参考にしてください
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
内視鏡検査の費用や保険適用の仕組み、検査内容による費用の違いについて詳しく解説しています。NBIシステムを用いた検査でも同様の費用体系となります。 - どの医療機関でもNBI検査を受けられますか?
-
NBIシステムは広く普及してきていますが、全ての医療機関に導入されているわけではありません。NBIシステムを搭載した内視鏡装置を備えている医療機関で受けることができます。
検査を希望する場合は、事前に医療機関のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりするとよいでしょう。
- NBIで観察すれば、がんは絶対に見つかりますか?
-
NBIは診断精度を大幅に向上させる優れた技術ですが、100%の診断を保証するものではありません。病変の大きさや場所、消化管内の状態(残渣や粘液の付着など)によっては、発見が困難な場合もあります。
しかし、NBIを用いることで見逃しのリスクを大きく減らせることは事実で、定期的な検査を受けることが重要です。
- NBI検査と拡大内視鏡は違うものですか?
-
NBIと拡大内視鏡は、それぞれ異なる機能を持つ技術ですが、組み合わせて使うことで相乗効果を発揮します。
NBIが特殊な光で病変を浮かび上がらせる技術であるのに対し、拡大内視鏡は画像を光学的に拡大して観察する技術です。
NBIで発見した病変を、さらに拡大内視鏡で詳しく観察することで、表面の模様や血管の形を詳細に分析し、より正確な診断に近づけることができます。
次に読むことをお勧めする記事
【内視鏡検査時の鎮静剤使用による苦痛軽減と注意事項】
NBIの利点を理解したら、実際の検査を快適に受ける工夫も知っておくと安心です。鎮静の可否や注意点を整理し、不安の少ない受診につなげます。
【内視鏡検査で使用するカメラの仕組みと特徴を解説】
NBIだけでなくBLI/LCIなどの画像強調も合わせて知ると、通常光との違いや機器の進歩が俯瞰できます。検査画像の見え方の理解が深まります。
以上
参考文献
Sano Y, Tanaka S, Kudo SE, Saito S, Matsuda T, Wada Y, Fujii T, Ikematsu H, Uraoka T, Kobayashi N, Nakamura H. Narrow‐band imaging (NBI) magnifying endoscopic classification of colorectal tumors proposed by the Japan NBI Expert Team. Digestive Endoscopy. 2016 Jul;28(5):526-33.
Sumimoto K, Tanaka S, Shigita K, Hirano D, Tamaru Y, Ninomiya Y, Asayama N, Hayashi N, Oka S, Arihiro K, Yoshihara M. Clinical impact and characteristics of the narrow-band imaging magnifying endoscopic classification of colorectal tumors proposed by the Japan NBI Expert Team. Gastrointestinal endoscopy. 2017 Apr 1;85(4):816-21.
Iwatate M, Sano Y, Tanaka S, Kudo SE, Saito S, Matsuda T, Wada Y, Fujii T, Ikematsu H, Uraoka T, Kobayashi N. Validation study for development of the Japan NBI Expert Team classification of colorectal lesions. Digestive Endoscopy. 2018 Sep;30(5):642-51.
Saito Y, Sakamoto T, Dekker E, Pioche M, Probst A, Ponchon T, Messmann H, Dinis‐Ribeiro M, Matsuda T, Ikematsu H, Saito S. First report from the International Evaluation of Endoscopic classification Japan NBI Expert Team: International multicenter web trial. Digestive Endoscopy. 2024 May;36(5):591-9.
Kobayashi S, Yamada M, Takamaru H, Sakamoto T, Matsuda T, Sekine S, Igarashi Y, Saito Y. Diagnostic yield of the Japan NBI Expert Team (JNET) classification for endoscopic diagnosis of superficial colorectal neoplasms in a large-scale clinical practice database. United European gastroenterology journal. 2019 Aug;7(7):914-23.
Sumimoto K, Tanaka S, Shigita K, Hayashi N, Hirano D, Tamaru Y, Ninomiya Y, Oka S, Arihiro K, Shimamoto F, Yoshihara M. Diagnostic performance of Japan NBI Expert Team classification for differentiation among noninvasive, superficially invasive, and deeply invasive colorectal neoplasia. Gastrointestinal Endoscopy. 2017 Oct 1;86(4):700-9.
Koyama Y, Fukuzawa M, Kono S, Madarame A, Morise T, Uchida K, Yamaguchi H, Sugimoto A, Nagata N, Kawai T, Takamaru H. Diagnostic efficacy of the Japan NBI Expert Team classification with dual-focus magnification for colorectal tumors. Surgical Endoscopy. 2022 Jul;36(7):5032-40.
Iwatate M, Ikumoto T, Hattori S, Sano W, Sano Y, Fujimori T. NBI and NBI combined with magnifying colonoscopy. Diagnostic and therapeutic endoscopy. 2012;2012(1):173269.
Hamamoto Y, Endo T, Nosho K, Arimura Y, Sato M, Imai K. Usefulness of narrow-band imaging endoscopy for diagnosis of Barrett’s esophagus. Journal of gastroenterology. 2004 Jan;39(1):14-20.
Higurashi T, Ashikari K, Tamura S, Takatsu T, Misawa N, Yoshihara T, Ninomiya Y, Okamoto Y, Taguri M, Sakamoto T, Oka S. Comparison of the diagnostic performance of NBI, Laser-BLI and LED-BLI: a randomized controlled noninferiority trial. Surgical Endoscopy. 2022 Oct;36(10):7577-87.










