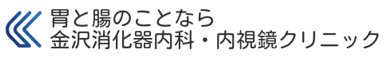下痢と血便が一度だけ生じてその後症状が治まったとしても、腸内で重大な病変が潜んでいる可能性は否定できません。
一過性の症状であっても、それが痔核の破裂によるものなのか、虚血性大腸炎のような血流障害なのか、あるいは大腸がんやポリープからの出血なのかを自己判断することは不可能です。
症状がなくなったからといって放置せず、専門医によるリスク評価を受けることが、健康を守ります。この記事では、一度きりの出血でも警戒すべき理由と、検査へ進むべき判断基準を解説します。
一度きりの下痢と血便でも大腸内視鏡検査を
一回だけの下痢や血便で症状が治まると、多くの方は一過性の不調だと考え安心してしまいますが、消化器内科の観点からは、出血が一度で止まったという事実だけで安全であるとは断言できません。
出血が自然に止まる現象は、粘膜の一時的な修復や血栓による止血が働いた結果に過ぎず、出血の原因となった病変そのものが消失したわけではないからです。
症状の消失と病変の治癒は必ずしも一致しない理由
腸管内の出血において、症状の消失は病変の治癒を意味しません。大腸憩室出血では、突然の大量出血のあとに出血が止まるケースが多く見られます。
これは憩室内の血管が破綻して出血した後、血管の収縮や血栓形成によって物理的に止血されるためですが、憩室自体は残っているため、再出血のリスクは続きます。
同様に、早期の大腸がんにおいても、腫瘍表面が崩れて出血した後に、組織修復機能が働いて一時的にカサブタのような状態になり出血が停止することがあります。
目に見える症状がなくなったとしても、腸内にある爆弾が撤去されたわけではないという認識を持つことが重要です。
粘膜の炎症と一過性の症状の関連性
腸の粘膜に炎症が起きると、粘膜は充血し脆くなり、容易に出血します。感染性腸炎や虚血性大腸炎の初期段階では、激しい下痢と共に粘膜が傷つき、鮮血が混じることがあります。
ウイルスや細菌が排出され、あるいは血流が改善することで炎症自体は沈静化し、下痢や血便も治まりますが、なぜ炎症が起きたのかという背景要因の特定が重要です。
単なる食あたりであれば良いのですが、慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)の初発症状であった場合、一度治まったように見えても、水面下で炎症がくすぶり続け、数ヶ月後にさらに重篤な状態で再発するリスクがあります。
一回の発作は、体が発している警告サインであると理解し、粘膜の状態を直接カメラで確認することが、疾患の悪化予防に推奨されます。
ハイリスクな徴候の整理
| 徴候の分類 | 具体的な症状や状況 | 想定されるリスク |
|---|---|---|
| 出血の量と性状 | 便器が真っ赤になるほどの量、あるいは凝血塊(レバー状の塊)が混じる | 大腸憩室出血、進行大腸がん、虚血性大腸炎 |
| 付随する腹部症状 | 激しい腹痛、持続する腹部違和感、残便感 | 虚血性大腸炎、腸閉塞の前兆、直腸がん |
| 全身状態の変化 | 発熱、体重減少、貧血症状(めまい、立ちくらみ) | 炎症性腸疾患、悪性腫瘍による消耗、慢性的な出血 |
見逃してはいけない隠れた病変の可能性
たった一度のことだからと放置された結果、進行した状態で発見される疾患の中に、進行大腸がんがあります。がんは初期には無症状ですが、ある程度の大きさになると表面が崩れて出血しますが、毎日続くとは限りません。
一度の血便をきっかけに内視鏡検査を受けた患者さんの中に、無症状の早期がんや、将来がん化するリスクの高い腺腫性ポリープが発見されるケースは日常的に経験します。
早期発見であれば内視鏡的な切除だけで完治が可能ですが、放置すれば開腹手術や抗がん剤治療が必要な段階へと進行してしまいます。
一過性の症状でも内視鏡検査を強く推奨する症状の組み合わせ
| 症状の組み合わせ | 背景にあるリスク | 検査の緊急度 |
|---|---|---|
| 激しい腹痛後の鮮血 | 虚血性大腸炎、大腸憩室出血 | 中〜高 |
| 粘液と血液の混入(粘血便) | 炎症性腸疾患(IBD)、重症感染症 | 高 |
| 40歳以上で無痛性の出血 | 大腸ポリープ、早期大腸がん | 中〜高(早期対応が必要) |
下痢と血便を同時に起こす主な疾患と病態
下痢と血便が同時に起こるという状況は、腸管内で水分吸収障害と粘膜傷害が同時に進行していることを示唆します。
大腸は通常、便から水分を吸収して固形化する役割を担っていますが、何らかのダメージを受けるとこの機能が低下し下痢となり、同時に粘膜が傷つくことで出血を伴います。
虚血性大腸炎による突然の腹痛と血便
高齢の方や便秘がちの方に多く見られるのが虚血性大腸炎で、大腸の粘膜へ送られる血流が一時的に低下し、虚血(酸欠)状態になることで粘膜が壊死し、炎症を起こす疾患です。
典型的な発症パターンは、突然の激しい腹痛に襲われ、その後に下痢、そして血便へと移行します。急激な血圧低下や便秘による腹圧上昇などが引き金となり、トイレで力んだ直後などに起こりやすいのが特徴です。
軽症であれば数日で安静にしていれば治癒し、血便も一回や数回で止まることが多いですが、重症化すると腸管壊死や狭窄をきたすこともあります。
一回で治まったとしても、動脈硬化などの血管系のリスク因子を抱えている可能性を示唆しているため、診断を確定させることが大切です。
疾患ごとの特徴的な症状
| 疾患名 | 痛みの特徴 | 便の性状と傾向 |
|---|---|---|
| 虚血性大腸炎 | 左下腹部に突然の激痛が走ることが多い | 最初は下痢、続いて鮮血や粘血便が出る |
| 感染性腸炎 | キリキリとした痛み、発熱を伴うことが多い | 水様便、悪臭、粘液混じりの血便 |
| 潰瘍性大腸炎 | 排便前のしぶり腹(テネスムス)、持続的な鈍痛 | 粘液と血液が混ざった泥状の便、頻回な便意 |
感染性腸炎における一過性の症状
カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌(O157など)といった細菌や、ノロウイルスなどのウイルスによる感染性腸炎も、下痢と血便の原因です。
カンピロバクター腸炎は、加熱不十分な鶏肉などを摂取してから数日後に発症し、激しい腹痛と血便を伴うことがありますが、免疫機能が正常であれば自然治癒に向かい、血便も一回限りで終わることもあります。
血便が出ている時点で腸管粘膜は強い炎症を起こしており、原因菌を特定し適切な抗生物質が必要か、あるいは二次感染を防ぐ手立てが必要かを判断する必要があります。
自己判断で市販の下痢止めを使用すると、菌を体内に閉じ込めてしまい症状が悪化することもあるため注意が必要です。
大腸憩室出血の病態
大腸の壁の一部が袋状に外側に飛び出したものを憩室(けいしつ)と呼びます。
憩室は加齢とともに増加し、憩室の底にある血管は壁が薄く傷つきやすい状態になっていて、何らかの拍子にこの血管が破れると、痛みを伴わずに突然大量の血便が出ることがあります(大腸憩室出血)。
特徴的なのは腹痛がないことであり、大量の血液が下剤のような働きをして下痢のように排出されます。出血は7割から8割程度のケースで自然に止まりますが、再出血率が高い疾患です。
一度止まったからといって放置すると、次はショック状態になるほどの大量出血を起こす可能性があるため、内視鏡検査で出血源を特定し、必要であればクリップで止血処置を行うことが安全策となります。
特に高齢者で、一過性の大量出血が見られた場合、まずこの疾患を疑います。
年齢と家族歴のリスク評価
血便や下痢が一回だけであった場合、直ちに内視鏡検査を行うべきか、あるいは経過観察とするかの判断において、患者さんの年齢と家族歴は極めて重要な決定因子となります。
40歳以上という年齢の境界線
大腸がんの罹患率は40歳代から増加し始め、50歳代以降で急激に上昇カーブを描くので、40歳以上の方が血便を認めた場合、それが例え一回だけであったとしても、大腸がんの可能性を念頭に置いた検査計画が必要です。
若い世代、例えば20代であれば、血便の原因は感染性腸炎や痔核である確率が高いですが、40歳を超えるとポリープやがんの確率が統計的に無視できなくなります。
年齢は変更不可能なリスク因子であり、40歳という年齢を一つの区切りとして、体のメンテナンスという意味でも内視鏡検査を受ける動機付けとするのが賢明です。
これまでに一度も大腸内視鏡検査を受けたことがない40歳以上の方は、検査を受けることを強く推奨します。無症状であっても、この年代は定期的なスクリーニング検査の対象です。
遺伝的要因と大腸がんリスク
血縁者に大腸がんや大腸ポリープを患った方がいる場合、遺伝的な体質として大腸に病変ができやすい可能性があります。
特に親、兄弟姉妹、子供といった第一度近親者に大腸がんの方がいる場合、自身の大腸がん発症リスクは一般の方と比較して2倍から3倍高くなると言われています。
また、リンチ症候群のような遺伝性腫瘍の家系であれば、若年での発症リスクも考慮しなければなりません。家族歴をお持ちの方に対しては、一回の血便や下痢であっても様子を見ましょうとは言わず、積極的に内視鏡検査を提案します。
遺伝的背景は変えられませんが、早期発見による介入は可能です。
リスク因子別の検査推奨度
- 40歳以上である(がん年齢への到達)
- 家族に大腸がんやポリープの治療歴がある
- 過去に大腸ポリープを指摘されたことがある
- 肥満傾向にある、または過度なアルコール摂取の習慣がある
生活習慣と腸内環境の関連
年齢や遺伝以外にも、生活習慣がリスク評価に影響を与えます。赤身肉や加工肉の過剰摂取、食物繊維不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒は、すべて大腸がんのリスクを高める要因です。
日頃から便秘と下痢を繰り返している、あるいは排便習慣が不規則であるといった背景がある中で、血便と下痢のエピソードが起きた場合、長年の生活習慣による腸への負担が表面化したサインかもしれません。
医師は問診で生活習慣についても聴取し、総合的なリスク判定を行います。不摂生な生活習慣の自覚がある場合は、症状が一回で治まったとしても、生活習慣の改善を促す意味で検査を受ける価値は十分にあります。
普段の便の状態と潜むリスクの目安
| 普段の便の傾向 | 今回の症状の解釈 | 内視鏡検査の意義 |
|---|---|---|
| 慢性的な便秘傾向 | 便秘による内圧上昇で痔や憩室出血を起こした | 痔や憩室、直腸の病変の確認 |
| 軟便や細い便が多い | 通過障害による症状か、炎症の兆候 | 大腸全体の運動機能や狭窄の有無の確認 |
| 普段から規則正しい | 突発的な病態(感染、虚血)か、がんの初期出血 | 炎症や腫瘍性病変の厳密な否定 |
血便の色調と量が語る出血源の特定
患者様が目撃した血の色や量は、出血部位を推定する上で極めて有用な情報源です。一回だけの下痢便に混じった血がどのような色をしていたか、どの程度の量であったかを医師に正確に伝えることで、診断の精度は向上します。
鮮血と暗赤色便の違いが意味するもの
血液の色は、出血してから肛門から排出されるまでの時間が短いほど鮮やかな赤色(鮮血)になります。
肛門に近い直腸やS状結腸からの出血であれば、真っ赤な血が付着したり、ポタポタと垂れたりし、これは主に痔核や直腸の炎症、あるいはS状結腸の病変が疑われるケースで多い色調です。
肛門から遠い大腸の奥(盲腸や上行結腸)からの出血であれば、血液が腸の中を移動する間に酸化し、便と混ざり合うため、暗赤色(あずき色やワインレッドのような色)になります。
一回だけの下痢に暗赤色の血便が出た場合は、大腸の奥の方での出血や、小腸からの出血の可能性も視野に入れる必要があり、内視鏡検査で全大腸を観察する意義がより強まります。
血便の色調と想定される出血部位
| 血便の色調 | 考えられる出血源 | 主な原因疾患の例 |
|---|---|---|
| 鮮血(真っ赤) | 直腸、肛門、S状結腸 | 内痔核、切れ痔、直腸がん、潰瘍性大腸炎(直腸型) |
| 暗赤色(赤黒い) | 大腸全体、特に右側結腸 | 大腸憩室出血、虚血性大腸炎、進行大腸がん |
| 黒色便(タール便) | 胃、十二指腸、食道 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん(胃カメラの適用) |
粘血便という特殊な状態
単なる血液だけでなく、鼻水のようなドロドロとした粘液が血液と混ざっている状態を粘血便と呼び、これは腸の粘膜が強い炎症を起こしている際に見られる特徴的な所見です。
正常な腸からも便を滑らかにするための粘液は分泌されていますが、炎症が起きると過剰に分泌され、そこに出血が混じることでイチゴジャムのような見た目になることがあります。
粘血便が見られた場合は、痔などによる物理的な出血ではなく、潰瘍性大腸炎やクローン病、重篤な感染性腸炎などの炎症性疾患を強く疑います。
たとえ一回の排便だけであったとしても、粘血便が確認されたならば、早急に専門医の診察を受ける必要があります。炎症性腸疾患の初期症状として見られることもあり、その後の治療方針を決定するためにも粘血便の有無は重要です。
出血量と緊急性の相関
トイレットペーパーに少しつく程度なのか、便器の水が真っ赤に染まるほどなのか、出血の量も重要です。一般的に、少量の出血であれば緊急性は低いことが多いですが、それでもがんやポリープの否定はできません。
逆に、一回だけであっても洗面器一杯分のような大量出血があった場合や、立ちくらみを伴うような出血があった場合は、大腸憩室出血などの動脈性出血の可能性があり、直ちに医療機関を受診する必要があります。
大量出血は貧血やショックを引き起こす可能性があるため、緊急性が高いです。
痛みの有無と種類による緊急度の判定
血便と下痢が生じた際、腹痛を伴っていたかどうかは、原因疾患を絞り込む上で決定的な手がかりとなります。痛みは体が発する危険信号ですが、疾患によっては全く痛みを伴わずに進行するものもあります。
排便時の痛みとしぶり腹
排便時に肛門付近に鋭い痛みが走る場合は、裂肛(切れ痔)の可能性が高いですが、下痢に伴って腹部全体が痛む場合は腸管の収縮による痛み(仙痛)が考えられます。特に注意が必要なのはしぶり腹(テネスムス)と呼ばれる症状です。
これは、便意があってトイレに行っても少ししか出ない、あるいは出ないのにお腹が痛い、便が出きっていない感じがして何度もトイレに行きたくなる状態を指します。
しぶり腹に血便が伴う場合、直腸がんや潰瘍性大腸炎による直腸の炎症が強く疑われ、不快な感覚が一回だけでなく続くようであれば、直腸診や内視鏡検査による確認が必要です。直腸付近の病変は早期に自覚症状が出やすいという特徴もあります。
腹痛のパターンと疑われる病態
| 痛みの性質 | 痛みの発生タイミング | 関連する可能性が高い疾患 |
|---|---|---|
| 突然の激痛(左側) | 排便前後や安静時 | 虚血性大腸炎 |
| 間欠的な痛み(波がある) | 食事後や排便前 | 腸閉塞(イレウス)の前兆、感染性腸炎 |
| 痛みなし(無症状) | 突然の出血時 | 内痔核、大腸憩室出血、早期大腸がん |
無痛性の血便が持つ危険性
痛みを伴う血便は患者さん本人も危機感を抱きやすいのですが、逆に注意が必要なのは痛くない血便です。内痔核(いぼ痔)は痛みを感じない部分に出血を起こすため、排便時に血が飛び散っても痛くありません。
また、大腸がんやポリープからの出血も、基本的に痛みを伴いません。腸の粘膜には痛みを感じる神経がないため、がんが大きくなって腸閉塞を起こしたり、周囲の組織に浸潤したりするまでは無症状で経過し、大腸憩室出血も同様に無痛です。
痛くないから大丈夫ではなく、痛くない血便こそ、内視鏡で原因をはっきりさせる必要があると認識を変えることが大切です。一回だけの下痢と無痛性の血便は、静かに進行する病気のサインである可能性があります。
全身症状を伴う場合のアラート
腹痛だけでなく、発熱、倦怠感、体重減少などの全身症状が伴う場合は、体全体に影響を及ぼす疾患が隠れていることがあります。微熱が続き下痢と血便がある場合は、クローン病や結核性腸炎なども鑑別に挙がります。
また、短期間で意図しない体重減少がある場合は、悪性腫瘍による消耗や、炎症による栄養吸収障害を疑います。特に体重減少は、進行した悪性疾患や慢性炎症性疾患の重要なサインです。
一回の血便エピソードをきっかけに、最近の体調変化を振り返ってみてください。もし、全身症状のサインが一つでも当てはまるなら、消化器内科医による全身的な評価と大腸内視鏡検査を組み合わせた診断が必要です。
大腸がんを見逃さないための検査
血便が大腸がんではありませんが、大腸がんの初期症状として血便が現れることは事実です。日本において大腸がんは、がんによる死亡数の上位を占める疾患ですが、早期発見・早期治療を行えば完治が望める病気でもあります。
便潜血検査と内視鏡検査の決定的違い
健康診断で行われる便潜血検査は、便に混じった微量の血液を検出するスクリーニング検査です。手軽で費用も安いですが、あくまで出血があるかどうかを見るものであり、どこから、何が原因で出血しているかまでは分かりません。
また、痔出血でも陽性になりますし、出血していないタイミングの便を提出すれば、進行がんがあっても陰性と判定される(偽陰性)可能性があります。
一方で大腸内視鏡検査は、医師が直接粘膜を観察するため、微小なポリープや平坦な病変、色調の変化を捉えることができます。
一回でも目に見える血便(肉眼的血便)があった場合は、便潜血検査を飛ばして、最初から内視鏡検査を行うことが診断のゴールドスタンダードです。
検査手法による精度の比較
| 比較項目 | 便潜血検査(検診) | 大腸内視鏡検査(精密検査) |
|---|---|---|
| 検査の目的 | 出血の有無をふるい分ける | 病変の確定診断と治療方針の決定 |
| 検出能力 | 出血していない病変は見逃す | 出血していない平坦な病変も発見可能 |
| 処置の可否 | 検査のみ | その場でポリープ切除や組織採取が可能 |
ポリープ発見と切除によるがん予防
大腸がんの多くは、腺腫(アデノーマ)と呼ばれる良性のポリープが数年かけて増大し、一部ががん化することで発生します(アデノーマ・カルチノーマ・シークエンス)。
つまり、良性のポリープの段階で内視鏡を使って切除してしまえば、将来そのポリープががんになる芽を摘むことができ、これはクリーンコロン(ポリープのない大腸)を目指す予防的治療です。
血便をきっかけに検査を行い、出血源とは関係のない別の場所にポリープが見つかることも多々あり、良性ポリープを切除することで、大腸がんの発生リスクを大幅に下げることができます。
早期発見が生存率に与えるインパクト
大腸がんは進行度(ステージ)によって生存率が大きく変わります。ステージ0やステージ1の早期段階で発見されれば、5年生存率は90%を超え、多くは内視鏡治療や腹腔鏡手術などの低侵襲な治療で完治します。
しかし、症状を放置し、貧血や腹部腫瘤(しこり)を自覚するほど進行してから発見されると、予後は厳しくなります。進行度が高くなるほど、手術だけでなく化学療法や放射線療法の併用が必要となり、身体的な負担も大きくなります。
一回だけの下痢と血便は、体が発してくれた早期のアラームかもしれません。このサインを治ったからと無視することなく、専門医を受診してください。
大腸がんの進行度別5年生存率と検査の役割
| 進行度(ステージ) | 5年生存率(目安) | 内視鏡検査の役割 |
|---|---|---|
| ステージ0・1(早期) | 90%以上 | 内視鏡的切除で完治を目指す |
| ステージ2(進行) | 80%前後 | 発見と手術適応の判断 |
| ステージ3(リンパ節転移) | 60%〜70% | 早期発見による生存率向上に貢献 |
大腸内視鏡検査の流れと負担軽減の工夫
内視鏡検査は痛い、恥ずかしい、準備が大変といったイメージが、受診の足かせになっていることが少なくありませんが、大腸内視鏡検査は以前に比べて格段に苦痛が少なく、楽に受けられるものへと変化しています。
検査当日の準備と下剤服用
正確な検査を行うためには、大腸の中を空っぽにして、粘膜のひだの裏まで観察できる状態にする必要があるため、検査当日の朝から(あるいは前日から)腸管洗浄液(下剤)を服用します。
以前は不味くて量が多いと言われていた下剤も改良が進み、味が飲みやすくなったり、飲む量が減ったり、錠剤タイプが選べたりと選択肢が増えています。トイレに数回通い、便が透明な水の状態になれば準備完了です。
自宅で飲むのが不安な方のために、院内で下剤を服用できるスペースを設けている医療機関も増えています。飲みにくい場合は、冷やしたり、味のついた水や飴で口直しをしながら服用する方法もあります。
苦痛を和らげるための現代的な手法
| 手法 | 目的と効果 | 患者様のメリット |
|---|---|---|
| 鎮静剤の使用 | 意識レベルを下げてウトウトした状態にする | 痛みや不安を感じずに検査が終了する |
| 炭酸ガス送気 | 腸を膨らませる空気を吸収されやすいCO2にする | 検査後のお腹の張りや痛みが速やかに解消する |
| 高解像度スコープ | 微細な血管構造や表面模様を強調表示する | 短時間で正確な診断が可能になり検査時間が短縮 |
鎮静剤を使用した検査の実際
多くの消化器内科クリニックでは、希望に応じて静脈麻酔(鎮静剤)を使用しており、点滴から少量の薬を入れることで、軽く眠っているような、あるいはリラックスしてボーッとしているような状態で検査を受けることができます。
医師と会話ができる程度の深さから、完全に寝てしまう深さまで調整が可能です。鎮静剤を使用すれば、スコープが腸の曲がり角を通過する際の圧迫感や不快感をほとんど感じることなく検査を終えられます。
検査中は体の向きを変える指示がある程度で、ほとんど眠った状態で全てが進行し、検査後は薬の効果が切れるまでリカバリールームで1時間ほど休憩してから帰宅です。
検査結果の説明と治療方針の決定
検査が終了し、休憩後に意識がはっきりしてから、撮影した画像を見ながら医師から結果の説明を受けます。
異常がなければ次は数年後で大丈夫ですと安心を得られますし、ポリープが見つかりその場で切除した場合は、病理検査の結果を後日聞くことになります。
もし炎症やがんが疑われる病変が見つかった場合は、組織を一部採取(生検)し、確定診断を行います。
大腸内視鏡検査に関するよくある質問
- 検査はどれくらいの時間がかかりますか?
-
観察のみであれば通常15分から20分程度で終了しますが、腸の長さや形状には個人差があり、癒着がある方などは挿入に時間がかかる場合があります。
また、ポリープが見つかりその場で切除を行う場合は、数や大きさによってさらに処置時間が追加されます。
検査前の着替えや点滴の準備、検査後の休憩時間(鎮静剤使用時)を含めると、来院から帰宅までは半日程度(3時間から4時間)を見ておくとよいでしょう。
- 生理中でも大腸内視鏡検査は受けられますか?
-
基本的には生理中でも問題なく検査を受けていただけます。大腸内視鏡は肛門からの挿入であり、膣とは経路が異なりますので検査手技に影響はありません。
検査中は専用の検査着(お尻の部分にスリットが入ったパンツ)を着用していただき、生理用品を使用したままでも検査は可能です。ただし、生理痛が酷い場合などは無理をせず、日程変更をご相談ください。
- 鎮静剤を使った場合、車で帰ることはできますか?
-
鎮静剤を使用した当日は、ご自身での車、バイク、自転車の運転は法律的にも医学的にも禁止されています。薬の影響で判断能力や反射神経が一時的に低下しており、事故につながる危険性が高いためです。
当日は公共交通機関、タクシー、またはご家族の送迎でご来院ください。運転が必要な事情がある場合は、鎮静剤を使用せずに検査を行うことになりますので、事前に医師へご相談ください。
- 下剤を全部飲めるか不安ですが大丈夫でしょうか?
-
以前に比べて飲みやすい下剤が開発されていますが、どうしても味や量が苦手という方もいらっしゃいます。そのような場合は、コップ一杯の水と共に服用する錠剤タイプの下剤を選択できることもあります。
また、どうしても飲みきれない場合や、途中で気分が悪くなった場合は、無理をせず直ちにスタッフへお申し出ください。
追加の水分摂取や浣腸の併用など、患者さんの状況に合わせた対応を行い、排便状態を確認しながら検査が可能かどうかを判断します。
以上
参考文献
Jin D, Liao X, Chen Y. A Rare Case of Bloody Diarrhea With a Rare Cause. Gastroenterology. 2024 Jul 1;167(2):213-7.
Holtz LR, Neill MA, Tarr PI. Acute bloody diarrhea: a medical emergency for patients of all ages. Gastroenterology. 2009 May 1;136(6):1887-98.
Brandt LJ. Bloody diarrhea in an elderly patient. Gastroenterology. 2005 Jan 1;128(1):157-63.
Al-Shamali MA, Kalaoui M, Hasan F, Khajah A, Siddiqe I, Al-Nakeeb B. Colonoscopy: evaluating indications and diagnostic yield. Annals of Saudi medicine. 2001 Sep;21(5-6):304-7.
Sujatha-Bhaskar S, Grigorian A, de Virgilio C. Fatigue and Bloody Diarrhea. InSurgery: A Case Based Clinical Review 2019 Oct 17 (pp. 303-309). Cham: Springer International Publishing.
TABRIZ CH, ZAHEDI M, HAYATBAKHSH AM, Jafari E, HAGHDOUST A, Hosseini SH. Frequency and distribution of microscopic findings in patients with chronic non-bloody diarrhea and normal colonoscopy.
Lu PH. Umbilical region pain, diarrhea, and bloody stools. Gastroenterology. 2011 Jan 1;140(1):e1-2.
Tsang L, Banerjee N, Tabibian JH. Bloody diarrhea and weight loss in a patient in remission from ulcerative colitis. Gastroenterology. 2019 Nov 1;157(5):1207-9.
Mantzaris GJ, Hatzis A, Archavlis E, Petraki K, Lazou A, Ladas S, Triantafyllou G, Raptis SA. The role of colonoscopy in the differential diagnosis of acute, severe hemorrhagic colitis. Endoscopy. 1995 Nov;27(09):645-53.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.