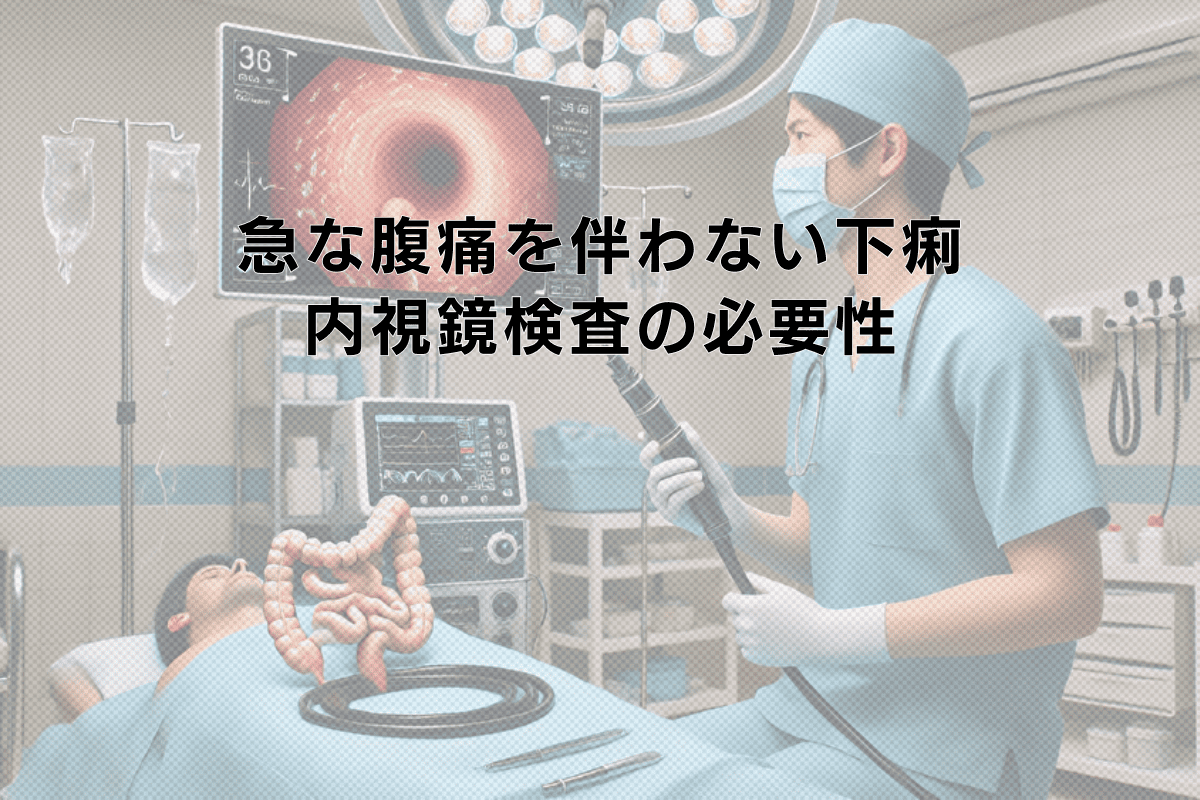食事や生活リズムを大きく変えていないのに、急に下痢が始まってしまうことがある方も少なくありません。しかも腹痛を伴わない場合、原因が特定しにくく、放置してしまうことがあります。
こういう場合、腸内環境の乱れやストレス、さまざまな病気の初期サインなど、いくつもの要因が潜んでいる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、腹痛をともなわずに突然下痢が起こる理由と、対策を中心に解説し、内視鏡検査の重要性にも触れます。検査タイミングを知り、体調管理や受診への意識を高めていただくきっかけになれば幸いです。
急に始まる下痢と腹痛がない状況とは
急な下痢にもかかわらず腹痛をあまり感じない、あるいは全く痛みがない状態は不思議に思われるでしょう。体調不良を起こすほどの下痢であれば、通常は腹部の不快感や痛みを伴うケースが多いからです。
しかし、痛みの感じ方や原因となるメカニズムは人によって異なるため、必ずしも強い痛みは出ません。
腸の過度な蠕動が痛みを伴わない例
腸が敏感に動きすぎる場合、水分の吸収が不十分になり便が水っぽくなります。過敏性腸症候群などでは腹痛を強く感じる人が多いですが、まれに腸が過度に動いているにもかかわらず痛みをそれほど感じないケースもあります。
自律神経のバランスが影響する場合
自律神経の乱れが原因となって下痢が急に起こることがあります。交感神経と副交感神経がうまく切り替わらないと、腸内が刺激を受けやすくなり、水分吸収が阻害されて下痢になります。
痛みの神経伝達にも影響が出るため、腹痛を強く感じないことがあります。
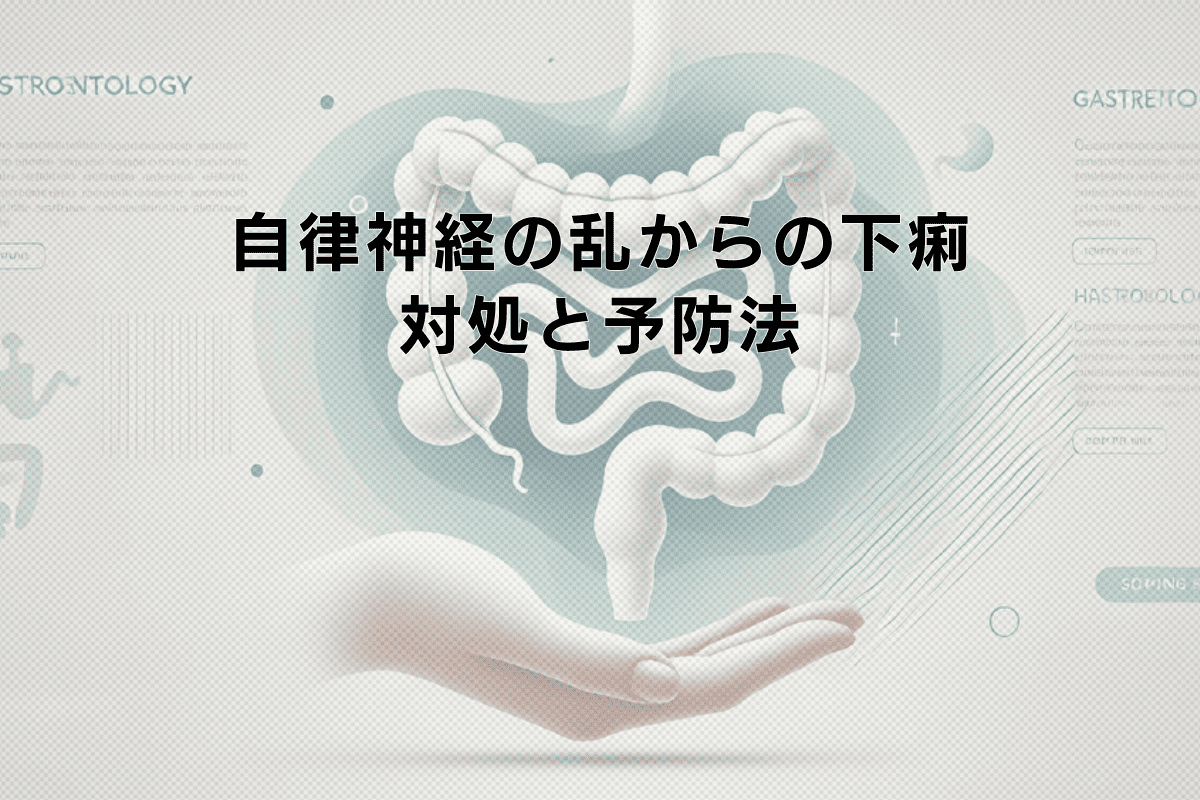
食事内容による軽微な炎症
脂肪分が多い食事や刺激の強い食品を摂取すると、腸内で軽い炎症が起こり、便がゆるくなりますが、炎症の度合いが軽度の場合、腹痛をあまり感じずに急な下痢だけが発生することがあります。
ストレスが引き金の下痢と痛みの感受性
ストレスが腸に大きく影響すると、多くの場合は下痢や便秘が交互に現れるなどの症状を起こしますが、人によっては痛みを自覚しにくいケースがあり、突然の下痢だけが目立つこともあります。
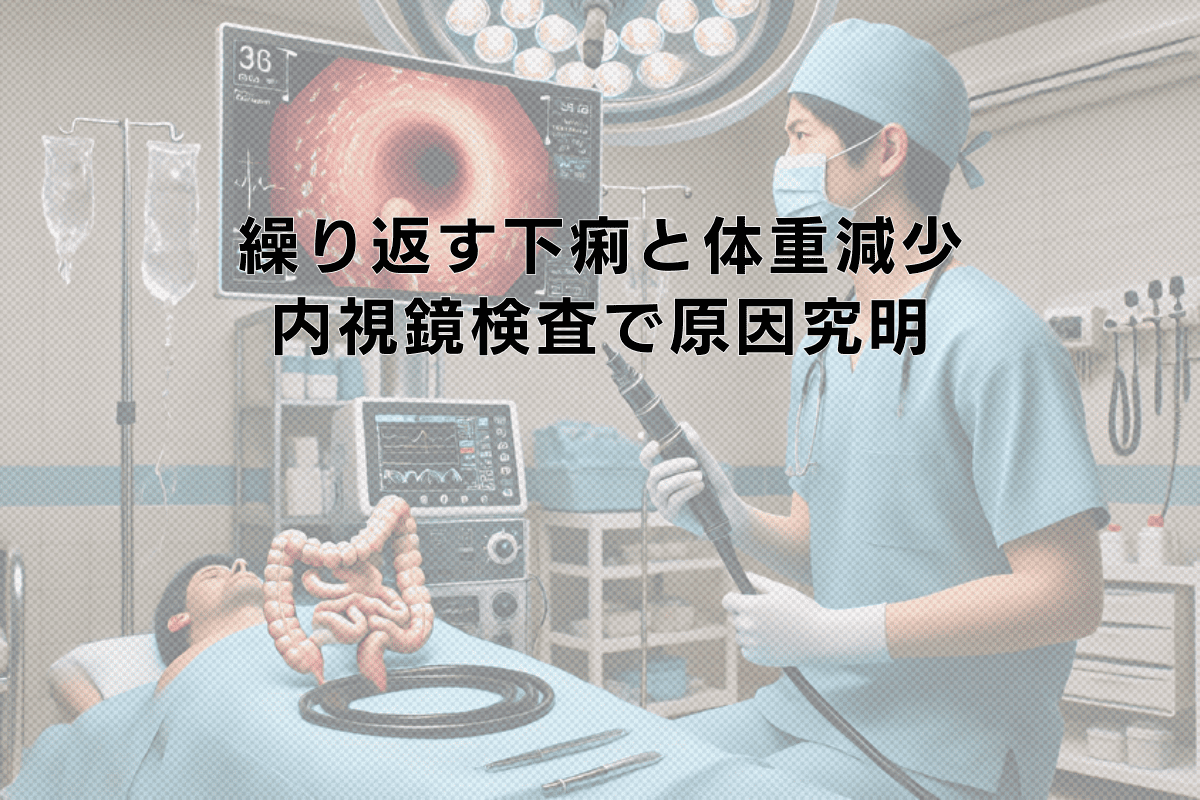
急な下痢が起こるタイミング
| タイミング | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| 朝起きた直後 | 睡眠による自律神経の変動で腸が敏感になる | 起床後すぐの排便に意識を向ける |
| 食事中または食後 | 食事による胃結腸反射が大きく働く | 食物繊維や脂肪の摂り方に注意 |
| 強いストレスにさらされた後 | 急に心配事や緊張状態に置かれた | ストレス管理と腸内環境との関連を考慮 |
| 急激な気温変化を感じたとき | 冷房の効きすぎや冬期の温度差など | 温度差が腸の自律神経を乱す原因になる |
下痢の原因が腹痛を伴わない理由
腹痛を伴う下痢はよく知られていますが、痛みをほとんど感じない下痢も珍しくありません。原因を理解することで、症状を長引かせないためのヒントが得られます。
痛みと下痢のメカニズムの違い
下痢は腸内で水分吸収が追いつかず便が水様化する状態です。一方の腹痛は腸が伸縮したり炎症が起こるときの神経刺激で起こります。この2つは密接に関連する場合が多いですが、同時に起きるとは限りません。
痛覚が鈍感になる背景
疲労やストレスがたまった状態では、体内のホルモンバランスが崩れ、痛覚が麻痺気味になることがあります。腸の異変を感じても、脳が強い痛みとして認識しない場合、下痢だけが前面に出てしまうことがあります。
軽度の炎症や感染症の場合
下痢の原因が軽度の感染症や炎症のとき、腸粘膜に浅い傷や細菌の増殖があっても痛みが少ないことがあり、本人が気づかないうちに自然回復する例もありますが、長引くと別の症状が出るかもしれません。
ダイエットや食生活の変化
急激に食物繊維を増やしたり、極端なダイエットをすると腸内の活動が急に活発化し、下痢を起こすことがあります。腹痛をともなう強い炎症ではなくても、水様便が続くと栄養バランスの乱れにつながりやすいです。
腹痛を伴わない下痢の原因
| 原因 | メカニズム | 補足 |
|---|---|---|
| ストレス過多 | 自律神経の乱れによる蠕動運動の亢進 | 痛みを感じにくい状態が続く場合あり |
| 食事性の軽い炎症 | 食物繊維・脂肪の摂りすぎによる腸への負担 | 下痢の回数は増えるが腹痛があまりない |
| 軽度の細菌・ウイルス感染 | 腸粘膜の軽微な炎症、自然免疫で回復可能 | 痛みを伴わないまま下痢だけが出続けることも |
| 内臓感覚の低下 | 痛覚の伝達がうまく行われない | 過度な疲労やストレスが関係する場合あり |
急な下痢のタイプ別にみる症状
腹痛がない下痢は、原因によって症状の現れ方が異なり、人によって特徴が変わるため、自分に合った対応策を見つけることが大切です。
突発的に下痢が出るタイプ
突然トイレに駆け込みたくなるほどの下痢が生じても、腹痛や腹部の違和感がほとんどない場合があります。精神的なプレッシャーや環境要因の影響が大きく、ストレスフルな状態で発症しやすいです。
水様性の下痢が続くタイプ
連続して水分量の多い便が出る状態で、回数が多くなるのが特徴です。ウイルス性の感染や食事の偏りなどが原因になることが多く、腹痛がないからと軽視すると脱水や栄養不足を起こしやすいです。
形がある軟便が断続的に出るタイプ
便が半固形~軟らかい状態で出るタイプは、腸の蠕動運動が活発になったり、腸内細菌叢が乱れていたりする可能性があります。体調によって硬さが変わる場合もあり、慢性的に続く場合は要注意です。
朝方に集中して下痢が起こるタイプ
朝方に腸が過剰に反応し、通勤通学前に何度も下痢を繰り返すことがあります。自律神経の変動に加え、朝食やコーヒーなどが刺激になる場合もあるため、朝方の習慣を見直すと改善する例も少なくありません。
急な下痢のタイプ
| タイプ | 症状の特徴 | 想定される原因 |
|---|---|---|
| 突発的な下痢 | 一気に便意が襲い、腹痛なしで排出される | 強いストレス、腸内細菌バランス |
| 水様性下痢が連続する | 何度も水のような便が出る | 食事の偏り、軽度の感染症 |
| 軟便が断続的に出る | 半固形の便が続き、ときどき形状が変化 | 過敏性腸症候群、腸内環境の乱れ |
| 朝方に集中して下痢になる | 朝起きた直後や食後に複数回下痢が起こる | 自律神経の変化、習慣の影響 |
急な下痢への対処法のポイント
- 水分補給をこまめに行う
- 過度な食物繊維や脂肪を控え、バランスの良い食事を意識する
- ストレス源を減らし、適度に休息を取る
- 症状が長引く場合や急激に悪化する場合は医療機関への相談を考える
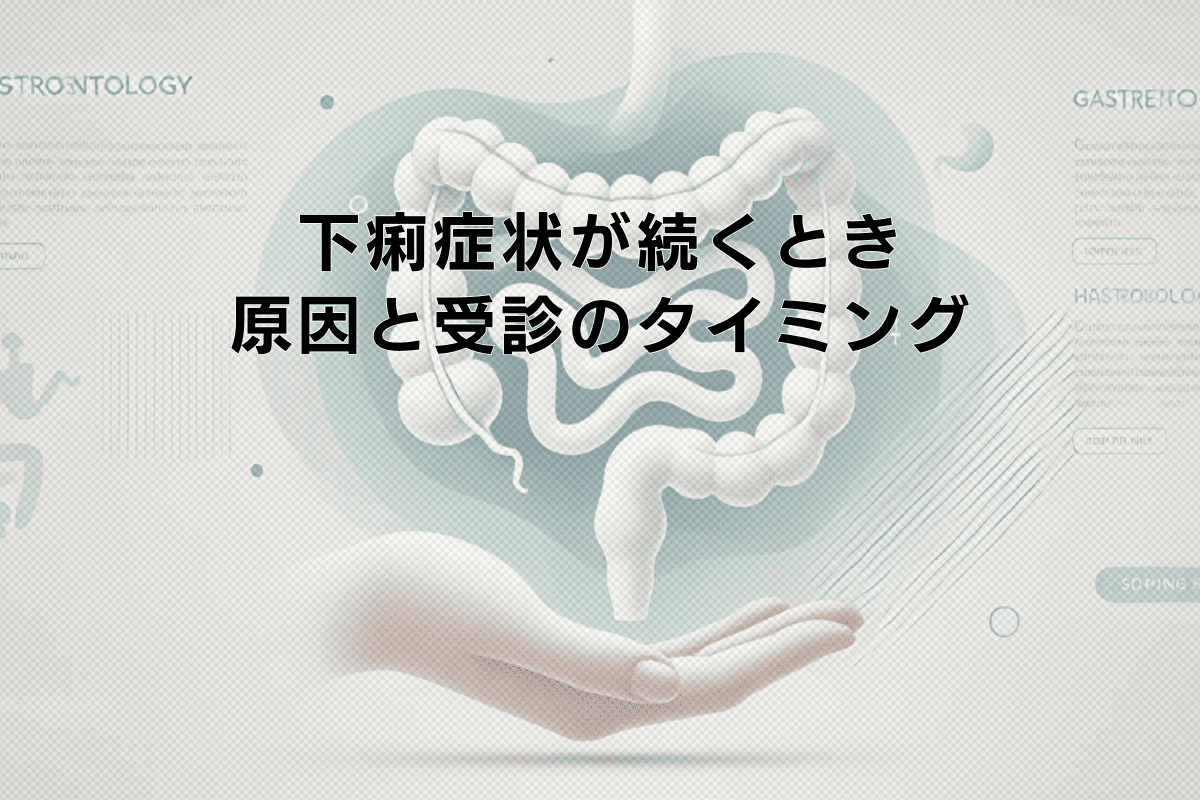
腹痛がない下痢が続くときに疑うべき病気
痛みをあまり感じないからといって放置していると、重篤な病気を見落とすリスクがあります。腹痛が目立たなくても、下痢が長期化する場合は注意が必要です。
炎症性腸疾患の初期症状
潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患は、腹痛がはっきりと感じられることもあれば、軽度の痛みしか出ない場合もあります。
下痢の頻度が多いわりに痛みを伴わない場合は、粘血便や体重減少などの他の症状がないかチェックしてください。
大腸ポリープや大腸がん
大腸ポリープは良性のものが多いですが、がん化する可能性があります。また大腸がんの初期段階では下痢や便秘などの便通異常がみられることがあり、腹痛をそれほど感じないまま症状が進行することがあります。
過敏性腸症候群とストレス関連
過敏性腸症候群は、下痢や便秘が繰り返し起こる機能性の腸疾患です。
ストレスが大きいときに症状が悪化する傾向がありますが、腹痛の程度には個人差があるため、特に痛みが少なく水様便のみが目立つ場合は医療機関で詳しい検査を検討しましょう。
腸内細菌バランスの乱れによる長期化
抗生物質の長期服用や食習慣の偏りにより、腸内細菌叢が大きく乱れると下痢が続く場合があり、痛みが少ないからといって自然治癒を待っていると、慢性化しやすいため注意が大切です。
長引く下痢が疑われる主な病気
| 病気名 | 主な特徴 | 受診時のポイント |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 血便や粘液便を伴うことが多い | 腸内視鏡検査で炎症範囲を確認 |
| クローン病 | 口から肛門まで炎症の可能性 | 下痢だけでなく、体重減少にも注目 |
| 大腸ポリープ | 良性だが放置でがん化リスクあり | 内視鏡検査で切除や生検が可能 |
| 大腸がん | 便通の変化や血便、体重減少など徐々に進行 | 早期発見により治療効果が期待できる |
| 過敏性腸症候群 | ストレスとの関連が大きく、慢性的に再発しやすい | 内視鏡検査で器質的異常の有無を確認 |
下痢を放置するリスクと対策
腹痛が少ないからといって油断すると、思わぬリスクを招く可能性があります。日常生活への支障が徐々に増すケースもあり、早期の対応が大切です。
栄養不足と脱水
頻回な下痢は水分だけでなく電解質やビタミン、ミネラルなどの重要な栄養素も失わせます。脱水状態になると血圧の低下や倦怠感を起こし、最悪の場合は入院が必要になることもあるため、こまめな水分補給と経口補水液の活用が有用です。
身近に取り組める下痢対策
取り入れると良い習慣
- 消化に良い食事を少量ずつ摂取
- 室温や衣類を調節し、身体を冷やしすぎない
- 十分な睡眠と休息を心がける
- 軽い運動やストレッチで腸の動きをサポート
内視鏡検査の重要性とメリット
腹痛がない下痢であっても、症状が続いたり再発を繰り返す場合、内視鏡検査を検討することを検討し、腸内を直接観察することで、さまざまな病変を早期に見つけられます。
大腸内視鏡検査でわかること
大腸内視鏡検査は肛門から内視鏡を挿入し、大腸全域から一部の小腸までを直接観察し、炎症の有無やポリープの存在、出血の痕跡なども明確に把握できるため、腸内環境を正確に評価できます。
症状が軽くても病変が見つかる例もあるため、下痢の原因追及には非常に有益です。

痛みに弱い方への配慮
鎮静剤を使用すれば、検査による不快感を大幅に抑えられます。腹痛がない方は痛みに敏感でないというわけではありませんので、事前に医療機関へ申し出て検査を受けやすい環境を整えてください。
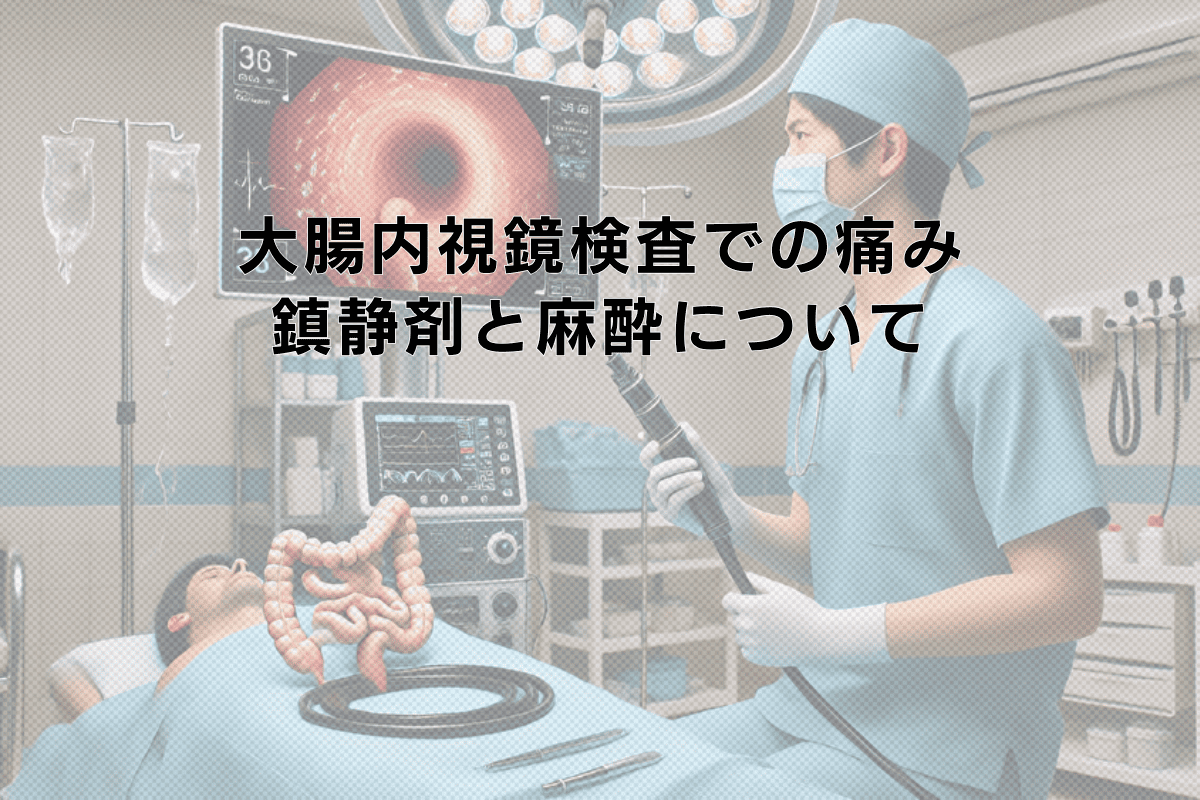
ポリープを見つけた場合の対応
大腸ポリープが検査中に見つかった場合、サイズや形状によってはその場で切除が可能で、切除した組織を病理検査に回すことで、がん化のリスクや炎症性疾患の特徴を調べられます。
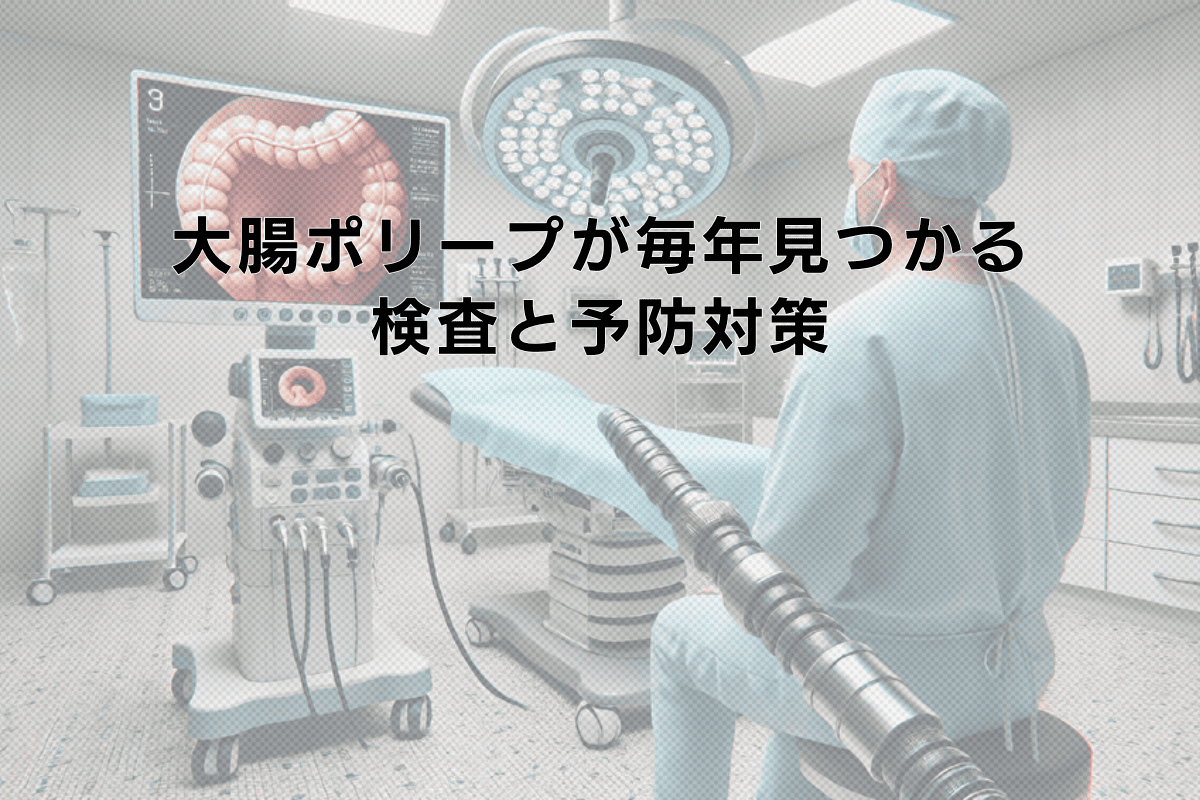
検査を先延ばしにしない利点
明確な結果が得られると、今後の治療方針を決定しやすくなります。また「どこにも問題がなかった」という安心感も得やすいです。
時間がない、痛みが怖いなどの理由で検査を敬遠するのではなく、自分の体調を把握するために積極的に検討すると良いでしょう。
内視鏡検査で判明しやすい病変
| 病変 | 主な特徴 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 粘膜が隆起した良性病変が大半 | 小さければ内視鏡下で切除が可能 |
| 大腸がん | 初期は無症状で見逃されがち | ステージによって手術や内視鏡治療を選択 |
| 潰瘍性大腸炎 | 粘膜にびらんや潰瘍が生じる | 薬物治療で炎症をコントロール |
| クローン病 | 消化管全体に及ぶ可能性がある難治性の炎症 | 内科的治療を主体に、重症時は手術検討 |
内視鏡検査を受ける際の心構え
- 検査前の食事制限や下剤の服用は正確に行う
- 鎮静剤の使用や検査時間の目安を事前に確認
- 血液をサラサラにする薬や慢性疾患の有無は医療機関に報告
- ストレスを減らしてリラックスして臨む

胃カメラ検査や大腸カメラ検査も視野に
下痢だけでなく、胃もたれや吐き気、胸やけが気になる場合は上部消化管のトラブルも疑われ、胃カメラ検査と大腸カメラ検査の両方を一度に受けるメリットや注意点を知っておくと、効率的に消化管をチェックできます。
胃カメラ検査と大腸内視鏡検査の違い
胃カメラ(上部内視鏡検査)は食道から胃、十二指腸までを観察し、逆流性食道炎や胃・十二指腸潰瘍などを確認し、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は大腸全体や回盲部付近を中心にチェックします。
下痢や腹部症状がある場合、いずれの領域のトラブルも考えられるときは両方の検査を検討すると安心です。

上部と下部内視鏡検査の比較
| 検査方法 | 観察範囲 | 主に疑われる病気 |
|---|---|---|
| 胃カメラ(上部内視鏡) | 食道~胃~十二指腸 | 胃潰瘍、逆流性食道炎、胃がんなど |
| 大腸カメラ(大腸内視鏡) | 大腸全域、回盲部付近など | ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患など |
同日に行うメリットとデメリット
同日に両方の内視鏡検査を行うと、一度の準備で消化管の大部分を調べられます。ただし身体への負担が大きくなり、検査時間も長めになる可能性があるので、体力や基礎疾患の有無に応じて、医師と相談しながら決めましょう。
症状が曖昧なときの総合的な検査
腹痛がない下痢だけでなく、胃腸全体の調子が悪い場合は、総合的な診断が早期に行えるよう、両方の検査を組み合わせる選択肢があり、不安を感じる症状をまとめてクリアにすることで、治療や生活改善につなげられます。
視野を広げた健康管理
下痢の原因が大腸だけでなく胃や十二指腸にも及ぶケースもあります。内視鏡検査を活用して広範囲の消化管をチェックし、自分の消化器官全体の健康状態を把握すると、より良い治療計画を立てやすいです。
検査後に意識したい項目
- 検査当日は激しい運動を控える
- 鎮静剤を使用した場合は車の運転を避ける
- 消化に良い食事を心がける
- 腹痛や血便など異常があればすぐに医療機関に連絡
よくある質問
下痢と内視鏡検査に関して、患者さんが抱きやすい疑問をまとめます。少しでも不安を軽減して、早期に受診していただくための参考になればと思います。
- 腹痛を感じない下痢がたまにあるだけでも検査は必要ですか?
-
頻度や期間、他の症状を考慮すると検査を検討する価値があります。月に数回程度の下痢が続く状態や、血液や粘液が混じる場合、体重の減少や倦怠感が見られる場合は早めに医療機関へ相談してください。
- 検査自体の痛みが心配なのですが、大丈夫でしょうか?
-
大腸内視鏡検査は鎮静剤を使用して行うことが多く、痛みや不快感を最小限に抑えられます。医療機関で希望を伝えれば、より楽な体勢や検査方法を提案されることもあります。
- 下剤がつらいという話を聞きます。飲み切る必要はありますか?
-
検査の正確性を高めるため、処方された下剤を正しく服用することがとても重要です。途中で断念すると腸内に便が残り、診断が不十分になります。どうしても苦痛が強いときは、量やタイミングについて医師と相談してください。
- 胃カメラや大腸カメラを一度に受けても安全ですか?
-
患者さんの全身状態や基礎疾患の有無によっては、一度に受けることが可能です。時間や費用面でのメリットがある一方で体力的な負担も増えるため、主治医とよく相談して決定すると良いでしょう。
次に読むことをお勧めする記事
【毎日の下痢症状が続くときの大腸内視鏡検査による診断基準】
腹痛がない下痢の背景を押さえたら、慢性的に続くケースで“いつ受診すべきか”を知ると安心です。毎日続く症状に悩む方に特に役立つ内容です。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
腹痛を伴わない下痢の基本を押さえたら、次は実際の内視鏡検査の準備について知っておくと安心です。検査を初めて受ける方や準備に不安がある方に特に参考になる内容です。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
Cappell MS, Friedel D. The role of sigmoidoscopy and colonoscopy in the diagnosis and management of lower gastrointestinal disorders: endoscopic findings, therapy, and complications. Medical Clinics. 2002 Nov 1;86(6):1253-88.
Powell DW. Approach to the patient with diarrhea. Principles of Clinical Gastroenterology. 2008 May 30:304-59.
Kudo T, Abukawa D, Nakayama Y, Segawa O, Uchida K, Jimbo K, Shimizu T. Nationwide survey of pediatric gastrointestinal endoscopy in Japan. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2021 Jun;36(6):1545-9.
Ashitani K, Tsuzuki Y, Yamaoka M, Ohgo H, Ichimura T, Kusano T, Nakayama T, Nakamoto H, Imaeda H. Endoscopic features and diagnostic procedures of eosinophilic gastroenteritis. Internal Medicine. 2019 Aug 1;58(15):2167-71.
Kinoshita Y, Furuta K, Ishimaura N, Ishihara S, Sato S, Maruyama R, Ohara S, Matsumoto T, Sakamoto C, Matsui T, Ishikawa S. Clinical characteristics of Japanese patients with eosinophilic esophagitis and eosinophilic gastroenteritis. Journal of gastroenterology. 2013 Mar;48:333-9.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.