健康診断や人間ドックの内視鏡検査で、ポリープが見つかったと告げられたら、誰もが不安になるものです。ポリープが良いものなのか悪いものなのかは、最も気になる点でしょう。
良性と悪性を判断するために行われるのが、生検検査です。
この記事では、なぜポリープの生検が必要なのか、どのような手順で行われ、採取された組織からどのようにして悪性度が判定されるのかを詳しく解説します。
ポリープとは何か なぜ生検による診断が必要なのか
内視鏡検査でポリープが発見された際、その場で全てを切除するわけではありません。まず生検という検査を行い、組織を詳しく調べることから始まることがあります。
ポリープの基本的な定義
ポリープとは、胃や大腸などの消化管の粘膜表面から、内側に向かってイボのように隆起した病変の総称です。形や大きさは様々で、キノコのような形をしたものや、平坦で盛り上がりが少ないものもあります。
重要なのは、ポリープという言葉自体は、あくまで見た目の形状を表す言葉であり、それ自体が良いもの(良性)か悪いもの(悪性、つまりがん)かを意味するものではないという点です。
良性から悪性まで 様々な種類のポリープ
ポリープには多くの種類があります。大腸ポリープの多くは腺腫(せんしゅ)と呼ばれる種類で良性ですが、放置すると将来的にがん化する可能性があり、腫瘍性ポリープと呼びます。
がん化のリスクがほとんどないとされる過形成性ポリープや炎症性ポリープなどもあり、非腫瘍性ポリープに分類され、見分けるためには、組織の一部を採取して顕微鏡で観察する必要があります。
主な消化管ポリープの種類
| 分類 | ポリープの種類 | がん化のリスク |
|---|---|---|
| 腫瘍性ポリープ | 腺腫(管状、絨毛状など) | あり(前がん病変) |
| 非腫瘍性ポリープ | 過形成性ポリープ | 基本的には低い(一部例外あり) |
| 炎症性ポリープ | なし(炎症の結果生じる) |
生検の目的 確定診断を得るために
生検の最大の目的は、ポリープの組織型を確定し良性か悪性かを正確に診断することです。内視鏡でポリープを見ただけでは、経験豊富な医師でもある程度の推測はできますが、最終的な確定診断はできません。
生検によって採取した組織を、病理医という専門の医師が顕微鏡で観察し、細胞の顔つきや並び方を詳細に調べることで初めて正確な診断が下されます。
内視鏡検査における生検の実際
生検は、胃カメラや大腸カメラといった内視鏡検査の際に行い、検査と同時に組織を採取できるため、改めて別の日に検査をする必要はありません。
検査前の準備と注意点
生検は内視鏡検査中に行うため、準備は基本的に内視鏡検査のものと同じで、胃カメラであれば検査前日の夜からの絶食、大腸カメラであれば検査食や下剤の服用による腸管洗浄が必須です。
注意が必要なのは、血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を服用している場合で、生検後に出血が止まりにくくなるリスクがあるため、事前に必ず主治医に申告し、指示に従って休薬などの対応をとる必要があります。
組織の採取方法 生検鉗子の使用
内視鏡の先端には、鉗子口という小さな穴が空いていて、医師は、内視鏡でポリープを観察しながら、鉗子口から生検鉗子という細長い器具を挿入します。
生検鉗子の先端は小さなスプーンが二つ合わさったような形をしており、ポリープに押し当てて、ごく小さな組織片(米粒の半分程度の大きさ)を数カ所から採取します。
消化管の粘膜には痛覚(痛みを感じる神経)がないため、痛みを感じることはほとんどありません。
生検後の生活上の注意
生検はごく小さな組織を採取するだけなので、通常は厳しい生活制限はありませんが、組織を採取した部分は小さな傷になっているため、検査当日はいくつかの注意点があります。
アルコールは血行を良くし出血のリスクを高めるため、当日の飲酒は控える必要があり、また、激しい運動や長時間の入浴も避けた方が安全です。食事は、消化の良いものから摂り始めるのが良いでしょう。
生検当日の主な注意事項
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 食事 | 消化の良い、刺激の少ないものから摂取する。 |
| 飲酒 | 出血のリスクを高めるため、当日は禁止。 |
| 入浴 | シャワー程度に留め、長時間の入浴は避ける。 |
| 運動 | 腹圧のかかる激しい運動は控える。 |
病理診断による悪性度の判定
生検で採取された組織片は病理診断科という部門に送られ、病理医が顕微鏡を用いて詳細な観察を行い、最終的な診断を下します。
病理医の役割と診断の手順
病理医は病気の最終診断を下す医師です。採取された組織はまずホルマリンで固定され、薄くスライスしてプレパラートというガラス標本が作られます。
病理医はプレパラートを顕微鏡で観察し、細胞の形、大きさ、核の状態、そして細胞の並び方(構造)などを詳細に評価し、ポリープがどの種類の組織型に分類されるのか、悪性の所見はないかを判定します。
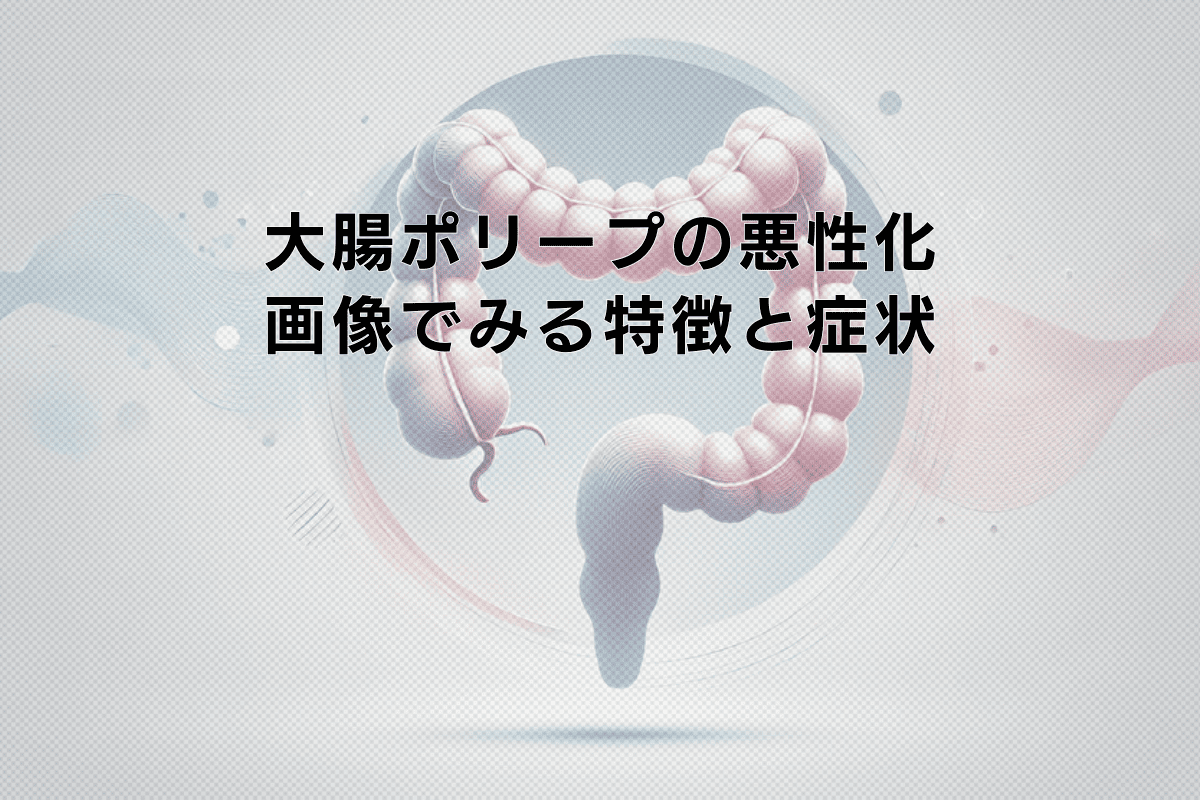
細胞異型と構造異型
悪性度を判断する上で重要なのが、細胞異型と構造異型という二つの観点です。細胞異型とは、個々の細胞の顔つきが悪性らしく変化している状態で、正常な細胞に比べて核が大きくなったり、形が不揃いになったりします。
一方、構造異型とは、細胞の集団としての並び方が乱れている状態です。正常な粘膜では細胞が規則正しく並んでいますが、悪性度が高まるにつれて、構造が崩れて複雑になります。
Group分類とVienna分類
生検の病理診断結果は、しばしば分類で報告され、日本では従来、Group(グループ)分類という5段階の分類が広く用いられてきました。Group1が正常、Group5が明らかながんと判定されます。
国際的にはVienna(ウィーン)分類が標準となりつつあり、これは、その後の治療方針に直結するように作られた分類で、大きく5つのカテゴリーに分けられます。
生検の組織学的分類(簡略版)
| Group分類(日本) | Vienna分類(国際) | 所見の概要 |
|---|---|---|
| Group 1 | カテゴリー1 | 正常または炎症性変化。悪性所見なし。 |
| Group 2 | カテゴリー2 | 異型はないが、良性のポリープなど。 |
| Group 3 | カテゴリー3 | 良性と悪性の境界。腺腫など。 |
| Group 4 | カテゴリー4 | がんを強く疑う。高度異型腺腫や粘膜内がん。 |
| Group 5 | カテゴリー5 | 明らかながん(浸潤がん)。 |
良性・境界病変・悪性の区別
病理診断では分類を用いて、ポリープを良性、境界病変、悪性のいずれかに区別します。Group1や2は良性、Group3は良性ですががん化のリスクがある境界病変(腺腫など)と考え、Group4や5は悪性(がん)と診断されます。
特に、Group4はがんを強く疑う所見であり、多くは粘膜内にとどまる早期のがんを含みます。
生検結果の解釈と治療方針の決定
数日から数週間後、病理診断の結果が出ます。医師から結果について説明を受けますが、専門的な内容も含まれるため、あらかじめどのような結果があり得るのかを知っておくと、理解の助けになります。
良性ポリープと診断された場合
生検の結果、過形成性ポリープや炎症性ポリープといった、がん化のリスクが極めて低い良性ポリープと診断された場合、通常は積極的な治療は行わず、経過観察です。
ただし、ポリープが大きかったり出血の原因となっている場合などは、切除を検討することもあります。
腺腫と診断された場合
腺腫は良性の腫瘍ですが放置するとがん化する可能性があるため、前がん病変と位置づけられています。
特に、大きさが1cmを超えるものや、形がいびつなもの、絨毛(じゅうもう)成分を多く含む腺腫はがん化のリスクが高いため、腺腫と診断された場合は将来のがん予防の観点から、内視鏡的に切除することが推奨されます。
ポリープの種類と基本的な対応方針
| 生検診断結果 | 基本的な対応 |
|---|---|
| 過形成性ポリープ | 原則として経過観察 |
| 腺腫 | 内視鏡的切除を推奨 |
| 早期がん(粘膜内がん) | 内視鏡的切除(根治が期待できる) |
| 進行がん | 外科手術や化学療法など |
悪性(がん)と診断された場合
ポリープからがんが見つかった場合でも、深さによって治療法は大きく異なります。
がんが粘膜内にとどまっている早期の段階(粘膜内がん)であれば、多くは内視鏡的切除で完全に取り除け根治が期待でき、これを内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)と呼びます。
しかし、がんが粘膜の下の層(粘膜下層)深くまで浸潤している場合は、リンパ節転移の可能性があるため、外科手術が必要です。
ポリープ切除が必要になった場合の治療法
生検の結果腺腫や早期のがんと診断された場合、内視鏡を用いたポリープ切除術が行われます。お腹を切ることなく、内視鏡検査と同様の手順でポリープを取り除くことができる、体への負担が少ない治療法です。
ポリペクトミー(Polypectomy)
ポリペクトミーは、キノコのように茎を持った形のポリープに対して行われる、最も一般的な切除法です。
内視鏡の先端からスネアと呼ばれる金属製の輪を出し、ポリープの根元に引っ掛け、スネアを締め付けながら高周波電流を流して、ポリープを焼き切ります。切除したポリープは、鉗子や吸引によって回収します。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)
EMR(Endoscopic Mucosal Resection)は、平坦で盛り上がりの少ないタイプのポリープや、少し大きめのポリープに対して用いられる方法です。
まず、ポリープの下の粘膜下層に生理食塩水などを注入して、病変全体を人工的に盛り上げスネアをかけて、ポリペクトミーと同様に焼き切ります。
主な内視鏡的切除術の比較
| 治療法 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| ポリペクトミー | 茎のあるポリープ | スネアで根元を焼き切る基本的な方法。 |
| EMR | 平坦なポリープ、やや大きめのポリープ | 粘膜下層に液体を注入し、病変を浮かせてから切除する。 |
| ESD | 大きな早期がん、EMRで切除困難な病変 | 電気メスで病変周囲の粘膜を切り、少しずつ剥がし取る。 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)は、EMRでは一括で切除するのが難しい、大きな早期がんなどに対して行われる、より高度な技術を要する治療法です。スネアではなく、ITナイフなどの特殊な電気メスを用います。
まず病変の周りの粘膜をマーキングし、全周にわたって切開を加え、その後粘膜下層を少しずつ剥がしながら、病変を一枚のシートのように剥ぎ取ります。大きな病変でも、確実に取り残しなく切除することが可能です。
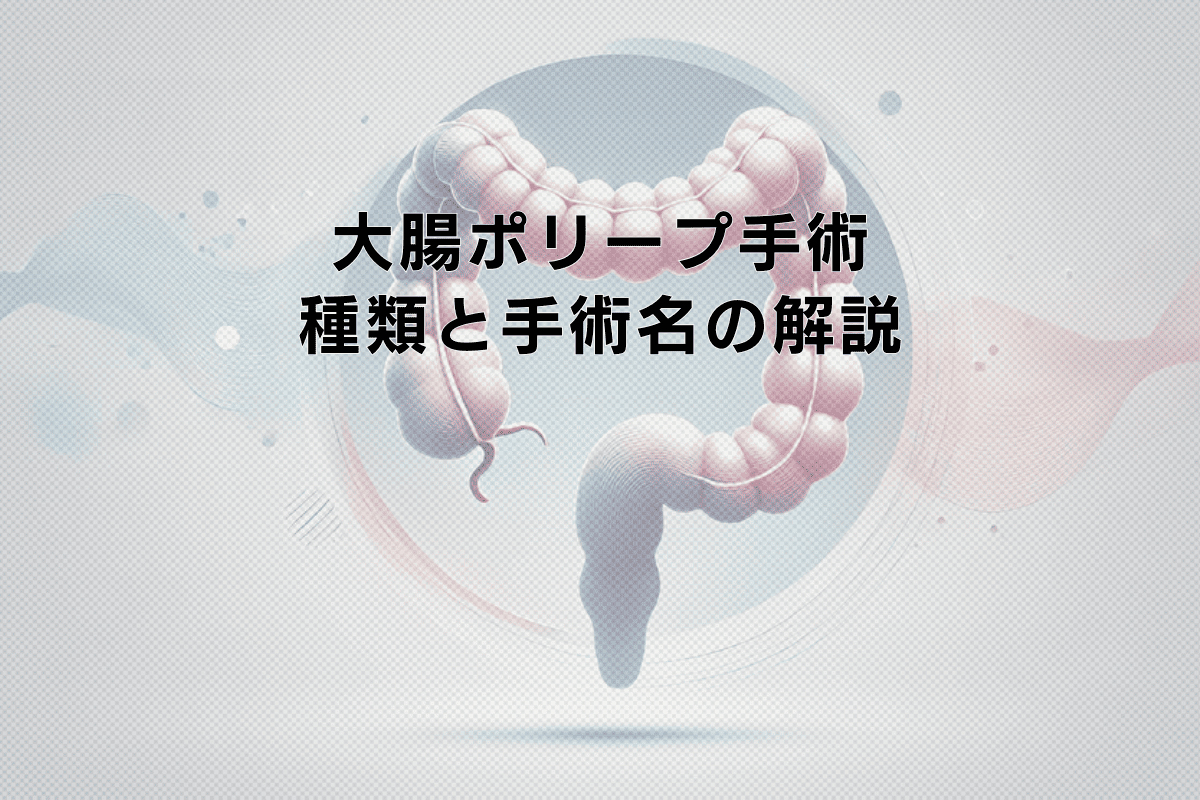
生検やポリープ切除に伴う偶発症
生検や内視鏡的切除術は非常に安全性の高い検査・治療ですが、医療行為である以上、ごくまれに偶発症と呼ばれる好ましくない事態が起こる可能性があります。
出血
最も頻度の高い偶発症は出血です。生検ではまれですが、ポリープを切除した際には傷口から出血することがあります。
ほとんどの出血は、治療中に内視鏡で止血処置を行うことで対応できますが、ごくまれに、治療後しばらくしてから出血すること(後出血)があります。
黒い便が出たり、血を吐いたり、ふらつきが強い場合は、すぐに治療を受けた医療機関に連絡してください。
穿孔(せんこう)
穿孔は消化管の壁に穴が開いてしまう、最も重篤な偶発症です。高周波電流が深く効きすぎたり、粘膜下層の剥離が深くなりすぎた場合に起こる可能性があります。
発生頻度は非常に低いですがもし起こった場合は、腹痛や発熱といった症状が現れ、緊急で内視鏡的な閉鎖術を行ったり、場合によっては外科的な緊急手術が必要です。
治療後に医療機関へ連絡すべき症状
| 症状 | 疑われる偶発症 |
|---|---|
| 黒い便、下血、吐血 | 後出血 |
| 我慢できないほどの強い腹痛、発熱 | 穿孔、穿孔後の腹膜炎 |
| 強いふらつき、冷や汗 | 出血による貧血や血圧低下 |
薬剤アレルギー
検査や治療の際に使用する鎮静剤や鎮痙剤、消毒薬などに対して、アレルギー反応が起こる可能性もゼロではありません。じんましんや発疹、血圧低下などの症状が現れます。
事前にアレルギー歴を正確に申告することが、大切です。

よくある質問
ポリープの生検や悪性度の判定に関して、多くの患者さんから寄せられる質問とその答えをまとめました。検査や診断への不安解消にお役立てください。
- 生検でがん細胞を刺激して、がんが広がることはありませんか
-
多くの患者さんが心配されることですが、医学的には明確に否定されています。
生検でポリープの一部を採取するという物理的な刺激によって、がん細胞が周囲に散らばったり、転移を促進したりするという科学的な根拠はありません。
生検を行わずに放置することの方が、がんを見逃したり、進行させてしまったりするリスクをはるかに高めます。
- 生検の結果、悪性ではなかったのに切除を勧められるのはなぜですか
-
生検の結果が良性の腺腫であっても、切除を勧められることはよくあります。これは、腺腫が前がん病変、つまり将来がんになる可能性を秘めたポリープだからです。
サイズが大きい腺腫や、特殊なタイプの腺腫は、一部にすでにがん細胞が隠れている可能性も否定できません。将来的ながん化を予防する観点から、がんの芽を早めに摘み取っておくという考え方で、切除が推奨されます。
- 生検で採取する場所によって、結果が変わることはありますか
-
大きなポリープの場合、良性の部分と悪性の部分が混在していることがあり、生検で偶然、良性の部分だけを採取してしまうと、本当はがんであっても良性と診断されてしまう可能性があります。
そのため医師はポリープの中で最も悪性を疑う部分を狙って、複数箇所から組織を採取するなどの工夫をします。最終的には、ポリープ全体を切除して調べることで、より正確な診断が確定します。
- 診断結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか
-
生検で採取した組織が病理診断に提出されてから結果が出るまでの期間は、一般的には1週間から2週間程度になります。
提出された組織でプレパラート標本を作成し、病理医が顕微鏡で詳細に観察・診断し、報告書を作成するという手順を踏むため、ある程度の時間が必要です。
次に読むことをお勧めする記事
【ポリープ摘出手術の方法と回復までの期間】
生検結果を踏まえた切除が必要になった場合、実際の手術手順や当日の流れ、入院の要否、目安費用まで把握しておくと安心です。検討段階の方に特に役立つ内容です。
【良性の大腸ポリープにおける経過観察のポイント】
生検と治療の考え方を押さえた皆さんには、再発・新生の観点も重要です。リスク別の再検査間隔を把握すると、全体像が一段と明確になります。
参考文献
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56:323-35.
Suzuki H, Yamamura T, Nakamura M, Hsu CM, Su MY, Chen TH, Chiu CT, Hirooka Y, Goto H. An international study on the diagnostic accuracy of the Japan Narrow-Band Imaging Expert Team classification for colorectal polyps observed with blue laser imaging. Digestion. 2020 May 13;101(3):339-46.
Yamashina T, Setoyama T, Sakamoto A, Hanaoka N, Tsumura T, Maruo T, Marusawa H. Prospective comparison of diagnostic performance of magnifying endoscopy and biopsy for sessile serrated adenoma/polyp. Annals of Gastroenterology. 2022 May 12;35(4):414.
Matsuda T, Fujii T, Sano Y, Kudo SE, Oda Y, Hotta K, Shimoda T, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M, Konishi K. Randomised comparison of postpolypectomy surveillance intervals following a two-round baseline colonoscopy: the Japan Polyp Study Workgroup. Gut. 2021 Aug 1;70(8):1469-78.
Hamada Y, Tanaka K, Katsurahara M, Horiki N, Yamada R, Yamada T, Takei Y. Utility of the narrow-band imaging international colorectal endoscopic classification for optical diagnosis of colorectal polyp histology in clinical practice: a retrospective study. BMC gastroenterology. 2021 Aug 28;21(1):336.
Kawamura T, Takeuchi Y, Yokota I, Takagaki N. Indications for cold polypectomy stratified by the colorectal polyp size: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Anus, Rectum and Colon. 2020 Apr 28;4(2):67-78.
Cleveland NK, Huo D, Sadiq F, Sofia MA, Marks J, Cohen RD, Hanauer SB, Turner J, Hart J, Rubin DT. Assessment of peri-polyp biopsy specimens of flat mucosa in patients with inflammatory bowel disease. Gastrointestinal endoscopy. 2018 May 1;87(5):1304-9.
Rath T, Tontini GE, Vieth M, Nägel A, Neurath MF, Neumann H. In vivo real-time assessment of colorectal polyp histology using an optical biopsy forceps system based on laser-induced fluorescence spectroscopy. Endoscopy. 2016 Jun;48(06):557-62.
Muehldorfer SM, Stolte M, Martus P, Hahn EG, Ell C. Diagnostic accuracy of forceps biopsy versus polypectomy for gastric polyps: a prospective multicentre study. Gut. 2002 Apr 1;50(4):465-70.
Dayyeh BK, Thosani N, Konda V, Wallace MB, Rex DK, Chauhan SS, Hwang JH, Komanduri S, Manfredi M, Maple JT, Murad FM. ASGE Technology Committee systematic review and meta-analysis assessing the ASGE PIVI thresholds for adopting real-time endoscopic assessment of the histology of diminutive colorectal polyps. Gastrointestinal endoscopy. 2015 Mar 1;81(3):502-e1.










