大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査でポリープを見つけた場合には、切除を行うことも多くあります。ポリープを切除した後に気になるのは、切除部位からの出血や痛みといった症状です。
治療を受けた後は身体をしっかりと休め、正しいタイミングで通院と検査を継続することが大切になります。
本記事では、ポリープの切除を行った後に生じやすい症状や対処法、そして日常生活で気をつけたいポイントを詳しく解説します。
ポリープ切除後の流れと身体の変化
内視鏡検査で見つかったポリープを切除すると、術後は身体のさまざまな部分で変化が起こるので、治療直後から退院後、自宅療養期間、そして再検査までの流れを把握すると、落ち着いて対処しやすくなります。
ポリープ切除を行う理由
大腸カメラや胃カメラで発見されたポリープは、その大きさや形状によって放置すると悪性化するリスクが上昇し、見つかった段階で切除し病理検査を実施することで、がん化の可能性を正確に判断できます。
特に大腸の場合、ポリープから大腸がんへ移行するケースが少なくありません。
- ポリープの種類によっては、切除を先延ばしにすると悪性化率が高まる
- 腸内視鏡や胃内視鏡で切除すると、施術自体の侵襲は比較的軽度
- 早期に治療すれば再発リスクを抑え、生活の質を維持しやすい
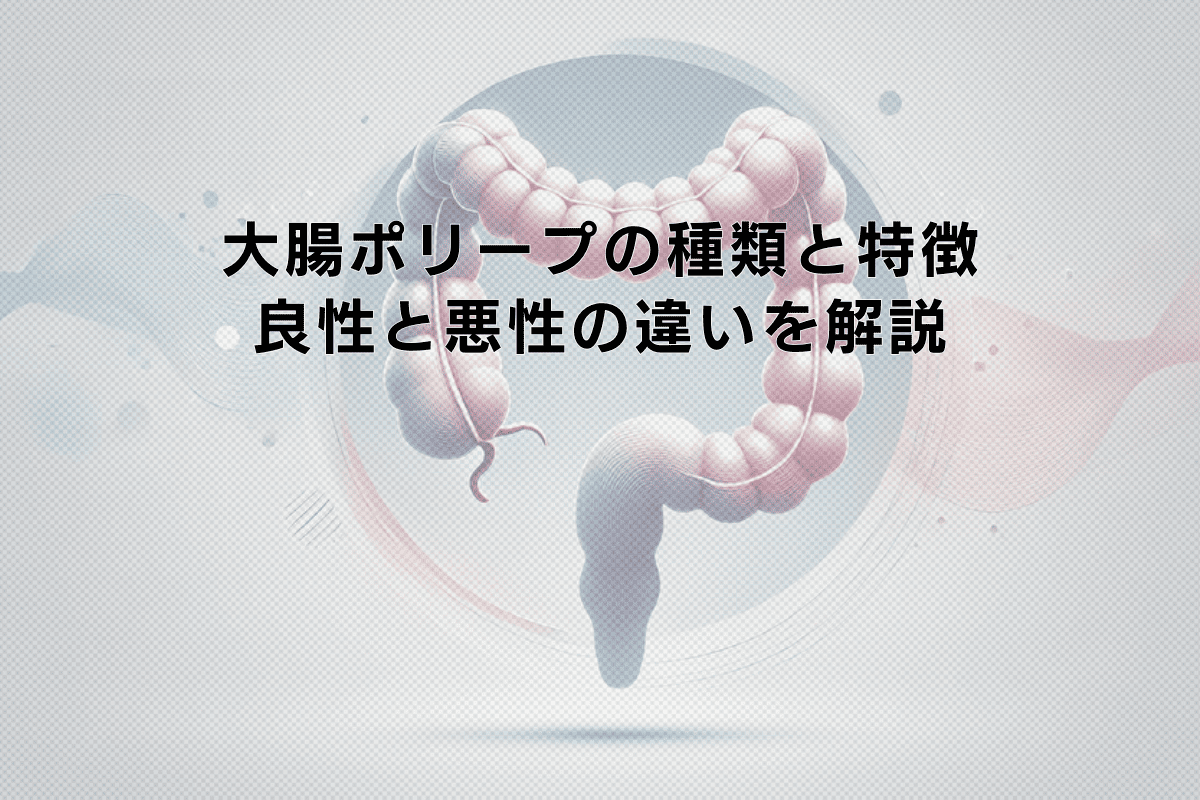
切除直後に気をつけるポイント
ポリープの切除直後は、切除部位に負担がかかっています。出血の可能性や腸内環境の乱れなど、さまざまな症状に注意が必要で、大腸カメラで切除した場合は、大腸の動き(蠕動運動)によって出血が起きやすくなることもあります。
切除後の当日は激しい運動を避け、安静を保つことが大切です。
入院か外来かの判断
ポリープを切除した後、入院が必要になるかどうかは、切除したポリープの大きさ、数、そして患者さん自身の健康状態や持病の有無などで変わります。
小さめのポリープであれば日帰りで帰宅できるケースも多く、逆に大きなポリープや多数のポリープを切除した場合は経過観察のために数日入院することがあります。
なお、胃のポリープは出血のリスクが高いため、外来で切除することはまれです。
ポリープ切除に関する治療
| ポリープの大きさ | 主な治療パターン | 入院の必要性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5mm未満 | 内視鏡での簡易切除 | 多くの場合は不要 | 病理検査の結果によって追加検査あり |
| 5mm~1cm前後 | 内視鏡での切除 | 状況に応じて1日程度 | 腸内視鏡の観察時間を延長することも |
| 1cm以上 | 内視鏡または外科的切除 | 数日間入院が必要な場合あり | 出血や穿孔リスクに注意 |
| 複数個 | 内視鏡での複数切除、または段階的切除 | 症状次第で入院期間の検討 | 合併症リスクが上がる可能性あり |
クリニックでのフォロー体制
クリニックでは、ポリープの切除を行った後のフォローを重視し、術後の感染症や出血など、さまざまなリスクを早期に発見するために、医師が状態を定期的にチェックします。
大腸カメラや胃カメラの再検査を予定している場合、検査前の食事指導や服薬指導も受けられるので、不安を感じずに通院できるようにすることが大切です。
- 術後の経過観察スケジュールをしっかりと組む
- 何か気になる症状が出た場合、早めに受診の相談を行う
- 切除部分の治癒具合を確認し、再発を防ぐためのアドバイスを受ける
出血への対処法と予防
ポリープを切除した後に起こる合併症のひとつが出血で、わずかな血液が便に混じる程度なら自然に止まることもありますが、量が多い場合は医療機関で処置を受ける必要があります。
普段の排便状況とは違う出血を感じたら、早めに対処しておくと安心です。
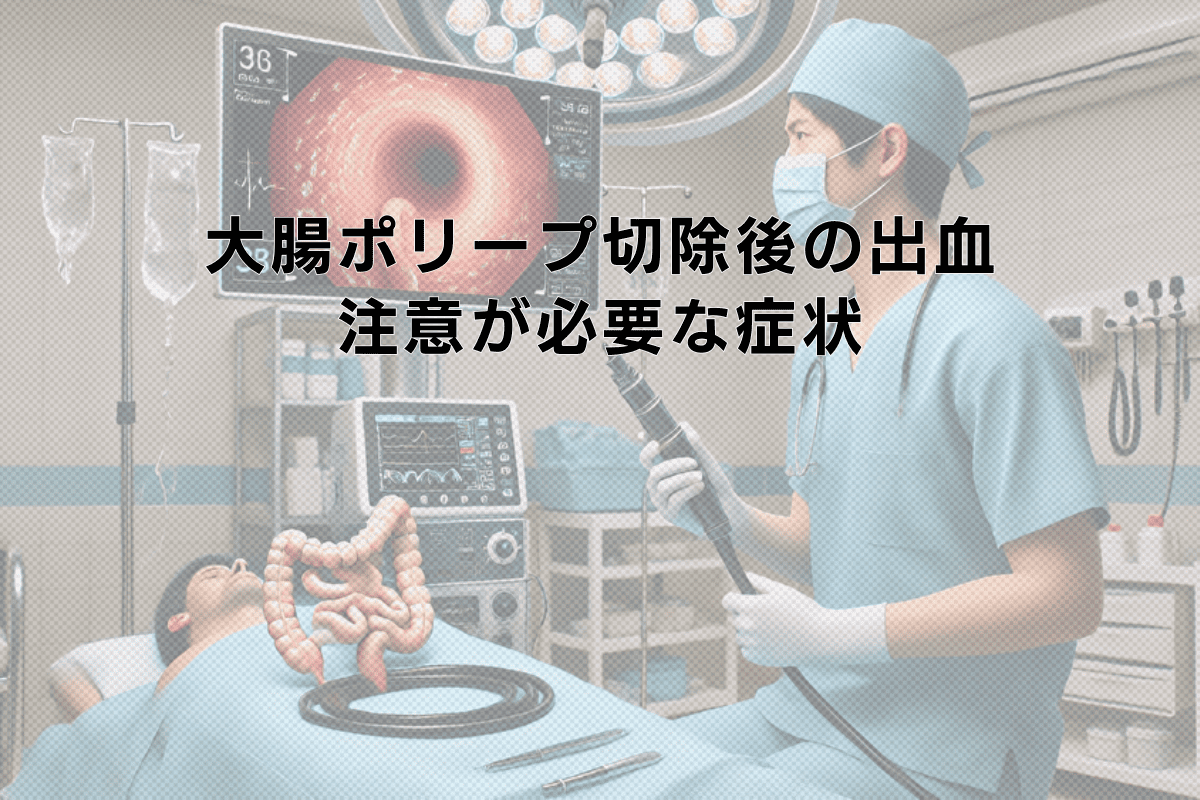
出血が起こる仕組み
切除部位は新しい傷口と同じ状態であり、血管が収縮しきらないうちに排便の刺激を受けると出血が生じやすくなり、排便時のいきみが強いと血管に負荷がかかり、切除創が開くリスクが高まります。
切除したポリープの種類や切除方法にもよりますが、実際に出血が見られるのは術後1~2日以内が多い傾向です。
血便や便潜血への対応
術後に赤い血液が混ざった便が出ると驚くかもしれませんが、少量の場合は大きな問題にならないケースがよくあります。
便の表面につく程度の出血なら様子をみながら過ごすことも可能ですが、以下のような場合には医療機関への連絡を検討してください。
- 出血量が多く、便器の水が赤く染まる
- 何度も血液が混ざった便が続く
- 動悸や息切れ、立ちくらみを伴う

自宅での止血方法と注意
少しの出血であれば、しばらく安静にして経過をみると自然に止まることがありますが、排便時のいきみを控えるよう心がけ、食事の内容を柔らかいものや消化に良いものに変えて腸を刺激しすぎないよう注意してください。
切除後の創部に強い刺激が加わると出血が長引く可能性があります。
出血を抑えるために役立つ工夫
- 食物繊維を取りすぎず、過度な下痢や便秘を避ける
- お風呂に長時間入らず、短いシャワーで済ませる
- 腹圧をかけすぎない姿勢や呼吸法を意識する
- アルコールやカフェインを極力控える
病院への受診が必要な症状
血液が止まらない、もしくは体調が悪化している場合は早めに医師の判断を仰いでください。
失神や息切れ、冷や汗などの症状がある場合や、急に血圧が下がったような感覚があるときは、重度の出血に発展しているかもしれないので、迷わず救急外来やかかりつけの医療機関に相談することが必要です。
出血の程度と受診目安
| 出血量の程度 | 主な症状 | 自宅安静か病院受診か | コメント |
|---|---|---|---|
| 少量 | 便にうっすら血が付着 | 自宅安静で経過観察可能 | 排便時の刺激を減らす工夫が必要 |
| 中等量 | 便器の水がほんのり赤く染まる | クリニックでの相談を推奨 | 血液検査や内視鏡で切除創を確認する場合がある |
| 多量 | 便器の水がはっきり赤くなる | すぐに医療機関に連絡を推奨 | 大量出血による貧血やショックに注意 |
| 持続的な出血 | トイレットペーパーが真っ赤になる | 緊急受診が望ましい | 点滴や止血の処置、入院が必要になる可能性が高い |
痛みや違和感への向き合い方
ポリープの切除時の痛みに加え、術後にもお腹の張りや違和感を覚える方がいて、こうした症状の程度は個人差が大きく、切除したポリープのサイズや部位によっても変わります。痛みや違和感とうまく向き合うことで、術後の生活が楽になります。
ポリープ切除後の痛みの原因
切除直後の痛みは、内視鏡を挿入した際の刺激や、切除部位にできた小さな傷からくるものです。
大腸の場合、蠕動運動やガスが溜まることによって腸壁が刺激され、鈍い痛みが出ることがあり、胃の場合も、胃酸が創部を刺激してむかつきや痛みを感じるケースが少なくありません。
薬の服用とセルフケア
術後の痛みが気になる場合は医師が鎮痛薬を処方しますが、処方薬の効果が充分でないと感じた場合は、無理をせずクリニックに相談して、薬の種類や服用回数を調整してもらうとよいでしょう。
また、セルフケアとして腹部を圧迫しない姿勢や服装、こまめな水分摂取も有効です。
痛みを和らげる対策
- 腹部を締めつけない緩めの衣服を選ぶ
- 小まめに休憩をとり、身体を温める
- 痛みが強いときは無理に動かずに休む
- トイレでは長時間いきまないようにする
痛みが続く場合の相談先
ごく軽い痛みであれば自然に治まるケースもありますが、激痛が続いたり、痛みが急激に増したりする場合は合併症の可能性を考え、医師への相談を早めに行ってください。痛みの状態をメモしておくと、医師に症状を正確に伝えられます。
内視鏡検査との関連性
ポリープを切除する際に使用した内視鏡の操作や、創部の大きさによって痛みの度合いが変わり、大腸カメラの場合は腸の長さや曲がり具合が人によって異なるため、人によって痛みが強く出るケースがあります。
胃カメラでも喉の違和感や、胃酸による刺激などで不快感を覚えることがあります。術後の痛みが不安な方は、次回の内視鏡検査時に麻酔や鎮痛剤の使用を検討してください。
痛みの原因と対応
| 痛みの種類 | 主な原因 | 対応策 | 医療機関での処置 |
|---|---|---|---|
| 鈍い腹痛 | 内視鏡の挿入・ガス注入 | 休息と温め、処方薬の服用 | ガス抜きや鎮痛剤の追加調整 |
| キリキリした痛み | 胃酸や腸液による創部の刺激 | 食事制限、粘膜保護薬の利用 | 内視鏡による創部検査、止血処置など |
| 立ち上がれないほどの激痛 | 穿孔や炎症の悪化 | すぐに受診、必要に応じて救急搬送 | 手術的処置や静脈投与、入院管理など |
| 持続的な重苦しさ | 粘膜の腫れやむくみ | 体位変換と安静、消炎剤の使用 | 内視鏡での状態確認、追加の治療方針検討 |
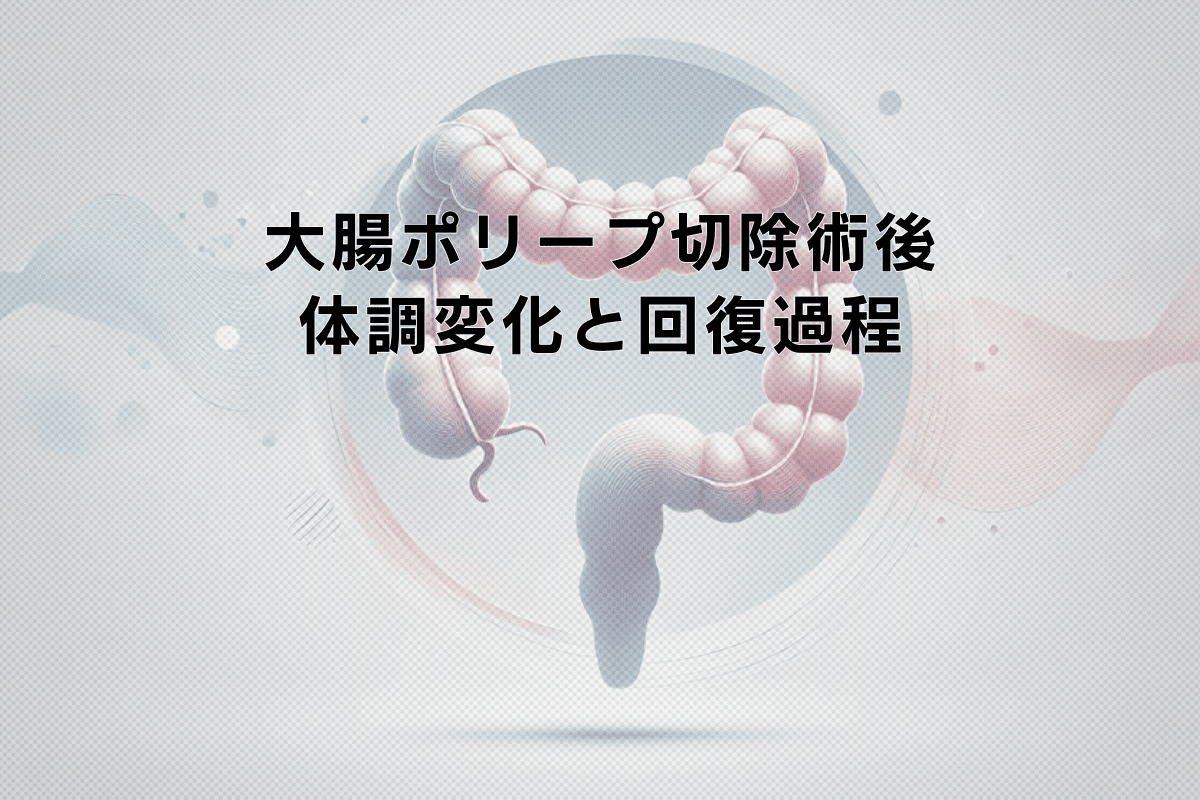
食事と生活習慣の注意点
ポリープ切除後は食事の内容や生活リズムを見直すことで、出血や痛みのリスクを低減でき、無理をしない範囲で腸に優しい生活を送ることが、回復を早めるうえでとても重要です。

術後の食事制限の必要性
切除後しばらくは胃腸への負担を減らすために、消化に良いものを少量ずつ摂取することが勧められ刺激、物や硬い食べ物は傷口を刺激して出血や炎症を起こしやすいので、控えめにするほうが安心です。
大腸ポリープの切除後は食物繊維の多い野菜を急に大量に取らないよう、徐々に増やしていく工夫が必要になります。
術後におすすめの食材
| 食材カテゴリー | おすすめ例 | 避けたい例 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 柔らかいお粥やうどん | ラーメンや麺の固ゆで、玄米 | 消化しやすさを優先。固いものは腸を刺激しやすい |
| タンパク質 | 魚のすり身、豆腐、白身魚 | 硬い肉、脂の多い肉 | 余分な脂質は創部への刺激になりやすい |
| 野菜 | 加熱した野菜スープ、ポタージュ | 生野菜サラダ、根菜の固ゆで | 繊維質が硬いと排便時の負担が大きくなる |
| 果物 | 柔らかく煮たり、すりおろしたもの | 繊維質の多い生フルーツ | 過度な食物繊維は腸を擦り、出血リスクを高める可能性がある |
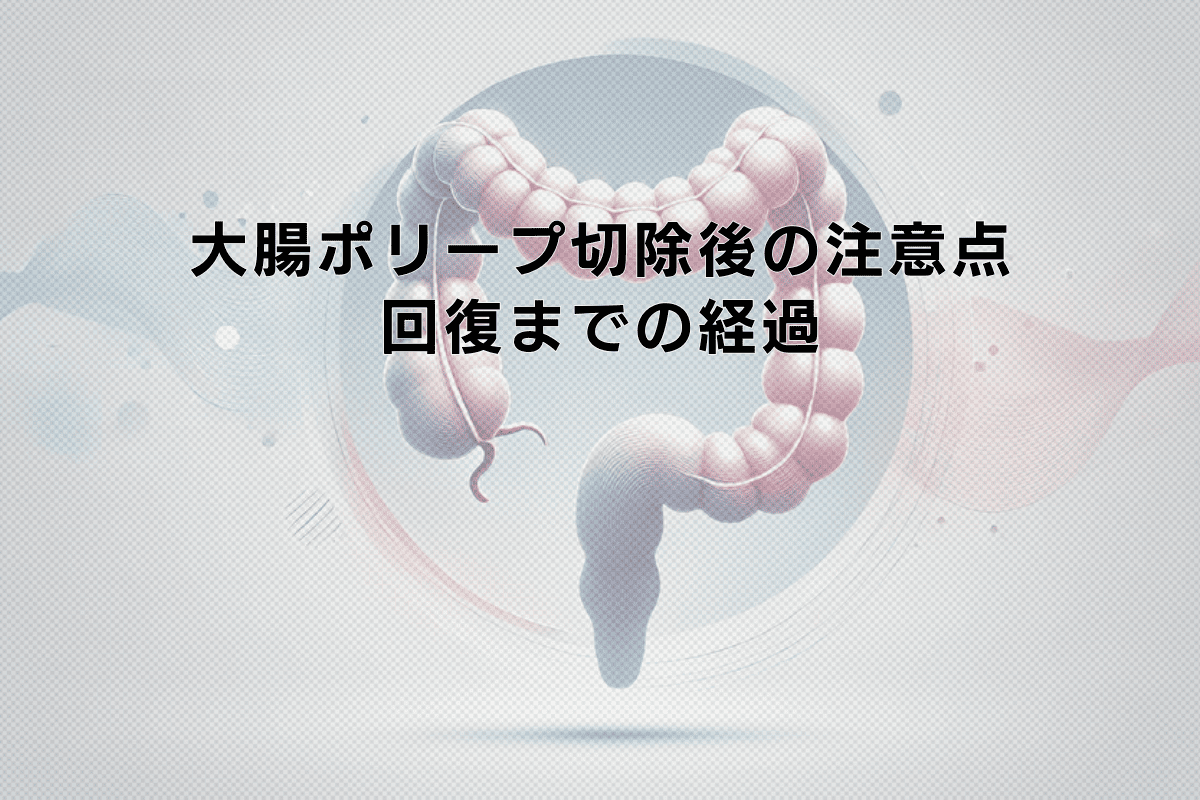
アルコールや喫煙のリスク
アルコールやタバコは、ポリープを切除したあとの傷口の回復を妨げる要因です。
アルコールは血管を拡張させて出血しやすくし、また胃酸の分泌を促して消化器を刺激し、喫煙は血流を悪化させ、組織の修復力を低下させるため、切除創の治りが遅れるリスクがあります。
術後しばらくはアルコールとタバコを控えましょう。
- 術後は最低1~2週間程度、アルコールは我慢したほうがよい
- たばこを吸う方は、切除後の回復期間を禁煙のきっかけにするのも一案
- ニコチンやタール成分が粘膜を傷つけ、炎症を起こしやすくする
運動や入浴のタイミング
軽度のウォーキング程度であれば、術後数日経過してから少しずつ始められ大腸がるものの、大きく揺さぶられるような激しい運動は、切除創への負担が大きいため避けてください。
入浴に関しても、長時間の入浴は血行が良くなりすぎて出血につながる恐れがあるため、短時間のシャワーで様子を見ます。
早期に再発予防を考える方法
ポリープは再発する可能性があるので、1度ポリープが見つかった方は定期的な内視鏡検査で状態を確認し、再発を早期に発見して対処することが必要です。
特に大腸ポリープは生活習慣との関連が深いとされてて、食習慣の見直しや適度な運動で腸内環境を整え、再発リスクを下げることを心がけると良い結果につながりやすくなります。
再検査や通院のタイミング
ポリープを切除して終わりではなく、定期的な再検査や通院が重要で、クリニックでのフォローアップにきちんと通うことにより、切除後の回復状況や再発の有無を確認できます。
大腸カメラや胃カメラを活用することで、がんなどの重い病気を未然に防ぐチャンスが高まります。


術後フォローアップの重要性
切除後の再検査には複数の意味があり、創部の治癒状態を確認し、出血や感染症などの合併症がないかをチェックするだけでなく、新たにポリープができていないかの確認も含まれます。
多くの場合、初回のフォローアップは術後1~3か月以内に行うことが多いです。
術後フォローアップの流れ
- 術後約1週間で簡単な問診や身体診察
- 術後1~2か月後に大腸カメラや胃カメラによる再検査(必要性は医師の判断)
- ポリープのサイズや数に応じて再診察の頻度を調整
内視鏡で確認する理由
出血や痛みなど、自覚症状がある場合だけでなく、症状がない時期にも内視鏡検査で直接観察することが大切です。
ポリープの再発や新たな病変は、症状が出る前に発見できるケースが少なくないので、大腸カメラや胃カメラを定期的に受ける習慣をつけると、早期発見・早期治療につながります。
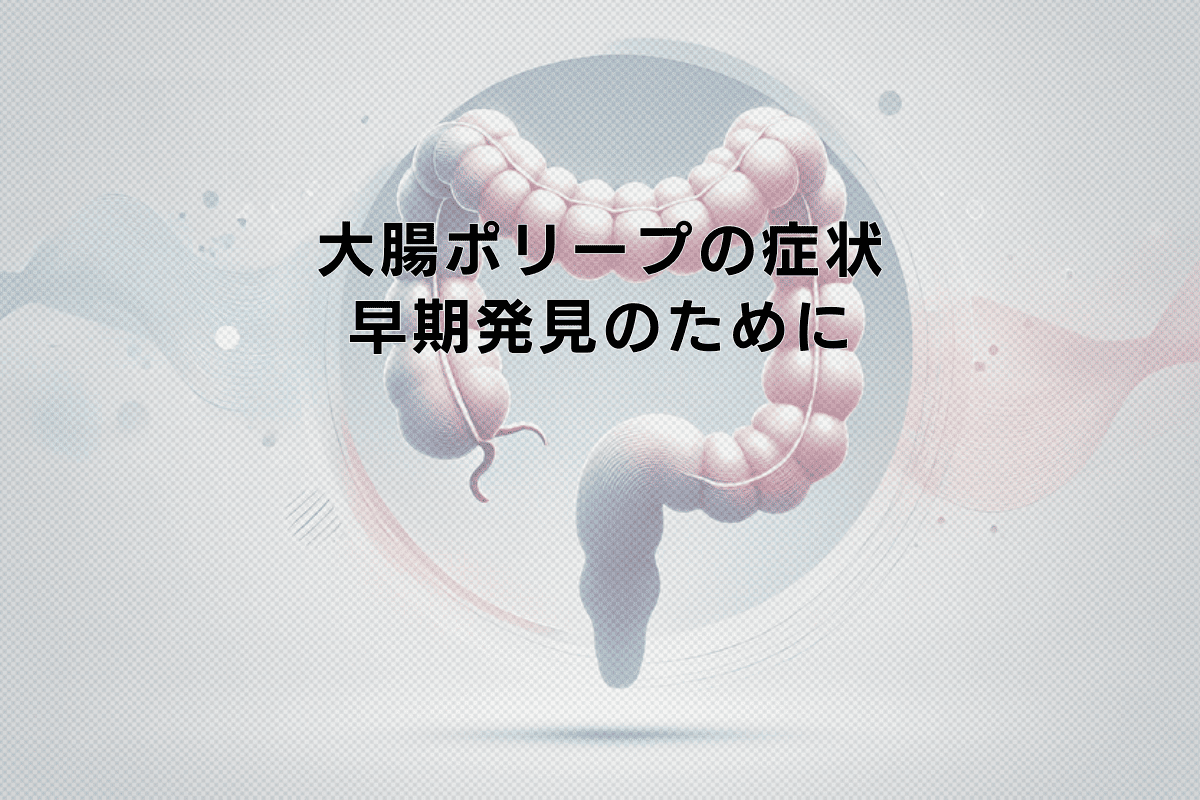
大腸カメラと胃カメラの活用
大腸ポリープの切除経験がある方は大腸カメラを、胃ポリープの切除経験がある方は胃カメラを適度な間隔で受けると安心です。どちらも消化器官の内面を直接確認できる検査なので、がんの前段階での発見に役立ちます。
自覚症状が乏しい時期こそ検査のタイミングになるため、「体調が良いから大丈夫」と自己判断して先延ばしにしないでください。
次回の受診を忘れないために
術後は何かと忙しく、次の受診をうっかり忘れてしまうこともあるので、スマートフォンのカレンダー機能や手帳に受診予定日を書き込んでおく、家族と共有しておくなどの工夫をすると安心です。
通院はおろそかにしないことで、将来的なリスクを減らせます。
術後に必要となる通院のタイミング
| 時期 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 術後約1週間 | 問診・傷口のチェック | 出血や感染症の早期発見 |
| 術後1か月前後 | 大腸カメラ・胃カメラ(必要に応じて) | 創部の状態確認、新たなポリープの発見 |
| 術後3か月~6か月後 | 定期健診・再度の内視鏡検査の検討 | 再発リスクの評価、生活指導 |
| 術後1年~数年後 | 状況に応じた検査間隔の調整 | 長期的な経過観察、がんリスクの低減 |
注意しておきたい合併症とリスク管理
ポリープの切除は、内視鏡技術の進歩によって安全性が高まっていますが、合併症がまったく起こらないわけではありません。出血や感染症、穿孔などのリスクを理解したうえで、早めに対策を講じることが重要です。
感染症や穿孔のリスク
切除創から細菌が侵入すると感染症を引き起こすことがあり、また、大腸内視鏡の操作時に腸壁を傷つけると、まれに穿孔が生じる場合もあります。強い腹痛や高熱、便が出なくなるなどの異常があれば、すぐに医師へ連絡してください。
合併症の代表例とチェックポイント
| 合併症 | 症状例 | チェックポイント | 処置 |
|---|---|---|---|
| 感染症 | 発熱、下痢、腹痛、倦怠感 | 体温や排便回数を測定し、体調変化を観察 | 抗生物質投与、点滴、状態が重い場合は入院管理 |
| 穿孔 | 激しい腹痛、腹部の板状硬化、発熱など | 腸管外へのガス漏れの有無を画像検査で確認 | 外科的処置、緊急開腹手術が必要な場合もある |
| 縫合不全や癒着など | 排便困難、腹部膨満感 | 便通異常や腹部の張り具合をモニタリング | 内視鏡的再処置または外科的治療 |
高齢者や基礎疾患がある方への配慮
高齢者や心疾患、糖尿病などの基礎疾患がある方は、一般的なケースよりもリスクが高い場合があり、麻酔や鎮痛薬の副作用も含め、術後の体調が不安定になりやすいので、担当医による慎重な経過観察が必要です。
普段飲んでいる薬の管理や、術後の生活指導を細やかに受けることが大切になります。
処方薬との相互作用
痛み止めや抗血栓薬を常用している場合、ポリープを切除した後の出血リスクが高まる可能性があります。自己判断で服薬を中断すると、基礎疾患が悪化する恐れもあるため、担当医や薬剤師とよく相談してください。
薬の調整を行うことで、合併症の発生率を下げられます。
日頃の体調管理ポイント
術後は免疫力も下がりやすい傾向にあるため、体をしっかり休めて回復を促す必要があり、バランスの良い食事や適度な睡眠時間の確保、ストレスの軽減など、基本的な生活習慣の見直しが合併症予防につながります。
- 規則正しい睡眠リズムを意識する
- 水分補給を忘れず、脱水を防ぐ
- 軽度の運動を取り入れ、血流を整える
- 便秘や下痢が続くと感じたら、早めに医師へ相談する
よくある質問
ポリープの切除後には、痛みや出血といったトラブルへの不安がつきまといます。さらに、旅行や仕事復帰など、いつもの生活に戻れるタイミングについても疑問を抱く方が少なくありません。以下に多く寄せられる質問と回答をまとめました。
- 切除後どのくらい安静が必要か
-
ポリープの大きさや部位によりますが、一般的には数日から1週間程度は激しい運動を避けるようアドバイスしています。
軽い家事やデスクワークであれば問題ないケースが多いものの、仕事で重い荷物を持つような方は、担当医と相談して休暇を確保すると安心です。痛みや出血の状況を見ながら無理なく過ごしてください。
- 旅行や仕事への復帰の目安
-
旅行の計画がある場合は、術後1~2週間ほど経過してからのほうが安心です。特に海外旅行は飛行機内での気圧変化や長時間の移動による負担が大きいので、万全の状態ではないと再出血などのリスクが高まります。
仕事復帰についても同様で、痛みや便通の状況を見ながら段階的に行うとよいでしょう。
- 痛みが強いときの連絡先
-
術後に痛みが強く出たり、痛み止めを飲んでも効果が感じられない場合は、クリニックまたはかかりつけの医療機関に連絡してください。
痛みの原因が切除創の炎症や感染症の可能性もあるため、自己判断ではなく早めの受診が必要です。連絡先や夜間救急の相談先を事前に確認しておくと焦らず対応できます。
- 内視鏡検査を受けたほうがいいタイミング
-
ポリープが見つかった方や切除経験のある方は、医師が指示した時期に内視鏡検査を受けてください。
特に、大腸ポリープは再発率が一定程度あるため、「何も症状がないから大丈夫」とは言わず、定期的な検査を受けることが将来の病気予防につながります。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープ切除後の出血|正常な経過と注意が必要な症状】
「出血はどこまでが正常?」と感じた方へ。症状別の受診目安を写真付きで示し、安心して術後を乗り切るポイントを解説しています。
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
術後フォローで再検査を検討中の方は、費用や保険適用の有無も気になるもの。検査当日の流れと費用目安を把握し、計画的な受診に役立てましょう。
参考文献
Inoue T, Ishihara R, Nishida T, Akasaka T, Hayashi Y, Nakamatsu D, Ogiyama H, Yamaguchi S, Yamamoto K, Mukai A, Kinoshita K. Prophylactic clipping not effective in preventing post‐polypectomy bleeding for< 20‐mm colon polyps: A multicenter, open‐label, randomized controlled trial. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2021 Feb;36(2):383-90.
Kawamura T, Takeuchi Y, Asai S, Yokota I, Akamine E, Kato M, Akamatsu T, Tada K, Komeda Y, Iwatate M, Kawakami K. A comparison of the resection rate for cold and hot snare polypectomy for 4–9 mm colorectal polyps: a multicentre randomised controlled trial (CRESCENT study). Gut. 2018 Nov 1;67(11):1950-7.
Gutta A, Gromski MA. Endoscopic management of post-polypectomy bleeding. Clinical Endoscopy. 2020 May 1;53(3):302-10.
Thirumurthi S, Raju GS. Management of polypectomy complications. Gastrointestinal Endoscopy Clinics. 2015 Apr 1;25(2):335-57.
Wehbe H, Gutta A, Gromski MA. Updates on the prevention and management of post-polypectomy bleeding in the colon. Gastrointestinal Endoscopy Clinics. 2024 Apr 1;34(2):363-81.
Du F, Xu F, Yang Z, Zhang Y, Gao Z. Post-Polypectomy Care: Balancing Comfort and Nutritional Needs. Current Topics in Nutraceutical Research. 2024 May 1;22(2).
Eleftheriadis D, Imalis C, Gerken G, Wedemeyer H, Duerig J. Risk factors for post-polypectomy bleeding; a retrospective case-control study of a high-volume colonoscopy center. Zeitschrift für Gastroenterologie. 2022 Oct;60(10):1475-82.
Fyock CJ, Draganov PV. Colonoscopic polypectomy and associated techniques. World journal of Gastroenterology: WJG. 2010 Aug 7;16(29):3630.
Shiffman ML, Farrel MT, San Yee Y. Risk of bleeding after endoscopic biopsy or polypectomy in patients taking aspirin or other NSAIDS. Gastrointestinal endoscopy. 1994 Jul 1;40(4):458-62.
Park SK, Seo JY, Lee MG, Yang HJ, Jung YS, Choi KY, Kim H, Kim HO, Jung KU, Chun HK, Park DI. Prospective analysis of delayed colorectal post-polypectomy bleeding. Surgical Endoscopy. 2018 Jul;32:3282-9.










