大腸内視鏡検査が無事に終わったあとで、これからの食事や生活について不安を感じている方もいるのではないでしょうか。検査後の腸は、ポリープ切除の有無にかかわらず、下剤の影響や検査中の処置によって一時的に敏感な状態になっています。
この時期に適切な食事と生活を心がけることは、腸の回復を穏やかにし、出血や腹痛といった合併症を防ぐ上でとても大事です。
この記事では、検査後の食事の段階的な進め方、メニュー例、日常生活での注意点、どのような場合に医療機関に相談すべきかなどを詳しく解説します。
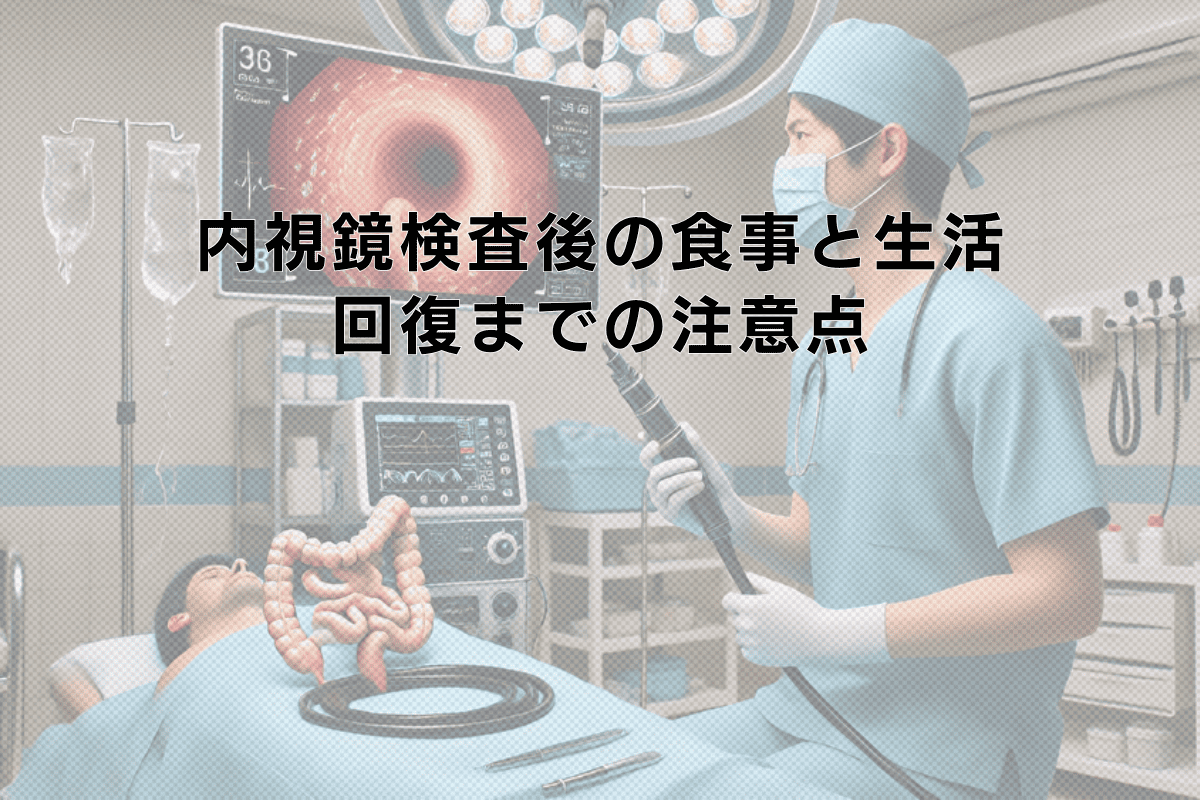
大腸内視鏡検査後の身体の状態を理解する
検査を終えた後の腸はデリケートな状態にあり、なぜ食事や生活に注意が必要なのかを知ることで、回復への意識も自然と高まります。
検査直後の腸の様子
大腸内視鏡検査では、腸内を詳しく観察するために、腸管を空気や二酸化炭素で膨らませるため、検査後はお腹の張り(腹部膨満感)を感じることがあります。特に空気を使用した場合、吸収されにくいため張りが残りやすいです。
また、内視鏡が腸の壁に触れることで、粘膜に軽い刺激が加わっており、ポリープを切除した場合は、電気メスなどによる小さな傷ができており、出血や、ごく稀に穿孔(せんこう)という合併症のリスクも考えられます。
ポリープを切除しなかった場合でも、強力な下剤によって腸内細菌のバランスが一時的に乱れたり、粘膜を保護する粘液が洗い流されたりしているため、腸は普段よりも敏感になっているのです。
なぜ食事制限が必要なのか
敏感になっている腸に、消化の悪い食べ物や刺激の強い食べ物が入ると、腸の動きが過剰になったり、粘膜を直接傷つけたりする可能性があり、腹痛や下痢、場合によっては出血の原因となることがあります。
食事制限は、いわば腸に休暇を与え、「腸管安静」を保ち、穏やかな回復を促すために行うのです。
消化の良い食事を摂ることで、腸は食べ物を分解し栄養を吸収するための負担が軽くなり、自身の回復、つまり傷の修復や粘膜の再生にエネルギーを集中させることができます。
この期間の食事は、身体を内側からいたわる大切な時間だと考えてください。
回復までにかかる時間の目安
回復までにかかる時間は、検査の内容(観察のみか、生検やポリープ切除を行ったか)、切除したポリープの大きさや数、個人の体質や年齢、普段の健康状態によっても異なります。
ポリープを切除しなかった場合は、通常1日から3日程度で普段の生活に戻れることが多く、ポリープを切除した場合は、1週間から2週間程度は食事や生活に配慮が必要です。
ただし、あくまで一般的な目安であり、無理をせずご自身の体調をよく観察しながら、ゆっくりと元の生活に戻していくことが何よりも大切です。
回復期間の目安
| 検査内容 | 食事の注意が必要な期間 | 運動などの制限が必要な期間 |
|---|---|---|
| 観察のみ(生検なし) | 当日~翌日 | 当日は安静 |
| 生検(組織採取)あり | 2~3日程度 | 2~3日は激しい運動を避ける |
| ポリープ切除あり | 1週間~2週間程度 | 1週間程度は激しい運動を避ける |
検査当日の食事の進め方
検査が無事に終わった当日は、回復に向けた最も重要な一日で、強い空腹感があるかもしれませんが、焦らず、身体に優しいものから摂取を始めましょう。特に最初の食事は、腸の反応を見ながら慎重に進めることが重要です。
検査後最初の食事のポイント
検査終了後、1時間ほど経過して吐き気やめまいなどがなければ、まずは水分から摂取を始め、その後、お腹の張りや痛みがなければ、重湯や具のないコンソメスープなど、消化の良い液体状のものから食べ始めます。
検査のために下剤を服用しているため、腸内はきれいになっていますが、その分、腸の壁を守る粘液も少なくなっているため、最初の食事は慎重に選ぶ必要があります。
よく噛むというよりは、ゆっくりと味わいながら、時間をかけて摂取することを心がけてください。
最初の食事のポイント
- 水分から摂取を開始する
- 消化の良い液体状のものから少量ずつ
- よく味わい、ゆっくり食べる
- お腹の張りや痛みがないか常に確認する
水分補給の重要性と適切な飲み物
下剤の影響で体内の水分が失われがちなので、意識的に水分を補給することが大切です。ただし、冷たすぎる飲み物は腸を収縮させ、蠕動運動を過剰に刺激することがあります。
また、糖分が多い飲み物は腸内で発酵しやすく、ガスやお腹の張りの原因になることがあるので、常温の水や白湯、カフェインの入っていない麦茶などが最も適しています。
カフェインは利尿作用があるだけでなく、胃腸を刺激する作用もあるため、コーヒーや緑茶、紅茶などは翌日以降にしましょう。水分補給は、脱水を防ぐだけでなく、腸の動きを正常に戻し、血流を維持して傷の回復を助けるためにも大事です。
検査当日の水分補給
| 推奨される飲み物 | 避けるべき飲み物 | 注意点 |
|---|---|---|
| 水、白湯、麦茶 | 炭酸飲料、コーヒー、アルコール | 常温で少量ずつ飲むのが基本です。 |
| 経口補水液、スポーツドリンク | 牛乳、乳製品、糖分の多いジュース | 糖分や脂肪分は腸の負担になります。 |
避けるべき食事と飲み物
検査当日は、腸に少しでも負担をかける可能性のある食事や飲み物は厳禁です。
脂っこい食事(天ぷら、ラーメン、中華料理など)、食物繊維が豊富な野菜(ごぼう、きのこ類、たけのこ)や果物、ナッツや種子類、香辛料などの刺激物、乳製品、アルコール飲料などが挙げられます。
このような食品は消化に時間がかかったり、腸の粘膜を直接刺激したり、腸内でガスを発生させたりするため、腹痛や下痢を起こす原因となり、回復を遅らせないためにも、この日は我慢が必要です。
検査翌日から数日間の食事メニュー
検査翌日以降は、体調を見ながら少しずつ食事の内容を普段のものに近づけていきますが、まだ腸は完全に回復したわけではありません。
消化しやすい食事を基本としながら、段階的に食事の幅を広げていくことが、スムーズな回復への鍵となります。
消化しやすい食事の基本
消化しやすい食事の基本は、低脂肪、低残渣です。低残渣とは、消化されにくい食物繊維が少なく、便の量を増やさない食事のことをで、食材そのものを選ぶだけでなく、調理方法にも工夫が必要になります。
揚げる、炒めるといった油を多く使う調理法は避け、煮る、蒸す、茹でるといったシンプルな調理法を選びましょう。
消化の良い食べ物の例
| 分類 | 具体的な食品名 | ポイント |
|---|---|---|
| 炭水化物 | おかゆ、うどん、食パン、じゃがいも | 柔らかく調理されたものを選びます。 |
| たんぱく質 | 豆腐、卵、白身魚、鶏ささみ、はんぺん | 脂肪分が少ないものを選びます。 |
| 野菜・果物 | 大根、かぶ、バナナ、りんご | 加熱して柔らかくするか、繊維の少ないものを選びます。 |
消化の悪い食べ物の例
| 分類 | 具体的な食品名 | 避けるべき理由 |
|---|---|---|
| 食物繊維が多いもの | ごぼう、きのこ類、海藻類、玄米 | 消化に時間がかかり、腸に負担をかけます。 |
| 脂肪分が多いもの | 揚げ物、バラ肉、バター、生クリーム | 消化に時間がかかり、下痢の原因になります。 |
| 刺激が強いもの | 香辛料、柑橘類、炭酸飲料、コーヒー | 腸の粘膜を直接刺激します。 |
段階的に食事を戻す方法
食事を元に戻す際は、焦らないことが何よりも大切です。まずは、おかゆやスープなどの流動食に近いものから始め、腹痛や下痢がなければ、次にうどんや豆腐など柔らかい固形物へ移行します。
その後、白身魚や鶏ささみなどを試し、最後に加熱して柔らかくした野菜や果物を少しずつ加えていく、というように段階を踏んで進めます。
一度にたくさんの量を食べるのではなく、一食の量を少なめにして、食事の回数を増やす(1日5~6回など)ことも、腸への負担を軽減するのに有効な方法です。
新しい食材を試すときは、一品ずつ加え、体調の変化がないか確認しながら進めるとより安全です。
食事を段階的に戻すスケジュール例
| 期間 | 食事の形態 | 主なメニュー |
|---|---|---|
| 検査当日 | 水分・流動食 | 水、お茶、具のないスープ、重湯 |
| 検査翌日~2日目 | 柔らかい食事 | おかゆ、うどん、豆腐、卵豆腐、パンがゆ |
| 検査3日目~1週間 | 通常の食事に近いもの | 白米、白身魚の煮付け、鶏ささみ、煮込み野菜 |
食事メニューの例
特に、ポリープを切除した方は、より慎重に、品数を絞ってシンプルな食事から始めることをお勧めします。
検査翌日のメニュー例としては、朝食は三分粥や五分粥、昼食は出汁で煮込んだ素うどん、夕食は七分粥と豆腐の味噌汁、たらの煮付けなどが考えられます。間食には、消化の良いバナナやプリン、ゼリーなどが適しています。
3日目以降、身体が慣れてきたら、全粥にし、鶏肉のひき肉を使ったあんかけや、皮をむいて柔らかく煮たカボチャや大根、すりおろしたりんごなどを加えていくと良いでしょう。
調理方法の工夫
同じ食材でも、調理方法を工夫することで、より消化しやすくなり、食材は細かく刻んだり、ミキサーにかけたりすることで、物理的に消化の負担を減らすことができます。野菜などは、すりおろしてスープに加えるのも良い方法です。
また、じっくりと時間をかけて煮込むことで、食材が柔らかくなり、消化酵素が働きやすくなります。味付けは薄味を基本とし、出汁のうま味などを活用して、香辛料や過剰な塩分、化学調味料は避けましょう。
回復を助ける調理方法
| 調理法 | ポイント | 具体的な料理 |
|---|---|---|
| 煮る | 食材を柔らかくし、消化しやすくする | 野菜の煮物、煮魚、ポトフ |
| 蒸す | 油を使わず、素材の味を生かす | 茶碗蒸し、蒸し鶏、蒸し魚 |
| 茹でる | アクや余分な脂肪分を取り除く | 茹で野菜、湯豆腐 |
回復を助ける栄養素と食材選び
腸の回復をサポートするためには、どのような栄養素を、どのような食材から摂るかが重要です。消化のしやすさを最優先に考えながら、身体のエネルギー源となる栄養素や、組織の修復を助ける栄養素をバランス良く摂取しましょう。
腸に優しい炭水化物
炭水化物は、身体を動かすための主要なエネルギー源で、検査後は、エネルギーを回復に使うためにも、消化の良い炭水化物を適切に摂取することが大事です。
食物繊維の多い玄米や雑穀米、全粒粉パンなどは避け、食物繊維が少ない精製された穀物である、白米やうどん、白い食パンなどを選びましょう。また、じゃがいもや里芋も、加熱すれば消化しやすいたんぱく質源となります。
腸に優しい炭水化物の例
- おかゆ・重湯
- うどん(煮込み)
- 食パン(耳なし)・パンがゆ
- じゃがいも(マッシュポテトなど)
良質なたんぱく質の選び方
たんぱく質は、傷ついた組織の修復に必要な、いわば身体の材料となる栄養素ですが、肉類には脂肪分が多いものもあり、選び方には注意が必要です。
脂肪分の少ない赤身肉や皮を取り除いた鶏肉(特にささみやむね肉)、白身魚(たら、かれい、たい)、そして豆腐や卵、はんぺんなどが、良質なたんぱく質源として適しています。豆乳などの植物性たんぱく質も良い選択肢です。
良質なたんぱく質の例
- 豆腐・豆乳
- 卵(半熟卵、茶碗蒸し)
- 鶏ささみ・鶏むね肉(皮なし)
- 白身魚(たら、かれい)
避けるべき脂質と食物繊維
脂質は消化に時間がかかり、胃腸に大きな負担をかけるので、揚げ物や炒め物、バターや生クリームを多く使った料理は、回復期には適していません。
また、食物繊維は健康的なイメージがありますが、検査後の敏感な腸にとっては刺激となり、腹痛やガスの原因になることがあります。
ごぼうやきのこ、海藻類などに多い不溶性食物繊維は、便の量を増やして腸を刺激するため、しばらくの間は控えましょう。
水に溶ける水溶性食物繊維(りんごやバナナに含まれるペクチンなど)は比較的穏やかですが、これも摂りすぎには注意が必要です。
検査後の生活で注意すべきこと
食事と同様に、日常生活の過ごし方にもいくつかの注意点があります。身体に過度な負担をかける行動は、腸の回復を妨げる可能性があるので、焦らず、ご自身のペースで活動レベルを上げていくことが大切です。
日常生活への復帰タイミング
検査当日は、鎮静剤を使用した場合はもちろん、使用しなかった場合でも、車の運転や精密な作業は避けて、家でゆっくりと過ごすのが基本です。
鎮静剤を使用した場合は影響が残り、判断力が低下している可能性があるため特に注意が必要です。
デスクワークなどの事務的な仕事であれば、体調に問題がなければ翌日から復帰できることが多いですが、力仕事や長時間の立ち仕事は、数日間様子を見てから再開するのが望ましいでしょう。
復帰後も、疲れを感じたら無理せず休憩をとるようにしてください。
運動はいつから再開できるか
ウォーキングなどの軽い運動は、血行を促進し、腸の動きを整える助けになることもありますが、検査当日は避けるべきです。翌日以降、体調が良ければ散歩程度から始めてみましょう。
腹圧がかかるような激しい運動(ジョギング、筋力トレーニング、ゴルフ、テニス、水泳など)は、特にポリープを切除した場合、傷口が開いて出血するリスクを高めるため、最低でも1週間は控える必要があります。
再開時期については、医師の指示に従ってください。
長距離の移動や旅行について
ポリープを切除した場合、検査後1週間程度は、飛行機に乗るような長距離の移動や旅行は避けましょう。
気圧の変化が腸に影響を与え、お腹の張りを強くしたり、傷に影響を与えたりする可能性や、万が一、後出血などの合併症が起きた場合に、すぐに医療機関を受診できないリスクがあるためです。
大切な予定がある場合は、検査を受ける前に医師に相談してください。
アルコールや喫煙の影響
アルコールは血行を良くする作用があるため、ポリープを切除した後の傷口から出血を促す危険性があるため、ポリープ切除後は最低でも1週間は禁酒が必要です。
観察のみであった場合でも、アルコールは胃腸の粘膜を刺激するため、2~3日は控えてください。喫煙も、血管を収縮させて血流を悪化させ、傷の治りを遅らせる可能性があるため、この機会に控えることをお勧めします。
入浴に関する注意点
検査当日の入浴は、長湯を避け、シャワー程度で済ませましょう。身体が温まりすぎると血管が拡張し、出血のリスクが高まるためです。
ポリープを切除した方は、数日間はシャワー浴にして、湯船に浸かるのは医師の許可が出てからにしてください。サウナなど、急激に血圧が変動するような活動も同様に避けるべきです。
こんな時は注意が必要 – 医療機関に相談すべき症状
ほとんどの場合は順調に回復しますが、ごく稀に合併症が起こることもあります。どのような症状に注意すべきかを知っておくことは、万が一の際に迅速に対応するために非常に重要です。
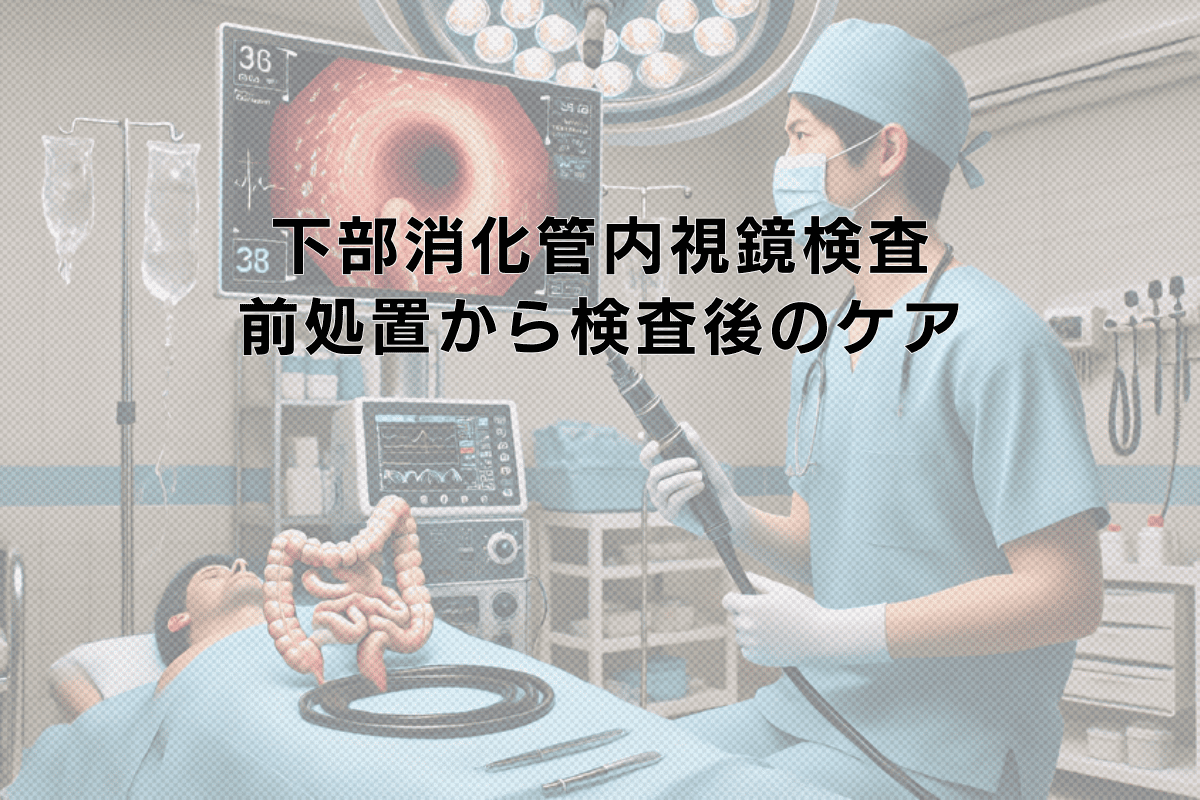
腹痛が続く場合
検査後にお腹が張る感じや、軽い腹痛が起こることは珍しくなく、腸を膨らませた空気や、腸の動きが一時的に活発になることによるものです。
しかし、我慢できないほどの強い痛みや、時間が経っても治まらない、むしろ悪化していくような腹痛は注意が必要で、腸に穴が開く穿孔(せんこう)などの重篤な合併症のサインである可能性も考えられます。
痛む場所が変わる、お腹が板のように硬くなる、といった症状も危険な兆候です。
出血が見られる場合
ポリープを切除した場合、数日間は便に少量の血液が混じることがありますが、量が多い場合(便器が真っ赤になるなど)、レバーのような血の塊が出る場合、または出血が何度も続く場合は、すぐに医療機関に連絡してください。
また、ポリープを切除していないにもかかわらず、黒い便(タール便)や血便が見られた場合も同様です。遅れて出血が起こることもあるため、検査後1~2週間程度は便の状態をよく観察しましょう。
相談すべき症状の目安
| 症状 | 注意すべき状態 | 考えられること |
|---|---|---|
| 腹痛 | 我慢できないほどの強い痛み、持続する痛み | 穿孔、腸炎など |
| 出血 | 便器が赤くなるほどの出血、血の塊 | 後出血 |
| その他 | 38度以上の発熱、繰り返す吐き気・嘔吐 | 感染、腸閉塞など |
発熱や吐き気がある場合
検査後に38度以上の高熱が出たり、吐き気や嘔吐が続いたりする場合も、注意が必要なサインです。悪寒や震えを伴うこともあり、腸炎や穿孔による腹膜炎など、何らかの感染や炎症が体内で起きている可能性を示唆しています。
たかが熱、たかが吐き気と思わずに、これらの症状が腹痛や出血と伴に見られる場合は特に、速やかな対応が重要です。
大腸内視鏡検査後の食事と生活に関するよくある質問
ここでは、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- ポリープ切除をした場合、食事内容は変わりますか。
-
食事内容はより慎重に進める必要があります。ポリープを切除した場合、腸の粘膜に治癒すべき傷ができている状態で、傷の治りを妨げないように、食事には注意が求められます。
検査当日は水分のみとし、翌日以降もおかゆなどの流動食から始め、数日間から1週間程度かけてゆっくりと通常の食事に戻していきます。
アルコールや香辛料などの刺激物は、出血のリスクを高めるため、医師の指示がある期間は厳禁で、ご自身の判断で食事を進めず、検査を受けた医療機関の指示に従うことが重要です。
- いつから普段通りの食事に戻せますか。
-
ポリープを切除しなかった場合は、2~3日後から、切除した場合は1~2週間後が目安となりますが、これはあくまで一般的な目安です。回復の速さには個人差があります。
食事を戻す際は、ご自身の体調をよく観察し、腹痛や下痢などの症状が出ないかを確認しながら進めることが大切です。
もし、何か特定の食べ物を食べた後にお腹の調子が悪くなるようなら、その食材はまだ避けた方が良いでしょう。
- 便秘になった場合はどうすればよいですか。
-
検査後は食事量が減ったり、食物繊維を控えたりするため、一時的に便秘になることがあります。まずは、こまめな水分補給を心がけると、便を柔らかくするのに役立ちます。
また、体調が許せば、軽いウォーキングなどでお腹を刺激するのも良いでしょう。食事面では、消化が良く、ある程度便の材料となるバナナや、柔らかく煮た野菜などを少しずつ試してください。
それでも改善しない場合や、お腹の張りがつらい場合は、自己判断で市販の下剤を使わず、まずはかかりつけの医療機関に相談してください。
- 乳製品はいつから摂取できますか。
-
乳製品の摂取は、数日間待ちましょう。牛乳に含まれる乳糖は、人によっては下痢の原因になることがあります。下剤で腸内環境がリセットされている検査後は、普段は問題ない方でもお腹が緩くなることがあります。
ヨーグルトやチーズなども同様に、腸の調子が完全に落ち着いたことを確認してから、少量ずつ試してください。目安としては、検査後3日~1週間程度経ってからが良いでしょう。
次に読むことをお勧めする記事
【下部消化管内視鏡検査の手順と注意点|前処置から検査後の合併症】
検査後”だけでなく、前処置や合併症まで全体像を押さえると安心です。出血・穿孔などのリスクと対策を理解し、落ち着いて回復期を過ごす助けになります。
【大腸ポリープの内視鏡治療 – 早期発見と切除術の重要性】
検査後の注意点を理解したら、なぜポリープの早期発見と切除が重要なのかについても知っておくと、定期的な検査の意義がより明確になります。ポリープの種類や切除方法、がん予防との関係について詳しく解説しています。
以上
参考文献
Yamaguchi H, Fukuzawa M, Minami H, Ichimiya T, Takahashi H, Matsue Y, Honjo M, Hirayama Y, Nutahara D, Taira J, Nakamura H. The relationship between post-colonoscopy colorectal cancer and quality indicators of colonoscopy: The latest single-center cohort study with a review of the literature. Internal Medicine. 2020 Jun 15;59(12):1481-8.
Miyakawa A, Kodera S, Sakuma Y, Shimada T, Kubota M, Nakamura A, Itobayashi E, Shimura H, Suzuki Y, Sato Y, Shimura K. Effects of early initiation of solid versus liquid diet after endoscopic submucosal dissection on quality of life and postoperative outcomes: a prospective pilot randomized controlled trial. Digestion. 2019 Oct 1;100(3):160-9.
Moriya T, Fukatsu K, Ueno C, Hashiguchi Y, Maeshima Y, Omata J. Effects of preoperative use of an immune-enhancing diet on postoperative complications and long-term outcome: a randomized clinical trial in colorectal cancer surgery in Japanese patients. Gastroenterol. Hepatol. 2015;2:1-8.
Mochida K, Ishibashi F, Suzuki S, Saito D, Kawakami T, Kobayashi K, Nagai M, Morishita T. Dietary restriction after cold snare polypectomy of colorectal polyp for prevention of delayed bleeding. JGH Open. 2023 Nov;7(11):777-82.
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Tanaka S, Kashida H, Saito Y, Yahagi N, Yamano H, Saito S, Hisabe T, Yao T, Watanabe M, Yoshida M, Saitoh Y. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):219-39.
Knudsen MD, Wang L, Wang K, Wu K, Ogino S, Chan AT, Giovannucci E, Song M. Changes in lifestyle factors after endoscopic screening: a prospective study in the United States. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2022 Jun 1;20(6):e1240-9.
Fu Z, Shrubsole MJ, Smalley WE, Wu H, Chen Z, Shyr Y, Ness RM, Zheng W. Lifestyle factors and their combined impact on the risk of colorectal polyps. American journal of epidemiology. 2012 Nov 1;176(9):766-76.
Wang L, Knudsen MD, Lo CH, Wang K, He M, Polychronidis G, Hang D, He X, Zhong R, Wu K, Chan AT. Adherence to a healthy lifestyle in relation to colorectal cancer incidence and all‐cause mortality after endoscopic polypectomy: A prospective study in three US cohorts. International journal of cancer. 2022 Nov 1;151(9):1523-34.
Hassan CE, Pickhardt PJ, Marmo R, Choi JR. Impact of lifestyle factors on colorectal polyp detection in the screening setting. Diseases of the colon & rectum. 2010 Sep 1;53(9):1328-33.










