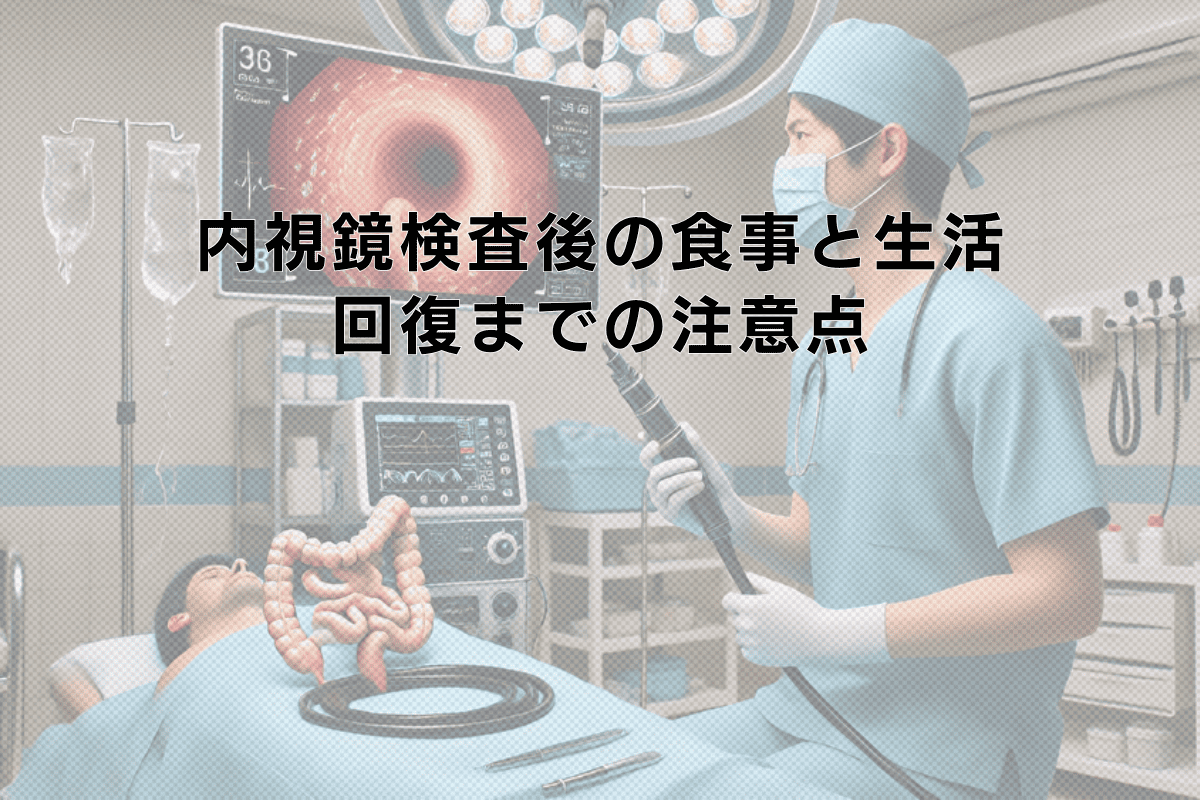内視鏡検査後の体はまだデリケートな状態で、食事や生活面ではいくつかの注意点があります。
この記事では、内視鏡検査を受けた方が、検査当日から普段の生活にスムーズに戻るために大事な、食事の進め方や生活上の注意点について詳しく解説します。
検査後の食事はいつから何を食べれば良いのか、ポリープを切除した場合はどうすれば良いのか、といった疑問にお答えします。ご自身の体をいたわりながら、回復させていきましょう。
内視鏡検査後の食事で基本となる考え方
内視鏡検査の後は、消化管が普段よりも敏感な状態になっているため、食事に対して普段以上の配慮をすることが、体の順調な回復を助けます。
なぜ食事制限が大事なのか
内視鏡を挿入する際どれだけ丁寧に操作しても、消化管の粘膜には物理的な刺激が加わります。
胃や大腸の内部を隅々まで観察しやすくするために、空気や炭酸ガスを送気して消化管を十分に膨らませるため、検査後にお腹の張りを感じることが少なくありません。
また、ポリープ切除や生検(組織を一部採取して詳しく調べる検査)を行った場合は、粘膜に意図的に小さな傷を作っている状態です。
このような状態で消化に負担のかかる食事をとると、胃腸のぜん動運動が過剰に活発になり、腹痛や不快感の原因になります。
さらに、まれに出血や穿孔(消化管に穴が開くこと)といった重篤な合併症を起こす危険性を高めることがあります。食事制限は、こうしたリスクを最小限に抑え、疲弊した消化管を優しく休ませてあげるためにとても重要です。
消化の良い食事を心がける
検査後の食事における最大の原則は、消化の良いものを選ぶことです。
消化が良い食べ物とは、胃腸に長く留まらず、少ない消化液でスムーズに分解・吸収されるもので、脂肪分や食物繊維が少なく、物理的に柔らかく調理されたものが適しています。
食べ物が胃腸に滞在する時間が短いほど、消化管への負担は軽くなります。
逆に、脂肪分を多く含む揚げ物や肉の脂身、食物繊維が豊富なきのこ・海藻類、硬い野菜などは消化に時間がかかり、胃腸に大きな負担をかけるため、回復期には避けてください。
調理法も重要で、「煮る」「蒸す」といった水分を多く含み、柔らかく仕上げる方法が推奨されます。
消化の目安となる食品の例
| 食品の種類 | 消化に良い食品(推奨) | 消化に悪い食品(避ける) |
|---|---|---|
| 炭水化物 | おかゆ、うどん、食パン、じゃがいも | 玄米、ラーメン、パスタ、さつまいも |
| タンパク質 | 豆腐、鶏ささみ、白身魚、卵 | 豚バラ肉、ソーセージ、青魚、貝類 |
| 野菜 | 大根、かぶ、人参(加熱したもの) | ごぼう、きのこ類、たけのこ、海藻類 |
刺激物を避ける理由
香辛料を多く使った辛い食べ物、過度に塩辛いものや甘いもの、極端に熱いものや冷たいもの、炭酸飲料、カフェイン、アルコールなどは、消化管の粘膜を直接的に刺激します。
検査後のデリケートな粘膜にとって刺激物は炎症を悪化させたり、血管を拡張させて出血のリスクを高めたり、腹痛を起こしたりする原因となります。
コーヒーやアルコールは胃酸の分泌を過剰に促す作用もあり、胃の不快感を増す可能性があります。胃腸が完全に落ち着き、普段の状態に戻るまでは、こうした刺激物は控えるようにしましょう。
ゆっくりよく噛んで食べることの重要性
食事の内容だけでなく、食べ方にも注意が必要です。早食いや大食いは、胃腸に一度に大きな負担をかけてしまうので、検査後は、一口ずつゆっくりと、時間をかけて食事をすることを心がけてください。
よく噛むことで食べ物が唾液と十分に混ざり合い、細かくなるため、胃での消化が助けられ、胃腸全体の負担が軽減されます。
食事の量は「腹八分目」を目安にし、満腹になるまで食べるのは避け、必要であれば、1日の食事回数を3回から5〜6回に増やして、一回あたりの量を減らすのも良い方法です。
検査当日の食事の流れと具体的なメニュー
検査が終わって一番気になるのが、その日の食事でしょう。検査当日は、特に慎重に食事を進める必要があります。
鎮静剤を使用した場合の注意点
鎮静剤を使用して検査を受けた場合、検査後もしばらく眠気やふらつき、判断力の低下が残ることがあります。個人差はありますが、通常1〜2時間程度、クリニックのリクライニングチェアなどで安静にしてから帰宅します。
鎮静剤の影響が残っている間は、飲み込む力が十分に回復していない可能性もあるため、食事を開始する前に、まずは常温の水を少量飲んでみて、むせたり、飲み込みにくさを感じたりしないかを入念に確認することが大切です。
問題がなければ食事を開始できますが、少しでも違和感があれば、焦らずにもう少し時間を置いてから食事をとり、当日は車の運転や機械の操作、重要な判断を伴う仕事は避けましょう。
検査後最初の食事のタイミング
食事を開始して良い時間は、受けた検査の種類によって異なります。胃カメラの場合、喉の局所麻酔が完全に切れるまで飲食はできません。
麻酔が効いている状態で飲食すると、食べ物や飲み物が気管に入ってしまう誤嚥(ごえん)を起こす危険があるためで、通常、検査後1〜2時間が目安です。
大腸カメラの場合は喉の麻酔はないため、医師の許可があれば比較的早く食事をとることが可能ですが、いずれの場合も、まずは水分(水や白湯、麦茶など)から試してください。
その後、お腹の張りや不快感がないことを確認してから、消化の良い固形物を口にするようにし、空腹を感じていても、焦って食事を始めないことが重要です。
検査当日の食事スケジュールの目安
| 時間 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 検査終了直後 | まずは安静にする | 鎮静剤や麻酔の影響が抜けるのを待つ |
| 検査後1〜2時間 | 水分補給(水・白湯) | むせないかを確認しながら少量ずつ飲む |
| 検査後2〜3時間以降 | 固形食(消化の良いもの) | お腹の様子を見ながらゆっくり食べる |
当日におすすめの食事例
検査当日の食事は、とにかく消化に優しく、胃腸に負担をかけないものが大前提で、エネルギーと水分を補給しつつも、体をいたわるメニューを選びましょう。
調理法は「煮る」「蒸す」が基本で、柔らかく、人肌程度の温かいものをゆっくりとよく噛んで食べてください。
- おかゆ(味付けは薄く)
- 具のない素うどん(温かいもの)
- 豆腐(湯豆腐や冷奴)
- ポタージュスープ(じゃがいもやかぼちゃなど)
当日は避けるべき食べ物
検査当日は、消化管をしっかりと休ませるために、いくつかの食品群は避けてください。知らずに食べてしまうと、腹痛や下痢、お腹の張りなどの不快な症状につながることがあります。
検査当日に避けるべき食品群
| 食品群 | 具体例 | 避けるべき理由 |
|---|---|---|
| 脂肪の多いもの | 揚げ物、中華料理、ラーメン、バター、菓子パン | 消化に非常に時間がかかり胃腸に大きな負担をかける |
| 食物繊維の多いもの | きのこ類、海藻類、こんにゃく、ごぼう、豆類 | 腸内でガスを発生させやすく、お腹が張りやすい |
| 刺激物 | 香辛料、柑橘類、炭酸飲料、コーヒー、アルコール | 消化管の粘膜を直接刺激し、炎症や痛みを引き起こす |
検査翌日からの食事の進め方と回復食
検査翌日になると、体調も少しずつ落ち着いてくる頃ですが、まだ油断は禁物です。ここからの数日間で、段階的に食事を普段の内容に戻していくことが、スムーズな回復への鍵となります。
2日目から3日目の食事
検査の翌日、お腹の張りや痛みがなければ、前日よりも少し食事の幅を広げることができ、おかゆから普通の柔らかめに炊いたご飯へ、具のないうどんから、溶き卵や細かく刻んだ鶏ささみなどを加えたうどんへと移行してみましょう。
ただし、引き続き消化の良いものを選ぶという基本原則は厳守し、調理法も、炒め物や揚げ物は避け、煮物や蒸し料理、スープなどを中心にします。
食事の量も一度にたくさん食べるのではなく、数回に分けて少量ずつ食べる方が胃腸への負担を減らせます。
回復期の食事メニュー例
| 食事 | メニュー例 | ポイント |
|---|---|---|
| 朝食 | 卵雑炊、野菜スープ、食パン(焼かずに) | 温かく、水分が多いものを選ぶ |
| 昼食 | 煮込みうどん(鶏肉、ネギ入り)、湯豆腐 | 消化の良いタンパク質を少しずつ加える |
| 夕食 | 白身魚の煮付け、柔らかく煮た大根 | 油を使わない調理法を心がける |
4日目以降の食事の目安
腹痛やお腹の張りなどの症状がなく、順調に回復していれば、4日目あたりからさらに食事を通常の状態に近づけていきます。
まだ揚げ物や香辛料の強いものは避けた方が無難ですが、使用する油の量が少ない炒め物(野菜炒めなど)を少しずつ試しても良いでしょう。食物繊維の多い野菜も、少量から、よく加熱して柔らかくした状態で試してみてください。
自分の体調とよく相談しながら、焦らずゆっくりと進めることが何よりも大事で、もし何かを食べてお腹の調子が悪くなった場合は、無理をせず、再び消化の良い食事に1〜2日戻してから再挑戦してください。
4日目以降に試せる食品の例
| 食品カテゴリ | 試せる食品の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 普通のご飯、パスタ(オイル系) | クリーム系やミートソースはまだ避ける |
| タンパク質 | 鶏もも肉(皮なし)、豚ヒレ肉、納豆 | 少量から試し、よく噛んで食べる |
| 野菜・果物 | 葉物野菜(加熱)、バナナ、りんご | 生の野菜や柑橘類はまだ慎重に |
通常食に戻すタイミング
通常食に戻す明確な日数が決まっているわけではなく、回復のペースには個人差が大きく影響します。一般的には、検査後1週間程度でほとんどの方が普段通りの食事に戻れますが、これはポリープ切除など特別な処置をしていない場合です。
ポリープを切除した場合は、さらに慎重な食事管理が求められます。通常食に戻す最終的な目安は、脂っこいものや刺激のあるものを食べても、腹痛やお腹の張り、下痢などの症状が全く出ないことです。
この状態になるまでは、消化の良い食事を基本とすることを忘れず、「もう大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。
胃カメラと大腸カメラ後の食事の違い
胃カメラ(上部消化管内視鏡)と大腸カメラ(下部消化管内視鏡)では、観察する場所が違うため、検査後の注意点にも少し違いがあります。
胃カメラ後の食事のポイント
胃カメラの最も大きな特徴は、検査をスムーズに行うために喉に局所麻酔を使用することです。
麻酔の影響で、検査後は嚥下(えんげ)、つまり食べ物や飲み物を飲み込む機能が一時的に低下するので、麻酔が完全に切れるまでは誤嚥のリスクがあり、飲食は厳禁です。
検査後1〜2時間経ち、水を少量飲んでみて、むせることなく確実に飲み込めることを確認してから食事を開始します。食事内容は、喉への刺激が少ない、柔らかくて熱すぎないものが良いでしょう。
最初のうちは、喉にいがらっぽさや違和感が残ることもありますが、数時間から1日程度で自然に改善することがほとんどです。
大腸カメラ後の食事で特に気をつけたいこと
大腸カメラでは、検査前に多量の下剤を服用して腸内を完全に空にするため、検査後は腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが一時的に乱れやすく、非常にデリケートな状態です。
また、観察のために腸を膨らませた空気や炭酸ガスが残り、お腹が張りやすくなるので、食事は、腸への負担が少なく、ガスが発生しにくいものを選んでください。
食物繊維の多い食品はガスの主な原因になりやすいため、数日間は控え、水分をしっかり摂ることは、腸の動きを助け、腸内環境を整える上で有効です。
検査別の注意点比較
| 項目 | 胃カメラ(上部) | 大腸カメラ(下部) |
|---|---|---|
| 麻酔の影響 | 喉の麻酔による嚥下機能の低下 | 鎮静剤を使用した場合の眠気など |
| 食事開始の目安 | 検査後1〜2時間(喉の麻酔が切れてから) | 医師の許可後、比較的早期に可能 |
| 特に注意する点 | 誤嚥、喉への刺激 | お腹の張り、腸内環境の乱れ |
生検(組織検査)を行った場合の違い
胃や大腸の粘膜に疑わしい部分があった場合、診断を確定するためにごく小さな組織片を採取する(生検)ことがあります。
生検で使用する器具は非常に小さく、採取する組織も数ミリ程度であるため、粘膜に残る傷はごくわずかで、食事制限は通常の内視鏡検査と大きく変わらないことがほとんどです。
ただし、担当した医師から食事に関する特別な指示(当日の飲酒を控えるなど)があった場合は、必ず従ってください。ごくまれに出血のリスクがあるため、基本的な注意点をより一層守ることが大切です。
ポリープ切除を行った場合の特別な食事注意点
大腸カメラ検査の際にポリープが見つかり、その場で切除することがあり、切除後は粘膜に人工的な潰瘍(傷)ができている状態なので、食事や生活にはより一層の注意が必要です。
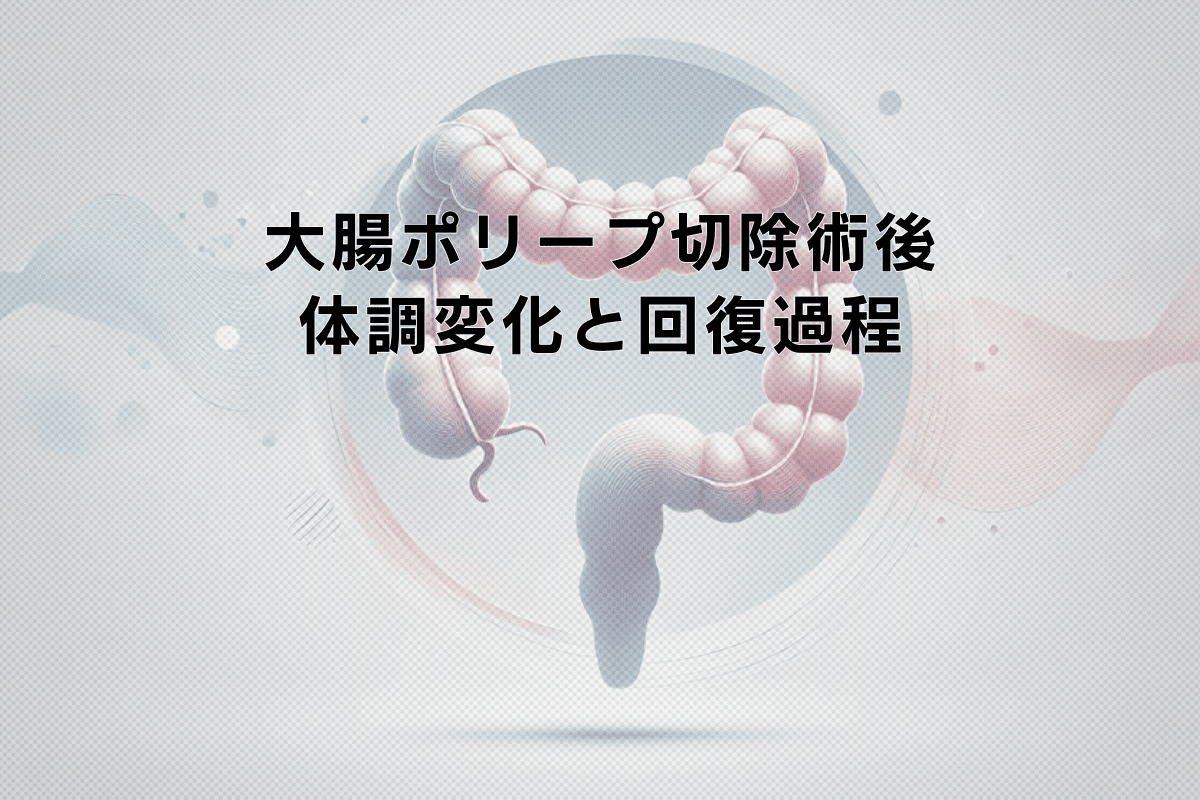
ポリープ切除後になぜ特別な配慮が必要か
ポリープを切除した部位は、傷が治る過程で出血(後出血)や穿孔(せんこう・腸に穴が開くこと)といった合併症を起こす可能性があり、切除後数時間から1週間後くらいに起こることがあります。
リスクをできるだけ低くするために、食事内容を厳しく管理し、腸管を安静に保つことが非常に重要です。消化の悪い食べ物や刺激物は、腸のぜん動運動を活発にし、傷口に物理的な負担をかけ、出血のリスクを高めることにつながります。
医師の指示に従い、慎重に食事を進めてください。
食事制限の期間はどのくらいか
食事制限の期間は、切除したポリープの大きさや数、場所、切除方法によって異なりますが、一般的には1週間から2週間程度、通常よりも厳しい食事制限が求められます。
最初の数日間は、おかゆや素うどん、具のないスープなど、極めて消化の良いものに限定されることもあり、2cm以上の大きなポリープを切除した場合は、より長期間の制限が必要になることもあります。
期間や食事内容については、検査を受けた医療機関の指示を必ず守り、自己判断で早く通常食に戻すことは絶対に避けましょう。
ポリープ切除後に特に避けるべき食品
| カテゴリ | 避けるべき食品の例 | 理由 |
|---|---|---|
| 脂肪・油分 | 天ぷら、フライ、バター、生クリーム、ラーメン | 消化に時間がかかり、腸に大きな負担をかける |
| 食物繊維 | 玄米、きのこ、海藻、ごぼう、豆類、ナッツ | 腸を刺激し、便の量を増やして傷口に触れるため |
| 刺激物 | 唐辛子、カレー、コーヒー、アルコール、炭酸飲料 | 血行を促進し、出血のリスクを高めるため |
回復を助ける食事の工夫
ポリープ切除後の食事制限期間中は、食べられるものが限られますが、少し工夫することで栄養を補い、回復を助けることができます。
- 調理法を工夫する(煮る、蒸す、ミキサーにかけるなど)
- 良質なタンパク質を補給する(豆腐、鶏ささみ、白身魚、卵豆腐など)
- 水分を十分に摂り、便を柔らかく保つ
野菜はそのまま食べるのではなく、柔らかく煮てポタージュスープにすると、消化しやすく栄養も摂りやすいです。食事はゆっくりとよく噛んで食べ、腸への負担をできるだけ軽くすることを常に意識しましょう。
食事以外で注意すべき生活上のポイント
検査後の順調な回復には、食事だけでなく生活全般にわたる配慮も大切です。アルコール、運動、入浴、移動などは、いつから再開して良いか、一般的な目安を解説します。
アルコール(飲酒)はいつから可能か
アルコールは血管を拡張させ血行を良くする作用があるため、検査後の飲酒は出血のリスクを著しく高める可能性があり、生検やポリープ切除を行った場合は、傷口からの出血を誘発する恐れがあるため、厳禁です。
何も処置をしていない場合でも、検査当日の飲酒は絶対に避け、翌日以降も、最低2〜3日は控えましょう。
ポリープを切除した場合は、医師の指示にもよりますが、最低でも1週間、できれば2週間程度の禁酒が必要で、再開する際も、まずは少量のビールなどから試し、体の調子を見ながらにしましょう。
運動や仕事復帰のタイミング
デスクワークなどの体に負担の少ない仕事であれば、検査翌日から復帰できることがほとんどですが、鎮静剤を使用した場合は、当日は車の運転や危険な作業はできません。
ジョギングや筋力トレーニングなどの激しい運動や、腹圧のかかる作業(重いものを持つ、ゴルフのスイングなど)は、食事制限と同様に、合併症のリスクを高める可能性があります。
ポリープ切除をした場合は注意が必要で、1週間程度は運動を控えるように指示されることが一般的です。排便時の強いいきみも腹圧をかけるので、便秘にならないよう水分摂取を心がけることも大切です。
ウォーキングなどの軽い運動から徐々に再開しましょう。
入浴に関する注意点
検査当日は、長時間の入浴や熱いお風呂は避けて、シャワー程度で済ませます。体を温めすぎると全身の血行が良くなり、消化管の血管も拡張して出血のリスクにつながることがあるためです。
特にポリープ切除後は、数日間シャワーのみとするのが安全です。サウナや岩盤浴なども血行を著しく促進するため、しばらくは控え、入浴を再開するタイミングについては、検査を受けた医療機関の指示に従いましょう。
生活上の活動再開目安
| 活動 | 処置なしの場合 | ポリープ切除ありの場合 |
|---|---|---|
| 飲酒 | 当日は禁止、翌日以降も2〜3日控える | 最低1週間〜2週間は禁止 |
| 運動 | 当日は安静、翌日から軽いものなら可 | 最低1週間程度は激しい運動を禁止 |
| 入浴 | 当日はシャワーのみを推奨 | 数日間はシャワーのみ |
飛行機や長距離移動について
ポリープ切除を受けた場合、飛行機の利用には注意が必要です。
上空では気圧が低下するため、腸管内のガスが膨張し、切除した傷口に圧力がかかって出血や穿孔を誘発する危険性があるため、ポリープ切除後、約1週間から10日間は飛行機に乗ることを避けるよう指導されるのが一般的です。
長距離の車や新幹線での移動も、体に振動が伝わり腹圧がかかるため、できれば数日間は避けてください。
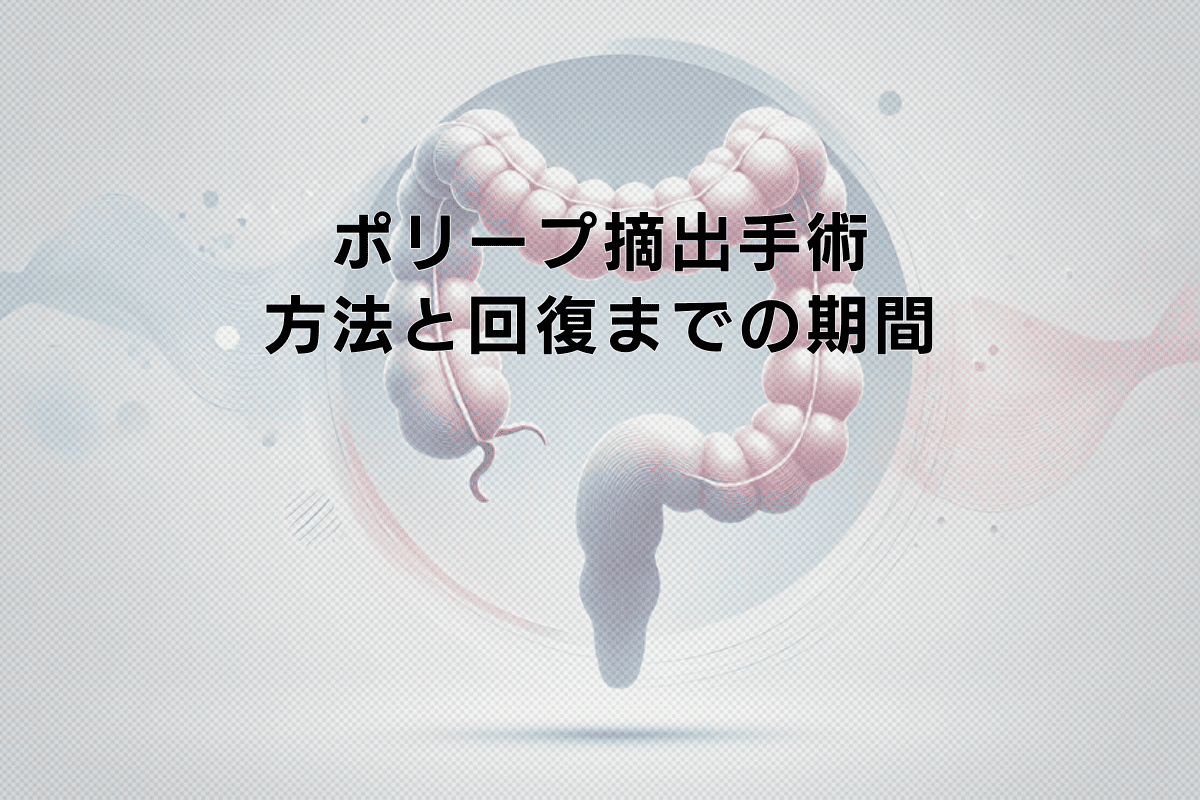
医療機関に相談すべきサイン
ほとんどの場合、内視鏡検査は安全に終わり、順調に回復しますが、ごくまれに合併症が起こることもあります。
腹痛が続く、または強くなる場合
検査後、お腹に溜まったガスによる軽い腹痛は起こることがありますが、これは排ガス(おなら)とともによくあることで、時間とともに改善します。
しかし、痛みが我慢できないほど強い場合、時間が経っても全く治まらない場合、どんどん悪化する場合は注意が必要で、消化管穿孔などの重篤な合併症のサインである可能性も考えられます。
発熱や吐き気がある場合
検査後に38度以上の熱が出る、吐き気が治まらない、嘔吐してしまう、といった症状も注意信号です。体内で炎症や感染が起きている可能性があります。
腹痛を伴う場合は、腹膜炎など緊急の対応が求められる状態の可能性もありますので、速やかな連絡が必要です。
- 我慢できないほどの強い腹痛
- 時間が経っても治まらない、悪化する腹痛
- 38度以上の発熱
- 黒い便(タール便)や血便
黒い便や血便が出た場合
便の色は消化管の状態を示す重要な指標です。
ポリープ切除後などに、ごく少量の血液が便に混じることはありますが、鮮やかな赤色の便(血便)が何度も出る場合や、イカ墨のような真っ黒でドロリとした便(タール便または下血)が出た場合は、消化管内で出血が起きているサインです。
黒い便は、胃や十二指腸など上部消化管で出血した血液が、胃酸の影響で黒く変色したことを示し、出血量が多い場合は貧血やショック状態に至る危険もあります。すぐに医療機関に連絡してください。
内視鏡検査後の食事に関するよくある質問
最後に、検査を受けた方からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- コンビニで買える食事はありますか?
-
検査後の食事として、おかゆ、レトルトのうどん、豆腐、茶碗蒸し、ポタージュスープ、ゼリー飲料などは多くのコンビニで手に入ります。ヨーグルトやプリンなどのデザートも良いでしょう。
選ぶ際は、成分表示を見て、脂質や塩分ができるだけ少ないものを選び、お弁当や総菜、ホットスナック類は、揚げ物や味の濃いものが多いため、回復期には避けた方が無難です。
- コーヒーやお茶はいつから飲めますか?
-
コーヒー、紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、胃酸の分泌を促し、胃腸を刺激する作用があります。検査当日は、水や麦茶、白湯などカフェインの含まれていない飲み物を選びましょう。
翌日以降、特に症状がなければ少量から試しても構いませんが、胃の不快感などがあれば中止してください。ポリープ切除後は、粘膜の傷が治るまで刺激を避けるため、1週間程度控えるのがより安全です。
- 辛いものや脂っこいものが好きなのですが、いつから食べられますか?
-
香辛料を多く使った料理や揚げ物、焼肉などの脂っこい食事は、消化管への負担が非常に大きいです。処置のなかった方でも、少なくとも検査後1週間は控えることを推奨します。
ポリープ切除をした場合は、傷口が安定するまで2週間以上は避けるようにしてください。再開する際は、本当に少量から試し、お腹の調子に変化がないか注意深く観察することが大切です。
- 食事制限中に栄養が偏らないか心配です。
-
数日間から1週間程度の食事制限であれば、栄養バランスについて過度に心配する必要はありません。この期間で最も重要なのは、消化管を休ませて安全に回復させることで、食事が通常に戻れば、栄養は自然と補えます。
無理に栄養を摂ろうとして消化の悪いものを食べることのほうが問題です。もし食事制限が長期間にわたる場合や、もともと持病があるなどで栄養面が心配な場合は、検査を受けた医療機関の医師や管理栄養士にご相談ください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査で行うポリープ切除後の経過と注意点】
本記事で基本を押さえたら、実際にポリープ切除後の数日〜2週間をどう過ごすかを具体的に把握すると安心です。切除があった方に特に参考になります。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
検査後の過ごし方を理解した皆さんには、次回検査の準備も合わせて知っておくと、負担や再検査リスクの軽減に繋がります。
以上
参考文献
Miyakawa A, Kodera S, Sakuma Y, Shimada T, Kubota M, Nakamura A, Itobayashi E, Shimura H, Suzuki Y, Sato Y, Shimura K. Effects of early initiation of solid versus liquid diet after endoscopic submucosal dissection on quality of life and postoperative outcomes: a prospective pilot randomized controlled trial. Digestion. 2019 Oct 1;100(3):160-9.
Goto O, Fujishiro M, Oda I, Kakushima N, Yamamoto Y, Tsuji Y, Ohata K, Fujiwara T, Fujiwara J, Ishii N, Yokoi C. A multicenter survey of the management after gastric endoscopic submucosal dissection related to postoperative bleeding. Digestive diseases and sciences. 2012 Feb;57(2):435-9.
Kim S, Cheoi KS, Lee HJ, Shim CN, Chung HS, Lee H, Shin SK, Lee SK, Lee YC, Park JC. Safety and patient satisfaction of early diet after endoscopic submucosal dissection for gastric epithelial neoplasia: a prospective, randomized study. Surgical endoscopy. 2014 Apr;28(4):1321-9.
Knudsen MD, Wang L, Wang K, Wu K, Ogino S, Chan AT, Giovannucci E, Song M. Changes in lifestyle factors after endoscopic screening: a prospective study in the United States. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2022 Jun 1;20(6):e1240-9.
Ferreira LE, Topazian MD, Harmsen WS, Zinsmeister AR, Baron TH. Dietary approaches following endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A survey of selected endoscopists. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy. 2010 Dec 16;2(12):397.
Romagnuolo J, Flemons WW, Perkins L, Lutz L, Jamieson PC, Hiscock CA, Foley L, Meddings JB. Post-endoscopy checklist reduces length of stay for non-variceal upper gastrointestinal bleeding. International Journal for Quality in Health Care. 2005 Jun 1;17(3):249-54.
Sutton MM, Gregoski MJ, Rockey DC. Delay in post-endoscopic refeeding in patients with upper GI bleeding leads to increased hospital length of stay. The American Journal of the Medical Sciences. 2024 Sep 1;368(3):190-5.
Cubillan MP, Flescher A, Srivastava S, Raphael K. TO EAT OR NOT TO EAT-DOES POST-ERCP DIET AFFECT THE DEVELOPMENT OF PANCREATITIS?. Gastrointestinal Endoscopy. 2023 Jun 1;97(6):AB652-3.
Huberty V, Boskoski I, Bove V, Van Ouytsel P, Costamagna G, Barthet MA, Devière J. Endoscopic sutured gastroplasty in addition to lifestyle modification: short-term efficacy in a controlled randomised trial. Gut. 2021 Aug 1;70(8):1479-85.
Normand E, Montero A, López-Nava G, Bautista-Castaño I. Review about psychological barriers to lifestyle modification, changes in diet habits, and health-related quality of life in bariatric endoscopy. Nutrients. 2022 Jan 29;14(3):595.