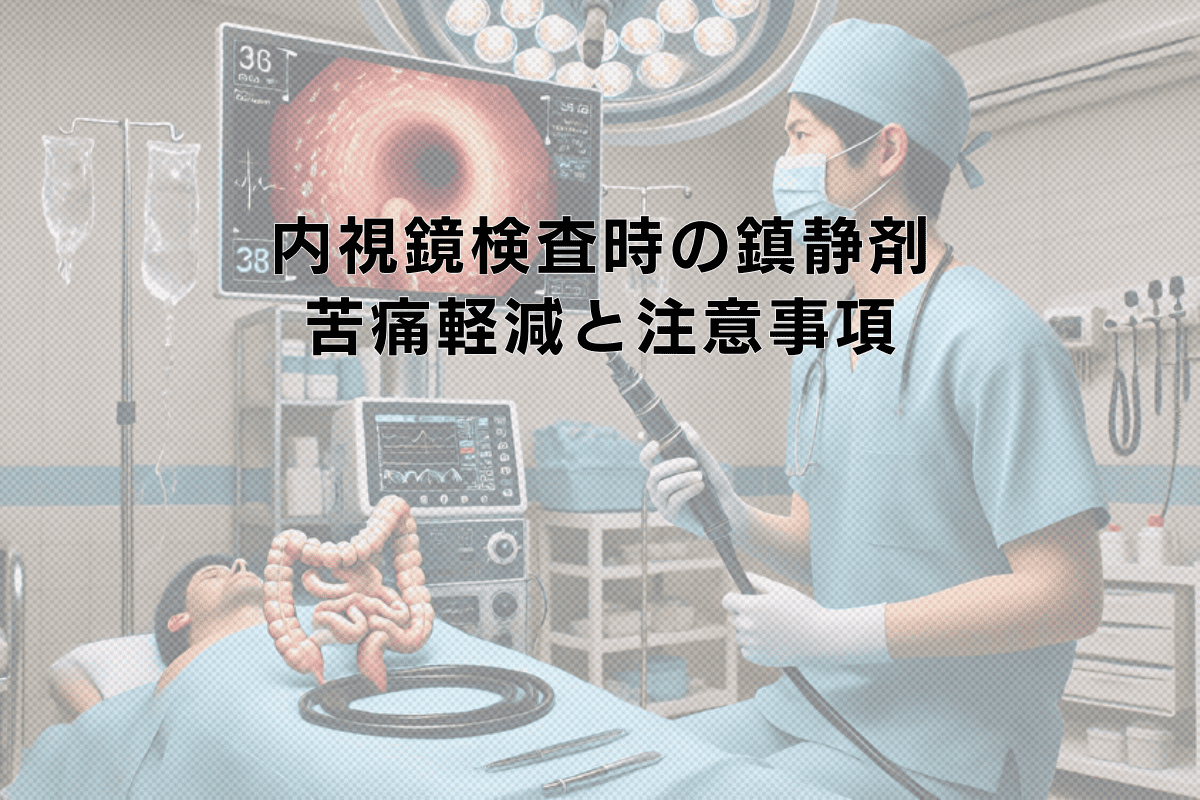内視鏡検査は、消化器の病気を正確に診断するために非常に有用な検査ですが、一部の患者さんは検査中の苦痛や不快感を心配し、検査を受けることに躊躇することがあります。
胃カメラや大腸カメラといった内視鏡検査では、挿入時の違和感や吐き気、お腹の張りなどが生じることがあり、近年では、苦痛を和らげるために鎮静剤を使用する方法が広く行われています。
鎮静剤を使うことで、患者さんはリラックスした状態で検査を受けられ、苦痛を軽減することが可能です。
内視鏡検査における苦痛の要因
内視鏡検査は、食道、胃、十二指腸、大腸などを直接観察し、病変の有無や状態を確認するために欠かせない医療行為です。しかし、性質上、患者さんにはいくつかの苦痛要因があります。
嘔吐反射とその対処
胃内視鏡検査において、多くの患者さんが最も心配されるのが「嘔吐反射」です。内視鏡スコープが喉を通過する際に、体が異物を排除しようとする生理的な反応として、強い吐き気やえづきが生じます。
反射は個人差が大きく、過去に胃カメラで苦しい経験をした方は、強い不安を感じるかもしれません。嘔吐反射を和らげるためには、喉の麻酔スプレーや、より細いスコープの使用、そして鎮静剤の使用が効果的な方法です。
鎮静剤は意識を穏やかに鎮めることで、嘔吐反射を抑え検査をスムーズに進める手助けをします。
検査中の不安と緊張
内視鏡検査を受ける多くの患者さんは、検査自体への不安や緊張を感じていて、これは、未知の検査に対する恐れや痛みへの懸念、あるいは検査結果に対する心配から生じるものです。
強い不安や緊張は体の筋肉を硬直させ、検査中の不快感を増幅させる可能性があります。鎮静剤を使用すると精神的な緊張が和らぎ、リラックスした状態で検査を受けられるため、体の余分な力が抜け検査中の不快感が軽減されます。
体位による身体的負担
大腸内視鏡検査では、検査中に体の向きを変えたり体位を調整したりします。これはスコープをスムーズに進めるためや、腸管のひだの裏側まで丁寧に観察するために必要な動作です。
患者さんによっては、特定の体位を保つことが身体的に負担となる場合があり、また、検査中に腸管に空気を注入することで、お腹の張りや痛みを覚えることもあります。
鎮静剤を使用することで、検査中の体位変換や空気注入による不快感を意識しにくくなり、身体的な負担が軽減されます。
検査中の主な不快感
| 不快感の種類 | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 |
|---|---|---|
| 吐き気・嘔吐 | 高い頻度 | 低い頻度 |
| お腹の張り | 低い頻度 | 高い頻度 |
| 痛み・違和感 | 中程度の頻度 | 中程度の頻度 |
鎮静剤とは何か
内視鏡検査をより快適に受けるために用いられる「鎮静剤」は、患者さんの意識レベルを穏やかに下げる薬剤で、検査中の苦痛や不安を和らげスムーズな検査進行を助けます。
鎮静剤の役割と種類
鎮静剤は、患者さんの意識を鎮め、リラックスした状態を作り出すことを主な役割とし、検査の種類や患者さんの状態に合わせて、様々な種類の鎮静剤が用いられます。
主なものは、ベンゾジアゼピン系の薬剤(例えば、ミダゾラムなど)や、プロポフォールなどです。
薬剤は脳の中枢神経系に作用し不安や緊張を軽減し、一時的な健忘効果をもたらすこともあり、検査中の不快な記憶が残りにくくなることも期待できます。
鎮静剤の効果
鎮静剤の効果は、患者さんの状態や使用する薬剤の種類と投与量によって異なりますが、一般的に鎮静剤が効くと、眠気を感じたりぼんやりとした状態になります。
意識は完全に失われるわけではなく、呼びかけに反応できる程度の意識レベルが保たれることが多いです。この状態では、検査中の吐き気や痛みに対する感受性が低下し、検査による刺激をほとんど感じずに済みます。
鎮静剤がもたらす安心感
内視鏡検査に対する不安が強い患者さんにとって、鎮静剤は大きな安心感を与え、検査中の苦痛を心配する必要が減るため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
また、検査中に不意に動いてしまうリスクも低減されるため、検査の安全性を高めることにもつながります。
一般的な鎮静剤の種類と特性
| 種類 | 効果 | 持続時間 | 主な使用目的 |
|---|---|---|---|
| ベンゾジアゼピン系 | 不安軽減、軽度の鎮静 | 短〜中程度 | 意識を保ちつつリラックス |
| プロポフォール | 強い鎮静、速効性 | 短時間 | 完全に近い鎮静状態 |
鎮静剤を使用するメリット
内視鏡検査において鎮静剤を使用することは、患者さんにとって多くのメリットがあり、苦痛の軽減はもちろんのこと、検査の質や安全性にも良い影響を与えます。
検査中の苦痛の軽減
鎮静剤を使用する最大のメリットは、内視鏡検査中に感じる苦痛を大幅に軽減できることです。胃内視鏡検査における強い嘔吐反射や、大腸内視鏡検査におけるお腹の張り、痛みといった不快な感覚が、鎮静剤によって和らげられます。
患者さんはほとんど眠っているような状態で検査を受けられるため、検査中の不快な記憶が残りにくいです。
検査の安全性の向上
鎮静剤によって患者さんがリラックスし体の緊張が和らぐことで、検査の安全性が向上します。医師は患者さんの動きを気にすることなく、丁寧に腸管内部を観察できるため、見落としのリスクを減らし診断の精度を高めることが可能です。
また、患者さんの精神的な負担が軽減されることで、血圧や心拍数の急激な変動も抑制され、全体的な安全性につながります。
患者さんの負担の軽減
内視鏡検査は、肉体的だけでなく精神的な負担も大きいものです。鎮静剤を使用することで負担を総合的に軽減し、検査前に抱える不安が和らぎ、検査中も不快感を感じにくいため、検査後の疲労感も少なくなる傾向にあります。
鎮静剤使用における注意点
鎮静剤は内視鏡検査の苦痛を軽減する上で非常に有用ですが、使用にはいくつかの重要な注意点があります。
鎮静剤の副作用とリスク
鎮静剤は安全に配慮して使用されますが、薬剤である以上副作用やリスクが全くないわけではありません。主な副作用は、眠気、ふらつき、めまい、吐き気などです。
稀に、アレルギー反応や呼吸抑制、血圧低下といった重篤な副作用が発生する可能性もあります。リスクを最小限に抑えるため、検査中は血圧、心拍数、酸素飽和度などのモニタリングを厳重に行い、患者さんの状態を常に確認します。
また、持病や服用している薬剤がある場合は、必ず事前に医師に正確に伝えることが必要です。
鎮静剤の主な副作用
| 副作用の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 眠気、ふらつき | 薬剤の効果が持続している間 |
| めまい | 起立時や体位変換時に多い |
| 吐き気 | 薬剤による一時的なもの |
| 血圧低下 | 薬剤の作用によるもの |
| 呼吸抑制 | 呼吸が浅くなる、呼吸回数が減る |
事前確認の重要性
鎮静剤の使用を希望する場合、検査前の医師との相談が非常に重要です。医師は患者さんの全身状態、既往歴、アレルギーの有無、現在服用している薬剤などを詳細に確認し、鎮静剤使用の可否を判断します。
特に心臓病、呼吸器疾患、腎臓や肝臓の病気がある場合、あるいは妊娠中は、鎮静剤の種類や量を慎重に検討する必要があります。
アルコールの常用者や精神安定剤を服用している方も、薬剤の効果に影響を与える可能性があるため、正確な情報提供が大切です。
検査前の準備と心構え
鎮静剤を使用する内視鏡検査を受ける前にはいくつかの準備と心構えが必要で、最も大事なのは、検査当日は車の運転や自転車の運転を避けることです。
鎮静剤の効果が完全に切れるまでには時間がかかり、判断力や集中力が低下している可能性があるため、公共交通機関を利用するか家族や知人に送迎を依頼してください。
また、検査後はすぐに激しい運動や飲酒を控えるなど、安静に過ごす計画を立てておくことが大切です。


鎮静剤使用後の帰宅基準
内視鏡検査で鎮静剤を使用した後は患者さんの安全を確保するため、明確な帰宅基準が設けられています。鎮静剤の効果は個人差があり、完全に覚醒するまでの時間も異なるため、医療機関では患者さんの状態を慎重に観察します。
鎮静からの回復状況
鎮静剤を使用した検査後、患者さんは安静な回復室で休憩します。医療スタッフは、患者さんの意識レベル、血圧、心拍数、酸素飽和度などを定期的に確認し、鎮静からの回復状況を評価します。
呼びかけに対する反応、簡単な指示への応答、自力で歩行できるか、吐き気やふらつきがないかなどを確認し、基準を満たし患者さんが十分に覚醒したと判断されて初めて、帰宅が許可されます。
帰宅許可の判断基準
| 確認項目 | 状態 |
|---|---|
| 意識レベル | 呼びかけに明確に反応する |
| 自力歩行 | ふらつきなく歩行できる |
| 吐き気・嘔吐 | なし、または軽度で安定 |
| めまい・ふらつき | なし、または軽度で安定 |
| 血圧・心拍数 | 安定している |
運転制限と公共交通機関の利用
鎮静剤の影響は意識がはっきりしていると感じても、判断力や反射能力に影響が残ることがあるため、鎮静剤を使用した検査当日は、自動車、バイク、自転車などの運転は絶対に避けてください。
帰宅の際は公共交通機関(タクシー、バス、電車など)を利用するか、家族や知人に送迎を依頼しましょう。
家族や付き添いの必要性
鎮静剤の効果が完全に消失するまでには、個人差がありますが数時間かかるので、帰宅後も万全を期すために、家族や付き添いの方がいらっしゃる方が安全です。
特に、高齢の方や遠方から来る方や一人暮らしの方などは、どなたかに付き添っていただくことを強く推奨します。付き添いが難しい場合は医療機関の指示に従い、公共交通機関の利用やタクシーの手配などを検討することが大切です。
検査後は無理をせず、自宅で安静に過ごすように心がけてください。
鎮静剤以外の苦痛軽減策
内視鏡検査における苦痛を軽減する方法は、鎮静剤の使用だけではありません。患者さんの状態や希望に応じて、他の様々な方法が採用されています。
経鼻内視鏡の選択
胃内視鏡検査において、喉からのスコープ挿入による嘔吐反射が強い方には、「経鼻内視鏡」が選択肢の一つです。
経鼻内視鏡は通常の経口内視鏡よりも細いスコープを使用し、鼻から挿入するため、舌の根元に触れにくく、嘔吐反射が起こりにくいという特徴があります。
検査中に会話することも可能なため医師とのコミュニケーションも円滑に行えます。ただし、鼻腔の狭い方や鼻炎のある方には適さない場合があります。
医師との事前相談の重要性
内視鏡検査を受ける前に医師と十分に相談することが、苦痛軽減の第一歩です。検査への不安や過去の経験、希望する苦痛軽減の方法について、医師に伝えてください。
医師は患者さんの状態を把握し、検査方法や鎮静剤の使用の有無、種類、量について提案します。疑問点や不安な点は、この事前相談の際にすべて解消しておくことが大切です。
検査中のリラックス方法
鎮静剤を使用しない場合や、鎮静剤の効果が完全に切れるまでの間でも、患者さん自身で苦痛を軽減する方法があります。検査中は、深呼吸を意識して行い、体をリラックスさせるよう努めてください。
胃内視鏡検査では、スコープが喉を通過する際に「力を抜いて、大きく息を吸い込む」ことを意識すると、喉の筋肉が緩み、スムーズな挿入につながることがあります。
また、医師や看護師が声かけをしてくれることもありますので、それに合わせて呼吸を調整することも大切です。
検査中のリラックスに役立つこと
| リラックス方法 | 特徴 |
|---|---|
| 深呼吸 | 意識的にゆっくりと行う |
| 全身の脱力 | 肩の力を抜く、顎を引く |
| 医師の声かけへの集中 | 検査指示に従い、安心感を得る |
医療機関選びのポイント
内視鏡検査を受ける医療機関を選ぶ際には、鎮静剤の使用や苦痛軽減に対する取り組みだけでなく、医療機関の全体的な体制や医師の経験も考慮することが重要です。安心して検査を受けられる医療機関を選ぶためのポイントを説明します。
鎮静剤使用の経験と実績
鎮静剤を使用した内視鏡検査を受ける場合、医療機関が鎮静剤使用に関して十分な経験と実績を持っているかを確認することが大切です。
鎮静剤の選択、投与量の調整、検査中の患者さんの状態管理には、専門的な知識と経験が求められます。多くの症例を経験している医療機関であれば、万が一の事態にも迅速に対応できる体制が整っている可能性が高いです。
設備と体制の確認
内視鏡検査を行う上で、充実した設備と安全管理体制は非常に重要です。
鎮静剤を使用する検査では、呼吸や心拍などをモニタリングする機器、緊急時に対応できる医療機器(酸素吸入装置、吸引器、蘇生セットなど)が十分に備わっているかを確認することが大切になります。
また、検査前後の休憩スペースが確保されているか、回復室での患者さんの状態を適切に管理できる看護師などの医療スタッフが配置されているかも確認すべき点です。
設備と人員体制が整っている医療機関は、安全な検査を提供する上で信頼できます。
医師の説明とインフォームドコンセント
検査を受ける前に医師が内視鏡検査の内容、鎮静剤使用のメリットとデメリット、起こりうるリスク、検査後の注意事項などについて、丁寧かつ分かりやすく説明してくれるかどうかは非常に重要な選択基準です。
患者さんが納得し、同意した上で検査を受ける「インフォームドコンセント」は、安全かつ円滑な医療行為の基本です。
疑問点や不安な点に対して医師が対応し、十分な説明時間を確保してくれる医療機関は、患者さんの立場に寄り添う姿勢があります。
医療機関選びの主な確認項目
| 確認項目 | 詳細 |
|---|---|
| 経験と実績 | 鎮静剤使用を含む内視鏡検査の症例数 |
| 設備 | モニタリング機器、緊急対応機器の有無 |
| 人員体制 | 経験豊富な医師、看護師の配置 |
| 説明の丁寧さ | 検査前後の十分な説明と質疑応答 |
よくある質問
内視鏡検査と鎮静剤に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- 鎮静剤は誰でも使用できますか?
-
鎮静剤は、ほとんどの患者さんにご使用いただけますが、すべての方に適応できるわけではありません。
心臓病、呼吸器疾患、重度の肝機能障害や腎機能障害がある方、妊娠中の方、あるいは特定のアレルギーをお持ちの方には、使用ができない場合や、薬剤の種類や投与量を慎重に検討する必要があります。
また、ご高齢の方や全身状態が不安定な方も、鎮静剤の使用について医師が判断します。
検査前に、必ずご自身の健康状態や服用している薬剤を医師に正確に伝えてください。
- 鎮静剤を使っても痛いことはありますか?
-
鎮静剤を使用することで、検査中の苦痛は大幅に軽減されますが、完全に痛みを感じなくなるわけではありません。鎮静剤は、意識を穏やかに鎮め、不安や不快感を和らげることを目的としています。
意識が完全に消失するわけではないため、検査中に軽い違和感や、お腹の張りを感じることが全くないとは言い切れません。しかし、鎮静剤の効果によって、感覚は記憶に残りにくくなることが期待できます。
もし検査中に何か強い痛みや不快感を感じた場合は、我慢せずに医療スタッフに伝えてください。
- 鎮静剤の効果はどのくらい持続しますか?
-
検査終了後30分から1時間程度で意識がはっきりしてきますが、薬剤の残存効果は数時間続くことがあります。
判断力や集中力には、意識がはっきりした後も影響が残ることがあるため、検査当日は運転を避け、激しい運動や飲酒も控えることが大切です。
医療機関では患者さんの状態を観察し、十分に回復したと判断されてから帰宅許可が出され、帰宅後も、半日程度は大事な決断や危険を伴う作業を避けて、安静に過ごしてください。
- 検査後、すぐに食事はできますか?
-
内視鏡検査後の食事については、検査の種類や鎮静剤の使用の有無によって指示が異なり、通常、胃内視鏡検査の場合は、咽頭麻酔が完全に切れるまで(検査後1時間程度)は飲食を控える必要があります。
これは、麻酔が効いている状態で飲食すると、誤嚥(ごえん)のリスクがあるためです。
鎮静剤を使用した場合は、意識が完全に回復し、吐き気がないことを確認してから飲食を開始します。
大腸内視鏡検査の場合は、特に飲食の制限がないことが多いですが、検査後の腸の安静を考慮して、刺激の少ないものから少量ずつ摂取するよう指導されます。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査での痛みを和らげる方法|鎮静剤と麻酔について】
鎮静の基本を押さえたら、次は実際の大腸内視鏡で痛みを抑える具体策を把握しておくと安心です。初めて受ける方に特に参考になります。
【内視鏡検査で使用するカメラの仕組みと特徴を解説|患者さんの不安解消】
鎮静だけでなく、器械側を知ると不快感の理由や対処がさらに理解できます。別の視点から検査を捉える手がかりになります。
参考文献
Matsubayashi M, Nakamura K, Sugawara M, Kamishima S. Nursing Difficulties and Issues in Endoscopic Sedation: Qualitative Research in Japan. Gastroenterology Nursing. 2022 May 1;45(3):174-83.
Gotoda T, Akamatsu T, Abe S, Shimatani M, Nakai Y, Hatta W, Hosoe N, Miura Y, Miyahara R, Yamaguchi D, Yoshida N. Guidelines for sedation in gastroenterological endoscopy. Digestive Endoscopy. 2021 Jan;33(1):21-53.
Kanno Y, Ohira T, Harada Y, Koshita S, Ogawa T, Kusunose H, Koike Y, Yamagata T, Sakai T, Masu K, Yonamine K. Safety and recipient satisfaction of propofol sedation in outpatient endoscopy: a 24-hour prospective investigation using a questionnaire survey. Clinical Endoscopy. 2021 May 1;54(3):340-7.
Obara K, Haruma K, Irisawa A, Kaise M, Gotoda T, Sugiyama M, Tanabe S, Horiuchi A, Fujita N, Ozaki M, Yoshida M. Guidelines for sedation in gastroenterological endoscopy. Digestive Endoscopy. 2015 May;27(4):435-49.
Tohda G, Higashi S, Wakahara S, Morikawa M, Sakumoto H, Kane T. Propofol sedation during endoscopic procedures: safe and effective administration by registered nurses supervised by endoscopists. Endoscopy. 2006 Apr;38(04):360-7.
Ikehara H, Ichijima R, Takeuchi Y, Kanazawa J, Wada T, Okuwaki K, Ueda T, Kogure H, Kusano C, Ono H. Efficacy and safety of remimazolam for sedation during endoscopic procedures in Japanese: A prospective phase III clinical trial. Digestive Endoscopy. 2025 Apr 3.
Saito Y, Uraoka T, Matsuda T, Emura F, Ikehara H, Mashimo Y, Kikuchi T, Kozu T, Saito D. A pilot study to assess the safety and efficacy of carbon dioxide insufflation during colorectal endoscopic submucosal dissection with the patient under conscious sedation. Gastrointestinal Endoscopy. 2007 Mar 1;65(3):537-42.
Imagawa A, Kato M, Koyama J, Fujishiro M. Investigation of the actual implementation of “post‐sedation discharge criteria” and “time‐out” immediately before procedure in endoscopy: A nationwide survey study in Japan. DEN open. 2026 Apr;6(1):e70149.
Kashiwagi K, Hosoe N, Takahashi K, Nishino H, Miyachi H, Kudo SE, Martin JF, Ogata H. Prospective, randomized, placebo‐controlled trial evaluating the efficacy and safety of propofol sedation by anesthesiologists and gastroenterologist‐led teams using computer‐assisted personalized sedation during upper and lower gastrointestinal endoscopy. Digestive Endoscopy. 2016 Sep;28(6):657-64.
Triantafillidis JK, Merikas E, Nikolakis D, Papalois AE. Sedation in gastrointestinal endoscopy: current issues. World journal of gastroenterology: WJG. 2013 Jan 28;19(4):463.