仕事や日常生活で悩みが重なると、ストレスが原因となって腸の調子が乱れ、下痢が続くなどの症状に苦しむ方が増えています。
そういうときは大腸の状態を正しく把握し、必要に応じた検査を受けて炎症の有無を確認することは重要です。
本記事では、ストレスによる下痢のメカニズムや大腸内視鏡検査の意味をできるだけわかりやすく解説し、さらに、胃カメラとの併用による消化管全体のチェック方法や、日常生活で実践しやすいストレス対策などにも触れていきます。
ストレスと下痢症状の基礎知識
日常の悩みや不安、環境の変化が引き金となり、ストレスが原因となる下痢を起こすことがあります。腸は自律神経の影響を受けやすく、感情面と密接につながっています。
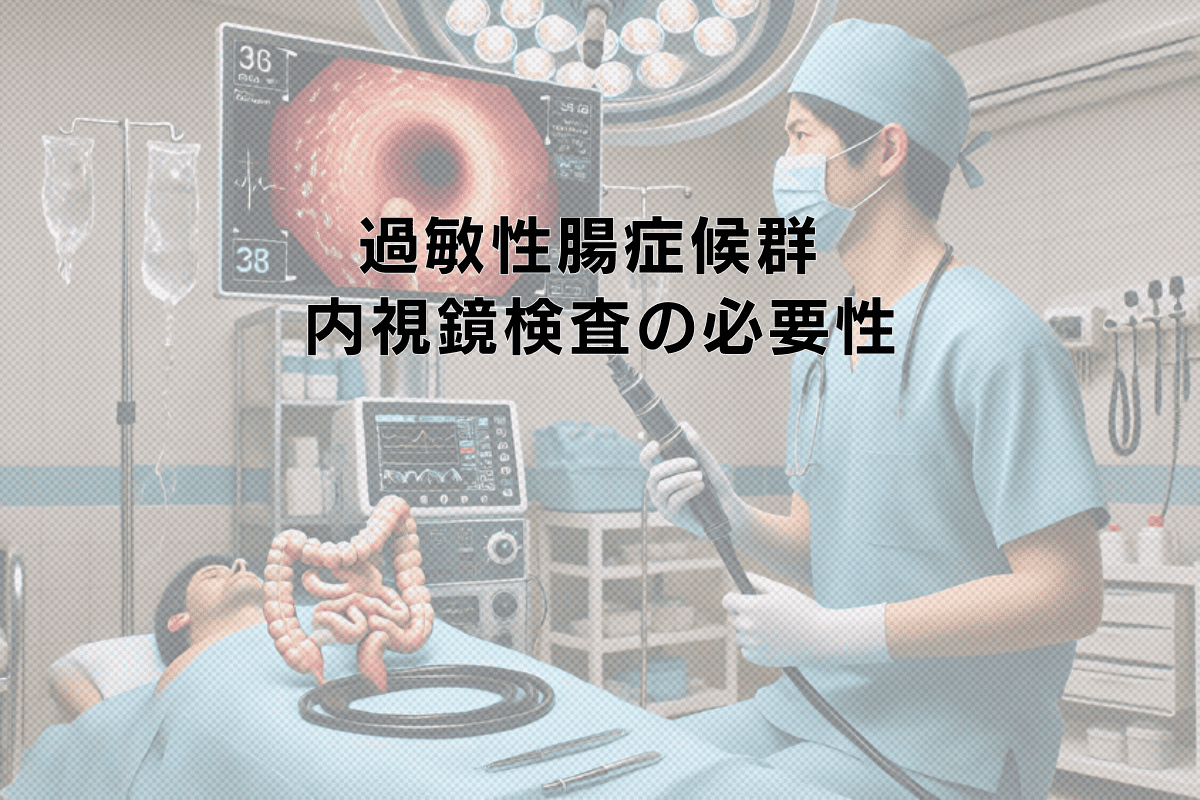
なぜストレスが腸に影響を及ぼすのか
ストレスを感じると、自律神経のうち交感神経と副交感神経のバランスが崩れやすくなります。
交感神経が優位な状態が続くと腸の動きが活発になり、内容物が速く腸内を通過しやすくなり、その結果、水分吸収が不十分となり、軟便や頻回の排便といった下痢症状につながるのです。
さらに、ストレスは腸内細菌のバランスにも影響し、悪玉菌が増えることで腸粘膜に刺激を与え、炎症や不調が起こりやすくなると考えられています。
下痢症状が続く背景
一時的なストレスが解消されれば下痢も軽快することがありますが、ストレスが続くと下痢が慢性的になりやすいです。加えて、暴飲暴食や栄養バランスの偏り、睡眠不足などが重なると、腸の粘膜が弱りやすくなります。
腸粘膜が傷ついている状態だと少しの刺激でも便が緩くなるため、症状が改善しにくく、こうした状況が続くと、本来であれば守るべき腸の免疫バリアが低下し、感染症や炎症も起こりやすいです。
腸内細菌バランスへの影響
腸内には多種多様な細菌があり、身体に有用な働きをする菌が多いほど健康な状態ですが、ストレスが大きい状態が続くと、腸内細菌の多様性が低下し、特定の細菌が過剰に繁殖しやすくなります。
これにより腸内環境が乱れ、便通異常や腹痛が起こるリスクが高まるので、善玉菌を増やす食事や適度な運動習慣を心がけることで、ストレスの影響を緩和しやすくなります。
ストレスと腸の関連性の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自律神経の乱れ | 交感神経が優位になり、腸の動きが過剰になる |
| 腸内細菌の変化 | 善玉菌の減少と悪玉菌の増加で腸内環境が乱れやすい |
| 免疫バリアの低下 | 粘膜の保護力が下がり、炎症や感染症のリスク増大 |
| 栄養不足 | バランスの悪い食事や過度な飲酒で腸粘膜が弱る |
急性と慢性の下痢におけるストレスの関与
ストレスが原因の下痢は、症状の経過期間によって大きく2種類に分けられ、急性の下痢は短期間で症状が落ち着くことも多いですが、慢性化すると別の合併症を起こすリスクがあります。
急性と慢性の下痢がどのようにストレスと関係しているかを掘り下げていきます。
急性の下痢症状の特徴
急性の下痢は、1~2週間以内の比較的短い期間で起こるものを指し、暴飲暴食や食当たり、ウイルス感染なども原因となります。また、過度な緊張や不安感が強いときに一時的に腸が過敏になり、急に軟便や頻回の排便が続くことがあります。
仕事のプレゼンや試験の直前など緊張が高まる場面で、お腹が痛くなってトイレに駆け込むといった経験をする方も珍しくありません。
慢性的な下痢症状の特徴
慢性的な下痢は、3~4週間以上にわたって下痢が続く状態で、ストレスが長期間続いていると、腸の粘膜が疲弊しやすくなり、少しの刺激でも下痢を起こす悪循環に陥りがちです。
精神的な負担が大きい環境下では、腸の動きだけでなく、食欲不振や睡眠障害が重なることもあり、その結果、下痢が続く状態が慢性化しやすくなり、生活の質が大きく低下してします。
下痢の原因としてのストレスとの関連
下痢を引き起こす要因は多岐にわたりますが、ストレスは大きなウェイトを占め、精神的な負担が高まると、交感神経が優位になりやすく、腸の蠕動運動が激しくなることで便が柔らかくなるのです。
また、ストレスによって血流が腸に十分に回らなくなることも、粘膜のダメージに影響すると考えられます。
ストレスが強いときに起こりやすい症状
- 頻回の排便や急な便意
- 腹痛をともなう軟便
- 食欲不振や過剰な食欲の変動
- 過度の緊張による胃部不快感
自分では気づかないうちにストレスが蓄積し、腸の働きに影響を与えるケースも少なくありません。原因不明の下痢が長引くときには、精神的な負担を振り返ってみることも大切です。
急性・慢性の下痢を見分ける目安
| 分類 | 期間 | 主な原因 | 代表的な症状 |
|---|---|---|---|
| 急性の下痢 | 1~2週間程度 | 食当たり、ウイルス感染、突発的な強い緊張など | 水様便、軽度の腹痛、急激な便意 |
| 慢性的な下痢 | 3週間以上持続 | 長期的なストレス、過敏性腸症候群など | 下痢と便秘の反復、腹部膨満、不安定な便通 |
検査を受けるべきタイミング
下痢が長引くと、腸内環境がさらに悪化し、他の病気を併発するリスクも生じ、一時的な下痢であれば自然に落ち着くこともありますが、慢性化する場合には専門的な診断が必要です。
ここでは、医療機関を受診する目安となるタイミングや、放置することのリスクなどを取り上げます。
下痢が続く状態が示すサイン
下痢が2週間以上続いている場合、単なる食生活の乱れや一過性の感染症が原因とは考えにくい場合があり、次のようなサインがある場合は、できるだけ早めに医療機関への相談を検討してください。
- 血便や黒色便が出る
- 腹部の痛みが激しく、生活に支障が出る
- 発熱や強い脱水症状を伴う
- 食欲不振や体重減少が著しい
体調不良が長期化するほど身体の抵抗力も落ち、さまざまな合併症を起こす可能性が高まるので、早期に診断し、必要に応じた治療を受けることが重要です。
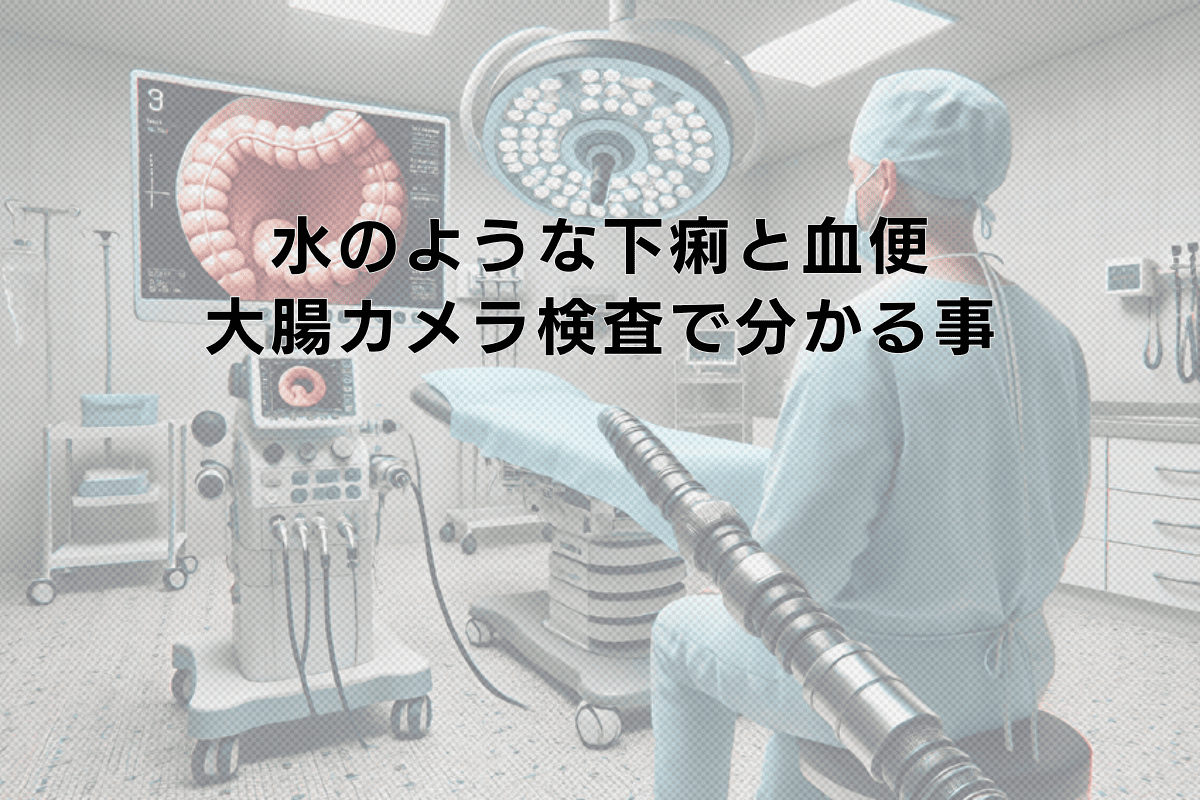
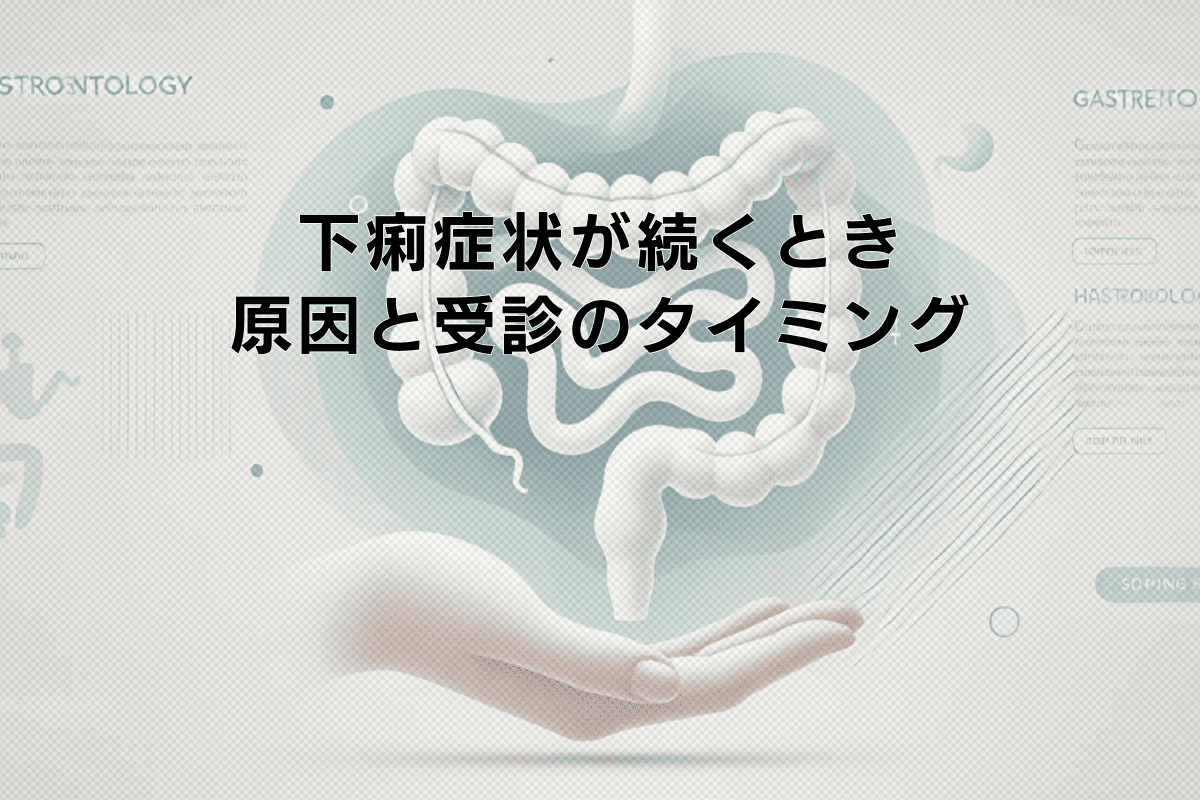
放置によるリスク
ストレスに伴う下痢の原因を把握せずに放置すると、腸粘膜がダメージを受け続け、炎症が進行することがあります。慢性的な炎症は、大腸ポリープや潰瘍性大腸炎など、より深刻な疾患が見つかるきっかけとなる可能性も否定できません。
下痢が長引くときには、大腸カメラなどの検査で粘膜を直接確認し、炎症や病変の有無を確認したほうが安心です。
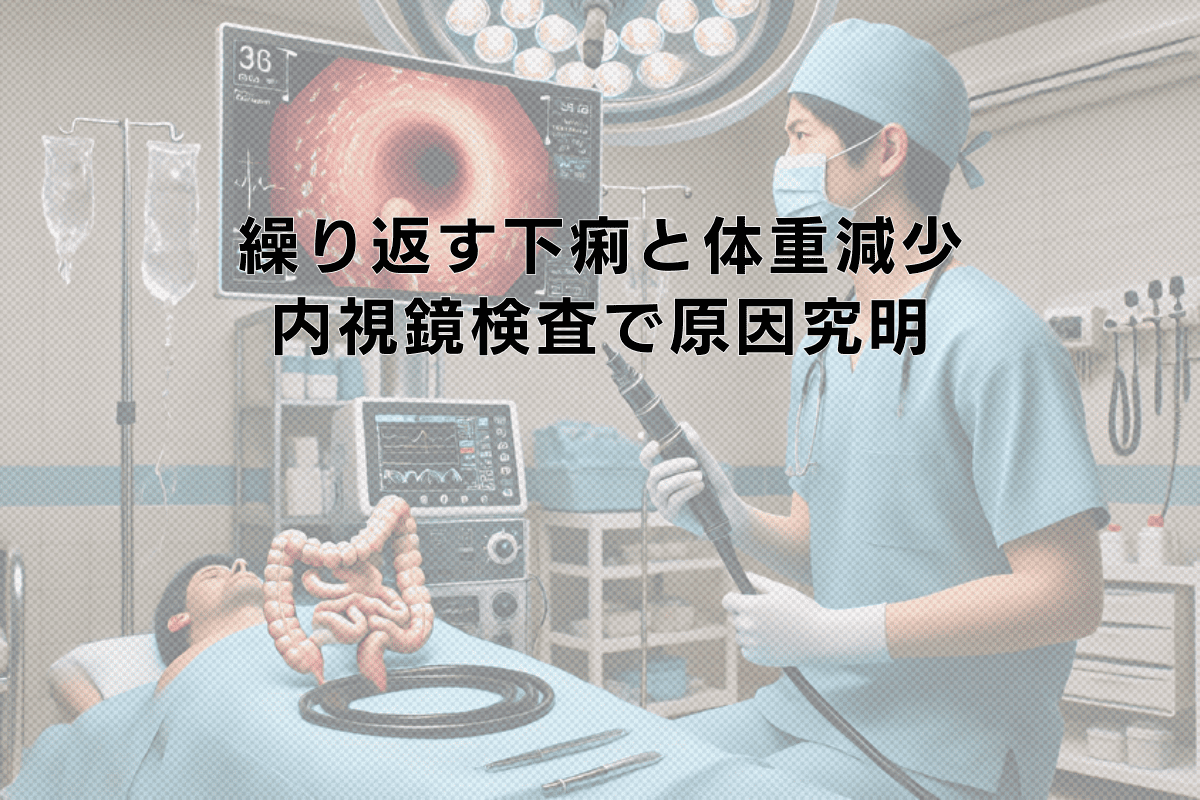
医療機関での相談の大切さ
下痢が続く症状を医療機関で相談すると、医師は問診や簡単な血液検査、便検査などで原因の絞り込みを進めます。
さらに、大腸内視鏡検査を行うことで腸の粘膜を直接観察し、必要に応じて生検(組織を一部採取して検査)を実施し、炎症の程度やポリープの有無を明確に確認することが重要です。

受診時にチェックしたいポイント
- 下痢の期間と頻度
- 便の性状(色や形状、血液の混入)
- 体調の変化やその他の症状(発熱、嘔吐、倦怠感など)
- 日常生活のストレス要因や睡眠状況
下痢放置によるデメリット
| 項目 | デメリット |
|---|---|
| 腸粘膜の損傷 | 慢性的な炎症が進むと粘膜が傷つき、回復に時間がかかる |
| 免疫力の低下 | 栄養吸収不良やストレスで全身の免疫力が落ち、他の感染症リスク増加 |
| 生活の質の低下 | 頻繁にトイレに行く必要があり、仕事や日常活動に支障をきたしやすい |
| 病気の見落とし | 大腸ポリープや潰瘍などの重大な病変を見逃す可能性 |
- 体重減少が顕著
- 明らかな出血を伴う便が認められる
- 発熱や嘔吐など他の症状が強く出る
受診を遅らせると、病気が悪化して治療期間や治療内容がより負担の大きいものとなる恐れもあります。
大腸内視鏡検査で確認する炎症とは
ストレスに伴う下痢が続くと、腸粘膜に少なからず負担がかかります。大腸内視鏡検査を行うと、粘膜面のわずかな変化から重大な病変まで直接確認できるため、早期発見と早期治療につなげやすいです。
腸内の炎症が示す可能性
腸内に炎症があると、粘膜が赤くただれたり、潰瘍ができたりすることがあります。炎症がひどいときには出血を伴う場合もありますが、初期段階では自覚症状がないケースも少なくありません。
炎症の原因としては、ストレスによる免疫機能の低下、腸内細菌のバランス崩壊、過敏性腸症候群(IBS)の発症などが考えられます。
大腸内視鏡検査の意義
大腸内視鏡検査では、大腸全体をカメラで観察して、以下のような点を確認します。
- 粘膜表面のただれや潰瘍の有無
- 出血やポリープの存在
- 炎症が見られた際の範囲と重症度
- 疑わしい部位があれば組織検査を実施
ストレスが原因となる下痢だと思っていても、実際には他の病気が潜んでいることもあります。検査を行うことで、確定診断と治療方針の決定がスムーズになり、身体的・精神的負担の軽減につながります。
検査による早期発見の利点
腸内に異常があるかどうかを肉眼で直接確かめられるため、小さなポリープでも見落としにくいメリットがあります。また炎症の程度が軽い段階で発見できれば、食事療法や薬物療法での改善も期待しやすくなります。
検査中にポリープを発見した場合は、その場で切除して病理検査に出すことが可能です。ポリープが大きくなる前に対処できれば、大腸がんなどへの進行リスクを抑えられます。
大腸内視鏡検査で見つかりやすい代表的な病変
| 病変名 | 特徴 |
|---|---|
| ポリープ | 粘膜が小さく隆起したもので、放置すると大きくなる可能性 |
| 潰瘍性大腸炎 | 炎症が大腸全体に及ぶことがあり、出血や粘液便を伴いやすい |
| クローン病 | 消化管の各所に潰瘍が生じる。口から肛門まで病変が及ぶ場合も |
| 過敏性腸症候群(IBS) | 腸粘膜に目立った病変がないことも多いが、機能的異常が確認される |
- 粘膜の赤みやただれ
- 出血斑や腫瘤
- 表面の隆起や陥凹
異常の種類や位置によって対処法は異なるため、正確な検査と診断が重要です。
大腸内視鏡検査の流れ
大腸内視鏡検査に対して「痛そう」「恥ずかしい」といった不安を抱える方は少なくありませんが、検査手順をあらかじめ知っておくと、実際の受検時の負担を軽く感じられる場合があります。
検査前に行う準備
大腸内視鏡検査の前日と当日には、腸内をきれいにする目的で下剤を飲んだり、食事制限を行ったりします。
腸内に内容物が残っていると、正確に観察できないばかりか、ポリープや潰瘍を見落とす原因にもなるので、医療機関の指示に従い、なるべく腸を空っぽにした状態で検査を受けることが大切です。

実際の検査手順
検査当日は、点滴などで鎮静を行うことも多く、痛みや不快感をやわらげる工夫が施されます。
肛門から内視鏡を挿入し、大腸の奥まで到達させてゆっくりと引き抜きながら粘膜を観察し、気になる部分があれば撮影や生検を行い、病理検査に回すことができます。
所要時間は個人差がありますが、検査自体はおよそ15~30分程度で終わることが多いです。
検査後の注意点
鎮静剤を使った場合は、検査終了後も数時間程度は眠気やふらつきが続くかもしれません。医師やスタッフから許可が出るまでは安静にし、その日は車の運転や激しい運動を控えたほうが安全です。
検査でポリープを切除した場合は、出血を防ぐためにアルコール摂取や入浴を一定期間控える必要があります。
検査前日~当日に気をつけたいポイント
| 時期 | 主な内容 |
|---|---|
| 検査前日 | 食事制限(消化に良いもの中心)、下剤の服用を開始 |
| 検査当日 | 朝から下剤を飲み、腸内をほぼ空にする |
| 検査中 | 鎮静剤を使用することが多く、痛みや不快感を軽減しながら検査を進める |
| 検査終了後 | 鎮静剤が残っている場合、数時間は安静にし、当日の運転は避ける |
- 水分補給はこまめに行う
- 指示された下剤を決められた時間にきちんと飲む
- 前日は繊維質の多い食事や種のある果物を避ける
- 飲酒や過度の運動は控える
胃カメラと大腸カメラの組み合わせ検査
消化管は口から肛門まで長くつながっており、ストレスの影響は大腸だけでなく胃にも及ぶので、胃カメラを同時期に受けることで、上部消化管と下部消化管を総合的に評価できます。
忙しい方や、より包括的な検査を希望される方には、一度の来院で上下部内視鏡検査を受ける方法が選択肢です。
上下部内視鏡検査とは
上下部内視鏡検査とは、胃カメラ(上部内視鏡)と大腸カメラ(下部内視鏡)を近いタイミングで行い、食道、胃、十二指腸、大腸を一通り観察する方法です。
場合によっては、鎮静剤を使用して午前中に胃カメラ、午後に大腸カメラを実施することもあり、複数回にわけて通院する負担を減らせるため、時間を有効に使いたい方に向いています。

一度の来院で多角的に調べるメリット
胃カメラと大腸カメラを組み合わせる最大のメリットは、消化管の広範囲な領域を同時期にチェックできる点です。
下痢が続くとき、実は胃酸過多やピロリ菌感染などの上部消化管の異常が関与しているケースもあり、包括的に原因を探ることができます。
また、上下部両方に病変が見つかった場合でも、一括で医師の診察や治療方針を相談しやすい利点があります。
内視鏡の組み合わせ検査に適した例
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 胃痛や胃もたれが同時にある | 大腸だけでなく胃酸分泌異常や胃潰瘍などが下痢を悪化させる可能性を確かめるため |
| 便に血が混じることがある | 消化管のどの部位で出血しているかを包括的に調べる |
| 家族に消化器系の病気が多い | 予防的な観点で上下部全体を観察し、リスク把握と早期対策に役立てる |
検査後の経過観察とフォローアップ
上下部内視鏡検査後には、各検査結果を総合的に判断しながら治療や生活指導が行われ、たとえば、ピロリ菌感染が確認された場合は除菌治療、ポリープが発見された場合は切除など、個々の状態にあわせた対応が可能です。
また、ストレスによる胃腸障害が疑われた場合は、生活習慣や食事指導の内容を総合的に検討できます。
- 一度の検査で広い範囲を調べられる
- 治療計画を短期間で立てやすい
- 時間や通院回数を節約できる
- 医師と綿密に相談しやすい

日常生活でできるストレス対策
ストレスが腸の不調を引き起こす大きな要因の1つである以上、日常生活の中でどう対処するかは重要です。下痢が続いてしまう前に、あるいは検査後の再発防止のためにも、継続しやすい方法でストレス軽減に努めましょう。
食生活の改善
偏った食事や不規則な食事時間は、腸内細菌のバランスを崩しやすくします。
特にストレスが多いときは、甘いものやアルコールに頼ってしまうこともあるかもしれませんが、さらに下痢が悪化する場合があります。野菜や果物、発酵食品を適度に取り入れ、水分補給をこまめに行うことで、腸内環境を整えてください。
ストレス緩和に役立つ食材
| 食材 | 特徴 |
|---|---|
| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、キムチなど。善玉菌を増やす |
| 食物繊維 | 野菜、果物、全粒穀物など。腸内の老廃物排出を促す |
| 良質なたんぱく質 | 魚や大豆製品、鶏肉など。腸粘膜の修復に役立つ |
| ミネラル | 海藻やナッツ類。腸の働きと免疫機能をサポート |

睡眠と休息の見直し
ストレス対策には十分な睡眠も欠かせません。就寝前のスマートフォン使用や強い光を避け、リラックスできる環境が大切で、寝つきが悪いと感じるときは、軽いストレッチや呼吸法を取り入れるのも有効です。
休日にまとめて寝るよりも、毎日一定のリズムを保つほうが身体への負担を減らせます。
運動やリラクゼーションの活用
ウォーキングやヨガなどの軽い運動は、血流を促進して腸の機能を健やかに保つのに役立ち、さらに、深い呼吸を意識することで副交感神経を優位にし、リラックスしやすくなる効果も期待できます。
心身が疲れ切ってしまう前に、気分転換となる運動や趣味の時間を意識的に作りましょう。
ストレスを軽減しやすい生活習慣
- 朝食を抜かず規則正しい食事を心がける
- 就寝前のブルーライト(スマホやPC)の使用を控える
- 軽い有酸素運動で血行を良くし、ストレスホルモンを減らす
- ときには趣味やレジャーで意識的に気分転換を図る
運動といっても無理にハードなものを取り入れる必要はありません。心地よいペースで続けられることが重要です。
運動・休息を取り入れる工夫
| 工夫 | 具体的アイデア |
|---|---|
| 手軽に始めるウォーキング | 朝や夕方の散歩、通勤ルートの一部を徒歩に変更 |
| リラクゼーション方法 | ヨガ、ストレッチ、深呼吸、瞑想 |
| 小休憩の取り方 | 1時間ごとに5分程度の休憩、画面から視線を外す |
| レジャーの活用 | ドライブや音楽鑑賞など、気分転換の時間を確保 |
よくある質問
- 検査前に薬を飲んでも大丈夫?
-
普段から高血圧や糖尿病などで薬を服用している方は、医師に事前相談してください。腸内視鏡検査では下剤を使用しますが、特定の薬との飲み合わせによっては注意が必要な場合もあります。
自己判断で中止するよりも、かかりつけ医や検査担当の医師に確認したうえで方針を決めたほうが安全です。
- 検査時の痛みや苦痛はある?
-
鎮静剤を使用した場合、多くの方は痛みをあまり感じずに検査を受けられ、個人差はありますが、意識がぼんやりした状態で検査を終える方も多いです。
痛みに弱い方や不安が強い方は、遠慮なく医療スタッフに伝えてください。検査前の準備で腸をきれいにしておくと、検査時間の短縮や負担軽減につながりやすいです。
- 診察から検査までどのくらい時間がかかる?
-
医療機関の予約状況や検査の内容によって異なりますが、初診で受診した日に検査を行うことはあまり多くありません。通常は問診や簡単な検査を経て、大腸内視鏡検査日を別途設定するケースが多いです。ただし、クリニックによっては診察当日の内視鏡検査を行っている場合もありますので、一度ご相談ください。
検査当日は下剤の服用を含めると、半日から1日程度はかかると考えておくとよいでしょう。
- 予約時に検査内容や所要時間を確認する
- 仕事や家事とのスケジュール調整をしておく
- 下剤の効果が出るまでには個人差がある
身体的負担を軽減するためにも、余裕をもった予定を組むと安心です。
次に読むことをお勧めする記事
【下痢が続くときの受診目安|慢性下痢の原因と検査方法】
ストレスが原因の下痢についての基本を押さえたら、次は実際の慢性下痢の診断方法について知っておくと安心です。下痢が慢性化する要因には腸内環境の乱れがあり、ストレスなどで腸の蠕動運動が乱れると水分吸収が不十分になります。
【胃が張る症状と下痢の関係|原因と受診のタイミング】
関連する胃の症状についても知りたくなる方はこの記事をお読みください。胃の張りと下痢が同時に起こる場合、過敏性腸症候群の下痢型や機能性ディスペプシアとIBSが併発している可能性も考慮されます
参考文献
Mizukami T, Sugimoto S, Masaoka T, Suzuki H, Kanai T. Colonic dysmotility and morphological abnormality frequently detected in Japanese patients with irritable bowel syndrome. Intestinal research. 2017 Apr 27;15(2):236.
Otani K, Watanabe T, Takahashi K, Nadatani Y, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Tanaka F, Nagami Y, Taira K. Upper gastrointestinal endoscopic findings in functional constipation and irritable bowel syndrome diagnosed using the Rome IV criteria: a cross-sectional survey during a medical check-up in Japan. BMC gastroenterology. 2023 May 3;23(1):140.
Watanabe Y, Arase S, Nagaoka N, Kawai M, Matsumoto S. Chronic psychological stress disrupted the composition of the murine colonic microbiota and accelerated a murine model of inflammatory bowel disease. PloS one. 2016 Mar 7;11(3):e0150559.
Ihana-Sugiyama N, Nagata N, Yamamoto-Honda R, Izawa E, Kajio H, Shimbo T, Kakei M, Uemura N, Akiyama J, Noda M. Constipation, hard stools, fecal urgency, and incomplete evacuation, but not diarrhea is associated with diabetes and its related factors. World journal of gastroenterology. 2016 Mar 21;22(11):3252.
Nakata R, Tanaka F, Sugawara N, Kojima Y, Takeuchi T, Shiba M, Higuchi K, Fujiwara Y. Analysis of autonomic function during natural defecation in patients with irritable bowel syndrome using real-time recording with a wearable device. Plos one. 2022 Dec 9;17(12):e0278922.
Funatsu T, Takeuchi A, Hirata T, Keto Y, Akuzawa S, Sasamata M. Effect of ramosetron on conditioned emotional stress-induced colonic dysfunction as a model of irritable bowel syndrome in rats. European journal of pharmacology. 2007 Nov 14;573(1-3):190-5.
Fukudo S, Nomura T, Muranaka M, Taguchi F. Brain-gut response to stress and cholinergic stimulation in irritable bowel syndrome: a preliminary study. Journal of clinical gastroenterology. 1993 Sep 1;17(2):133-41.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Chan Y, So SH, Mak AD, Siah KT, Chan W, Wu JC. The temporal relationship of daily life stress, emotions, and bowel symptoms in irritable bowel syndrome—diarrhea subtype: a smartphone‐based experience sampling study. Neurogastroenterology & Motility. 2019 Mar;31(3):e13514.
Konturek PC, Brzozowski T, Konturek SJ. Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options. J Physiol Pharmacol. 2011 Dec 1;62(6):591-9.










