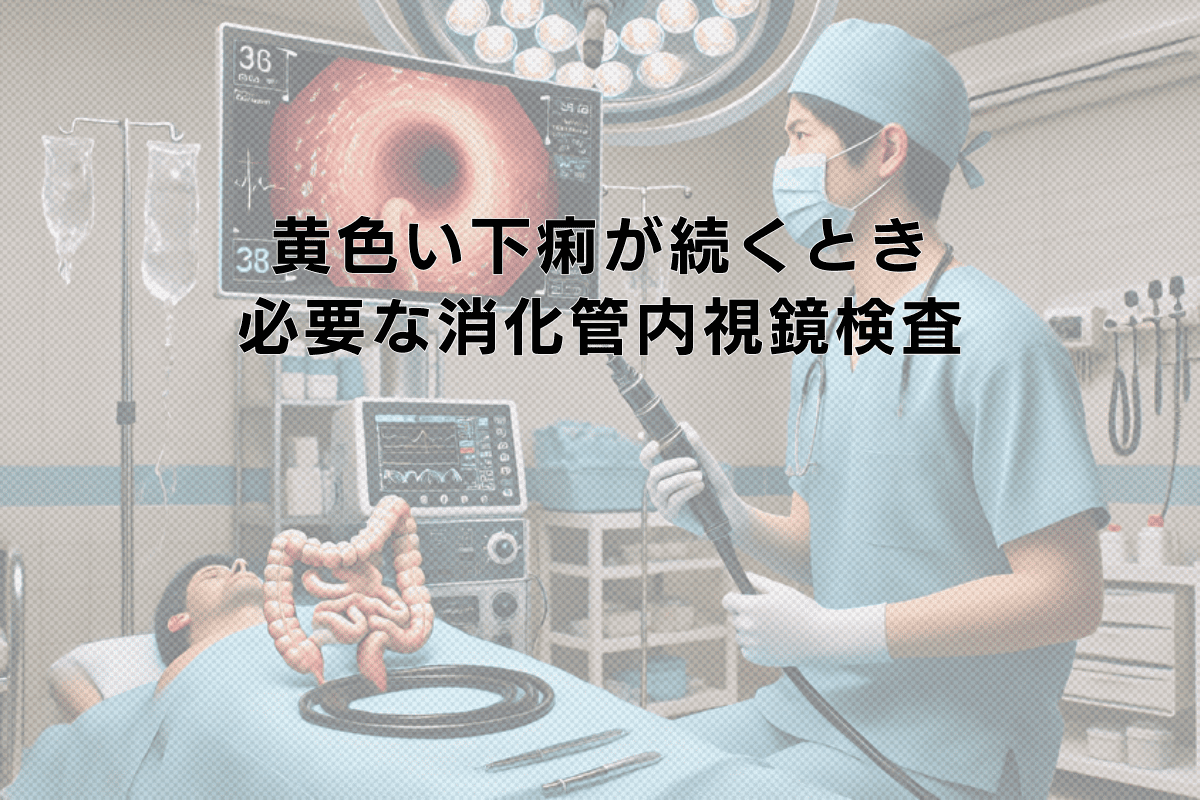黄色っぽい下痢が何日も続くと、食べ物が合わなかっただけなのか、何か特別な病気が潜んでいるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。
とくに胃腸の不調を自覚し始めると、普段とは違う便の色やにおい、腹痛や吐き気など、さまざまな症状に敏感になります。
こうした違和感が長引く場合は、単なる体調不良だけでなく、胆汁や消化吸収の乱れが影響している可能性も否定できません。
放置すると重篤化する病気が隠れているケースもあるため、早い段階から専門医による内視鏡検査を含む評価を考えることが重要です。

黄色い下痢が続く原因と特徴
黄色い下痢が長引いていると感じるときは、単に食事内容だけではなく、胆嚢や肝臓、膵臓などの消化液に関係する臓器も考慮することが大切です。
胆汁が影響する便の色の仕組み
胆汁は肝臓で作られ、胆嚢に蓄えられて十二指腸に分泌され、脂質の消化を補助する役割を持ち、この胆汁が腸内で酵素や細菌と作用して便の色を変化させます。
通常は茶色から濃褐色の便になることが多いですが、胆汁の分泌量や流れに異常が起こると、便が薄い黄色や灰白色に近づく場合があります。脂質の吸収がうまくいかないため、脂っぽい便になりやすいことも特徴的です。
黄色い下痢の特徴
黄色みを帯びた下痢は水分が多く、かつ消化が不十分な状態を示唆することがあります。
脂肪分が多い食品を摂取したときに一時的に黄色っぽくなることもありますが、それが連日続いたり、腹痛や発熱、嘔吐などの症状を伴ったりするなら、腸管の炎症や感染症を疑う必要があるかもしれません。
あるいは胆汁の流れが滞る閉塞性黄疸に関連した色調変化の可能性もありますので、注意が必要になります。
腸内細菌と便の色合い
健康的な便の色は腸内細菌のバランスにも左右されます。腸内細菌叢が正常に働くと、消化過程で生成されるビリルビンが変化して茶褐色の便になります。
一方、何らかの理由で腸内のバランスが乱れるとビリルビンの代謝過程に変化が生じ、黄色い便が出現するケースも考えられます。短期間の腸内環境の乱れなら自然に回復することもありますが、長く続くときは専門医の診断が欠かせません。
黄色い下痢に関連する主な要因
| 要因 | 具体例 | 考えられる影響 |
|---|---|---|
| 胆汁分泌や排泄の異常 | 胆管閉塞、胆石、肝機能障害など | 十分に腸内でビリルビンが作用せず、色が薄くなりやすい |
| 脂質消化不良 | 膵液の不足、消化酵素の低下、脂肪分の過剰摂取など | 便に脂肪が残り、黄色く油っぽい下痢になる |
| 腸内細菌叢の乱れ | 過度の抗生物質使用、食生活の偏りなど | 便の色や形に変化が生じ、下痢が続く |
| 消化管感染症 | 細菌やウイルスが腸粘膜に感染 | 水様便や腹痛、嘔吐などを伴い便が黄色っぽくなることがある |
自己判断のリスク
一時的に黄味を帯びた便が出たからといってすぐに重い病気だと断定する必要はありませんが、数日から数週間継続しているようなら、軽視するのはリスクが高いです。
自己流の食事療法や民間療法で解決を図ろうとしても、実際に胆管系や膵臓に異常がある場合は根本的な解決にはつながりません。医療機関を受診し、消化管内視鏡検査など客観的な評価を受けることが回復への近道です。
消化管のしくみと黄色い便の関係
黄色い下痢が続く背景には、消化管のどこかに異常が潜んでいることが少なくありません。人の消化管は食道、胃、小腸、大腸などが連続して機能するシステムであり、それぞれの部位がうまく連携できないと消化不良や吸収障害を起こします。
胃での消化過程
胃は食物を消化液と混ぜ合わせて粥状にする器官で、胃酸やペプシンと呼ばれる酵素によって主にタンパク質が分解されますが、脂質を分解するためには膵液や胆汁が必要になります。
そのため、胃内の消化が十分でも脂質の多い食べ物は次の段階で胆汁の働きが不可欠です。もし胃の機能が低下していたり、胃炎などで粘膜がダメージを受けていたりすると、消化不良が起こりやすくなり、下痢の一因になります。
小腸での消化と吸収
十二指腸に到達した食物は胆汁や膵液と混ざり、脂質や炭水化物、タンパク質などがさらに分解されたあと、小腸全体にわたって栄養素が吸収されます。小腸の粘膜に炎症や潰瘍があると、吸収不良による下痢や便色の変化を招きやすくなります。
セリアック病やクローン病など、小腸に特有の慢性的な炎症性疾患でも黄色っぽい便が続くことがあります。
大腸での水分調節
大腸は主に水分の再吸収と便の形成を担当し、正常なバランスが崩れると、水分が多いまま便が排出され、下痢になります。
大腸の粘膜に炎症性ポリープや腫瘍があると、粘液や血液が混じって便の色が普段と異なることもあるため、黄色い便のほかに赤や黒っぽい変化を見た場合は警戒が必要です。
消化管の各部位と役割
| 部位 | 主な役割 | 黄色い下痢との関連性 |
|---|---|---|
| 胃 | 食物を消化液と混ぜ粥状に分解、殺菌作用も担う | 胃の機能低下や胃酸過多が消化不良を起こし、下痢を誘発することがある |
| 小腸(十二指腸含む) | 膵液・胆汁と混ぜ合わせて栄養素を吸収 | 胆汁や酵素の不足で脂質が分解されにくく、黄色い便が続く可能性がある |
| 大腸 | 水分の再吸収と便の形成 | 炎症や腫瘍で便の通過が早くなると下痢が続き、色の変化や粘液便を伴うこともある |
胆嚢や膵臓とのかかわり
黄色い下痢が続く背景には、胆嚢や膵臓に関連した障害も見逃せません。胆石や胆管が詰まると胆汁が適切に腸へ流れないため、便の色が薄くなったり油脂を含む食後に下痢が起こりやすくなります。
膵臓の機能が落ちる慢性膵炎や膵がんなどでも脂質の消化が不完全になり、便が油っぽくなるケースがあります。これらの状態では内視鏡検査だけでなく、血液検査や画像診断も必要になることが多いです。
黄色い下痢が続くときに疑われる病気
黄色い下痢が長期にわたって続く際は、腸管だけでなく胆嚢や肝臓、膵臓の病気も含めた幅広い原因を視野に入れる必要があります。
機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群
機能性ディスペプシア(FD)や過敏性腸症候群(IBS)は、検査で明確な器質的異常が見つからないにもかかわらず、胃腸の働きに不調が生じる疾患です。
FDでは胃もたれや胃痛が中心で、IBSでは下痢や便秘が交互に現れたり、下痢型の場合は水っぽい便や黄色っぽい便が頻繁に出るなどの症状が続くことがあります。ストレスや食習慣が悪化要因になるケースも多く、生活環境の改善が重要です。

胆汁酸吸収不良症候群
小腸や大腸で胆汁酸が適切に再吸収されないと、胆汁酸が過剰に大腸へ流れ込み、下痢を起こすことがあります。大腸の粘膜が胆汁酸で刺激され、黄色い便が長引くことも特徴的です。
クローン病や小腸切除後などで腸の吸収面積が減っている患者さんに多いですが、腸内細菌の変化や腸管運動の乱れが原因となることもあります。
膵臓の障害(慢性膵炎など)
膵臓はリパーゼやアミラーゼなど脂質やデンプンを分解する酵素を分泌します。慢性膵炎などで膵機能が低下すると、脂質が十分に分解されないまま排泄されるため、脂肪便と呼ばれる油っぽい便が出やすくなります。
これが長期にわたる場合、便は黄色みを帯びた下痢となり、体重減少や栄養障害を伴うこともあります。
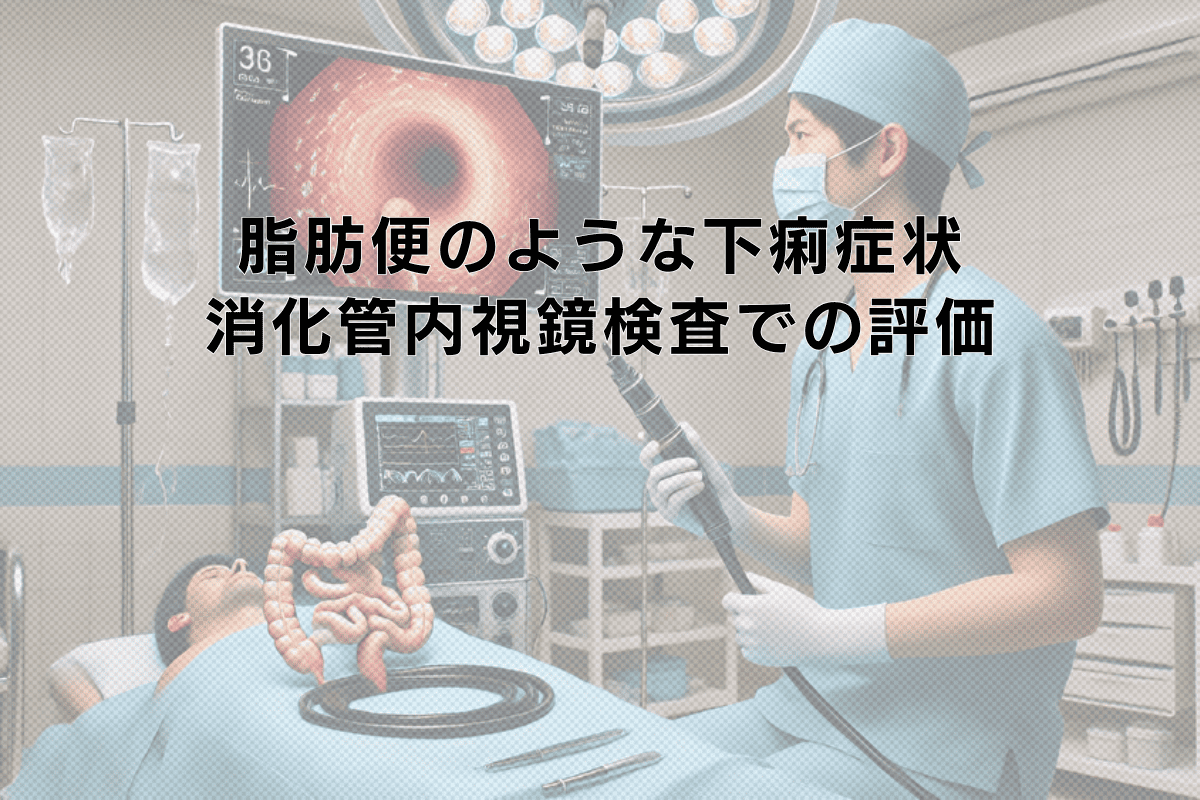
黄色い下痢を伴う可能性がある主な病気
| 疾患名 | 特徴 | 症状の例 |
|---|---|---|
| 機能性ディスペプシア | 上部消化管に異常なしでも胃痛や胃もたれが持続 | 下痢や便秘を伴うことがある |
| 過敏性腸症候群 | 器質的異常が見られず、ストレスで便通が乱れる | 水溶性の黄色い便や腹痛、ガス溜まりなど |
| 胆汁酸吸収不良症候群 | 胆汁酸の再吸収がうまくいかない | 脂っぽい黄色い下痢や腹部の不快感 |
| 慢性膵炎 | 膵液の分泌が低下し脂質分解が不十分 | 脂肪便、体重減少、腹部の鈍痛 |
| 胆管閉塞・胆石症 | 胆汁の流れが妨げられ便の色が薄くなる | 黄疸、右上腹部痛、脂質の消化不良 |
潰瘍性大腸炎やクローン病
炎症性腸疾患の代表である潰瘍性大腸炎やクローン病も、下痢が長期間続くことが特徴です。
粘膜がただれたり潰瘍を形成するため、血便や粘液便が多いケースが一般的ですが、発症部位や炎症度合いによっては黄色っぽい下痢が出ることもあります。
食事制限や免疫調節薬で症状をコントロールする場合が多く、必要に応じて内視鏡検査で炎症範囲を確認します。
消化管内視鏡検査が必要な理由
黄色い下痢の原因は多岐にわたるため、問診だけで特定するのは難しいことが多いです。そこでカギとなるのが、直接消化管を観察できる内視鏡検査です。
症状だけでは判断が難しい
下痢が続く場合、腹痛や発熱、血便などの伴随症状の有無だけで判断しようとしても、似た症状を示す病気が多く、誤診のリスクが残ります。
色や性状からおおよその推測はできても、実際にどこまで炎症が広がっているかは内視鏡検査をすることで確実に把握できます。
消化管を直視できるため、小さな潰瘍やポリープ、早期がんなども発見しやすく、適切な治療へつなげやすいのが大きな利点です。
合併症の早期発見
黄色い下痢を引き起こす病気の中には、放置すると肝臓や胆嚢、膵臓など他の臓器にも影響が及び合併症を起こすものがあります。
胆管閉塞が長期間続くと黄疸や肝機能障害を誘発する可能性があり、胆管炎を伴うと命に関わる危険性もあり、内視鏡検査を通じて早期に兆候を見つければ、こうした合併症を回避できるチャンスが広がります。
内視鏡検査で確認できる主なポイント
| 観察対象 | 確認できる内容 | 意義 |
|---|---|---|
| 胃 | 潰瘍や炎症、ポリープ、腫瘍 | 上部消化管由来の下痢や食欲不振、悪心の原因特定に役立つ |
| 小腸(主に十二指腸まで) | 潰瘍、粘膜のびらん、胃液や胆汁の逆流 | 消化不良や脂肪便が続く場合の状態把握に重要 |
| 大腸 | 炎症、ポリープ、腫瘍、憩室 | 潰瘍性大腸炎やポリープによる下痢、便性状の変化の評価ができる |
| 経鼻内視鏡・カプセル内視鏡など | 通常の胃カメラ・大腸カメラで届きにくい小腸内部をチェック | 小腸疾患の確定診断や炎症範囲の測定などに活用 |
生検や組織検査の重要性
内視鏡検査では、疑わしい病変を発見した場合にその場で組織を採取し、生検と呼ばれる詳細な検査を行うことも可能です。
病変が急性炎症なのか炎症性腸疾患なのか、それとも悪性腫瘍なのかを顕微鏡レベルで調べられるため、正確な診断ができます。こうした精密検査は血液検査や画像診断では得られない情報を提供し、治療方針の決定に大いに役立ちます。
受診のタイミング
下痢といっても、数日程度の軽い症状であれば、食事の調整や水分補給で回復するケースもありますが、1週間以上連続する、あるいは発熱や嘔吐、強い腹痛を伴う場合は早急に医療機関を受診することが賢明です。
特に便が黄色く油っぽい、体重が急激に減少している、貧血や黄疸が見られるときは、内視鏡検査を含めた総合的な評価が強く推奨されます。
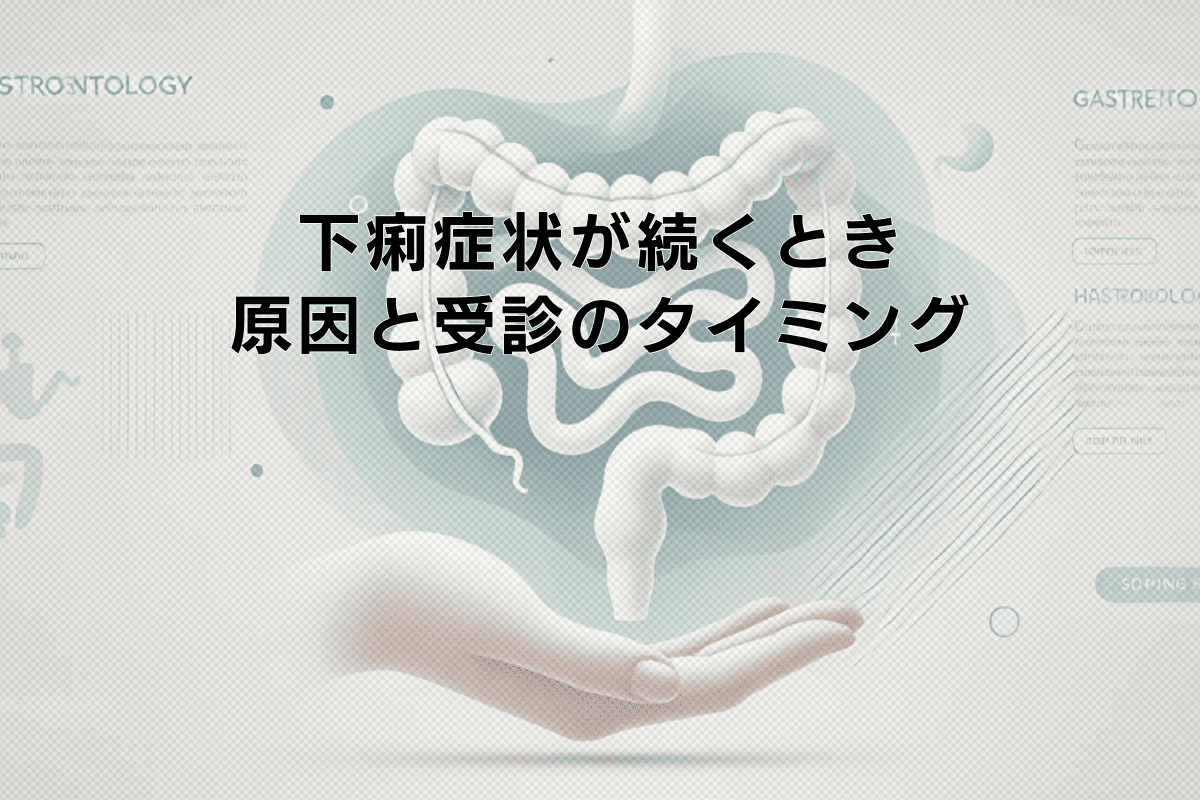
胃カメラ検査の流れと注意点
黄色い下痢の原因が上部消化管に関連していると疑われる場合、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)が第一の選択肢になります。
食道から胃、十二指腸までを直接観察し、必要に応じて粘膜の一部を採取することができるため、疾患の有無や進行度を正確に把握できます。

検査前の準備
胃カメラ検査を受ける際は、通常前日の夜から食事を絶つことが求められ、これは胃内に食物が残らないようにし、検査の精度を高めるためで、当日朝も絶食のまま受診し、水やお茶のみ少量摂取してよいと指示される場合が一般的です。
また、高血圧や糖尿病など持病がある人は、飲み薬のタイミングを医師と相談して調整する必要があります。
胃カメラ検査前に確認しておきたい項目
| 項目 | 注意点 | 目的 |
|---|---|---|
| 絶食時間 | 前日夜~当日朝まで食事を控える | 検査時の視野をクリアにし、嘔吐や誤嚥を防ぐ |
| 水分摂取 | 水・お茶などは少量なら飲めることが多い | 脱水を防ぎ、飲み薬などを必要に応じて服用できる |
| 内服薬の確認 | 高血圧、糖尿病、抗凝固薬など | 検査当日の服用タイミングを事前に確認し、安全に検査を行う |
| 体調チェック | 発熱や風邪症状がないか確認 | 安全に検査できる状態かを判断し、感染予防にも配慮する |

検査の進め方
検査前に局所麻酔剤のスプレーや鎮静剤を使用する場合があります。検査機器を口から挿入し、食道、胃、十二指腸の順にモニターを確認しながら粘膜を観察します。
炎症や潰瘍、腫瘍、ポリープなどの異常があれば画像や動画を撮影し、必要に応じて組織を採取し、検査時間は個人差はありますが、おおむね数分から15分程度で終了することが多いです。
組織採取と痛み
組織を採取する際、粘膜を一部つまむイメージですが、胃の粘膜自体には痛覚がほとんどないため、多くの人は痛みを感じず、体感的には少し違和感がある程度です。
検査後に多少の胃もたれや腹部の張りを感じる人もいますが、安静にしていれば数時間から1日程度で落ち着きます。
検査後の注意点
鎮静剤を使用した場合、検査後数時間は眠気やふらつきが残ることがあるので、車の運転は避け、付き添いがいるとより安全です。
胃カメラ検査後は喉や食道に違和感を覚える人もいますが、翌日には改善する場合が大半です。持病や服用薬によっては検査後も注意が必要なケースがあるため、医師の指示に従いましょう。
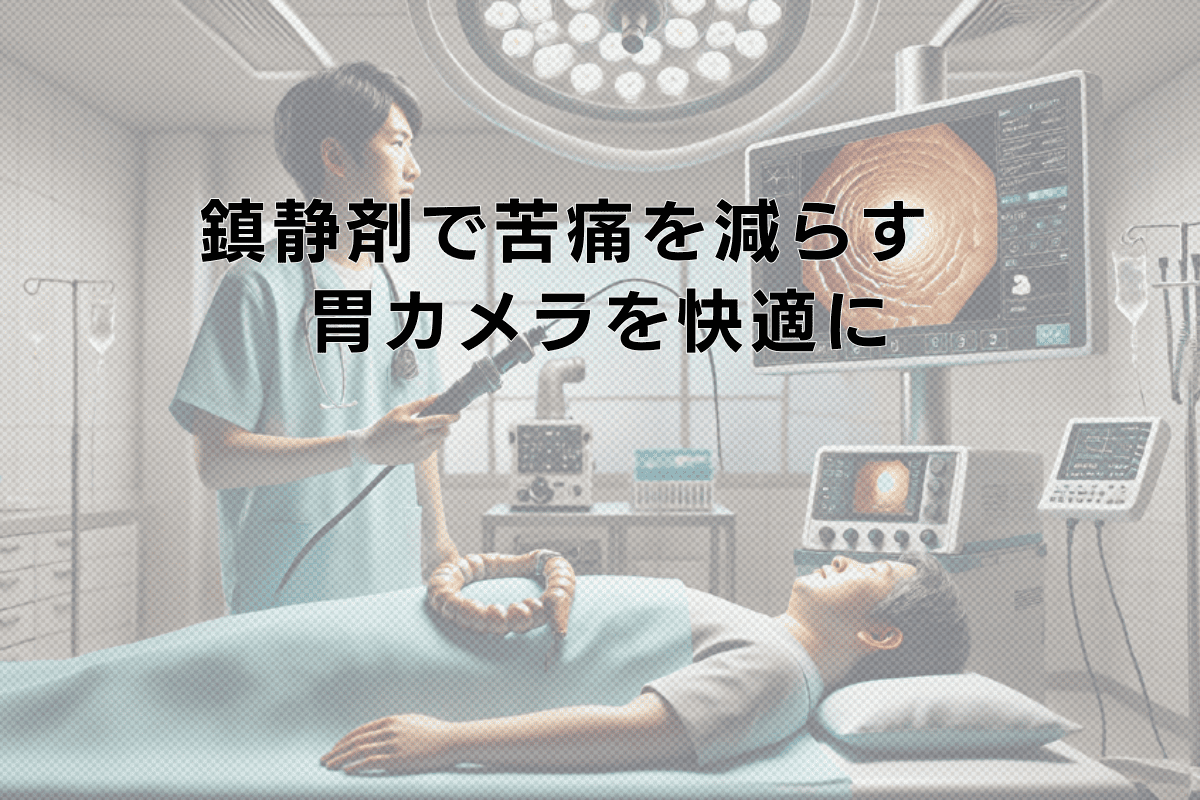
検査後に意識しておきたいこと
- 鎮静剤使用後は公共交通機関を利用し、可能であれば誰かの付き添いを頼む
- 激しい運動や飲酒、刺激物の摂取は当日は控える
- 少しずつ食事を再開し、負担の少ないものを選ぶ
- 組織採取をした場合、医師の指示があるまで抗血栓薬などの再開タイミングを守る
大腸カメラ検査の流れと注意点
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)は大腸内を隅々まで観察し、ポリープや炎症、腫瘍などを直接確認できる方法です。
黄色い下痢が続く背景に大腸の病気が疑われる場合や、血便や体重減少といった症状が併発している場合は、大腸カメラが診断の要となることがあります。

検査前の下剤による腸管洗浄
大腸カメラ検査では、腸内に便が残っていると視野が妨げられて正確な観察が難しくなるため、検査前日に食事制限を行い、当日に下剤を飲んで腸管をきれいに洗浄します。
下剤は大量の電解質を含む飲み薬を数時間かけて摂取し、透明か薄黄色の液体便が出るまで続けることが一般的です。便が完全に出切っていない場合、検査の精度が落ちるだけでなく検査時間も長くなる可能性があります。
大腸カメラ前の準備でチェックしたい項目
| 項目 | 注意点 | 目的 |
|---|---|---|
| 前日の食事 | 消化にやさしいものを少量に制限 | 腸内をきれいにしやすくする |
| 下剤の摂取 | 規定量を時間をかけて飲みきる | 腸管を洗浄し、便を全て排出して視野を確保 |
| 飲み薬の確認 | 糖尿病薬や抗凝固薬など | 検査当日の飲み薬のタイミングや休薬を医師と相談する |
| 十分な水分補給 | 水分を多めに取り脱水を防ぐ | 下剤で失われる水分を補い、腸内をきれいに保つ |
検査の進め方
大腸カメラは肛門からスコープを挿入して大腸全体を観察し、検査中は腸内を膨らませるために少量の空気や二酸化炭素を入れ、しわを伸ばして粘膜を確認します。
ポリープや出血点などの異常を見つけた場合、その場で切除や止血処置を行うことが可能です。検査自体は個人差がありますが、10分から30分程度かかることが多く、腸が長い人や癒着がある場合はやや時間が延びる場合もあります。
痛みや違和感への対処
大腸カメラで感じる痛みは、腸が伸ばされるときの張り感が主な原因です。最近では鎮静剤を使用する医療機関もあり、リラックスした状態で受けることで苦痛を軽減できます。
検査後はおなかに空気が溜まったような膨満感が続くことがありますが、ガスを排出すれば徐々に解消します。ただし、痛みが強い場合はスタッフや医師に伝えて対処してもらいましょう。
検査後の過ごし方
大腸カメラ後は、場合によってはポリープ切除などの処置を行うケースもあり、その場合は出血予防のため当日や翌日の激しい運動や飲酒を控えるよう指示されることがあります。
水分や消化にやさしい食事を少しずつ取り、異常がなければ通常の生活に戻れることがほとんどです。ただし、強い腹痛や便に血が混じるなどの症状が続くなら、再度受診して医師に相談してください。
検査当日のポイント
- 移動は公共交通機関を利用し、可能なら付き添いを頼む
- 検査後は腸内に残ったガスを意識的に排出して膨満感を減らす
- ポリープ切除などを行った場合は1~2日は無理せず安静を心がける
- 水分補給を十分に行い、脱水を防ぐ
黄色い下痢を改善する生活の工夫
黄色い下痢が続くとき、内視鏡検査などの医療的アプローチも重要ですが、日常生活での工夫によって症状が軽減する可能性もあります。
原因が特定できた場合はもちろん、軽度の異常だった場合も、腸内環境を整えたり体に負担をかけない食生活を意識することで回復を早められます。
脂肪分の多い食事を控える
黄色い下痢が続くときは、脂肪を多く含む食品(揚げ物、バター、生クリームなど)を大量に摂取すると、下痢が悪化することがあります。これは消化が追いつかず脂肪便が増えるためです。
調理方法を変えて蒸し料理や煮物を増やし、オイルを使う場合も良質な油を適量使うようにすると胃腸に優しくなります。
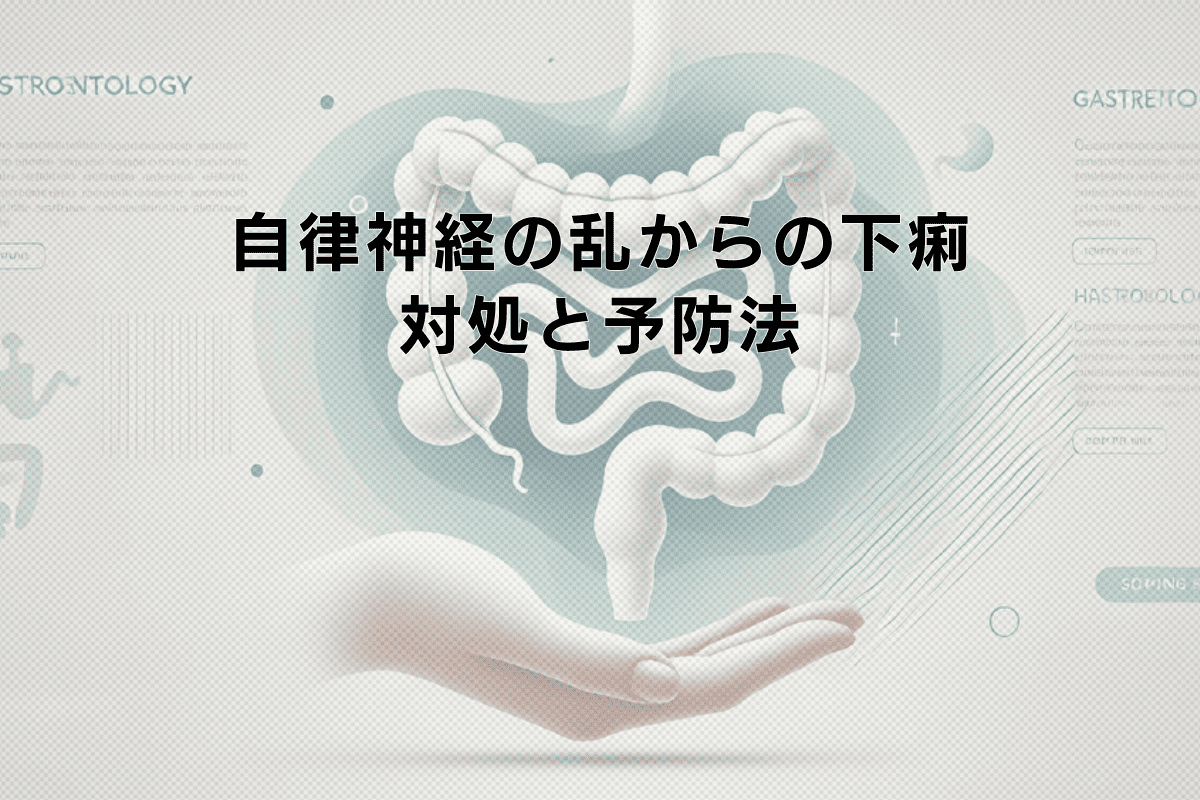
腸内環境を整える食品
ヨーグルトや発酵食品に含まれる乳酸菌・ビフィズス菌などは、腸内の善玉菌を増やし悪玉菌の活動を抑える働きが期待できます。
納豆や漬物、キムチなどの発酵食品も同様の効果があるとされ、継続して摂ることで腸内環境の改善に寄与するかもしれません。ただし、過度に酸味が強いものは胃腸に刺激となる場合があるので、体調を見ながら適量に抑えることが大切です。
おすすめの食材と期待できる働き
| 食材 | 主な栄養素 | 働き |
|---|---|---|
| 白身魚 | 良質なたんぱく質、低脂肪 | 消化にやさしく、胃腸の負担が少ない |
| 大根、にんじん | 食物繊維、ビタミンCなど | 便を適度にかさ増しし腸内環境を整える |
| おかゆ、うどん | 炭水化物、適度な食物繊維 | 水分を含み、下痢時でも消化しやすい |
| ヨーグルト | 乳酸菌 | 善玉菌を増やし腸内バランスを安定させる |
| バナナ | 食物繊維、カリウム | 胃腸にやさしく、程よい甘さでエネルギー補給になる |

ストレス管理と休養
ストレスや過労が大きいと自律神経が乱れやすく、腸管の動きが不安定になります。下痢や便秘を繰り返す方は、睡眠時間の確保や適度な運動、リラクゼーションを取り入れることで症状が緩和するケースがあります。
仕事や家事で忙しくても、意識的に休息を取り、自分がリラックスできる時間を確保すると、腸だけでなく全身のコンディションが改善しやすいです。
薬物療法との併用
医師から整腸剤や胆汁酸結合薬、膵酵素剤などが処方されることがあり、これらを服用しながら食事や生活習慣を整えることで、より早く下痢が落ち着くことが期待できます。
ただし、処方薬を独断で中断すると症状が悪化する可能性があるので、必ず医師の指示を守って継続しましょう。
日常で心がけたい対策
- 野菜や果物、発酵食品を意識的に摂る
- こまめな水分補給で脱水を防ぐ
- ストレスを溜めず、十分な睡眠を取る
- 下痢が落ち着いてきたら運動を習慣づける
よくある質問
- 黄色い下痢が続けば必ず大きな病気なのでしょうか?
-
一時的な食生活の乱れや体調不良で黄色い下痢になる人もいます。ただし、1週間以上続いたり、体重減少や発熱、腹痛が伴うなどの異常が見られる場合は精密検査が必要になる可能性があります。
原因が良性の疾患でも放置すると症状が悪化することがあるため、早めに受診して問題の有無を確認することが大切です。
- 自宅でできる対処法はありますか?
-
まずは刺激物や脂肪分の多い食事を控え、ヨーグルトなど腸内環境を整える食品を適度に摂取する方法が考えられます。また、こまめに水分を補給して脱水を防ぎ、できるだけ規則正しい生活を送ることも有効です。
症状が改善しない場合や、むしろ悪化するようなら無理に我慢せず医療機関を受診してください。
- 内視鏡検査は苦痛が大きいのでしょうか?
-
医療機関によって鎮静剤や鎮痛剤を用いた方法が一般的になってきており、昔に比べて苦痛は軽減されています。胃カメラの場合は鼻から挿入する経鼻内視鏡を選択できるケースもあります。
大腸カメラの場合は腸に空気を入れるときの張り感がある程度ですが、検査に慣れたスタッフが対応し、鎮静を使えば痛みや不快感は少なく抑えられます。
以下の記事も参考になります。
⇒【鎮静剤で苦痛を減らす 胃カメラを快適に受けるために】
鎮静剤使用のメリット・注意点を解説し「痛い検査」という先入観を払拭します。 - 内視鏡検査の結果、異常がなかった場合はどうすればよい?
-
異常が確認されなかった場合は、機能性のトラブルや軽度の吸収不良が考えられます。生活習慣や食事内容を見直し、整腸剤や漢方薬などを試しながら経過観察することが多いです。
医師の指示に従い、定期的な診察や必要に応じた再検査を受けると安心です。
次に読むことをお勧めする記事
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
黄色い下痢を学んだ皆さんには、消化器官全体の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
【脂肪便のような下痢症状と消化管内視鏡検査での評価基準】
黄色い下痢の原因で気になる『脂肪便』について、実際にどんな検査で確認し、どんな疾患が潜むのかを具体的な流れとともに解説しています。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Turdiyev T. DIARRHEA: ETIOLOGY, CLINICAL PRESENTATION, TREATMENT, AND PREVENTION. International journal of medical sciences. 2025 Mar 22;1(2):69-74.
Bhattacharjee S, Siyad I, Maramattom BV. Chronic diarrhea-the poetic masquerade. Journal of Postgraduate Medicine. 2022 Oct 1;68(4):239-42.
Pugliese ME, Battaglia R, Cerasa A, Lucca LF. A rare case of severe diarrhea: gastrocolic fistula caused by migration of percutaneous endoscopic gastrostomy tube. InHealthcare 2023 Apr 28 (Vol. 11, No. 9, p. 1263). MDPI.
Wahnschaffe U, Ignatius R, Loddenkemper C, Liesenfeld O, Muehlen M, Jelinek T, Burchard GD, Weinke T, Harms G, Stein H, Zeitz M. Diagnostic value of endoscopy for the diagnosis of giardiasis and other intestinal diseases in patients with persistent diarrhea from tropical or subtropical areas. Scandinavian journal of gastroenterology. 2007 Jan 1;42(3):391-6.
Martínez C, Rosales M, Calvo X, Cuatrecasas M, Rodriguez-Carunchio L, Llach J, Fernández-Avilés F, Rosiñol L, Rovira M, Carreras E, Urbano-Ispízua A. Serial intestinal endoscopic examinations of patients with persistent diarrhea after allo-SCT. Bone marrow transplantation. 2012 May;47(5):694-9.
DuPont HL. Persistent diarrhea: a clinical review. Jama. 2016 Jun 28;315(24):2712-23.
Cheng S, Cooper C, Chao CY. Persistent Diarrhea: What Else Could It Be?. Gastroenterology. 2025 Feb 24.
Boland K, Bedrani L, Turpin W, Kabakchiev B, Stempak J, Borowski K, Nguyen G, Steinhart AH, Smith MI, Croitoru K, Silverberg MS. Persistent diarrhea in patients with Crohn’s disease after mucosal healing is associated with lower diversity of the intestinal microbiome and increased dysbiosis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2021 Feb 1;19(2):296-304.