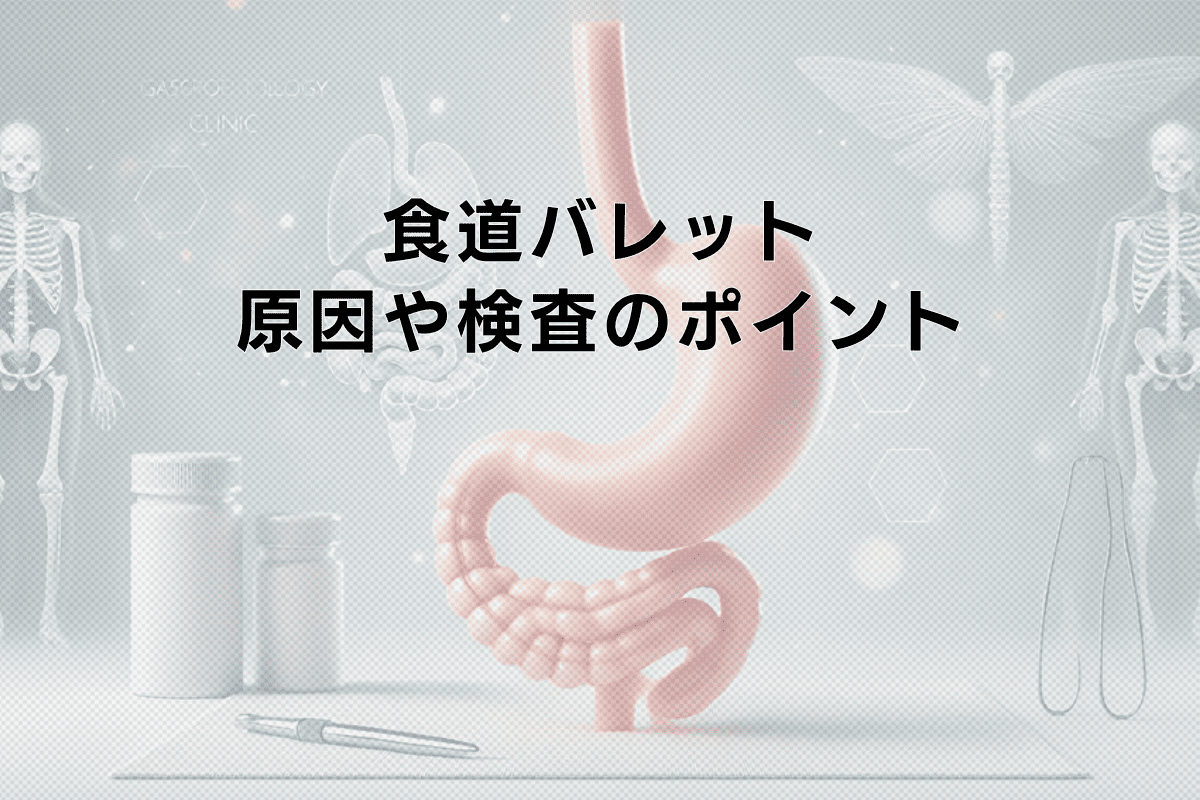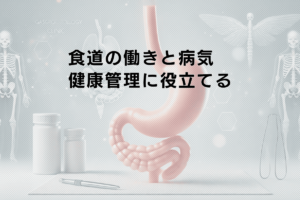バレット食道とは、長期間の胃酸の逆流によって食道の粘膜が変化し、本来の扁平上皮から胃や腸の粘膜に似た円柱上皮へと置き換わる特徴があります。
とくに逆流性食道炎が慢性的に続く場合にバレット食道を発症しやすく、食道がん(腺がん)のリスクが高まることから注意が必要です。
食後の胸やけや呑酸(酸っぱい液がこみ上げる感じ)、吐き気などに悩む方が増えており、定期的な内視鏡検査(胃カメラ)を受けることが大切です。
ここでは、バレット食道の原因や症状、発生のしくみ、検査や治療の方法、生活習慣の改善点などを詳しくお伝えします。
バレット食道とは何か
バレット食道は、もともと扁平上皮で覆われている食道の最下部付近が、慢性的な胃酸の逆流や炎症によって腸や胃の粘膜に近い円柱上皮へ置き換わる状態です。
日本人にはなじみが薄いかもしれませんが、生活習慣の変化や肥満の増加などに伴い、近年、発症が注目されています。
食道の基本的な構造
食道は口から摂取した食べ物や飲み物を胃へと運ぶ大切な器官です。長さは約25cmほどで、胸部を通過する過程で複数の生理的狭窄部位をもつことが知られています。
食道内部が薄い扁平上皮(外部からの刺激にある程度強い組織)で覆われていて、胃に近い部分では強い胃酸の刺激から保護されるため、胃の粘膜とは異なる組織構造を保ちます。
バレット食道の定義と粘膜変化
バレット食道は、食道の下部が胃酸の逆流などの炎症によって、扁平上皮から腺上皮へと置き換わる状態です。
腺上皮は胃や腸の粘膜に近い特徴をもち、欧米などではこの病気から食道がん(腺がん)が増加していると報告されていて、日本でも生活習慣の変化とともに食道バレットの患者数が増えています。
逆流性食道炎との関係
逆流性食道炎は胃酸や消化酵素が逆流することで食道に炎症が起こる病気です。この慢性的な逆流や炎症が続くと、食道の粘膜が本来の扁平上皮から腺上皮へ変化しやすくなります。
逆流性食道炎を放置するとバレット食道に進行する可能性があり、症状や胸やけを「たいしたことない」と放置しないことが重要です。
SSBEとLSBEの違い
バレット粘膜が置き換わる範囲によって、SSBE(Short Segment Barrett’s Esophagus:短い範囲)とLSBE(Long Segment Barrett’s Esophagus:長い範囲)に区分されます。
SSBEは日本人に多いタイプで、LSBEは欧米で多く報告されていて、LSBEでは食道がんに発展するリスクが高いといわれ、どちらの場合でも定期的な内視鏡検査が重要です。
バレット粘膜の広がりに関する目安
| 分類 | バレット粘膜の長さ | 主な特徴 |
|---|---|---|
| SSBE | 3cm未満 | 日本人に多い、がんリスクは比較的低め |
| LSBE | 3cm以上 | 欧米で多い、がんリスクが高まる |
バレット食道の原因と発生のしくみ
長期化した胃酸の逆流や強い炎症が、もともと扁平上皮であった粘膜を円柱上皮へ変化させる大きな要因です。食道裂孔ヘルニアや肥満、喫煙、アルコールの過剰摂取なども逆流を助長し、粘膜へ絶えずダメージが加わります。
慢性的な胃酸逆流
主な原因として、胃酸が食道へ長期にわたって逆流し続ける状態が挙げられ、胃酸や消化酵素が食道粘膜を刺激し、慢性的な炎症を引き起こすため、粘膜が本来の扁平上皮から円柱上皮へ変化しやすくなります。
特に食道裂孔ヘルニアがある場合、胃の一部が胸腔に出てしまって逆流を助長し、より食道がダメージを受けることがあります。
肥満や生活習慣との関係
肥満や食事の欧米化は、バレット食道の発生に大きく影響します。肥満は腹圧の上昇を招き、胃酸が逆流しやすくなり、高脂肪食、アルコールの多量摂取、喫煙なども逆流性食道炎を悪化させる要因となります。
ピロリ菌感染と胃酸分泌
胃がんの原因として有名なピロリ菌ですが、近年の除菌治療によって胃酸の分泌が増加しやすい状況を作り出すケースも指摘されていて、胃酸分泌が過剰になると逆流が起こりやすくなり、バレット食道の原因の一つです。。
長期的な慢性炎症と粘膜の置換
胃酸が引き起こす炎症は、粘膜細胞にダメージを与え続けます。そのダメージを修復する際に修復時に腺上皮が生じ、粘膜が変化していくのがバレット化のメカニズムです。このメカニズムは短期間では進行せず、長年にわたる炎症の蓄積によって発生します。
バレット食道の主な原因
| 原因・要因 | 解説 |
|---|---|
| 長期間の逆流性食道炎 | 胃酸・消化液の逆流で食道粘膜に慢性的な炎症が起こる |
| 肥満 | 腹圧上昇により逆流が起こりやすくなる |
| 食道裂孔ヘルニア | 胃の一部が上部へ移動して胃酸逆流を助長 |
| ピロリ菌除菌後 | 胃酸分泌が増え逆流を招く可能性がある |
| 喫煙・飲酒 | 食道粘膜への刺激や逆流性食道炎の悪化を促しやすい |
主な症状と合併症のリスク
胸やけや呑酸、吐き気など逆流性食道炎の症状と重なる場合が多く、バレット食道自体の自覚症状は必ずしもはっきりしないことがあります。
慢性的な炎症が続くことで食道狭窄や潰瘍のリスクも高まり、組織がさらに変化して食道がん(腺がん)を発症する懸念も生じます。
胸やけや呑酸
食道バレットそのものには強い痛みが出るケースは少ないですが、もともとの逆流性食道炎を合併している場合は胸やけや呑酸、吐き気、げっぷなどの症状が多く見られます。
これらの症状が頻繁に現れる人は、食事の内容や時間帯を見直したり、消化器クリニックで相談することが必要です。
食道がんのリスク
バレット食道は、放置すると腺がんなどの食道がんに発展するリスクがあり、日本人に多い扁平上皮由来の食道がんとは異なる発生経路をたどり、欧米ではこの腺がんの増加が顕著です。
日本でも食事の欧米化や肥満の増加によって腺がんのリスクが高まる可能性があります。
胃がんや大腸がんとの関連
バレット食道が直接的に胃がんや大腸がんを増やすわけではありませんが、生活習慣が原因になっている場合、ほかの消化器系疾患も合併しやすい傾向が報告されています。
胃がんや大腸がんのリスクを考える意味でも、定期的に内視鏡検査を受けることが望ましいです。
合併症への注意点
慢性的な逆流や炎症は潰瘍を生じやすくし、出血や狭窄などの合併症に繋がる場合があります。胸やけや痛みが続く、吐き気や食欲不振が強いなどの症状があれば、早めにクリニックを受診してください。
バレット食道が疑われる症状のチェックリスト
- 胸やけが週に数回以上続く
- 就寝中に酸っぱい液がこみ上げる感じがある
- 背中や胸の痛み、違和感を感じる
- 呑酸をよく感じる
- 食後すぐに横になる習慣がある
内視鏡検査と診断の流れ
バレット食道を疑った場合、最も信頼できる方法は内視鏡検査です。カメラを使って食道粘膜を直接観察し、必要に応じて組織を採取して病理検査を行い、腺がんが含まれていないかを確かめます。
受診のきっかけ
食道バレットは症状が軽度なことが多く、本人が気づかないうちに進行するケースがあります。胸やけが長引く、寝ているときに逆流を感じるなどの症状がある場合、消化器内科や内視鏡を専門とするクリニックを受診してください。
胃カメラによる観察
バレット食道の診断には胃カメラによる観察が最も有効です。内視鏡検査では、食道の粘膜がどの程度置き換わっているかを直接観察し、腺上皮の広がりや炎症の度合いを確認できます。
必要に応じて組織を採取し、病理検査でがん細胞の有無を調べることがあります。
内視鏡検査の主な流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 症状や既往歴、生活習慣の確認 |
| 前処置 | 食道や胃をきれいにするための薬剤投与 |
| 胃カメラ挿入 | 麻酔で痛みを抑えて内視鏡を挿入 |
| 観察 | 食道から胃まで、粘膜の状態を細かく観察 |
| 組織採取 | 必要に応じて生検し病理診断へ |
| 診断 | 組織検査の結果を踏まえ総合的に診断 |

診断基準とバレット粘膜の評価
内視鏡検査では、EGJ(食道と胃の境界)からどの程度上部まで腺上皮が広がっているかを評価します。バレット粘膜の長さ、炎症の有無、腺上皮の形態などを総合して診断し、治療方針を立てます。
定期検診の必要性
バレット食道と診断された場合、年に1回程度の定期的な内視鏡検査を行ってがん発生の有無を観察します。早期発見によって、内視鏡下で粘膜切除が可能な場合もあります。症状がなくても、内視鏡検査を怠らないことが大切です。

バレット食道の定期検診を受けるメリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| がんの早期発見 | 腺がんや扁平上皮がんを初期段階で見つけることができる |
| 症状の把握・管理 | 逆流性食道炎の再発や悪化を早めに確認できる |
| 治療計画の最適化 | 薬の種類や生活習慣へのアドバイスを適切に行える |
| 総合的な消化器評価 | 同時に胃や大腸など他の部位の異常もチェックし、胃がん・大腸がん対策に |
バレット食道の治療方法
まずは逆流性食道炎の治療と同様に、胃酸抑制薬や生活習慣の改善を行い、炎症を抑えます。バレット腺がんと診断されたら、内視鏡治療や外科的手術を検討します。
薬物療法による胃酸分泌抑制
バレット食道の治療では、まず逆流や炎症を抑えることが重要です。代表的な薬としてプロトンポンプ阻害薬(PPI)やヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)があり、胃酸の分泌を抑えて食道粘膜へのダメージを軽減します。
バレット食道の治療に用いられる主な薬剤
| 薬剤 | 特徴 |
|---|---|
| プロトンポンプ阻害薬(PPI) | 強力に胃酸分泌を抑える、長期服用が多い |
| H2ブロッカー | 比較的軽度の場合に使用しやすい |
| 制酸薬 | 胸やけなど急性症状の緩和 |
| 胃腸運動促進薬 | 逆流や胃内容物の停滞を改善しやすい |
内視鏡治療と粘膜切除
もし食道粘膜に早期のがんや高度の異常が見つかった場合は、内視鏡を使った粘膜切除(EMRやESD)が検討されます。腫瘍がまだ粘膜層にとどまっている段階ならば大掛かりな手術を行わずに取り除ける可能性があります。

手術の選択肢
進行がんになっている場合は、外科的な手術が必要です。食道や周囲リンパ節の切除が必要になることがあり、術後の生活の質を考慮した治療計画が求められます。
食事の摂取方法やリハビリなど、専門家の指導のもとで進めることが大切です。
定期的な薬物調整と検診
薬物療法によって胃酸分泌を抑え、粘膜を保護することでバレット食道の進行を遅らせたり、症状を緩和できます。
ただし長期服用による副作用リスクの問題もあるため、医師の指示のもとで定期的に薬剤を調整し、内視鏡検査で粘膜の状態を評価します。
生活習慣の改善と食事の注意
胸やけをはじめとする症状を和らげるには、腹圧を高めない工夫や胃酸分泌を増やす食品の摂取を控えるなどの生活改善が求められます。
生活習慣の見直しが重要
バレット食道では、生活習慣の改善が治療の柱となります。とくに肥満を解消し、腹圧を下げることは逆流の軽減に直結します。適度な運動やバランスの良い食事、喫煙や過度な飲酒の制限など、患者本人の努力が重要です。
生活習慣を見直すポイント
食事内容や食べ方の工夫
胃酸の逆流を防ぐため、食事内容や食べ方にも気を配る必要があります。脂っこいものやスパイシーな刺激物、炭酸飲料などは逆流を引き起こしやすいので控えるほうが無難です。よく噛んでゆっくり食べることで胃腸に負担をかけにくくします。
食事の注意点
| 食材・飲料 | 注意点 |
|---|---|
| 高脂肪食 | 胃内容物の停滞を招き、逆流を助長 |
| 刺激物(香辛料) | 粘膜を刺激しやすいため量に注意 |
| 炭酸飲料 | 胃内ガスを増やし、げっぷや逆流を起こしやすい |
| コーヒー | カフェインが胃酸分泌を増加させる場合がある |
| チョコレート | 食道下部括約筋を弛緩させる可能性 |
ストレスとの関わり
ストレスは自律神経バランスを乱し、胃酸の分泌や食道下部括約筋の緊張に影響することが報告されています。十分な睡眠や休養、趣味や運動などを通じてストレスをコントロールすることが大切です。
定期的な体重管理
肥満が原因となって逆流を生じているケースでは、体重管理に取り組むだけで症状が大幅に改善することがあります。体重を測る習慣をつけ、適切な摂取カロリーを守って食事を楽しむことが勧められます。
まとめと今後の診療の考え方
バレット食道は、逆流性食道炎がもたらす粘膜変化として知られ、食道がん(腺がん)のリスクを高める点が問題視されています。
胸やけや呑酸などが頻繁に起こる方は、早期に内視鏡検査を受けて状態を確認することが重要です。
バレット食道の理解が深まるメリット
バレット食道は、日本人にはまだ比較的なじみの薄い疾患ですが、胃酸逆流が持続することで粘膜が変化し、将来的に食道がんのリスクを高めることがわかっています。
早めに正しく理解し、定期的に内視鏡検査を受けることで、合併症や進行を防ぐことが可能です。
消化器クリニックでの診療
バレット食道を含む消化器の疾患全般を扱うクリニックでは、胃カメラや大腸内視鏡検査を通じて患者の消化器官全体を丁寧に観察します。
胸やけや胃もたれなどの症状が長引く場合は、早めにクリニックや内科を受診し、診療を受けることが望ましいです。
消化器クリニックで受けられる主な診療メニュー
- 胃カメラ検査(経鼻・経口)
- 大腸内視鏡検査
- 逆流性食道炎・潰瘍性大腸炎など各種炎症疾患の診療
- 便秘や下痢などの一般的な消化器症状の相談
- 人間ドックや健診での異常検査後の精密検査
日本人における発症傾向と対策
近年は食生活の欧米化や肥満の増加により、バレット食道とそれに続く食道がんが増えてきたとの報告があります。
喫煙習慣や糖尿病、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病とあわせて管理し、症状が少なくても年に1回程度の胃カメラ検診を受けることが推奨されています。
さらなる予防・診断への心がけ
バレット食道の治療においては、定期的な内視鏡による観察と、薬剤による胃酸抑制、生活習慣の見直しが3つの柱となります。
これらを継続的に行うことで、合併症やがんへの進行を抑え、より良い生活の質を維持しやすくなります。
次に読むことをお勧めする記事
【胃カメラで分かる症状 検査の流れ】
バレット食道の基礎知識について理解できたら、次は実際の診断に必要な胃カメラ検査について、一緒に勉強してまいりましょう。検査を受ける可能性のある方に特におすすめです。
【食道の働きと病気を理解 健康管理に役立てる】
バレット食道についての理解が深まりましたら、さらに食道全体の働きと関連する病気についても知っておくと、より包括的な理解につながります。以下の記事で一緒に学んでまいりましょう。
参考文献
Spechler SJ, Goyal RK. Barrett’s esophagus. New England Journal of Medicine. 1986 Aug 7;315(6):362-71.
Falk GW. Barrett’s esophagus. Gastroenterology. 2002 May 1;122(6):1569-91.
Sharma P. Barrett’s esophagus. New England journal of medicine. 2009 Dec 24;361(26):2548-56.
Spechler SJ, Souza RF. Barrett’s esophagus. New England Journal of Medicine. 2014 Aug 28;371(9):836-45.
Spechler SJ. Barrett’s esophagus. New England Journal of Medicine. 2002 Mar 14;346(11):836-42.
Phillips WA, Lord RV, Nancarrow DJ, Watson DI, Whiteman DC. Barrett’s esophagus. Journal of gastroenterology and hepatology. 2011 Apr;26(4):639-48.
Peters JH, Hagen JA, DeMeester SR. Barrett’s esophagus. Journal of gastrointestinal surgery. 2004 Feb;8(1):1-7.
Hvid-Jensen F, Pedersen L, Drewes AM, Sørensen HT, Funch-Jensen P. Incidence of adenocarcinoma among patients with Barrett’s esophagus. New England Journal of Medicine. 2011 Oct 13;365(15):1375-83.
Sharma P. Barrett esophagus: a review. Jama. 2022 Aug 16;328(7):663-71.
Skinner DB, Walther BC, Riddell RH, Schmidt HE, Iascone CL, DeMeester TR. Barrett’s esophagus. Comparison of benign and malignant cases. Annals of surgery. 1983 Oct;198(4):554.