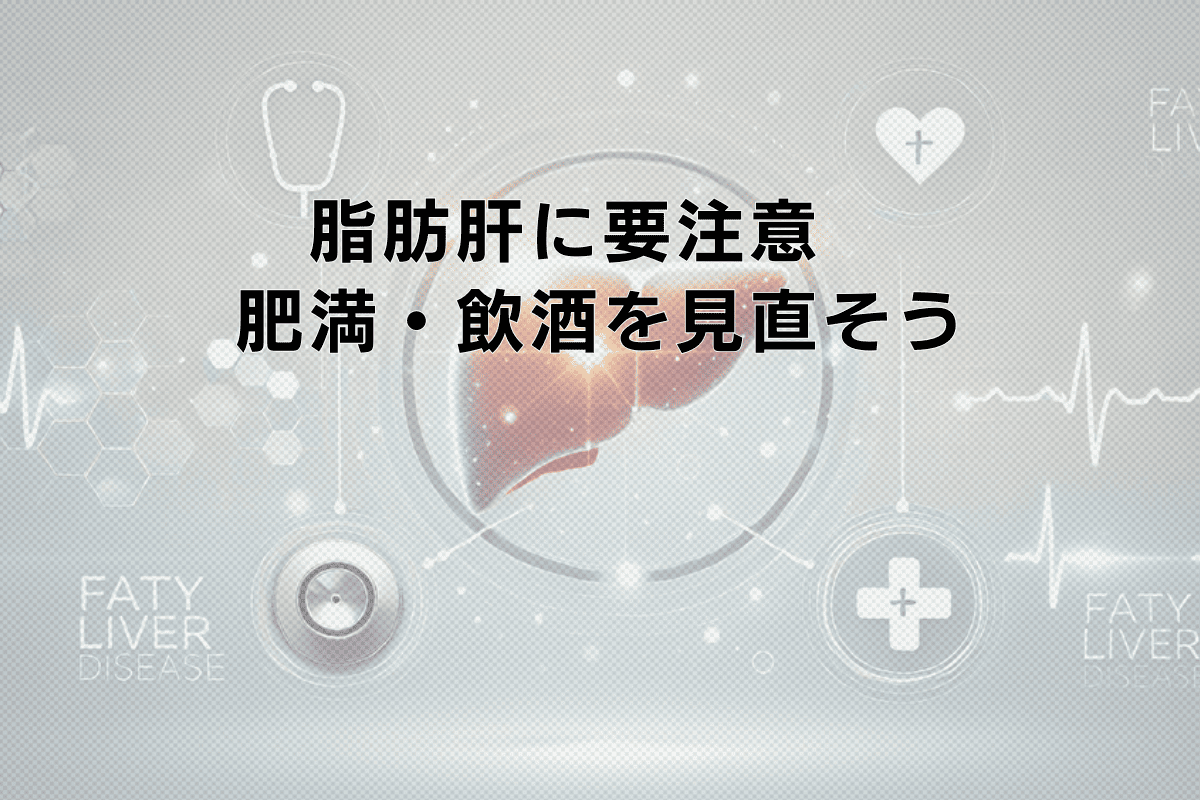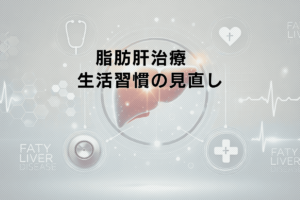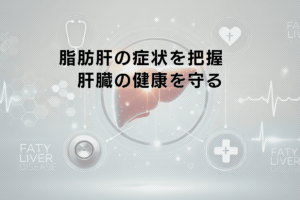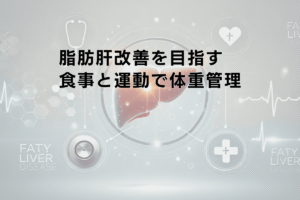肝臓に脂肪が過剰に蓄積し、深刻な肝硬変や肝がんへと進行する可能性をもつ脂肪肝は、日本でも非常に多い疾患として知られています。
自覚症状がないままじわじわと進む場合が多く、健診や人間ドックで指摘されて初めて「自分の肝臓に脂肪肝がある」と気づく人も珍しくありません。
とくにアルコールの飲酒量が多い方や肥満の方、さらに糖尿病や脂質異常症、高血圧などの生活習慣病を複数抱えている方は注意が必要です。
ここでは、脂肪肝の原因や症状、診断方法、治療に向けた食事と運動の工夫などを解説します。
脂肪肝とはどのような状態か
肝臓は体内の有害物質やアルコールを分解し、エネルギー源のグリコーゲンを蓄え、胆汁を合成して消化を助けるなど、多くの重要な機能を担っており、全身の代謝や免疫にも大きく関わっています。
こうした肝臓に脂肪が過剰に蓄積すると、中性脂肪が肝細胞内にたまり、肝の機能を妨げることがあり、これが脂肪肝の状態です。
肝臓と脂肪の関係
肝臓は脂質や糖質などをエネルギーに変換する働きがあり、過剰に摂取した脂肪や糖は、肝での合成を経て中性脂肪として蓄えられやすくなります。
飲酒や肥満、過剰なカロリー摂取などにより、この蓄積が常態化すると脂肪肝に至る可能性が高いです。
脂肪肝とMASLD・MASH
代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)は、アルコール摂取量の少ない人でも起こる脂肪肝の総称であり、このうち肝細胞に炎症が生じて進行するものが代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)です。
MASHは肝硬変や肝がんへと進むリスクが高く、肥満やインスリン抵抗性、糖尿病を伴うことが多いとされています。
アルコール性脂肪肝
アルコールを多く摂取する人に見られる脂肪肝はアルコール性脂肪肝と呼ばれ、長期かつ過剰な飲酒が習慣になると肝臓でのアルコール分解が追いつかなくなり、中性脂肪や毒性をもつ代謝物が肝細胞を傷つけます。
アルコール性脂肪肝も、進行するとアルコール性肝炎や肝硬変につながりやすいです。
女性や若年層の増加傾向
以前は中高年の男性に多いと考えられていた脂肪肝ですが、近年は食生活の欧米化や運動不足の傾向などに伴って、若い女性にも増えています。
特に無理なダイエットで急激に体重を落とすと、血液検査でALTなど肝機能に異常値が見られることがあり、脂肪肝を指摘されるケースもあります。
脂肪肝にかかわる主なキーワード早見表
| キーワード | 意味やポイント |
|---|---|
| 脂肪肝 | 肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態 |
| 肝臓 | 全身の代謝・解毒・合成を担う重要な臓器 |
| 中性脂肪 | 体内のエネルギー源となる脂肪で、過剰だと蓄積が起こりやすい |
| アルコール | 肝臓に大きな負担をかけ、過剰な飲酒は脂肪肝の原因となりうる |
| 肥満 | 脂肪肝の大きな要因。内臓脂肪が多いとリスク上昇 |
| MASLD・MASH | 代謝異常に伴う脂肪肝で、進行すると肝硬変の可能性あり |
脂肪肝の原因とリスク要因
脂肪肝の原因は大きくアルコール性と非アルコール性に分けられますが、実際にはどちらも共通して過剰な中性脂肪の蓄積が引き金となっています。ここでは主なリスク要因と原因を概説し、放置した場合の注意点を確認します。
アルコールの過剰摂取
アルコールの分解産物アセトアルデヒドは有害性が高く、肝細胞へダメージを与え、さらに、アルコール分解の過程で肝臓のエネルギーを使い果たしてしまい、脂肪の分解や代謝が滞ることもあります。
したがって、飲酒量が多い人ほど脂肪肝を含む肝疾患のリスクが高まります。
適度な飲酒量は人によって異なりますが、厚生労働省のガイドラインでは一般的に男性は1日当たり約20g以下、女性は約10g以下のアルコール摂取が望ましいです。
アルコール飲料の目安
| 飲料 | 容量の目安 | アルコール度数(%) | 含まれるアルコール量 |
|---|---|---|---|
| ビール | 500ml | 5 | 20g |
| 日本酒 | 180ml | 15 | 22g |
| 焼酎(25%) | 100ml | 25 | 20g |
| ワイン(12%) | 200ml | 12 | 19g |
| ウイスキー(40%) | 60ml | 40 | 19g |
肥満や内臓脂肪の蓄積
肥満は脂肪肝の最大の原因のひとつであり、特にウエスト周囲径が大きく内臓脂肪型肥満となっている人ではリスクが高く、運動不足や食生活の乱れで、エネルギー摂取量が消費量を上回る状態が続くと、脂質が肝細胞に蓄積していきます。
体重とウエスト周囲径の両方を意識してコントロールすることが重要です。
糖尿病や脂質異常症との関連
糖尿病や脂質異常症(高脂血症)があるとインスリン抵抗性が増し、血糖値や中性脂肪が上昇しやすくなります。
この状態はMASLDへ進むリスクを高め、とくに糖尿病を患っている人はMASHへ移行する可能性が高いです。
無理なダイエットや栄養バランスの欠如
極端な糖質制限やカロリー制限などで急激に体重を落とすと、肝臓での代謝が混乱し、かえって中性脂肪がたまりやすくなることがあります。
ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養をバランスよくとることが大切で、無理なダイエットは脂肪肝の悪化を招くケースもあるため、医師や栄養士に相談することがおすすめです。
生活習慣病の重複とメタボリックシンドローム
脂肪肝は生活習慣病のひとつと位置づけられ、肥満・糖尿病・高血圧・脂質異常症などが重複している場合は、心臓や血管にも負担がかかりやすくなります。
メタボリックシンドロームと呼ばれる状態に至ると、脂肪肝だけでなく動脈硬化や脳卒中など全身の合併症リスクが高まる点にも注意が必要です。
脂肪肝による症状と進行の特徴
脂肪肝は初期の段階では自覚症状がほとんどありませんが、進行すると倦怠感、食欲不振、肩こり、集中力の低下など、さまざまな症状があらわれることがあります。
自覚症状の乏しさ
脂肪肝になっていても特に体の痛みを感じないことが多いです。
そのため「肝臓は沈黙の臓器」といわれ、自覚症状のないまま進行し、ある日健康診断や人間ドックの血液検査でAST、ALT、γGTPなどの肝機能数値が異常に高くなっていると判明するケースがしばしばあります。
慢性的な疲労感や倦怠感
倦怠感、疲労感、肩のこり、頭が重いといった漠然とした不調を感じる人もいます。これらの症状は他の病気でもよく見られるため、脂肪肝に起因していると気づかず放置してしまうことがある点に注意が必要です。
肝炎・肝硬変への進行
アルコール性脂肪肝でもMASLDでも、放置すると肝細胞に炎症が生じ、肝炎へと悪化し、アルコール性の場合はアルコール性肝炎、非アルコール性の場合はMASHを発症し、そこからさらに肝硬変に進む可能性があります。
肝硬変まで進むと肝の修復が難しくなり、さらなる合併症を引き起こすリスクが高まります。
肝がんや合併症のリスク
肝硬変を経て肝がんが発生するリスクも見逃せません。また、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった他の生活習慣病との併発で、心血管疾患など全身的な病気を引き起こす可能性が高くなるため、早期の診断・治療が大切です。
脂肪肝が進行したときに起こりやすい合併症
- 肝硬変(腹水や黄疸などの症状があらわれる可能性あり)
- 肝がん(慢性的な肝炎の状態が続くと発生リスクが上昇)
- 2型糖尿病や脂質異常症の悪化(インスリン抵抗性がさらに強まる)
- 高血圧や動脈硬化(血管への負担が増大する)
脂肪肝の検査と診断の流れ
脂肪肝は自覚症状に乏しいため、健康診断や人間ドックの結果で初めて指摘されることが多いです。ここでは、診断のために行われる主な検査方法について解説します。
血液検査
血液検査では、GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTPなどの肝機能を示す値や中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール、血糖値を確認し、脂肪肝がある場合、ALTがASTよりも大きく高くなる傾向がよく見られます。
ただし、血液検査の値が必ずしも重症度を反映しない場合もあるため、画像検査やその他の指標と合わせて総合的に判断することが必要です。
血液検査で見る主な項目と意義
| 項目 | 意義 |
|---|---|
| GOT(AST) | 肝や筋肉など幅広い組織に由来。肝炎などで上昇 |
| GPT(ALT) | 肝細胞の障害で特に上昇しやすい |
| γ-GTP | 飲酒量や胆道系の異常で上昇 |
| 中性脂肪 | 脂質異常症の指標。脂肪肝と関連性が高い |
| LDLコレステロール | 動脈硬化リスクを判断するうえで重要 |
| HDLコレステロール | 善玉コレステロール。低いほど動脈硬化リスクが高い |
| 血糖値 | 糖尿病やインスリン抵抗性の有無を探る手がかり |
画像検査
超音波(エコー)検査、CT検査、MRI検査などの画像診断で肝臓の脂肪蓄積状態を調べます。特にエコー検査は体への負担が少なく、脂肪肝のスクリーニングとしてよく用いられます。
CTやMRIは、より詳細な画像を得られる反面、放射線被ばくやコストの面で検討が必要となる場合もあります。
肝生検
肝硬変や肝がんの疑いが強い場合、肝生検による組織学的診断を行うことがあります。これは肝臓の一部を採取して、顕微鏡で肝細胞の状態や炎症の程度を確認するもので、MASHの診断には有用です。
ただし身体への負担が大きいため、一般的には血液検査や画像検査で十分な診断ができない際の最終手段となります。
診断基準と医療機関への受診
血液検査や画像検査で脂肪肝が疑われる結果が出た場合は、内科や消化器内科を受診すると良いでしょう。
クリニックによっては専門外来を設置しているところもあり、詳しい診断と治療方針の相談が可能です。放置せずに早めに診断を受けることで、重症化や合併症の発生を抑える可能性が高まります。
脂肪肝を予防し進行を食い止める方法
脂肪肝の最大の改善策は生活習慣の見直しです。具体的には食事や運動を中心としたセルフケアが基本であり、場合によっては医薬品の助けを借りることも検討されます。
食事の見直し
炭水化物や脂質の摂取量を適度にコントロールしながら、ビタミンや食物繊維、良質なたんぱく質をバランスよくとる食生活が大切です。特に糖質をとりすぎると中性脂肪が増えやすくなり、肥満の悪化につながります。
食事で意識したい栄養素と役割
| 栄養素 | 役割 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 筋肉や肝細胞の再生を助ける | 魚・肉・大豆製品・卵 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝を促進 | レバー・豚肉・納豆など |
| ビタミンC | 抗酸化作用で肝細胞の保護に寄与 | 柑橘類・イチゴ・緑黄色野菜 |
| ビタミンE | 活性酸素を抑制し、炎症を抑える働き | ナッツ類・植物油・かぼちゃなど |
| 食物繊維 | 血糖値の急上昇を抑え、脂質代謝にも良い影響 | 野菜・果物・海藻・きのこ類 |
| 不飽和脂肪酸 | コレステロールを下げ、動脈硬化を予防 | 青魚・オリーブオイル・アボカドなど |
適度な運動の取り入れ
運動不足は体重増加やインスリン抵抗性悪化の原因となり、脂肪肝リスクを高めます。
有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)を週に150分~200分程度行うとよいとされ、筋力を維持するための筋トレも併用することでエネルギー消費が増え、肝臓に蓄積しにくい体質づくりに役立ちます。
運動の種類と期待できる効果
| 運動の種類 | 主な例 | 効果 |
|---|---|---|
| 有酸素運動 | ウォーキング・ジョギング・サイクリングなど | 脂肪燃焼、心肺機能向上、インスリン抵抗性の改善 |
| レジスタンス運動 | スクワット・腕立て伏せ・ダンベル運動など | 筋力増強、基礎代謝量増加 |
| ストレッチ | 動的ストレッチ・ヨガ・太極拳など | 血行促進、柔軟性向上、リラックス効果 |
| 生活活動量の増加 | 階段の使用・立っている時間を増やす・家事など | 日常的なエネルギー消費増加、体重管理のサポート |
アルコールの制限
アルコール性脂肪肝であれば、何よりもまず禁酒が大切です。飲酒量を制限し、肝臓への負担を減らすことで、肝細胞の修復が期待できます。お酒を楽しみたい場合は、アルコール度数の低いものを少量飲むなど、飲み方を工夫するとよいでしょう。
- アルコール消費量を意識して管理する
- 休肝日を週に2日程度もうける
- 飲酒時には一緒に水も十分にとる
医薬品やサプリメントの活用
脂肪肝の改善を目的とした薬としては、ビタミン剤や脂質代謝を調整する薬、糖尿病治療薬の一部(SGLT2阻害薬など)が使用される場合があります(保険適応外です)。
ただし、薬やサプリメントはあくまでも補助的な位置づけであり、基本は生活習慣の改善です。
サプリメントの中には肝臓の健康に良いとされる成分が含まれているものもありますが、効果や安全性が十分に証明されていないものもあるため、必ず医師に相談してください。
クリニック受診の目安と治療の流れ
脂肪肝は生活習慣の調整で改善が期待できる一方、早期の診断と経過観察が非常に大切です。
自覚症状がない状態でも進行してしまうおそれがあるため、定期的な健診や血液検査の結果に注意し、異常があれば内科や消化器内科を早めに受診しましょう。
こんな症状や検査結果は要注意
- 健康診断でALTやγ-GTPが高いと言われた
- お酒を飲む量が多く、疲れやすさが続く
- 運動不足や肥満傾向があり、糖尿病や脂質異常症の治療中
- 肝臓にたまりを感じる、右上腹部に重苦しい違和感がある
受診するときに知っておきたいこと
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| 過去の健診結果や検査データを準備 | 経年変化を追うことで正確な診断や治療方針の決定がしやすい |
| 飲酒量や食生活を記録 | 問診で医師に正確な情報を伝えると原因の特定に役立つ |
| 内服中の薬やサプリメントを把握 | 相互作用の有無や治療上の調整が必要か確認できる |
| かかりつけ医がいれば相談 | 専門医への紹介などスムーズな治療連携が期待できる |
治療のステップ
- 原因の特定: アルコール性か非アルコール性か、または両方の要因があるのかを確かめる。
- 生活習慣の改善指導: 食事・運動・飲酒制限に関するアドバイスを受け、具体的な目標を設定する。
- 薬物療法の検討: 状態や合併症の有無に応じて医師が薬を処方する。
- 定期的な検査と経過観察: 血液検査や画像検査を定期的に行い、効果や病態の進行度をチェックする。
放置した場合のリスクと注意点
脂肪肝を放置すると肝炎や肝硬変、さらには肝がんへの進行だけでなく、糖尿病や脂質異常症、高血圧なども悪化しやすくなります。
合併症が重なると治療が複雑になり、クリニックの受診間隔が短くなるなど、心身・経済的にも大きな負担になるので、異常が見つかった場合は早期受診を心がけ、医師の指示のもと改善を進めていきましょう。
脂肪肝に負けないための生活の工夫とサポート
日常生活のちょっとした工夫によって、脂肪肝のリスクを下げたり、進行を抑えたりすることが期待できます。さらに必要に応じて、医師や管理栄養士、運動指導士など専門家のサポートを受けると効果的です。
日常で気をつけたい生活習慣
- 食べるタイミング: 夜遅い時間の食事は脂質蓄積を促しやすい
- アルコール以外の飲み物を意識: アルコールを避け、水やお茶など糖分を含まない飲み物を飲む
- ストレスケア: ストレスが過度になると食事が乱れやすくなり、飲酒量も増える傾向がある
- 睡眠の質: 睡眠不足はホルモンバランスを乱し、体重増加や血糖値の上昇につながる
脂肪肝の予防や改善に役立つ実践的なアイデア
| 習慣・アイデア | 効果・ポイント |
|---|---|
| 朝に軽い体操や散歩 | 血行を促進し、基礎代謝を上げる。朝日を浴びることで体内リズムも整う |
| 間食をフルーツやナッツに切り替える | 過剰な糖質や脂質を摂りにくくし、ビタミンや食物繊維を補給できる |
| 食事は野菜から食べ始める | 血糖値の急上昇を抑え、肥満リスクや中性脂肪の上昇を防ぎやすい |
| エレベーターよりも階段を利用 | 日常生活の中で運動量を増やし、エネルギー消費をアップする |
| 週末の買い物や外出は歩く距離を少し意識して増やす | 有酸素運動の時間を無理なく確保し、身体機能を維持・向上させる |
サポートを受けるメリット
自分で生活習慣を見直すことが難しい人や、すでに肥満や糖尿病などの生活習慣病がある人は、医療機関でのサポートを受けると効率的に改善を図れます。
管理栄養士が栄養指導を行うところもあれば、医師の指示のもとでトレーニングメニューを組んでくれるフィットネスプログラムを紹介してくれるクリニックもあります。
定期的にフォローアップすることでモチベーションを維持しながら、的確に軌道修正を図ることが可能です。
脂肪肝で受診が考えられる診療科
- 内科(一般内科・消化器内科)
- 糖尿病内科(糖尿病やメタボリックシンドロームがある場合)
- 肝臓専門外来(肝機能障害やMASHの疑いがある場合)
受診後の継続的なフォロー
治療方針を立てて終わりではなく、定期検査やカウンセリングで経過を確認し、必要に応じて方針を変えていくことが大切で、アルコール性脂肪肝で飲酒習慣のある人は、断酒や節酒を継続できるよう心理的サポートも受けると効果的です。
まとめ
脂肪肝は、飲酒、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病の存在や、食事・運動の習慣の乱れによって、肝臓に中性脂肪が蓄積することで発症します。
進行すると肝炎、肝硬変、肝がんへと至るリスクがあるため、健診で指摘を受けた場合や血液検査の結果に異常が見られた場合は早めに医師に相談することが必要です。
症状がなくとも放置せず、セルフケアの意識を持ちながら内科や消化器内科を受診し、正確な診断と適切な治療を受けてください。
食事のバランスや運動の取り入れ方を見直し、アルコールを含めた生活習慣を改善するだけでも、脂肪肝の進行を抑える効果が期待できます。
参考文献
Okanoue T, Umemura A, Yasui K, Itoh Y. Nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2011 Jan;26:153-62.
Kojima SI, Watanabe N, Numata M, Ogawa T, Matsuzaki S. Increase in the prevalence of fatty liver in Japan over the past 12 years: analysis of clinical background. Journal of gastroenterology. 2003 Oct;38:954-61.
NOMURA H, KASHIWAGI S, HAYASHI J, KAJIYAMA W, TANI S, GOTO M. Prevalence of fatty liver in a general population of Okinawa, Japan. Japanese journal of medicine. 1988;27(2):142-9.
Eguchi Y, Hyogo H, Ono M, Mizuta T, Ono N, Fujimoto K, Chayama K, Saibara T, JSG-NAFLD. Prevalence and associated metabolic factors of nonalcoholic fatty liver disease in the general population from 2009 to 2010 in Japan: a multicenter large retrospective study. Journal of gastroenterology. 2012 May;47:586-95.
Kamada Y, Takahashi H, Shimizu M, Kawaguchi T, Sumida Y, Fujii H, Seko Y, Fukunishi S, Tokushige K, Nakajima A, Okanoue T. Clinical practice advice on lifestyle modification in the management of nonalcoholic fatty liver disease in Japan: an expert review. Journal of Gastroenterology. 2021 Dec 1:1-7.
Hashimoto E, Yatsuji S, Kaneda H, Yoshioka Y, Taniai M, Tokushige K, Shiratori K. The characteristics and natural history of Japanese patients with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology Research. 2005 Oct 1;33(2):72-6.
Tobari M, Hashimoto E. Characteristic features of nonalcoholic fatty liver disease in Japan with a focus on the roles of age, sex and body mass index. Gut and liver. 2020 Sep 9;14(5):537.
Omagari K, Kadokawa Y, Masuda JI, Egawa I, Sawa T, Hazama H, Ohba K, Isomoto H, Mizuta Y, Hayashida K, Murase K. Fatty liver in non‐alcoholic non‐overweight Japanese adults: incidence and clinical characteristics. Journal of gastroenterology and hepatology. 2002 Oct;17(10):1098-105.
Sumida Y, Yoneda M, Hyogo H, Itoh Y, Ono M, Fujii H, Eguchi Y, Suzuki Y, Aoki N, Kanemasa K, Fujita K. Validation of the FIB4 index in a Japanese nonalcoholic fatty liver disease population. BMC gastroenterology. 2012 Dec;12:1-9.
Okushin K, Takahashi Y, Yamamichi N, Shimamoto T, Enooku K, Fujinaga H, Tsutsumi T, Shintani Y, Sakaguchi Y, Ono S, Kodashima S. Helicobacter pylori infection is not associated with fatty liver disease including non-alcoholic fatty liver disease: a large-scale cross-sectional study in Japan. BMC gastroenterology. 2015 Dec;15:1-0.