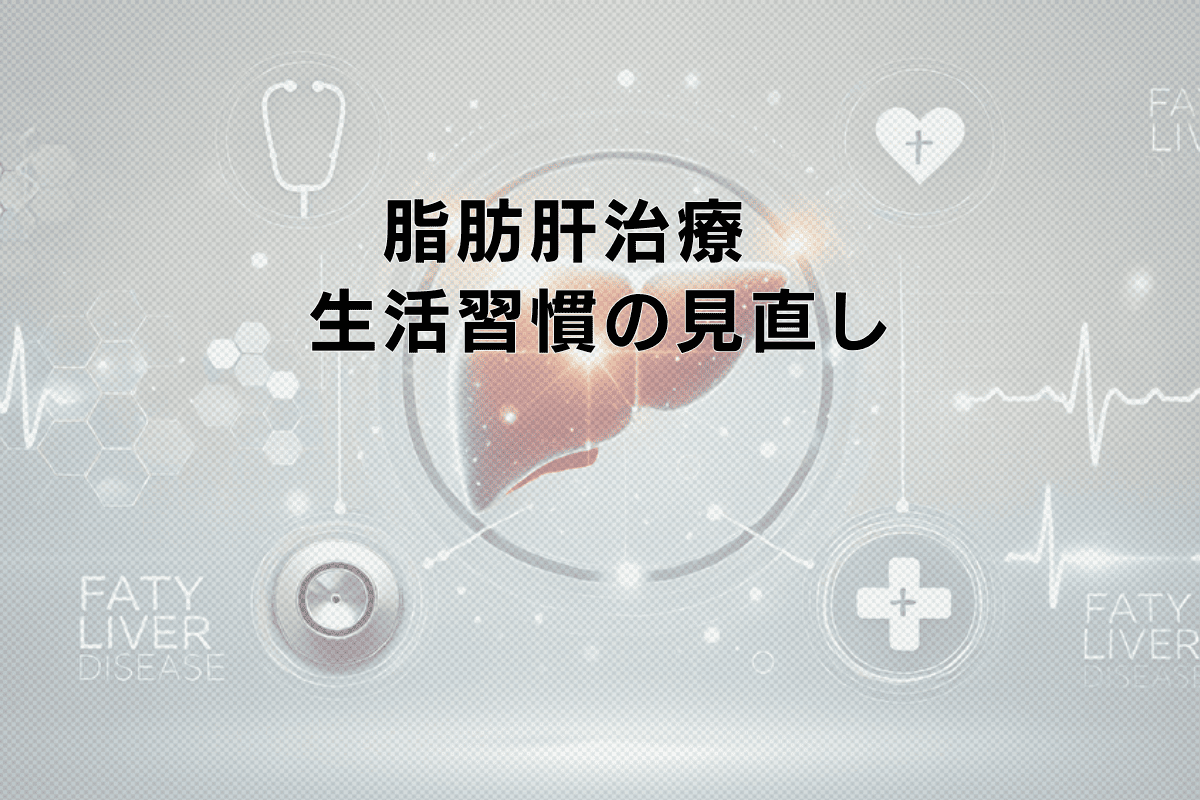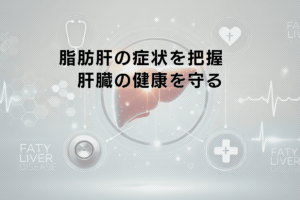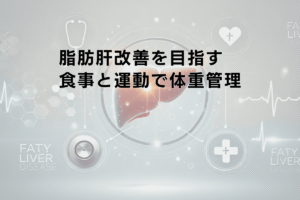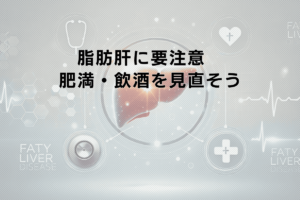脂肪肝は、肝臓に脂肪が過剰にたまる状態で、放置するとさまざまな肝機能障害や合併症につながるおそれがあります。
軽度であっても油断は禁物であり、早期から食事や運動、薬物治療を視野に入れた総合的なアプローチが大切です。治療を行う際は、医師と連携しながら定期的に肝臓の状態を検査し、必要に応じて方針を調整することが効果的です。
悪化すると肝硬変や肝がんに至る可能性もあるため、予防と治療を意識して取り組んでいく必要があります。
脂肪肝とは何か
脂肪肝は、肝臓に脂肪が多く蓄積した状態を意味し、特に代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)やアルコール性脂肪肝として分類されるケースが一般的です。
肝臓は体内で大切な代謝や解毒を担う器官であり、この部位に過剰な脂肪がたまると、肝機能の低下や慢性的な炎症が起こり、将来的にさまざまな病気を引き起こす原因となります。
アルコール性脂肪肝と代謝機能障害関連脂肪性肝疾患の違い
アルコール性脂肪肝は飲酒量が多い方によく見られ、長期にわたる多量飲酒が肝臓に負荷をかけ、肝細胞への脂肪蓄積を促進することが特徴です。
一方、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)は生活習慣の乱れや肥満、糖尿病などに伴って起こり、アルコール摂取量がそれほど多くないにもかかわらず脂肪肝になるケースを指します。
脂肪肝の原因と背景
脂肪肝に至る原因としては、食事の過剰摂取や運動不足が代表的であり、特に糖質や脂質の摂りすぎによって体重が増加すると肝臓への脂肪の蓄積が加速します。
また、肥満やメタボリックシンドロームを抱えている人ほど脂肪肝を発症しやすい傾向があります。
遺伝的要素や性別・年齢の影響もあり、女性より男性が多いとは限らず、女性でも閉経後にホルモンバランスの影響で脂肪肝を発症するケースもあるため注意が必要です。
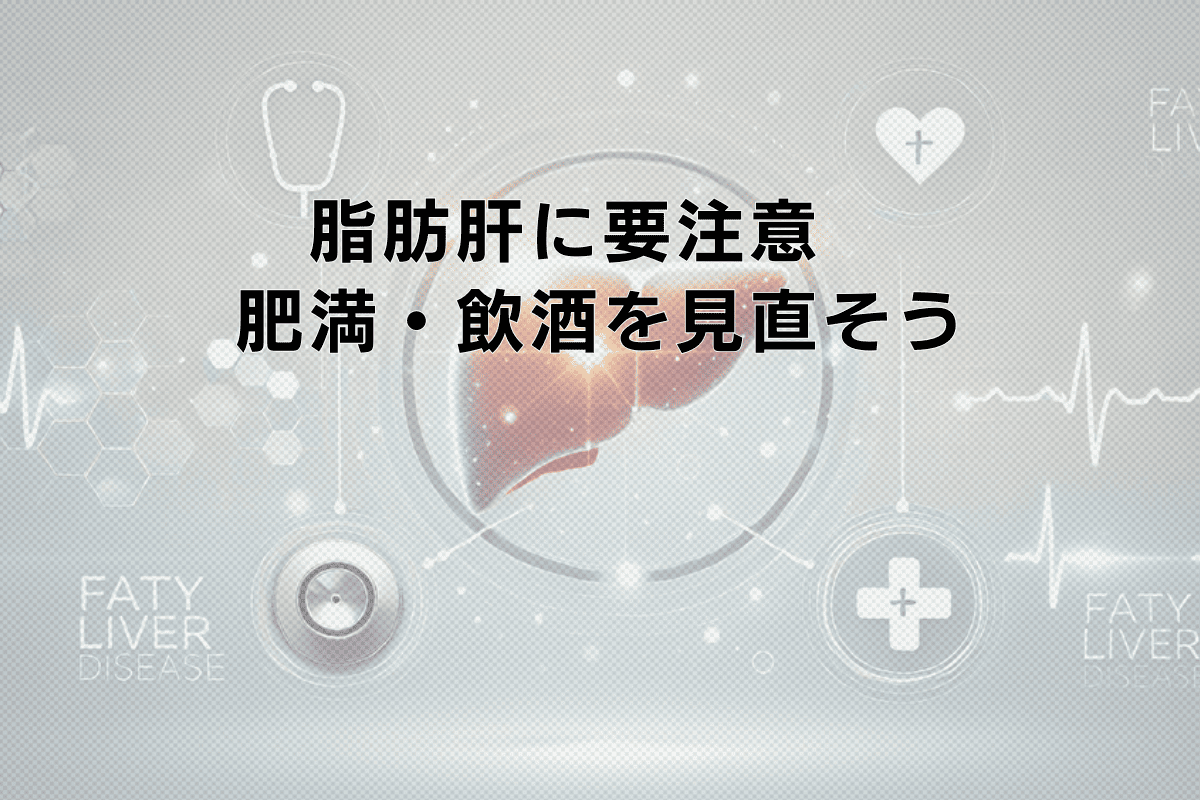
脂肪肝の診断と検査方法
脂肪肝の診断では、腹部エコー検査や血液検査(肝機能の数値や中性脂肪、コレステロール値など)を行い、必要に応じてCTやMRIなどの画像検査やフィブロスキャンで肝臓の状態を詳しく調べます。
検査結果を医師が総合的に判断し、脂肪肝かどうかを診断します。腹部エコー検査やフィブロスキャンは患者さんの負担が少なく、肝臓の脂肪蓄積を簡易的に確認できる点が特徴です。
進行すると起こる合併症
脂肪肝が長期間にわたり持続すると肝臓の炎症が進み、代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)に移行する場合があり、MASHになると肝細胞の障害がさらに進行し、やがて肝硬変や肝がんにつながるリスクが高まります。
また、脂肪肝は2型糖尿病や高血圧、脂質異常症などの代謝性疾患とも関連が深く、これらの合併症を予防する観点からも早期の治療が重視されます。
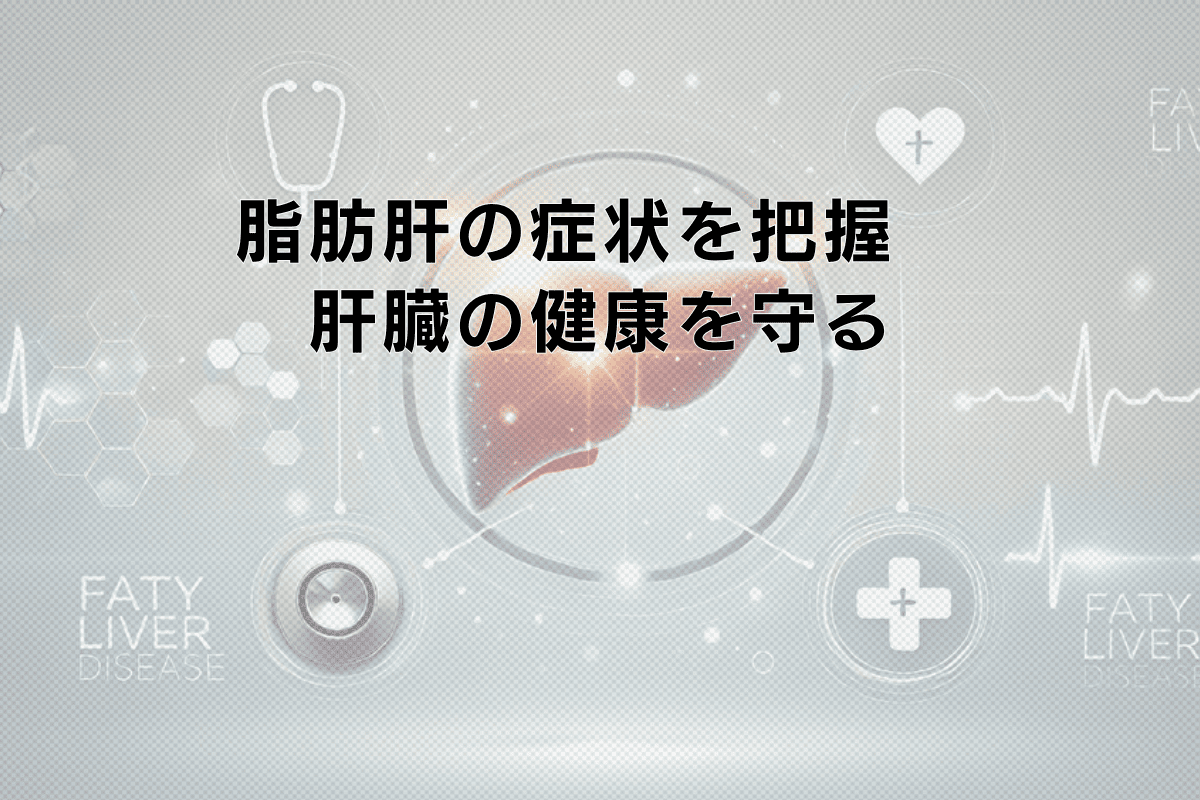
脂肪肝治療の目的と基本方針
脂肪肝の治療を行う意義は、肝機能の正常化をめざすだけでなく、肝臓以外の合併症を防いだり、将来的な肝硬変や肝がんのリスクを下げたりするところにあります。
医師の診察のもとで、個々の患者さんの状態やライフスタイルに合わせた目標を設定し、必要に応じて薬物療法や栄養指導、運動療法などを組み合わせることが有効です。
体重管理と生活習慣の改善
過剰体重や肥満が原因で脂肪肝を発症した場合、適度なカロリー制限や糖質制限、脂質のコントロールなどの食事療法が重要です。
あわせてウォーキングやジョギングなどの有酸素運動、筋力トレーニングを取り入れ、体脂肪を適正範囲に近づける努力が必要です。肥満を合併している場合、体重の7%程度の減量が肝組織(脂肪化、炎症、線維化)の改善に有効と報告されています。
無理なダイエットよりも、長期的に継続可能な健康的な生活習慣が望ましいです。
薬物療法の活用
脂肪肝治療では、糖尿病の合併がある場合には血糖コントロールを改善する薬物を使用したり、高脂血症を合併している場合には脂質異常症の薬を活用したりすることがあります。
直接的に脂肪肝の改善を狙う薬物も研究されていますが、現段階では特定の薬にのみ頼るより、複数の要素(食事・運動・投薬)を組み合わせるほうが効果的です。
アルコール量の制限
アルコール性脂肪肝であれば当然ながら飲酒量を大幅に減らすか、中止する必要があり、MAFLDであっても、過度のアルコール摂取は肝臓への負担を増やすため控えることが基本的な方針です。
飲み会や趣味の晩酌などで完全にアルコールを絶つのが難しいと感じる場合は、医師と相談しながら少しずつ制限していく方法を検討してください。
目標達成までの道のり
脂肪肝治療は、症状が軽度であっても数カ月以上の時間をかけて取り組むことが大切であり、短期間で劇的な改善を期待するのは難しい場合が多いです。
持続的な努力を重ねることで、肝機能の数値や腹部エコーの所見が改善し、炎症が落ち着いてくるケースも少なくありません。
脂肪肝治療のステップと検査
脂肪肝治療を進めるうえで、医療機関での定期検査や評価が欠かせないポイントです。初回の診察で肝臓の状態を評価し、その後は数カ月ごとに血液検査や画像検査で進捗を確認しながら治療方針を修正していきます。
血液検査の活用
血液検査ではAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの肝機能に関連する数値や、中性脂肪、LDLコレステロール、空腹時血糖などを調べます。これらの数値から肝炎や脂質代謝異常、糖尿病の有無を確認し、状態の変化を客観的に追跡できます。
主な血液検査項目と意味
| 項目 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| AST(GOT) | 肝細胞の障害を示す酵素 | 肝細胞が傷つくと血中へ流出する |
| ALT(GPT) | ASTと並んで肝障害を表す酵素 | ALTのほうが肝特異性が高い |
| γ-GTP | 肝胆道系の障害や飲酒量と関係 | 酒量が多いと高くなりやすい |
| 中性脂肪 | 血液中の脂肪の一種 | 脂質異常症や肥満と関係が深い |
| LDLコレステロール | 動脈硬化に関連し「悪玉コレステロール」と呼ばれる | 生活習慣で増えやすく心血管リスクも高まる |
| 血糖 | 糖尿病や代謝異常の有無を確認 | 脂肪肝と糖尿病は相互に悪影響を及ぼす |
画像検査による評価
腹部エコー、CT、MRIなどを用いると、肝臓に蓄積した脂肪の程度や炎症の有無を確認でき、腹部エコー検査は外来でも簡便に行えるため、定期的な状態把握には有効です。
ただし、エコーで詳細な定量評価が難しい場合はCTやMRI、FibroScan®などを活用し、必要に応じてさらに精密な評価を受けることもあります。
治療効果の判定
定期的に検査を受けることで、血液検査や画像検査の結果に変化が出ているかどうかをチェックします。
たとえばALTやASTの数値が改善し、腹部エコー、FibroScan®でも脂肪蓄積の減少が確認できれば、食事療法や運動療法がうまく機能している可能性が高いです。
一定期間たっても改善が見られない場合は、食事内容や運動の頻度、薬の種類などを見直す必要があります。
専門医との連携
脂肪肝治療を続けるうえで、消化器内科の医師や管理栄養士の助言が重要です。定期的な受診で、血液検査や画像検査の結果を評価し、次の方針を決定します。
また、脂肪肝以外の消化器疾患が疑われる場合や、すでに何らかの合併症を抱えている場合は、さらに専門的な検査や治療が必要になることも考えられます。
食事療法と生活習慣の見直し
脂肪肝治療では、食事のコントロールと生活習慣の改善が中心です。摂取カロリーの過多を抑え、過剰な脂質や糖質をバランスよく調整することで、体重や肝機能への負担を軽減できます。
食事のポイントと注意点
栄養バランスを整えることが基本であり、特に以下の点を意識すると取り組みやすいです。
- 過剰な糖質(特に精製された糖質)を控える
- 揚げ物や脂身の多い肉などの摂取を減らす
- 野菜や果物、食物繊維の豊富な食材を積極的に取り入れる
- 良質なたんぱく質(魚、大豆製品、鶏肉など)を適度に摂取する
- 外食や惣菜では塩分や脂質が多くなりやすいためメニュー選びに気をつける
食材の分類とおすすめ
| カテゴリ | 具体的な食材 | 特徴 |
|---|---|---|
| 野菜・果物 | キャベツ、ブロッコリー、りんごなど | 食物繊維やビタミンが豊富 |
| 良質なたんぱく質 | 魚(鮭、さばなど)、鶏肉、豆腐など | 肝臓の修復や代謝を助ける |
| 穀物・炭水化物 | 玄米、全粒粉パン、オートミールなど | 血糖値の急上昇を抑える |
| 脂質 | オリーブオイル、アボカド | 不飽和脂肪酸を多く含む |
| 乳製品 | ヨーグルト、低脂肪牛乳 | 腸内環境を整えやすい |
運動療法の重要性
食事療法だけで体重や脂肪量をコントロールしきれない場合は、運動療法も積極的に取り入れると効果が期待しやすいです。
有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、自転車など)はエネルギー消費を増やし、脂肪を燃焼させる助けになります。あわせて筋トレを行うことで基礎代謝が上がり、長期的に体脂肪を減らすことができます。
週に3~5日程度の運動習慣を目標にすると継続しやすいです。
ストレスとの関係
ストレスがたまると、過食やアルコール摂取が増えるなどして、生活習慣の乱れを引き起こす可能性があり、さらにホルモンバランスの変化や免疫力の低下を通じ、肝機能への悪影響が生じることも考えられます。
運動や趣味、十分な睡眠時間の確保などを意識して、ストレスを発散できる方法を見つけておくことが望ましいです。
長期的な取り組み
ダイエットや運動は「一時的にがんばれば良い」というものではなく、できるだけ生活の一部として習慣化する意識が肝要です。
急激にやせようとして無理をすると、リバウンドで体重が戻ってしまったり、体調を崩してしまったりするおそれもあり、緩やかでも、継続的に体重を減らしていくアプローチが理想的です。
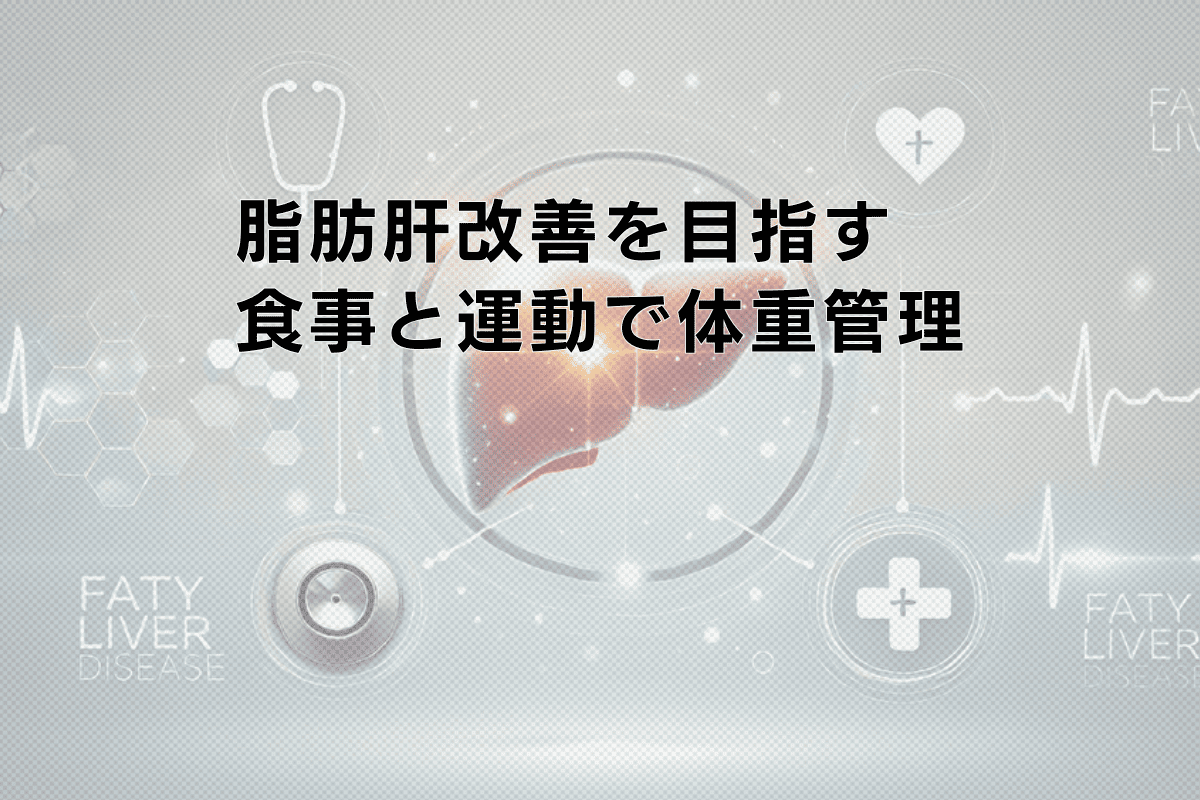
薬物療法やサプリメントの活用
脂肪肝治療において、薬物療法は副次的な位置づけとされることが多いですが、特定の状態では有効です。
また、栄養素や漢方薬を利用したサプリメントについても、医師と相談して適切に取り入れることで生活習慣の改善を後押しする場合があります。
血糖コントロールや脂質異常症への薬
糖尿病を合併している方は血糖値を改善する薬を使うと肝臓への負担が軽減され、脂質異常症を合併している方はスタチン系薬などが効果を発揮しやすいです。
ただし、投薬による副作用もあるため、定期的に医師と相談して用量や種類を再評価することが大切になります。
肝保護作用を狙った薬やサプリメント
肝臓の働きをサポートする薬や成分として、ウルソデオキシコール酸やシリマリンなどが挙げられ、これらは肝細胞の修復や胆汁の流れを改善する働きが期待できます。
サプリメントの中にはビタミンEやオルニチン、タウリンなど、肝機能を補助する成分を含む商品もありますが、正しい情報に基づいて選び、医師や薬剤師と相談しながら利用してください。
肝保護作用をもつおもな成分
| 成分名 | 主な働き | 注意点 |
|---|---|---|
| ウルソデオキシコール酸 | 胆汁の流れを改善し、肝臓負担を減らす | 医師の指示に従い、定期的な検査が必要 |
| シリマリン | 肝細胞の修復・酸化ストレスの軽減 | 海外サプリも多く、品質確認が大切 |
| オルニチン | アンモニア解毒を助け、肝機能をサポート | 劇的な効果は期待しづらく補助的に活用 |
| タウリン | 抗酸化作用、血中コレステロール低下への寄与 | エネルギードリンクで過剰摂取に注意 |
| ビタミンE | 抗酸化作用 | 過度摂取は他のビタミンバランスを崩す恐れ |
漢方薬の検討
脂肪肝の治療では、体質改善や代謝向上を目的に漢方薬が利用される場合があり、たとえば、防風通聖散は肥満傾向の方に処方されることが多く、脂質代謝を促す作用が期待されます。
ただし、漢方薬にも副作用や相互作用があるため、自己判断で長期服用を続けるのではなく、必ず医療機関での診察や処方を受けたうえで活用することが望ましいです。
食事・運動との併用が大切
薬物療法やサプリメントに頼るだけでなく、基本的には食事の見直しや運動量の増加などの生活習慣改善を組み合わせることで、より効果を高められます。
薬やサプリを飲んでいるから大丈夫と安心して暴飲暴食に走ると、本来の目的が損なわれることを認識しておきましょう。
進行した脂肪肝の合併症と対策
脂肪肝が長く続くと、炎症を伴う代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)への移行、そして肝硬変、さらには肝がんのリスクが高まります。
代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)について
MASHは、MASLDの中でも炎症と肝細胞の障害が顕著な状態で、ALTやASTなどの肝機能数値がさらに上昇し、組織学的にも繊維化が進む傾向があります。
この段階になると、単なる食事療法と運動だけでは改善が難しくなる場合があり、より厳密なコントロールや専門的な治療を検討する必要が出てきます。
NASHの診断に活用する検査
| 検査項目 | 特徴 | 確認できる主な情報 |
|---|---|---|
| 腹部エコー | 脂肪蓄積の簡易チェック | 肝臓の形状や脂肪の入り方を視覚的に確認 |
| CT/MRI | 画像の解像度が高く、脂肪量をより正確に評価 | 肝臓内部の詳細な構造や炎症を推定 |
| FibroScan(超音波弾性検査) | 肝臓の硬さ(繊維化の度合い)を数値化 | 肝硬変に至る手前の状態を把握しやすい |
| 血液検査(FibroTestなど) | NASH特有のマーカーや線維化の指標を確認 | 血液から肝臓の繊維化を間接的に評価 |
肝硬変・肝がん
MASHがさらに進行すると、肝硬変へと至ります。肝硬変になった肝臓は線維化が高度に進み、元の機能を回復するのが非常に困難な状態です。
さらに肝硬変の患者さんは肝がんを発症するリスクが高くなるため、定期的な画像検査(エコーやCT、MRIなど)を行い、早期発見に努めることが大切です。
他の生活習慣病や心血管リスク
脂肪肝を抱えている方の多くが肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を併発しています。
これらの疾患は動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの重篤な病気の引き金にもなるため、体重管理や血圧、血糖値、血中脂質のコントロールが求められます。
専門医療機関との連携
脂肪肝が進行し、MASHや肝硬変が疑われる場合は、消化器内科や肝臓内科など専門医が在籍するクリニックや総合病院への受診が推奨されます。
専門医と相談しながら治療方針を決定し、必要なら早めの段階で高度医療に移行することで、予後を改善できる可能性があります。
定期受診と治療継続のコツ
脂肪肝治療は一時的な対処でなく、生活そのものを見直す長期的な取り組みがポイントです。モチベーションを保ちながら治療を継続するには、定期的な受診や医師、栄養士からのフォローアップが大きな助けとなります。
定期検査のスケジュール
治療初期には1~3カ月ごとに血液検査や腹部エコー検査を行い、肝機能や体重変化を追っていき、状態が安定してきたら、医師の判断に応じて検査間隔を少しずつ伸ばすことが考えられます。
ただし、日常生活の改善がうまくいっていない場合や血液検査の結果が思わしくない場合は、スケジュールを短くするなどの対応が必要です。
モチベーションを保つ方法
- 小さな目標を設定し、達成するたびに自分をほめる
- 家族や友人と一緒に運動したり、食事の見直しをしたりする
- 体重や血圧、肝機能数値の変化を記録して可視化する
- 医師や看護師、管理栄養士との相談を定期的に行う
続けやすい運動種類と目安
| 運動の種類 | 内容 | 週間目安 |
|---|---|---|
| ウォーキング | 30分程度、軽いスピードで行う | 週3~5回(合計150分以上) |
| ジョギング | 息が切れない程度のペース | 週2~3回 |
| 筋力トレーニング | スクワットや軽いダンベル運動 | 週2~3回 |
| スイミング | 自分のペースで泳ぐ | 週1~2回 |
クリニックでのサポート
継続が難しいと感じる場合は、クリニックが提供する栄養指導や健康教室を活用すると良いでしょう。
管理栄養士から食事メニューの提案を受けたり、運動専門スタッフから効果的なトレーニング方法を教えてもらったりすることで、無理なく日常生活を改善できます。
脂肪肝Q&A
脂肪肝治療に関して、よく寄せられる疑問や質問をまとめました。いざ治療を始めようと思っても、困ったり迷ったりする場合は少なくありません。わからない点はクリニックや医師に確認しながら進めると安心です。
Q1. 痩せていても脂肪肝になるのか
体格がやせ型であっても、食生活の乱れや糖質の過剰摂取、運動不足などによって脂肪肝になるケースはあります。また、過度なダイエットによる栄養失調や急激な体重減少で脂肪の代謝が滞り、肝臓に負担をかけることもあり得ます。
Q2. 脂肪肝は改善すると再発しないのか
一度改善に成功しても、生活習慣が元に戻れば再び脂肪肝を発症する可能性があります。定期的な検査で肝臓の状態を確認し、食事や運動を継続的に意識することで再発リスクを抑えることが大切です。
Q3. サプリや漢方薬だけで治療できるのか
サプリメントや漢方薬はあくまで補助的な手段です。基本的には食事療法や運動療法を柱とし、必要に応じて薬物療法を併用するアプローチが求められます。サプリの選び方や使用量は専門家のアドバイスを受けて決めるようにしましょう。
Q4. 痛みや倦怠感などの自覚症状はあるのか
脂肪肝は初期に自覚症状が出ないことが多く、定期健診や血液検査で初めてわかるケースが多々あります。
逆に症状が出るほど進行した場合は、肝炎や肝硬変など深刻な状態に達しているおそれがあるため、症状の有無にかかわらず定期的な受診が望ましいです。
まとめと治療継続へのメッセージ
脂肪肝治療は、肝硬変や肝がんなどの重篤な合併症を防ぎ、健康的な生活を続けるためにも欠かせない取り組みです。
食事や運動といった生活習慣の見直しはもちろん、定期的な検査や医師による診察が治療成功の要となります。
自分に合ったペースや方法で体重管理や運動習慣を実践し、必要に応じて薬物療法やサプリメントを活用することが大切です。
何よりも、長期的に継続しながら少しずつ改善を重ねる姿勢が、脂肪肝の克服や肝機能の維持に大きく貢献します。
参考文献
Paternostro R, Trauner M. Current treatment of non‐alcoholic fatty liver disease. Journal of internal medicine. 2022 Aug;292(2):190-204.
Angulo P, Lindor KD. Treatment of nonalcoholic fatty liver: present and emerging therapies. InSeminars in liver disease 2001 (Vol. 21, No. 01, pp. 081-088). Copyright© 2001 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA. Tel.:+ 1 (212) 584-4662.
Ahmed MH, Byrne CD. Current treatment of non‐alcoholic fatty liver disease. Diabetes, Obesity and metabolism. 2009 Mar;11(3):188-95.
Torres DM, Williams CD, Harrison SA. Features, diagnosis, and treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2012 Aug 1;10(8):837-58.
Musso G, Gambino R, Cassader M, Pagano G. A meta‐analysis of randomized trials for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2010 Jul;52(1):79-104.
Rong L, Zou J, Ran W, Qi X, Chen Y, Cui H, Guo J. Advancements in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Frontiers in endocrinology. 2023 Jan 16;13:1087260.
Angulo P. Treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Annals of hepatology. 2002;1(1):12-9.
Oh MK, Winn J, Poordad F. diagnosis and treatment of non‐alcoholic fatty liver disease. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2008 Sep;28(5):503-22.
Adams LA, Angulo P. Treatment of non-alcoholic fatty liver disease. Postgraduate medical journal. 2006 May;82(967):315-22.
Siebler J, Galle PR. Treatment of nonalcoholic fatty liver disease. World journal of gastroenterology: WJG. 2006 Apr 4;12(14):2161.