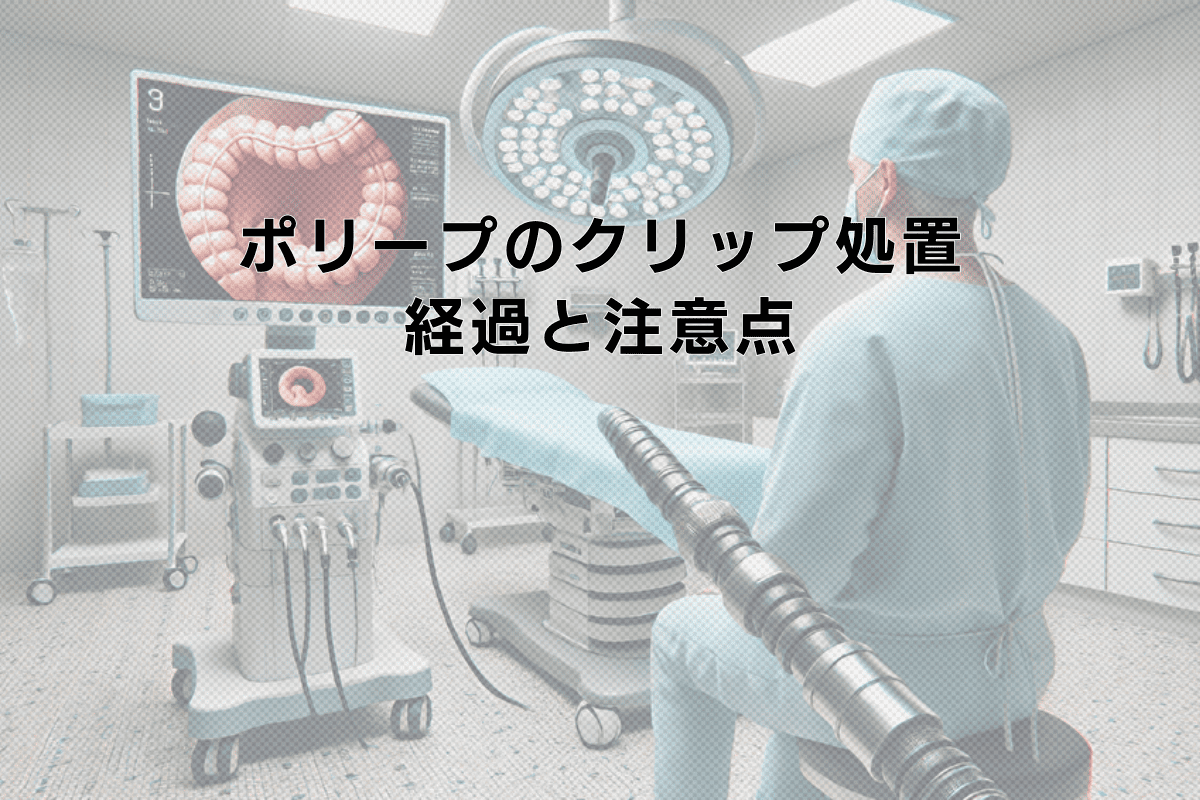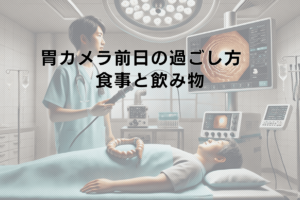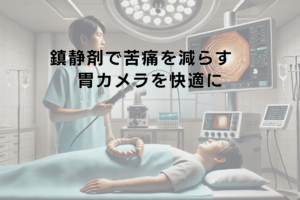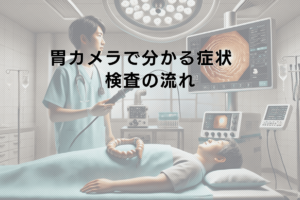大腸内視鏡検査(大腸カメラ)でポリープを切除した際に、出血を予防する目的で金属製のクリップを使用することがあり、安全性を高めるためにとても重要です。
しかし、処置を受けた方の中には、このクリップがいつ取れるのか、あるいは体内に残ってしまわないかと不安に感じる方もいるでしょう。
この記事では、大腸ポリープ切除後に用いるクリップの基本的な役割から、自然に排出されるまでの期間、体内に残る可能性と安全性について詳しく解説します。
あわせて、クリップ処置後の食事や運動といった日常生活で気をつけるべき点や、万が一の異常に早く気づくためのポイントも紹介します。
大腸ポリープ切除で使うクリップの基本的な役割
大腸ポリープの切除は、将来のがん化を防ぐために重要な処置です。切除方法にはいくつか種類がありますが、出血リスクを最小限に抑えるために、クリップが大きな役割を果たします。
クリップが必要となる理由
大腸の壁(粘膜)は、たくさんの血管が通っているため、ポリープを切除すると傷口から出血しやすいです。
ポリープの根元が太い場合や、血流が豊富な場所にあるポリープ、1センチを超えるような比較的大きなポリープを切除した際には、出血のリスクが高まります。
また、大腸の右側(盲腸や上行結腸)は壁が薄いため、より慎重な止血処置が求められ、処置中の出血はもちろん、処置から数日経ってから起こる後出血(こうしゅっけつ)という合併症を防ぐことが、安全な治療を行う上でとても大切です。
クリップは、後出血の予防を主な目的として使用し、医師は、ポリープを切除した後の傷口の状態や、ポリープの大きさ、部位などを総合的に判断し、クリップの使用を決定します。
クリップによる止血の仕組み
クリップは、小さな洗濯ばさみのような形状をしており、内視鏡の先端から出して操作します。医師はモニター画面で詳細に観察しながら、ポリープを切除した傷口を正確に狙い、クリップで粘膜を挟み込みます。
傷口を両側からしっかりと寄せて閉じることで、出血している血管を圧迫し、物理的に止血し、機械的な圧迫により、傷口が安定し、かさぶたが作られて治癒が進むまでの時間を安全に確保できます。
通常、一つの傷口に対して1個から数個のクリップを使用しますが、傷の大きさや部位、出血のリスクによっては、さらに多くのクリップを用いることもあります。
この処置は、外科手術で用いる縫合糸の代わりとなる、内視鏡治療における重要な技術です。
クリップ留置後の創傷治癒過程
| 期間 | 傷口の状態 | クリップの役割 |
|---|---|---|
| 処置直後 | 切除による傷があり、出血リスクが高い状態 | 傷口を閉鎖し、血管を圧迫して止血する |
| 処置後1日~3日 | 傷口の表面が少しずつ治り始める(上皮化) | 後出血を防ぎ、傷口を物理的に保護する |
| 処置後1週間前後 | 粘膜が再生し、傷がほぼ治癒した状態 | 役割を終え、自然に脱落し始める |
クリップの材質と安全性
治療で用いるクリップは、体内で使用してもアレルギー反応などが起こりにくい、安全性の高い材質で作られていて、主にチタン合金やステンレス鋼が使用されています。
このような金属は、長年の医療現場での使用実績があり、生体適合性(体によく馴染む性質)が高く、また、MRIなどの画像検査に影響を与えにくい材質が選ばれることがほとんどです。
クリップが一時的に体内にあること自体が、健康上の問題を起こすことはまずなく、処置後は体にとって異物となりますが、傷が治れば自然に体外へ排出されるように設計されているため、安心して治療を受けることができます。
クリップはいつどのように体外へ排出されるのか
処置後に留置されたクリップは、永続的に体内にとどまるものではありません。傷が治癒する過程で、役割を終えたクリップは自然に外れて、便と一緒に体外へ排出されます。
クリップが自然に脱落する仕組み
クリップは、大腸の粘膜を挟んで傷口を閉じていて、ポリープを切除した傷は、体の自然な治癒力によって、少しずつ新しい粘膜で覆われていきます。粘膜の再生(上皮化)が進むにつれて、傷口は完全に塞がります。
傷がしっかりと治ると、クリップは粘膜を掴んでいる必要がなくなり、挟む力が徐々に弱まっていき、最終的には、腸が内容物を先に送るためのぜん動運動による物理的な刺激なども加わり、粘膜から自然に外れます。
脱落したクリップは、食べ物の残りかすなどと同じように腸内を移動し、便に混ざって肛門から排出されます。
排出されるまでの一般的な期間
クリップが脱落して排出されるまでの期間には個人差がありますが、一般的には処置後1週間から2週間程度が目安です。早い方では数日で、長い方では1ヶ月近くかかることもあります。
この期間の差は、クリップで留めた傷の深さ、個人の治癒能力、腸の動きの活発さなど、さまざまな要因によって変わり、便秘傾向の方は腸の動きが緩やかなため排出が遅れることがあり、下痢傾向の方は早まることもあります。
ただし、あくまで傾向であり、特に心配する必要はなく、自然な生理現象の一部として捉えることが大切です。医師から指示がない限り、クリップがいつ取れるかを過度に気にする必要はありません。
クリップ脱落期間に影響を与える要因
| 要因 | 内容 | 期間への影響 |
|---|---|---|
| 個人の治癒能力 | 傷の治りが早いか遅いか | 治りが早いと脱落も早い傾向にある |
| ポリープの大きさ・部位 | 切除したポリープのサイズや場所 | 傷が大きいと治癒に時間がかかり、脱落が遅くなることがある |
| 腸のぜん動運動 | 腸の動きの活発さや便通の状態 | 動きが活発な場合は、物理的な刺激で早く脱落することがある |
排出されたクリップの確認は必要か
排出されたクリップを、ご自身の目で確認する必要は全くありません。クリップは非常に小さく、大きさは数ミリ程度なので、便の中に混ざっていても気づかないことがほとんどです。
無理に便の中を探すことは衛生的ではありませんし、見つからないことでかえって不安を増大させることにもなりかねません。
クリップが排出されたかどうかを確認することよりも、処置後のご自身の体調変化、特に腹痛や血便の有無に注意を払うことの方がはるかに重要です。
もし体調に異常を感じた場合は、クリップの排出を確認するのではなく、速やかに医療機関に相談してください。
クリップが体内に残り続ける可能性と安全性
多くの場合、クリップは自然に排出されますが、ごくまれに長期間体内に残り続けるケースも報告されています。ここでは、クリップが残る可能性や、その場合の安全性、どのような時に受診を検討すべきかについて解説します。
クリップがまれに長期間残る理由
クリップが想定よりも長く体内にとどまる理由として、いくつかの可能性が考えられます。一つは、クリップが粘膜を深く強力に掴んでいる場合で、この状態だと、傷が治癒してもなかなか外れません。
また、傷の治癒過程で、再生した粘膜がクリップを覆いかぶさるように治ってしまうこと(埋没)も、まれにあり、この場合、クリップは粘膜の下に埋もれた状態です。
大腸の壁には、ひだや憩室(けいしつ)と呼ばれる小さなくぼみがあり、そうした場所に脱落したクリップが引っかかることで、排出されにくくなるケースもあります。
ただし、これらは非常にまれなケースであり、ほとんどのクリップは問題なく排出されます。
体内に残ったクリップの安全性
もしクリップが長期間体内に残ったとしても、健康上の問題を起こすことはほとんどありません。クリップは生体適合性の高い材質で作られているため、体内で炎症を起こしたり、アレルギーの原因になったりする危険性は極めて低いです。
粘膜に埋没した場合でも、体はクリップを異物として認識しつつも、その周囲を安定した組織で覆うため、問題となることはまずありません。
また、クリップがあることで、将来的に腸の動きが悪くなる、腸閉塞の原因になるといった心配もまず不要です。多くの場合、無症状のまま経過し、何かの機会で内視鏡検査やCTなどの画像検査を行った際に、偶然発見される程度です。
MRIなどの画像検査への影響
医療用のクリップは、MRI検査で強い磁力に引かれたり、発熱したりしない非磁性または弱磁性の材質(チタン合金など)で作られているのが一般的で、クリップが体内に残っていても、MRI検査を受けることは可能です。
ただし、安全を期すために、検査を受ける際には、いつ頃、どの部位に大腸ポリープのクリップ処置を受けたかを、検査担当の医師や技師に申告してください。
クリップの材質と特徴
| 材質 | 特徴 | MRI検査への影響 |
|---|---|---|
| チタン合金 | 軽量で強度が高く、生体適合性に優れる。非磁性。 | ほとんど影響しない |
| ステンレス鋼 | 耐久性が高く、医療器具に広く使用される。弱磁性のものが多い。 | 種類によるが、多くは影響が少ないものが使われる |
長期間残っている場合の対応
クリップが残っていること自体は問題になりませんが、もし腹痛や違和感など、何らかの自覚症状が続く場合は、クリップ以外の原因も考えられるため、一度処置を受けた医療機関に相談することをお勧めします。
相談の結果、医師が必要と判断した場合には、内視鏡検査などで腸内の状態を確認することがあり、もしクリップが症状の原因となっている可能性が考えられれば、内視鏡を使って回収することもできます。
しかし、症状がなく、ただクリップが残っているというだけで、予防的に回収することは通常行いません。
クリップ処置後の日常生活における注意点
クリップで傷口を閉鎖しても、処置後の数日間はまだ不安定な状態です。日常生活の過ごし方によっては、後出血のリスクを高めてしまう可能性があり、食事、運動、入浴など、血圧や腹圧が上昇する行為には注意が必要です。
運動や仕事に関する制限
処置後、少なくとも1週間は、腹圧のかかる激しい運動は避けてください。
- ジョギング、マラソン
- 筋力トレーニング(腹筋、スクワットなど)
- ゴルフ、テニス、水泳
- その他、息が上がるようなスポーツ全般
腹圧のかかる激しい運動は、腹部に力がかかることで血圧が上昇し、傷口からの出血を誘発する可能性があります。重い物を持つ仕事や、長時間かがむ姿勢をとる農作業なども注意が必要です。
デスクワークや家事など、身体的な負担が少ない活動は、処置の翌日から再開しても問題ないことが多いですが、ご自身の体調と相談しながら無理のない範囲で行ってください。
長距離の移動や海外旅行(特に飛行機)も、気圧の変化や長時間同じ姿勢でいることが体に負担をかけるため、1週間程度は避けましょう。活動再開の具体的な時期については、医師の指示に従うことが最も安全です。
処置後の活動レベルの目安
| 期間 | 推奨される活動 | 避けるべき活動 |
|---|---|---|
| 当日~3日間 | 自宅での安静、近距離の歩行 | 運動全般、力仕事、長距離移動、入浴 |
| 4日~1週間 | デスクワーク、軽い家事、散歩 | 激しい運動、飲酒、旅行、サウナ |
| 1週間以降 | 徐々に通常の活動へ(医師の許可を得てから) | 体調に異変を感じたら活動を中止する |
入浴やシャワーについて
処置当日は、体を温めすぎると血行が良くなり、出血のリスクが高まるため、湯船には浸からず、軽いシャワー程度で済ませます。
翌日以降は体調に問題がなければ入浴も可能ですが、長湯や熱いお湯は避け、ぬるめのお湯で短時間にとどめましょう。サウナや岩盤浴など、体を極端に温める行為は、血圧を大きく変動させるため、少なくとも1週間は控えることが重要です。
体を洗う際も、腹部を強くこすることは避けてください。
飲酒と喫煙の影響
アルコールは血管を拡張することで血流を増加させ、治りかけている傷口から再び出血するリスクが高まるので、処置後1週間は禁酒を守ることがとても重要です。
ノンアルコール飲料であっても、炭酸が腸を刺激することがあるため、念のため控えましょう。また、喫煙は血管を収縮させて血流を悪化させ、傷の治りを遅らせる要因となります。
回復を順調に進めるためにも、この機会に禁煙や節煙を検討することも大切です。
食事で気をつけるべきことと具体的な食事内容
処置後の大腸は、傷がありデリケートな状態で、食事の内容によっては、腸に負担をかけてしまい、回復を妨げたり、出血の原因になったりすることがあります。消化が良く、腸を刺激しない食事を心がけることが、順調な回復への鍵です。
消化の良い食事の基本
基本は胃腸に優しく、消化しやすい食品を選ぶことで、食べ物はよく噛んで、ゆっくりと時間をかけて食べてください。
一度にたくさん食べると腸への負担が大きくなるため、腹八分目を心がけ、場合によっては食事の回数を増やして一回量を減らす工夫も有効です。
調理法としては、揚げる、炒めるといった油を多く使う方法は避け、煮る、蒸す、茹でるといった方法が適しています。香辛料の使用も控えめにしましょう。
消化に良い食品と避けるべき食品
| 分類 | 消化に良い食品(推奨) | 消化に悪い食品(避けるべき) |
|---|---|---|
| 炭水化物 | おかゆ、うどん、食パン、じゃがいも、豆腐 | 玄米、ラーメン、パスタ、菓子パン、さつまいも |
| タンパク質 | 鶏ささみ、鶏むね肉(皮なし)、白身魚、卵、はんぺん | 豚バラ肉、ソーセージ、ベーコン、貝類、豆類 |
| 野菜・果物 | 大根、かぶ、人参(加熱)、ほうれん草(加熱)、バナナ | きのこ類、ごぼう、海藻類、柑橘類、パイナップル |
避けるべき食べ物と飲み物
腸管を刺激する可能性のある食べ物は、回復を遅らせる原因となります。
控える必要がある食べ物
- 食物繊維の多い食品(きのこ、海藻、こんにゃく、ごぼう、豆類など)
- 脂肪分の多い食品(揚げ物、脂身の多い肉、生クリーム、バターなど)
- 香辛料などの刺激物(唐辛子、カレー粉、こしょう、わさび、ニンニクなど)
上記のような食品は、消化に時間がかかったり、腸内でガスを発生させたり、腸のぜん動運動を過剰に活発にさせたりして、傷口に負担をかけます。
飲み物では、アルコールの他に、コーヒーや濃い緑茶などのカフェインを多く含むものや、腸を刺激する炭酸飲料も、処置後しばらくは避けた方が安全です。
処置後の食事スケジュールの例
処置後の食事は、段階的に通常の食事に戻していくのが基本です。体の回復に合わせて、ゆっくりと食事の内容を変えていきましょう。
食事内容の段階的な進め方
| 期間 | 食事の形態 | 具体的なメニュー例 |
|---|---|---|
| 処置当日~翌日 | 水分、流動食 | 重湯、具なしのコンソメスープ、経口補水液 |
| 2日~3日目 | 消化の良い固形物 | 三分粥~全粥、素うどん、豆腐、白身魚の煮付け |
| 4日~1週間 | 通常の食事に近いが低脂肪・低刺激なもの | 軟らかいご飯、鶏ささみの蒸し物、加熱した野菜 |
医療機関へ相談する目安
大腸ポリープ切除後の合併症として最も注意すべきなのが、後出血と穿孔(せんこう:腸に穴が開くこと)で、まれな合併症ですが、万が一起こった場合には迅速な対応が必要です。
注意すべき腹痛のサイン
処置後、お腹が張るような軽い痛みや違和感は、腸内に残った空気などが原因で起こることがありますが、時間とともに改善することがほとんどです。ただし、下記のような腹痛は危険なサインである可能性があります。
- 我慢できないほどの強い痛み、突き刺すような鋭い痛み
- 時間が経つにつれてどんどん痛みが強くなる、痛みの範囲が広がる
- お腹を押すと響くような痛み、板のように硬くなっている感じ
このような症状は、腸に穴が開いている穿孔の可能性があります。穿孔は腹膜炎を起こし、緊急手術が必要となる重篤な状態なので、少しでもおかしいと感じたら、様子を見ずにすぐに医療機関に連絡してください。
腹痛の危険度チェック
| 症状 | 考えられる原因 | 緊急度 |
|---|---|---|
| お腹の張り、軽い鈍痛 | 処置による刺激、腸内の空気 | 低い(安静にして改善することが多い) |
| 持続する強い痛み、冷や汗、嘔吐 | 後出血による腹腔内出血、穿孔・腹膜炎 | 非常に高い(すぐに医療機関へ連絡) |
血便の色と量で判断するポイント
処置後、1~2回程度、便の表面に少量の血液が付着することはあり得、傷口に残っていた血液が排出されたものであることが多いです。
しかし、便器が真っ赤になるほどの大量の出血や、レバーのような血の塊が出る、繰り返し出血が見られる場合は後出血の可能性があります。
便の色も重要な判断材料で、真っ赤な鮮血が大量に出る場合は、肛門に近い場所からの出血が考えられます。また、黒くてドロドロした便(黒色便)は、大腸の奥の方で出血し、血液が腸内を通過する間に変色したサインです。
どちらの場合も、活動性の出血が続いている証拠ですので、速やかな受診が必要です。
発熱やその他の体調不良
38度以上の高熱、繰り返す嘔吐、強い倦怠感なども注意すべき症状です。特に、強い腹痛とともに発熱が見られる場合は、穿孔による腹膜炎を起こしている可能性が高く、体内で重篤な炎症が起きていることを示唆します。
いずれにしても通常の回復過程ではありません。このような症状が現れた場合は、自己判断で様子を見たり、市販の解熱剤などで対処したりせず、必ず医療機関に連絡して指示を仰いでください。
医療機関へ連絡する際に伝えること
実際に医療機関へ連絡する際は、慌てずに状況を正確に伝えることが大切で、いくつかの点を整理しておくと、スムーズに話が進みます。
- いつ、どこの医療機関で内視鏡処置を受けたか
- どのような症状が、いつから始まったか(腹痛、血便、発熱など)
- 症状の具体的な内容(痛みの強さ、便の色と量、回数など)
- 現在の体温や血圧(もし測定できれば)
大腸ポリープのクリップ処置に関するよくある質問
最後に、クリップ処置に関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で解説します。
- クリップは金属アレルギーでも問題ありませんか
-
ほとんどの場合、問題ありません。医療用クリップに使われるチタン合金などは、アレルギー反応をきわめて起こしにくい金属として知られています。
歯科治療や整形外科領域のインプラントなどにも広く使われている安全性の高い材質です。もし、特定の金属に対して重篤なアレルギーの既往がある場合は、念のため内視鏡検査を受ける前に医師に申告しておくと、より安心です。
- 処置後に普段から飲んでいる薬は続けても良いですか
-
必ず医師の指示に従ってください。特に、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬や抗血小板薬)を内服している方は、処置後の出血リスクを管理するために、一時的に休薬や変更が必要な場合があります。
自己判断で薬を中止したり再開したりすることは大変危険です。
高血圧や糖尿病などの薬についても、処置前後の食事内容の変更に合わせて調整が必要なこともありますので、処置を受ける前に必ず主治医や内視鏡医に相談し、指示を確認してください。
- クリップが便と一緒に出てきた場合、どうすればよいですか
-
特に何もする必要はありません。クリップが排出されるのは、傷が順調に治った証拠であり、自然な経過です。
排出されたクリップに気づくこと自体がまれですが、万が一見つけたとしても、そのままトイレに流して問題ありません。回収したり、医療機関に持参したりする必要はありません。
- クリップが残っていると、大腸がん検診の便潜血検査に影響しますか
-
影響しません。便潜血検査は、便の中に含まれるヒトの血液(ヘモグロビン)に反応する検査です。クリップは金属であり、血液成分ではないため、検査結果が陽性になる原因にはなりません。
クリップが残っていても、定期的な大腸がん検診はこれまで通り受けることが大切です。
もし検診で陽性反応が出た場合は、クリップとは別の新たな出血源が考えられるため、精密検査である大腸内視鏡検査を受けることを検討してください。
以上
参考文献
Shioji K, Suzuki Y, Kobayashi M, Nakamura A, Azumaya M, Takeuchi M, Baba Y, Honma T, Narisawa R. Prophylactic clip application does not decrease delayed bleeding after colonoscopic polypectomy. Gastrointestinal endoscopy. 2003 May 1;57(6):691-4.
Miyakawa A, Tamaru Y, Mizumoto T, Kanazawa N, Uchiyama S, Maehara K, Sumida Y, Nakamura A, Itobayashi E, Shimura H, Suzuki Y. Prophylactic clip closure after endoscopic submucosal dissection of large flat and sessile colorectal polyps: a multicentre randomised controlled trial (EPOC trial). Gut. 2025 May 30.
Inoue T, Ishihara R, Nishida T, Akasaka T, Hayashi Y, Nakamatsu D, Ogiyama H, Yamaguchi S, Yamamoto K, Mukai A, Kinoshita K. Prophylactic clipping not effective in preventing post‐polypectomy bleeding for< 20‐mm colon polyps: A multicenter, open‐label, randomized controlled trial. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2021 Feb;36(2):383-90.
Mizukami T, Hiroyuki I, Hibi T. Anchor clip technique helps in easy prevention of post‐polypectomy hemorrhage of large colonic polyps. Digestive Endoscopy. 2010 Oct;22(4):366-9.
Pohl H, Grimm IS, Moyer MT, Hasan MK, Pleskow D, Elmunzer BJ, Khashab MA, Sanaei O, Al-Kawas FH, Gordon SR, Mathew A. Clip closure prevents bleeding after endoscopic resection of large colon polyps in a randomized trial. Gastroenterology. 2019 Oct 1;157(4):977-84
Ji JS, Lee SW, Kim TH, Cho YS, Kim HK, Lee KM, Kim SW, Choi H. Comparison of prophylactic clip and endoloop application for the prevention of postpolypectomy bleeding in pedunculated colonic polyps: a prospective, randomized, multicenter study. Endoscopy. 2014 Jul;46(07):598-604.
Gweon TG, Lee KM, Lee SW, Kim DB, Ji JS, Lee JM, Chung WC, Paik CN, Choi H. Effect of prophylactic clip application for the prevention of postpolypectomy bleeding of large pedunculated colonic polyps: a randomized controlled trial. Gastrointestinal endoscopy. 2021 Jul 1;94(1):148-54.
O’Mara MA, Emanuel PG, Tabibzadeh A, Duve RJ, Galati JS, Laynor G, Gross S, Gross SA. The use of clips to prevent post-polypectomy bleeding: a clinical review. Journal of Clinical Gastroenterology. 2024 Sep 1;58(8):739-52.
Shah ED, Pohl H, Rex DK, Morales SJ, Feagins LA, Law R. Routine prophylactic clip closure is cost saving after endoscopic resection of large colon polyps in a Medicare population. Gastroenterology. 2020 Mar 1;158(4):1164-6.
Chen B, Du L, Luo L, Cen M, Kim JJ. Prophylactic clips to reduce delayed polypectomy bleeding after resection of large colorectal polyps: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Gastrointestinal endoscopy. 2021 Apr 1;93(4):807-15.