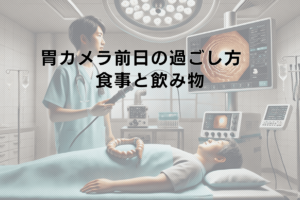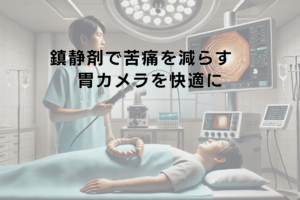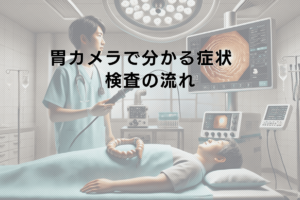胃カメラ検査を受けてみたいけれど費用がどのくらいかかるのか、と気になる方も多いでしょう。
実際に保険診療か自費診療かで負担額が異なるほか、検査中に組織を切り取って病理診断を行う場合や、鎮静剤を使用するケースなどによっても変動があります。
また、胃カメラだけでなく大腸の内視鏡検査を同日に行う場合も費用に影響することがあります。
この記事では、胃カメラ費用のしくみを中心に、検査の流れや保険診療の仕組み、症状がある場合の受診の目安などを詳しく解説します。
胃カメラ検査の基本的な内容
胃カメラ検査では内視鏡を用いて、消化管の中でも胃や食道、十二指腸までを直接観察します。口または鼻から細いカメラを挿入し、粘膜の状態やポリープなどの病気を探し、必要があれば組織を採取して詳細に診断します。

胃の粘膜を詳しく確認する理由
胃は強い胃酸にさらされながら食物を消化する器官であり、負担がかかりやすい構造です。
またピロリ菌感染による慢性胃炎により胃がん、胃潰瘍が発生するリスクがあります。
食道や十二指腸と合わせて内視鏡で直接観察することで、潰瘍やがん、ポリープの早期発見が期待できます。ピロリ菌の有無などを確かめる場合にも内視鏡検査を活用するケースが多く、症状があるなしにかかわらず定期的なチェックが重要です。

経口か経鼻か
挿入経路は経口と経鼻に分かれます。経口は口からカメラを入れる方法で、一般的に操作性が高く詳細に観察しやすいという特徴があります。
一方、嘔吐反射が強い方には鼻から通す経鼻のほうが負担感が少ない場合もありますが、鼻腔が狭い方には向かないなどの注意が必要です。
経口、経鼻いずれでも内視鏡検査自体の費用は同じですが、検査時に使用する薬剤が異なる場合があり、わずかに金額は異なることがあります。
保険診療と自費診療での違い
症状があって医師が検査が必要と判断した場合などは保険が適用されますが、健康診断などで自費診療として受ける場合は10,000円〜25,000円程度かかることがあります。
鎮静剤を使用するかどうかや、組織の切除の有無、医療機関が設定している検査料金によって負担額は変動します。
大腸内視鏡検査との同時実施
大腸内視鏡検査もあわせて受けるケースがあり、消化器全体を1度にチェックすることで通院回数を減らせる利点がありますが、胃カメラと大腸カメラを同日に行うと麻酔の種類や時間の都合もあって費用が別途かかることがあります。
医師に相談しながらスケジュールを決めることが大切です。
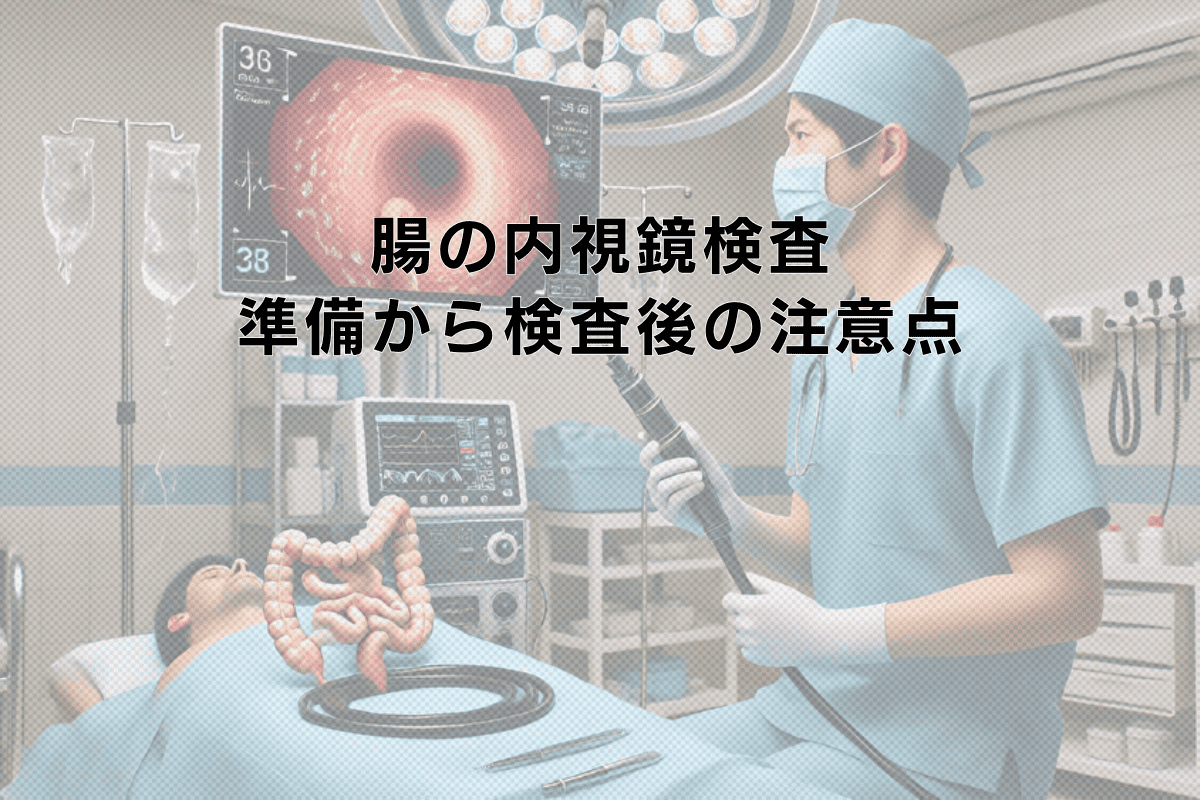
主な内視鏡検査の観察範囲と特徴
| 検査方法 | 観察部位 | 特徴・目的 | 費用の目安(保険診療/自費) |
|---|---|---|---|
| 胃カメラ(経口) | 食道・胃・十二指腸 | 嘔吐反射が出やすいが操作性が高い 一部機種では詳細な拡大観察が可能 | 5,000〜15,000円/10,000〜25,000円 |
| 胃カメラ(経鼻) | 食道・胃・十二指腸 | 口呼吸ができ比較的楽だが鼻腔の状態に左右される | 同上 |
| 大腸内視鏡 | 大腸全域 | 大腸ポリープ切除が可能な検査 | 8,000〜20,000円/20,000〜40,000円 |
胃カメラ費用のしくみ
胃カメラ検査の費用は検査そのものと診察料、麻酔薬の費用、組織検査の費用など、さまざまな要素が組み合わさって決まります。
保険診療の場合でも検査の内容によって自己負担額が変わるため、実際にいくらかかるのか分かりづらいと感じる方は少なくありません。
保険診療が適用される条件
医師が胃カメラ検査を行う必要があると診断したら保険診療が適用されます。症状としては胃の痛みや吐き気、げっぷの増加、胸やけ、黒色便などを認める場合が該当します。
健康診断でピロリ菌感染が疑われたり、バリウム検査で異常が見つかった後の精密検査も含まれます。
自費診療のケース
人間ドックなどの検診で胃カメラを受けるときには、病気の可能性よりも予防・チェック目的が強いため、自費診療となることが多いです。
保険診療とは違って検査内容や医療機関の料金設定で費用幅が大きい場合がありますが、早期発見や予防の観点で定期的に受ける意義を感じる方は多く、年に1回〜2回程度受診する例もあります。
組織検査の有無
内視鏡で怪しい病変やポリープを見つけたときには、その場で組織を採取(生検)して顕微鏡で詳しく調べる場合があります。組織検査を追加すると費用が上乗せされますが、がんや胃潰瘍など病気を正確に診断するうえで欠かせません。
保険診療内でも負担は増えますが、早期治療につながる大切な検査だと考えると、受けたほうが良いケースが多いです。
静脈麻酔の使用
嘔吐反射が強い方や検査への恐怖が大きい方には、静脈麻酔を使って眠っている間に検査を行う選択肢があります。
麻酔が入ると苦痛は軽くなりますが、追加費用がかかる場合があり、検査後はしばらく安静が必要になります。
車やバイクを運転しての帰宅は避ける必要があるため、事前に医師やスタッフとの相談が大切です。
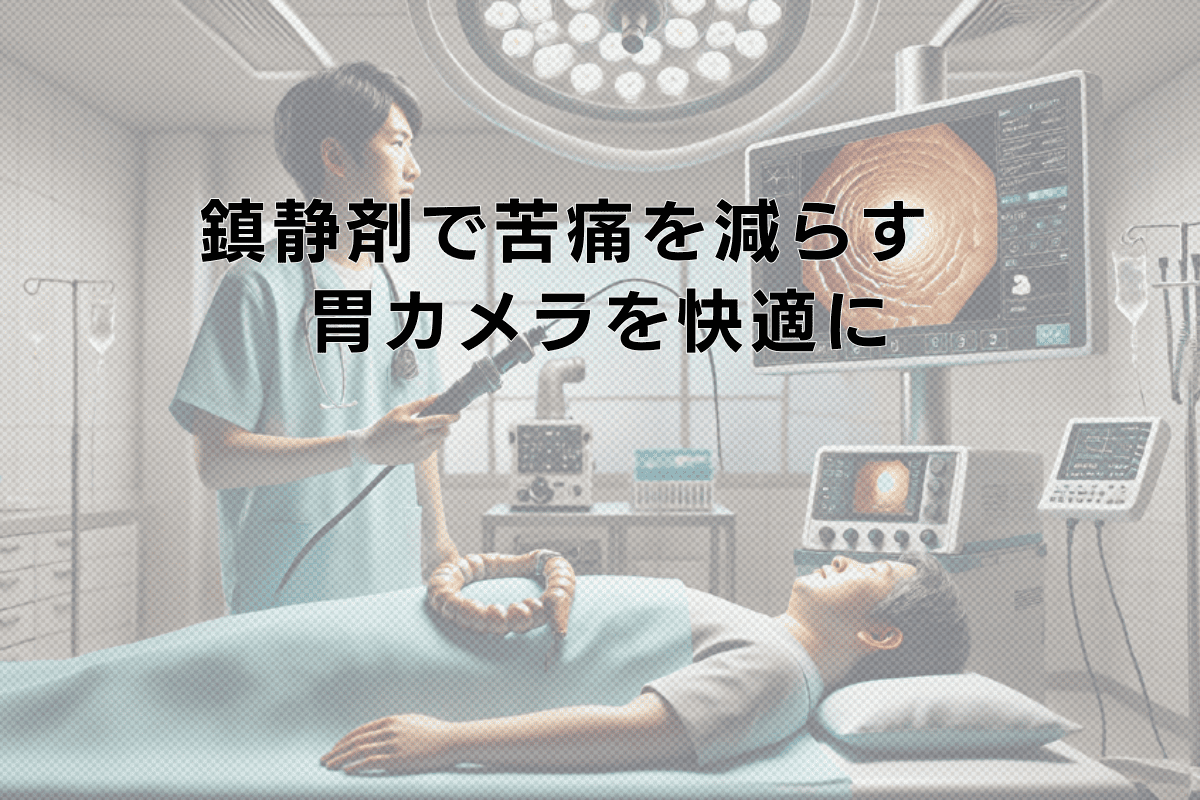
保険診療・自費診療の違い
| 区分 | 主な対象 | 自己負担率 | 価格帯(例) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 保険診療 | 症状がある場合など | 3割または1割 | 5,000〜15,000円程度 | 医師の判断で検査が必要なとき適用される |
| 自費診療 | 健診や人間ドック | 全額自己負担 | 10,000〜25,000円程度 | 予防・早期発見を目的に受けることが多い |
| 組織検査 | 胃がん、食道がんを疑う場合など | 保険診療内で加算 | +2,000〜5,000円程度 | がんや病気を正確に診断するために重要 |
費用に影響するポイント
同じ胃カメラ検査であっても、クリニックや医療機関によって最終的な費用が異なることがあります。検査に伴う麻酔や薬剤、組織切除が追加されると負担額に幅が出るため、自分の身体の状態や検査の目的に合ったところを選ぶことが重要です。
医療機関の診療方針と設定
医療機関ごとに診療報酬点数の扱い方や、追加処置に関する設備が異なる場合があります。
たとえば、内視鏡専門クリニックであれば検査件数が多く、検査経験が豊富な分だけ効率的に行うケースがあり、結果的に生検などもスムーズに進むことが期待できます。
一方で、総合病院などは緊急時の対応もしやすいというメリットがありますが、紹介状がないと初診時に追加の費用が加わる場合があります。
経口・経鼻スコープの太さ
経鼻内視鏡は経口よりも細いスコープを使用するため、検査自体の時間や辛さが軽減しやすいという利点がありますが、一部の医療機関では経鼻に対応していなかったり、経口とは使用する薬剤が異なる場合は負担も若干変化します。
組織切除や内視鏡的治療
内視鏡検査は発見だけでなく治療を兼ねることもあります。多くの場合は病気の発見と同時に治療することはありませんが、内視鏡的治療となると手術費用や病理診断費用などが発生するため、負担も変化します。
胃カメラと大腸カメラのセット
胃と大腸を一度に調べたい方は、同日セットでの内視鏡検査を受けることが可能な場合があります。
1度の予約で済み、費用も個別で受ける場合と比べても特に変わりはありません。ただ麻酔の使用量が増えたり、検査時間が長くなったりする場合があります。
費用に関わる主な要素
- 麻酔の有無(静脈麻酔・局所麻酔)
- 組織検査やポリープ切除を行うかどうか
- 内視鏡検査と同時に追加の検査(採血など)を行うか
- 健康保険の負担割合(3割・1割・公費など)
- 医療機関の検査料金設定や診察料
検査当日までの流れ
胃カメラ検査を受けることが決まったら、予約から検査終了後の過ごし方までの流れをイメージしておくと安心感が高まります。
予約と事前診察
症状がある場合や不安を感じる場合は、まず内科や消化器内科を受診して医師に相談し、胃痛や胸やけなどがあれば胃カメラを検討してみる価値があります。また、下痢や腹痛などの大腸の症状があれば大腸内視鏡もあわせて計画することがあります。
予約時には保険適用の可否や見込み費用を尋ねると、事前準備が進めやすくなります。
胃カメラ検査を予約する際に確認しておくと良い点
| 確認内容 | 具体例 |
|---|---|
| 保険適用の可否 | 症状があるか、医師の診断はどうか |
| 費用の概算 | 麻酔の利用、組織検査の可能性 |
| 時間と流れ | 検査所要時間、前日からの食事制限の説明 |
| 大腸カメラの同日希望 | 同時実施の可否、負担額の見込み |
| 鎮静剤使用の希望 | 検査後の送迎・付き添いの必要性 |
前日の準備
一般的に検査前日の夜9時以降は食事を控え、胃を空にしておくよう求められます。水やお茶など、透明な飲料は許可される場合が多いですが、医師やスタッフの説明にしたがってください。
また、糖尿病の治療薬や血液をサラサラにする薬(抗凝固薬など)を服用している場合は、事前の指示をしっかり確認します。

検査当日の受付から検査実施まで
予約当日は空腹状態でクリニックに到着し、受付で問診票を記入し、体調確認後に鎮静剤を使うかどうかを再度打ち合わせしたのち、検査が始まります。
経口の場合はのどの麻酔を行い、経鼻の場合は鼻へ局所麻酔薬を注入するなど事前準備があります。
内視鏡自体は5分〜15分程度で終了することもありますが、麻酔を使用する場合は前後の準備や安静時間を含めて1時間〜2時間ほどを見込むとよいでしょう。
検査当日の流れ
- 受付・問診・体調確認
- 鎮静剤や局所麻酔などの準備
- 内視鏡挿入と観察、組織採取が必要な場合は追加処置
- 検査終了後の安静・休憩
- 医師からの結果説明(当日分かる範囲、組織検査は後日)
検査後の注意点
鎮静剤を使用した場合は運転などができないため、公共交通機関の利用や付き添いの方と一緒に帰宅するほうが安心です。
検査直後は胃に空気が残っているため、膨満感やゲップが出やすいですが、時間とともに落ち着いていきます。食事は検査後の医師の説明に応じて開始してください。水分補給をまめに行うと体調管理に役立ちます。

生検や追加検査で生じる費用
胃カメラ検査中に病変が見つかったときには生検を行います。正確な診断と早期治療に役立つ重要です。
生検(組織検査)の概要
粘膜に異常が疑われる部位があった場合、内視鏡の先端から小さな鉗子で組織の一部をつまみ取り、病理医が顕微鏡で細胞をチェックし、がん細胞や炎症の有無を確認します。
保険適用の範囲内であれば3割負担(または1割)で受けられますが、複数の臓器から採取すると1臓器ごとに費用が加算されることがあります。
組織検査にかかる目安費用
| 項目 | 目安費用(3割負担) | 説明 |
|---|---|---|
| 組織採取(1箇所あたり) | 約1,000円 | 部位によって異なる |
| 病理組織検査 | 約3,000円 | 採取した組織の解析費用 |
| 合計(1箇所分) | 約4,000円 | 生検する箇所が増えると加算 |
ピロリ菌検査
組織検査の一環としてピロリ菌の有無を調べる場合があります。
尿素呼気試験や抗体検査、迅速ウレアーゼ試験、PCR検査などの方法があり、保険適用の対象かどうかは検査の目的によって異なることが多いです。
胃カメラ検査と同時に行うメリットは、採血や内視鏡検査を一度に済ませられる点ですが、結果的に費用が合算になるため、事前に予算をイメージしておいてください。
追加検査の判断
もし検査の最中に予想外の病変が見つかった場合、医師がその場で治療や追加検査を提案することがあります。
検査当日では患者さんが詳しい費用イメージを持たずに「想定外の出費」と感じるかもしれませんが、体調や将来のリスクを考えると、そのまま行ったほうがいい場合が多いです。
組織検査や追加検査のメリット
- 病気の有無を正確に判定し、早期治療につなげる
- 出血や腫瘍の進行リスクを未然に抑える
- ピロリ菌感染が確定すれば除菌治療を行う
胃カメラを受けるメリットと注意点
費用面から胃カメラを受けるか迷う方もいますが、胃がんやポリープ、胃潰瘍などを早期に発見する機会として大変重要です。一方で検査前後に気をつけたい注意点もあるため、全体像を理解して自分に合ったタイミングで受けましょう。
早期発見につながる
胃がんや食道がんは早期だと自覚症状がほとんどない場合もあり、放置すると進行して手術や化学療法が必要になるケースがあるため、負担を抑えながら早期治療できることは大きなメリットです。
費用はかかりますが、健康への投資ととらえる方が多く、定期的なチェックを習慣にしている患者さんも増えています。
胃や食道、十二指腸を直接観察
バリウム検査では得られない細かな粘膜の色や形状、出血の有無などをダイレクトに確認できます。逆流性食道炎や胃潰瘍、ピロリ菌による慢性胃炎なども把握しやすく、がん以外の病気が発見されることも珍しくありません。
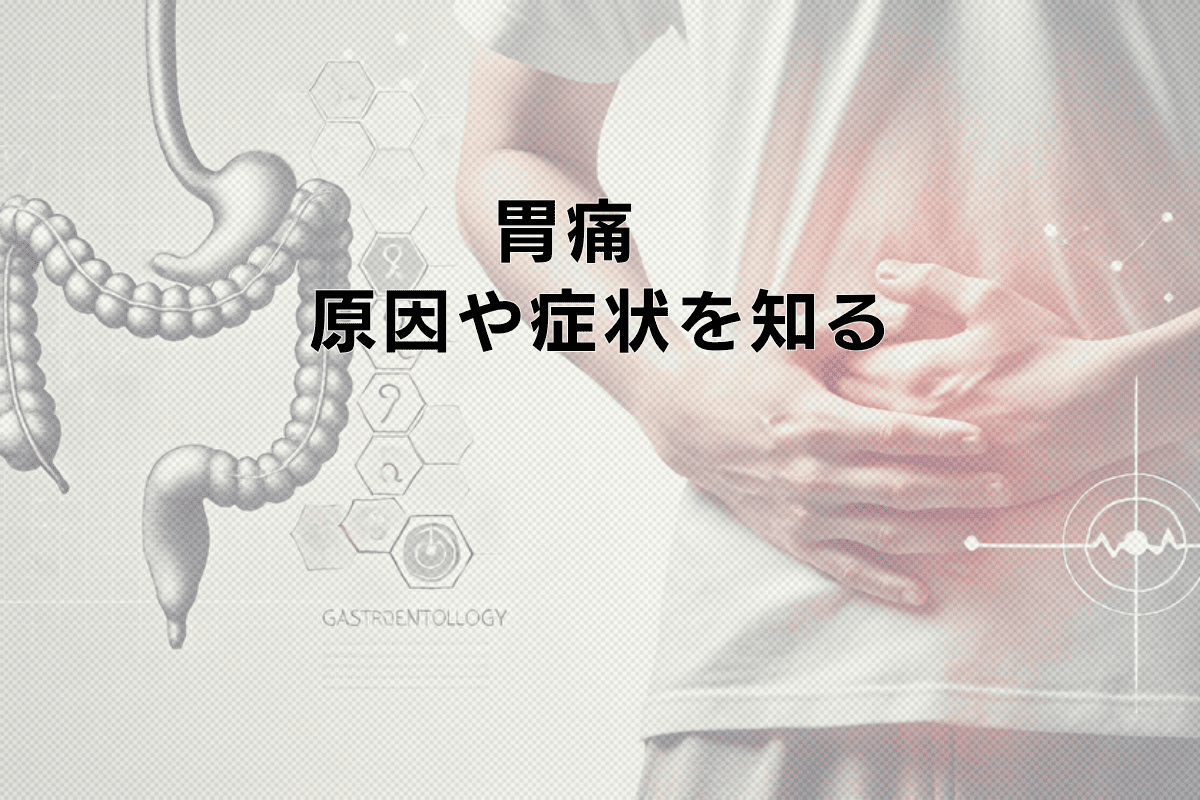
麻酔や嘔吐反射
胃カメラ検査で抵抗を感じる方が多いのは、やはり内視鏡の挿入時の嘔吐反射です。
麻酔を使用することで苦痛を軽減できますが、費用が上乗せされ、また、鎮静剤を使うと検査後も数時間ほど注意が必要で、当日の車やバイクの運転を控えるなど、生活面の制限が生じる点を理解しておきます。
受ける時期
症状がある場合は早めに受診するのが基本で、症状がなくても年齢や家族歴、普段のストレスや生活習慣を踏まえ、医師と相談して胃カメラ検査を定期的に受けるかを決めると安心です。
大腸内視鏡検査と合わせるかどうかも含め、自分のライフスタイルに合った方法を選択します。
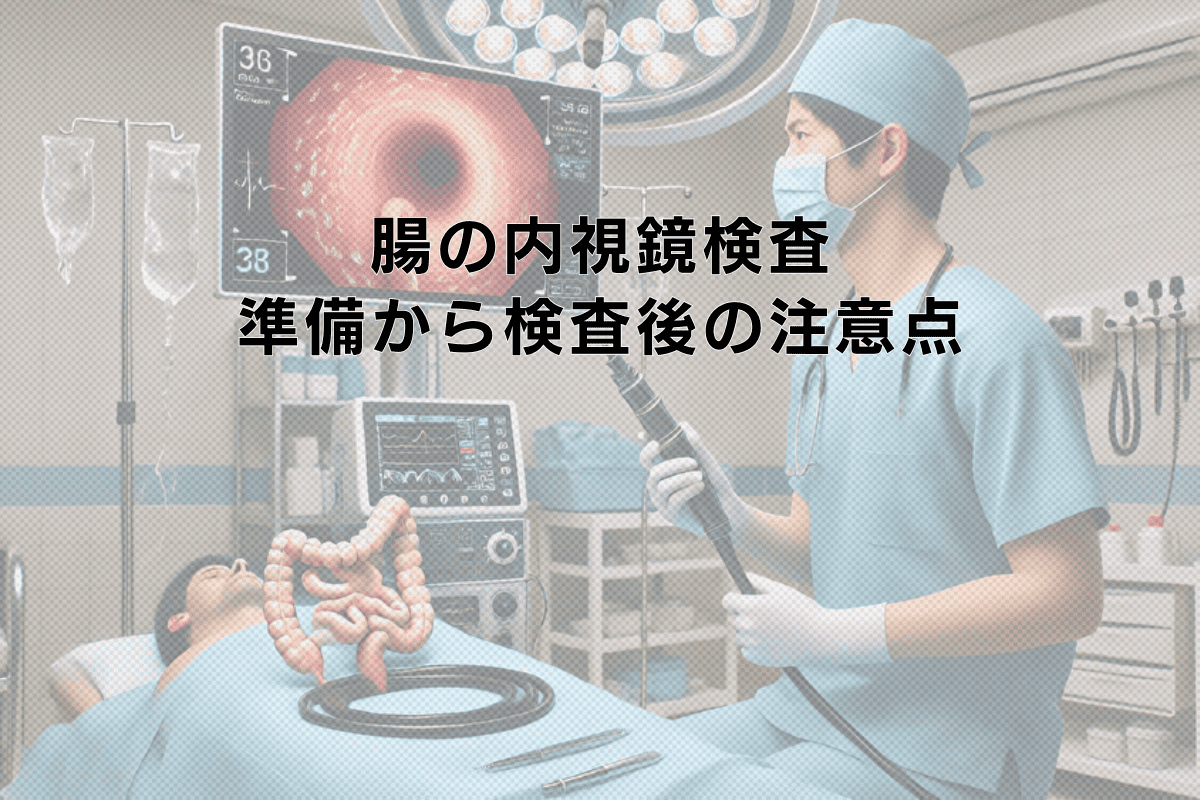
胃カメラ検査を選ぶメリット
| 項目 | メリット |
|---|---|
| 直接観察 | 粘膜の異常を詳細に確認でき、小さな病変を見逃しにくい |
| 生検・切除 | ポリープの切除や組織検査が同時に可能 |
| 炎症の発見 | 食道から十二指腸にかけて広い範囲をチェックできる |
| 早期治療 | 胃がんや潰瘍を早期に治療して負担を減らしやすい |
クリニック選びのポイント
胃カメラ検査や内視鏡検査は、設備やスタッフの経験が大きく費用や検査の快適さに影響します。保険診療か自費診療かにかかわらず、安心して受けられる医療機関を探すことが大切です。
消化器内科や内視鏡専門医
日本消化器内視鏡学会専門医などの資格を持つ医師が在籍しているかは、検査の精度や対応の幅においてチェックしておきたいポイントです。経口と経鼻の両方に対応しているクリニックなら、患者さんの希望に合わせた方法を選択しやすくなります。
院内の雰囲気と予約の取りやすさ
胃カメラ検査はどうしても緊張しやすいため、スタッフや看護師の対応が丁寧であるか、予約が取りやすいかどうかも重要です。
検査に関する詳細な説明や費用の概算など、患者さんが納得しやすいようにサポートしてくれるクリニックを選ぶと安心感が高まります。
クリニックを選ぶときに意識したい点
- 消化器内科・内視鏡専門医が常駐しているか
- 経鼻内視鏡に対応しているか(嘔吐反射が強い方)
- 鎮静剤を使用できる体制があるか
- 予約のスケジュールや土・日診療の有無
- 大腸内視鏡検査やピロリ菌検査も同時に受けられるか
保険診療のアドバイス
医師が必要と判断すれば保険診療になりますが、問診の段階で症状をきちんと伝えることも大切です。
漠然とした不調を具体的に説明し、検査の必要性を医師が確認できれば保険適用となる確率が高くなり、逆に明確な症状がない場合や定期的な健康診断目的だと自費になる場合があります。
長く通えるかどうか
胃の調子はストレスや食習慣、年齢などさまざまな要因と関連するため、1回だけでなく継続して受診する必要が出てくる場合があり、同じクリニックで受け続けるほうが経過を追いやすく、費用や検査の煩わしさも抑えられます。
胃カメラ費用と受診タイミングのまとめ
胃カメラ費用は保険診療なら5,000〜15,000円程度、自費診療なら10,000〜25,000円程度と幅がありますが、組織検査や麻酔の使用など追加要素によって変動することが多いです。
検査を受けることで胃がんや食道がんなどの早期発見が期待でき、治療の機会を逃さずに済む点は大きな利点といえます。
症状がない場合でも、胃や腸に不安がある方や40代以降になった方、ピロリ菌感染のリスクが高いと感じている方は、一度消化器内科などで相談してみると良いでしょう。
大腸内視鏡との同日検査を希望する場合は、予約時にその旨を伝えて費用や注意点を確認してください。適切な時期に検査を受けることで、負担を抑えながら健康を守る選択につながります。
受診タイミングを考えるポイント
| 状況 | 検査の目安 |
|---|---|
| 胃痛・胸やけ・吐き気などの症状がある | 早めに内科や消化器内科へ受診し、必要に応じて胃カメラへ |
| バリウム検査で異常が見つかった | 精密検査として胃カメラを追加し、保険診療の対象になりやすい |
| ピロリ菌感染が疑われる | 血液検査などの結果を踏まえ、内視鏡検査を検討 |
| 大腸カメラも同時に受けたい | 予約時に伝え、麻酔や費用をチェック |
| 健康診断・人間ドックで検査したい | 自費診療になる可能性が高いが早期発見につながる |
次に読むことをお勧めする記事
【胃カメラ前日どう過ごす? 準備で気をつけたい食事と飲み物】
胃カメラの費用について理解できたら、次は実際に検査を受ける際の準備方法について、以下の記事で一緒に学んでまいりましょう。検査を予定されている方や検査を検討中の方に特におすすめの実践的な内容です。
【鎮静剤で苦痛を減らす 胃カメラを快適に受けるために】
カメラの費用についての理解が深まりましたら、さらに検査を快適に受ける方法についても知っておくと、より安心して検査に臨めます。この記事で一緒に学んでまいりましょう。
参考文献
Bytzer P. Cost-effectiveness of gastroscopy. Italian Journal of Gastroenterology and Hepatology. 1999 Nov 1;31(8):749-60.
Muro EA, Celaya FB, Virseda JM, Aguilar EB, Legaz SO, Pérez FJ. Analysis of the clinical benefits and cost-effectiveness of performing a systematic second-look gastroscopy in benign gastric ulcer. Gastroenterologia y hepatologia. 2009 Jan;32(1):2-8.
Lahner E, Hassan C, Esposito G, Carabotti M, Zullo A, Dinis-Ribeiro M, Annibale B. Cost of detecting gastric neoplasia by surveillance endoscopy in atrophic gastritis in Italy: A low risk country. Digestive and Liver Disease. 2017 Mar 1;49(3):291-6.
Loras C, Mayor V, Fernández-Bañares F, Esteve M. Study of the standard direct costs of various techniques of advanced endoscopy. Comparison with surgical alternatives. Digestive and Liver Disease. 2018 Jul 1;50(7):689-97.
Lewis D, Jimenez L, Mansour MH, Horton S, Wong WW. A systematic review of cost-effectiveness studies on gastric cancer screening. Cancers. 2024 Jun 27;16(13):2353.
Yashima K, Shabana M, Kurumi H, Kawaguchi K, Isomoto H. Gastric cancer screening in Japan: a narrative review. Journal of clinical medicine. 2022 Jul 26;11(15):4337.
Yao K, Uedo N, Kamada T, Hirasawa T, Nagahama T, Yoshinaga S, Oka M, Inoue K, Mabe K, Yao T, Yoshida M. Guidelines for endoscopic diagnosis of early gastric cancer. Digestive Endoscopy. 2020 Jul;32(5):663-98.
Mori Y, Kudo SE, Mohmed HE, Misawa M, Ogata N, Itoh H, Oda M, Mori K. Artificial intelligence and upper gastrointestinal endoscopy: Current status and future perspective. Digestive endoscopy. 2019 Jul;31(4):378-88.
Yoshida N, Doyama H, Yano T, Horimatsu T, Uedo N, Yamamoto Y, Kakushima N, Kanzaki H, Hori S, Yao K, Oda I. Early gastric cancer detection in high-risk patients: a multicentre randomised controlled trial on the effect of second-generation narrow band imaging. Gut. 2021 Jan 1;70(1):67-75.
Uedo N, Gotoda T, Yoshinaga S, Tanuma T, Morita Y, Doyama H, Aso A, Hirasawa T, Yano T, Uchita N, Ho SH. Differences in routine esophagogastroduodenoscopy between Japanese and international facilities: a questionnaire survey. Digestive Endoscopy. 2016 Apr;28:16-24.