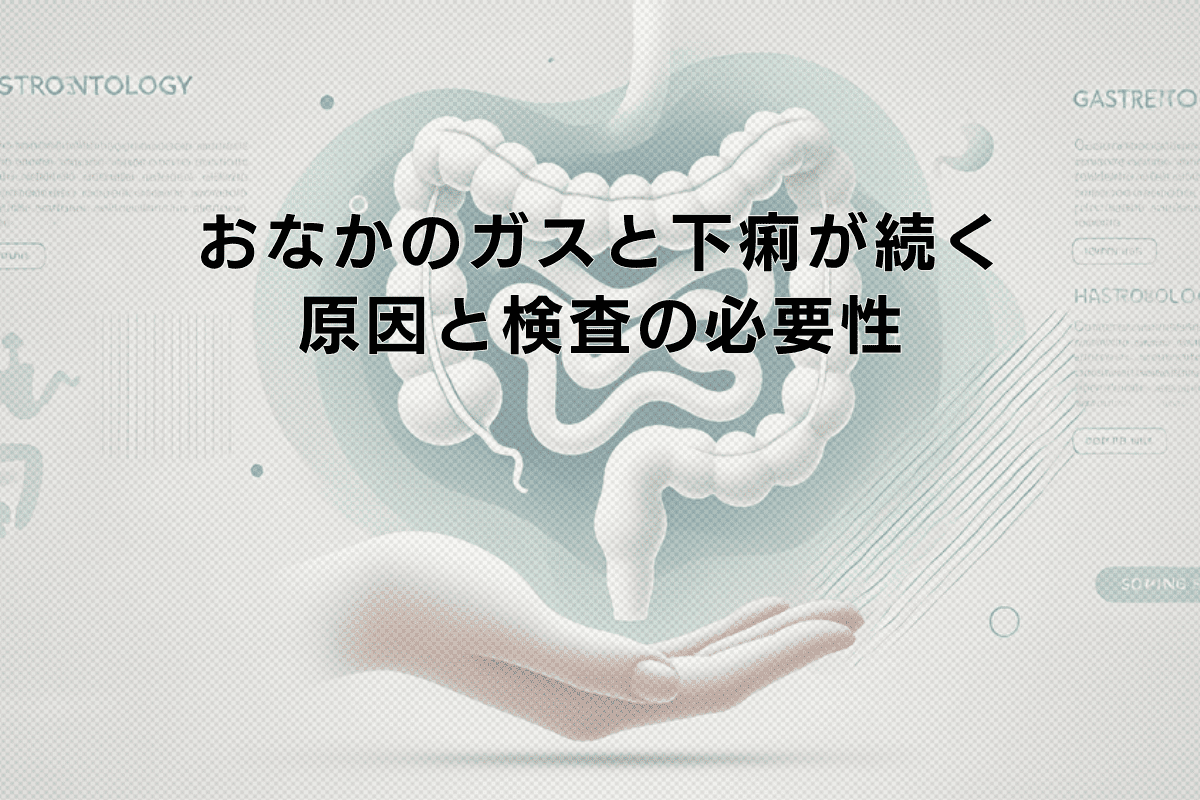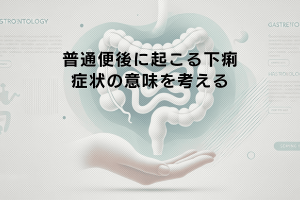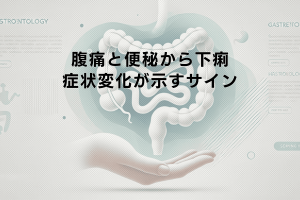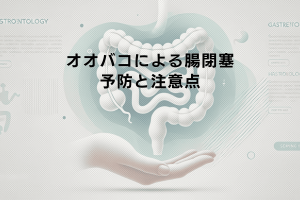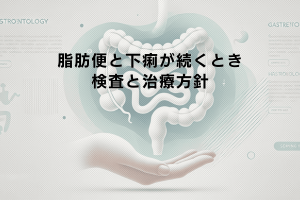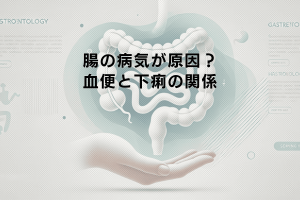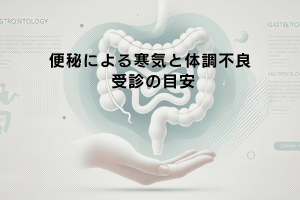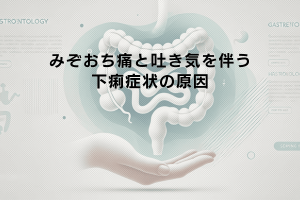おなかが張って苦しいガス溜まりと、急にやってくる下痢。この二つの不快な症状が一緒に、しかも繰り返し続くことで、日常生活に大きな影響が出ている方も多いのではないでしょうか。
通勤中の電車や大切な会議中など、状況を選ばずに起こる腹部の不調は、精神的なストレスにもつながります。
この記事では、なぜおなかのガスと下痢が同時に起こるのか、背景にある原因を日常生活から考えられる病気まで幅広く探ります。
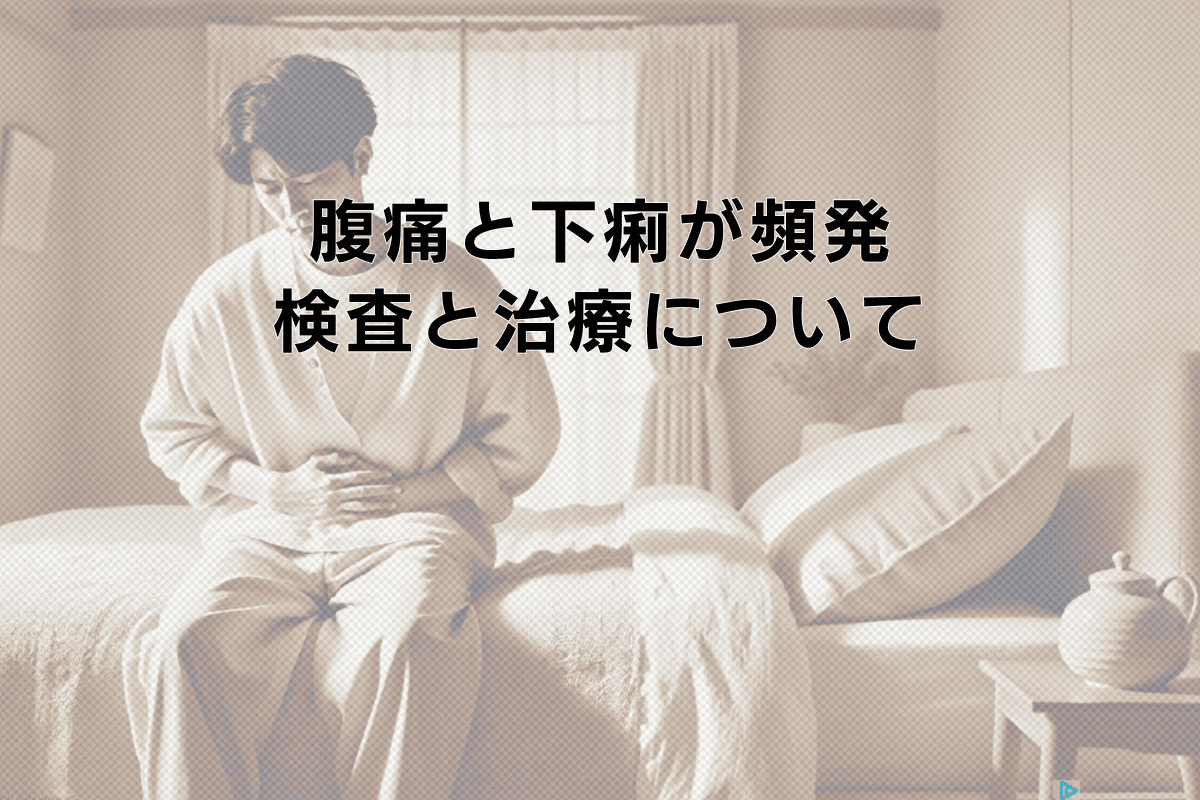
なぜおなかのガスと下痢は同時に起こるのか
おなかのガスと下痢は、一見すると別々の症状のように思えるかもしれません。しかし、消化器、特に腸の中では、この二つの症状は密接に関連し合っています。
多くの場合、腸内環境の乱れという共通の土台の上で発生し、互いに影響し合うことで症状を悪化させることさえあります。
腸内でのガス発生の仕組み
おなかのガスは、主に二つの経路で発生し、一つは、食事や会話の際に無意識に飲み込む空気です。これを呑気症と呼びます。もう一つは、腸内細菌が食べ物の残りかすを分解する際に発生するガスです。
健康な人でも一定量のガスは発生しますが、特定の食品の摂取や腸内環境の乱れによって、ガスが過剰に発生することがあります。
特に、食物繊維が豊富な食品や、消化されにくい糖質などは、大腸の細菌によって発酵しやすく、多くのガスを生み出す原因となります。
下痢がガスを誘発する理由
下痢の状態では、腸の蠕動運動が過剰に活発になり、食べ物が十分に消化・吸収されないまま大腸へと送られます。これにより、大腸内の細菌が分解するべきエサが増え、結果としてガスの発生量も増加します。
また、下痢便は腸内を速いスピードで通過するため、正常な便よりも多くの未消化物や水分を含んでいて、腸内細菌の異常発酵を促し、ガス溜まりや腹部の張り感をさらに強くする原因となるのです。
腸内環境の乱れが共通の原因
ガスと下痢が同時に起こる背景には、多くの場合、腸内フローラのバランスの乱れがあります。私たちの腸内には、多種多様な細菌が生息しており、善玉菌、悪玉菌、そしてどちらでもない日和見菌が互いにバランスを保っています。
しかし、ストレスや不規則な食生活、抗生物質の使用などによってこのバランスが崩れ、悪玉菌が優勢になると、腸内で異常な発酵が起こりやすくなります。
異常発酵は、有害物質やガスを産生し、腸の粘膜を刺激して蠕動運動を異常にさせ、下痢を起こすのです。
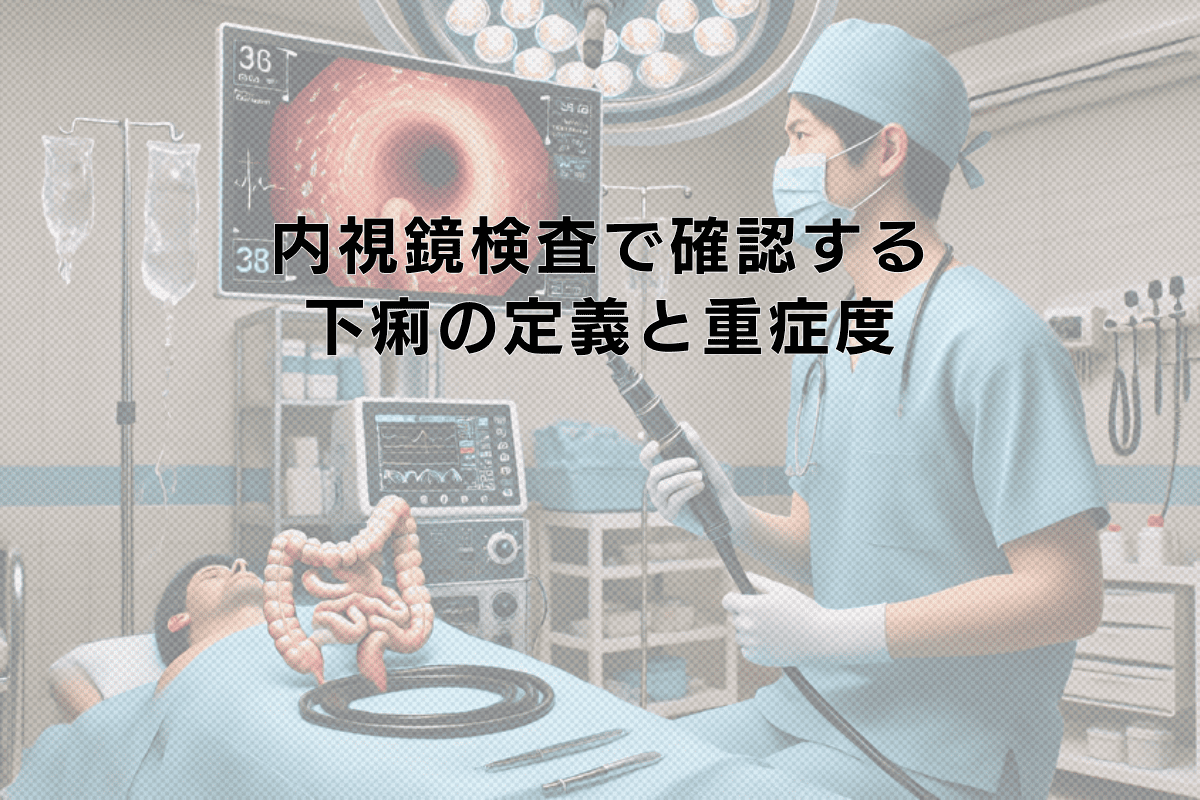
症状の悪循環について
おなかのガスと下痢は、一度始まると悪循環に陥りやすい特徴があります。下痢によって腸内環境が悪化すると、さらにガスが発生しやすくなります。
そして、ガスが溜まることによる腹部の不快感や腹痛がストレスとなり、そのストレスが自律神経を乱してさらに腸の動きを不安定にし、下痢を悪化させる、という負の連鎖です。
サイクルを断ち切るためには、単に下痢を止めたり、ガスを抑えたりするだけでなく、根本にある腸内環境や生活習慣全体を見直す視点が重要になります。
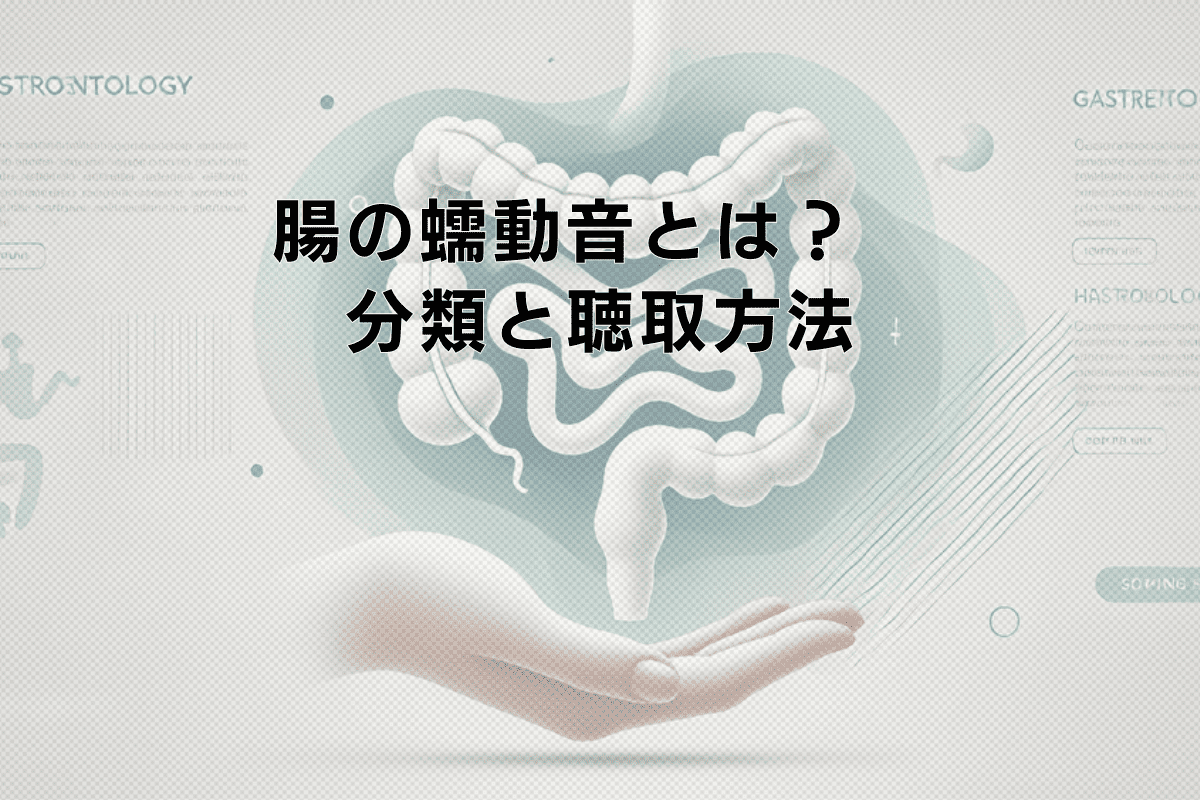
日常生活に潜むガスと下痢の原因
多くの人が経験するおなかのガスや下痢は、特別な病気だけでなく、日々の何気ない生活習慣の中に原因が隠れていることが少なくありません。
食事の内容や食べ方、精神的なストレスなど、ご自身の生活を振り返ることで、症状改善のヒントが見つかるでしょう。
食生活の乱れとガスの発生
食事は、腸内環境に最も直接的な影響を与えます。特に、脂肪分の多い食事や、香辛料などの刺激物は、腸の粘膜を刺激し、蠕動運動を活発にしすぎることで下痢の原因となります。
豆類、いも類、キャベツ、玉ねぎといった食品や、炭酸飲料は、腸内でガスを発生させやすいことで知られています。
一度にたくさん食べたり、早食いをしたりすると、消化不良を起こし、ガスと下痢の両方を引き起こしやすくなります。バランスの取れた食事を、よく噛んでゆっくり食べることが基本です。
ガスを発生させやすい食品の例
| 食品カテゴリー | 具体的な食品例 | 理由 |
|---|---|---|
| 豆類・いも類 | 大豆、あずき、さつまいも、じゃがいも | 食物繊維や消化しにくい糖質が豊富 |
| 野菜類 | キャベツ、ブロッコリー、玉ねぎ、にんにく | 硫黄化合物や発酵しやすい糖質を含む |
| その他 | 炭酸飲料、乳製品(乳糖不耐症の場合) | ガスそのものを含む、または分解酵素が不足 |
ストレスと腸の過敏な反応
脳と腸は、自律神経などを介して密接に連携しており、これを脳腸相関と呼びます。そのため、精神的なストレスを感じると、信号が腸に伝わり、腸の機能に異常をきたすことがあります。
ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、腸の蠕動運動が過剰になって下痢を起こしたり、逆に動きが鈍くなって便秘になったりするのです。
また、腸が知覚過敏の状態になり、通常では気にならない程度のガスの発生や腸の動きでも、強い腹痛や不快感として感じてしまうことがあります。
空気の飲み込みすぎ(呑気症)
呑気症(どんきしょう)とは、無意識のうちに大量の空気を飲み込んでしまい、胃や腸に溜まることで、げっぷやおなかの張り、ガスなどの症状を起こす状態です。
早食いや、麺類をすする、ガムをよく噛むといった習慣がある人は、空気を飲み込みやすい傾向があります。また、精神的なストレスや不安を感じると、唾液を飲み込む回数が増え、それに伴って空気も飲み込みやすいです。
溜まった空気が腸へと移動し、下痢などの他の症状と結びつくこともあります。
特定の食品に対する不耐性
病気というほどではないものの、特定の食品に含まれる成分をうまく消化・吸収できない体質(不耐性)が、ガスや下痢の原因となることがあり、代表的なものが乳糖不耐症です。
牛乳や乳製品に含まれる乳糖(ラクトース)を分解する酵素が少ないために、乳製品を摂ると下痢やガス、腹痛を起こすもので、日本人には比較的多い体質です。
他にも、果物に含まれる果糖や、人工甘味料などが原因で同様の症状が出る人もいます。特定のものを食べた後に症状が出やすい場合は、食品不耐性を疑う必要があります。
ガスと下痢を伴う代表的な消化器疾患
日常生活の改善を試みても、ガスや下痢の症状が長く続く場合、背景に何らかの消化器疾患が隠れている可能性があります。症状が似ていても、原因となる病気によって治療法は大きく異なります。
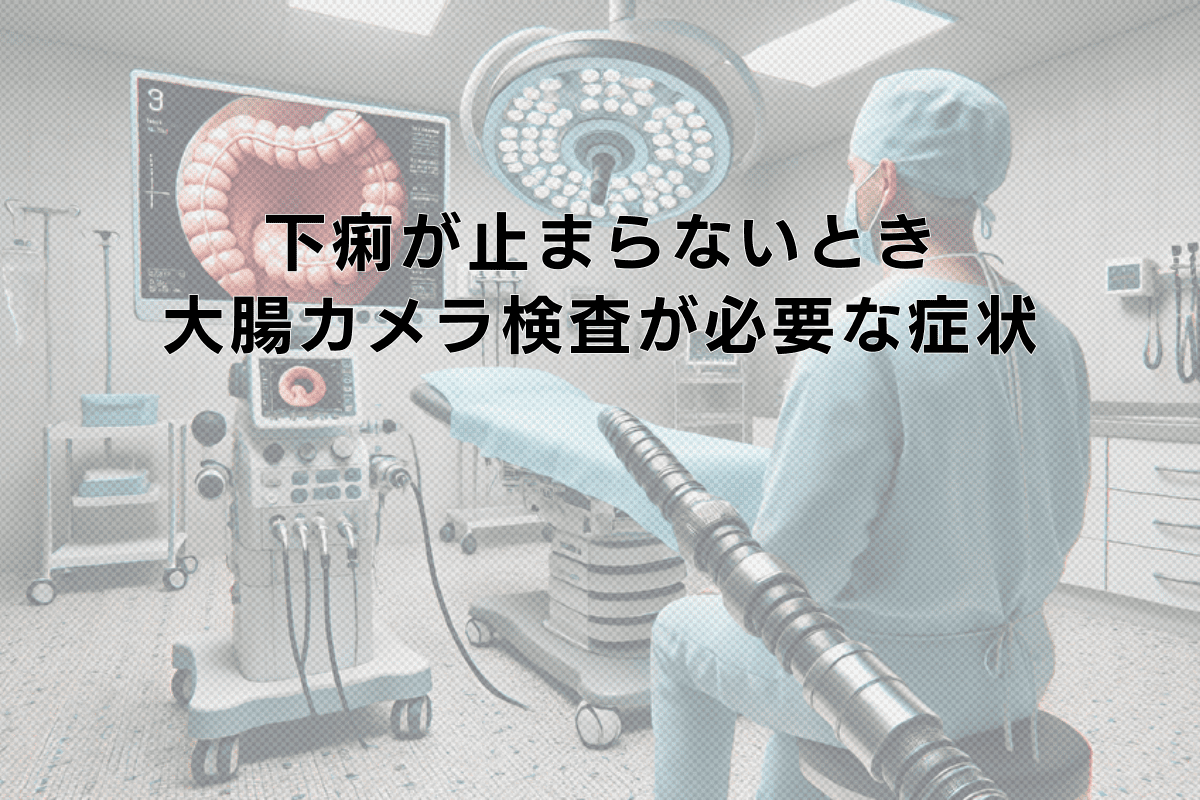
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(IBS)は、検査をしても腸に明らかな炎症や潰瘍などの異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感、そして便通異常(下痢や便秘)が慢性的に続く病気です。
ストレスが症状の悪化に関わっていることが多く、脳腸相関の異常が主な原因と考えられています。IBSはいくつかのタイプに分類され、下痢が主な症状である下痢型、便秘が主な便秘型、そして下痢と便秘を繰り返す混合型があります。
特に下痢型では、突然の激しい便意と共に、ガスを伴う下痢が頻繁に起こることが特徴です。
IBSとIBDの主な違い
| 項目 | 過敏性腸症候群(IBS) | 炎症性腸疾患(IBD) |
|---|---|---|
| 腸の状態 | 内視鏡で明らかな異常は見られない | 腸の粘膜に炎症や潰瘍が見られる |
| 主な原因 | ストレス、脳腸相関の異常など機能的な問題 | 免疫系の異常による器質的な問題 |
| 特徴的な症状 | 腹痛、便通異常(下痢・便秘)、ガス | 腹痛、下痢、血便、発熱、体重減少 |
感染性胃腸炎
ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルスなど)や細菌(カンピロバクター、サルモネラ菌など)への感染によって引き起こされるのが感染性胃腸炎です。一般的に食あたりや食中毒と呼ばれる状態もこれに含まれます。
主な症状は、突然の下痢、吐き気、嘔吐、腹痛、発熱などです。病原体が腸の粘膜にダメージを与えたり、毒素を出したりすることで腸が炎症を起こし、激しい下痢となります。
この過程で腸内環境も大きく乱れるため、回復期にガスの発生が増えることもあります。通常は数日から1週間程度で改善しますが、症状が激しい場合は脱水に注意が必要です。
炎症性腸疾患(IBD)
炎症性腸疾患(IBD)は、腸に慢性的な炎症や潰瘍を起こす原因不明の病気の総称で、主に潰瘍性大腸炎とクローン病の二つがあります。
どちらも免疫系の異常が関与していると考えられており、良くなったり悪くなったりを繰り返す(再燃と寛解)のが特徴で、主な症状は、長期にわたる下痢、血便、腹痛、発熱、体重減少などです。
腸の炎症によって消化吸収機能が低下し、慢性的な下痢やガスの発生が見られます。過敏性腸症候群と症状が似ていることもありますが、IBDは腸に器質的な変化を伴う、全く異なる病気です。
小腸内細菌増殖症(SIBO)
小腸内細菌増殖症(SIBO)は、本来は細菌が少ないはずの小腸で、細菌が異常に増殖してしまう病態です。
増殖した細菌が、小腸で消化されるべき糖質などを早期に発酵させてしまうため、大量のガス(水素やメタン)が発生し、おなかの張り、腹痛、げっぷなどの症状が起こります。
また、産生されたガスや細菌の代謝物が腸を刺激し、下痢や便秘を起こすこともあります。過敏性腸症候群と診断された人の中に、実はSIBOが隠れているケースも少なくありません。
- 慢性的なおなかの張り、腹部膨満感
- 原因不明の下痢または便秘
- げっぷやガスの増加
- 腹痛
自分でできる症状緩和のためのセルフケア
医療機関での適切な診断と治療が基本ですが、日々の生活の中でセルフケアを実践することも、不快な症状を和らげ、再発を防ぐ上で非常に重要です。特に、食事の内容や食べ方、ストレス管理は、腸の健康に直接影響します。
ガスを発生させにくい食事の工夫
おなかの張りに悩む方は、ガスを発生させやすい食品を一度にたくさん摂るのを避ける工夫が有効です。いも類や豆類、食物繊維の多い野菜を食べるときは、少量から試したり、よく加熱して消化しやすくしたりすると良いでしょう。
また、低FODMAP(フォドマップ)食という食事法も注目されています。これは、腸で発酵しやすい特定の糖質(FODMAP)を多く含む食品を一時的に制限する方法で、過敏性腸症候群の症状改善に効果があると報告されています。
ただし、自己流で厳格に行うと栄養が偏る可能性もあるため、試す場合は専門家のアドバイスを受けるのが望ましいです。
低FODMAP食で避ける食品と推奨される食品の例
| 分類 | 避けるべき食品(高FODMAP) | 推奨される食品(低FODMAP) |
|---|---|---|
| 野菜 | 玉ねぎ、にんにく、ごぼう、アスパラガス | トマト、きゅうり、なす、にんじん、ほうれん草 |
| 果物 | りんご、梨、桃、スイカ、マンゴー | バナナ、いちご、ぶどう、オレンジ、キウイ |
| 穀物 | 小麦、ライ麦(パン、パスタなど) | 米、米粉パン、オートミール(少量) |
腸内環境を整える食生活
長期的な視点で見ると、腸内フローラのバランスを整えることが、ガスや下痢に悩まされない体質づくりの鍵となります。善玉菌を多く含むヨーグルト、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品を日常的に食事に取り入れましょう。
同時に、善玉菌のエサとなる水溶性食物繊維(海藻類、大麦、果物など)やオリゴ糖(玉ねぎ、ごぼう、バナナなど)も一緒に摂ると、より効果的です。
ただし、下痢の症状が強い時は、食物繊維が刺激になることもあるため、体調を見ながら量を調整することが大切です。

ストレスとの上手な付き合い方
脳と腸の密接な関係を考えると、ストレス管理は欠かせないセルフケアの一つで、まずは、十分な睡眠と休息を確保し、心身の疲労を回復させることが基本です。その上で、自分がリラックスできる時間を持つことを意識しましょう。
軽い運動やストレッチ、趣味への没頭、ゆっくりとした入浴、好きな音楽を聴くなど、方法は人それぞれです。
腹式呼吸は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせるのに効果的で、1日数分でも良いので、意識的に深い呼吸をする習慣を取り入れてください。
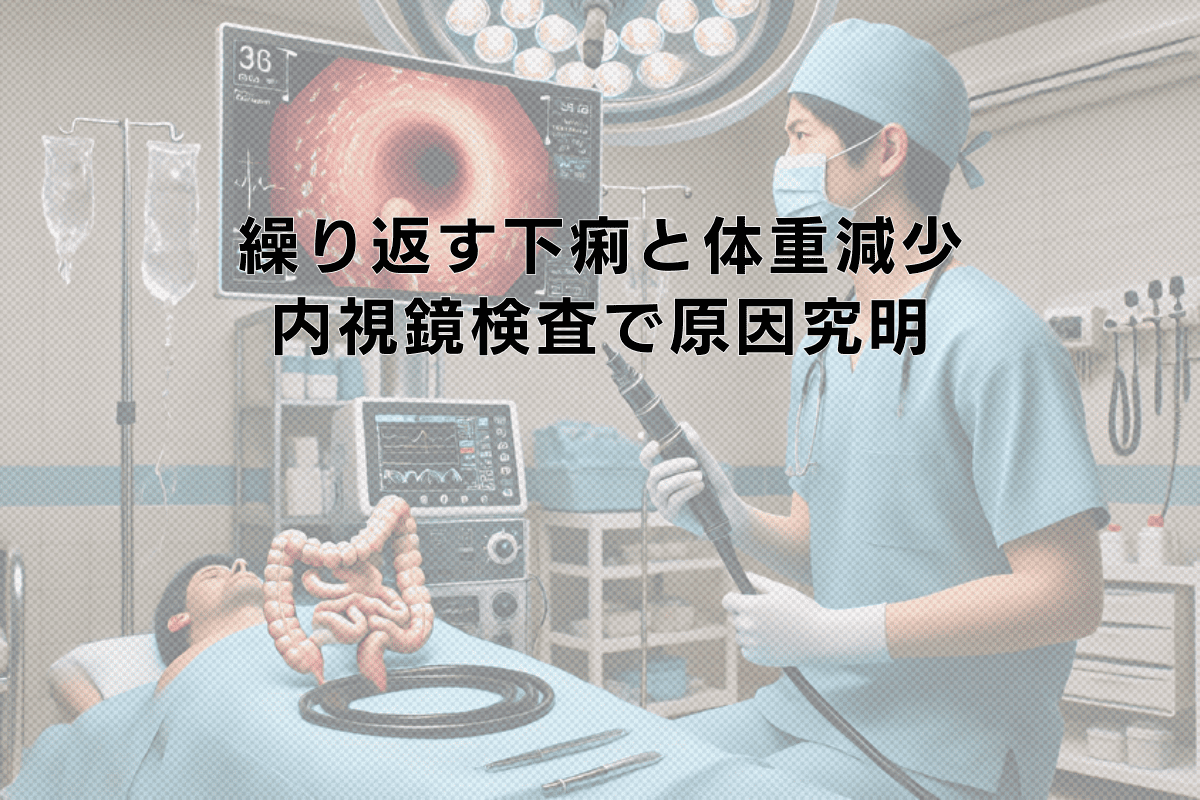
適度な運動のすすめ
定期的な運動は、腸の働きを正常に保つ上で多くのメリットがあります。ウォーキングやヨガ、水泳などの有酸素運動は、全身の血行を促進し、腸の蠕動運動を穏やかに整える助けとなります。
また、運動は気分転換になり、ストレス解消にも非常に効果的です。激しい運動はかえって腸への負担となることがあるため、自分が心地よいと感じるペースで、継続できるものを見つけることが重要です。
日常生活の中で、一駅分歩く、階段を使うなど、少しでも体を動かす機会を増やすことから始めてみましょう。
医療機関での検査の重要性
セルフケアは症状緩和に有効ですが、根本的な原因を特定し、適切な治療を受けるためには、専門の医療機関での検査が不可欠です。特に、症状が長引く場合や、生活に支障が出ている場合は、自己判断で様子を見続けるべきではありません。
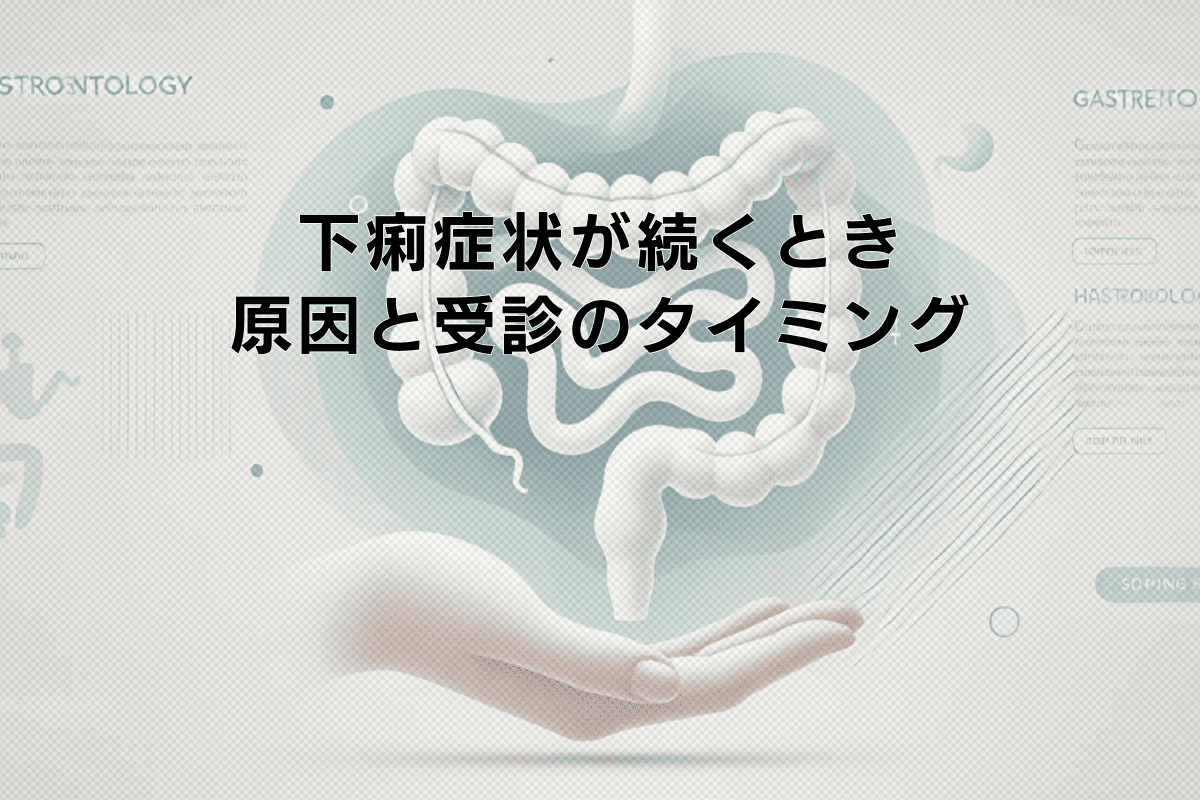
なぜ専門家による診断が必要なのか
おなかのガスと下痢という症状は、比較的ありふれたものである一方、背後には様々な原因が考えられます。
食生活やストレスといった生活習慣に起因するものから、過敏性腸症候群(IBS)、さらには炎症性腸疾患(IBD)や、まれに大腸がんといった重篤な病気まで、可能性は多岐にわたります。
これらの病気は、専門的な検査を行わなければ正確に区別することはできません。正しい診断が治療への第一歩であり、不必要な不安を解消することにもつながります。
放置するリスクと隠れた病気
たかがガスや下痢と軽視して放置すると、思わぬリスクにつながることがあります。
炎症性腸疾患(IBD)のような病気の場合、治療が遅れると炎症が進行し、腸が狭くなったり(狭窄)、穴が開いたり(穿孔)する合併症を引き起こす可能性があります。
また、長期にわたる下痢は、栄養障害や脱水、貧血の原因にもなります。何よりも、症状の裏に大腸がんなどの見逃してはならない病気が隠れている可能性もゼロではありません。
早期発見・早期治療のためにも、続く症状は放置しないことが鉄則です。
- 炎症性腸疾患(IBD)の進行
- 大腸がんなどの重篤な病気の見逃し
- 慢性的な栄養障害や脱水
- 生活の質(QOL)の著しい低下
症状を正確に伝えるための準備
診察を受ける際には、ご自身の症状をできるだけ具体的に医師に伝えることが、正確な診断に大きく役立ちます。
いつから症状が始まったか、どのような時に悪化するか、便の性状(色、形、血は混じっていないか)、ガスの頻度、腹痛の場所や性質など、事前にメモにまとめておくと良いでしょう。
また、食事内容や生活での変化、ストレスの有無、服用中の薬なども重要な情報で、症状日記をつけることも客観的に自分の状態を把握し、医師に伝える上で非常に有効です。
医師に伝えるべき情報
| 情報カテゴリー | 具体的な内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 症状の詳細 | 開始時期、頻度、便の性状、腹痛の場所と性質 | 原因疾患を推測するための最も重要な手がかり |
| 生活背景 | 食事内容、ストレスの有無、海外渡航歴、生活の変化 | 生活習慣に起因する原因や感染症などを探るため |
| 既往歴・服薬歴 | 過去の病気、家族歴、服用中の薬、サプリメント | 関連する病気の可能性や薬の副作用を考慮するため |
自己判断による市販薬のリスク
ドラッグストアでは様々な胃腸薬が手に入りますが、自己判断での使用には注意が必要です。下痢止め薬は、細菌やウイルスを体外に排出しようとする体の防御反応を妨げてしまい、かえって病状を悪化させることがあります。
特に、血便や発熱を伴う下痢の場合、下痢止め薬の使用は原則として避けるべきです。原因がわからないまま市販薬を使い続けることで、本来受けるべき治療の機会を逃してしまう可能性もあります。
消化器内科で行う主な検査
消化器内科では、ガスや下痢の原因を特定するために、症状や診察所見に応じて様々な検査を組み合わせて行います。ここでは、代表的な検査と目的について説明します。
問診と身体診察
すべての診断の基本となるのが、問診と身体診察です。問診では、前述したような症状の詳細や生活習慣、既往歴などを詳しく聞き取ります。
身体診察では、聴診器でおなかの音(腸の動き)を確認したり、おなかを触って張りや痛みの場所、しこりの有無などを調べたりします。これらの情報から、医師はある程度の原因を推測し、次に必要となる検査を判断します。
血液検査・便検査
血液検査では、体内で炎症が起きていないか(CRP、白血球数など)、貧血はないか、栄養状態はどうか、肝臓や腎臓の機能に異常はないかなど、全身の状態を幅広く調べることができます。便検査は、腸内の情報を得るために非常に重要です。
便に血液が混じっていないか(便潜血検査)、O-157などの病原性細菌がいないか、寄生虫はいないかなどを調べ、検査は、患者さんの負担が少なく、多くの情報を得られる基本的な検査です。
便検査でわかることの例
| 検査項目 | 主な目的 | 疑われる状態や病気 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 消化管からの目に見えない出血の有無を調べる | 大腸がん、ポリープ、炎症性腸疾患など |
| 便培養検査 | 下痢の原因となる細菌の有無を調べる | 感染性胃腸炎(サルモネラ、カンピロバクターなど) |
| 便中カルプロテクチン | 腸の炎症の程度を数値で評価する | 炎症性腸疾患の診断補助や活動性の評価 |
腹部超音波(エコー)検査
腹部超音波検査は、超音波を使っておなかの中の臓器の状態を画像として映し出す検査です。肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓などの実質臓器のほか、腸管の壁が厚くなっていないか、腹水が溜まっていないかなどを観察します。
痛みや放射線被ばくの心配がなく、体への負担が少ないため、スクリーニング検査として広く用いられます。特に、胆石や脂肪肝、腸のむくみなどの評価に有用です。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
症状の原因を特定するために最も重要な検査の一つが内視鏡検査です。
口や鼻から細いカメラを挿入して食道・胃・十二指腸を観察するのが胃カメラ(上部消化管内視鏡)、肛門からカメラを挿入して大腸全体を観察するのが大腸カメラ(下部消化管内視鏡)です。
粘膜の状態を直接見ることができるため、炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの病変を正確に診断できます。また、検査中に疑わしい部分の組織を少量採取し(生検)、顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査を行うことも可能です。
よくある質問
最後に、おなかのガスと下痢に関する症状で、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
- 症状はどれくらい続いたら受診すべきですか
-
明確な基準はありませんが、一般的に、市販の整腸剤などを試しても症状が2週間以上続く場合は、一度医療機関を受診することを推奨します。
また、期間にかかわらず、下痢に血が混じる、急激な体重減少がある、夜中に腹痛で目が覚める、発熱を伴う、といった症状がある場合は、早めに専門医に相談してください。
- 食物アレルギーとの違いは何ですか
-
食物アレルギーは、特定の食品(アレルゲン)に対して、体の免疫系が過剰に反応して起こるものです。
腹痛や下痢といった消化器症状のほかに、じんましん、皮膚のかゆみ、咳、呼吸困難など、全身に症状が現れることが多いのが特徴です。
一方、食物不耐症や過敏性腸症候群は、免疫系が直接関与するものではなく、症状は主に消化器系に限られます。ただし、鑑別が難しい場合もあるため、専門医による診断が重要です。
- 子供でも同じような症状は起こりますか
-
子供の場合は、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎が原因であることが多いです。また、牛乳などを飲み始めた時期に乳糖不耐症の症状が出たり、特定の食品が体質に合わなかったりすることもあります。
ストレスが原因となる過敏性腸症候群も、小学生高学年くらいから見られるようになります。
お子さんの場合は、大人に比べて脱水症状を起こしやすいため、下痢が続く場合は特に注意深く様子を見て、早めに小児科や消化器内科を受診してください。
- プロバイオティクスは効果がありますか
-
プロバイオティクスは、ヨーグルトや整腸剤などに含まれる、体に良い影響を与える生きた微生物のことです。腸内フローラのバランスを整えることで、便通を改善したり、腸のバリア機能を高めたりする効果が期待できます。
過敏性腸症候群の症状緩和に有効であるという研究報告も多くあります。ただし、効果の現れ方には個人差があり、また、菌の種類によっても働きが異なります。
次に読むことをお勧めする記事
【毎日の下痢症状が続くときの大腸内視鏡検査による診断基準】
ガスと下痢の基本を押さえたら、次は実際の検査で何がわかるかを知ると安心です。受診の迷いがある方に特に役立つ内容です。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
ガスや下痢の背景には腸内環境があります。食事・睡眠・ストレスを含む総合的な整え方を押さえると、再発予防の見通しが立ちます。
参考文献
Lacy BE, Cangemi D, Vazquez-Roque M. Management of chronic abdominal distension and bloating. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2021 Feb 1;19(2):219-31.
Azpiroz F, Malagelada JR. Abdominal bloating. Gastroenterology. 2005 Sep 1;129(3):1060-78.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Schiller LR. Chronic diarrhea. GI/Liver Secrets Plus E-Book: GI/Liver Secrets Plus E-Book. 2014 Nov 17:414.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Jones MP. Bloating and intestinal gas. Current Treatment Options in Gastroenterology. 2005 Aug;8(4):311-8.
Malagelada JR, Accarino A, Azpiroz F. Bloating and abdominal distension: old misconceptions and current knowledge. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2017 Aug 1;112(8):1221-31.
Hasler WL. Gas and bloating. Gastroenterology & hepatology. 2006 Sep;2(9):654.
Foley A, Burgell R, Barrett JS, Gibson PR. Management strategies for abdominal bloating and distension. Gastroenterology & hepatology. 2014 Sep;10(9):561.
Wilkinson JM, Cozine EW, Loftus CG. Gas, bloating, and belching: approach to evaluation and management. American family physician. 2019 Mar 1;99(5):301-9.