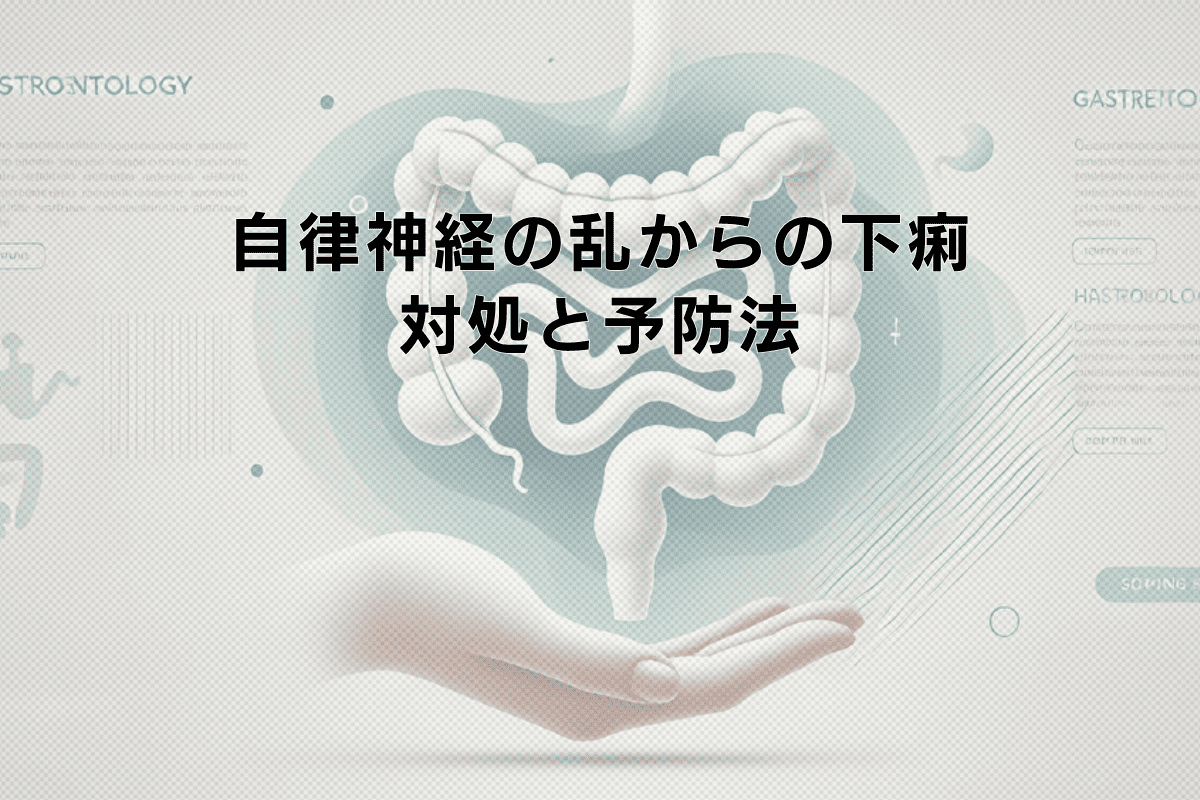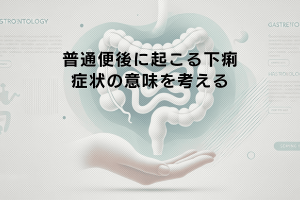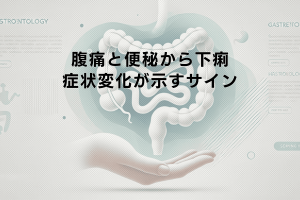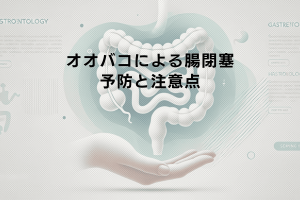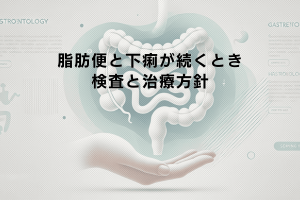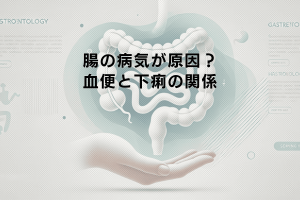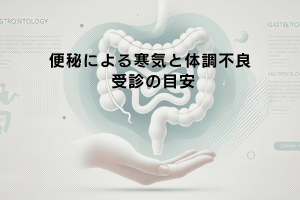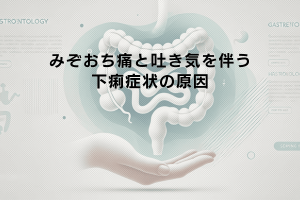ストレス社会といわれる現代において、原因の特定が難しい体調不良に悩む方が増えていて、特に、お腹の不調、中でも急な下痢は、日常生活に大きな影響を与えます。
背景には、自律神経の乱れが関係していることが少なくありません。
この記事では、自律神経の乱れがなぜ下痢を起こすのか、そして私たちが日々実践できる対処法や予防策について、分かりやすく解説します。
自律神経とは?その役割とバランスの重要性
私たちの身体は、意識しなくても心臓が動き、呼吸をし、食べたものを消化するなど、生命を維持するための様々な活動を自動的に行っていて、活動をコントロールしているのが自律神経です。
自律神経の基本的な働き
自律神経は、内臓の働き、血液循環、体温調節、消化吸収、ホルモン分泌など、生命維持に欠かせない機能を24時間体制で調整していて、私たちが眠っている間も、自律神経は休むことなく働き続けています。
この神経系は、私たちの意思とは無関係に働くため、「自律」神経と呼ばれます。
交感神経と副交感神経の役割分担
自律神経は、交感神経と副交感神経という2つの神経から成り立っていて、互いに反対の作用を持ち、状況に応じて切り替わることで身体のバランスを保っています。
交感神経と副交感神経の働き
| 項目 | 交感神経(活動・緊張モード) | 副交感神経(リラックス・休息モード) |
|---|---|---|
| 心拍数 | 増加させる | 減少させる |
| 血管 | 収縮させる(血圧上昇) | 拡張させる(血圧下降) |
| 消化管の動き | 抑制する | 促進する |
例えるなら、交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキのような役割です。日中活動している時や緊張している時は交感神経が優位になり、リラックスしている時や睡眠中は副交感神経が優位になります。
自律神経のバランスが崩れるとは?
健康な状態では、交感神経と副交感神経がシーソーのようにバランスを取りながら働いていますが、ストレス、不規則な生活、睡眠不足、偏った食事などが続くと、このバランスが崩れてしまいます。
どちらか一方が過剰に働いたり、両方の働きが低下したりする状態が自律神経の乱れや自律神経失調です。
バランスの乱れが引き起こす身体への影響
自律神経のバランスが崩れると、身体の様々な部分に不調が現れ、頭痛、めまい、動悸、息切れ、肩こり、不眠、そして消化器系の症状である便秘や下痢なども、自律神経の乱れが原因で起こることがあります。
症状は多岐にわたり、人によって現れ方も異なります。
なぜ自律神経の乱れが下痢を起こすのか
自律神経のバランスが崩れると、なぜ下痢という症状が現れるのでしょうか。ここでは、腸の働きと自律神経の密接な関係について解説します。
腸の動きと自律神経の関係
腸の蠕動(ぜんどう)運動、つまり食べ物を消化・吸収しながら肛門へと運ぶ動きは、自律神経によってコントロールされていて、特に副交感神経が優位になると腸の動きは活発になり、交感神経が優位になると抑制されます。
このコントロールがうまくいかなくなると、腸の動きに異常が生じます。
ストレスと腸の過敏性
強いストレスを感じると、交感神経が過剰に刺激され、腸の動きが一時的に抑制された後、反動で副交感神経が過剰に働き、腸が異常に収縮したり、痙攣することがあります。
また、ストレスは腸の知覚過敏を起こし、わずかな刺激でも腹痛や便意を感じやすくなることがあり、これが過敏性腸症候群(IBS)の要因の一つです。
ストレスが腸に与える影響
| ストレスの種類 | 腸への影響(例) | 結果として起こりうること |
|---|---|---|
| 精神的ストレス(不安、緊張) | 腸の蠕動運動の異常 | 下痢、便秘、腹痛 |
| 身体的ストレス(過労、睡眠不足) | 腸内環境の悪化 | 免疫力低下、下痢 |
| 環境的ストレス(温度変化、騒音) | 自律神経の乱れ | 消化機能の低下 |
蠕動運動の異常と水分吸収
自律神経の乱れによって腸の蠕動運動が過剰に活発になると、食べたものが急速に腸を通過してしまい、腸内で十分に水分が吸収される前に便として排出されるため、便が緩くなり下痢を起こします。
逆に、蠕動運動が低下すると便秘になることもあります。
腸内フローラの乱れとの関連性
腸内には多種多様な細菌が生息しており、腸内フローラと呼ばれる生態系を形成していて、自律神経の乱れやストレスは、この腸内フローラのバランスを崩し、悪玉菌が増殖しやすい環境を作ることがあります。
腸内環境が悪化すると、腸の機能が低下し、下痢や便秘といった症状が現れやすいです。
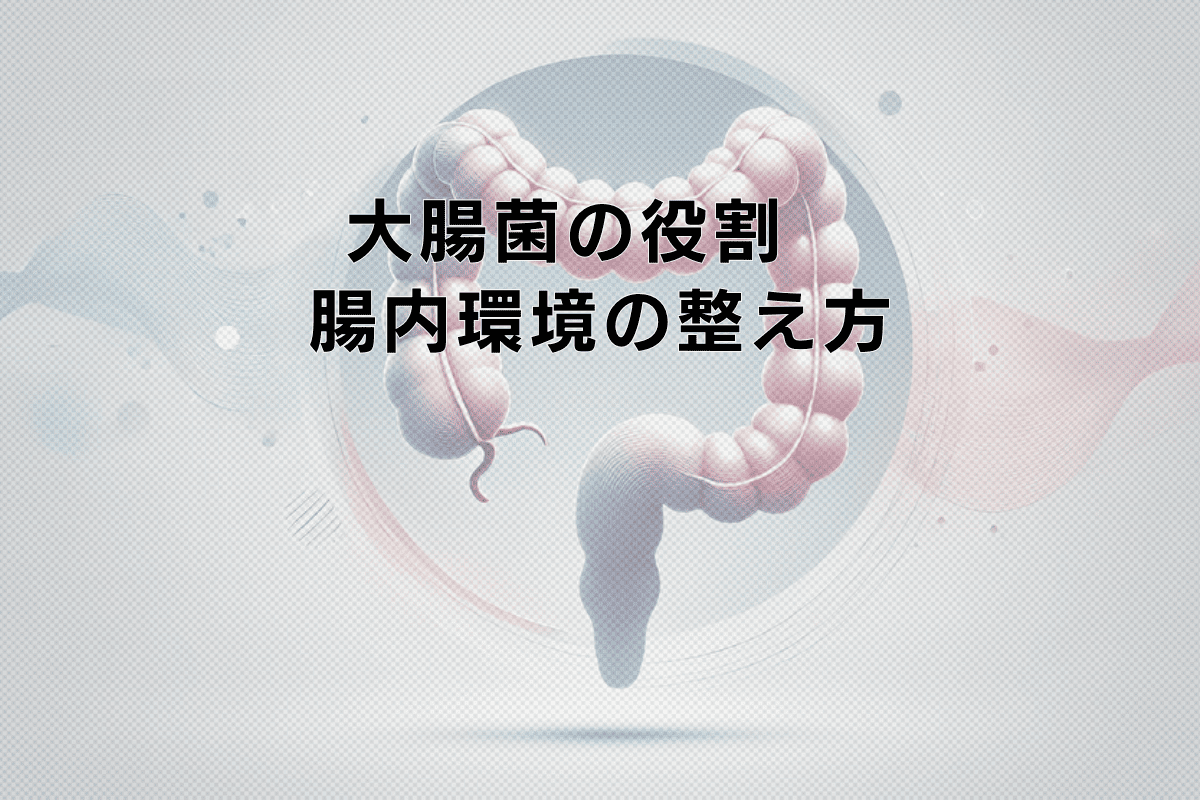
自律神経の乱れによる下痢の特徴的な症状
自律神経の乱れが原因で起こる下痢には、いくつかの特徴的な症状が見られます。
突然起こる便意と腹痛
特に外出中や会議中など、緊張する場面やストレスを感じる状況で、突然強い便意に襲われ、差し込むような腹痛を伴うことがあり、トイレに行くと症状が一時的に和らぐものの、また繰り返すことも少なくありません。
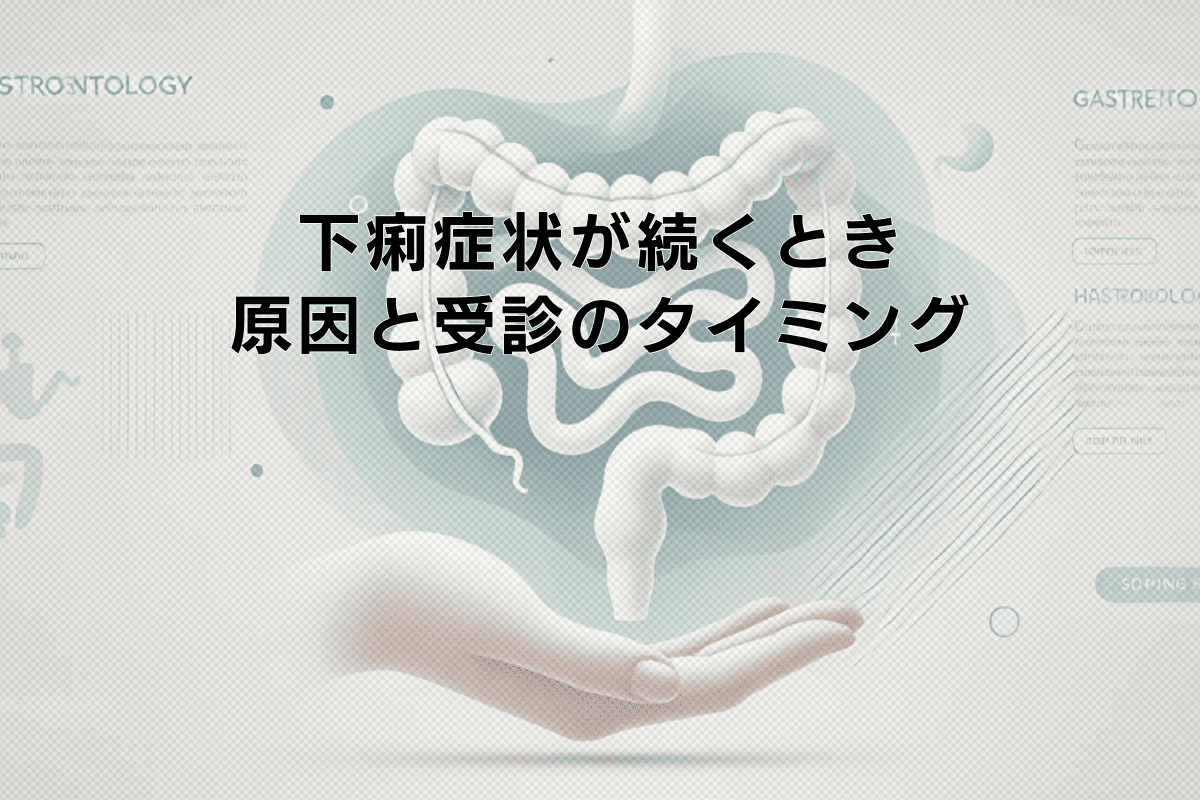
ストレスを感じると症状が悪化する
精神的なプレッシャーや不安、緊張が高まると、下痢の症状が悪化する傾向があり、試験前や大事なプレゼンテーションの前、電車に乗っている時などに症状が出やすいと感じる方がいます。
便秘と下痢を繰り返す場合もある
常に下痢が続くわけではなく、数日間は便秘だったのに、その後急に下痢になるというように、便通異常を繰り返すことも特徴の一つです。これは、自律神経のバランスが不安定で、腸の動きが正常にコントロールされていないために起こります。
下痢と便秘のサイクル
- 数日間の便秘
- 突然の腹痛と下痢
- 症状の一時的な改善
- 再び便秘へ
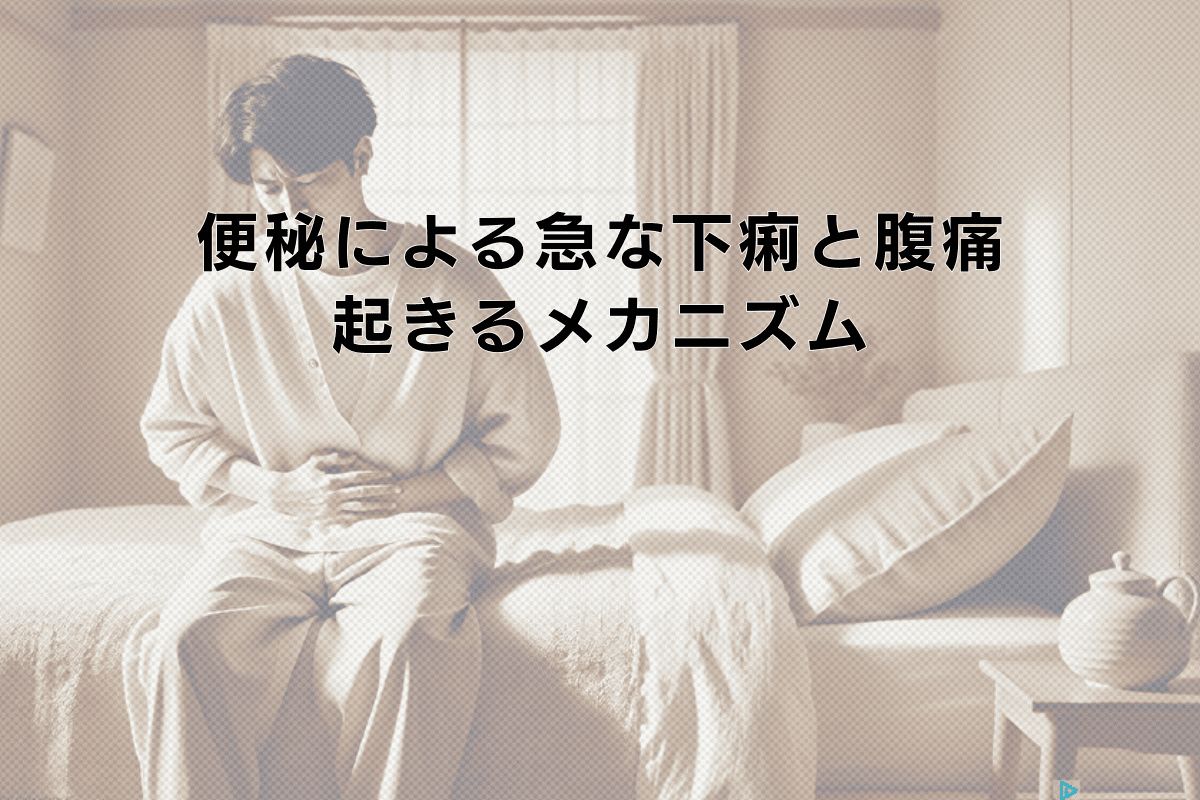
他の身体症状を伴うことも
自律神経の乱れは全身に影響を及ぼすため、下痢だけでなく、頭痛、肩こり、めまい、不眠、動悸、吐き気、食欲不振、疲労感など、他の身体的な不調や精神的な症状を伴うことがよくあります。
伴いやすい他の症状
| 身体的症状 | 精神的症状 |
|---|---|
| 頭痛、めまい | 不安感、イライラ |
| 動悸、息切れ | 気分の落ち込み |
| 肩こり、倦怠感 | 集中力低下 |
日常生活でできる自律神経の乱れによる下痢への対処法
自律神経の乱れによる下痢は、日常生活の見直しによって症状の改善が期待できます。ここでは、具体的な対処法を紹介します。
食生活の見直しと改善点
腸に負担をかけない食事を心がけることが大切です。消化しやすく、腸内環境を整える食事を意識しましょう。
消化の良い食べ物の選び方
おかゆ、うどん、白身魚、鶏のささみ、豆腐、バナナ、りんごなどは消化が良く、調理法も、煮る、蒸すなど油をあまり使わない方法を選んでください。
避けるべき刺激物
香辛料の多い食事、脂っこいもの、冷たい飲み物や食べ物、アルコール、カフェインを多く含む飲料(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)は、腸を刺激し下痢を悪化させる可能性があるため、控えましょう。
食事の注意点まとめ
| 推奨されること | 避けるべきこと |
|---|---|
| 温かく消化の良い食事 | 冷たい飲食物、刺激物 |
| よく噛んでゆっくり食べる | 早食い、ドカ食い |
| 規則正しい時間に食事をする | 不規則な食事、夜遅い食事 |

ストレスマネジメントの具体的な方法
ストレスは自律神経の大きな敵です。自分に合ったストレス解消法を見つけ、上手に付き合っていくことが重要です。
リラックスできる時間を作る
忙しい毎日の中でも、意識してリラックスできる時間を作りましょう。好きな音楽を聴く、温かいお風呂にゆっくり浸かる、アロマテラピーを楽しむなど、自分が心地よいと感じる方法で心身を休ませることが大切です。
趣味や運動を取り入れる
趣味に没頭する時間や、ウォーキングやヨガなどの軽い運動は、気分転換になりストレス軽減に役立ち、運動は血行を促進し、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
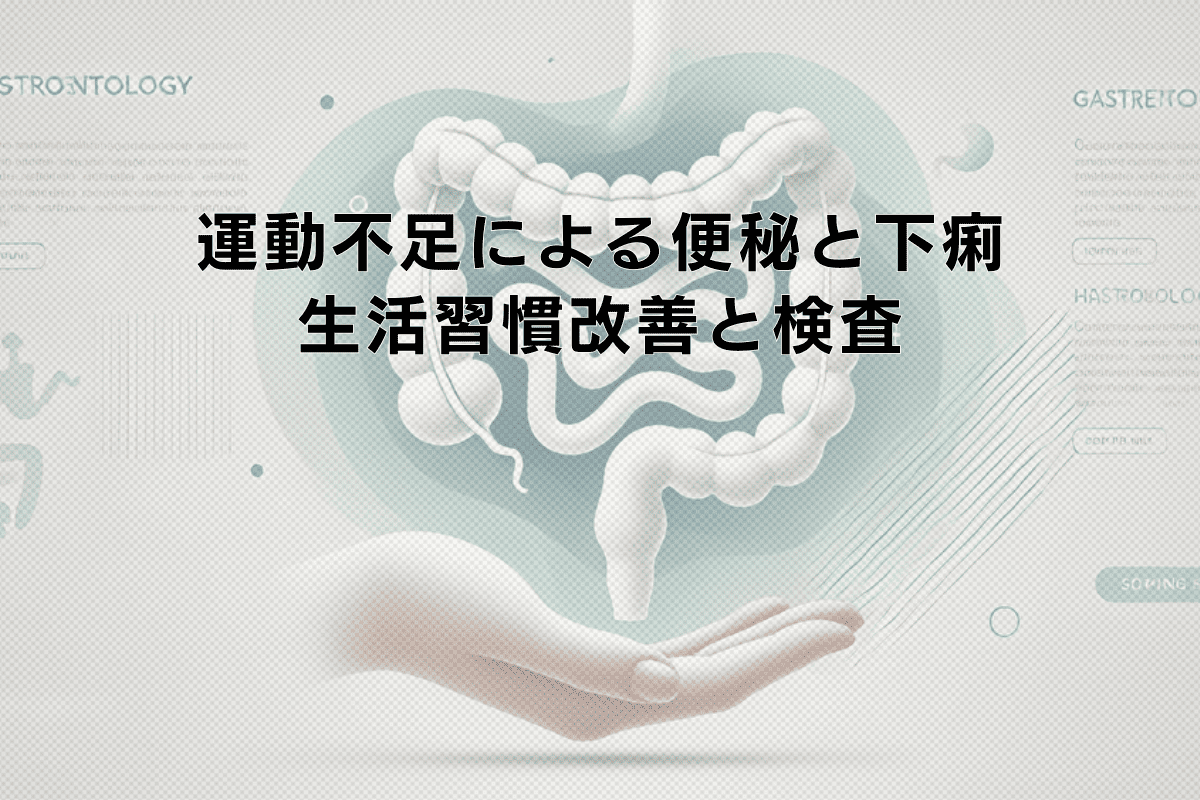
睡眠の質を高める工夫
質の高い睡眠は、自律神経のバランスを整えるために非常に重要です。睡眠不足は自律神経の乱れを助長し、下痢の症状を悪化させる可能性があります。
就寝前の過ごし方
就寝前は、スマートフォンやパソコンなどの強い光を避け、カフェインの摂取も控え、リラックスできる音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりするのも一案です。
寝室環境の整備
寝室の温度や湿度、明るさなどを快適に保ち、自分に合った寝具を選ぶことも質の高い睡眠につながります。
睡眠改善のためのポイント
- 毎日同じ時間に寝起きする
- 寝る前のカフェイン・アルコールを避ける
- 寝る直前の食事は控える
- 適度な運動習慣を持つ
症状緩和に役立つセルフケアと注意点
日常生活での対処法に加えて、症状が出た時に試せるセルフケアや、気をつけるべき点について説明します。
お腹を温めることの効果
お腹を温めると、腸の血行が良くなり、過剰な蠕動運動が和らぎ、腹巻きをしたり、カイロを貼ったり(低温やけどに注意)、温かい飲み物をゆっくり飲んだりするのも良いでしょう。
適度な運動のすすめ
激しい運動は症状を悪化させることがありますが、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、血行を促進し、ストレス解消にもつながり、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。無理のない範囲で継続することが大切です。
運動の種類と目安
| 運動の種類 | 頻度・時間の目安 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| ウォーキング | 毎日20~30分程度 | 血行促進、ストレス軽減 |
| ストレッチ・ヨガ | 毎日10~15分程度 | リラックス効果、柔軟性向上 |
| 軽いジョギング | 週2~3回、15~20分程度 | 体力向上、気分転換 |
市販薬を使用する際の注意点
下痢止めなどの市販薬は、一時的に症状を抑えるのに役立つ場合がありますが、自己判断で長期間使用し続けるのは避けましょう。
薬を使用しても症状が改善しない場合や、頻繁に繰り返す場合は、医療機関を受診することが重要です。薬剤師に相談し、用法・用量を守って正しく使用してください。
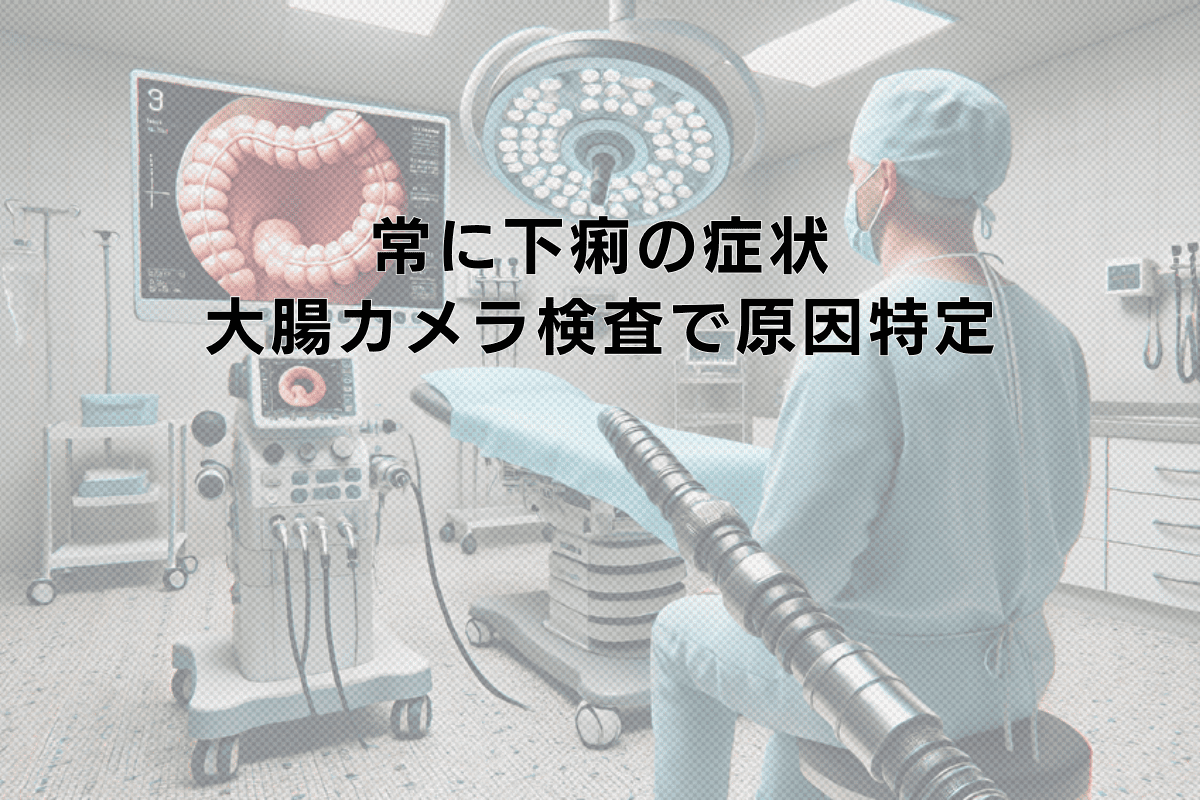
症状日記をつけることのメリット
いつ、どのような状況で症状が出やすいのか、食事内容やストレスの有無などを記録する症状日記をつけることは、自分の症状のパターンを把握するのに役立ちます。
また、医療機関を受診する際に、医師に正確な情報を提供するための貴重な資料となります。
症状日記に記録する項目
- 症状が出た日時
- 症状の具体的な内容(腹痛の程度、便の状態など)
- その日の食事内容
- ストレスを感じた出来事
- 睡眠時間
自律神経のバランスを整えるための予防策
症状が出てから対処するだけでなく、日頃から自律神経のバランスを整える生活を心がけることが、下痢の予防につながります。
規則正しい生活リズムの確立
自律神経は体内時計と深く関わっています。毎日同じ時間に寝起きし、食事の時間もできるだけ一定にすることで、体内時計が整い、自律神経のバランスも安定しやすいです。
起床・就寝時間の一定化
休日でも平日と大きく生活リズムを変えず、早寝早起きを心がけましょう。質の高い睡眠を確保することが、自律神経の安定には欠かせません。
食事の時間と内容
1日3食、決まった時間にバランスの取れた食事を摂り、特に朝食は、体内時計をリセットし、一日の活動をスタートさせるために重要です。
生活リズムを整えるポイント
| 習慣 | ポイント |
|---|---|
| 睡眠 | 毎日同じ時刻に就寝・起床する |
| 食事 | 1日3食、決まった時間に、バランス良く |
| 日中の活動 | 適度に太陽光を浴びる |
バランスの取れた食事の継続
腸内環境を良好に保つことは、自律神経の安定にもつながり、特定の食品に偏らず、多様な食材を摂取することが大切です。
腸内環境を整える食材
食物繊維が豊富な野菜、きのこ類、海藻類や、発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)を積極的に摂ると、善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを整えるのに役立ちます。
水分補給の重要性
下痢の症状がある時はもちろん、普段からこまめな水分補給を心がけましょう。ただし、冷たすぎる飲み物は腸を刺激することがあるので、常温か温かい飲み物がおすすめです。
効果的なリフレッシュ方法
日常生活の中で上手に気分転換をし、ストレスを溜め込まないようにすることが予防につながります。
短時間でできる気分転換
仕事や勉強の合間に深呼吸をする、軽いストレッチをする、窓を開けて外の空気を吸うなど、短時間でも意識的にリフレッシュする時間を取り入れてください。
定期的な休息と心身のケア
疲労は自律神経の乱れを起こす大きな要因になります。無理をせず、疲れを感じたら早めに休息を取り、また、自分の心と体の声に耳を傾け、セルフケアを怠らないことが大切です。
医療機関を受診する目安と受診時のポイント
セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、日常生活に支障をきたすような場合は、医療機関を受診することを検討しましょう。
こんな症状が出たら医療機関へ
以下のような症状が見られる場合は、自己判断せずに医療機関に相談してください。
- 下痢が1週間以上続く
- 発熱や血便がある
- 体重が急激に減少した
- 夜間に下痢で目が覚める
- 症状がどんどん悪化している
これらの症状は、他の消化器疾患の可能性も考えられるため、専門医による正確な診断が必要です。
どの診療科を受診すべきか
まずはかかりつけの内科医に相談するか、消化器内科や心療内科の受診を検討しましょう。
受診を検討する診療科
| 診療科 | 主な対象 |
|---|---|
| 内科・消化器内科 | 一般的な腹痛、下痢、便秘などの消化器症状全般 |
| 心療内科・精神科 | ストレスが強く関与していると考えられる場合、精神的な不調も伴う場合 |
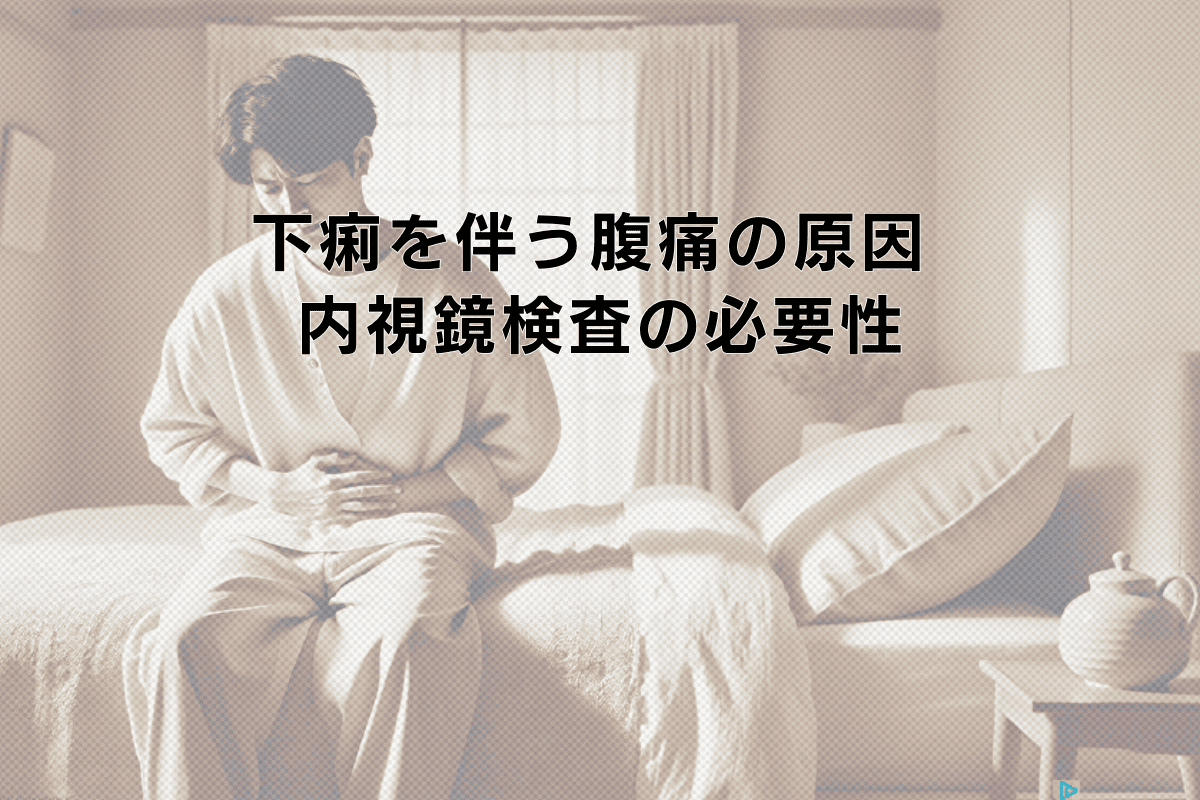
医師に伝えるべき情報
診察時には、医師にできるだけ正確に症状や状況を伝えることが、適切な診断と治療につながります。事前に情報を整理しておくと良いでしょう。
症状の具体的な内容
いつから症状があるのか、どのような時に症状が出やすいか、便の状態(水様便、泥状便など)、腹痛の有無や程度、下痢以外の症状(吐き気、発熱、体重減少など)について具体的に伝えてください。
生活習慣やストレス状況
普段の食事内容、睡眠時間、飲酒や喫煙の習慣、仕事や家庭環境におけるストレスの状況なども重要な情報で、正直に伝えることが大切です。
医師に伝える情報
| 項目 | 伝える内容の例 |
|---|---|
| 症状の開始時期 | 約1ヶ月前から、など |
| 症状の頻度・タイミング | 毎朝、食後、緊張した時、など |
| 便の状態 | 水っぽい、形がない、粘液が混じる、など |
| 既往歴・服用中の薬 | 過去にかかった病気、現在飲んでいる薬 |
検査や治療の流れ
医療機関では、問診に加えて、必要に応じて血液検査、便検査、腹部X線検査、大腸内視鏡検査などが行われることがあり、検査によって、他の病気が隠れていないかを確認し、治療方針を決定します。
治療は、生活習慣の改善指導、食事療法、薬物療法(整腸剤、抗不安薬、抗コリン薬など)が中心です。
よくある質問
自律神経の乱れによる下痢に関して、多くの方が疑問に思う点をまとめました。
- 自律神経の乱れによる下痢は治りますか?
-
適切な対処と生活習慣の見直しにより、症状をコントロールし、改善することは十分に可能です。
ただし、完治というよりは、症状とうまく付き合っていく、あるいは症状が出にくい状態を維持するという考え方が近いかもしれません。根気強く治療やセルフケアを続けることが大切です。
- 食事以外で気をつけることはありますか?
-
食事以外では、十分な睡眠、適度な運動、ストレスを溜めない工夫が重要で、特に、質の高い睡眠は自律神経のバランスを整える上で非常に大切です。
また、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、アロマテラピーを取り入れるなど、リラックスできる習慣を見つけるのも良いでしょう。喫煙や過度な飲酒は自律神経のバランスを乱すため、控えることをおすすめします。
- 子供でも自律神経の乱れで下痢になりますか?
-
子供でも自律神経の乱れによって下痢や腹痛などの症状が出ることがあります。学校生活でのストレス、友人関係の悩み、受験勉強などが原因となることがあります。
大人の場合と同様に、規則正しい生活、バランスの取れた食事、十分な睡眠、そしてストレスケアが重要です。気になる症状が続く場合は、小児科医や専門医に相談してください。
- 薬を飲み続けないとダメですか?
-
薬物療法は症状を和らげるための一つの手段であり、必ずしも長期間飲み続ける必要があるわけではありません。医師は症状の程度や原因、生活習慣などを総合的に判断し、薬の必要性や種類、期間を決定します。
生活習慣の改善やストレスマネジメントによって症状が安定すれば、薬を減らしたり中止したりすることも可能です。
次に読むことをお勧めする記事
【緊張による下痢症状と過敏性腸症候群 – 内視鏡検査の必要性】
自律神経の乱れによる下痢について読んで、「過敏性腸症候群とは具体的にどのような病気なのか」と思った方もいらっしゃるのでは?そんな疑問にお答えする詳しい内容をご紹介しています。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
自律神経と腸の関係を学んだ皆さんには、腸内環境の基礎も合わせて知ると、食事・運動・睡眠の総合的な整え方が見えてきます。
参考文献
Chelimsky G, Wszolek Z, Chelimsky TC. Gastrointestinal dysfunction in autonomic neuropathy. InSeminars in neurology 1996 Sep (Vol. 16, No. 03, pp. 259-268). 1996 by Thieme Medical Publishers, Inc..
Hamrefors V, Fedorowski A, Ohlsson B. Susceptibility to diarrhea is related to hemodynamic markers of sympathetic activation in the general population. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2019 Dec 2;54(12):1426-32.
Mathias CJ, Freeman R. Autonomic dysfunction. InNeurological Disorders 2003 Jan 1 (pp. 1453-1477). Academic Press.
Manabe N, Tanaka T, Hata J, Kusunoki H, Haruma K. Pathophysiology underlying irritable bowel syndrome-from the viewpoint of dysfunction of autonomic nervous system activity. Journal of Smooth Muscle Research. 2009;45(1):15-23.
Chelimsky G, Chelimsky TC. Evaluation and treatment of autonomic disorders of the gastrointestinal tract. InSeminars in neurology 2003 (Vol. 23, No. 04, pp. 453-458). 2003 by Thieme Medical Publishers, Inc.,
Aggarwal A, Cutts TF, Abell TL, Cardoso S, Familoni B, Bremer J, Karas J. Predominant symptoms in irritable bowel syndrome correlate with specific autonomic nervous system abnormalities. Gastroenterology. 1994 Apr 1;106(4):945-50.
Heitkemper M, Jarrett M, Cain KC, Burr R, Levy RL, Feld A, Hertig V. Autonomic nervous system function in women with irritable bowel syndrome. Digestive diseases and sciences. 2001 Jun;46:1276-84.
Brandon LH. Autonomic nervous system involvement in diabetic neuropathy: With emphasis upon diarrhea as a manifestation thereof. The American Journal of Medicine. 1954 Dec 1;17(6):866-70.
Wood JD. Sympathetic and Enteric Divisions of the Autonomic Nervous System. Chinese Journal of Physiology. 1999;42(4):201-10.
Tougas G. The autonomic nervous system in functional bowel disorders. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology. 1999;13:15A-7A.