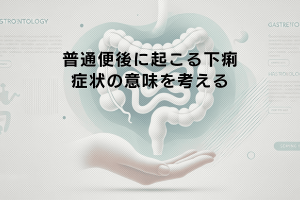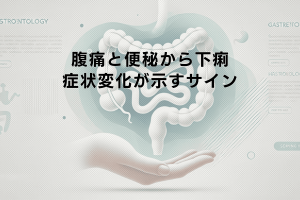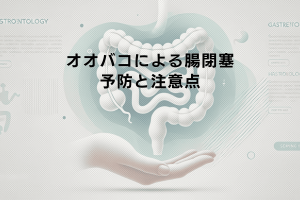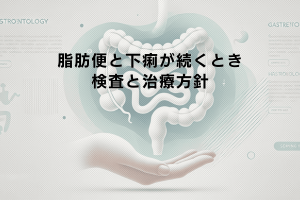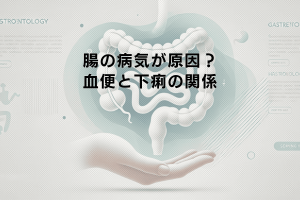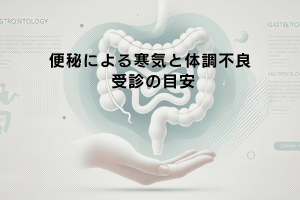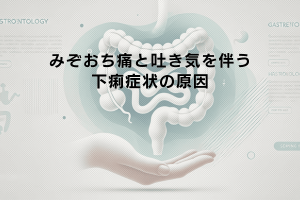便秘の際に血便が見られると、多くの方が不安を感じるでしょう。この症状は、硬い便による一時的なものであることもあれば、消化管の病気が隠れているサインである可能性もあります。
この記事では、血便を伴う便秘がなぜ起こるのか、その原因や考えられる病気、ご自身でできる対処法、そして医療機関を受診する目安について、分かりやすく解説します。
便秘と血便は、それぞれ独立した症状として現れることもあれば、同時に起こることもあります。これらの症状が一緒に見られる場合、その背景には様々な要因が考えられます。まずは、便秘と血便の基本的な理解を深めましょう。
便秘とはどのような状態か
便秘とは、一般的に排便が順調に行われない状態を指し、毎日排便がないと便秘と考える方もいますが、排便の頻度には個人差があります。
医学的には、週に3回未満の排便、排便時に強くいきむ必要がある、便が硬くて出しにくい、残便感があるなどの状態が続く場合に便秘と判断することが多いです。
便秘は、腹部膨満感や腹痛、食欲不振など、様々な不快な症状を起こします。
血便とは何か なぜ便秘と関連するのか
血便とは、便に血液が混じっている状態のことです。血液の色や量、混じり方によって、出血している場所や原因をある程度推測できます。
便秘の際には、硬くなった便が肛門や直腸を通過する際に粘膜を傷つけ、出血することがあり、便秘と血便が関連して起こる一つの典型的なパターンです。
しかし、それ以外にも消化管の様々な病気が原因で血便が生じることもあり、注意が必要です。
血便を伴う便秘の一般的な誤解
便秘で血が出るのは、いつものことだから大丈夫、痔だろうから放っておけば治る、といった誤解は危険です。
確かに、切れ痔やいぼ痔による出血は頻繁に見られますが、血便は大腸がんのような重大な病気のサインである可能性も否定できません。自己判断せずに、症状が続く場合や気になる場合は専門医に相談することが大切です。
主な誤解と注意点
| 誤解 | 考えられるリスク | 対応のポイント |
|---|---|---|
| 痔だから大丈夫 | 大腸がんなど他の病気を見逃す可能性 | 繰り返す場合は検査を検討 |
| 少しの血なら問題ない | 少量でも持続する場合は注意が必要 | 出血量だけでなく頻度も重要 |
| 自然に治るはず | 原因によっては悪化することも | 症状の変化に注意する |
放置するリスクの概要
血便を伴う便秘を放置すると、原因となっている病気が進行してしまう恐れがあり、大腸がんの場合、早期発見・早期治療が非常に重要です。
また、炎症性腸疾患なども、適切な治療を受けずにいると症状が悪化し、生活の質を大きく低下させる可能性があります。貧血が進行したり、緊急手術が必要な状態になったりすることもあるため、軽視は禁物です。
便秘で血便が出る主な原因
便秘の際に血便が見られる原因は多岐にわたり、硬い便による物理的なものから、消化管の病気まで様々です。
硬い便による物理的な刺激
便秘によって便が硬くなると、排便時に肛門や直腸の粘膜を傷つけやすくなり、血便の最も一般的な原因の一つです。
切れ痔(裂肛)
硬い便が肛門の皮膚を通過する際に裂けてしまう状態で、排便時に強い痛みを感じ、トイレットペーパーに鮮血が付着することが多いです。痛みのため排便を我慢してしまい、さらに便秘が悪化するという悪循環に陥ることもあります。
いぼ痔(痔核)からの出血
肛門周辺の血管がこぶ状に腫れたもので、排便時のいきみなどで出血しやすくなり、内痔核の場合、痛みは少ないものの排便時に出血したり、痔核が肛門の外に脱出したりすることがあります。
外痔核では血豆(血栓性外痔核)ができて強い痛みを伴うこともあります。
消化管の炎症や潰瘍
消化管の粘膜に炎症や潰瘍ができると、そこから出血して血便となることがあります。
虚血性大腸炎
大腸の血流が悪くなることで粘膜に炎症や潰瘍が生じる病気です。突然の腹痛とともに下痢や血便が見られ、高齢者や動脈硬化のある方に多いですが、若い方でも便秘で強くいきんだ後などに発症することがあります。
潰瘍性大腸炎やクローン病
これらは炎症性腸疾患と呼ばれ、免疫の異常などが関与して消化管に慢性の炎症や潰瘍を起こす病気です。下痢や血便、腹痛、体重減少などが主な症状で、若い世代にも発症し、長期的な治療が必要になります。
炎症性腸疾患の主な症状
- 持続する下痢
- 血便・粘血便
- 腹痛
- 発熱
- 体重減少
大腸ポリープや大腸がん
大腸ポリープや大腸がんは、初期には自覚症状がないことが多いですが、進行すると出血して血便の原因となることがあります。
ポリープからの出血
大腸ポリープは、大腸の粘膜にできるいぼ状の隆起です。多くは良性ですが、一部はがん化する可能性があり、ポリープが大きくなると、便が通過する際に擦れて出血することがあります。
進行がんによる出血
大腸がんが進行すると、がん組織がもろくなって出血しやすくなり、便に血が混じる、便が細くなる、便秘と下痢を繰り返すなどの症状が現れることがあります。早期発見のためには、定期的な検診が重要です。
大腸がんが疑われる症状
| 症状 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 血便 | 持続的、暗赤色の場合も | 痔と自己判断しない |
| 便通異常 | 便秘と下痢を繰り返す、便が細い | 急な変化に注意 |
| 腹痛・腹部膨満感 | 持続する、原因不明 | 他の症状と合わせて判断 |
| 体重減少・貧血 | 食欲不振を伴うことも | 進行している可能性 |
その他の原因
上記以外にも、血便を起こす原因はいくつかあります。
薬剤の副作用
一部の痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs)や血液をサラサラにする薬(抗血小板薬、抗凝固薬)は、消化管の粘膜を荒らしたり、出血しやすくしたりする副作用があります。
薬を服用中に血便が見られた場合は、処方医に相談が必要です。
感染性腸炎
細菌やウイルスによる感染性腸炎でも、下痢や腹痛とともに血便が出ることがあり、サルモネラ菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O157など)が代表的です。
血便の色と特徴から推測できること
血便の色や性状は、出血部位を推測する上で重要な手がかりとなりますが、自己判断は禁物であり、あくまで目安として参考にしてください。
鮮血便(真っ赤な血)の場合
便の表面に付着するような真っ赤な血、あるいは排便後にポタポタと垂れるような出血は、肛門に近い部分からの出血を示唆します。
肛門や直腸付近の出血の可能性
切れ痔(裂肛)やいぼ痔(痔核)、直腸ポリープ、直腸がんなどが考えられ、トイレットペーパーに付着する程度の少量であることも多いですが、量が多い場合や続く場合は注意が必要です。
考えられる主な疾患(鮮血便)
| 疾患名 | 主な特徴 | 伴いやすい症状 |
|---|---|---|
| 切れ痔(裂肛) | 排便時痛、少量の鮮血 | 痛みによる排便恐怖 |
| いぼ痔(痔核) | 排便時出血、脱肛、痛みは程度による | 残便感 |
| 直腸ポリープ・直腸がん | 無症状のことも、便への付着血 | 便通異常(進行時) |
暗赤色便(赤黒い血)の場合
便全体に混じっているような、やや黒みを帯びた赤色の血便は、大腸の奥(盲腸、上行結腸、横行結腸など)からの出血が考えられます。
大腸の奥からの出血の可能性
大腸憩室出血、虚血性大腸炎、大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)などが原因として挙げられ、出血量が多いと貧血を起こすこともあります。
考えられる主な疾患(暗赤色便)
| 疾患名 | 主な特徴 | 伴いやすい症状 |
|---|---|---|
| 大腸憩室出血 | 突然の多量出血、腹痛は少ない | 貧血症状 |
| 虚血性大腸炎 | 突然の腹痛、下痢、血便 | 吐き気 |
| 大腸がん(右側) | 発見が遅れやすい、持続的な出血 | 貧血、体重減少 |
黒色便(タール便)の場合
コールタールのように黒くてドロドロした便は、タール便と呼ばれますが、食道、胃、十二指腸といった上部消化管からの出血が原因であることが多いです。
胃や十二指腸など上部消化管の出血
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんなどが代表的な原因で、血液が胃酸と反応して黒くなるため、このような色になります。出血量が多い場合は、貧血やショック状態を起こすこともあり、緊急の対応が必要です。

緊急性が高い黒色便のサイン
- めまい、立ちくらみ
- 冷や汗
- 動悸、息切れ
- 意識が遠のく感じ
便に付着する血液と便に混じる血液の違い
一般的に、便の表面に血液が付着している場合は肛門に近い部位からの出血(例:痔)、便全体に血液が混じり合っている場合は大腸の奥や小腸からの出血(例:大腸炎、大腸がん)が考えられます。
ただし、これはあくまで目安であり、出血量や腸の動きによっても変わるため、専門医の診断が重要です。
血便を伴う便秘のセルフケアと注意点
血便を伴う便秘に対して、ご自身でできることもありまが、症状によっては医療機関の受診が優先されることを念頭に置いてください。
食生活の見直し
便秘の改善には、食生活が大きく関わっています。
食物繊維の積極的な摂取
食物繊維は、便の量を増やし、便を柔らかくする働きがあり、水溶性食物繊維(海藻類、果物など)と不溶性食物繊維(穀類、豆類、野菜など)をバランス良く摂ることが大切です。
水分補給の重要性
便の硬さは水分量に影響され、十分な水分を摂取することで、便が柔らかくなり排出しやすくなります。特に朝起きた時や運動後などは意識して水分を摂りましょう。
避けるべき食事
| 食事の種類 | 理由 | 代替案・工夫 |
|---|---|---|
| 脂肪分の多い肉類 | 腸内環境を悪化させる可能性 | 魚や鶏むね肉、大豆製品 |
| 加工食品・インスタント食品 | 食物繊維が少なく塩分が多い傾向 | 自炊を心がける、野菜を追加 |
| 刺激物(香辛料、アルコール) | 腸を刺激しすぎる可能性 | 摂取量を控える |

生活習慣の改善
規則正しい生活習慣も、便秘解消には重要です。
適度な運動のすすめ
ウォーキングやストレッチなどの適度な運動は、腸の動きを活発にし、排便を促します。運動不足を感じている方は、日常生活に少しでも運動を取り入れることをおすすめします。
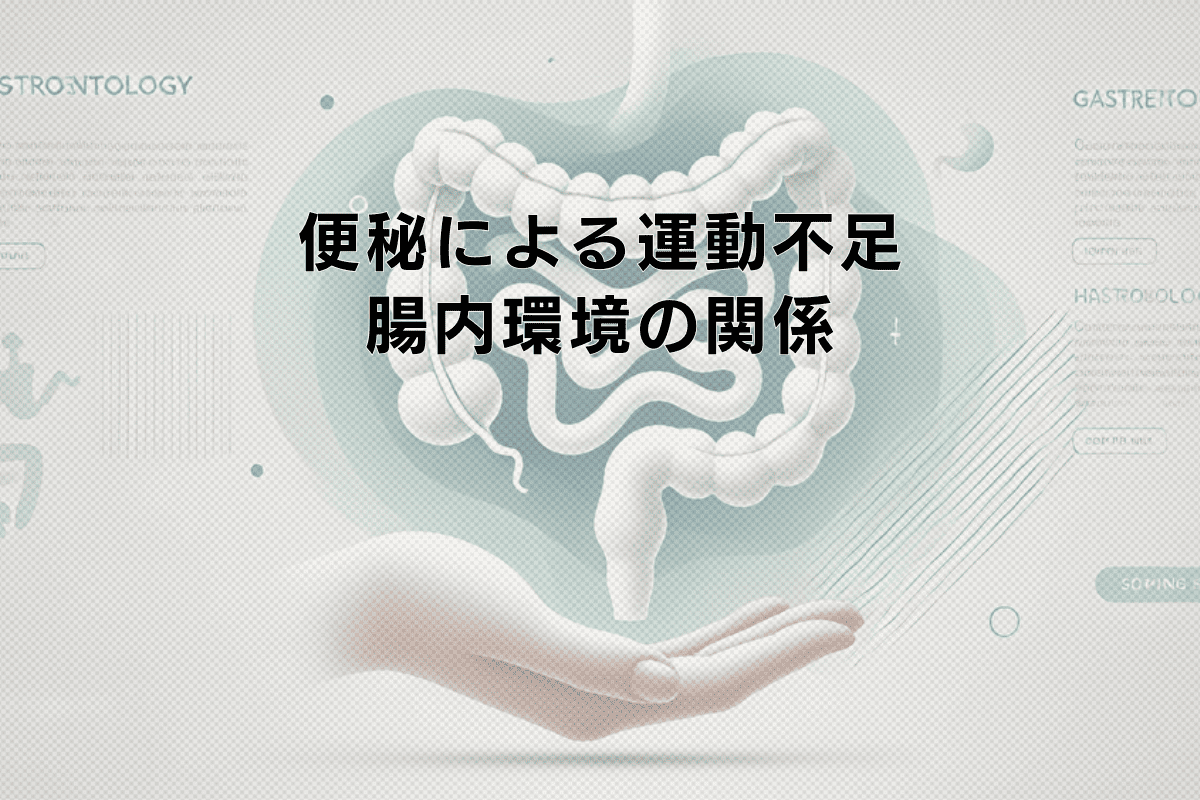
規則正しい排便習慣
毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけると、自然な便意が起こりやすくなり、便意を感じたら我慢しないことも大切です。
ストレス管理
ストレスは自律神経のバランスを乱し、腸の働きを悪くすることがあり、十分な睡眠、趣味やリラックスできる時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。
市販薬を使用する際の注意
便秘薬は手軽に入手できますが、使用には注意が必要です。
便秘薬の選び方
便秘薬には、便を柔らかくするタイプや腸を刺激するタイプなど、様々な種類があります。自分の便秘のタイプに合ったものを選ぶことが大切ですが、薬剤師に相談してください。
自己判断の危険性
血便がある場合に自己判断で刺激性の便秘薬を長期間使用すると、大腸メラノーシス(大腸粘膜が黒ずむ状態)を起こしたり、薬への依存性が高まったりすることがあります。
また、重大な病気が隠れている可能性を見逃すことにもつながりかねません。
こんな時はセルフケアを中止
セルフケアを行っても症状が改善しない、あるいは悪化する場合は、すぐに医療機関を受診してください。特に、次のような症状が見られる場合は、自己判断せずに専門医の指示を仰ぐことが重要です。
- 血便の量が増えた、または頻回になった
- 腹痛が強くなった、または持続するようになった
- 発熱、嘔吐、体重減少など、他の症状が現れた
医療機関を受診するべきタイミング
血便を伴う便秘は、放置せずに医療機関を受診した方が良い場合があります。以下のような場合は、消化器内科などの専門医にご相談ください。
血便が続く 量が多い場合
一度きりの少量の出血であれば、硬い便による切れ痔などの可能性が高いですが、血便が何日も続く場合や、出血量が多い(便器が真っ赤になるなど)場合は、詳しい検査が必要です。貧血が進行する恐れもあります。
激しい腹痛や発熱を伴う場合
血便とともに、我慢できないほどの激しい腹痛や38度以上の発熱がある場合は、虚血性大腸炎や感染性腸炎、憩室炎などの急性疾患の可能性があります。速やかに医療機関を受診しましょう。
体重減少や貧血症状がある場合
特に思い当たる原因がないのに体重が急に減ってきた、あるいは顔色が悪い、立ちくらみ、動悸、息切れなどの貧血症状がある場合は、消化管からの慢性的な出血や、大腸がんなどの悪性疾患が隠れている可能性も考えられます。
貧血が疑われるサイン
| 症状 | チェックポイント |
|---|---|
| 顔面蒼白 | まぶたの裏側が白い |
| 動悸・息切れ | 階段などで以前より息が切れる |
| 倦怠感・易疲労感 | 疲れやすく、体がだるい |
| 頭痛・めまい | 立ちくらみを起こしやすい |
便秘と下痢を繰り返す場合
便秘だと思っていたら急に下痢になり、また便秘になるというように、便通異常を繰り返す場合も注意が必要で、過敏性腸症候群のこともありますが、大腸がんなどでも見られる症状です。
家族歴や既往歴から注意が必要なケース
ご家族(特に親子や兄弟姉妹)に大腸がんや炎症性腸疾患にかかった方がいる場合や、ご自身が以前に大腸ポリープを指摘されたことがある場合は、血便が見られたら早めに受診することをおすすめします。
遺伝的な要因や再発のリスクを考慮することが必要です。
消化器内科での検査と治療法
血便を伴う便秘で消化器内科を受診すると、原因を特定するためにいくつかの検査が行われ、その結果に基づいて適切な治療法が選択されます。
問診と診察
医師はまず、患者さんから症状について詳しく話を聞きます。
症状の詳しい聞き取り
いつから症状があるのか、血便の色や量、便秘の程度、腹痛の有無や性質、他に症状はないか、既往歴や家族歴、服用中の薬などについて詳しく質問し、正確な情報が診断の手がかりとなります。
腹部の触診など
お腹を触って、しこりや圧痛(押すと痛む場所)がないかなどを調べ、必要に応じて直腸診(肛門から指を入れて直腸の状態を調べる診察)を行うこともあります。
行われる主な検査
問診や診察の結果を踏まえ、必要な検査を選択します。
便潜血検査
便の中に目に見えない微量の血液が混じっていないかを調べる簡単な検査です。大腸がん検診として広く行われています。
血液検査
貧血の有無や程度、炎症反応の有無などを調べます。全身状態を把握するのに役立ちます。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体の粘膜を直接観察する検査で、ポリープやがん、炎症などを発見でき、必要であれば組織を採取して病理検査(顕微鏡で詳しく調べる検査)を行ったり、ポリープを切除できます。
血便の原因診断には最も重要な検査の一つです。
その他の画像検査(CTなど)
必要に応じて、腹部CT検査や腹部超音波検査などを行い、腸管や周囲の臓器の状態を詳しく調べることがあります。
主な検査の目的
| 検査名 | 主な目的 | わかること(例) |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 消化管出血のスクリーニング | 目に見えない出血の有無 |
| 血液検査 | 全身状態の評価 | 貧血、炎症の程度 |
| 大腸内視鏡検査 | 大腸粘膜の直接観察、組織採取、治療 | ポリープ、がん、炎症性腸疾患など |

原因に応じた治療法
検査で原因が特定されたら、それに応じた治療を行います。
痔の治療
切れ痔やいぼ痔に対しては、軟膏や坐薬などの薬物療法、生活習慣の改善指導が中心です。症状が強い場合や保存的治療で改善しない場合は、手術を検討することもあります。
炎症性腸疾患の治療
潰瘍性大腸炎やクローン病では、炎症を抑える薬(5-ASA製剤、ステロイド、免疫抑制薬、生物学的製剤など)を用いた内科的治療が基本となり、寛解導入と寛解維持を目指し、長期的な管理が必要です。
ポリープや早期がんの内視鏡治療
大腸ポリープや早期の大腸がんであれば、多くの場合、大腸内視鏡検査の際に切除(ポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術:EMRなど)が可能で、体への負担が少ない治療法です。
進行がんの治療
進行した大腸がんの場合は、外科手術が主な治療法で、がんの進行度や患者さんの状態に応じて、化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療を組み合わせることもあります。
検査後のフォローアップ
治療後も、定期的な検査や診察によるフォローアップが重要です。
特に大腸ポリープを切除した場合や炎症性腸疾患、大腸がんの治療後は、再発や新たな病変の早期発見のために、医師の指示に従って定期的な大腸内視鏡検査などを受けることが大切になります。
血便を伴う便秘に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、血便を伴う便秘に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 血便は一度きりなら心配ないですか
-
一度きりの少量の鮮血で、排便時の痛みなどから切れ痔が強く疑われる場合は、様子を見ることもあります。
しかし、血便の色が暗赤色や黒色であったり、量が多い場合、腹痛や発熱などの他の症状を伴う場合、または繰り返す場合は、一度医療機関にご相談ください。
- 便秘薬を飲んでいますが血便が出ました。どうすればよいですか
-
まずは、かかりつけ医や薬剤師に相談しましょう。便秘薬の種類によっては、腸を刺激することで出血を助長する可能性も考えられます。また、便秘薬とは関係なく、別の原因で血便が出ている可能性もあります。
自己判断で薬を中止したり変更したりせず、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
- 大腸内視鏡検査は痛いですか。受けるのが不安です
-
大腸内視鏡検査は、腸の形や走行に個人差があるため、多少の痛みや不快感を伴うことがありますが、多くの医療機関では、鎮静剤(眠くなる薬)や鎮痛剤を使用することで、苦痛を最小限に抑える工夫をしています。
不安な点や疑問点は、検査前に医師や看護師に遠慮なく伝え、よく説明を聞くことが大切です。
- 血便の色が毎回変わるのはなぜですか
-
血便の色は、出血部位や出血量、血液が腸内を通過する時間などによって変化します。
肛門に近い部位からの少量の出血であれば鮮血便になりやすいですが、同じ部位でも出血量が多い場合や、腸の動きが遅い場合は、やや暗赤色になることもあります。また、複数の箇所から出血している可能性も否定できません。
- 子供でも血便を伴う便秘になりますか
-
お子さんでも血便を伴う便秘になることがあります。最も多いのは硬い便による切れ痔ですが、その他にも感染性腸炎、アレルギー性腸炎、稀ですが若年性のポリープや炎症性腸疾患なども考えられます。
お子さんの血便に気づいたら、小児科や小児外科、あるいは消化器内科を受診して相談してください。
次に読むことをお勧めする記事
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
血便と便秘の基本を押さえたら、次は実際の内視鏡検査の流れを知っておくと安心です。準備・当日の様子・検査後の過ごし方まで、初めて受ける方に役立つ情報です。
【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ 便の変化や腹痛の基本知識】
血便の背景を学んだ皆さんには、大腸がんの初期症状も合わせて知っておくと、より包括的な理解が得られます。受診の目安や検査の意義も整理されています。
参考文献
Ohkubo H, Yoshihara T, Misawa N, Ashikari K, Fuyuki A, Matsuura T, Higurashi T, Imajo K, Hosono K, Yoneda M, Kobayashi N. Relationship between stool form and quality of life in patients with chronic constipation: an internet questionnaire survey. Digestion. 2021 Mar 1;102(2):147-54.
Arce DA, Ermocilla CA, Costa H. Evaluation of constipation. American family physician. 2002 Jun 1;65(11):2283-91.
Rao SS, Meduri K. What is necessary to diagnose constipation?. Best practice & research Clinical gastroenterology. 2011 Feb 1;25(1):127-40.
Rao SS, Ozturk R, Laine L. Clinical utility of diagnostic tests for constipation in adults: a systematic review. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2005 Jul 1;100(7):1605-15.
Bharucha AE, Wald A. Chronic constipation. InMayo Clinic Proceedings 2019 Nov 1 (Vol. 94, No. 11, pp. 2340-2357). Elsevier.
Jamshed N, Lee ZE, Olden KW. Diagnostic approach to chronic constipation in adults. American family physician. 2011 Aug 1;84(3):299-306.
Aichbichler BW, Wenzl HH, Ana CS, Porter JL, Schiller LR, Fordtran JS. A comparison of stool characteristics from normal and constipated people. Digestive Diseases and Sciences. 1998 Nov;43:2353-62.
Arai YC, Shiro Y, Funak Y, Kasugaii K, Omichi Y, Sakurai H, Matsubara T, Inoue M, Shimo K, Saisu H, Ikemoto T. The association between constipation or stool consistency and pain severity in patients with chronic pain. Anesthesiology and pain medicine. 2018 Aug 11;8(4):e69275.
Su GS, Chen TW, Chou JW. A rare cause of abdominal pain with bloody stool. The Turkish Journal of Gastroenterology. 2020 Jan 1;31(1):73.
Zoppi G, Cinquetti M, Luciano A, Benini A, Muner A, Minelli EB. The intestinal ecosystem in chronic functional constipation. Acta paediatrica. 1998 Aug;87(8):836-41.