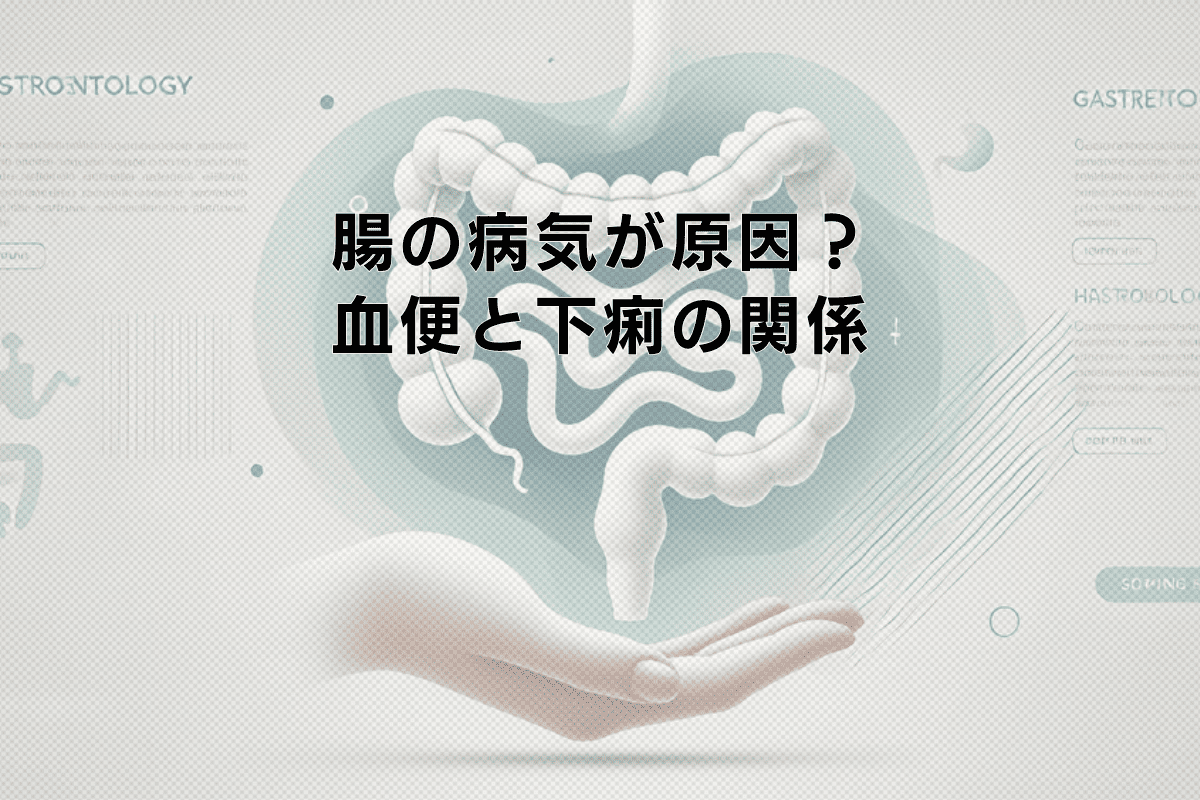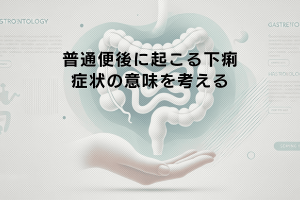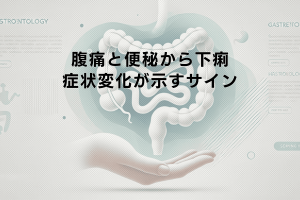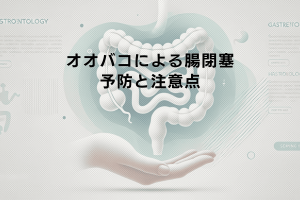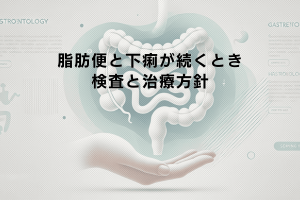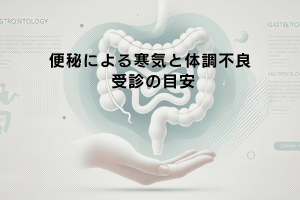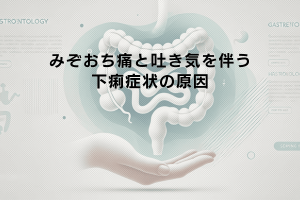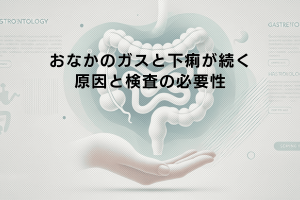突然の腹痛とともに、下痢や血便の症状が現れると、多くの方が不安を感じるでしょう。血便と下痢が同時に見られる場合、背景には腸のさまざまな病気が隠れている可能性があります。
この記事では、血便と下痢がなぜ同時に起こるのか、どのような腸の病気が考えられるのか、症状から考えられることや医療機関での対応について、詳しく解説します。
血便と下痢の基本的な理解
血便と下痢は、消化器系の異常を知らせる代表的な症状で、それぞれが単独で現れることもありますが、同時に起こる場合は、腸管内で炎症や出血が起きている可能性を示唆します。
血便とはどのような状態か
血便とは、便に血液が混じっている状態で、血液の由来は、食道から肛門までの消化管のいずれかの部位です。出血している場所や出血量によって、便の色や状態は大きく異なります。
肛門に近い場所からの出血であれば鮮やかな赤色(鮮血便)になり、胃や十二指腸など、肛門から遠い場所からの出血であれば、血液中のヘモグロビンが胃酸によって酸化されヘマチンに変わるため、黒っぽい色(黒色便、タール便)になります。
また、大腸からの出血では、赤黒い色や粘液と混じった血液が見られることもあります。血便は、見た目で判断できる場合もあれば、検査をしないとわからない微量な場合(便潜血)もあります。
血便の色の違いと出血部位の目安
| 便の色 | 考えられる出血部位 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 鮮血便(鮮やかな赤色) | 肛門、直腸など | 排便時にポタポタと出血する、紙に付着する |
| 暗赤色便(赤黒い色) | 大腸の奥 | 便全体に血液が混ざっている、粘液を伴うことがある |
| 黒色便(タール便) | 胃、十二指腸、小腸 | 黒くて粘り気のある便、特有の臭いを伴う |
下痢とはどのような状態か
下痢は、便の水分量が異常に増加し、固形ではない泥状または水様状の便が頻繁に排出される状態で、健康な状態の便の水分量は約70〜80%ですが、下痢の場合は90%以上です。
下痢は、腸の蠕動運動が過剰になる、腸管からの水分吸収が不十分になる、あるいは腸管内への水分分泌(腸液の分泌)が過剰になることなどが原因で起こります。
期間によって、数日から2週間程度で治まる急性下痢と、3週間以上続く慢性下痢に分けられます。急性下痢の多くは感染症が原因ですが、慢性下痢の場合は、生活習慣や他の病気が背景にあることが多いです。
下痢は発生原因から、滲出性、分泌性、浸透圧性、運動亢進性の4つに大別され、血便を伴う下痢は特に滲出性下痢に分類されます。
下痢の主な分類
| 分類 | 主な原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 滲出性下痢 | 腸粘膜の炎症(感染症、IBDなど) | 血液、粘液、組織液が腸管内に漏れ出す。血便を伴う。 |
| 分泌性下痢 | 毒素、ホルモンなどによる腸液の過剰分泌 | 大量の水様性下痢。絶食しても改善しにくい。 |
| 浸透圧性下痢 | 吸収されにくい物質(下剤、乳糖など) | 腸管内の浸透圧が上昇し、水分が引き寄せられる。 |
| 運動亢進性下痢 | ストレス、甲状腺機能亢進症など | 腸の蠕動運動が過剰になり、水分の吸収時間が短縮する。 |
なぜ血便と下痢が同時に起こるのか
血便と下痢が同時に起こる主な理由は、腸の粘膜に炎症や潰瘍が生じているためで、この状態を滲出性下痢と呼びます。
腸の粘膜が炎症を起こすと、サイトカインなどの炎症性物質が放出され、血管の透過性が高まり、細胞と細胞の結合が緩み、そこから血液成分(赤血球、白血球、血小板)や組織液、粘液などが腸管内に漏れ出してきます(滲出)。
この滲出液が便の水分量を増やし、下痢を起こし、同時に、炎症が強くなり粘膜の血管が破綻すると出血し、血液が便に混じって血便となります。
腸の粘膜がダメージを受けているという共通の原因が、血便と下痢という二つの症状を起こすのです。感染症や炎症性腸疾患など、腸に強い炎症が生じる病気では、この二つの症状が同時に現れやすくなります。
血便と下痢を起こす主な腸の病気
血便と下痢を同時に起こす病気は多岐にわたり、原因は感染によるものから、免疫の異常、血流障害、薬剤、さらには腫瘍まで様々です。ここでは代表的な病気について、より詳しく解説します。
感染性腸炎
ウイルスや細菌などの病原体に感染することで腸に炎症が起こる病気で、サルモネラ菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O157など)といった細菌や、ノロウイルス、ロタウイルスといったウイルスが主な原因です。
病原体が腸の粘膜に感染すると、激しい炎症が起こり、腹痛、発熱、嘔吐とともに、水様性の下痢や血便が見られます。
腸管出血性大腸菌はベロ毒素を産生し、溶血性尿毒症症候群(HUS)という重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、特に注意が必要です。
また、抗生物質の使用によって腸内細菌のバランスが崩れ、特定の菌(クロストリディオイデス・ディフィシルなど)が増殖して偽膜性腸炎を起こし、血便を伴う下痢をきたすこともあります。
炎症性腸疾患(IBD)
炎症性腸疾患は、腸に原因不明の慢性的な炎症が起こる病気の総称で、主に潰瘍性大腸炎とクローン病があります。
遺伝的な要因に、食事や腸内細菌などの環境因子が複雑に関与して、免疫系が異常に働き、自身の腸を攻撃してしまうことで発症すると考えられています。症状が良くなったり(寛解)、悪くなったり(再燃)を繰り返す長い経過をたどります。
腹部の症状だけでなく、関節炎や皮膚症状、眼の症状など、腸管外合併症と呼ばれる全身の症状を伴うこともあります。治療の目標は、まず炎症を抑えて症状を改善させ(寛解導入)、良い状態を長く維持する(寛解維持)ことです。
潰瘍性大腸炎とクローン病の比較
| 項目 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 好発部位 | 大腸(特に直腸から連続的に広がる) | 消化管のあらゆる部位(特に小腸と大腸) |
| 炎症の深さ | 粘膜層(浅い) | 全層性(深い) |
| 主な症状 | 粘血便、下痢、腹痛 | 腹痛、下痢、体重減少、発熱 |
虚血性大腸炎
大腸への血流が一時的に悪くなることで、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が起こる病気です。動脈硬化が背景にある高齢者や、糖尿病、高血圧などの生活習慣病を持つ方、また便秘で強くいきむ習慣のある方などに起こりやすいとされています。
大腸の中でも血流が乏しくなりやすい下行結腸からS状結腸にかけて好発し、突然の激しい腹痛(特に左下腹部痛)から始まり、その後に下痢、そして鮮やかな血便が見られるのが典型的な症状の経過です。
多くは一過性で、腸を休める(絶食や点滴)ことで数日のうちに改善しますが、まれに血流障害が改善せずに腸が狭くなる(狭窄型)や、腸が壊死してしまう(壊疽型)重篤な状態に陥ることもあります。
大腸憩室症(憩室出血・憩室炎)
大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出したものを大腸憩室といい、腸管の内圧の上昇が原因と考えられ、憩室がある状態を大腸憩室症と呼びます。
憩室内の血管が破綻して出血すると、突然の腹痛を伴わない大量の血便(憩室出血)が見られる一方、憩室に便などが詰まって細菌感染を起こすと憩室炎となり、腹痛や発熱、炎症による下痢を起こします。
憩室炎が重症化すると、出血を伴うこともあります。憩室は加齢とともに増える傾向にあり、特に右側結腸に多いです。
薬剤性腸炎
特定の薬剤の副作用として腸に炎症が起こり、血便や下痢を起こすことがあり、代表的な原因薬剤は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)です。
痛み止めとして広く使われていますが、長期的に使用すると腸の粘膜を保護する物質の産生を抑制し、潰瘍やびらんを形成することがあります。その他にも、一部の抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬、抗生物質なども腸炎の原因となりえます。
何か新しい薬を飲み始めてから症状が出現した場合は、薬剤性腸炎の可能性も考えることが必要です。
大腸がん・ポリープ
大腸がんや大きなポリープがあると、表面から慢性的に出血することがあり、硬い便ががんやポリープの表面を通過する際にこすれて出血し、便に血液が混じります。
多くのがんは、腺腫という良性のポリープから発生するため、ポリープの段階で切除することががんの予防に繋がります。出血が少量の場合は、便潜血検査で初めて陽性となることもあります。
進行すると、出血量が増えて肉眼でもわかる血便となったり、腸が狭くなることで便秘と下痢を繰り返したり、便が細くなるなどの症状が現れます。
大腸がんの予防や早期発見のためには、40歳を過ぎたら定期的に大腸内視鏡検査を受けることが重要です。
腸液と下痢の関係性
下痢の原因の一つに、腸液の分泌が過剰になる状態があり、いわゆる腸液下痢と呼ばれるもので、腸の機能異常が深く関わっています。腸液の働きと下痢のつながりを理解することは、症状の原因を探る上で大切です。
腸液の役割と分泌の仕組み
腸液は、小腸や大腸の壁から分泌される液体で、消化酵素を含み食べ物の消化を助けるとともに、腸の粘膜を保護する役割を担っています。腸液の分泌は、食べ物が腸に入ってくる刺激や、自律神経、ホルモンなどによって精密に調節されています。
健康な状態では、1日に数リットルもの腸液が分泌されますが、水分の多くは腸で再び吸収され、便の硬さが適切に保たれます。
腸液の主な成分と働き
| 成分 | 主な働き | 分泌場所 |
|---|---|---|
| 水分 | 内容物を溶かし、移動を助ける | 小腸・大腸 |
| 消化酵素 | 炭水化物、タンパク質、脂質を分解する | 小腸 |
| 粘液(ムチン) | 腸の粘膜を保護し、便の滑りを良くする | 小腸・大腸 |
腸液の過剰分泌が下痢を引き起こす理由
何らかの原因で腸液の分泌が異常に増加したり、水分の再吸収がうまくいかなくなったりすると、腸管内の水分量が過剰になり、吸収しきれなかった大量の水分が、便として排出されるのが分泌性の下痢、つまり腸液下痢です。
コレラ菌が産生する毒素は、腸の上皮細胞にあるイオンチャネル(CFTRなど)を恒常的に活性化させ、塩化物イオンを腸管内に強制的に分泌させます。
すると浸透圧によって水分も大量に引き寄せられ、米のとぎ汁のような激しい水様性下痢を起こします。
また、一部のホルモン産生腫瘍や薬剤、あるいはVIP(血管作動性腸管ペプチド)などのホルモンの異常によっても、腸液の分泌が促され、下痢の原因となることがあります。
腸液性下痢を伴う病気
腸液の過剰分泌による下痢は、特定の病気のサインである場合があり、感染性腸炎の中でも、毒素を産生するタイプの細菌感染症では、顕著な腸液下痢が見られます。
また、まれな病気ですが、ホルモンを過剰に産生する神経内分泌腫瘍(カルチノイドなど)やVIP産生腫瘍(ビポーマ)では、難治性の分泌性下痢が起こることが知られています。
このような病気では、絶食しても下痢が改善しないという特徴があります。下痢が長期間続く場合や、水分補給が追いつかないほどの激しい下痢の場合は、専門的な診断が必要です。
腸重積症と下痢について
腸重積症は主に乳幼児に見られる特殊な病気ですが、成人でも起こり、この病気もまた下痢や血便といった症状を起こすことがあり、注意が必要です。
腸重積症とは何か
腸重積症とは、腸の一部が、隣接する肛門側の腸の中にはまり込んでしまう状態で、望遠鏡を縮めるような状態をイメージすると分かりやすいかもしれません。
腸がはまり込むことで、腸管の血流が悪くなり、時間が経つと腸がむくんで、最終的には壊死してしまうこともある緊急性の高い病気です。
腸重積症の主な症状
乳幼児の腸重積症では、特徴的な症状が見られ、それまで元気にしていた赤ちゃんが、突然、激しく泣き出します。この腹痛は間欠的で、数分から数十分おきに激しく泣くのと、けろりとしている状態を繰り返し、間欠的啼泣といいます。
症状が進行すると、嘔吐やぐったりするなどの症状が現れ、特徴的なイチゴゼリー状の粘血便が出ることがあります。
成人の場合は、このような典型的な症状を示すことは少なく、慢性的または断続的な腹痛や嘔吐、腹部膨満感、腸重積による下痢など、非特異的な症状が続くことが多いです。
腸重積症の治療
小児の場合、診断がつけば高圧浣腸(空気や造影剤を肛門から注入し、その圧力で整復する)による治療が試みられます。
早期であれば多くはこの方法で治すことができますが、発症から時間が経っている場合や、整復が難しい場合は手術が必要です。
一方、成人の腸重積症は、ポリープやがんなどの器質的な病変が先進部となっていることがほとんどであるため、原則として手術による治療が行われます。
なぜ腸重積症で下痢や血便が起こるのか
腸が重なり合うことで、腸管の血流が障害され、血流が悪くなると、腸の粘膜がむくみ(浮腫)、傷つきやすくなります。むくんだ粘膜からは、腸液が過剰に分泌されるため、下痢(腸重積下痢)が起こることがあります。
さらに血流障害が続くと、粘膜から出血し、剥がれ落ちた粘膜と血液、粘液が混ざり合って、特徴的なイチゴゼリー状の粘血便となります。これは腸の組織がダメージを受けているサインであり、早期の対応が重要です。
症状から考えられる病気と注意点
血便や下痢といった症状に加えて、便の色や状態、腹痛の有無や性質、その他の体の不調などを総合的に見ることで、背景にある病気をある程度推測することができます。
すぐに医療機関を受診すべき症状
以下の症状が一つでも見られる場合は、夜間や休日であっても、速やかに医療機関を受診してください。
- 意識がもうろうとしている、ぐったりしている
- 冷や汗が出る、顔色が悪い、脈が速い
- これまでに経験したことのないような激しい腹痛
- 腹部が板のように硬くなっている
- 呼吸が苦しい、息切れがする
- 高熱が続いている
- 嘔吐が止まらず、水分が全く摂れない
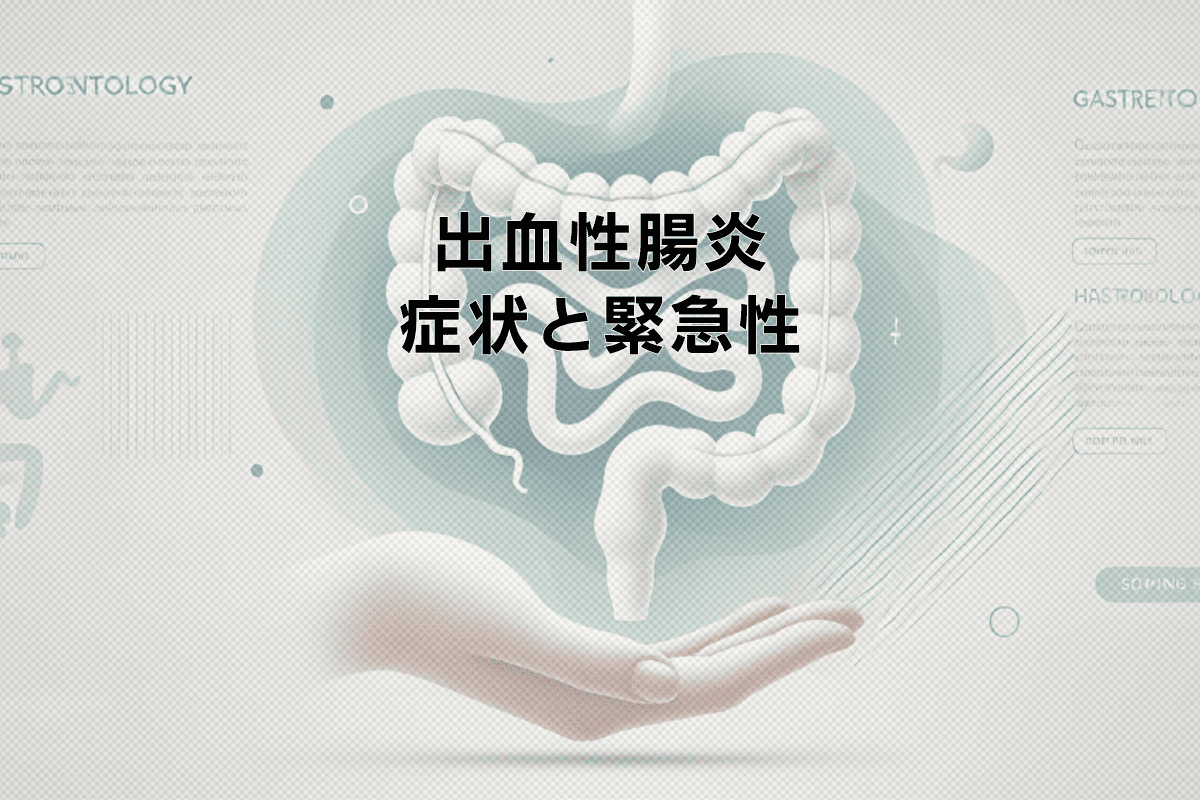
便の色や状態で判断する
便の色は、出血部位を推測する上で重要な手がかりです。鮮やかな赤色であれば痔などの肛門疾患の可能性が高いですが、大腸がんの可能性も否定できず、赤黒い便や粘液が混じる場合は、大腸の奥の方での炎症や腫瘍が疑われます。
黒いタール状の便であれば、胃や十二指腸潰瘍などが考えられます。便の状態も重要で、水のような下痢なのか、泥状なのか、粘液が多く混じるのかなどを確認しましょう。
便の状態と関連する病気の可能性
| 便の状態 | 考えられる主な病気 | 注意点 |
|---|---|---|
| 粘血便 | 潰瘍性大腸炎、クローン病、感染性腸炎 | 粘液と血液が混じっている状態。炎症が示唆される。 |
| 水様便(血液混入) | 感染性腸炎(特にウイルス性や毒素性) | 脱水症状に注意が必要。 |
| イチゴゼリー状の便 | 腸重積症 | 特に乳幼児の場合、緊急性が高いサイン。 |

腹痛の有無や特徴
腹痛の場所や痛みの種類も診断の助けになります。お腹のどのあたりが痛むのか、キリキリとした痛みか、鈍い痛みか、差し込むような周期的な痛みかなどを把握しておきましょう。
虚血性大腸炎では突然の激しい腹痛が特徴的ですし、腸重積症では周期的に繰り返す強い痛みが現れます。潰瘍性大腸炎では、下腹部のシクシクとした痛みが続くことが多いです。
発熱や吐き気などの随伴症状
血便や下痢以外の症状にも注意を払いましょう。高熱を伴う場合は、感染性腸炎の可能性が高まり、吐き気や嘔吐も感染性腸炎でよく見られる症状です。
明らかな理由なく体重が減少している場合や、食欲不振が続く場合は、炎症性腸疾患や大腸がんなどの慢性的な病気も考える必要があります。
また、関節の痛みや皮膚の発疹など、お腹以外の症状が現れる場合は、炎症性腸疾患の腸管外合併症の可能性もあります。
医療機関での検査と診断の流れ
血便や下痢が続く場合、自己判断は禁物で、正確な診断と適切な治療のために、消化器内科などの専門医療機関を受診することが大切です。医療機関では、症状や体の状態に応じて、段階的に検査を進めていきます。
まずは問診と身体診察
診察では、まず医師が詳しく症状について尋ねます。いつから症状が始まったか、便の色や回数、腹痛の有無や性質、食事の内容、最近の海外渡航歴、服用中の薬、過去の病歴など、できるだけ正確に伝えることが重要です。
その後、お腹の音を聞いたり、触って痛みやしこりの場所を確認したりする身体診察を行います。
血液検査と便検査
血液検査では、体内の炎症の程度(CRP値や白血球数)や、貧血の有無(赤血球数やヘモグロビン値)、栄養状態(アルブミンなど)を調べ、病気の活動性や重症度を評価するのに役立ちます。
便検査では、便の中に血液が混じっていないか(便潜血検査)を調べるほか、細菌やウイルスがいないかを確認するための便培養検査や抗原検査を行います。
また、便中カルプロテクチン検査は、腸の炎症の程度を評価するのに役立ち、特に炎症性腸疾患の診断や経過観察で有用です。
腹部超音波検査やCT検査
画像検査は、お腹の中の状態をより詳しく調べるために行います。
腹部超音波検査は、体に負担なく腸の壁の厚さやむくみ、腹水の有無などを評価でき、CT検査は、腸の炎症の範囲や程度をより詳細に把握したり、膿のたまり(膿瘍)や腸閉塞の有無、あるいは腫瘍などの病変を特定したりするのに非常に有用です。
腹痛が強い場合や、症状が重い場合には、画像検査が診断の手がかりとなります。
内視鏡検査(大腸カメラ)の重要性
血便の原因を特定するために最も重要で確実な検査が、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)です。先端に小型カメラがついた細いスコープを肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体の粘膜を直接観察します。
炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの病変を直接見ることができるため、確定診断に繋がります。検査前には、腸の中をきれいにするために下剤を服用する必要がありますが、検査中は鎮静剤を使用して、苦痛を少なく受けることも可能です。
近年では、特殊な光を用いて粘膜表面の血管や模様を強調する画像強調観察(NBIなど)や、画像を拡大して観察する拡大内視鏡の技術も進歩しており、より精密な診断ができます。
疑わしい部分の組織を採取して(生検)、病理検査で詳しく調べることもできます。
日常生活でできるセルフケアと予防策
腸の健康を保ち、血便や下痢といった症状を予防するためには、日々の生活習慣が大きく影響します。症状がある時はもちろん、普段から腸をいたわる生活を心がけることが大切です。
食生活で気をつけること
下痢や腹痛があるときは、腸に負担をかけない食事が基本で、消化の良いおかゆやうどん、スープ、豆腐などを中心に、少量ずつ摂取しましょう。
香辛料などの刺激物、脂肪分の多い食事、冷たい飲み物、アルコールは腸を刺激するため避けてください。症状が落ち着いている時でも、バランスの取れた食事を心がけ、食物繊維を適度に摂ることが腸内環境を整える上で役立ちます。
また、発酵食品やプロバイオティクスを含む食品を意識的に摂ることも、腸内環境の改善に繋がる可能性があります。
十分な水分補給の重要性
下痢や発熱があると、体から多くの水分と電解質(塩分やカリウムなど)が失われ、脱水状態に陥りやすくなります。脱水は倦怠感やめまい、頭痛などを起こし、重症化すると意識障害に至ることもあり、高齢者や子供は注意が必要です。
症状があるときは、こまめに水分を補給することが何よりも大切で、水やお茶だけでなく、失われた電解質も補給できる経口補水液やスポーツドリンクなどを上手に利用しましょう。
ストレス管理と十分な休養
腸の働きは自律神経によってコントロールされており、ストレスの影響を非常に受けやすく、過度なストレスは腸の動きを乱し、下痢や便秘の原因となります。
自分なりのリラックス方法を見つけ、趣味の時間や休息の時間を確保することが重要で、軽い運動や瞑想、深呼吸なども有効です。
また、睡眠不足は体の免疫力を低下させ、腸の不調を招きやすくするので、毎日十分な睡眠時間を確保し、体をしっかりと休ませてあげましょう。
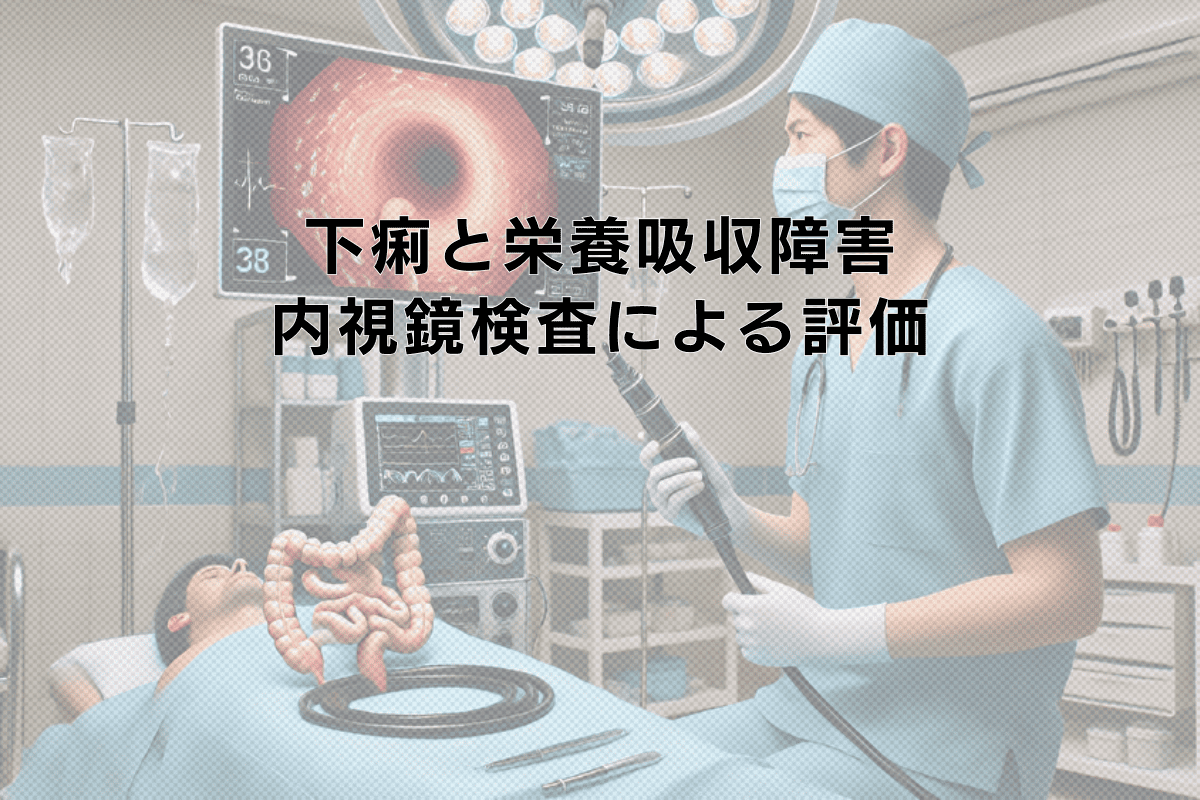
血便と下痢の関係に関するよくある質問
- 血便が出たらすぐに病院に行くべきですか?
-
血便は消化管のどこかから出血しているサインですので、原則として医療機関の受診が必要です。腹痛や発熱、下痢など他の症状を伴う場合、便全体が黒っぽい場合、血便が続く場合は、早めに消化器内科を受診してください。
たとえ痔による出血だと思っていても、自己判断せずに一度専門医の診察を受けることが大切です。
- 血便があれば、大腸がんの可能性は高いのでしょうか?
-
血便の原因として最も頻度が高いのは痔などの良性の肛門疾患ですが、大腸がんの可能性も常に考える必要があります。血便をきたす病気は非常に多岐にわたるため、症状だけでがんかどうかを判断することはできません。
40歳以上の方や、ご家族に大腸がんの既往がある方で血便が見られた場合は、必ず大腸内視鏡検査を受けましょう。自己判断で様子を見るのではなく、専門医に相談して原因を正確に調べることが重要です。
- ストレスだけで血便や下痢になることはありますか?
-
ストレスは、過敏性腸症候群(IBS)などを起こし、下痢や便秘、腹痛の原因となることが知られていて、これは腸の機能的な異常であり、腸の動きが過剰になることで下痢が起こります。
しかし、通常、ストレスや過敏性腸症候群だけで血便が起こることはありません。
もし下痢に加えて血便が見られる場合は、ストレスとは別に、腸に炎症や潰瘍、腫瘍など、出血の原因となる器質的な病気が隠れている可能性が高いため、医療機関での精査が必要です。
- 市販の下痢止めを自己判断で飲んでも良いですか?
-
自己判断での下痢止めの服用は、注意が必要です。
特に、細菌性腸炎が原因の場合、下痢止めによって腸の動きを止めてしまうと、病原菌や毒素が体外に排出されにくくなり、かえって症状を悪化させたり、治癒を遅らせたりする可能性があります。
血便や高熱を伴う下痢の場合は、下痢止めは使用せず、まずは医療機関を受診して原因を特定することが最優先です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
血便+下痢の原因特定には大腸カメラが必要となります。検査の流れや観察範囲、その場のポリープ切除や生検まで、実際の進み方を先に知っておくと不安が軽減します。
【大腸ポリープの基本症状から治療法まで – 患者さんのための総合案内】
血便と下痢について学んだ皆さんには、大腸がんの前段階であるポリープの知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。予防の観点からも重要な情報です。
以上
参考文献
Holtz LR, Neill MA, Tarr PI. Acute bloody diarrhea: a medical emergency for patients of all ages. Gastroenterology. 2009 May 1;136(6):1887-98.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y, Funabiki T, Fujimori S, Kaise M. Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion. 2019 Jan 14;99(Suppl. 1):1-26.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Barr W, Smith A. Acute diarrhea in adults. American family physician. 2014 Feb 1;89(3):180-9.
Brandt LJ. Bloody diarrhea in an elderly patient. Gastroenterology. 2005 Jan 1;128(1):157-63.
Gouveia MA, Lins MT, Silva GA. Acute diarrhea with blood: diagnosis and drug treatment. Jornal de pediatria. 2020 Apr 17;96(suppl 1):20-8.
Lu PH. Umbilical region pain, diarrhea, and bloody stools. Gastroenterology. 2011 Jan 1;140(1):e1-2.
Kuşkonmaz B, Yurdakök K, Yalçin SS, Ozmert E. Comparison of acute bloody and watery diarrhea: a case control study. The Turkish Journal of Pediatrics. 2009 Apr 25;51(2):133-40.