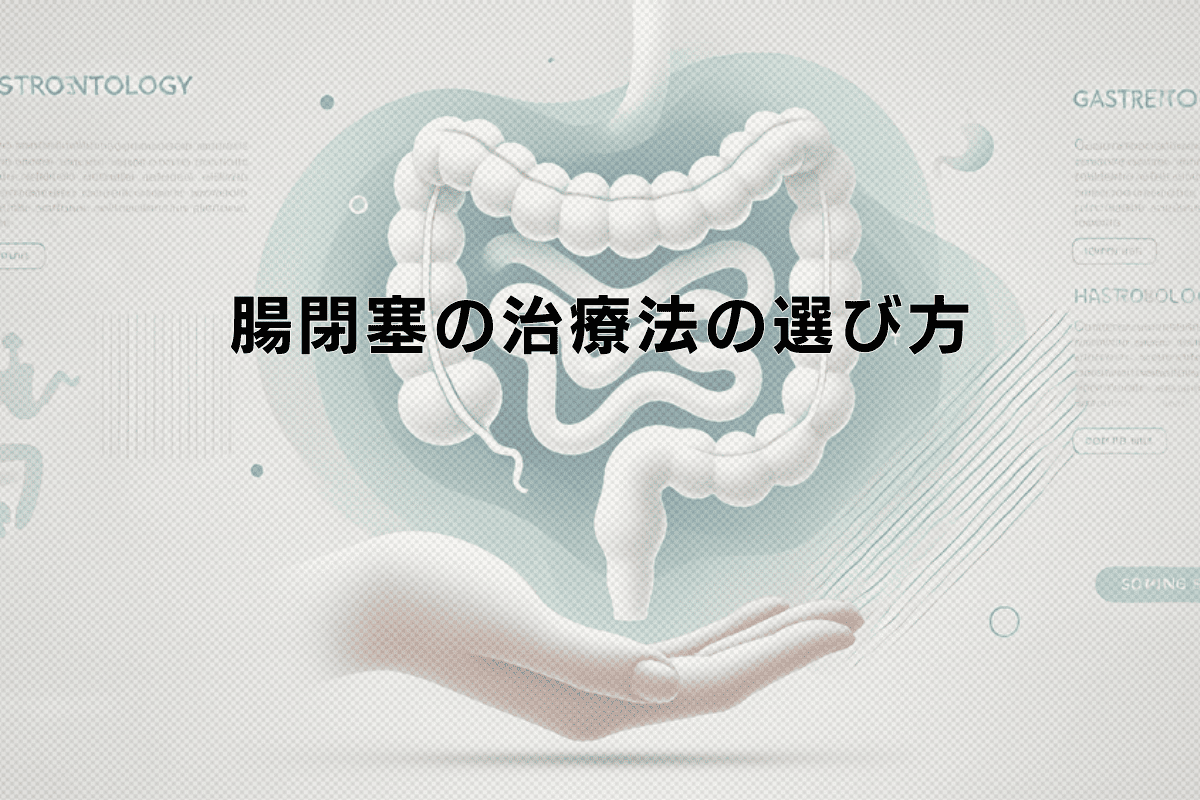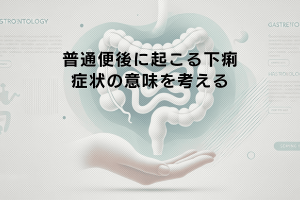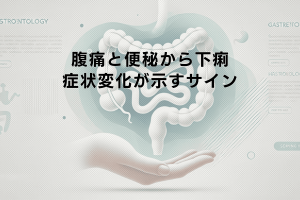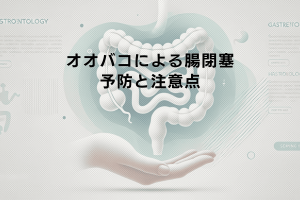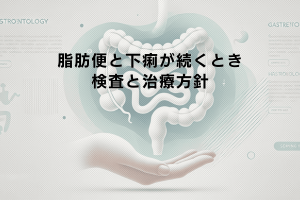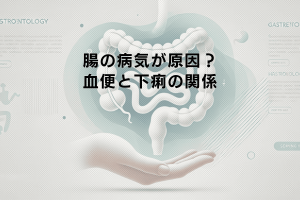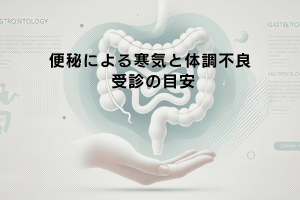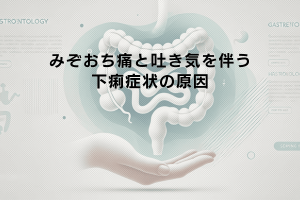腸閉塞は、腸管の一部が詰まり、便やガスなどがうまく通過しなくなる疾患で、放置すると腹痛や嘔吐が長引き、日常生活に大きな支障をきたす場合があります。治療を行う際は、原因や症状の進行度合いを総合的に考えて判断することが重要です。
検査の段階で胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡を利用する場面もあり、早期受診が回復の近道となります。
再発を防ぎながら快適な生活を維持するには、腸閉塞を理解し、自分に合った治療法を選択することが必要です。
腸閉塞とは何か
腸閉塞は、腸管の中身が正常に流れなくなる状態を指します。主な症状には激しい腹痛や嘔吐、腹部膨満などが含まれます。
原因はいくつかの種類があり、機械的に腸がふさがっている場合(腸閉塞)と、腸の動きが低下して詰まっている場合(イレウス)があり、初期症状の段階で医療機関に相談することで、重症化を予防しやすいです。
腸閉塞の基本的な定義
腸閉塞の定義は、腸管の内容物がうまく通過できなくなることです。
ガスや便が停滞すると、腸内に圧力がかかり、痛みや吐き気を起こします。完全に詰まっている場合と、一部だけが狭くなっている場合があります。
症状の特徴
激しい腹痛や嘔吐が典型的な症状ですが、そのほかにも下記のような特徴があります。
- 腹部膨満が長引く
- 便やガスがほとんど出ない
- 体温が上がる場合がある
- 脱水症状を引き起こしやすい
痛みや嘔吐のタイミングによって、詰まっている部位を推測することもあります。
腸閉塞が疑われる場合の検査
腸閉塞の検査は、問診と画像診断が中心です。X線撮影やCTによって、腸管内のガスのたまり方や位置関係を確認し、場合によっては大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡を使用して、直接原因となっている部位を探る場合もあります。
腸閉塞の主な兆候
| 主な兆候 | 具体的な特徴 |
|---|---|
| 腹部の痛み | 切り裂くような激痛が周期的に起こることが多い |
| 嘔吐 | 繰り返し吐くと脱水状態に陥りやすい |
| 腹部膨満 | ガスや水分が腸管内に滞留して膨らみが強まる |
| 便・ガスの停止 | 完全につまった場合、排便や放屁がほぼ止まる |

腸閉塞の原因とリスク要因
腸閉塞の原因は大きく分けて機械的原因と機能的原因に分類でき、手術後の癒着や腫瘍による狭窄は機械的原因に含まれ、腸の動きが極端に低下する麻痺性のものは機能的原因に含まれます。
高齢者や持病がある方は腸閉塞を引き起こしやすい傾向があるため、日頃から自分の体調を管理することが大切です。
原因の分類(機械的・機能的)
機械的原因では、物理的に腸がふさがっているため、内容物が通過しにくくなり、機能的原因(イレウス)では、腸管の動きそのものが大きく低下している場合が中心です。両者は治療法が異なり、正確な原因特定が重要です。
既往歴や術後癒着との関係
腹部手術の既往歴がある場合、術後の癒着が腸管を引っ張って通過障害を起こしやすく、特に開腹手術後は癒着しやすいため、腸閉塞のリスクが高まる傾向があります。過去に何度も腹部手術を受けた方は注意が必要です。
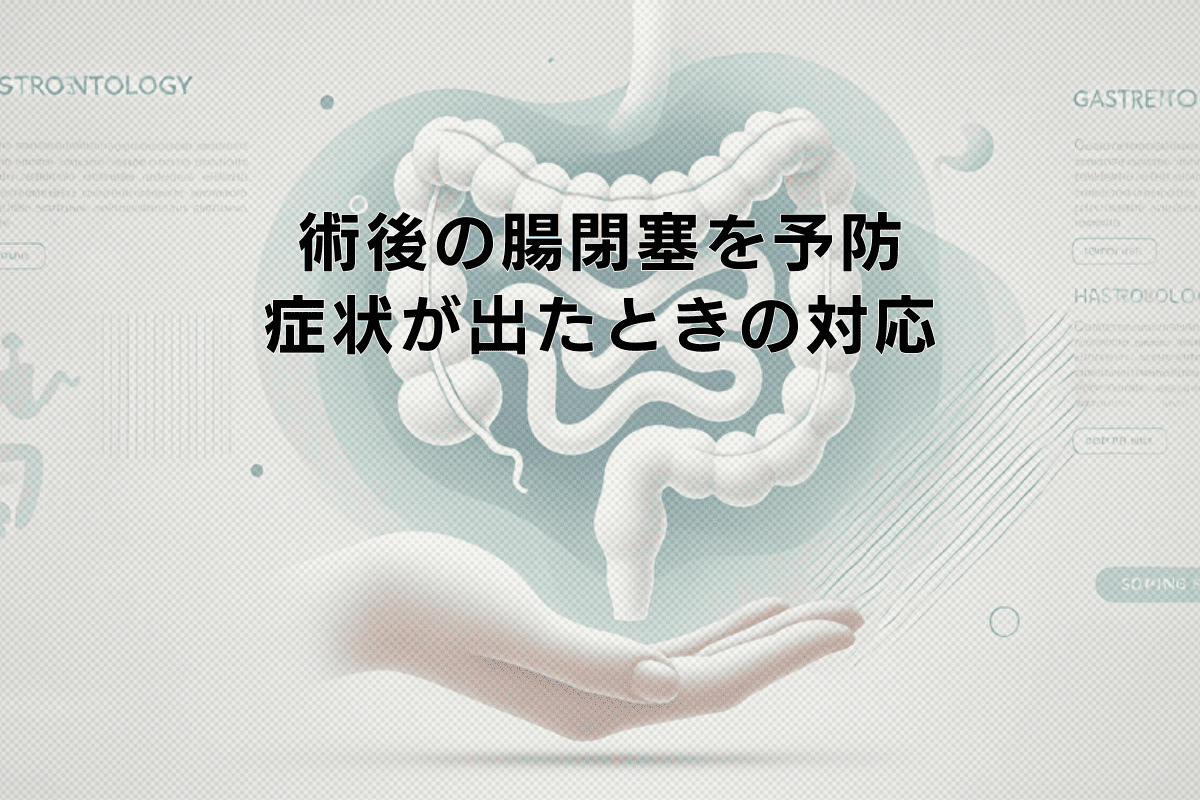
高齢者や持病がある方への注意
高齢者は腸の蠕動運動が弱まりやすく、機能的な腸閉塞を起こしやすいです。また、糖尿病などの慢性疾患を持つ方は血流や免疫の問題から腸の動きが低下しやすく、腸閉塞の危険度が上がることがあります。
腸閉塞の主なリスク要因
| リスク要因 | 具体例 |
|---|---|
| 過去の腹部手術 | 手術後の癒着が腸管を圧迫または牽引 |
| 腸の腫瘍・ポリープ | 腫瘍が大きくなり腸管を狭窄させる |
| 高齢化による蠕動低下 | 腸の動きが鈍くなることで停滞が起こりやすい |
| 慢性疾患(糖尿病など) | 代謝や血流の問題から腸の働きが低下することがある |
腸閉塞の治療を考える重要性
腸閉塞は放っておくと症状が急激に悪化しやすいです。早めに医療機関へ行き、状態を正確に把握することが回復への道を開きます。原因や重症度によっては内科的治療で十分に対応できる場合もあれば、外科的な処置が必要となる場合もあります。
再発しやすい方もいるため、根本的な対策を意識した生活改善が大切です。
医療機関を早期に受診する意義
腸閉塞による腹痛や嘔吐が続くと、体力が低下して命に関わる合併症を起こす可能性が高まり、初期の段階で受診すれば、治療の選択肢が増え、入院期間や身体的負担を軽減しやすくなります。
身体に異常を感じたら早期受診を優先したほうが良いでしょう。
内科的療法と外科的療法の選択
腸閉塞の治療は、腸管が完全にふさがっているかどうかや、腸管の血流が保たれているかどうかで方針が分かれます。
点滴で腸を休ませたり、内視鏡で詰まりを取り除いたりするのが内科的療法です。
腸管の血行障害が疑われる場合や腫瘍が原因で狭くなっている場合などは外科的に解消する必要があります。
再発を防ぐ工夫
腸閉塞は、原因を取り除いても再発しやすい特徴があります。特に癒着が原因の場合、再手術や生活習慣の乱れなどが引き金となります。医師の指導に従い、食事内容や生活リズムを整える工夫を続けることで再発リスクを下げられます。
治療を遅らせた場合に起こりうるリスク
| 主な合併症 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 腸管壊死 | 血行不良で腸の組織が壊死に至る | 早期に診断を受け、必要に応じて手術で除去 |
| パフォレーション(穿孔) | 腸壁に穴が開き腹膜炎や敗血症を起こす | 腸に過度の圧力が加わる前に治療し、常に経過を観察 |
| 脱水症 | 嘔吐と下痢により体内水分が急激に減る | 電解質バランスを重視した点滴やこまめな水分補給を行う |
早期受診のメリット
- 重症化を防ぎやすい
- 治療期間が短くなる可能性がある
- 身体的・経済的負担を減らしやすい
- 再発リスクをコントロールしやすい
腸閉塞の治療法の選び方
腸閉塞の治療法を選ぶときは、症状の重症度や原因によって方法が異なり、単純な詰まりであれば、内科的に腸を休ませる治療で回復を目指すことも多いです。腸管の血流障害や腫瘍が原因の場合は、手術が選択肢に挙がります。
治療方針を決定する際には、内視鏡検査などで詳細を把握するケースがあるので、自分の症状を知り、医師の説明をしっかり受けることが大切です。
内科的治療と外科的治療の違い
内科的治療は、まず点滴で腸を休ませることや、管を使って腸内のガス・液体を抜く方法が代表的です。
外科的治療は、腸管を物理的に切除・再建したり、腹腔鏡を使って詰まりを除去したりし、患者さんの体力や腫瘍の有無などを考慮して、内科と外科を組み合わせることもあります。
内視鏡や大腸カメラが活躍するケース
腸閉塞の原因が、大腸の腫瘍やポリープなどの可能性があるときは、大腸カメラを使用して直接内部を観察します。小腸の一部までならバルーン内視鏡を利用できる場合もあります。
内視鏡は診断だけでなく、ポリープ切除や狭くなった部分を広げるためにも活躍します。
食事療法や生活習慣の見直し
腸閉塞が軽度の場合や、すでに手術を終えて回復期に入っている場合は、腸に負担をかけにくい食事や生活習慣の改善が重要です。低脂肪・高たんぱく中心の食事や、こまめな水分補給、適度な運動を取り入れると腸の動きを助けやすくなります。
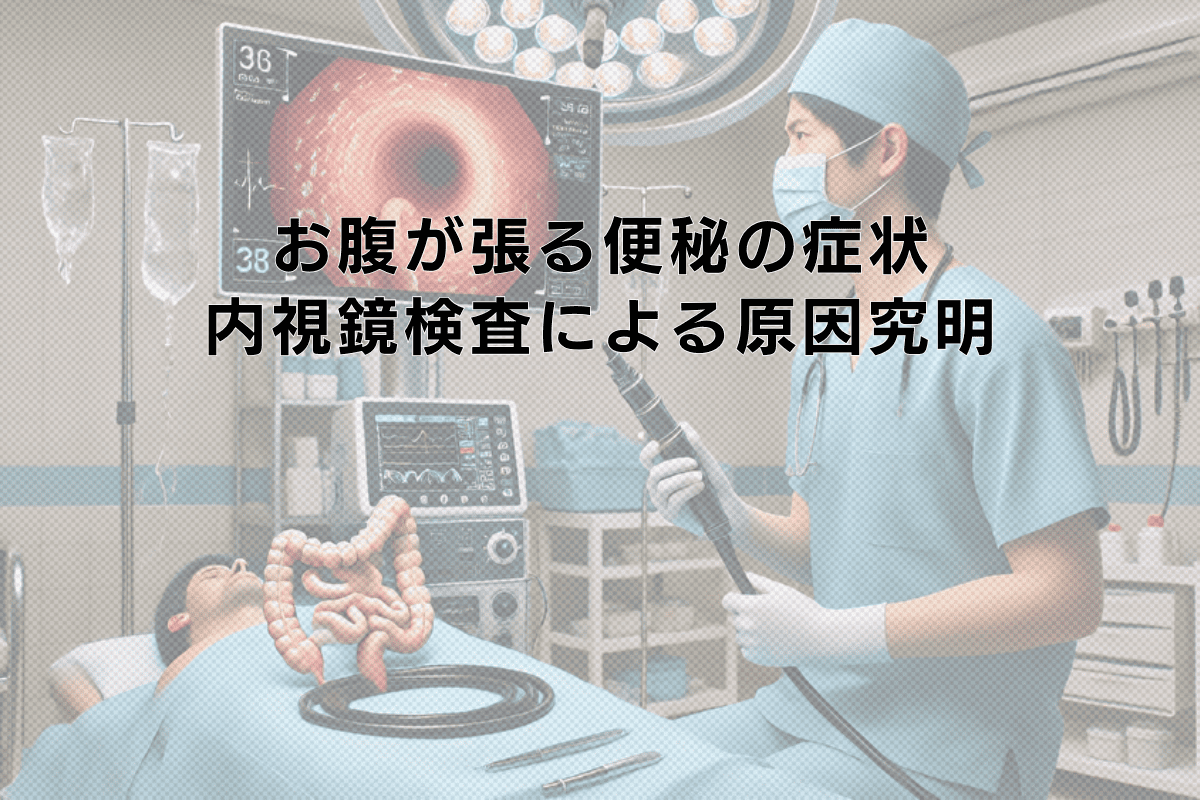
緊急性が高い場合の対処
激しい腹痛や血便、嘔吐が止まらないといった状態は、緊急度が高いと考えられます。疑わしい症状があるときは、休日や夜間でも救急病院などを利用し、早急に医療機関へ駆け込む姿勢が望ましいです。
判断に迷う場合は、電話相談や救急の対応窓口に問い合わせてもよいでしょう。
治療法の特徴
| 治療法 | 治療の流れ | メリット | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 内科的治療 | 点滴やチューブで腸管内容を減圧、食事制限を実施 | 体への負担が比較的少ない | 原因によっては改善しないことがある |
| 内視鏡治療 | 大腸カメラなどで直接観察し、ポリープや狭窄を処置 | 低侵襲な方法で原因除去が目指せる | 症状が重い場合は対応が難しいことがある |
| 腹腔鏡手術 | 小さな切開で器具を挿入し、詰まりを除去または再建 | 開腹に比べて術後の回復が早いことが多い | 癒着の程度が強い場合や出血リスクが高い場合は困難 |
| 開腹手術 | 腹部を大きく切開して原因を確認し、詰まりや腸管を切除 | 腸の状態を直接把握しやすい | 侵襲が大きく、入院期間が長引くことがある |
治療法を検討する際のポイント
- 症状の緊急度を医師と共有する
- 原因が腫瘍や癒着かどうかを正確に把握する
- 自分の体力や既往症、年齢などを考慮する
- 入院期間や術後の痛みに関して事前に理解を深める
内視鏡検査や大腸カメラ検査が必要となる場合
腸閉塞の原因が判別しにくい場合や、腸内に腫瘍やポリープの存在が疑われる場合は、胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査が必要となることがあります。
画像検査ではわからない細部を直接観察できるメリットがあるため、正確な診断につながりやすいです。
胃カメラや大腸カメラでわかること
胃カメラでは食道から胃・十二指腸までを確認でき、大腸カメラでは大腸全域と一部の小腸までを観察できます。
粘膜の状態や出血の有無、ポリープや潰瘍などの病変を詳細に把握しやすく、場合によっては組織を採取して病理検査を行うケースもあります。
大腸ポリープや腫瘍との関連
大腸ポリープや腫瘍が一定の大きさに達すると、腸内を狭くし、腸閉塞につながる場合があります。内視鏡検査を受ければ、原因が大腸ポリープなのか、腫瘍なのか、あるいは別の要因なのかを早期に見極められます。
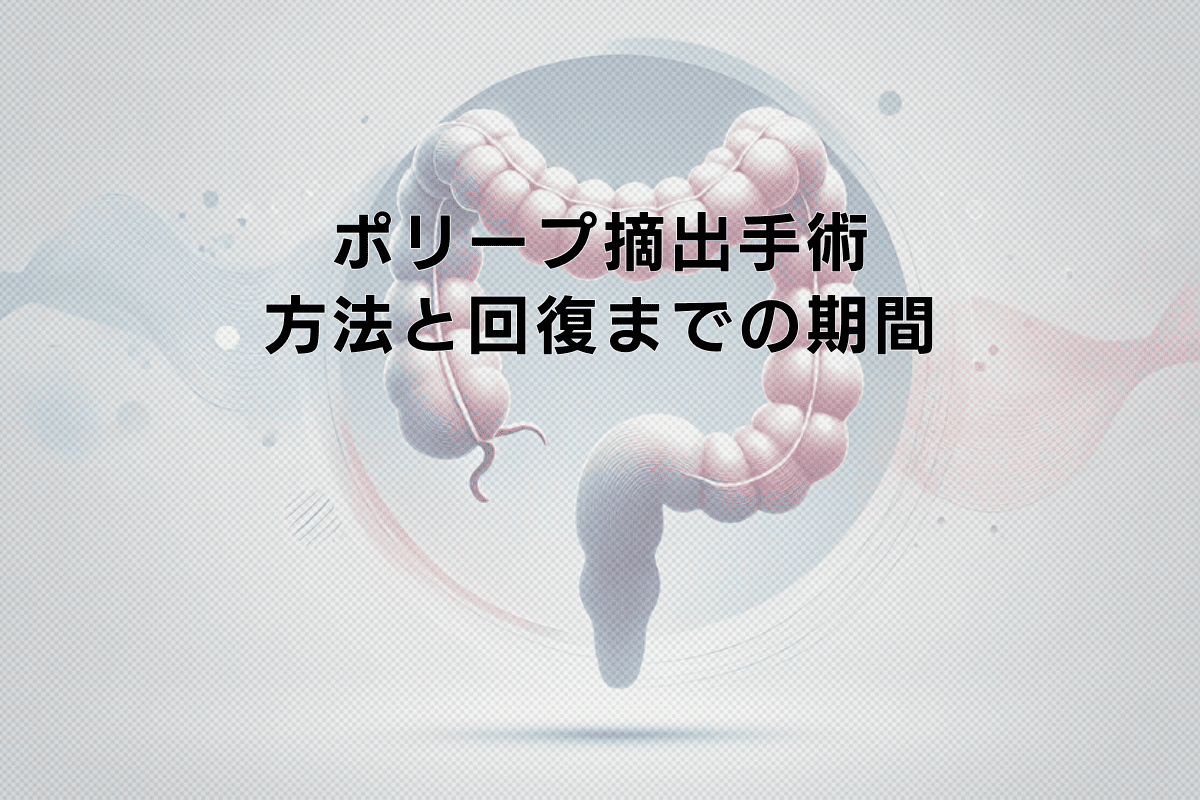
受診のタイミングと検査の流れ
腹痛や便通異常が長引き、腸閉塞が疑われると診断された場合は、医師の判断により適切なタイミングで内視鏡検査を勧められることがあります。
検査を受ける前日は食事制限が必要になる場合があり、当日は腸内を洗浄するための下剤を飲むことが多く、検査後は経過観察を行い、問題がなければ日帰りで帰宅可能なこともあります。
消化管内視鏡の種類
| 検査の種類 | 観察部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 胃カメラ | 食道・胃・十二指腸まで | 上部消化管を直接観察し、潰瘍や腫瘍の有無を確認しやすい |
| 大腸カメラ | 盲腸から直腸までの大腸全域 | 大腸の炎症やポリープ、狭窄を詳細に把握できる |
| カプセル内視鏡 | 小腸の全域(状況によっては一部観察が困難) | カプセル型カメラを飲み込み、体外レシーバーで画像を確認する |
| バルーン内視鏡 | 小腸の長い範囲 | バルーンを膨らませながら進めて小腸をくまなく調べられる |
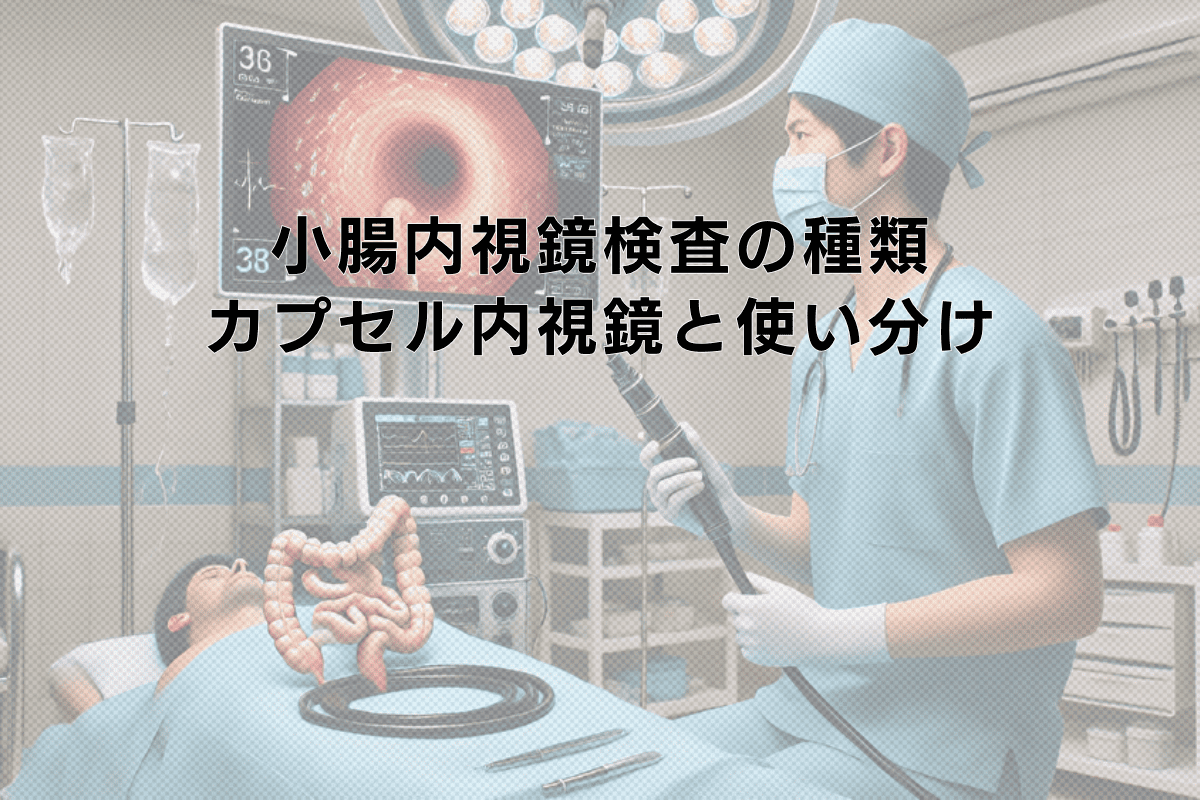
手術を選択するケースと術後の管理
腸閉塞が重症で、腸管の血行障害や組織の壊死が疑われる場合、または腫瘍が大きくて狭窄している場合などでは手術を選ぶことが多いです。
手術の形態は開腹手術と腹腔鏡手術に大別され、術後は腸の状態を観察しながら、再発防止のためのケアが必要となります。
開腹手術と腹腔鏡手術の違い
開腹手術は腹部を大きく切開し、広い視野で腸の状態を確認しながら治療を行い、腹腔鏡手術は小さな穴からカメラと器具を挿入し、画面を見ながら操作を行います。
どちらの手術を選ぶかは、腫瘍の状態や癒着の範囲、患者さんの体力などを踏まえて判断します。
術後の腸閉塞リスクを下げるために
手術後は癒着によって再び腸閉塞を起こすリスクがあり、腸の動きが鈍っているうちは、無理な飲食を避けることが大切です。
医師の指示に従いながら、体力が回復するまで少量の食事をこまめにとり、水分補給を十分に行いましょう。
退院後のフォローアップ
退院後も数週間から数か月間は再発に気を配る必要があり、定期的な外来受診で画像検査や血液検査を行い、腸の回復状態を確認します。手術部位の痛みや日常生活での負担を医師に相談することで、再発を防ぎながら生活の質を高められます。
手術法の違い
| 手術方法 | 侵襲性 | 入院期間の目安 | 術後リハビリの特徴 |
|---|---|---|---|
| 開腹手術 | 比較的大きい | 状況によるが1週間以上 | 切開部が大きいため、痛み対策と創部ケアが重要 |
| 腹腔鏡手術 | 小さい場合が多い | 3~7日程度 | 小さい創から行うため、回復が早いことが多い |
術後に心がけたい生活習慣
- 医師の指導に従った食事制限
- 水分とミネラルのバランスを意識した補給
- ウォーキングなどの軽度な運動で腸の蠕動運動をサポート
- 傷口や体調の変化を見逃さず、疑問点は早めに相談
腸閉塞と日常生活の注意点
腸閉塞の原因や程度によっては、治療後の日常生活で少しの工夫が必要で、食事や運動など、腸にかかる負担を意識しながら生活すると、再発や症状の悪化を防ぎやすくなります。
いつもと違う腹部症状を感じた場合は早めに受診し、再発の芽を摘むことが重要です。
食事の基本
野菜や果物、食物繊維を適量にとりながら、無理に脂肪分や食物繊維を増やしすぎないことがポイントです。
消化しやすいように加熱調理や刻む工夫を行い、胃腸への負担を和らげます。水分補給もこまめに行い、便をやわらかく保つと良いでしょう。
運動と生活リズム
適度な運動は腸の動きを活発にし、排便リズムを整えるのに役立ち、ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で継続的に取り組むと効果的です。毎日の就寝・起床時間を一定に保ち、規則正しい生活リズムを心がけてください。
早期発見のために注意したい症状
腸閉塞の再発や他の消化器疾患を早期に発見するには、腹部に異常を感じたときに素早く気づくことが大切で、下痢や便秘が長引く、腹部が痛む、嘔吐があるなどの症状は放置しないようにしましょう。
定期的な検診や内視鏡検査も視野に入れておくと安心です。
食事のポイント
| 食材の例 | 推奨調理法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 野菜(にんじん、かぼちゃ) | 柔らかく煮る、スープにする | 食物繊維を摂りながら消化を助ける |
| 白身魚 | 蒸す、茹でる | 油を控えてたんぱく質を効率的に摂取できる |
| 乳製品(ヨーグルトなど) | 常温で食べる | 腸内環境を整えるが、冷やしすぎに注意 |
日常で注意すべきサイン
- 腹痛や腹部の違和感が急に増した
- 便やガスの通過が止まったように感じる
- 嘔吐や吐き気が繰り返し続く
- 腹部に触れると硬い部分がある
よくある質問
- 内視鏡検査は痛いのか
-
個人差がありますが、大腸カメラや胃カメラの挿入時に不快感を覚える場合があります。鎮静剤を使うことで痛みを和らげることが可能です。医師に遠慮なく相談すると安心につながりやすいです。
- 手術はどのくらいの期間で退院できるのか
-
手術の種類や合併症の有無、個人の回復力によって異なります。
腹腔鏡手術の場合は3日から7日程度で退院するケースが多いですが、開腹手術だと1週間以上の入院となることがあります。退院後も外来フォローを受けると安心です。
- 腸閉塞は再発するのか
-
腸閉塞は原因によって再発の頻度が変わります。術後の癒着がある場合や腫瘍が一部残っている場合は再発しやすい傾向があります。定期的な診察と生活習慣の見直しによってリスクを軽減できます。
- 検査や治療費は保険適用されるのか
-
多くの場合、腸閉塞の検査や治療は健康保険の適用対象です。ただし、検査内容や治療法によって自己負担額が変わるため、事前に医療機関の窓口や保険組合に確認しておくと良いでしょう。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の原因と治療法|早期発見と対処の重要性】
腸閉塞の治療法について理解が深まったところで、さらに原因別の対処法や早期発見のポイントについても知っておくと、より包括的な理解ができます。
【術後の腸閉塞を予防する方法と症状が出たときの対応】
治療選択を知ったら、再発予防と日常の管理も確認。運動・便通管理・再発サインをやさしく整理しています。
参考文献
Yamada T, Okabayashi K, Hasegawa H, Tsuruta M, Yoo JH, Seishima R, Kitagawa Y. Meta-analysis of the risk of small bowel obstruction following open or laparoscopic colorectal surgery. Journal of British Surgery. 2016 Apr;103(5):493-503.
Ohmiya N. Management of obscure gastrointestinal bleeding: comparison of guidelines between Japan and other countries. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):204-18.
Ohmiya N, Yano T, Yamamoto H, Arakawa D, Nakamura M, Honda W, Itoh A, Hirooka Y, Niwa Y, Maeda O, Ando T. Diagnosis and treatment of obscure GI bleeding at double balloon endoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2007 Sep 1;66(3):S72-7.
Dolan EA. Malignant bowel obstruction: a review of current treatment strategies. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2011 Dec;28(8):576-82.
Dolan EA. Malignant bowel obstruction: a review of current treatment strategies. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2011 Dec;28(8):576-82.
Pujahari AK. Decision making in bowel obstruction: a review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2016 Nov 1;10(11):PE07.
Ripamonti CI, Easson AM, Gerdes H. Management of malignant bowel obstruction. European Journal of Cancer. 2008 May 1;44(8):1105-15.
Demarest K, Lavu H, Collins E, Batra V. Comprehensive diagnosis and management of malignant bowel obstruction: a review. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2023 Jan 2;37(1):91-105.
Rami Reddy SR, Cappell MS. A systematic review of the clinical presentation, diagnosis, and treatment of small bowel obstruction. Current gastroenterology reports. 2017 Jun;19:1-4.
Frago R, Ramirez E, Millan M, Kreisler E, del Valle E, Biondo S. Current management of acute malignant large bowel obstruction: a systematic review. The American Journal of Surgery. 2014 Jan 1;207(1):127-38.