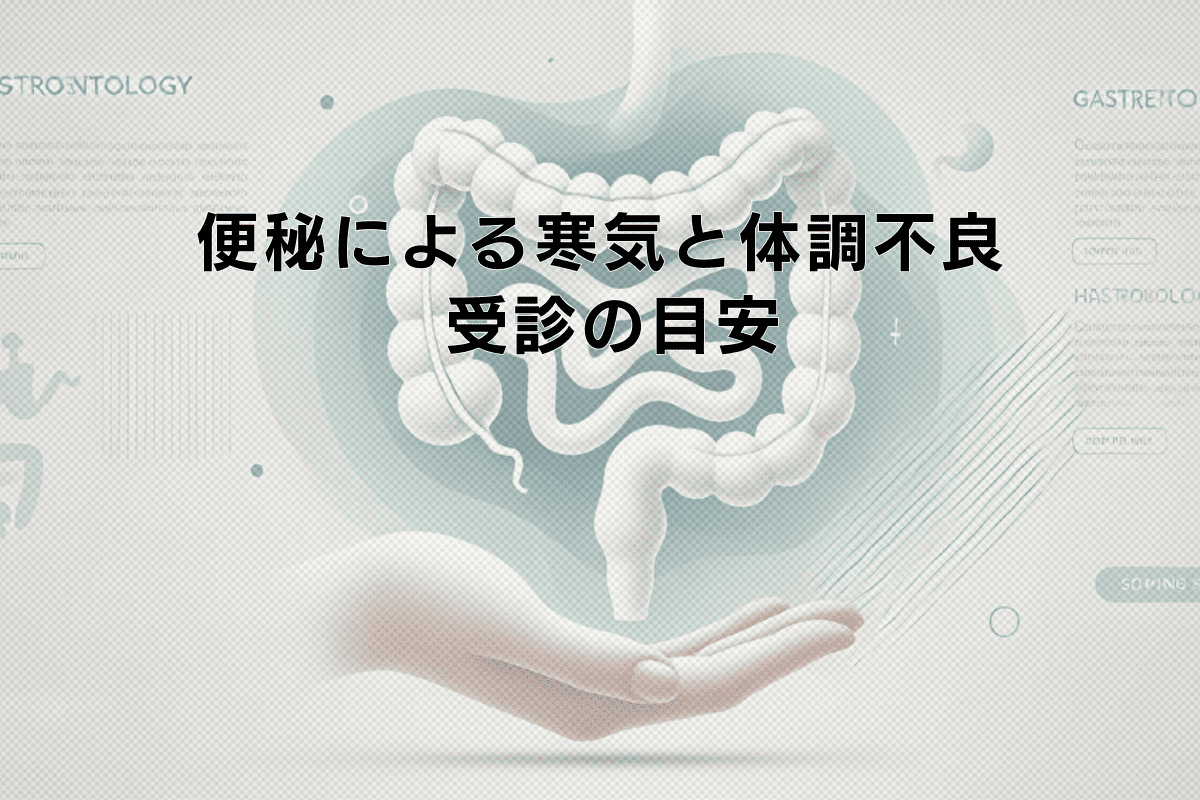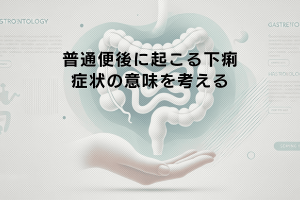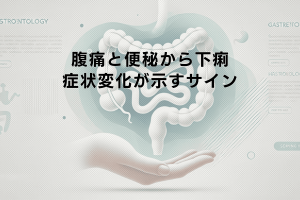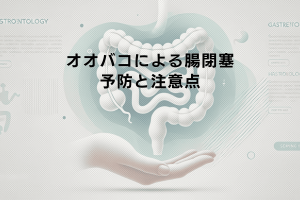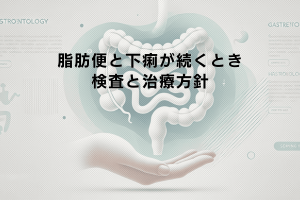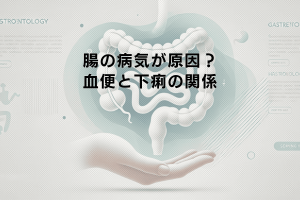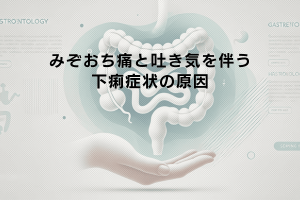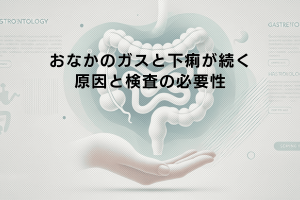便秘は、多くの人が一度は経験する非常に身近な症状ですが、便秘が長引くことで、体はさまざまなサインを発します。その一つが、無関係に思える寒気です。
その他にも、原因不明の頭痛や繰り返す肌荒れ、気分の落ち込みといった全身の体調不良が、腸内の問題に起因していることがあります。
この記事では、便秘がなぜ寒気や多様な体の不調を起こすのか、その深い関連性について、体の内側で起きていることを基に詳しく解説します。
便秘が引き起こす寒気と体調不良の全体像
便秘は、排便が滞ることで腹部の不快感を生むだけでなく、影響が全身に及ぶことを理解することが重要です。特に、原因がはっきりしない寒気や慢性的な体調不良を感じている場合、根本に便秘が隠れている可能性を考える必要があります。
便秘とはどのような状態か
便秘の定義は一つではありませんが、医学的には「本来体外へ排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」とされていて、単に排便回数が少ないことだけを指すのではありません。
排便回数が週に3回未満、排便時に強くいきむ必要がある、便が硬くて出しにくい、排便後も便が残っている感じがする(残便感)、お腹が張って苦しい、といった状態も便秘に含まれます。
便が腸内に長時間とどまることは、腸内環境の悪化を招き、さまざまな健康問題の引き金となります。
便秘の主な種類
| 種類 | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 機能性便秘 | 大腸の働きそのものに問題が生じて起こる便秘。ほとんどの慢性便秘がこのタイプに分類される。 | 不規則な食生活、食物繊維や水分不足、運動不足、ストレス、排便の我慢など。 |
| 器質性便秘 | 腸管そのものに物理的な問題(病気)があり、便の通過が妨げられて起こる。 | 大腸がん、炎症性腸疾患(クローン病など)、腸閉塞、手術後の癒着など。 |
| 症候性便秘 | 何らかの全身性の病気や、服用している薬の副作用が原因で二次的に起こる。 | 甲状腺機能低下症、糖尿病、パーキンソン病、降圧薬や抗うつ薬などの副作用。 |
なぜ便秘で寒気がするのか
便秘と寒気の結びつきは、腸内環境の悪化が引き起こす一連の体の反応によって説明できます。
便が腸内に長く滞留すると、腸内では悪玉菌が優勢になり、悪玉菌はタンパク質などを分解する過程で、アンモニア、インドール、スカトールといった有害物質(毒素)を産生します。
有害物質は腸壁から血液中に吸収され、全身の血流に乗って巡り、体は毒素を解毒しようとしますが、その過程で自律神経のバランスが乱れます。
自律神経は体温調節や血流のコントロールを担っているため、働きが乱れると血管が収縮することで、特に手足の末端への血流が悪化し、体が熱を効率的に産生・運搬できなくなり、体の芯から冷えるような寒気を感じるのです。
便秘と関連する全身の不調
腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、神経細胞が豊富で、全身の健康状態と密接に関わっているため、便秘による腸内環境の悪化は、寒気以外にも心身にわたる広範な不調を引き起こします。
血行不良は頭痛や肩こりを誘発し、吸収された毒素は肌のターンオーバーを乱して肌荒れやニキビの原因となり、また、体のエネルギー代謝も低下するため、慢性的な疲労感や倦怠感につながります。
さらに、幸福感に関わる神経伝達物質セロトニンの多くが腸で産生されるため、腸内環境の悪化はイライラや気分の落ち込みといった精神的な不調の原因にもなり得るのです。
便秘で寒気が起こる詳しい理由
便秘が寒気を起こす背景には、「自律神経の乱れ」「腸内環境の悪化と血行不良」「毒素の蓄積による代謝低下」という三つの主要な要因が複雑に絡み合っています。
自律神経の乱れが原因
自律神経は、私たちの意思とは関係なく、心臓の鼓動、呼吸、消化、体温調節といった生命維持に必要な機能を24時間体制でコントロールしていて、活動時に優位になる「交感神経」と、休息時に優位になる「副交感神経」があります。
腸の蠕動運動(便を肛門側へ送り出す動き)は、主に体がリラックスしている状態、つまり副交感神経が優位なときに活発になります。
しかし、便秘による腹部の不快感や痛み、精神的なストレスが続くと、体は常に緊張状態となり、交感神経が過剰に刺激され、自律神経全体のバランスが大きく崩れてしまうのです。
交感神経と副交感神経のバランス
交感神経が優位な状態が続くと、体は戦闘モードになり、血管は収縮し、血圧は上昇、心拍数は増加します。血管収縮は、特に手足の末端にある毛細血管で顕著に起こるため、血流が著しく低下します。
血液は体中に酸素や栄養素だけでなく、熱を運ぶ重要な役割も担っているため、血流が悪化すると体の末端から冷え始め、やがて全身の寒気として感じられます。
さらに、交感神経の緊張は消化管の働きを抑制するため、便秘をさらに悪化させるという負のスパイラルに陥りやすいです。
自律神経の乱れによる影響
| 神経 | 主な働き | 乱れた場合の影響 |
|---|---|---|
| 交感神経 | 体を活動的にする、血管を収縮させる、心拍数を上げる | 過剰になると血行不良、冷え、高血圧、消化機能の抑制(便秘の悪化)を招く |
| 副交感神経 | 体をリラックスさせる、血管を拡張させる、腸の働きを促進する | 働きが低下すると消化不良、便秘、不眠、疲労回復の遅れなどが生じる |
腸内環境の悪化と血行不良
健康な腸内では、善玉菌が悪玉菌の増殖を抑え、腸内フローラのバランスが保たれていて、善玉菌は、食物繊維などをエサにして、酪酸や酢酸といった短鎖脂肪酸を作り出します。
短鎖脂肪酸は、大腸の粘膜細胞の主要なエネルギー源となるだけでなく、腸の蠕動運動を促進したり、全身の炎症を抑えたり、免疫機能を調節したりと、非常に重要な役割を果たします。
しかし、便秘によって腸内に便が滞留すると、悪玉菌が繁殖しやすい環境となり、短鎖脂肪酸の産生が減少し、エネルギー源が不足した腸の細胞は活力を失い、蠕動運動がさらに鈍くなります。
この悪循環が血行不良を助長し、寒気を引き起こす一因となるのです。
毒素の蓄積と体の反応
腸壁には、体に必要な栄養素だけを吸収し、有害な物質の侵入を防ぐバリア機能が備わっています。
便秘によって悪玉菌が産生した毒素に長時間さらされると、バリア機能がダメージを受け、腸壁の細胞間の結合が緩んでしまう可能性が示唆されており、これは一般的にリーキーガット症候群と呼ばれる概念です。
本来であれば体内に入るはずのない毒素や未消化物までもが血液中に漏れ出してしまい、異物を処理するために、体の免疫システムや解毒を担う肝臓に大きな負担がかかります。
体は解毒作業に多くのエネルギーを費やすため、基礎代謝、つまり生命維持に必要なエネルギー産生量が低下し、基礎代謝が落ちると、体温を生み出す力も弱まり、結果として体温が上がりにくく、冷えやすい体質になってしまうのです。
ただし、腸のバリア機能については現在も研究が進められている分野であり、リーキーガット症候群は現在のところ標準的な医療として確立された疾患ではありません。
体調不良の原因として腸の状態が関係する可能性はありますが、まずは便秘の改善から取り組むことが大切です。
便秘に伴うさまざまな体調不良
便秘がもたらす影響は、お腹の張りや痛みといった局所的な症状に限りません。腸内環境の悪化は、水面に広がる波紋のように、消化器系から全身、そして精神状態にまで影響を及ぼします。
消化器系の症状
便秘は消化器系の問題であり、最も直接的な影響が現れる場所で、便の滞留は、腸そのものや関連する臓器に多大な負担をかけます。
腹痛・腹部膨満感
腹痛・腹部膨満感は最も多くの人が経験する症状です。腸内に排出されない便や、悪玉菌によって異常発酵したガスが溜まることで、お腹がパンパンに張り、重苦しい不快感や痛みが生じます。
また、溜まった便を何とか排出しようと腸が過剰に収縮することで、キリキリとした差し込むような痛み(痙攣性腹痛)を感じることもあります。
吐き気・食欲不振
大腸の動きが悪くなると、渋滞は上流の消化管である小腸や胃にまで影響を及ぼします。
胃から小腸へ内容物がスムーズに送られなくなるため、胃もたれや胸やけ、吐き気を催しやすく食欲も自然と湧かなくなり、食事量が減ることでさらに便の材料が不足し、便秘が悪化するという悪循環に陥ることも少なくありません。
重度の便秘では、腸の内容物が逆流し、嘔吐に至るケースも見られます。
全身に現れる症状
腸壁のバリア機能を通過して血液中に侵入した有害物質は、血流に乗って全身を巡り、さまざまな臓器や組織で「小さな火事」のような炎症や機能低下が起こります。
頭痛・肩こり
便秘による自律神経の乱れと血行不良は、頭痛や肩こりの典型的な原因です。
交感神経の緊張によって首や肩周りの筋肉が常にこわばり、血流が滞ることで、疲労物質が溜まりやすくなり、ズキズキとした緊張型頭痛や、岩のように重い肩こりを起こします。
また、腸内で発生した毒素が神経を刺激することも、頭痛の一因と考えられています。
肌荒れ・ニキビ
「肌は腸の鏡」という言葉があるように、腸内環境の状態は肌に顕著に現れます。腸から吸収された有害物質は、体外へ排泄されようとしますが、便という正規のルートが機能不全に陥っているため、皮膚が代替の排泄器官として使われます。
その結果、皮脂腺が刺激されて皮脂の分泌が過剰になったり、皮膚の正常なターンオーバーが乱れたりして、ニキビや吹き出物、くすみ、乾燥といった肌トラブルが頻発するようになるのです。
便秘と関連する全身症状の例
| 症状の部位 | 具体的な症状 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 頭・肩 | 緊張型頭痛、肩こり、首のこり、めまい、耳鳴り | 持続的な血行不良、自律神経の乱れ、筋肉の緊張 |
| 皮膚 | ニキビ、吹き出物、肌のくすみ、乾燥、かゆみ | 腸内からの毒素の吸収、皮膚のターンオーバーの乱れ、代謝の低下 |
| 全身 | 慢性的な倦怠感、疲労感、冷え、むくみ、口臭や体臭 | 基礎代謝の低下、栄養吸収の阻害、毒素の全身への影響 |
精神的な影響
脳と腸は、自律神経やホルモン、免疫系などを介して双方向に情報をやり取りしており、この関係は腸脳相関と呼ばれ、腸の状態は私たちの気分や感情にも深く影響します。
イライラ・気分の落ち込み
精神を安定させ、幸福感をもたらす働きから「幸せホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質セロトニンは、約90%が腸内の細胞でつくられています。
便秘によって腸内環境が悪化すると、セロトニンの産生が著しく低下し、精神的なバランスが崩れやすくなり、ささいなことでイライラしたり、理由もなく不安になったり、気分が沈んでやる気が起きなくなったりすることがあります。
慢性的な便秘による不快感そのものがストレスとなり、さらに精神状態を悪化させることも少なくありません。
危険な便秘のサインと受診の目安
多くの便秘は生活習慣の見直しで改善が期待できる機能性便秘ですが、中には重大な病気が背景に隠れている器質性便秘の可能性もあります。自己判断で市販薬を使い続けたり、放置したりすることは危険です。
すぐに医療機関を受診すべき症状
便秘に加えて、以下に挙げるような警告サインが一つでも見られる場合は、緊急を要する病気の可能性があります。夜間や休日であっても、ためらわずに救急外来などを受診してください。
- これまでに経験したことのないような激しい腹痛、冷や汗を伴う腹痛
- 便意があるのに全く便もガスも出ず、お腹がパンパンに張って苦しい
- 便秘に伴う吐き気や嘔吐が続いている
- 原因不明の発熱を伴う
- 便に鮮やかな赤い血や黒いタール状の血が混じる(血便)
このような症状は、腸が完全に詰まってしまう腸閉塞、腸に穴が開く消化管穿孔、大腸憩室炎、虚血性大腸炎など、命に関わる可能性のある病気のサインかもしれません。
緊急受診を要する症状のチェック
| 症状 | 考えられる病気 | 対応 |
|---|---|---|
| 立っていられない、動けないほどの激しい腹痛 | 腸閉塞、急性虫垂炎、消化管穿孔など | 直ちに救急車を要請するか、救急外来を受診 |
| 便もガスも出ず、嘔吐が続く | 腸閉塞(イレウス)の可能性が高い | 飲食を控え、直ちに救急外来を受診 |
| 便に鮮血が大量に混じる、または黒い便が出る | 大腸からの出血、胃や十二指腸からの出血など | 出血量が多い場合は救急、少量でも消化器科を早めに受診 |
慢性的な便秘で相談を検討するタイミング
緊急性はないものの、以下のような状態が長期間続いている場合は、一度専門医に相談することを強くお勧めします。
市販薬で一時的に対処し続けるのではなく、便秘の根本的な原因を特定し、ご自身の体質や生活習慣に合った適切な対処法を見つけることが、長期的な健康につながります。
- 市販の便秘薬を常用しており、薬がないと排便できない
- 便秘と下痢を頻繁に繰り返している(過敏性腸症候群の可能性)
- これまで便秘とは無縁だったのに、急に便秘がちになり、それが数週間以上続いている
- 便秘とともに、原因不明の体重減少が見られる
- 排便後も常に便が残っている感じがして、すっきりしない
- 便が鉛筆のように細くなった
何科を受診すればよいか
便秘の症状で受診する場合、まずは消化器内科や胃腸科が専門です。もし、かかりつけの内科医がいる場合は、そちらで相談するのも良いでしょう。
診察では、まず詳しい問診を行い、その後、お腹の音を聞いたり触ったりする腹部診察を行います。原因を詳しく調べるために、血液検査や腹部のレントゲン検査、そして必要に応じて大腸内視鏡検査(大腸カメラ)などを提案します。
特に、大腸がんのリスクが高まり始める40歳を過ぎたら、症状がなくても一度は大腸内視鏡検査を受けることが、がんの早期発見のために大切です。

自宅でできる便秘と寒気の対策
医療機関の受診が必要な危険な便秘でない場合、日々の生活習慣を見直すことが、便秘そのものと、それに伴う寒気や体調不良を改善するための最も基本的で効果的な方法です。ここでは、今日からでも実践できる対策を紹介します。
食生活の見直し
腸内環境を整え、健康的な便通を取り戻すためには、毎日の食事が非常に重要です。3食をバランス良く食べることを基本に、特に以下の点を意識してみてください。
食物繊維の積極的な摂取
食物繊維は、消化されずに大腸まで届き、便の材料となったり、善玉菌のエサになったりする重要な成分です。食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、両方をバランス良く摂取することが、理想的な便を作るための鍵となります。
食物繊維を多く含む食品
| 食物繊維の種類 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| 水溶性 | 便に水分を与えて柔らかくする。善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える。 | 海藻類(わかめ、昆布)、こんにゃく、熟した果物(りんご、バナナ)、大麦、オーツ麦 |
| 不溶性 | 水分を吸収して膨らみ、便のかさを増やす。腸壁を刺激して蠕動運動を促進する。 | きのこ類、豆類、ごぼうなどの根菜類、玄米、穀物、さつまいも |
水分補給の重要性
健康的な便の約80%は水分で構成されていて、体内の水分が不足すると、便は硬く、排出しにくい状態になります。
不溶性食物繊維を多く摂取しているにもかかわらず水分が不足すると、腸内で便が詰まりやすくなり、かえって便秘を悪化させる原因にもなり得ます。
1日に1.5リットルから2リットルを目安に、喉が渇く前に、こまめに水分を摂る習慣をつけましょう。
朝起きてすぐにコップ1杯の常温の水や白湯を飲むことは、睡眠中に休んでいた腸を目覚めさせ、蠕動運動を促すスイッチとなるため非常にお勧めです。
発酵食品とオリゴ糖の活用
ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品には、善玉菌そのものであるプロバイオティクスが豊富に含まれています。
また、玉ねぎ、ごぼう、アスパラガス、大豆製品、バナナなどに含まれるオリゴ糖は、善玉菌のエサとなるプレバイオティクスです。組み合わせて摂取することで、腸内の善玉菌を効率的に増やし、腸内環境を根本から改善する助けとなります。

生活習慣の改善
食事と同様に、日々の生活リズムや運動習慣も、腸のコンディションに大きく影響を及ぼします。
適度な運動のすすめ
運動不足は、腹筋の衰えや血行不良を招き、腸の蠕動運動を低下させる大きな原因です。ウォーキングや軽いジョギング、サイクリングなどの有酸素運動を週に数回、30分程度行うだけでも、全身の血行が促進され、腸の動きが活発になります。
また、腹筋を鍛えることは、排便時に効果的にいきむ力をつける上で重要で、日常生活の中で、エレベーターを階段にする、一駅手前で降りて歩くなど、少しでも体を動かす意識を持つことが大切です。
体を温める工夫
体が冷えると、血管が収縮して全身の血行が悪くなり、胃腸の機能も低下します。寒気を感じる場合は、体を内側と外側の両方から温める工夫が必要です。
シャワーだけで済ませるのではなく、38〜40度程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かる入浴は、副交感神経を優位にして心身をリラックスさせ、血行を促進する絶好の機会です。
また、腹巻きやカイロを活用してお腹周りを直接温める、ショウガや根菜など体を温める食材を食事に取り入れる、冷たい飲み物を避けて温かい飲み物を選ぶといった工夫も効果的です。
ストレス管理とリラックス法
過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、交感神経を優位にさせることで腸の働きを直接的に低下させます。
現代社会においてストレスを完全に取り除くことは困難ですが、自分なりの方法で上手に発散し、心身をリラックスさせる時間を作ることが非常に重要です。
趣味に没頭する、好きな音楽を聴きながら過ごす、自然の中で深呼吸をする、アロマテラピーを取り入れる、気の置けない友人と話すなど、自分が心から心地よいと感じるリラックス法を見つけ、意識的に日常生活に取り入れましょう。
医療機関で行う便秘の検査と対処法
セルフケアを続けても便秘が改善しない場合や、何らかの病気が疑われる場合には、医療機関での専門的な診断と対処が必要です。消化器内科などでは、原因を正確に突き止め、個々の患者さんに合わせた適切なアプローチを行います。
便秘の原因を探る検査
まず問診から始め、いつから便秘が始まったのか、便の性状、排便の頻度、食事や生活習慣、既往歴、現在服用中の薬、ストレスの状況などについて詳しく伺います。
その後、必要に応じて以下のような検査を行い、便秘の背後にある原因を客観的に評価します。
主な検査方法
| 検査名 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 腹部診察 | 腸の動きやガスの状態を直接把握する | 聴診器で腸の音を聞いたり、お腹を触診して張りや痛みの場所を確認したりする。 |
| 血液検査 | 全身状態や、便秘の原因となる他の病気の有無を調べる | 貧血の有無、炎症反応、甲状腺機能や電解質の異常などをチェックする。 |
| 大腸内視鏡検査 | 大腸の内部を直接観察し、器質的な病気がないか確認する | 肛門から内視鏡(カメラ)を挿入し、大腸がんやポリープ、炎症の有無などを詳細に調べる。 |
薬物療法によるアプローチ
検査結果と症状に基づき、薬物療法が必要と判断された場合は、個々の状態に最適な薬を選択します。便秘薬には作用の仕方が異なる多くの種類があり、自己判断で市販薬を漫然と使い続けることは、腸本来の機能を損なうリスクも伴います。
医師の診断のもとで、適切な薬を適切な期間使用することが大切です。
代表的な便秘薬の種類
| 薬の種類 | 主な作用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 機械的下剤(酸化マグネシウムなど) | 腸管内に水分を引き込み、便を柔らかくして量を増やす | 体に吸収されにくく、習慣性が少ないため第一選択薬として広く使われる。 |
| 刺激性下剤(センナ、ビサコジルなど) | 大腸の粘膜を直接刺激して、強制的に蠕動運動を促す | 効果は強力だが、長期連用すると腸が刺激に慣れて効きにくくなるため、頓用が原則。 |
| 新規便秘治療薬(上皮機能変容薬など) | 小腸からの水分分泌を促すなど、新しい作用で自然な排便を促す | さまざまなタイプの慢性便秘症に効果が期待でき、長期使用も可能。 |
生活習慣指導の重要性
医療機関での対処は、薬を処方するだけではありません。便秘を根本的に改善し、再発を防ぐためには、生活習慣の見直しが不可欠です。
薬物療法と並行して、個々のライフスタイルに合わせた食事指導、運動指導、排便習慣の指導などを行います。
便意がなくても毎朝決まった時間にトイレに座る習慣をつけることや、朝食を抜かずにしっかり食べることの重要性を説明し、患者さんと二人三脚で排便リズムの再構築を目指します。
薬はあくまでサポートであり、治療の主役は患者さん自身の生活改善への取り組みです。
便秘と寒気に関するよくある質問
最後に、便秘やそれに伴う寒気、体調不良に関して、患者さんから日々の診療でよく寄せられる質問と回答を、より詳しく解説する形でまとめました。
- 便秘薬を飲むと寒気が改善しますか
-
便秘薬を使用して腸内に滞留していた便が排出され、腸内環境が改善に向かうことで、寒気が軽減される可能性は十分にあります。
これは、便秘が引き起こしていた自律神経の乱れや血行不良といった根本原因が、排便によって一時的に解消されるためですが、対症療法的な側面に過ぎません。
寒気の背景に、長年の生活習慣によって作られた体質的な冷えや、慢性的なストレスによる自律神経の不調が根強く存在する場合、便秘薬だけでは根本的な改善には至らないことが多いです。
体を温める食事や入浴、適度な運動といった生活習慣の改善を併せて行い、体質そのものを変えていくという視点が重要です。
もし、便通が整っても寒気が続く場合は、便秘以外に原因がある可能性も考えられるため、改めて医療機関に相談してください。
- 子供や高齢者の便秘と寒気で注意すべき点はありますか
-
子供の場合、まだ体の機能が未熟であることに加え、学校のトイレでは排便したくないといった心理的な要因が便秘の引き金になることが少なくありません。
体調不良を的確に言葉で伝えることが難しいため、食欲がない、機嫌が悪い、お腹を痛がるそぶりを見せるなどのサインを、保護者が注意深く観察してあげることが大切です。
高齢者は、食事量の減少や活動量の低下、複数の持病に対する薬の副作用など、便秘になりやすい要因が複合的に絡み合っています。
また、加齢に伴い体温調節機能そのものが低下しているため、便秘による血行不良が寒気や体調不良に直結しやすい傾向があります。
本人が自覚しないうちに進んでいる脱水が便秘を悪化させているケースも多いため、喉の渇きを訴えなくても、こまめな水分補給を周囲が促してあげることが非常に重要です。
- 食事以外で気をつけることは何ですか
-
食事以外で最も重要なのは、規則正しい生活リズムを確立し、特に朝の時間を大切にすることです。
人間の体は、朝食を摂ることで胃が刺激され、その信号が大腸に伝わって蠕動運動が活発になる「胃・結腸反射」という仕組みを持っています。
一日の中で最も便意が起こりやすいゴールデンタイムを逃さないために、少し早起きをして、朝食をしっかり食べ、その後リラックスしてトイレに座る時間を確保する習慣をつけましょう。
たとえ便意がなくても、トイレに座るという行為自体が、脳に排便を意識させ、習慣化の第一歩です。
また、日中の適度な運動は腸への物理的な刺激となり、夜間の質の良い睡眠は、腸の働きをコントロールする副交感神経を優位にします。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞となるお腹の症状と前兆の見分け方】
便秘の影に重大な『通過障害』が隠れることも。腹部膨満や嘔吐など、注意したいサインを具体的に確認できます。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
便秘改善のメカニズムを学んだ皆さんには、実践的な腸内環境改善の知識も合わせて持っていただくと、より効果的な対策ができます。
参考文献
Tokuda Y, Takahashi O, Ohde S, Shakudo M, Yanai H, Shimbo T, Fukuhara S, Hinohara S, Fukui T. Gastrointestinal symptoms in a Japanese population: a health diary study. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2007 Jan 28;13(4):572.
Kawamura Y, Yamamoto S, Funaki Y, Ohashi W, Yamamoto K, Ozeki T, Yamaguchi Y, Tamura Y, Izawa S, Hijikata Y, Ebi M. Internet survey on the actual situation of constipation in the Japanese population under 70 years old: focus on functional constipation and constipation-predominant irritable bowel syndrome. Journal of gastroenterology. 2020 Jan;55(1):27-38.
Paudel R, Selby S. Symptoms: Abdominal Pain, Diaphoresis, Fever, Nausea, and Constipation. Emergency Medicine News. 2023 Jun 1;45(6):19-20.
Hauser SC. Gastrointestinal manifestations of systemic disease. Mayo Clinic Gastroenterology and Hepatology Board Review. 2011 Jun 23:149.
Getto L, Zeserson E, Breyer M. Vomiting, diarrhea, constipation, and gastroenteritis. Emergency medicine clinics of North America. 2011 Apr 29;29(2):211.
Lacy BE, Spangler CC. Acute, Recurrent, and Chronic Abdominal Pain. Problem‐Based Approach to Gastroenterology and Hepatology. 2012 Jan 17:44-63.
Morré SA, de Vries HJ. systemic symptoms including fever, malaise, chills. Emerging Infectious Diseases. 2005;11(7-12):1090.
Hellysaz A, Neijd M, Vesikari T, Svensson L, Hagbom M. Viral gastroenteritis: sickness symptoms and behavioral responses. MBio. 2023 Apr 25;14(2):e03567-22.
Mulhem E, Khondoker F, Kandiah S. Constipation in children and adolescents: evaluation and treatment. American family physician. 2022 May;105(5):469-78.
Mekhael M, Kristensen HØ, Larsen HM, Juul T, Emmanuel A, Krogh K, Christensen P. Transanal irrigation for neurogenic bowel disease, low anterior resection syndrome, faecal incontinence and chronic constipation: a systematic review. Journal of clinical medicine. 2021 Feb 13;10(4):753.