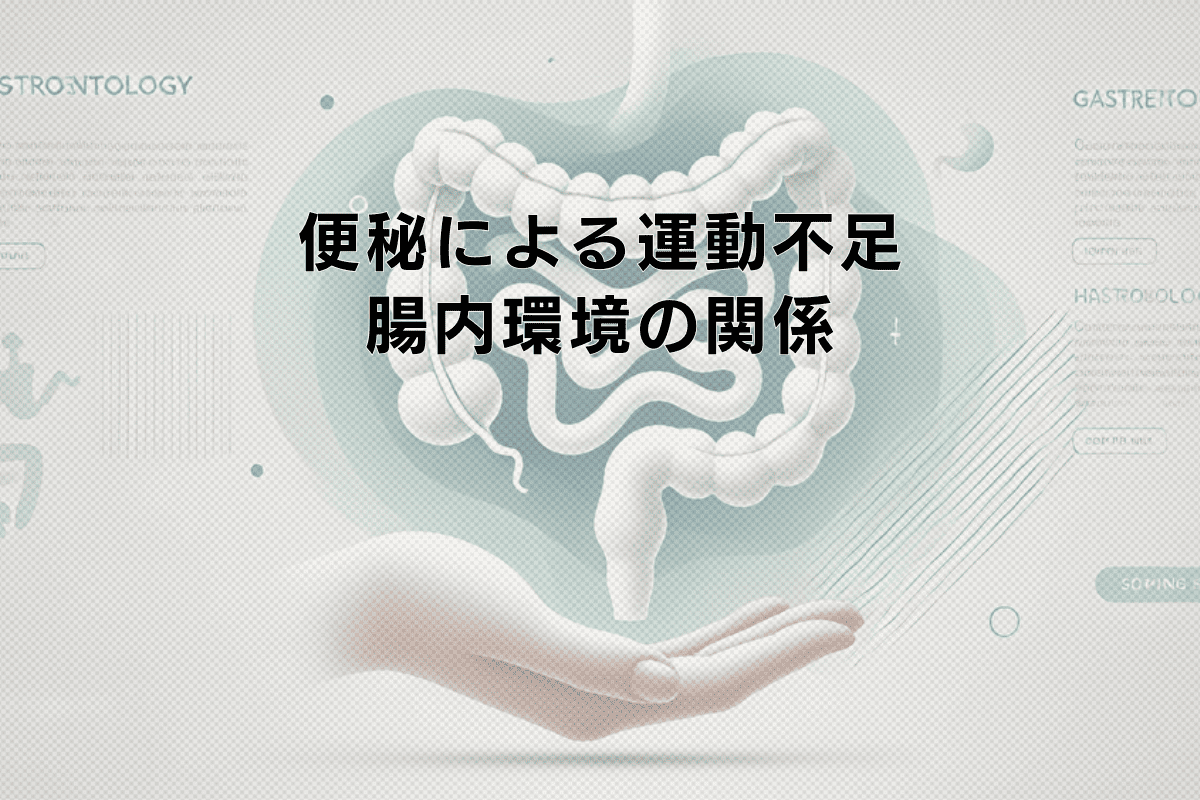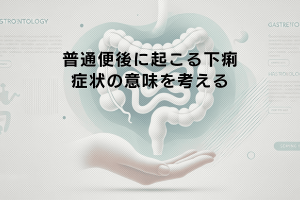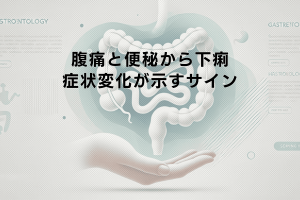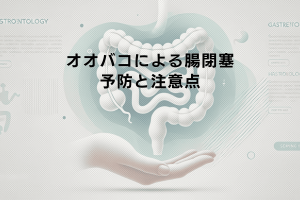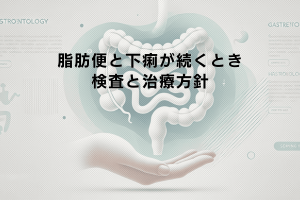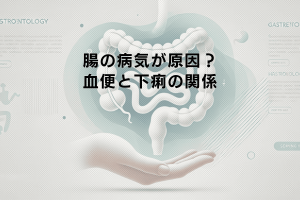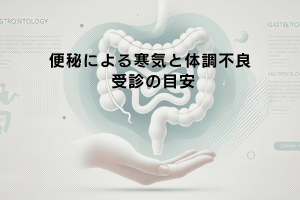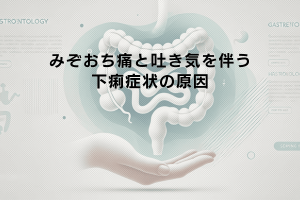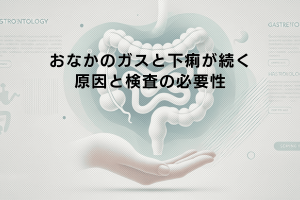便秘と運動不足、多くの人が抱えるこの二つの悩みは、互いに深く影響し合っています。
運動不足が腸の動きを鈍らせて便秘を招く一方で、便秘によるお腹の張りや不快感が、体を動かす意欲を奪ってしまうという悪循環に陥ることも少なくありません。
この記事では、便秘と運動不足の密接な関係を解き明かし、腸内環境を整える食事の基本から、無理なく始められる効果的な運動、さらには生活習慣全般の見直しまで、改善のポイントを詳しく解説します。
なぜ運動不足は便秘を起こすのか
体を動かす機会が減ると、なぜ便秘になりやすいのでしょうか。背景には、腸の働きや排便に関わる体の機能が、身体活動によって大きく支えられているという事実があります。
運動不足は、単にカロリー消費が減るだけでなく、消化管の生理的な活動そのものを停滞させる要因です。
腸のぜん動運動の低下
腸は食べ物を消化・吸収しながら、不要になったものを便として肛門まで運ぶために、常に収縮と弛緩を繰り返していて、これをぜん動運動と呼びます。
ウォーキングやジョギングなどの全身運動は、腸に物理的な刺激を与え、ぜん動運動を活発にします。
座りっぱなしの時間が長くなるなど運動不足の状態が続くと、腸への刺激が減少し、ぜん動運動が鈍くなり便が腸内に留まる時間が長くなることで水分が過剰に吸収されて硬くなり、排出しにくい便秘の状態が起きます。
腹筋力の低下と排便困難
便を体外へ押し出す際には腹圧が重要な役割を果たし、腹圧を生み出すのが、お腹周りの筋肉、特に腹筋群です。運動不足によって腹筋が衰えると、十分な腹圧をかけることが難しくなります。
便が直腸まで下りてきて便意を感じても、いきむ力が弱いために便をスムーズに押し出せず、排便に困難を感じるようになります。これは特に、加齢とともに筋力が低下しやすい高齢者や、もともと筋力が弱い女性によく見られる傾向です。
排便に関わる主な筋肉
| 筋肉名 | 役割 | 鍛える運動の例 |
|---|---|---|
| 腹直筋 | 腹圧を高めて便を押し出す | クランチ(腹筋運動) |
| 腹横筋 | 内臓を支え、腹圧を維持する | ドローイン、プランク |
| 骨盤底筋群 | 排便のコントロールを助ける | 骨盤底筋体操 |
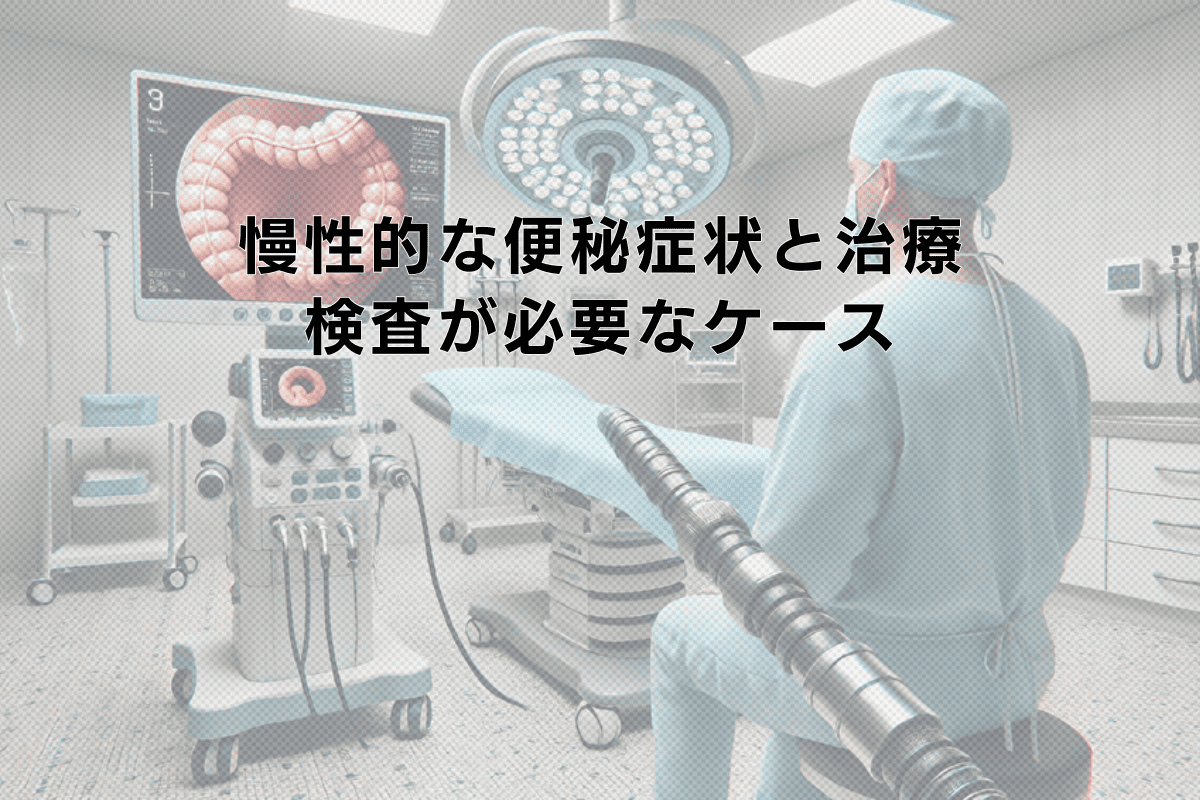
自律神経の乱れと腸機能
腸の働きは、私たちの意識とは無関係に、自律神経によってコントロールされていてます。
自律神経には、体を活動的にする交感神経と、リラックスさせる副交感神経があり、腸のぜん動運動は、主にリラックスしている時に優位になる副交感神経によって活発化します。
適度な運動は、この自律神経のバランスを整える効果がありますが、運動不足はストレスの蓄積や生活リズムの乱れにつながりやすく、自律神経のバランスを崩す原因になります。
交感神経が優位な状態が続くと、腸の動きが抑制され、便秘を引き起こしやすくなるのです。
運動不足が腸の動きに与える具体的な影響
運動不足が便秘の原因となることは理解できても、体の中で何が起こっているのかをイメージするのは難しいかもしれません。ここでは、運動不足が腸の物理的な動きや内部環境にどのような影響を及ぼすのかを、さらに詳しく見ていきます。
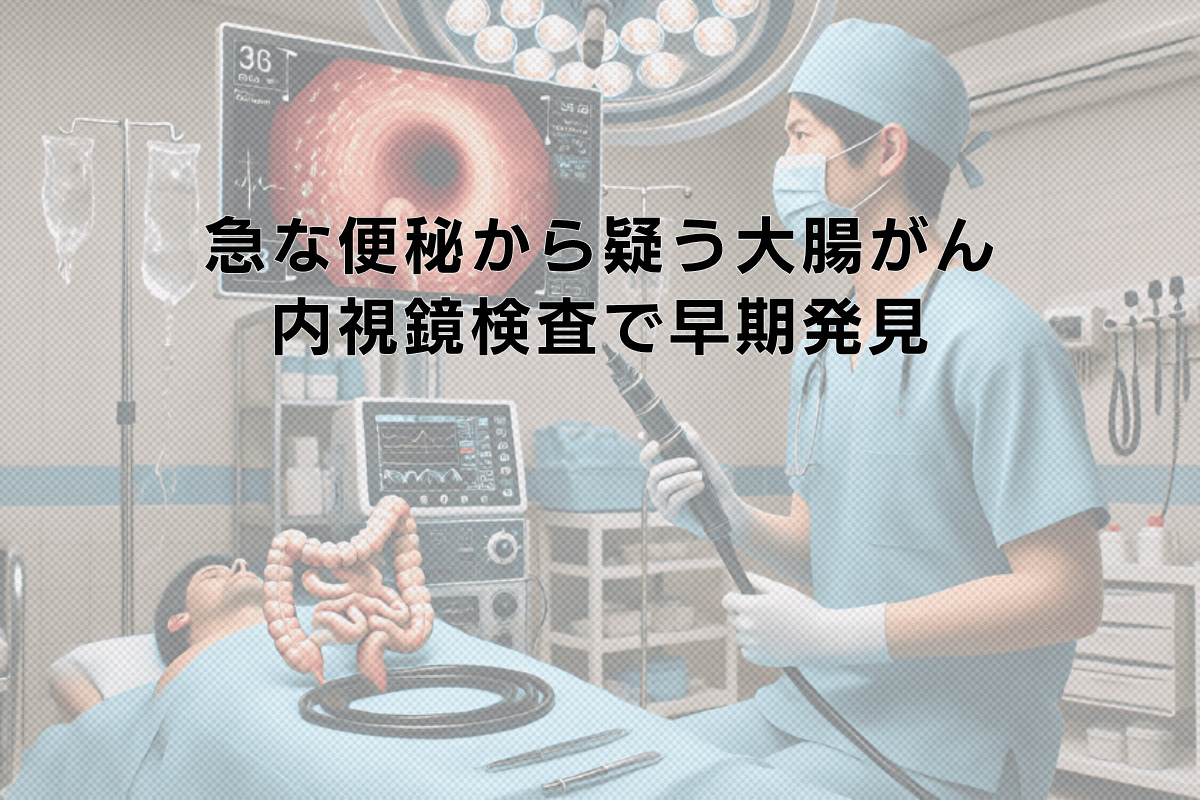
大腸の通過時間の遅延
運動不足になると、食べたものが消化されて便として排出されるまでの時間、大腸通過時間が長くなる傾向があります。
健康な状態では、便は適度な水分を含んだまま大腸を通過し、スムーズに排出されますが、ぜん動運動が鈍ることで大腸を通過する速度が遅くなると、便が腸内に滞留する時間が長引きます。
その間に、大腸で便の水分が必要以上に吸収され、便は硬く小さくなることでさらに腸内を移動しにくくなり、便秘を悪化させるという悪循環を生みます。
便の硬さと水分の関係
| 便の状態 | おおよその水分量 | 特徴 |
|---|---|---|
| 理想的な便 | 70~80% | バナナ状で、するりと出る |
| 硬い便 | 60~70% | コロコロとしていて、出すのに力が必要 |
| 水様便(下痢) | 90%以上 | 形がなく、液体状 |
血行不良による腸の冷え
体を動かさないと全身の血行が悪くなり、特に心臓から遠い腹部は、血行不良の影響を受けやすい部位です。
腸の働きも、血液によって運ばれる酸素や栄養素に支えられていて、血行が悪くなると、腸の筋肉の動きが鈍くなり、消化吸収能力も低下します。
腸が冷えた状態になり、ぜん動運動がさらに弱まる原因となります。女性は男性に比べて筋肉量が少なく、体が冷えやすいため、運動不足による血行不良が便秘に直結しやすいです。
ガスが溜まりやすくなる
腸内では、食べ物の消化の際に常にガスが発生しますが、適度な運動は腸の動きを活発にして、発生したガスを自然に排出するのを助けます。しかし、運動不足で腸の動きが悪いと、ガスが腸内に溜まりやすくなります。
溜まったガスは、お腹の張りや不快感の原因になるだけでなく、腸壁を圧迫してさらに腸の動きを妨げ、便秘を助長することがあります。お腹がゴロゴロ鳴る、おならがよく出る、といった症状は、腸内にガスが溜まっているサインかもしれません。
便秘が運動不足を招く悪循環
これまでは運動不足が便秘を起こす側面を見てきましたが、逆に便秘そのものが運動する気力を削ぎ、さらなる運動不足を招くという負の連鎖もあります。この悪循環を断ち切ることが、便秘解消の重要な鍵です。
お腹の張りや腹痛による不快感
便秘になると腸内に便やガスが溜まり、お腹が張って苦しく感じることがあります。時には、シクシクとした腹痛を伴うこともあり、このような不快な症状があると、体を動かすこと自体が億劫になります。
運動をしようと思っても、お腹のことが気になって集中できなかったり、体をひねったり曲げたりする動作で痛みを感じたりするため、自然と活動量が減ってしまい、さらなる便秘の悪化と運動不足を招くのです。
全身の倦怠感と意欲の低下
便秘が続くと腸内で悪玉菌が増殖し、有害物質が発生します。有害物質が腸から吸収されて血液中に入り込むと、全身を巡って様々な不調を起こし、肌荒れや頭痛のほか、原因のはっきりしないだるさや疲労感もその一つです。
体が重く感じ、何事にもやる気が出ない状態では、積極的に運動に取り組むことは難しいでしょう。便秘による体調不良が、精神的な意欲さえも低下させてしまいます。
便秘が起こす可能性のある不調
- お腹の張り、腹痛
- 肌荒れ、吹き出物
- 頭痛、肩こり
- 全身の倦怠感、疲労感
- 食欲不振、吐き気
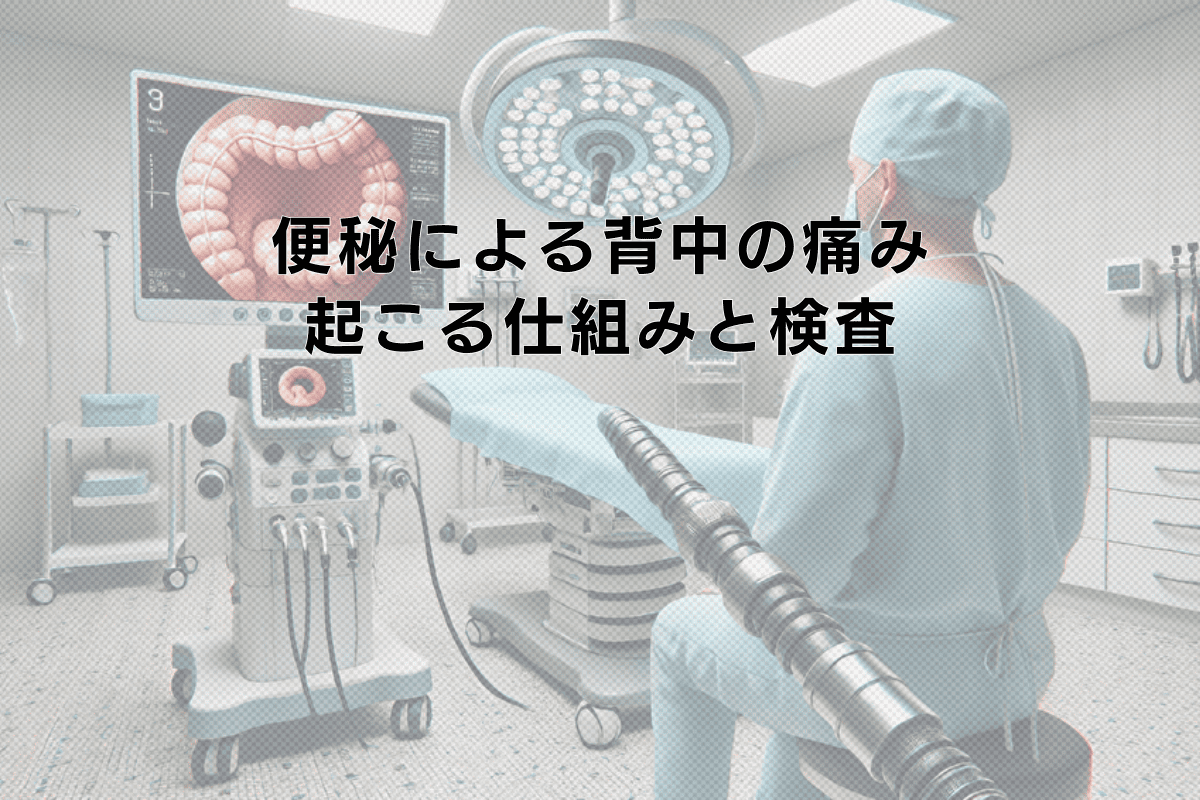
悪循環を断ち切るための考え方
便秘と運動不足の悪循環を断ち切るためには、完璧を目指さないことが大切です。お腹が苦しい時に無理に激しい運動をする必要はありません。
まずは、気分転換に近所を少し散歩する、テレビを見ながら簡単なストレッチをするなど、ごく軽い活動から始めてみましょう。少しでも体を動かすことで、腸が刺激され、気分もリフレッシュできます。
小さな一歩が、悪循環を断ち切るきっかけになるので、できることから少しずつ取り組む姿勢が重要です。
腸内環境を整える食事の基本
運動と並行して便秘改善に欠かせないのが日々の食事で、腸内に棲む無数の細菌、腸内フローラのバランスを整えることが、快便への近道です。
食物繊維の重要性と種類
食物繊維は、便秘解消に役立つ栄養素の代表格で、水に溶けにくい不溶性食物繊維と、水に溶けやすい水溶性食物繊維の2種類があり、それぞれ異なる働きで腸に作用します。両方をバランス良く摂取することが理想的です。
不溶性食物繊維は、水分を吸収して便のカサを増やし、腸壁を刺激してぜん動運動を促します。水溶性食物繊維は、水に溶けてゲル状になり、便を柔らかくして滑りを良くし、また、善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える働きもあります。
食物繊維を多く含む食品
| 食物繊維の種類 | 主な働き | 多く含む食品の例 |
|---|---|---|
| 不溶性食物繊維 | 便のカサを増やす | 玄米、ごぼう、きのこ類、豆類 |
| 水溶性食物繊維 | 便を柔らかくする | 海藻類、こんにゃく、果物、大麦 |
善玉菌を増やす発酵食品
腸内には、体に良い影響を与える善玉菌、悪い影響を及ぼす悪玉菌、そしてどちらでもない日和見菌があります。便秘の人の腸内は、悪玉菌が優勢になっていることが多く、腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やすことが大切です。
ヨーグルトやチーズ、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌が含まれていて、日常的に食事に取り入れることで腸内の善玉菌を補充し、働きを助けることができます。

十分な水分補給
便秘解消のためには、十分な水分を摂ることも非常に重要で、水分が不足すると便が硬くなり、排出しにくくなります。
特に食物繊維を多く摂ることを意識している場合は、水分もセットで摂取しないと、かえって便が硬くなり便秘を悪化させることがあるため注意が必要です。1日に1.5リットルから2リットルを目安に、こまめに水分を補給しましょう。
朝起きてすぐにコップ1杯の水を飲むと、腸が刺激されて便意を催しやすくなります。
水分補給のポイント
| タイミング | ポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 起床時 | コップ1杯の常温の水か白湯を飲む | 胃・結腸反射を促し、腸の目覚めを助ける |
| 食事中 | スープや味噌汁などを取り入れる | 食べ物の消化を助け、水分も補給できる |
| 日中 | のどが渇く前にこまめに飲む | 体内の水分量を常に一定に保つ |

便秘改善におすすめの運動とストレッチ
食事の見直しと合わせて運動することも大切で、腸を優しく刺激し全身の血行を促すような、続けやすい運動を取り入れることが改善への鍵です。
手軽に始められるウォーキング
特別な道具も場所も必要なく、誰でもすぐに始められるのがウォーキングです。歩くことによるリズミカルな振動が腸に伝わり、ぜん動運動を促進し、また、全身の血行が良くなり、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
まずは1日15分から20分程度、普段より少し大股で、腕を軽く振って歩くことを意識し、慣れてきたら、徐々に時間や距離を延ばしていくと良いでしょう。景色を楽しみながら、リラックスして行うことが継続のコツです。
お腹周りを刺激するストレッチ
硬くなったお腹周りの筋肉をほぐし、腸に直接的な刺激を与えるストレッチも効果的です。特に、体をひねる動作は、大腸の走行に沿って刺激を与えることができ、便の移動を助けます。
寝る前や朝起きた時など、リラックスした状態で行うのがおすすめです。痛みを感じない、気持ち良い範囲でゆっくりと行いましょう。
お腹ひねりストレッチ
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. 仰向けに寝て、両膝を立てる | 肩は床から離さないようにする |
| 2. 両膝を揃えたまま、ゆっくりと右に倒す | 顔は膝と反対の左側を向く |
| 3. その状態で20秒ほどキープし、ゆっくり元に戻す | 深い呼吸を意識する |
| 4. 反対側も同様に行う | 左右交互に数回繰り返す |
腹筋を鍛える軽いエクササイズ
排便に必要な腹圧を高めるために、腹筋を鍛えることも有効です。ただし、便秘で苦しい時に無理な腹筋運動を行うのは避けましょう。
まずは、お腹をへこませた状態をキープするドローインのように、体に負担の少ないエクササイズから始めてください。ドローインは、インナーマッスルである腹横筋を鍛えることができ、立ったままでも座ったままでも行える手軽な運動です。
ドローインのやり方
- 背筋を伸ばして立つ、または座る
- 息をゆっくりと吐きながら、おへそを背中に近づけるイメージでお腹をへこませる
- お腹をへこませたまま、浅い呼吸を15~30秒続ける
ヨガやピラティス
ヨガやピラティスは、深い呼吸とともに行うポーズや動きが特徴です。体をねじったり、股関節を広げたりするポーズは、直接的に腸を刺激し、その働きを活性化させます。
また、深い呼吸は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があるため、ストレス性の便秘にも有効です。自律神経のバランスを整えながら、インナーマッスルを鍛えることができるため、便秘改善には非常に適しています。
運動以外で見直したい生活習慣
便秘の改善には、運動や食事だけでなく、日々の何気ない生活習慣も大きく関わっています。規則正しい生活リズムを整えることが、腸の健康を取り戻すための土台となります。
規則正しい生活リズム
私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる体内時計が備わっていて、腸の活動も体内時計のリズムに影響されます。
毎日同じ時間に起きて同じ時間に食事を摂り、同じ時間に寝るという規則正しい生活は、体内時計を正常に保ち自律神経のバランスを整えます。
特に、朝食をしっかり摂ることは、睡眠中に休んでいた腸を目覚めさせ、ぜん動運動を開始させるために重要です。
便意を我慢しない
便意は、便が直腸に到達したことを知らせるサインです。便意を我慢することを繰り返していると、直腸のセンサーが鈍くなり、便が来ても便意を感じにくくなってしまい、直腸性便秘の原因になります。
便意を感じたら、できるだけ時間を確保してトイレに行く習慣をつけましょう。朝食後は胃に食べ物が入ることで大腸が動き出す胃・結腸反射が起こりやすく、便意を感じやすいゴールデンタイムです。
少し余裕を持って起床し、朝の排便習慣を確立することが理想です。
トイレ環境を整えるポイント
| 項目 | 工夫の例 | 目的 |
|---|---|---|
| 時間 | 朝食後に5~10分程度のトイレタイムを確保する | 焦らずに排便に集中できる環境を作る |
| 姿勢 | 足元に小さな台を置き、前傾姿勢をとる | 直腸がまっすぐになり、便を排出しやすくなる |
| 環境 | リラックスできる本や音楽を持ち込む | トイレがプレッシャーの場にならないようにする |
ストレスマネジメント
腸は第二の脳とも呼ばれるほどストレスの影響を敏感に受け、強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になります。
その結果、腸の動きが抑制されてしまい、けいれん性の便秘(ストレスで腸が過敏になり、便がスムーズに送られない状態)などを起こすことがあります。
自分なりのストレス解消法を見つけることが重要です。趣味に没頭する時間を作ったり、ゆっくり入浴してリラックスしたり、信頼できる人に話を聞いてもらったりするなど、心と体を休ませる時間を意識的に作りましょう。
セルフケアで改善しない場合の考え方
これまで紹介した食事や運動、生活習慣の改善を試みても、便秘がなかなか良くならない場合もあります。また、便秘の背景に何らかの病気が隠れている可能性もゼロではありません。
セルフケアは基本ですが、限界を感じた時には専門家の助けを借りることも大切です。
医療機関を受診する目安
市販薬を試しても効果がない、便秘と下痢を繰り返す、急にひどい便秘になった、腹痛や吐き気、体重減少などを伴う、便に血が混じる、などの場合は自己判断で様子を見ずに、消化器内科や胃腸科などの医療機関を受診してください。
このような症状は、大腸がんや炎症性腸疾患など、他の病気のサインである可能性も考えられます。
便秘治療で用いる薬の種類
医療機関では、便秘のタイプや患者さんの状態に合わせて様々な薬を処方します。
市販薬で一般的なのは、腸を直接刺激してぜん動運動を促す刺激性下剤ですが、長期間使用すると効果が弱まったり、腸の機能が低下したりすることがあり注意が必要です。
医療機関では、便の水分量を増やして柔らかくする酸化マグネシウムや、新しい作用で自然な排便を促す薬など、選択肢が豊富にあります。
主な便秘治療薬
- 酸化マグネシウム(便を柔らかくする)
- ルビプロストン、リナクロチド(腸液の分泌を促す)
- エロビキシバット(胆汁酸の再吸収を抑制し、大腸を刺激する)
- 刺激性下剤(ピコスルファートナトリウムなど)
よくある質問
最後に、便秘と運動に関するよくある質問にお答えします。
- 運動はどのくらいの頻度で行うべきですか
-
毎日行うのが理想ですが、まずは週に3回程度から始めてみましょう。大切なのは、強度よりも継続することです。
1回30分の運動を週3回行う、あるいは毎日10分のストレッチと15分のウォーキングを組み合わせるなど、ご自身のライフスタイルに合わせて続けやすい計画を立てることが成功の鍵です。
- 運動するのに良い時間帯はありますか
-
基本的には、ご自身がリラックスして取り組める時間帯であればいつでも構いません。ただし、食後すぐの激しい運動は消化の妨げになるため、食後1時間以上は空けるのが良いでしょう。
朝の運動は交感神経を活発にし、一日を活動的に始めるのに役立ちます。夕方から夜にかけての軽い運動やストレッチは、副交感神経を優位にし、質の良い睡眠につながるため、これもまた便秘改善に効果的です。
- お腹が張っている時に運動しても大丈夫ですか
-
お腹の張りが強い時や痛みがある時に、無理に運動する必要はありません。そのような時は、体を休ませることを優先しましょう。ただし、全く動かないでいると、かえってガスが溜まりやすくなることもあります。
もし動けるようであれば、室内をゆっくり歩いたり、仰向けになって膝を抱えるガス抜きのポーズをとったりする程度の軽い動きは、不快感の緩和に役立つ場合があります。
- プロテインを飲むと便秘になりますか
-
プロテインの摂取が直接便秘の原因になるわけではありませんが、間接的に影響する可能性はあります。
プロテインを多く摂取することで、食事全体のバランスが崩れ、便のカサを増やす食物繊維の摂取量が減ってしまうことがあります。また、一部のプロテインは消化に時間がかかり、腸に負担をかけることも考えられます。
プロテインを利用する場合は、それだけに頼らず、野菜や海藻など食物繊維が豊富な食品も意識して食事に取り入れ、十分な水分を補給することを忘れないようにしましょう。
次に読むことをお勧めする記事
【慢性的な便秘の症状と治療法|検査が必要なケース】
運動や食事で良くならない場合、“次は検査や薬は?”と迷う方も多いはず。治療の選択肢と受診の目安を丁寧に解説しています。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
腸内環境の全体像を掴むと、発酵食品や食物繊維の活かし方が一段と明確になります。日々の選択に役立つ内容です。
参考文献
Ohkusa T, Koido S, Nishikawa Y, Sato N. Gut microbiota and chronic constipation: a review and update. Frontiers in medicine. 2019 Feb 12;6:19.
Watanabe J, Furukawa S, Yamamoto Y, Kato A, Kusumoto K, Takeshita E, Ikeda Y, Yamamoto N, Saeki Y, Miyake T, Yoshida O. Exercise Habits, Including Exercising With Partners, and the Prevalence of Self-Reported Constipation in Young Japanese People: A Cross-Sectional Study. Cureus. 2024 Nov 25;16(11).
Shiba S, Masunaga T, Tamamura Y, Matsuura M, Nishikimi T. The Relationship between the Severity of Constipation and Exercise Status in the Japanese Population according to Questionnaire Survey. GastroHep. 2022;2022(1):2378353.
Morita E, Yokoyama H, Imai D, Takeda R, Ota A, Kawai E, Hisada T, Emoto M, Suzuki Y, Okazaki K. Aerobic exercise training with brisk walking increases intestinal bacteroides in healthy elderly women. Nutrients. 2019 Apr 17;11(4):868.
Gao R, Tao Y, Zhou C, Li J, Wang X, Chen L, Li F, Guo L. Exercise therapy in patients with constipation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Scandinavian journal of gastroenterology. 2019 Feb 1;54(2):169-77.
Erhardt R, Harnett JE, Steels E, Steadman KJ. Functional constipation and the effect of prebiotics on the gut microbiota: a review. British Journal of Nutrition. 2023 Sep;130(6):1015-23.
HU X, YE J, WANG L, PANG R, WANG W, ZHANG A. Possible mechanism of chronic constipation improvement via exercise-induced changes in gut microbiota composition and metabolites. Chinese General Practice. 2021 May 20;24(15):1984.
Flanczewski S, Gajek-Flanczewska W, Walczak A, Wirkijowski J, Niegowska W, Woźniak P, Kidacki K, Wiklińska A, Śliwińska M, Wójtowicz K, Jaroń A. Clinical management of constipation–the role of physical activity-systematic review. Quality in Sport. 2024 Nov 10;31:55135-.
Al-Beltagi M, Saeed NK, Bediwy AS, El-Sawaf Y, Elbatarny A, Elbeltagi R. Exploring the gut-exercise link: A systematic review of gastrointestinal disorders in physical activity. World Journal of Gastroenterology. 2025 Jun 14;31(22):106835.
Kim SJ. Diet, physical activity, and chronic constipation: unveiling the combined effects for better treatment strategies. Journal of Neurogastroenterology and Motility. 2024 Jul 30;30(3):255.