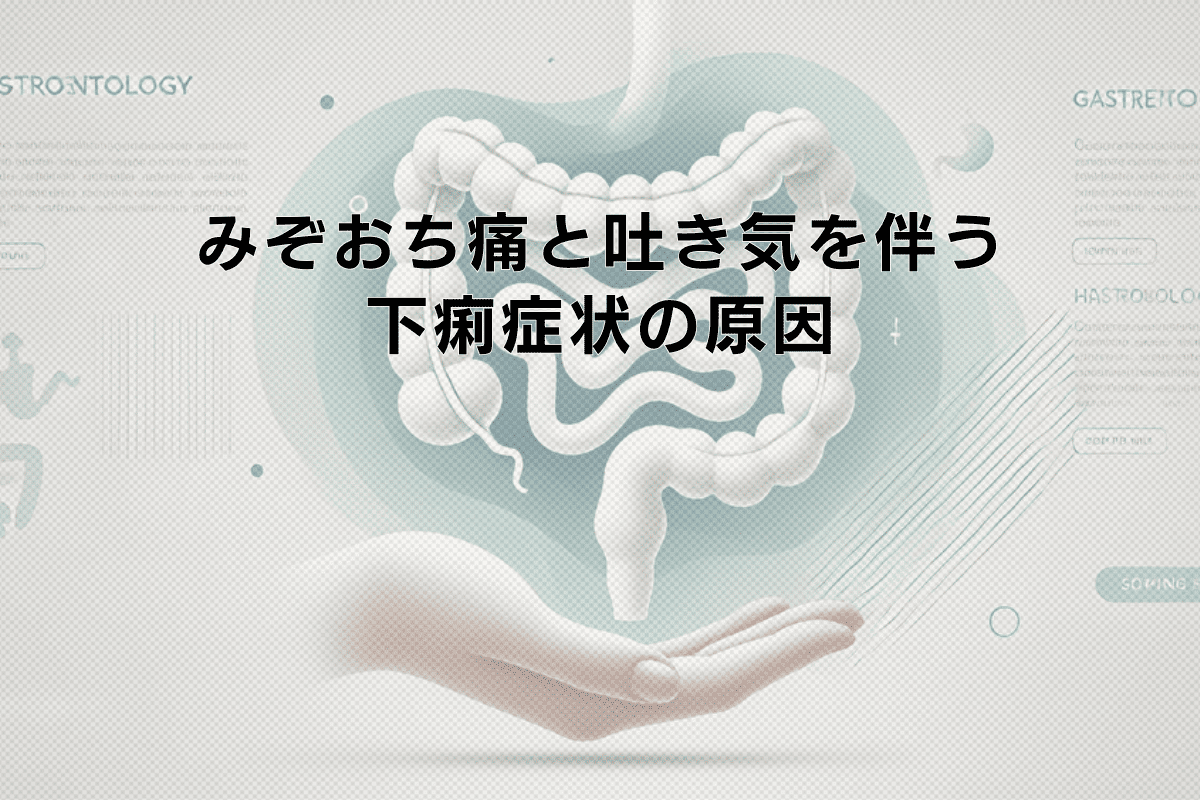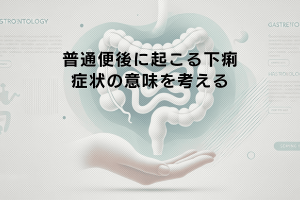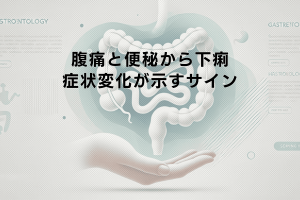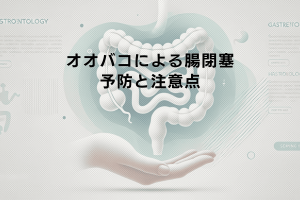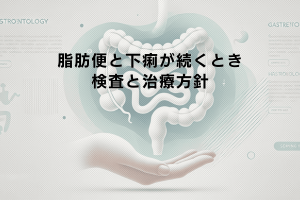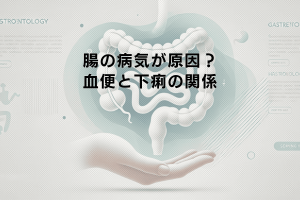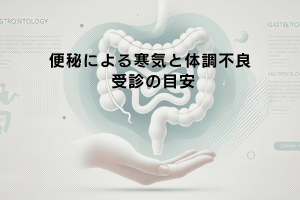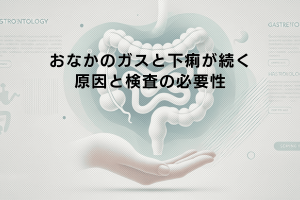突然襲ってくる、みぞおちのキリキリとした痛み。それに加えて、吐き気やむかつき、さらには下痢まで伴うと、何か重い病気ではないかと大きな不安を感じるものです。
このような症状は、誰もが一度は経験する可能性のある、ありふれた不調である一方、中には注意が必要な病気が隠れていることもあります。
この記事では、みぞおちの痛み、吐き気、下痢という3つの症状が同時に起こる場合に考えられる主な原因について、解説します。
みぞおちの痛み・吐き気・下痢は体の危険信号
不快な症状が同時に現れる時、私たちの消化器系は一体どのような状態にあるのでしょうか。まず、症状が示す体のサインと、背景にある消化管の働きについて説明します。
みぞおち(心窩部)とはどのあたりか
一般的にみぞおちと呼ばれる場所は、医学的には心窩部(しんかぶ)といい、胸骨の下端、左右の肋骨が合わさる少し下の、くぼんだ部分です。
周辺には、胃や十二指腸、膵臓、胆のうといった、消化に重要な役割を果たす臓器が集中しているため、みぞおちの痛みは、臓器のいずれかに何らかの異常が起きていることを示す重要なサインとなります。
なぜ3つの症状が同時に起こるのか
みぞおちの痛み、吐き気、下痢は、それぞれ別の症状に見えますが、消化器系の働きという観点からは密接に関連しています。
ウイルスや細菌が胃腸に侵入すると、体は異物を体外へ排出しようとし、この時、胃は内容物を上(口)から排出しようとして吐き気を、腸は下(肛門)から排出しようとして下痢を起こします。
そして、胃や腸の粘膜が炎症を起こすことで、みぞおち周辺に痛みを感じるのです。
症状から考えられる消化器の働き
消化管は口から入った食べ物を消化・吸収し、不要なものを便として排泄するまでの一連の流れを、自律神経によって精巧にコントロールしています。
しかし、感染やストレス、刺激物の摂取などによってこの働きに異常が生じると、様々な不調が現れます。
各症状と消化管の働きの関連
| 症状 | 関連する消化管の働き | 目的・原因 |
|---|---|---|
| 吐き気・嘔吐 | 胃の蠕動運動の逆流 | 有害物質を体外へ排出しようとする防御反応 |
| みぞおちの痛み | 胃や腸の痙攣、粘膜の炎症 | 臓器の異常を知らせる警告サイン |
| 下痢 | 腸の蠕動運動の亢進、水分吸収の低下 | 有害物質を速やかに体外へ排出しようとする防御反応 |
放置するリスクと早期対応の重要性
多くの場合症状は数日で自然に改善しますが、中には胃潰瘍や急性膵炎といった、放置すると重篤化する可能性のある病気が隠れていることもあります。
また、激しい下痢や嘔吐は脱水症状を起こし、特に高齢の方やお子様では危険な状態に陥ることもあります。
症状が強かったり長引く場合は自己判断で様子を見るのではなく、医療機関を受診して原因を特定し、適切な治療を受けることが大切です。
ウイルスや細菌の感染による急性胃腸炎
みぞおちの痛み、吐き気、下痢の最も一般的な原因は、ウイルスや細菌に感染して起こる急性胃腸炎です。いわゆるお腹の風邪とも呼ばれ、誰でもかかる可能性があります。

感染性胃腸炎の基本的な知識
感染性胃腸炎は、病原体が付着した手で口に触れたり、汚染された飲食物を摂取したりすることで発症し、原因となる病原体によって、潜伏期間や症状の強さなどが異なります。
ウイルス性は冬場に、細菌性は夏場に流行する傾向がありますが、年間を通じて発生します。多くは自然に治癒するものの、症状が激しい場合は脱水症状を防ぐための点滴治療などが必要です。
ウイルス性胃腸炎(ノロウイルスなど)
ウイルスによる胃腸炎は、突然の激しい吐き気や嘔吐で発症することが多いです。その後、水のような下痢や腹痛、発熱を伴います。
代表的な原因ウイルスはノロウイルスやロタウイルスで、特にノロウイルスは感染力が非常に強く、家庭内や施設内で集団発生することもあります。
アルコール消毒が効きにくいという性質を持つため、石鹸による丁寧な手洗いや、次亜塩素酸ナトリウムによる環境消毒が予防に重要です。
細菌性胃腸炎(カンピロバクターなど)
細菌による胃腸炎は汚染された食品の摂取が主な原因で、カンピロバクター(鶏肉など)、サルモネラ(卵など)、腸管出血性大腸菌(O-157など)が代表的です。ウイルス性と比べて腹痛や下痢の症状が強く、血便を伴うこともあります。
原因菌によっては、重篤な合併症を引き起こすこともあるため、加熱が不十分な肉料理などを食べた後に発症した場合は注意が必要です。
ウイルス性と細菌性胃腸炎の主な違い
| 項目 | ウイルス性胃腸炎 | 細菌性胃腸炎 |
|---|---|---|
| 主な原因 | ノロウイルス、ロタウイルスなど | カンピロバクター、サルモネラなど |
| 主な症状 | 突発的な嘔吐、水様性の下痢 | 激しい腹痛、血便を伴う下痢 |
| 流行時期 | 冬期に多い | 夏期に多い |
感染経路と予防策
感染性胃腸炎の予防の基本は、手洗いの徹底です。食事の前やトイレの後、調理の前には、石鹸と流水で指の間や手首まで丁寧に洗いましょう。また、食品は中心部まで十分に加熱し、調理器具は清潔に保つことが大切です。
特に、家族に感染者が出た場合は、吐物や便の処理に注意が必要で、使い捨ての手袋やマスクを着用し、次亜塩素酸ナトリウムを用いて汚染された場所を消毒するなど、二次感染を防ぐための対策を徹底してください。
ストレスや生活習慣の乱れが引き起こす胃腸の不調
明らかな感染や炎症がないにもかかわらず、みぞおちの痛みや胃腸の不調が続く場合、ストレスや生活習慣が原因となっている可能性があり、機能性消化管疾患と呼ばれます。
機能性ディスペプシアと症状の関連
機能性ディスペプシアは、胃カメラなどの検査をしても潰瘍やがんといった器質的な異常が見つからないのに、みぞおちの痛みや胃もたれ、早期飽満感(すぐに満腹になる感じ)といった症状が慢性的に続く病気です。
胃の運動機能の異常や、知覚過敏(わずかな刺激で痛みを感じやすい状態)、ストレスなどが複雑に関与していると考えられています。みぞおちの痛みが主な症状ですが、吐き気や腹部の張りなどを伴うこともあります。

過敏性腸症候群(IBS)の可能性
過敏性腸症候群は、主に大腸の運動機能や知覚機能の異常によって、腹痛や腹部の不快感、そして下痢や便秘などの便通異常が繰り返し起こる病気です。
ストレスを感じると症状が悪化しやすいのが特徴で、下痢型、便秘型、混合型などのタイプに分かれます。腹痛は下腹部に多いですが、みぞおちの辺りに痛みを感じることもあり、吐き気を伴うケースも見られます。
機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群の比較
| 項目 | 機能性ディスペプシア | 過敏性腸症候群(IBS) |
|---|---|---|
| 主な症状の場所 | 上腹部(みぞおち周辺) | 下腹部が多いが上腹部にも起こりうる |
| 中心となる症状 | 痛み、胃もたれ、早期飽満感 | 腹痛と便通異常(下痢・便秘) |
| 関連する要因 | 胃の運動異常、知覚過敏、ストレス | 腸の運動異常、知覚過敏、ストレス |
自律神経の乱れと消化機能への影響
胃や腸の働きは、交感神経と副交感神経からなる自律神経によってコントロールされていて、強いストレスや不規則な生活が続くと、自律神経のバランスが乱れ、消化管の運動に異常が生じます。
胃酸が過剰に分泌されたり、胃の動きが悪くなって吐き気を催したり、腸が過剰に動いて下痢になったりと、様々な症状の原因になります。
生活習慣の見直しポイント
機能性の不調を改善するためには、薬物療法と合わせて、生活習慣の見直しが非常に重要です。
- 十分な睡眠と休養をとる
- バランスの取れた食事を3食規則正しく摂る
- 適度な運動を習慣にする
- 趣味やリラックスできる時間を持つ
- アルコールやカフェイン、香辛料などの刺激物を避ける
生活のリズムを整え、心身のストレスを軽減することが、症状の改善への第一歩となります。
食事が原因で起こる食中毒
特定の食べ物を食べた後に急にみぞおちの痛みや吐き気、下痢が始まった場合、食中毒の可能性を考えます。原因となる病原体や物質は多様です。
食中毒の主な原因菌と潜伏期間
食中毒は、細菌やウイルスが付着した食品を摂取することで起こります。原因菌によって、症状が現れるまでの潜伏期間や、主な症状が異なります。
黄色ブドウ球菌は食後数時間で激しい嘔吐を起こし、カンピロバクターは数日経ってから腹痛や下痢が現れるなど、様々です。原因として疑われる食事の内容や、一緒に食事をした人の症状の有無などが、診断の重要な手がかりとなります。
主な食中毒の原因と特徴
| 原因 | 主な原因食品 | 潜伏期間 |
|---|---|---|
| カンピロバクター | 加熱不十分な鶏肉 | 2~7日 |
| サルモネラ | 鶏卵、食肉 | 6~72時間 |
| 黄色ブドウ球菌 | おにぎり、弁当など | 1~6時間 |
アニサキス症による激しい腹痛
サバやアジ、イカなどの魚介類を生で食べた後、数時間以内に激しいみぞおちの痛みと吐き気が現れた場合、アニサキス症の可能性があります。
アニサキスは魚介類に寄生する線虫で、生きたまま体内に入ると胃や腸の壁に突き刺さり、アレルギー反応を伴う激しい痛みが起きます。下痢を伴うことは少ないですが、症状の現れ方として鑑別に挙げることが必要です。
胃カメラで虫体を確認し、摘出することで症状は劇的に改善します。
暴飲暴食や刺激物の過剰摂取
病原体による食中毒だけでなく、食べ過ぎや飲み過ぎ、あるいは唐辛子などの香辛料やアルコール、カフェインといった刺激物を大量に摂取したことが原因で、胃の粘膜が荒れて急性胃炎を起こし、みぞおちの痛みや吐き気、下痢を起こすこともあります。
特に、脂肪分の多い食事は消化に時間がかかり、胃腸に大きな負担をかけるため、症状の引き金になりやすいです。
胃・十二指腸の病気が原因の場合
みぞおちの痛みは、胃や十二指腸そのものに潰瘍や炎症などの病変が生じているサインである可能性もあります。感染性胃腸炎と比べて、痛みが持続したり、食事との関連が見られたりするのが特徴です。
急性胃炎・急性十二指腸炎
暴飲暴食、ストレス、薬剤(特に痛み止め)の影響など、様々な原因で胃や十二指腸の粘膜に急性の炎症が起こる病気です。
みぞおちの痛みや不快感、吐き気、腹部膨満感などが主な症状で、粘膜からの出血を伴うと、黒い便(タール便)が出たり、吐血したりし、下痢を伴うことも少なくありません。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃酸によって胃や十二指腸の粘膜が深く傷つき、えぐれてしまう病態で、主な原因は、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染と、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれる痛み止めです。
みぞおちの痛みが特徴的で、食事との関連が見られることがあり、胃潰瘍では食後に、十二指腸潰瘍では空腹時に痛みが強くなる傾向があります。
潰瘍から出血すると黒い便や吐血、穿孔(穴が開くこと)を起こすと突然の激痛に見舞われるなど、緊急の対応が必要な状態になることもあります。
胃潰瘍と十二指腸潰瘍の痛みの特徴
| 項目 | 胃潰瘍 | 十二指腸潰瘍 |
|---|---|---|
| 痛みのタイミング | 食後 | 空腹時、夜間 |
| 食事との関連 | 食事をすると悪化することがある | 食事をすると一時的に和らぐことがある |
逆流性食道炎との関連
胃酸が食道へ逆流することで、食道の粘膜に炎症が起きる病気です。主な症状は胸やけや、酸っぱいものがこみ上げてくる呑酸ですが、人によってはみぞおちの痛みとして感じることもあります。
胃酸の逆流は胃の運動機能の低下を伴うことが多く、吐き気や胃もたれの原因にもなり、直接下痢を起こすわけではありませんが、胃腸全体の不調の一部として現れる可能性があります。
膵臓や胆のうなど周辺臓器の病気の可能性
みぞおちの痛みは、胃や十二指腸だけでなく、近くにある膵臓や胆のうといった臓器の病気によっても起こることがあり、重篤化しやすいため注意が必要です。
急性膵炎の症状と特徴
急性膵炎は、膵臓自体が分泌する消化酵素によって、膵臓自身が消化されてしまうことで起こる急性の炎症で、主な原因はアルコールの飲み過ぎと胆石です。
症状は、突然発症する持続的なみぞおちから背中にかけての激しい痛みで、吐き気や嘔吐、発熱を伴います。
前かがみになると痛みが少し和らぐという体位による変化が見られることもあり、重症化すると命に関わる危険な病気であり、緊急の入院治療が必要です。
胆石症・胆のう炎の可能性
胆のうは、肝臓で作られた胆汁を一時的に蓄えておく袋状の臓器です。
胆のうの中に石(胆石)ができるのが胆石症で、多くは無症状ですが、食後、特に脂肪分の多い食事を摂った後などに、胆石が胆のうの出口に詰まると、みぞおちから右上腹部にかけての激しい痛み(胆石発作)を起こします。
さらに、胆石が原因で胆のうに細菌感染が起こると急性胆のう炎となり、持続的な痛みと発熱、吐き気などを伴います。
急性膵炎と胆石発作の痛みの比較
| 項目 | 急性膵炎 | 胆石発作 |
|---|---|---|
| 痛みの場所 | みぞおち~背中 | みぞおち~右上腹部 |
| 痛みの性質 | 持続的で激しい | 周期的、波がある激しい痛み |
| 関連要因 | アルコール、胆石 | 脂肪分の多い食事 |
心臓の病気との見分け方
非常に稀ですが、心筋梗塞など心臓の病気による痛みを、みぞおちの痛みとして感じることがあります。高齢の方や糖尿病をお持ちの方では、典型的な胸の痛みではなく、胃の痛みとして現れることがあります。
冷や汗を伴う、締め付けられるような痛みである、少し動くだけで痛みが強くなるといった場合は、心臓の病気も念頭に置き、速やかに医療機関を受診することが重要です。
自宅でできる対処法と医療機関を受診すべき症状
急な症状に見舞われた時、まずは自宅でどのように対処すれば良いのか、どのような状態であれば医療機関を受診すべきなのか、判断基準を知っておくことは非常に大切です。
安静と水分補給の重要性
症状がある時はまず胃腸を休ませることが第一で、無理に動かず、楽な姿勢で安静にしましょう。下痢や嘔吐が続くと、体から水分と電解質が失われ、脱水症状に陥ります。
脱水は倦怠感や頭痛を悪化させ、重症化すると意識障害などを起こすこともあります。水分補給は非常に重要ですが、一度に大量に飲むと吐き気を誘発することがあるため、経口補水液などを少量ずつ、こまめに摂取することを心がけてください。
食事の摂り方と消化に良い食べ物
痛みが強い間や吐き気があるうちは、無理に食事を摂る必要はありません。症状が少し落ち着いてきたら、おかゆやうどん、すりおろしたリンゴなど、消化が良く、胃腸に負担をかけないものから少量ずつ試しに食べてみましょう。
脂肪分の多いもの、香辛料などの刺激物、食物繊維の多いもの、冷たいもの、熱すぎるものは、胃腸を刺激して症状を悪化させる可能性があるため、避けてください。
症状がある時の食事のポイント
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 消化に良い食べ物 | おかゆ、うどん、パン、豆腐、白身魚、鶏のささみ、バナナ、リンゴ |
| 避けるべき食べ物 | 揚げ物、ラーメン、香辛料、ごぼう、きのこ類、炭酸飲料、アルコール |
市販薬を使用する際の注意点
自己判断での市販薬の使用には注意が必要で、下痢止めの使用は慎重に行うべきです。
感染性胃腸炎の場合、下痢は病原体を体外に排出しようとする体の防御反応で、安易に下痢止めで動きを止めてしまうと、かえって病原体が腸内にとどまり、回復を遅らせたり、症状を悪化させたりする可能性があります。
痛み止めも、胃の粘膜を荒らす種類のものがあり、胃潰瘍などを悪化させる危険性があります。市販薬を使用する場合は、必ず薬剤師に相談し、用法・用量を守ってください。
すぐに医療機関を受診すべき危険なサイン
以下のような症状が見られる場合は、重篤な病気が隠れている可能性や、脱水が進行しているサインです。様子を見ずに、速やかに医療機関を受診してください。
- 我慢できないほどの激しい痛み、痛みがどんどん強くなる
- 冷や汗を伴う、胸にも痛みがある
- 黒い便(タール便)や血便が出る、吐血した
- 水分が全く摂れず、ぐったりしている、意識がもうろうとしている
- 高熱が続く
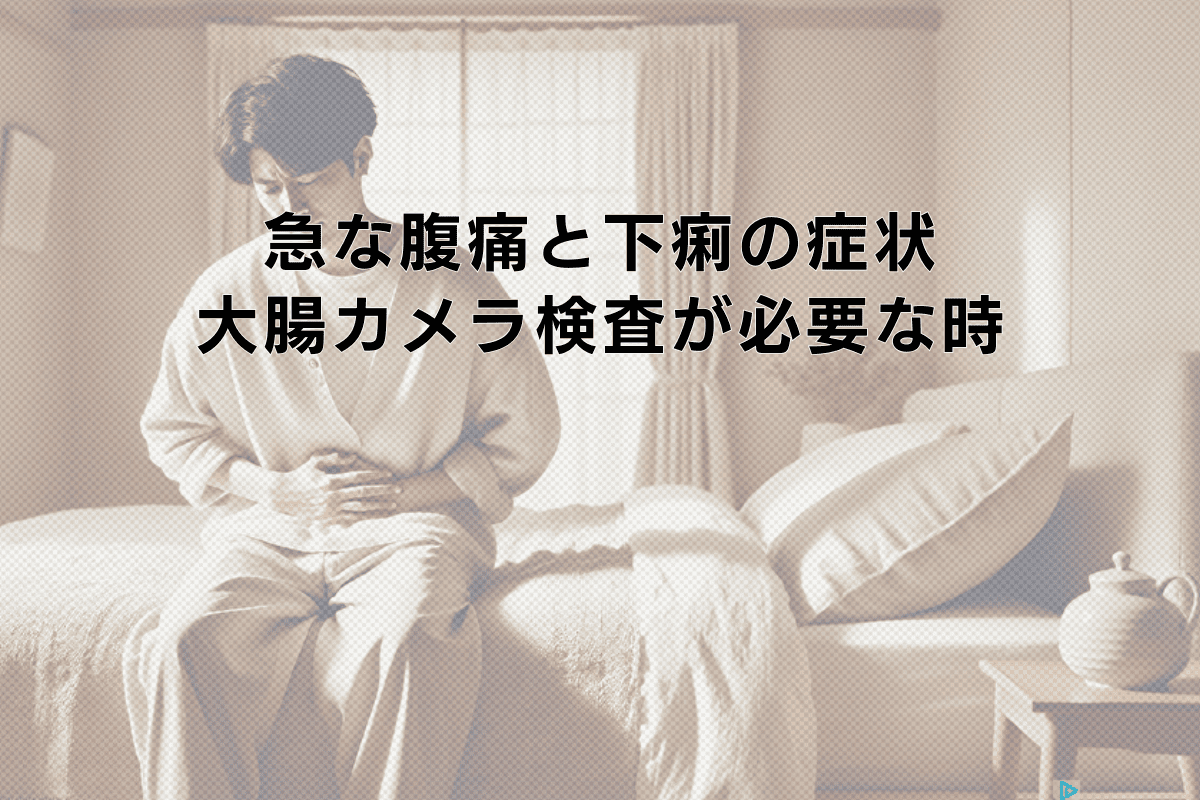
みぞおちの痛みと下痢に関するよくある質問
最後に、みぞおちの痛みと下痢の症状に関して、寄せられる質問と回答をまとめました。
- 症状がある場合、何科を受診すれば良いですか?
-
みぞおちの痛み、吐き気、下痢は、主に消化器系の症状ですので、まずは消化器内科や胃腸科の受診をお勧めします。かかりつけの内科がある場合は、そちらに相談するのも良いでしょう。
もし、我慢できないほどの激しい痛みや血便、意識がはっきりしないなどの危険なサインがある場合は、ためらわずに救急外来を受診してください。
- 子供が同じ症状を訴えている場合はどうすれば良いですか?
-
お子様、特に乳幼児は、大人に比べて脱水症状が急速に進行しやすく、重症化するリスクが高いです。
水分が摂れずにぐったりしている、おしっこの回数や量が極端に少ない、泣いても涙が出ないといった症状は、脱水が進んでいるサインなので、様子を見ずに、早めに小児科を受診してください。
家庭でのケアは大人と同様に、経口補水液などを少量ずつこまめに与えることが大切です。
- 症状はどのくらいで治まりますか?
-
ウイルス性の急性胃腸炎など、比較的軽いものであれば、通常は2~3日から1週間程度で自然に回復します。
しかし、症状が1週間以上続く場合や、一度良くなった後に再び悪化する場合は、他の病気が隠れている可能性も考えられます。症状の経過が長引くようであれば、医療機関で原因を調べてもらうことが重要です。
- 症状がある時に仕事や学校は休むべきですか?
-
まず、ご自身の体を休ませて回復に専念することが第一です。また、原因がノロウイルスなどの感染性胃腸炎であった場合、出勤や登校をすることで、職場や学校で感染を広げてしまう可能性があります。
特に、食品を扱う仕事や、医療・介護関係の仕事に従事している方は、症状が完全に治まり、医師の許可が出るまで仕事を休む必要があります。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【おなかのガスと下痢が続く症状 – 原因と検査の必要性】
みぞおちの痛み・吐き気・下痢の基本を押さえたら、次は実際の腸内環境の詳しい状態について知っておくと安心です。ガス症状でお悩みの方に特に参考になる内容です。
【繰り返す下痢と体重減少の症状|内視鏡検査による原因究明】
みぞおちの症状について理解が深まると、関連する体重減少などの別の症状についても知りたくなる方が多いようです。意外な繋がりが見えてくる内容です。
参考文献
Matsuura H, Yamamoto K, Kageyama H, Komura A, Kishida M. Neutropenic patient with acute severe epigastric pain. Internal and Emergency Medicine. 2025 Jul 4:1-2.
Ito T, Satoh K, Sakaki K, Sakusabe M. Acute Esophageal Necrosis as an Unusual Cause of Epigastric Pain in the Emergency Department. Case Reports in Acute Medicine. 2022 Dec 27;5(2-3):6-11.
Yamawaki H, Futagami S, Kawagoe T, Maruki Y, Hashimoto S, Nagoya H, Sato H, Kodaka Y, Gudis K, Akamizu T, Sakamoto C. Improvement of meal‐related symptoms and epigastric pain in patients with functional dyspepsia treated with acotiamide was associated with acylated ghrelin levels in Japan. Neurogastroenterology & Motility. 2016 Jul;28(7):1037-47.
Shinozaki S, Osawa H, Sakamoto H, Hayashi Y, Lefor AK, Yamamoto H. The effect of acotiamide on epigastric pain syndrome and postprandial distress syndrome in patients with functional dyspepsia. The Journal of Medical Investigation. 2016;63(3.4):230-5.
Matsuura H, Fujita R. Unusual cause of acute severe epigastric pain in a Japanese woman. European Journal of Internal Medicine. 2023 Sep 1;115:132-3.
Suzuki H, Kusunoki H, Kamiya T, Futagami S, Yamaguchi Y, Nishizawa T, Iwasaki E, Matsuzaki J, Takahashi S, Sakamoto C, Haruma K. Effect of lansoprazole on the epigastric symptoms of functional dyspepsia (ELF study): a multicentre, prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. United European Gastroenterology Journal. 2013 Dec;1(6):445-52.
Manabe N, Haruma K, Kamada T, Kusunoki H, Inoue K, Murao T, Imamura H, Matsumoto H, Tarumi KI, Shiotani A, Hata J. Changes of upper gastrointestinal symptoms and endoscopic findings in Japan over 25 years. Internal Medicine. 2011;50(13):1357-63.
Fujikawa Y, Tominaga K, Tanaka F, Kamata N, Yamagami H, Tanigawa T, Watanabe T, Fujiwara Y, Arakawa T. Postprandial symptoms felt at the lower part of the epigastrium and a possible association of pancreatic exocrine dysfunction with the pathogenesis of functional dyspepsia. Internal Medicine. 2017 Jul 1;56(13):1629-35.
Okagawa Y, Sumiyoshi T, Imagawa T, Sakano H, Tamura F, Arihara Y, Kanari Y, Sakurada A, Oiwa S, Jin T, Tomita Y. Clinical factors associated with acute abdominal symptoms induced by gastric anisakiasis: a multicenter retrospective cohort study. BMC gastroenterology. 2023 Jul 18;23(1):243.
Miwa H, Nagahara A, Asakawa A, Arai M, Oshima T, Kasugai K, Kamada K, Suzuki H, Tanaka F, Tominaga K, Futagami S. Evidence-based clinical practice guidelines for functional dyspepsia 2021. Journal of gastroenterology. 2022 Feb;57(2):47-61.