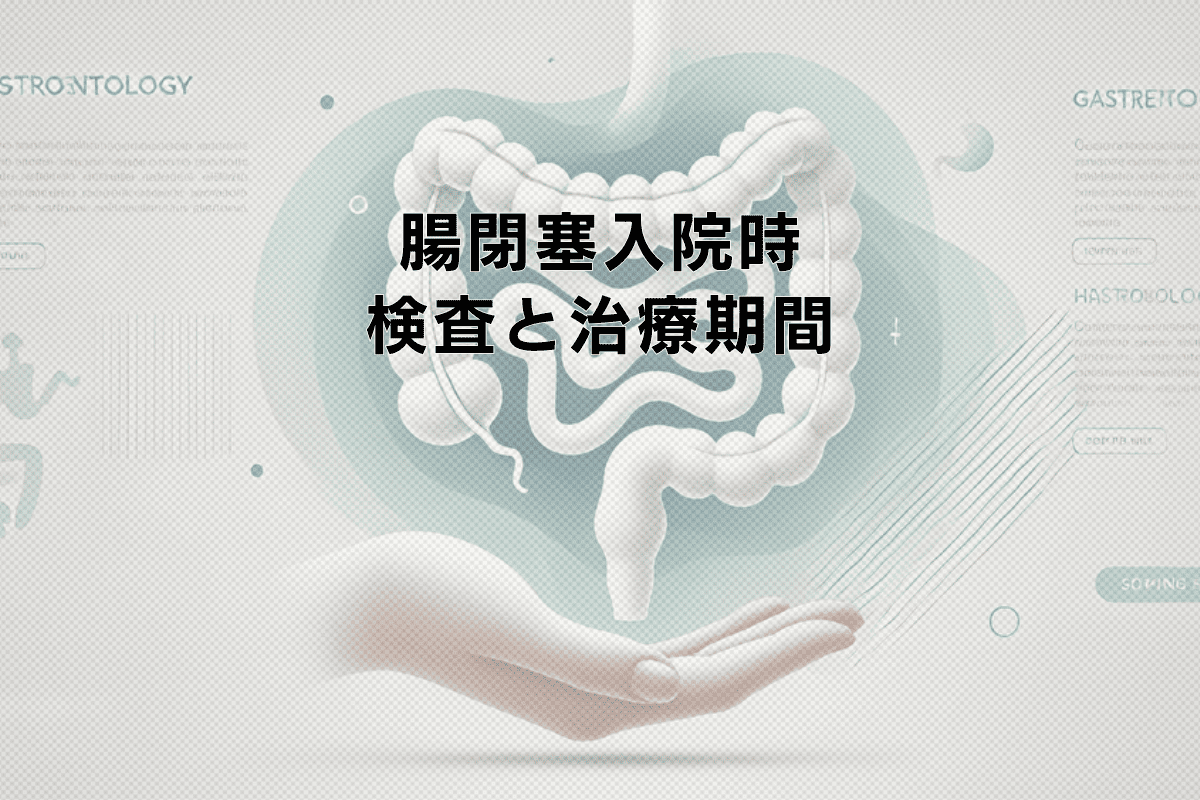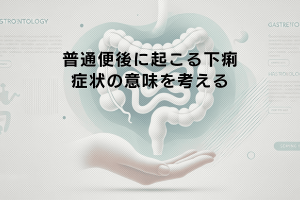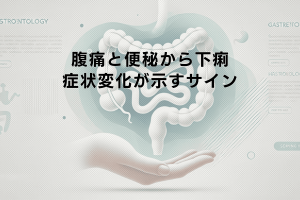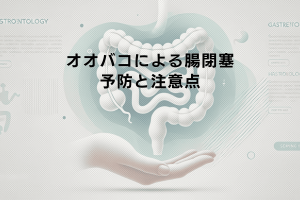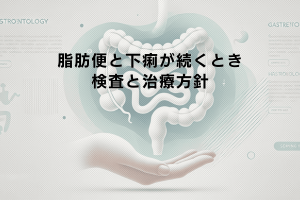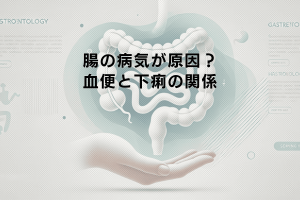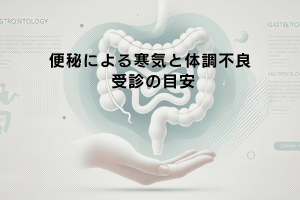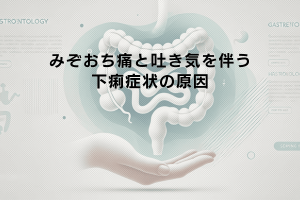腸閉塞は、腸管の通過障害によって便やガスがうまく排出されなくなる状態で、強い腹痛や嘔吐などを起こし、重症度が高い場合には入院による治療が必要です。
しかし、腸閉塞で入院した場合、どのような検査や治療を行い、どれくらいの期間がかかるのか、明確なイメージを持っている方は少ないでしょう。
腸閉塞の概念から入院中に行われる検査や手術の概要、さらに退院後の過ごし方などを解説します。
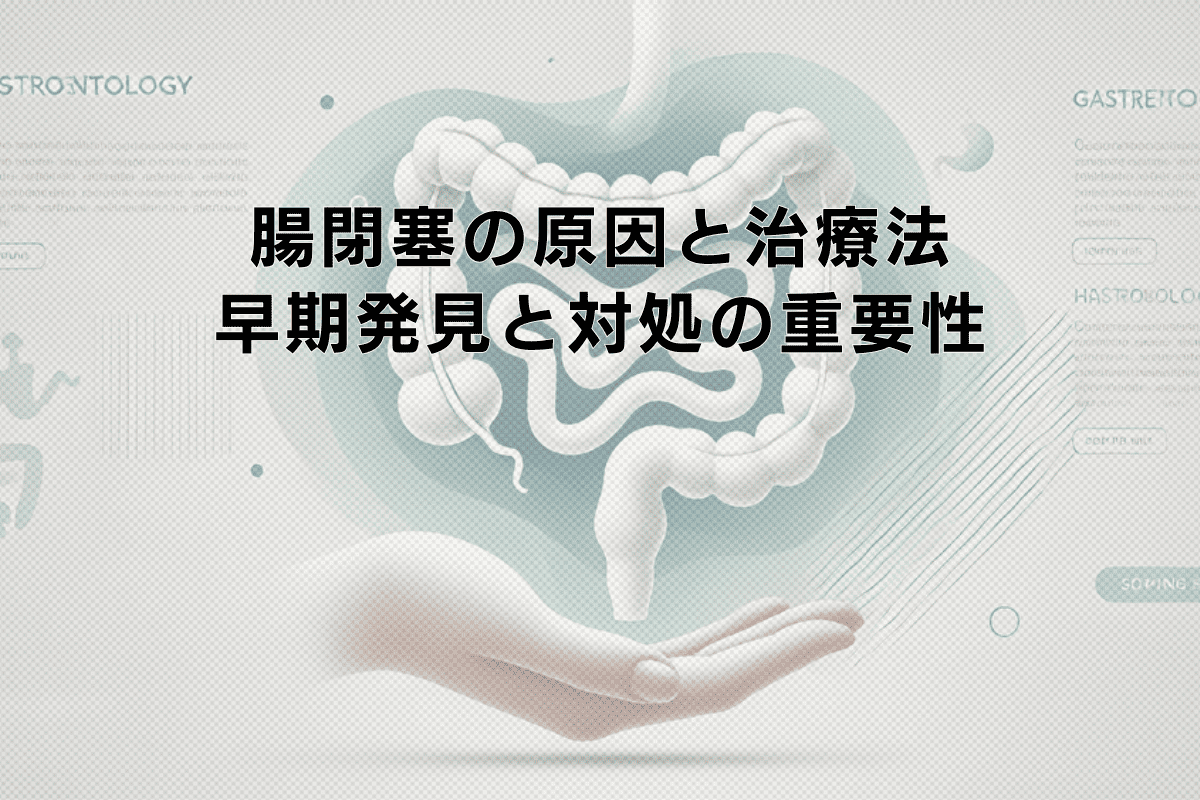
腸閉塞の基礎知識
腸の通過が滞り、体内のバランスが乱れると深刻な症状が現れ、入院を要するケースに至ることがあります。全体像を知ると、検査や治療の流れをイメージしやすいです。
腸閉塞とは
腸閉塞とは、小腸や大腸などの消化管が何らかの要因で狭窄や閉塞を起こし、腸内容物が先へ進めなくなる状態です。
腹部の張りや痛み、嘔吐などが代表的な症状で、正しい対応をしないと体内の水分バランスや電解質バランスが崩れ、生命にかかわることもあります。
腸閉塞の原因には機械的閉塞と機能的イレウスがあり、機械的閉塞は腸管そのものに物理的な狭窄や閉塞が生じるタイプで、腸管に生じた癒着や腫瘍、腸重積などが原因です。
機能的イレウスは腸管の運動が低下するタイプで、神経や筋肉の異常などによって生じます。
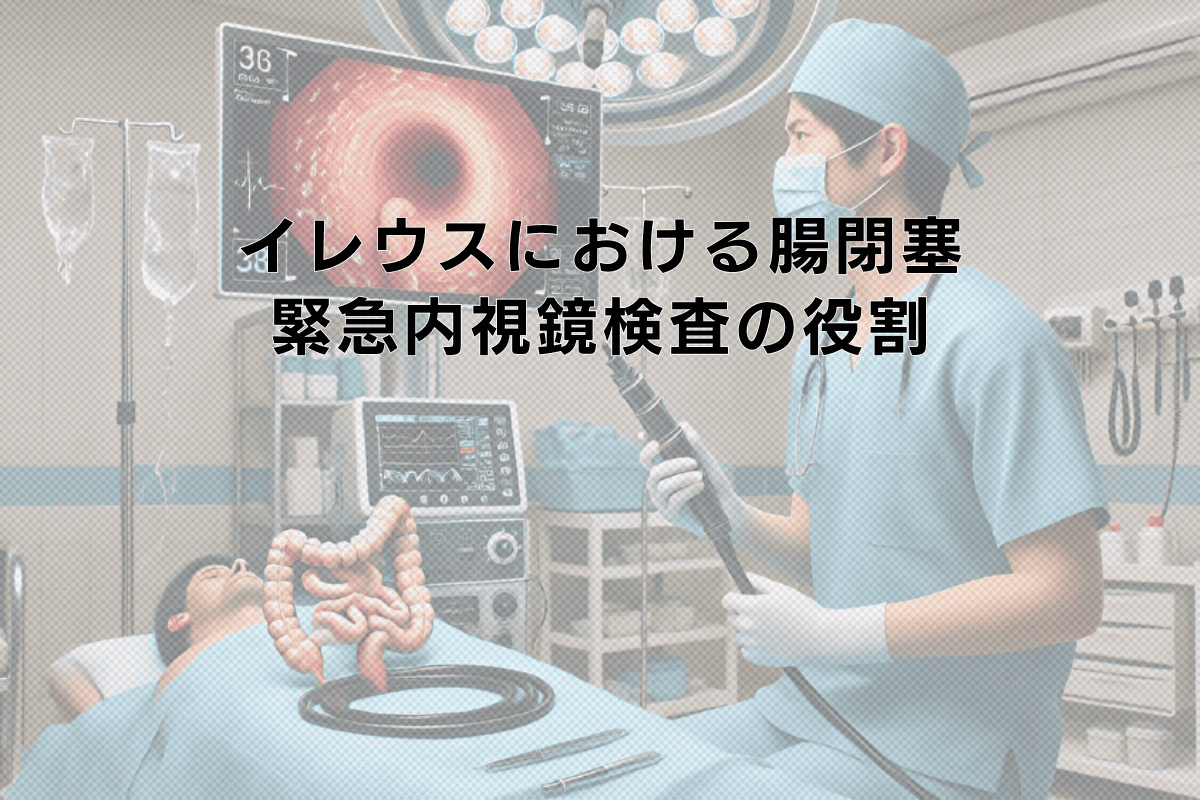
腸閉塞が疑われる症状
- 激しい腹痛と腹部膨満
- 吐き気や嘔吐(内容物により胃液や腸液が混ざる)
- 便やガスがほとんど出ない状態
- 食欲不振や全身の倦怠感
これらの症状が長引く場合、早めに医療機関で診断を受けることが大切です。
腸閉塞を疑う指標
| 症状 | 特徴 | 医療受診の目安 |
|---|---|---|
| 腹痛 | 差し込むような痛みが繰り返される | 痛みが数時間以上続く場合 |
| 嘔吐 | 食後すぐに嘔吐する・胆汁や血液が混ざる | 連続して嘔吐が続く場合 |
| 便秘または便排泄量の著しい減少 | ガスも出ない | 数日以上排便がない |
| 腹部膨満 | 触れると硬い感触がある | 常時張ったような感覚がある |
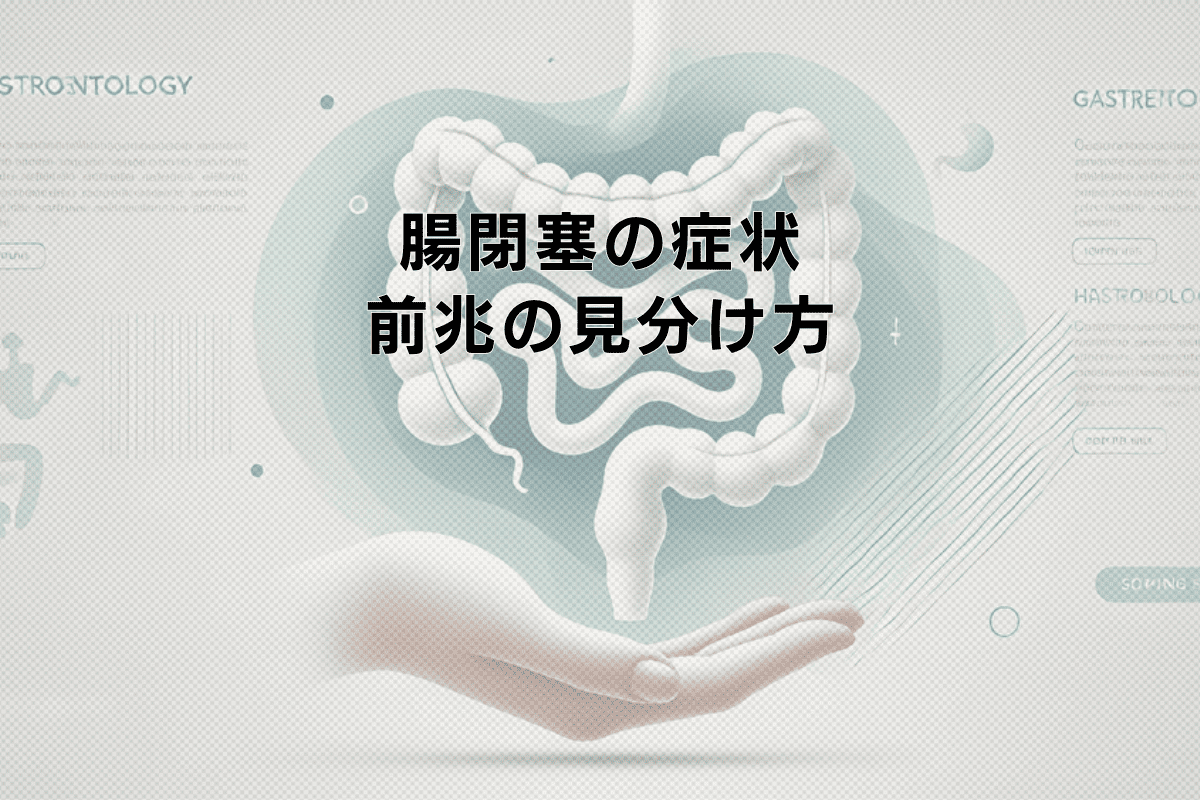
腸閉塞の主な原因
腸閉塞の原因は多岐にわたります。過去に腹部手術を受けた人は、腸管同士や腹壁との癒着が起こっている可能性があり、それが原因で閉塞が起こる場合があります。
また、大腸がんや腸ポリープなど腸内の腫瘍が詰まることで生じることもあるため、腸の病変を疑うときは内視鏡検査を視野に入れた診断が必要です。
腸重積や大腸憩室炎などの特有の病態、さらには高齢者で腸の蠕動運動が低下しているケースでは機能的な腸閉塞が発症しやすくなります。原因を正しく把握するには画像検査や血液検査などを組み合わせることが重要です。

早期診断の意義
腸閉塞は放置すると体内に溜まった腸液やガスが腸管を圧迫し、やがて血流障害を引き起こすリスクがあります。血流が途絶えると腸管が壊死に至り、短期間で重篤化する恐れがあるため、早期診断が生死を分ける場合もあります。
早めに対処すれば保存的治療で回復できることも多く、入院が長期化せずに済む可能性が高いです。
入院が必要になる場合の症状や合併症
入院の必要性は、腸閉塞の重症度や合併症の有無などによって変わり、軽症の場合は外来での治療や経過観察で済むこともありますが、重度の症状があれば入院加療が求められることが少なくありません。
入院の判断基準
腸閉塞の疑いがある患者さんでは、腹痛の程度、嘔吐の有無、血液検査の結果、画像検査の所見などを総合して入院の必要性が判断されます。
中高年以降の方や、糖尿病・心臓病などの基礎疾患を持つ場合は、重症化リスクが高まり、早めの入院検討が必要です。
ポイント
- 既往歴:過去の腹部手術やがんの有無
- 症状の強度:激しい腹痛や嘔吐量
- 血液検査:白血球数やCRPなどの炎症反応
- 画像所見:腸管の拡張度や閉塞の位置
医師はこれらを見極めながら、入院治療で迅速な対応を行う必要があると判断します。
腸閉塞によるリスク
腸閉塞が進行すると、腸管にたまった内容物によって腸管内部の圧力が上昇し、血行障害を起こし、さらに腸管の粘膜がダメージを受け、細菌や毒素が血中に入り込み、敗血症など重大な合併症を誘発する可能性があります。
また嘔吐を繰り返したり、腸内容物が貯留し腸液の吸収が停滞したりすることで、脱水症状や電解質異常が生じ、全身の臓器に影響が及びます。
手術治療の必要性
保存的治療(絶食や点滴など)で改善が見込めない、あるいは腸管に物理的な閉塞要因が顕著な場合は手術を検討することがあります。癒着がひどく腸が完全に塞がっている場合や、大腸がんなどの腫瘍が閉塞の原因になっている場合などです。
また、血流障害がある場合は命に係わる危険が高く緊急手術となることも多いです。
手術によって狭窄部位を切除する、あるいは腸管を再度つなぎ直すなどの対応が取られます。
手術適応を考える指標
| 項目 | 手術の検討材料 | 事例 |
|---|---|---|
| 閉塞の部位と程度 | 小腸・大腸の完全閉塞 | 癒着や腸重積がひどい |
| 腫瘍の存在 | 大腸がんやポリープによる閉塞 | 組織検査で悪性が疑われる |
| 保存的治療の効果 | 絶食や点滴で改善なし | 症状がむしろ悪化 |
| 患者の全身状態 | 高熱、重度脱水、腸管虚血 | 緊急手術の可能性が高い |
内視鏡検査への移行の可能性
腸閉塞の中には、原因となる病変を内視鏡的に除去することで改善が見込めるケースもあります。
大腸ポリープが原因で腸閉塞が生じている場合は、大腸カメラを用いてポリープを切除し、腸管通過を回復させる方法を検討することがあります。手術でお腹を開くより侵襲が少なく、患者さんの負担を軽減できることが利点です。

腸閉塞の検査方法
腸閉塞を確定診断するためには、さまざまな検査を組み合わせて実施し、画像診断や血液検査を通じて閉塞の原因や部位、重症度を評価し、適切な治療方針を立てます。
X線検査とCT検査の役割
腸閉塞を疑う際、初期診断で重要な検査がX線(腹部単純撮影)で、腹部X線撮影では、腸管内にガスがどの程度貯留しているかが分かり、閉塞部位の特定や重症度を推察できるケースがあります。
さらに詳細な情報を得るためにCT検査が用いられ、腸管の形状やほかの臓器との関係、腫瘍の有無などが立体的に把握することが可能です。
画像検査の特徴
| 検査 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 腹部X線 | 簡便で時間がかからない | 腸管ガスの有無や規模を迅速に確認 |
| CT検査 | より詳しい3D情報を得られる | 腫瘍や炎症の部位を正確に把握しやすい |

胃カメラや大腸カメラの必要性
腸閉塞の原因として腫瘍やポリープなどの腸内病変が疑われる場合、胃カメラや大腸カメラで直接粘膜を観察することが重要です。
大腸カメラは特に大腸がんや大きなポリープを発見しやすく、その場で切除できる場合もあり、胃カメラは小腸や十二指腸付近の病変が原因の閉塞を疑うときに利用されることがあります。
検査の流れと注意点
- 診察と問診で症状や既往歴を確認する
- 血液検査で炎症反応や電解質バランスを把握する
- X線やCTで閉塞の位置や重症度を評価する
- 必要に応じて内視鏡検査で腫瘍やポリープの有無を確認する
- 治療方針を総合的に決定する
画像検査では造影剤を使う場合があり、アレルギーや腎機能の状態を事前にチェックしておくことが望ましいです。
検査前に知っておきたい項目
| 項目 | 具体的内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| アレルギー | 造影剤や薬剤に対する過敏症 | 問診で詳細を伝える |
| 腎機能 | 造影剤の排泄能力があるか | 血清クレアチニン値などを確認 |
| 絶食指示 | 内視鏡検査時や点滴が必要な場合 | 医師の指示に従う |
| 既往歴 | 心臓病・糖尿病など | 検査でのリスクを考慮 |
画像所見からわかること
画像検査では腸管の拡張程度や閉塞ポイント、周囲の臓器への影響度合いなどがわかり、CT検査では、癒着や腫瘍による腸管の閉塞がどこに集中しているのか、血流障害があるのかを詳細に把握でき、外科的処置が必要かどうかの判断を助けます。
複数の病変がある場合にも、画像所見をもとに優先度の高い治療を見極められます。
入院の期間と治療の進め方
腸閉塞で入院が決定した場合、どのくらいの期間になるのか気になる方も多いでしょう。治療期間は原因や症状の重症度、患者の全身状態によって大きく変わります。
入院期間の目安
保存的治療(絶食や点滴)で改善が期待できる軽症〜中等症の腸閉塞であれば、およそ1週間前後で退院が見込めることもありますが、手術が必要となった場合や合併症がある場合には、2週間から数週間に及びます。
腸閉塞で入院が長引く要因
| 要因 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 手術の有無 | 外科的処置が必要かどうか | 術後管理で延長する |
| 合併症 | 感染症・腸管損傷など | 症状の安定まで時間がかかる |
| 基礎疾患 | 糖尿病・心不全など | 回復が遅れる場合がある |
| 高齢 | 体力や免疫力の低下 | 社会的サポートも含め調整が必要 |
絶食や点滴治療
腸閉塞では、腸を休ませるために絶食を行い、点滴で必要な水分や栄養素を補給します。嘔吐や腹痛が落ち着き、腸管の通過が安定してきたタイミングで、医師の判断により少しずつ経口摂取が再開されます。
経口摂取を開始する際には消化に優しい食事(重湯やスープなど)から様子を見ながら進めることが多いです。
手術が必要なケース
癒着が強い、腫瘍が見つかった、大腸ポリープが原因で内視鏡だけでは対応しきれないなど、物理的な閉塞因子が明らかなケースでは手術が考慮されます。
手術の方法は開腹手術や腹腔鏡手術などがあり、患者さんの全身状態や閉塞部位、病変の性質によって選択します。
ポイント
- 開腹手術:広範囲の病変や複雑な癒着に対応しやすい
- 腹腔鏡手術:傷が小さく、術後回復が比較的早い場合がある
- 術後の合併症リスク:腸管損傷や感染症に注意
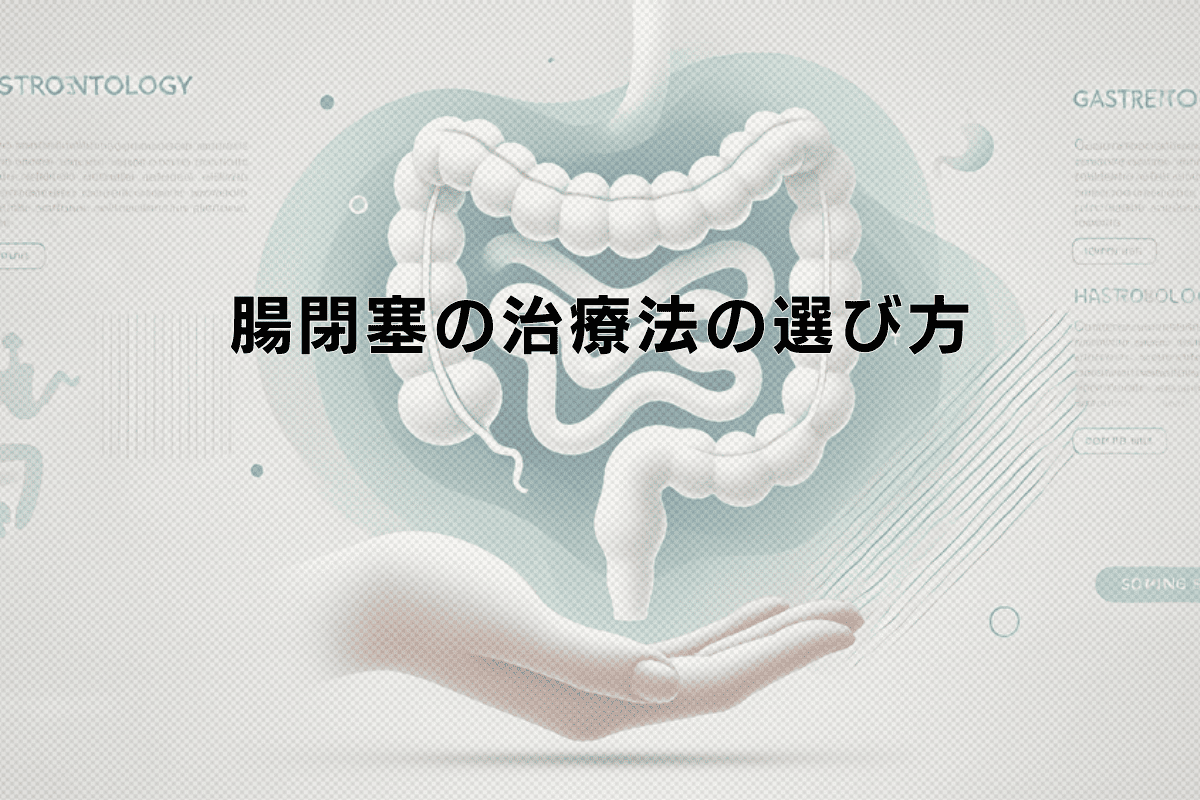
退院後のフォローアップ
入院期間を経て症状が改善し退院しても、腸の状態が完全に回復しているとは限らず、退院後も食生活や生活習慣に気をつけながら、必要に応じて通院や検査を継続します。
腸閉塞を再発すると、短期間に再入院を余儀なくされることもあるため、早めの受診や経過観察が重要です。
退院後の管理ポイント
| 項目 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 食事 | 消化に優しいメニューから徐々に | 無理な食べ過ぎを避ける |
| 水分摂取 | 適度な水分補給で便を軟らかく | 脱水が再発を招く恐れあり |
| 運動 | 軽めの散歩やストレッチ | 腹部への負担が大きい運動は控える |
| 通院 | 定期的な診察と検査 | 異変を感じたら早めに相談 |
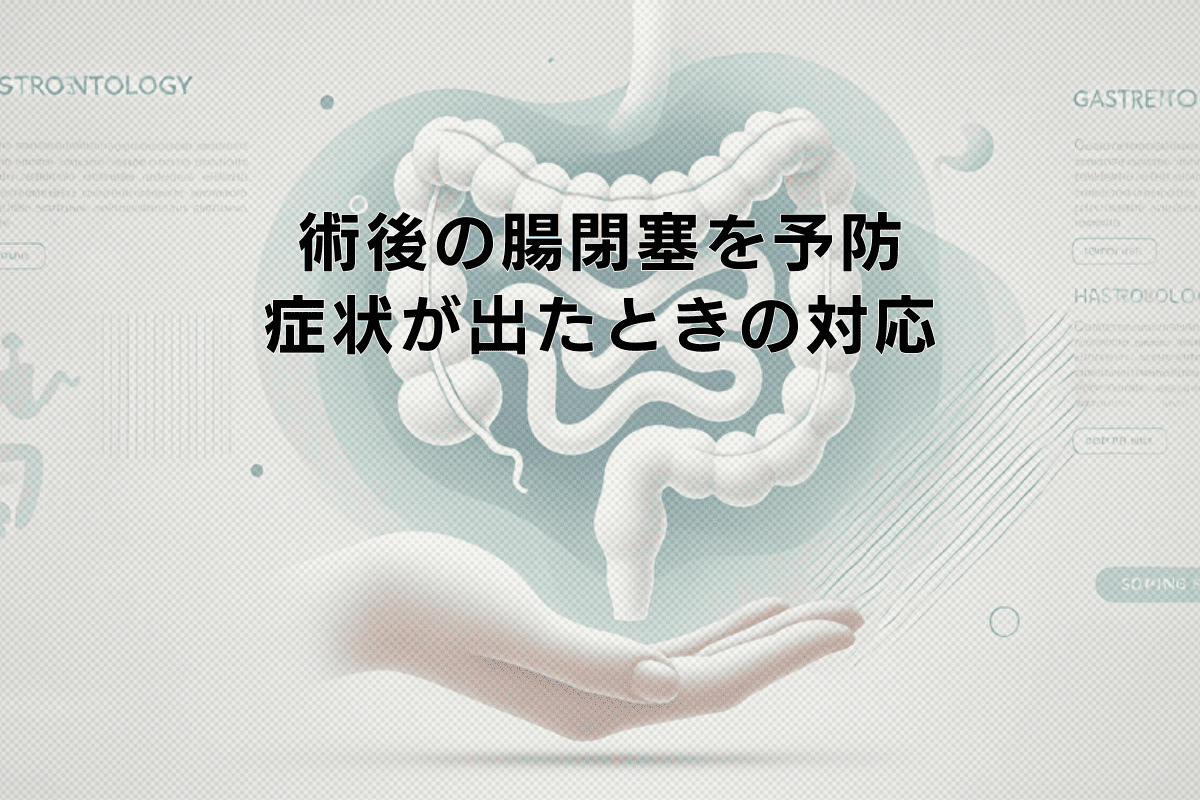
入院中の患者の生活と注意事項
腸閉塞で入院中は、食事制限やリハビリなど普段の生活とは異なる点が多数あり、身体を安静に保ちつつも、早期回復に向けた活動を意識することが大切です。
ベッド上での活動とリハビリ
腸閉塞の場合、腹痛や嘔吐が続く間はベッド上での安静を余儀なくされます。
ただし、症状が落ち着いてきたら、医療スタッフや理学療法士と相談しながら無理のない範囲で起き上がったり、軽い歩行練習を行ったりして、体力の低下を防ぐことが望ましいです。
長期にわたりベッド上の生活が続くと、筋力や血行が悪化して回復を妨げることがあります。
入院中の活動度に応じたケア
| 活動レベル | 主な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 完全安静 | ベッド上での姿勢変換のみ | 腸への負担を減らす |
| 軽度の活動 | 病室内で座る・立つ | 体力維持と循環促進 |
| 歩行練習 | 廊下を数分歩く | 血行改善とリハビリ効果 |
| 通常活動 | トイレや洗面への移動 | 早期社会復帰に向けた準備 |
食事制限や水分補給
腸閉塞の治療では、腸を休ませるために絶食となるケースが多く、点滴や経静脈栄養で必要量を補う一方、少しずつ食事を再開するときは医師や栄養士の指示のもと、消化に優しい形態(流動食、軟食など)から始めます。
また、脱水を防ぐためにも水分補給は重要ですが、一度に大量に摂取すると嘔吐や腹痛がぶり返す可能性があるため、少量をこまめに摂る工夫が大切です。
排泄管理と腸管の観察
腸閉塞の入院治療では、看護師や医師が便の状態や排ガスの有無を細かく観察し、排泄の状況は腸がどれほど回復しているかを判断する指標のひとつです。
また、場合によっては胃管(チューブ)を鼻から挿入し、胃液や腸液を体外へ排出して腸の負担を軽減する処置が取られることもあります。こうした処置は一時的に不快感を伴いますが、腸管内圧を下げ腸を休ませて回復を促すうえで有効です。
ポイント
- 排ガスの有無をこまめに報告
- 便の色や形状に注意を払う
- 下痢が続く場合、原因を検討(感染症や腸管の炎症など)
- 腹痛の有無や強度を看護師に伝える
腸閉塞手術の概要と術後管理
保存的治療で改善が見込めない場合や、腸の狭窄が重度で原因が明確な場合には外科的アプローチが選択されることがあります。
外科的治療の選択肢
腸閉塞手術では、詰まっている部位を切開して障害となっている組織を取り除き、腸を縫合・切除・再吻合する開腹手術が一般的な方法ですが、技術や設備によっては腹腔鏡下で手術を行うことも選択肢です。
腹腔鏡手術は体への侵襲が軽減される可能性があるものの、大きな癒着がある場合などは十分な視野が確保できずに開腹に切り替えることもあります。
外科的治療のメリットとデメリット
| 術式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 開腹手術 | 広い視野で確実な処置ができる | 術後の回復期間がやや長い |
| 腹腔鏡手術 | 傷口が小さく回復が早い傾向 | 高度な技術と機材が必要 |
術後の経過観察
手術後は、腸管の動きや創部の回復具合、感染症の徴候がないかなどを慎重に観察し、腸閉塞の手術後には再癒着や腸管運動の低下、吻合部の不具合などのリスクがあり、再度の通過障害に陥らないように管理することが大切です。
術後1〜2日ほどは絶食状態を継続し、腸の動きが戻ってから少しずつ食事を再開します。
退院に向けた準備
術後の症状が落ち着き、腸が正常に動き始めれば退院へ向けた準備に入ります。退院後も食事制限や生活習慣の改善が必要なケースが多いため、医師や看護師、管理栄養士からの指導を受けましょう。
自宅での過ごし方だけでなく、仕事復帰や日常生活への戻り方なども含めた総合的なアドバイスが行われます。
退院時に確認しておきたい項目
| 項目 | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 食事指導 | どの程度の固さ・量が適切か | 管理栄養士・医師 |
| 運動制限 | 散歩や軽い家事が可能か | リハビリスタッフ・医師 |
| 創部ケア | 傷口の消毒や入浴のタイミング | 看護師・医師 |
| 通院予定 | 術後検診や再診のタイミング | 外来予約システムなど |
再発防止のポイント
腸閉塞の原因によっては再発のリスクがあります。特に癒着が原因の場合は、別の部位で同様の問題が再度起こることもあり、術後管理を徹底することが重要です。
生活習慣の見直しだけでなく、定期的な画像検査や内視鏡検査で腸の状態をチェックし、問題が早めにみつかれば小さな処置で済む可能性もあります。
腸閉塞からの回復を促すための工夫
腸閉塞を一度経験すると、再発を恐れて日常生活に不安を覚える方が少なくありません。体の回復だけでなく、心の面でもサポート体制を整えることが大事です。
生活習慣の見直し
腸の健康を保つには、食事内容や食べ方、適度な運動、ストレス管理などが大切で、食事は、よく噛んでゆっくり食べる習慣をつけることが腸への負担を減らす秘訣です。
また、脂質や刺激物を控えめにし、食物繊維や水分をしっかりとりましょう。
ポイント
- 1口当たり20回以上噛む
- 食物繊維の多い野菜や果物をバランスよく摂取
- アルコールやスパイシーな食べ物は控えめに
- ストレスをためない工夫(趣味や適度な運動)
内視鏡検査で腸内をチェック
過去に腸閉塞を起こした場合、原因が腸内にあった可能性を否定できないことがあります。大腸カメラや胃カメラによる検査を受けることで、ポリープや腸管の炎症など、再発リスクに直結する要素を早期発見できるチャンスが広がります。
大腸カメラは大腸がんや大きな腸ポリープの存在を直接確認できるため、中年以降の方や再発リスクが高い方は定期的に検討してください。
内視鏡検査のメリット
| 項目 | 内容 | 利点 |
|---|---|---|
| 直接観察 | 腸管内部をリアルタイムで視認 | 小さな病変も見逃しにくい |
| ポリープ切除 | その場で異常を切除可能 | 追加手術が不要な場合も |
| 組織検査 | 疑わしい部分を細胞レベルで検査 | がんの早期発見につながる |
腸の健康維持に大切な栄養
腸の壁を健康に保つためには、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂ることが理想的で、また、食物繊維や発酵食品(ヨーグルト、納豆など)は腸内環境の改善に寄与します。
退院後の食事作りに不安がある場合は、栄養士に相談したり、健康的なレシピ本を活用したりするのも有効です。
腸のために取り入れたい食品の例
| 食品群 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 乳酸菌食品 | ヨーグルト、漬物、納豆 | 腸内フローラのバランス維持 |
| 食物繊維 | ゴボウ、サツマイモ、キノコ類 | 便通改善・有害物質の排泄を促進 |
| ビタミンやミネラル | 緑黄色野菜、果物、海藻 | 粘膜を保護し免疫力をサポート |
| 良質なたんぱく質 | 魚、豆腐、鶏肉 | 腸管組織の修復と維持に必要 |

よくある質問
- 入院費用の目安はどのくらいか
-
腸閉塞で入院する場合、入院期間や治療内容によって費用は大きく変わり、絶食や点滴のみで済む場合は短期間の入院で済むこともありますが、手術や長期的な管理が必要なら費用は高額になりがちです。
医療保険や高額療養費制度などを活用して負担を軽減できる可能性がありますので、事前に医療機関の相談窓口で相談してみるとよいでしょう。
- 内視鏡検査と手術はどちらを先に行うか
-
閉塞の原因が不明瞭な場合は、まず画像診断や内視鏡検査で詳細を確認するケースが多く、大腸カメラでポリープや腫瘍を発見し、その場で対応が可能ならば手術をせずに処置することもあります。
ただし、腸閉塞が重症で緊急に対処すべき状況の場合は、内視鏡検査よりも手術が優先されることがあります。
- 再発の可能性はどのくらいあるか
-
腸閉塞の再発リスクは、原因と術後管理の状況によって変動します。癒着が主な原因の場合、別の場所で新たな癒着が生じることもあるため、定期的な診察や検査が大切です。
腸が弱っている状態で無理に食事を再開したり、運動を極端に控えたりすると腸管の動きが低下し、再発に結びつく可能性があります。
- 退院後、医療機関へ相談する目安
-
腹痛や排便異常が数日続く、あるいは嘔吐や発熱などが生じたときは、早めに医療機関へ連絡することをおすすめします。
退院後しばらくは、腸がまだ万全の状態ではないことが多いため、少しでもおかしいと感じたら躊躇せずに受診してください。特に手術後は体力の回復にも時間がかかるため、こまめなフォローが大切です。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の初期症状と予防|早期発見のポイント】
腸閉塞の入院治療について理解が深まったら、次は初期症状の見分け方や予防法について知っておくと安心です。日常生活での注意点や早期発見のポイントを詳しく解説しています。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
腸閉塞について学んだ皆さんには、原因となることもある大腸がんの検査方法についても知っておくと、より包括的な理解ができます。早期発見につながる検査の選び方を詳しく解説しています。
参考文献
Ohmiya N. Management of obscure gastrointestinal bleeding: comparison of guidelines between Japan and other countries. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):204-18.
Iida H, Ohkubo H, Inamori M, Nakajima A, Sato H. Epidemiology and clinical experience of chronic intestinal pseudo-obstruction in Japan: a nationwide epidemiologic survey. Journal of epidemiology. 2013 Jul 5;23(4):288-94.
Yoshimaru K, Kinoshita Y, Matsuura T, Esumi G, Wada M, Takahashi Y, Yanagi Y, Hayashida M, Ieiri S, Taguchi T. Bowel obstruction without history of laparotomy: Clinical analysis of 70 patients. Pediatrics International. 2016 Nov;58(11):1205-10.
Kunitomi Y, Nakashima M, Takeuchi M, Kawakami K. Efficacy of Daikenchuto in the prevention of bowel obstruction in patients with colorectal cancer undergoing laparoscopic surgery: An observational study using a Japanese administrative claims database. Supportive Care in Cancer. 2023 Feb;31(2):133.
Kothari AN, Liles JL, Holmes CJ, Zapf MA, Blackwell RH, Kliethermes S, Kuo PC, Luchette FA. “Right place at the right time” impacts outcomes for acute intestinal obstruction. Surgery. 2015 Oct 1;158(4):1116-27.
Rami Reddy SR, Cappell MS. A systematic review of the clinical presentation, diagnosis, and treatment of small bowel obstruction. Current gastroenterology reports. 2017 Jun;19:1-4.
Diaz Jr JJ, Bokhari F, Mowery NT, Acosta JA, Block EF, Bromberg WJ, Collier BR, Cullinane DC, Dwyer KM, Griffen MM, Mayberry JC. Guidelines for management of small bowel obstruction. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2008 Jun 1;64(6):1651-64.
Williams SB, Greenspon J, Young HA, Orkin BA. Small Bowel Obstruction: Conservativevs. Surgical Management. Diseases of the colon & rectum. 2005 Jun 1;48(6):1140-6.
Schraufnagel D, Rajaee S, Millham FH. How many sunsets? Timing of surgery in adhesive small bowel obstruction: a study of the Nationwide Inpatient Sample. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2013 Jan 1;74(1):181-9.
Landercasper J, Cogbill TH, Merry WH, Stolee RT, Strutt PJ. Long-term outcome after hospitalization for small-bowel obstruction. Archives of Surgery. 1993 Jul 1;128(7):765-71.