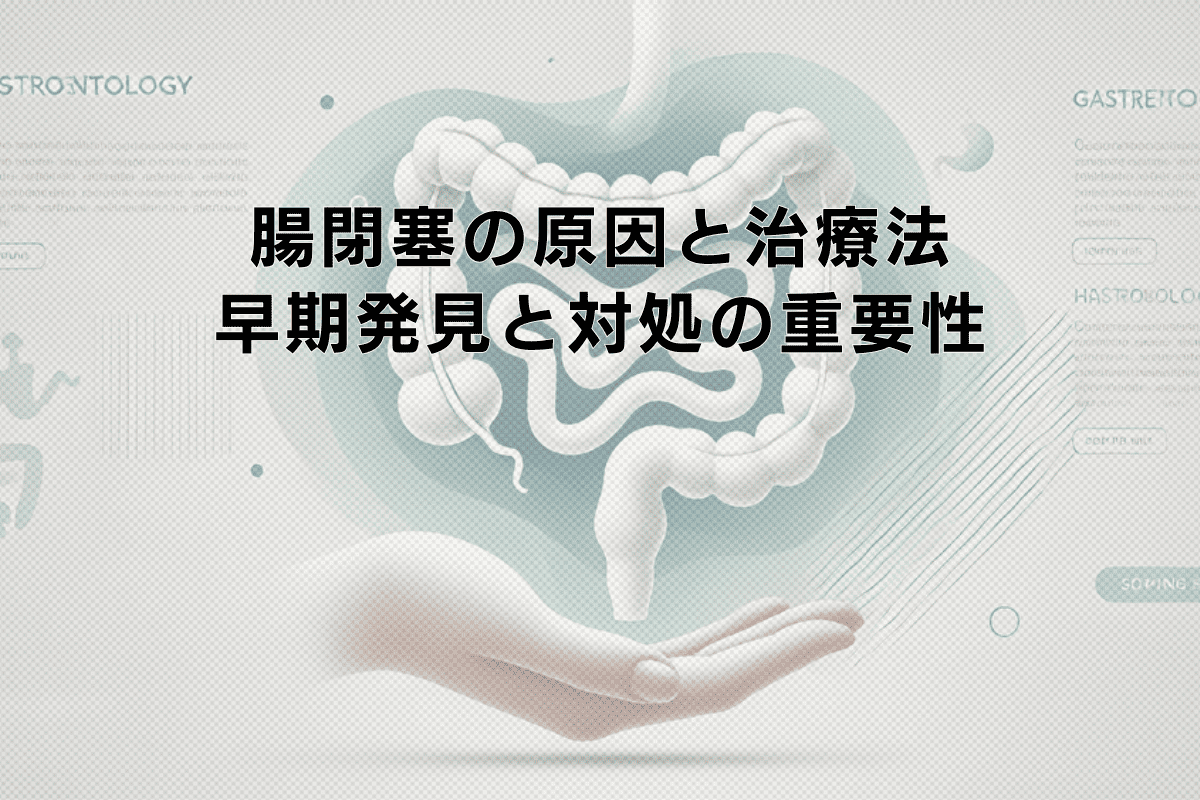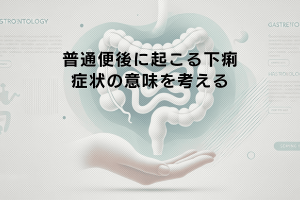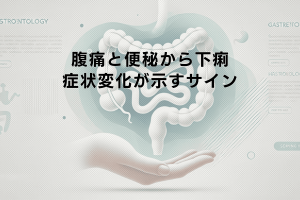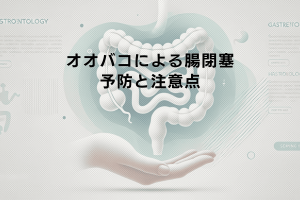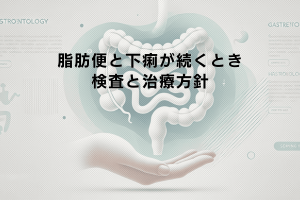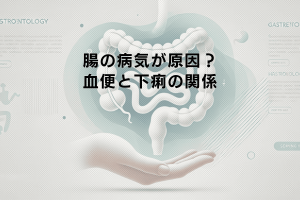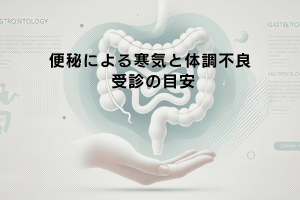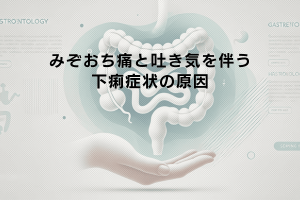腸閉塞は腸管の通過障害によって食物や消化液がうまく流れなくなり、腹痛・嘔吐などを引き起こす状態で、放置すると深刻な合併症を招く可能性があるため、早めに原因を見極めて治療につなげることが重要です。
腸閉塞の主な原因や治療法を理解し、早期発見や予防に役立ててください。
また内視鏡検査、大腸カメラ、胃カメラなどでの精密検査につながるケースもあるので、症状が気になる場合には専門医へ相談することをおすすめします。
腸閉塞とは何か
腸閉塞は、腸の内容物が正常に流れなくなる状態で、急性に発症するケースでは、短時間で強い痛みや嘔吐がみられることが多く、命にかかわる場合もあります。
腹部の違和感や便通異常に気づいたときに早めに医療機関を受診することで、重症化を防げる可能性があります。
腸閉塞の概要
腸の通過障害を総称して腸閉塞と呼びます。食物や消化液が腸の中をスムーズに移動できなくなると、腸内にガスや液体がたまり、腹部膨満や痛み、嘔吐などを引き起こします。
脱水状態や電解質バランスの乱れを伴うこともあるため、早期の診断と治療が欠かせません。
腸閉塞の原因には、腸管そのものに物理的な障害がある場合と、腸管の運動が低下する機能的な問題があり、手術後の癒着や腫瘍などが代表的な例で、放置すると重篤な合併症につながりやすいです。
必要に応じて内視鏡検査(大腸カメラや胃カメラ)を行い、原因を突き止めることが重要になります。
症状の特徴
腸閉塞の症状として多いのは、以下のような変化です。
- 強い腹痛や張り
- 嘔吐(内容物が胃液や胆汁混じりになることもある)
- ガスや便が出にくくなる
- 腹部が膨らんだような感じ
- 食欲不振
腹痛や嘔吐の程度は個人差がありますが、急激な症状の変化を見逃さずに早期受診を心がけてください。長時間放置すると腸管に壊死が起こるリスクがあり、緊急手術が必要になる場合があります。
腸閉塞の種類
腸閉塞は主に物理的な閉塞と機能的な閉塞の2つに大別できます。物理的閉塞は、腫瘍や腸内の癒着によって腸管が詰まる状態で、機能的閉塞は、腸管の動き(蠕動運動)が低下し、腸内容物の移動がうまくいかない状態です。
主な腸閉塞の種類
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 物理的閉塞 | 癒着や腫瘍、腸重積などが原因となり、腸管を直接ふさいでいる状態。緊急性が高い場合が多い。 |
| 機能的閉塞 | 腸自体はふさがれていないが、蠕動運動が低下している状態。イレウスとも呼ぶことがある。 |
物理的閉塞は外科的治療が必要になることが多く、機能的閉塞は保存的治療で経過観察する場合があります。ただし初期症状だけでは区別が難しいため、医療機関で正確に診断することが大切です。
腸閉塞の原因を知る重要性
腸閉塞の原因を把握すると、再発防止や早期発見につながりやすくなります。腸管がふさがる理由は多岐にわたりますが、手術後の癒着や腫瘍などが代表的です。
腸内の癒着や腫瘍
腸閉塞原因としてよく見られるのが、過去に受けた開腹手術による癒着です。開腹手術を行うと、腸管同士や腸管と腹膜がくっついてしまい、腸の通過を妨げることがあります。
腫瘍がある場合も同様に、腸管をふさいでしまう可能性が高く、腸の内腔が狭くなると、食物やガスが先へ進めなくなり、急性の腸閉塞を起こします。
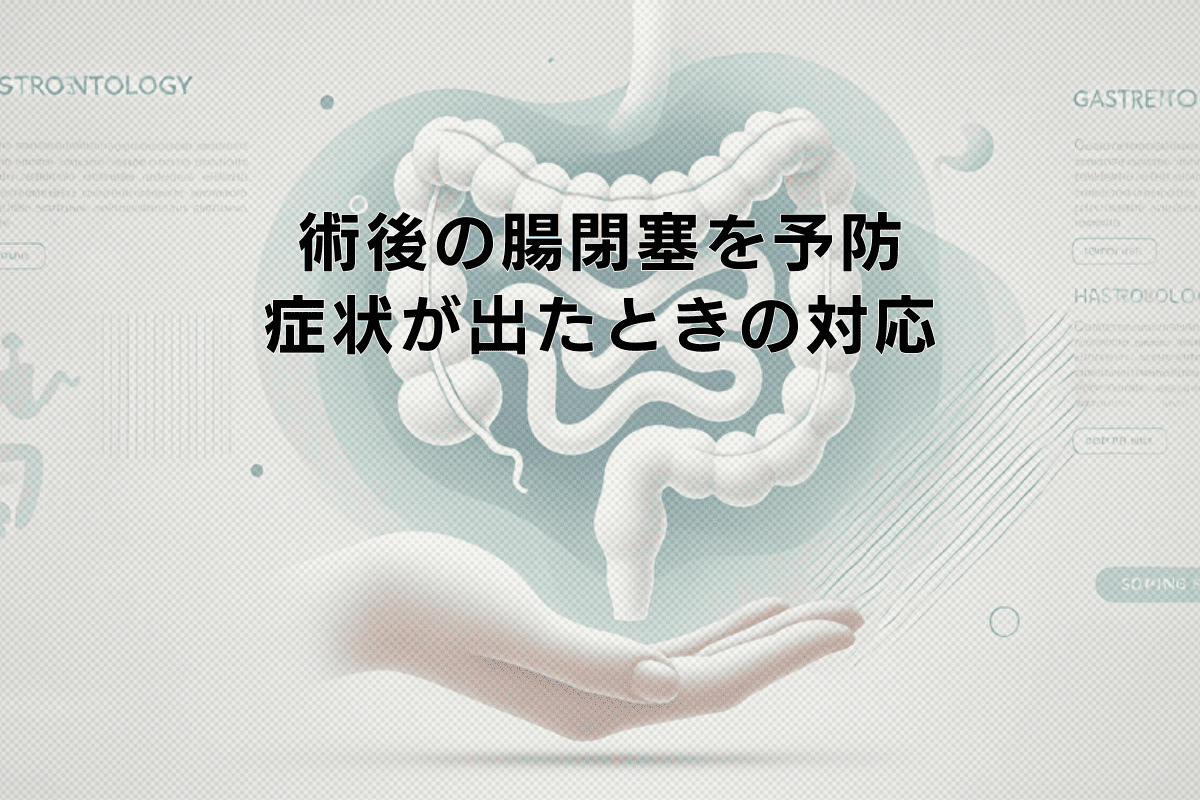

主な物理的原因と特徴
| 原因 | 特徴 |
|---|---|
| 癒着 | 手術創部周辺で腸管や腹膜がくっつく状態。時期によっては慢性的に小さな閉塞を起こすこともある。 |
| 腫瘍 | 腸管内にできた腫瘍によって内腔が狭くなる。大腸がんなど悪性の場合は急激に進行することがある。 |
| 憩室炎 | 憩室部分で炎症や膨隆が起こり、閉塞を招くことがある。慢性化すると潰瘍や穿孔のリスクが高まる。 |
| 腸重積 | 腸管の一部が別の腸管に入り込む。小児に多いが、成人でもポリープや腫瘍がきっかけで発生するケースがある。 |
| 腸のねじれ | 腸管が回転してしまうことで、血流障害や閉塞を起こす。迅速な処置を行わないと腸管壊死につながるリスクが上昇する。 |
癒着などは自分の力で予防できるものではありませんが、手術歴がある方は腸閉塞を疑った場合に早めに医療機関を受診することが大切です。腫瘍による場合も、早期に発見できれば治療の選択肢が広がります。

消化器官の機能不全
腸閉塞治療を考える上で見逃せないのが、腸そのものの運動機能が低下してしまう機能的閉塞です。
血流障害や代謝疾患、電解質異常、あるいは高齢者の全身状態の悪化が原因になるケースがあり、機能的閉塞の場合は、腸自体の形態に明らかな異常がなくても、動きが極端に遅れてしまいます。
機能的閉塞の背景にはさまざまな要因があり、糖尿病や心疾患、腎不全などがあると腸の血流や自律神経機能が乱れやすくなり、消化管の蠕動運動に影響を与えます。
さらに、長期臥床や低栄養、薬剤(麻薬系鎮痛薬、抗コリン薬など)の影響で腸の動きが弱まる場合もあるため、全身状態の管理が重要です。
そのほかのリスク要因
腸閉塞は、次のような生活習慣や疾患とも関係します。
- 不規則な食習慣や暴飲暴食
- 繰り返す便秘
- 長期の寝たきりや運動不足
- 腸内環境の乱れ
- 慢性疾患(糖尿病、腎機能障害 など)
リスク要因がいくつも重なると、腸閉塞の発症確率が上昇する傾向があります。
腸の動きを維持するために、生活習慣の見直しや適度な運動習慣が重要で、便秘が続く方は、医師の指導のもとで下剤や整腸薬などを使い、腸への負担を軽減するとよいでしょう。
腸閉塞の代表的な症状
腸閉塞の症状は腹部の不快感だけでなく、嘔吐や便通異常がはっきり現れることが多く、排便や排ガスが止まった際には、腸閉塞を疑うきっかけになるため注意が必要です。
症状の強弱や持続時間にも個人差がありますが、急性の痛みや長引く違和感がある場合は医療機関を受診してください。
腹痛や嘔吐
腸閉塞で多くの方が経験するのは、突発的に起こる腹痛で、痛みは波のように襲う場合があり、痛みの程度が強いときには日常生活を続けるのが難しくなります。
また、進行すると嘔吐を伴うことが多く、胃内容物だけでなく黄色や緑色を帯びた胆汁混じりの嘔吐物が出ることもあります。
嘔吐の量が多い場合は脱水や電解質異常を引き起こすため、水分補給などで対応しながら早めに医療機関を受診することが肝心です。
腸閉塞時に考えたいポイント
- 痛みの発生頻度や強さの変化を記録する
- 嘔吐回数や吐いた物の色を把握する
- 水分補給が困難になる前に病院へ連絡する
- 過去の手術歴や基礎疾患の情報を医師に伝える
急性腹症は自己判断で放置すると症状が急速に悪化する恐れがあるので、医療機関での受診が重要です。
排便や排ガスの停止
腸の通過障害があると、便やガスが正常に排出されず、数日続くと腹部膨満や張りが強くなり、さらなる苦痛につながります。特にガスが一切出ない状態が続くと腸内圧が上がり、腸粘膜が損傷を受けるリスクが高まります。
排便や排ガスの停止を初期症状として捉え、早い段階で医療機関を訪れると治療につながりやすいです。
腸閉塞による排便・排ガス障害と合併症
| 障害内容 | 影響 |
|---|---|
| 排便停止 | 腸内に老廃物がたまり、毒素が再吸収されるリスクが上昇。腹痛や悪心、全身倦怠感を伴うこともある。 |
| 排ガス停止 | 腸内圧が高まり、血流障害や腸管損傷の可能性が高まる。 |
| 脱水 | 嘔吐や食欲低下により、体内の水分量が減少。血圧の低下やめまい、ふらつきを起こすことがある。 |
| 電解質バランス乱れ | カリウムやナトリウムなどが不均衡になり、不整脈や筋力低下を引き起こすことがある。 |
排便や排ガスがまったく出ない状態が続くときには、我慢せずに病院を受診して詳しい検査を受けたほうが安全です。
脱水とその他の合併症
嘔吐の頻度や量が増すと、体内の水分や電解質が急激に失われ、脱水状態に陥りやすくなるので、口が渇きやすくなる、尿量が減る、めまいがするなどのサインを見逃さないようにしてください。
脱水が進むと全身状態が悪化しやすく、血圧低下や腎機能の低下を招く恐れがあり、重症の場合は点滴などで水分や電解質を補う必要があります。
腸閉塞が長引くと、腸管が膨張して血流障害を起こし、腸管壊死へ進行するリスクも高まり、腹膜刺激症状と呼ぶ激しい痛みや圧痛があれば、緊急手術が視野に入ります。
こうした重篤な状態を防ぐためにも、早めに医療機関で検査と治療を受けることが大切です。
病院での検査方法
腸閉塞が疑われる場合、医師はまず問診や身体診察を行い、画像検査や血液検査で状態を確認します。必要に応じて大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査も選択肢となります。
検査結果を総合的に判断し、腸閉塞の原因と重症度を確かめて治療方針を決定します。
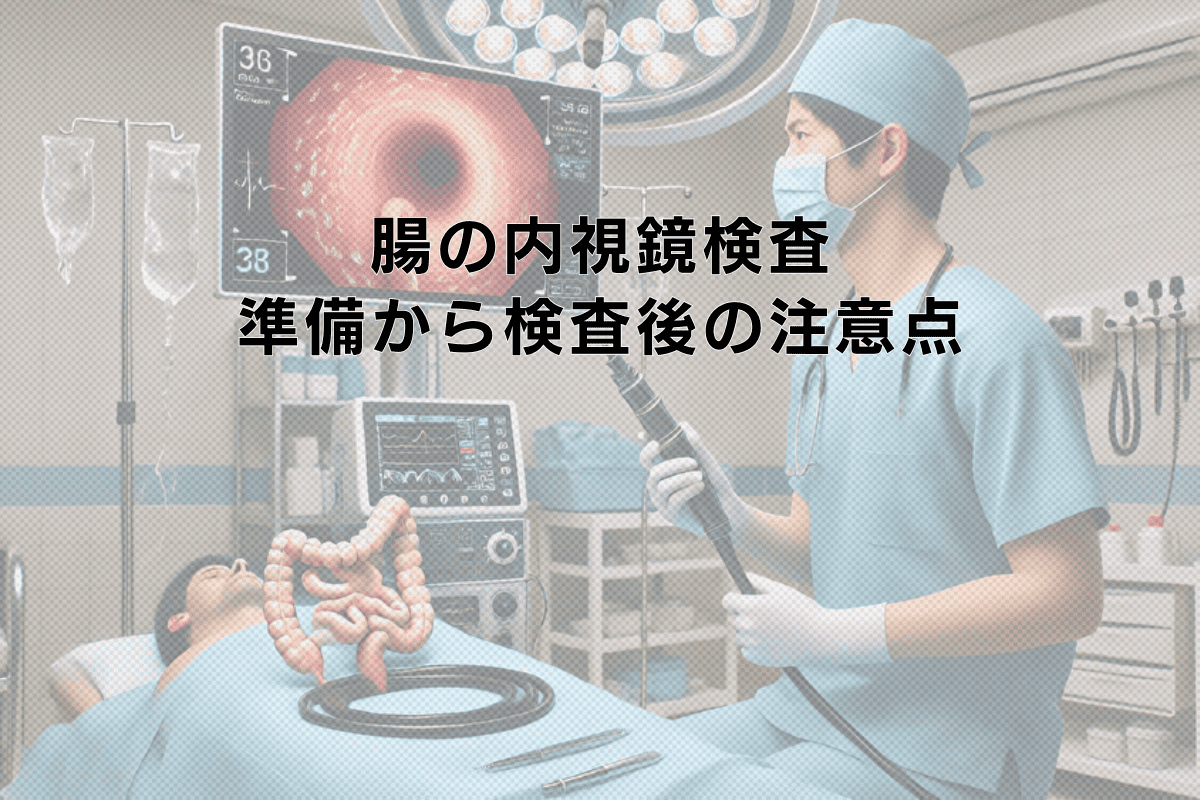

画像検査
腸閉塞の診断にはX線検査やCT検査が重要な役割を果たします。X線により、腸管内にたまったガスや液体の位置関係を把握し、腸閉塞の有無を推測します。CT検査では、腸のねじれや腫瘍の有無、癒着による腸管の変形などをより正確に確認できます。

画像検査の特徴
| 検査方法 | 特徴 |
|---|---|
| X線検査 | シンプルに腸管ガスのパターンを確認できる。立位・仰臥位など体位を変えて撮影し、液面形成を診断材料にすることが多い。 |
| CT検査 | 腸管の走行や腫瘍、ねじれ具合などを多角的に把握できる。造影剤を使うと血流状態の評価もしやすい。 |
腸閉塞の程度や原因を把握するために、画像検査を複数回行うこともあり、一度の撮影で明らかにならない場合は定期的に再検して、腸の変化を観察します。
血液検査や身体所見
血液検査では脱水や炎症の程度、電解質バランスを確認し、白血球数が増加している場合は感染症や炎症が進んでいる可能性があるため、慎重に経過を追うことになります。腎機能や肝機能の数値もチェックし、全身状態を評価することが大切です。
身体所見として、聴診器で腸の蠕動音を聞いたり、腹部を軽く押してみて痛みや抵抗感を調べ、腸閉塞では蠕動音が過度に亢進していたり、逆にまったく聞こえなくなっていたりと特徴的な所見が認められます。
内視鏡検査の役割
腸閉塞が疑われる場合、内視鏡検査を行うこともあります。大腸カメラや胃カメラを使って実際に腸内の状態を観察し、閉塞の原因を直接確認できる場合があります。
特に腫瘍の疑いがあるケースでは、内視鏡で組織を一部採取して病理検査を行うことが重要です。
腸閉塞が進行していて内視鏡を挿入することが難しい場合もありますが、症状が軽度であったり部分的閉塞であったりする場合には、原因の特定や治療方針の決定に役立ちます。
また、胃カメラでは上部消化管を、大腸カメラでは大腸全体を精密に観察するため、部位によって検査を分けることもあります。
腸閉塞の治療法
腸閉塞治療法は、閉塞の原因や症状の重さによって異なり、保存的に治す場合と、手術が必要な場合があり、状況に応じて最善のアプローチを選択します。
腸閉塞の原因が腫瘍か癒着か機能的問題かによって、治療方針や予後が変わるため、正確な診断が重要です。
保存的治療
腸閉塞が軽度や機能的閉塞の場合、まずは保存的治療を検討します。
鼻から管を通して胃液や腸液を吸引し、腸管内の圧力を下げる手技がよく行われ、吐き気や腹痛が和らぎ、腸が自力で通過機能を回復することを狙います。また大腸がんが原因の場合はがんによる狭窄部にステントを留置して減圧を図ります。絶食や点滴での栄養補給を続け、腸の安静を保つことも大切です。
保存的治療に用いる方法
| 手技・方法 | 目的 |
|---|---|
| 絶食と点滴 | 腸の負担を減らすと同時に、脱水や栄養不足を防ぐために点滴で補給を行う。 |
| 胃管・腸管の吸引 | 鼻から管を挿入し、胃や腸にたまった内容物やガスを排出して腹部膨満を軽減する。 |
| 電解質バランス調整 | 血液検査で乱れた電解質を点滴で補い、不整脈や筋力低下を予防する。 |
| 薬物療法(整腸剤など) | 腸の蠕動運動を調整し、腸閉塞の悪化を防ぐ。 |
保存的治療で症状の改善がみられない場合や、痛みが強くなって腸管壊死のリスクが高まったと判断された場合には外科的治療を検討します。
外科的治療
物理的に腸管がふさがっている場合や、腸管壊死の可能性がある場合には、手術による腸閉塞治療が必要になることが多いです。癒着をはがす処置や腫瘍の切除、壊死した腸管の切除など、原因に応じて対応が異なります。
手術を受ける際には患者さんの全身状態や基礎疾患の有無も考慮し、大きな開腹手術だけでなく、内視鏡下で行う低侵襲の手術が選択されることもあります。
術後は再び癒着が起こるリスクがあるため、医師の指示に従ったリハビリや生活管理を続けることが重要です。
内視鏡治療
腸内に良性のポリープや腫瘍がみられる場合には、内視鏡治療で腸閉塞の原因を取り除け、大腸カメラを挿入してポリープを切除したり、ステントを置いて通過路を確保する手技が検討されます。
腫瘍が悪性で大きい場合には外科的治療が必要になることもありますが、小さい病変であれば内視鏡での切除が有効です。
内視鏡治療は開腹手術に比べて身体への負担が軽く、入院期間を短く抑えられる利点があります。
ただし、腸閉塞がすでに進行していて内視鏡を通せないほどの狭窄がある場合など、状況によっては適用外となるため、主治医との相談が欠かせません。
腸閉塞を早期に発見するために
腸閉塞は気付かずに放置すると重篤化するリスクが高まります。普段から腸の健康を意識し、何らかの異変を感じた際には早めに受診することが重要で、早期発見のカギは、生活習慣の管理と定期的な検査です。

普段の生活習慣と体調観察
腸閉塞を予防するうえで、食生活や運動習慣の見直しが役立ちます。
腸管の動きが鈍ると便秘が続いたり、ガスがたまりやすくなるので、食事の内容や水分量を整え、適度に体を動かして腸の蠕動運動を活発にするのが望ましいです。
- 水分をこまめに摂取する
- 野菜や食物繊維の多いメニューを意識する
- お腹を温めて血流を促す
- 適度なウォーキングや軽い運動を取り入れる
過去に開腹手術の経験がある方は、とくに腸閉塞のリスクが高まります。腹部の違和感や便通が急に変化した場合は、医師に相談して早期診断へつなげてください。
症状を感じた時の対処
腹痛や嘔吐、便が出ない状態が続いたときに、自己判断で下剤を多用したり、市販薬に頼り続けたりするのは避けましょう。
腸閉塞の場合、無理に腸を動かそうとすると悪化する可能性があり、早めに専門医の診察を受け検査を受けることが安全策です。
受診前に意識しておきたいこと
- 痛みや吐き気の出始めた時間と経過をメモしておく
- 嘔吐物の色や量などを確認しておく
- 過去の手術歴や慢性疾患の有無を整理しておく
- 普段の便通や食事量の変化を振り返る
医療機関でこれらの情報を伝えると、検査と診断が進めやすくなります。
定期的な内視鏡検査
大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査は、腸内の異常を直接確認できる有力な手段で、腸閉塞の原因となるポリープや腫瘍を見つけた場合に、早期の段階で処置につなげやすくなります。
大腸がんや潰瘍性大腸炎などのリスクがある方は、定期的な内視鏡検査を検討してください。

内視鏡検査のタイミングとメリット
| タイミング | メリット |
|---|---|
| 40歳以上で年1回程度 | 腸内環境やポリープの発生状況を早期に把握し、腸閉塞予防につなげる。 |
| 家族歴や手術歴がある場合 | 癒着や腫瘍のリスクが高いので、計画的に検査を実施して症状を早期発見。 |
| 不定愁訴が続く、便通異常が顕著 | 軽度の炎症や粘膜病変を発見し、早めの投薬治療や生活指導が可能になる。 |
検査は負担が大きいと感じる方もいますが、適切に腸の状態を確認することで腸閉塞だけでなく、ほかの消化器疾患の予防や早期治療にも役立ちます。
日常生活で意識したいポイント
腸閉塞のリスクを低減するには、食生活を中心とした日常生活の管理が大切です。便秘を防ぎ、腸内環境を良好に保つための基本的な習慣を身につけると、腸閉塞の再発リスクを下げる効果が期待できます。
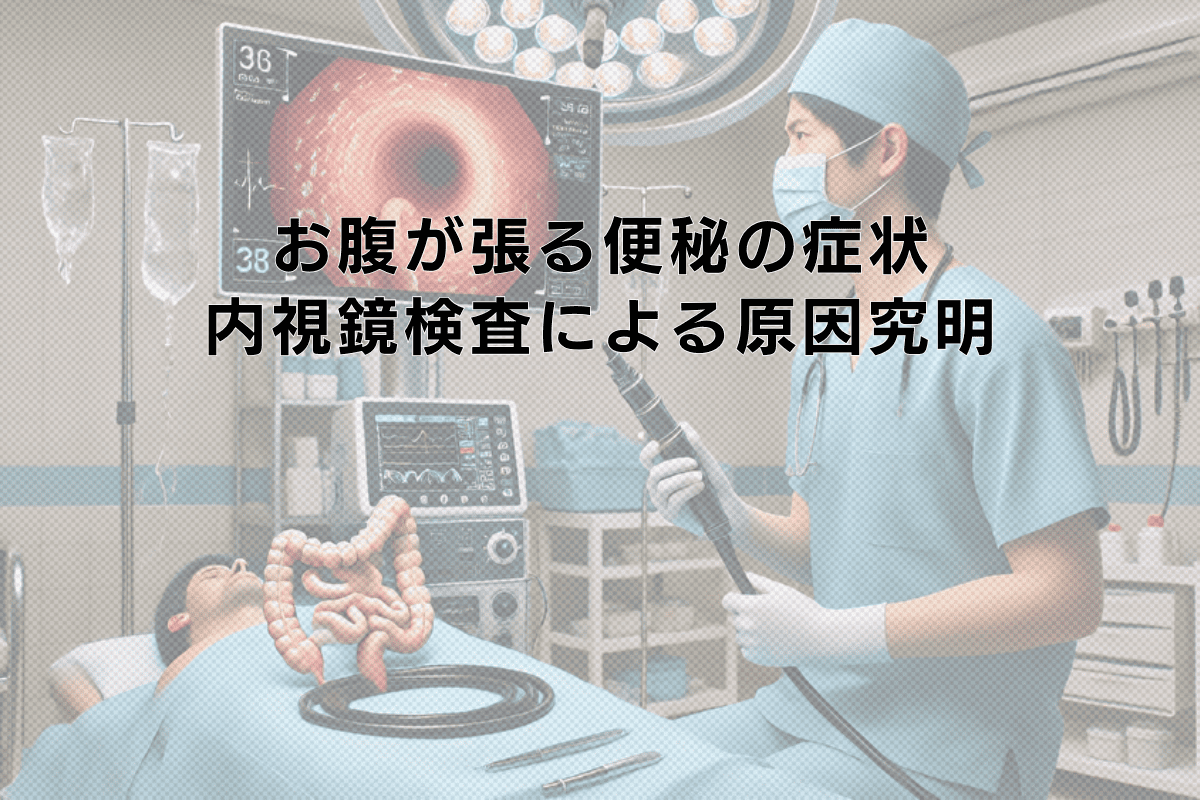
食事の工夫と水分補給
腸内環境を整えるうえで食事は大切な要素で、適度な食物繊維、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取し、腸の蠕動運動を促進させると便通がスムーズになります。水分不足は便が硬くなる原因になるため、意識して水やお茶を飲みましょう。
過度のアルコールや刺激物は腸を荒らす場合があるため、控えめにしてください。
腸内環境をサポートする食材
| 食材 | 効果 |
|---|---|
| 野菜(特に根菜類) | 食物繊維が豊富で腸のぜん動運動を促す。 |
| 発酵食品(味噌、納豆、ヨーグルトなど) | 腸内の善玉菌を増やし、便通を改善。 |
| 海藻類、キノコ類 | ミネラルや食物繊維を多く含み、腸内を掃除する働きがある。 |
| 白身魚や鶏肉 | 脂肪分が比較的少なく、消化に負担がかかりにくいタンパク源。 |
| 水やお茶など | こまめな水分補給で便が柔らかくなり、排便がスムーズになる。 |
食物繊維の過剰摂取はかえってガスがたまりやすくなる場合もあるため、体調や便通の状態をみながら調整していきます。
生活リズムの整え方
腸の動きは自律神経と深く関わっていて、過度のストレスや寝不足は自律神経のバランスを乱し、蠕動運動が低下することにつながります。規則正しい睡眠時間を確保し、リラックスできる時間を設ける工夫が必要です。
軽い運動やストレッチで体を動かすと血流が促進され、腸への血流も増えやすくなります。
- 毎日同じ時間に起床・就寝する
- 適度にストレッチや呼吸法を取り入れる
- 入浴や散歩で心身をリラックスさせる
- 必要に応じて医療機関でカウンセリングなどを活用する
生活リズムが安定すると腸の調子も整いやすくなり、腸閉塞のリスクを下げる効果が期待できます。
継続的な通院と再発防止
腸閉塞を一度経験した方や手術歴がある方は、再発リスクが高まる傾向があるので、定期的に通院して画像検査や血液検査、内視鏡検査を受けると、原因となる病変を早期に見つけやすくなります。症状がなくても定期的なチェックが重要です。
再発防止のために心がけたい事項
- 定期健診で腸の状態をチェックし続ける
- 便通や腹痛などの軽い異変も医師に報告する
- 医師の指導にしたがって食事管理や生活習慣を見直す
- 胃カメラや大腸カメラで腸内環境を定期観察する
医療機関と連携しながら生活習慣を管理すると、腸閉塞の再発リスクを下げられる可能性が高まります。
内視鏡検査の利点と受診のタイミング
内視鏡検査は、大腸カメラや胃カメラを利用して直接消化管を観察できる強力な手段です。腸閉塞の原因として疑われる病変の早期発見や治療に直結する場合もあり、必要に応じて積極的に検討するとよいでしょう。
内視鏡検査が必要な理由
腫瘍やポリープなど、腸閉塞を引き起こしやすい病変を早期発見しやすい点が内視鏡検査の利点で、レントゲンやCTでは発見が難しい小さな病変でも、内視鏡であれば直接視認でき、病変の一部を採取して組織検査することも可能です。
また、検査中にポリープを切除できるため、同時に治療が行える場合があります。
大腸カメラや胃カメラでチェックしたいケース
| ケース | 検査の目的 |
|---|---|
| 便に血が混ざる、下血がある | 腸内の炎症やポリープ、がんの有無を確認する |
| 腹痛や下痢、便秘が慢性的 | 炎症性腸疾患や腫瘍などが潜んでいないかを調べる |
| 過去にポリープや腫瘍が見つかった | 再発や新たな病変の発生を定期的に観察する |
| 腹部膨満感や食欲不振が続く | 消化管全体の状態を直接確認し、機能低下や閉塞のリスクを探る |
内視鏡検査を受けるときには、下剤を飲んで腸内をきれいにする必要があり、検査前後には医師や看護師の指示を守り、体調に応じて十分な休息をとるとスムーズに受けられます。
大腸カメラや胃カメラの流れ
検査を受ける際には、前日から食事制限を行い、当日は指定の下剤で腸を洗浄します。腸内に内容物が残っていると正確な観察や処置が難しくなるため、可能な限りしっかりと準備をすることが大切です。
検査中は鎮静剤を使う場合が多く、痛みや不快感を軽減できます。医療機関によって手順が少しずつ異なりますが、検査自体は数十分程度で終了することが多いです。
検査後は一定時間の安静を経て、体調に大きな問題がなければ帰宅できますが、ポリープ切除などの処置を行った場合には、入院が必要になるケースもあります。
相談のタイミングと受診ガイド
腸閉塞の症状を疑うときだけでなく、慢性的な便秘や下痢、血便などが続くときにも、できるだけ早めに医師に相談してください。特に40歳以上や基礎疾患がある方は、大腸カメラを定期検査として受けることを検討する価値があります。
- 体調不良が続いて医療機関を受診する際に内視鏡検査を提案された場合
- 定期健康診断で異常を指摘された場合
- 親族に大腸がんなどの消化器系の病歴が多い場合
- 過去に腹部手術を受けている場合
早めに受診すると検査や治療の選択肢が広がり、腸閉塞を未然に防いだり早期に治療を開始したりできる可能性が高まります。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の初期症状と予防|早期発見のポイント】
「治療法は分かったけれど、もっと早く気付く方法は?」という疑問に応える内容です。初期症状の見分け方や再発予防のコツを詳しくまとめています。
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
腸閉塞について理解が深まったところで、消化器全体の機能についても知っておくと、より包括的な健康管理ができます。
参考文献
Franklin Jr ME, Gonzalez Jr JJ, Miter DB, Glass JL, Paulson DJ. Laparoscopic diagnosis and treatment of intestinal obstruction. Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques. 2004 Jan;18:26-30.
Jackson PG, Raiji M. Evaluation and management of intestinal obstruction. American family physician. 2011 Jan 15;83(2):159-65.
Jackson P, Cruz MV. Intestinal obstruction: evaluation and management. American family physician. 2018 Sep 15;98(6):362-7.
Ferguson HJ, Ferguson CI, Speakman J, Ismail T. Management of intestinal obstruction in advanced malignancy. Annals of medicine and surgery. 2015 Sep 1;4(3):264-70.
Berry RE. Diagnosis and treatment of acute intestinal obstruction. Journal of the American Medical Association. 1952 Feb 2;148(5):347-55.
Irvin TT, Greaney MG. The treatment of colonic cancer presenting with intestinal obstruction. Journal of British Surgery. 1977 Oct;64(10):741-4.
Griffiths S, Glancy DG. Intestinal obstruction. Surgery (Oxford). 2023 Jan 1;41(1):47-54.
Holder Jr WD. Intestinal obstruction. Gastroenterology Clinics of North America. 1988 Jun 1;17(2):317-40.
Osteen RT, Guyton S, Steele G, Wilson RE. Malignant intestinal obstruction. Surgery. 1980 Jun 1;87(6):611-5.
McEntee G, Pender D, Mulvin D, McCullough M, Naeeder S, Farah S, Badurdeen MS, Ferraro V, Cham C, Gillham N, Matthews P. Current spectrum of intestinal obstruction. Journal of British Surgery. 1987 Nov;74(11):976-80.