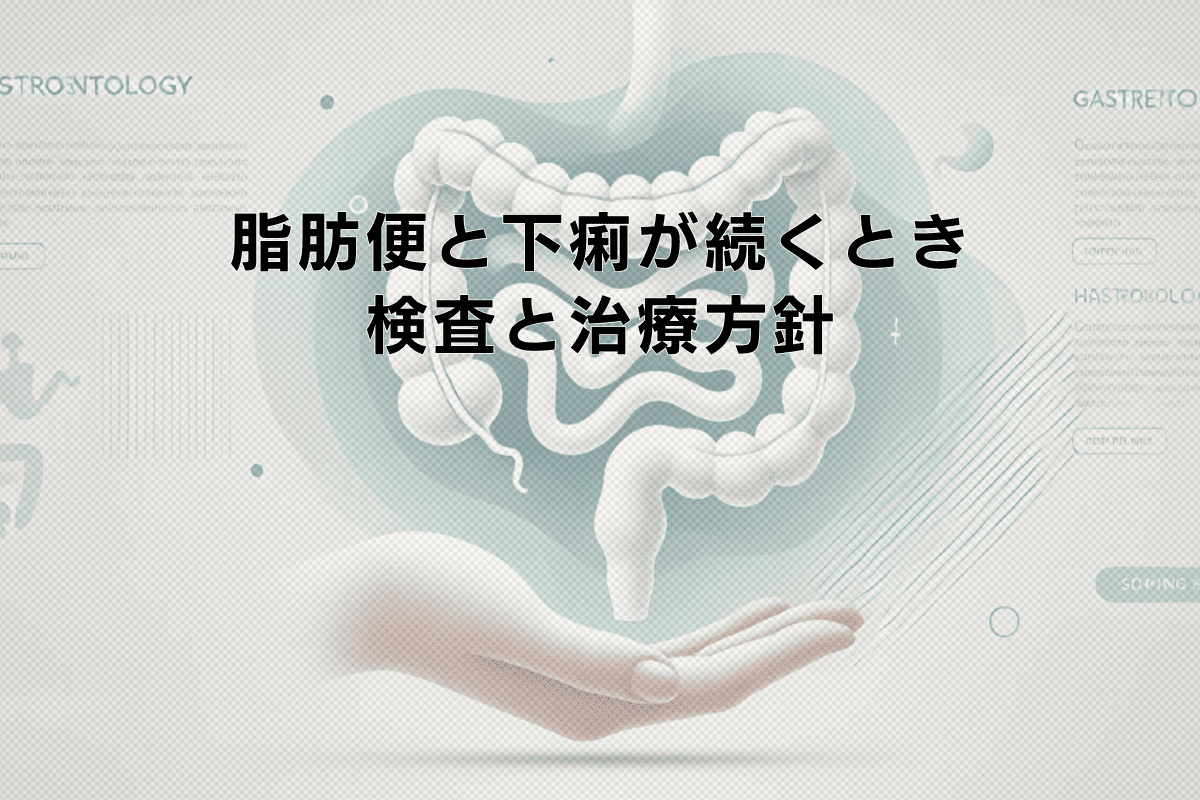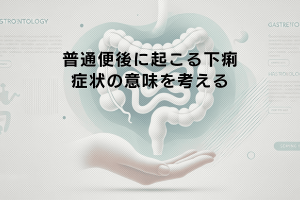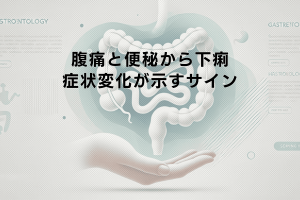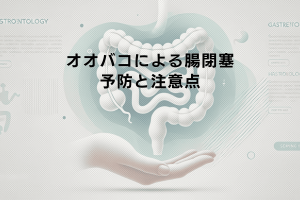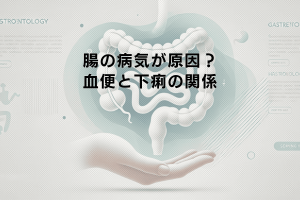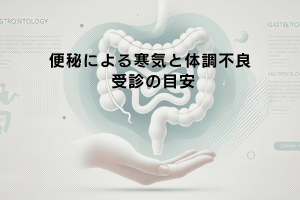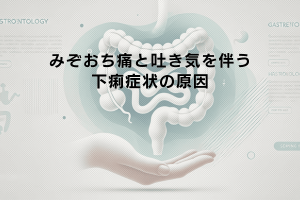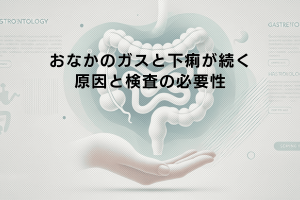便が白っぽく、水に浮き、油のようなものが混じる脂肪便と呼ばれる症状が下痢と共に続くと、何か体に異常があるのではないかと不安になるものです。
多くの場合、脂っこい食事を摂りすぎた後の一時的な現象ですが、慢性的に続く場合は、食べたものの脂肪分がうまく消化・吸収できていないサインかもしれません。
この状態は脂肪吸収不良と呼ばれ、単なるお腹の不調にとどまらず、体重減少や必須栄養素の欠乏といった深刻な栄養障害につながることもあります。
この記事では、脂肪便と下痢がなぜ起こるのか、背景にある消化吸収の複雑な仕組みから、考えられる病気、医療機関で行う検査、今後の治療方針までを解説します。
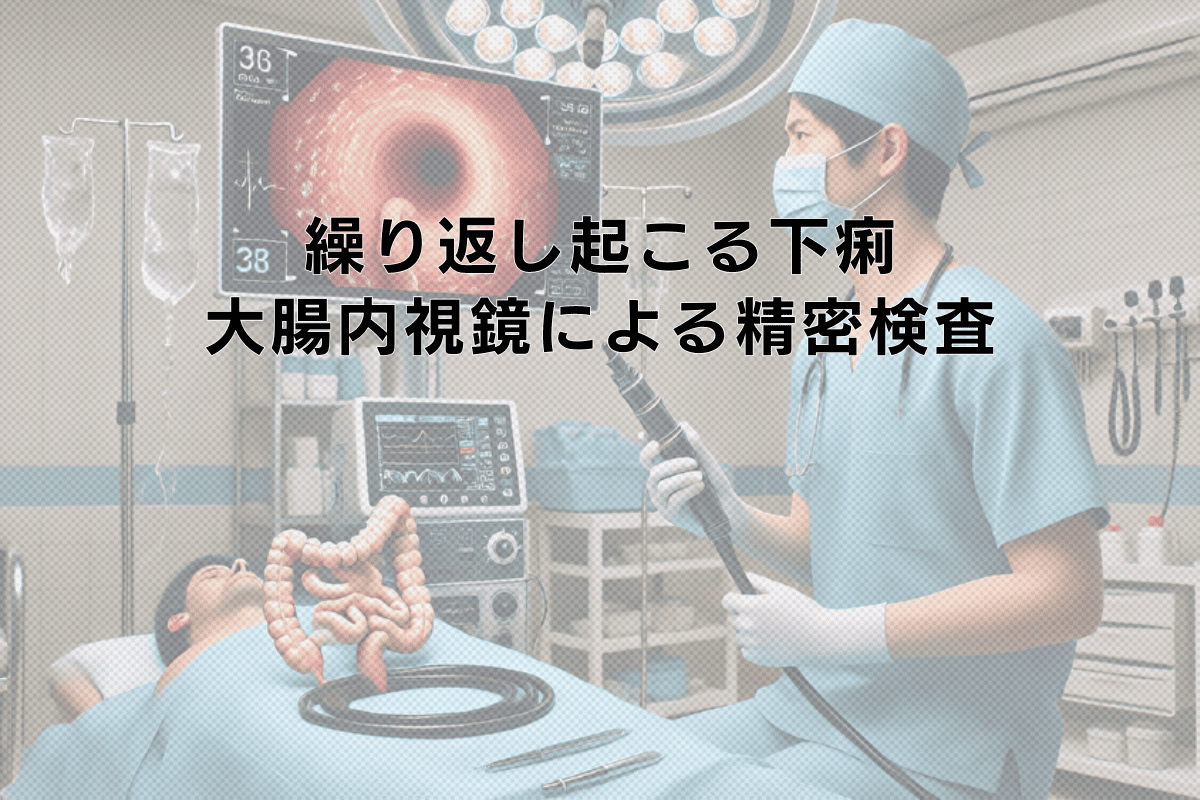
脂肪便とはどのような便か
脂肪便とは、消化吸収されなかった脂肪分が異常に多く含まれた便のことで、医学的には脂肪便症とも呼ばれます。何らかの原因で脂肪の吸収がうまくいかない状態が起こると、便中の脂肪量がそれを大きく上回り、特徴的な性状を示します。
脂肪便の見た目と特徴
脂肪便にはいくつかの特徴的な見た目や性質があり、まず、色が通常よりも白っぽく、淡黄色や銀色に見えることがあります。
これは、正常な便の色素であるビリルビン(胆汁に含まれる色素で、最終的に便を茶色くする)が、大量の脂肪によって薄められたり、胆汁の分泌自体が滞って便中に排出されなくなったりするために起こります。
また、脂肪は水よりも比重が軽いため、便器の水にぷかぷかと浮く傾向があり、さらに、便の表面が油でテカテカと光って見えたり、水面にラー油のような油滴が分離して浮いたりすることもあります。
臭いも特徴的で、未消化の脂肪が腸内細菌によって分解される際に、酸っぱいような、あるいは腐敗したような強い臭気を放つことが多いです。
便が粘土のようにべったりとしていて、便器に付着して流れにくい、というのもよく見られる特徴で、これは未消化の脂肪分が粘着性を高めるためです。
脂肪便の主な特徴
| 項目 | 特徴 | 理由 |
|---|---|---|
| 色 | 白色、淡黄色、銀色 | 便中色素が脂肪で薄まる、または胆汁分泌の低下 |
| 浮力 | 水に浮きやすい | 脂肪は水より軽いため |
| 臭い | 酸っぱいような強い臭気 | 未消化の脂肪が腸内細菌で分解されるため |
脂肪の消化吸収の仕組み
食事から摂取した脂肪(主に中性脂肪)は、分子が大きいためそのままでは小腸から体内に吸収できず、いくつかの消化器が連携して、吸収可能な形にまで細かく分解することが必要です。
まず、胃で食物が粥状になるまで攪拌され、十二指腸に送られます。十二指腸で脂肪の本格的な消化が始まり、ここで、肝臓で作られ胆のうに蓄えられていた胆汁が、食事の刺激に応じて分泌されます。
胆汁に含まれる胆汁酸は、大きな脂肪の塊を界面活性剤のように包み込み、非常に小さな油滴に分散させ、これを乳化と呼びます。
次に、膵臓から分泌される強力な脂肪分解酵素であるリパーゼが、乳化されて表面積が大きくなった油滴に効率よく作用し、脂肪を脂肪酸とモノグリセリドという小さな分子に分解します。
最終的に、小さな分子が胆汁酸によってさらにミセルという微小な粒子を形成し、小腸の粘膜上皮細胞から吸収されます。吸収された後はリンパ管や血管を通って全身に運ばれ、エネルギー源として利用されたり、貯蔵されたりします。
この一連の精巧な流れのどこか一つでも滞ると、脂肪は吸収されずに大腸へと送られ、脂肪便として排出されてしまうのです。
なぜ下痢を伴うのか
脂肪便と下痢は密接に関連していて、小腸で吸収されなかった脂肪酸や胆汁酸は、そのまま大腸へと流れ込み、大腸の粘膜に対して強い刺激物となります。
この刺激により、大腸の粘膜は腸管内に水分を過剰に分泌し、同時に腸のぜん動運動が異常に活発になり、分泌性下痢と呼ばれる状態です。
さらに、未消化の脂肪分が腸管内の浸透圧を高め、腸の外から水分を引き込む浸透圧性下痢の要素も加わることで、便の水分量が著しく増え十分に固まる時間がなくなり、水様性または泥状の下痢として排出されます。
つまり、消化不良を起こした脂肪そのものが、下痢を起こす原因物質となっている状態です。このため、脂肪便が見られるときは、多くの場合、腹痛を伴う下痢症状がセットで現れます。
脂肪便と下痢を引き起こす主な原因
脂肪便と下痢が続く場合、原因は多岐にわたり、一時的な食生活の乱れから、特定の臓器の機能不全まで、様々な可能性を考える必要があります。ここでは、主な原因を消化吸収の段階に沿って、より詳しく解説します。
食生活による一時的な要因
最も一般的で、かつ多くの人が経験する原因は、脂質の過剰摂取です。
天ぷらや唐揚げ、こってりしたラーメン、生クリームをたっぷり使ったケーキなど、一度に大量の脂肪を摂取すると、胆汁や膵液の分泌が追いつかず、消化能力の限界を超えてしまいます。
消化酵素の分泌能力には個人差があり、加齢によっても低下することがあり、消化しきれなかった脂肪がそのまま便として排出され、一時的に脂肪便や下痢を起こします。これは健康な人でも起こりうる生理的な反応であり、病気ではありません。
暴飲暴食の翌日などに経験することが多く、食生活を通常に戻せば数日で自然に改善することがほとんどですが、頻繁に起こる場合は、ご自身の消化能力に対して食生活が合っていない可能性があります。
脂肪分が多く消化に負担をかけやすい食品
| 食品カテゴリー | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 揚げ物 | 天ぷら、フライドポテト、とんかつ | 衣が油を多く吸収するため高脂質になる |
| 肉類の脂身 | 豚バラ肉、牛カルビ、ベーコン | 飽和脂肪酸が多く、消化に時間がかかる |
| 乳製品 | 生クリーム、バター、チーズ | 動物性脂肪を多く含む |
膵臓の機能低下
膵臓は、脂肪を分解する酵素リパーゼを分泌する極めて重要な臓器です。膵臓の機能が何らかの理由で著しく低下すると、リパーゼの分泌量が減少し、食べた脂肪を十分に分解できなくなり、これを膵外分泌機能不全と呼びます。
慢性膵炎や膵臓がん、膵嚢胞などの病気によって膵臓の正常な細胞が破壊されたり、置き換わったりすると、この状態に陥ります。慢性膵炎は、長年のアルコール多飲が主な原因とされ、持続的な脂肪便と下痢を起こす代表的な病気です。
膵臓は予備能力が高いため、機能が正常の10%以下になるまで症状が出にくいという特徴があり、脂肪便が出る頃には、膵臓の機能が相当程度損なわれている可能性があります。
肝臓・胆のう・胆管の問題
肝臓は脂肪の乳化に必要な胆汁を生成し、胆のうはそれを濃縮して蓄える役割を担っていて、総胆管という管を通って十二指腸に分泌されます。
胆石や胆管がん、膵臓がんなどでこの総胆管が狭くなったり詰まったりすると、胆汁が十分に分泌されなくなり、脂肪の乳化がうまくいかず、リパーゼが効率よく働けなくなり、脂肪吸収不良を起こします。
また、肝硬変などで肝臓の機能自体が著しく低下した場合も、胆汁の生成能力が落ちてしまい、同様に脂肪便の原因となることがあります。
原発性胆汁性胆管炎(PBC)や原発性硬化性胆管炎(PSC)のような自己免疫性の病気も、胆汁の流れを悪くする原因の一つです。
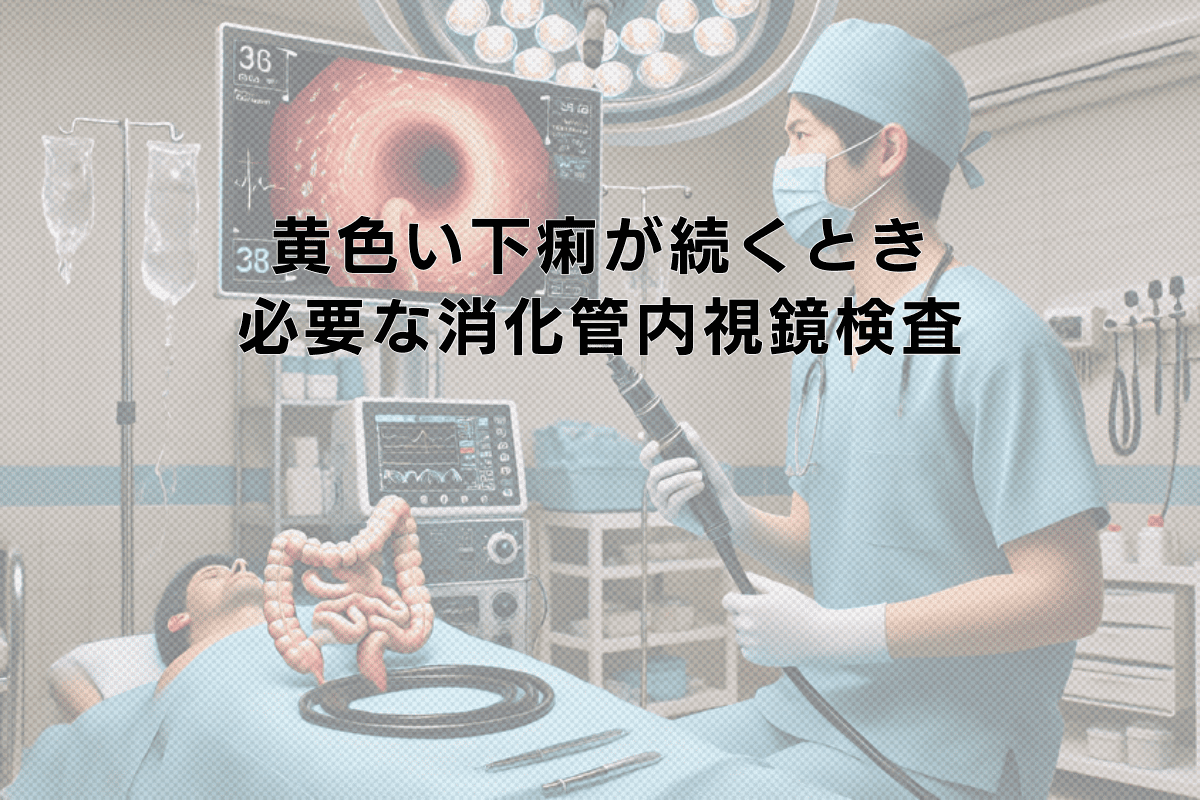
脂肪の消化吸収に関わる臓器の役割
| 臓器 | 主な役割 | 機能低下時の影響 |
|---|---|---|
| 膵臓 | 脂肪分解酵素(リパーゼ)の分泌 | 脂肪が分解されず脂肪便となる |
| 肝臓 | 胆汁の生成 | 脂肪の乳化が不十分になる |
| 胆のう・胆管 | 胆汁の貯蔵と十二指腸への排出 | 胆汁が分泌されず脂肪の乳化が滞る |
小腸の吸収不良
脂肪が適切に分解されたとしても、最終的に吸収する場所である小腸の粘膜に問題があれば、脂肪は体内に取り込まれません。
クローン病やセリアック病のように小腸の粘膜に広範囲な炎症や萎縮が起こる病気、腸管を広範に切除した後(短腸症候群)、あるいは細菌が小腸で異常増殖する状態(小腸内細菌異常増殖症:SIBO)などが原因です。
このような場合、脂肪だけでなく、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど他の栄養素の吸収も同時に障害されることが多く、より複雑で重篤な栄養障害を起こす可能性があります。
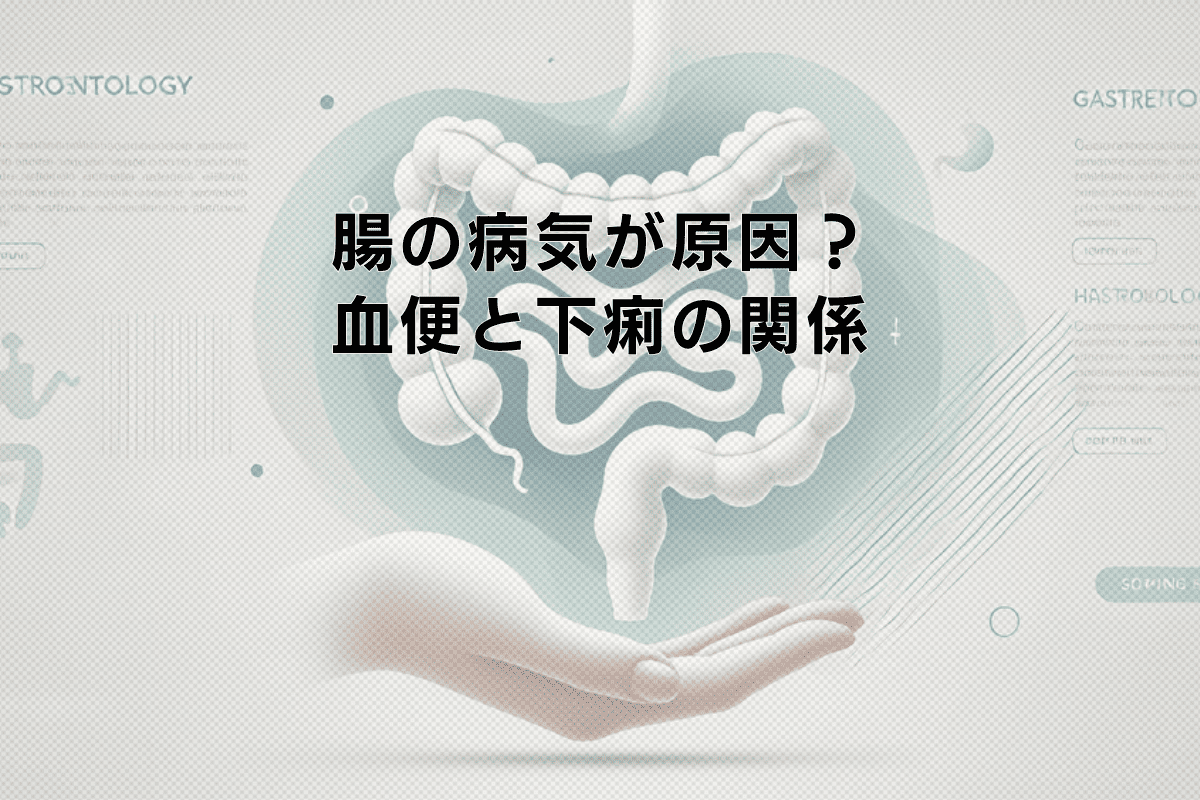
脂肪便に伴うその他の症状
脂肪便と下痢が慢性的に続くと、単にお腹の不調だけでなく、エネルギーや必須栄養素の欠乏により、全身に様々な影響が及び、随伴症状は、診断の手がかりになることもあります。
体重減少と栄養障害
脂肪は1グラムあたり9キロカロリーと、炭水化物やタンパク質の2倍以上のエネルギーを持つ、非常に効率の良いエネルギー源です。
脂肪の吸収が慢性的に妨げられると、食事から得られる総摂取カロリーが大幅に減少し、意図しない体重減少につながります。食事量は変わらない、あるいはむしろ食べているのに痩せていく、という場合は特に注意が必要です。
長期にわたると、タンパク質やビタミン、ミネラルの吸収も悪化し、筋肉量が減少して体力が落ちる(サルコペニア)、疲れやすくなるなど、全身的な栄養障害を招きます。
脂溶性ビタミンの欠乏
ビタミンには水に溶けやすい水溶性ビタミンと、油に溶けやすい脂溶性ビタミンがあります。
ビタミンA、D、E、Kは代表的な脂溶性ビタミンであり、小腸で吸収されるためには、脂肪や胆汁と一緒にミセルという小さな粒子を形成する必要があります。
脂肪吸収不良の状態が続くと、これらのビタミンの吸収も阻害され、欠乏しやすくなり、体に特有の症状を引き起こします。
脂溶性ビタミン欠乏による主な症状
| ビタミン | 主な働き | 欠乏時の症状 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 視力、皮膚や粘膜の健康維持 | 夜盲症(暗い所で見えにくい)、皮膚の乾燥、感染症にかかりやすくなる |
| ビタミンD | カルシウムの吸収促進、骨の健康維持 | 骨軟化症(骨の痛み)、骨粗しょう症、くる病(小児) |
| ビタミンE | 抗酸化作用、細胞の保護 | 神経障害(ふらつき)、筋力低下、溶血性貧血 |
| ビタミンK | 血液凝固作用 | 出血しやすくなる(鼻血、青あざ、けがの血が止まりにくい) |
腹部膨満感や腹痛
消化されなかった脂肪が大腸に達すると、常在している腸内細菌によって分解(発酵)され、この過程でメタンや水素などのガスが大量に発生し、お腹がパンパンに張る感じ(腹部膨満感)や、お腹がゴロゴロと鳴る不快な音の原因となります。
また、脂肪便に伴う下痢は腸のぜん動運動を過剰にするため、お腹が差し込むような、けいれん性の腹痛を伴うことも少なくありません。症状は、食事、特に脂質の多い食事を摂った後に強くなる傾向があります。
医療機関を受診するべきタイミング
脂肪便や下痢は誰にでも起こりうる症状ですが、放置してはいけないケースもあります。どのような場合に専門医に相談すべきか、目安を知っておくことが、病気の早期発見と早期治療につながります。
一過性の症状との見分け方
脂っこい食事をした翌日に一時的に便が緩くなったり、白っぽくなったりすることは珍しくありません。
原因が食事内容であると明確に自覚できており、1〜2日で症状が改善し、他に気になる症状がなければ、まずは食生活を見直しながら様子を見てもよいでしょう。
ただし、特定の食事に関係なく脂肪便や下痢が2週間以上続いたり、一度治まっても何度も繰り返したりする場合は、背景に何らかの病的な原因が隠れている可能性を考え、医療機関の受診を検討してください。
注意が必要な危険なサイン
脂肪便や下痢に加えて、以下のような症状が見られる場合は、より詳しい検査が必要です。膵臓がんや慢性膵炎の悪化、進行した肝疾患など、重篤な病気を示唆している可能性があるので、速やかに消化器内科を受診してください。
速やかな受診を要する症状
- 意図しない持続的な体重減少(例 6ヶ月で5%以上)
- 背中やみぞおちに広がる持続的な痛み(特に食事で悪化する)
- 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)と、濃い色の尿
- 急に糖尿病と診断された、または既存の糖尿病の血糖コントロールが急に悪化した
何科を受診すればよいか
脂肪便と下痢が続く場合は、消化器系の病気が専門である消化器内科または胃腸科を受診するのが最適です。脂肪吸収不良の原因となる膵臓、肝臓、胆のう、小腸といった臓器全体を総合的に診断し、必要な検査や治療を行うことができます。
かかりつけ医がいる場合は、まずはそこで相談し、専門医への紹介状を書いてもらうのも良い方法です。その際は、いつからどのような症状があるのか、具体的に伝えられるように準備しておくと診察がスムーズに進みます。
消化器内科で行う主な検査
消化器内科では、症状の原因を正確に突き止めるために、問診から始まり、血液検査、便検査、画像検査などを段階的に、体系的に行います。
問診と身体診察
診察ではまず詳しい問診を行い、いつから症状があるか、便の状態(色、形、臭い、頻度)、食事内容、飲酒歴(種類、量、期間)、既往歴、服用中の薬(お薬手帳を持参するとよい)、体重の変化、家族の病歴などについて詳しく伝えてください。
特にアルコールの摂取量と期間は、慢性膵炎を診断する上で非常に重要な情報となります。その後、腹部の触診で痛みやしこりの有無、圧痛の場所などを確認したり、黄疸の有無を皮膚や眼で視診したりします。
血液検査と便検査
血液検査では、膵臓から分泌される酵素(アミラーゼ、リパーゼ)の数値を調べて、膵臓に急性の炎症がないかを確認します。
また、肝機能(AST, ALT)や胆道系酵素(γ-GTP, ALP)の数値を調べて肝臓や胆管に異常がないかを確認したり、血中のアルブミン値やコレステロール値から栄養状態を評価したりします。
腫瘍マーカー(CA19-9など)を測定し、膵臓がんなどの悪性疾患の可能性を探ることもあります。
便検査では、便の中の脂肪分を直接調べる検査(便中脂肪染色)や、膵臓の消化機能の客観的な指標となるエラスターゼという酵素を測定する検査を行い、基準値以下に低下している場合、膵外分泌機能不全が強く疑われます。
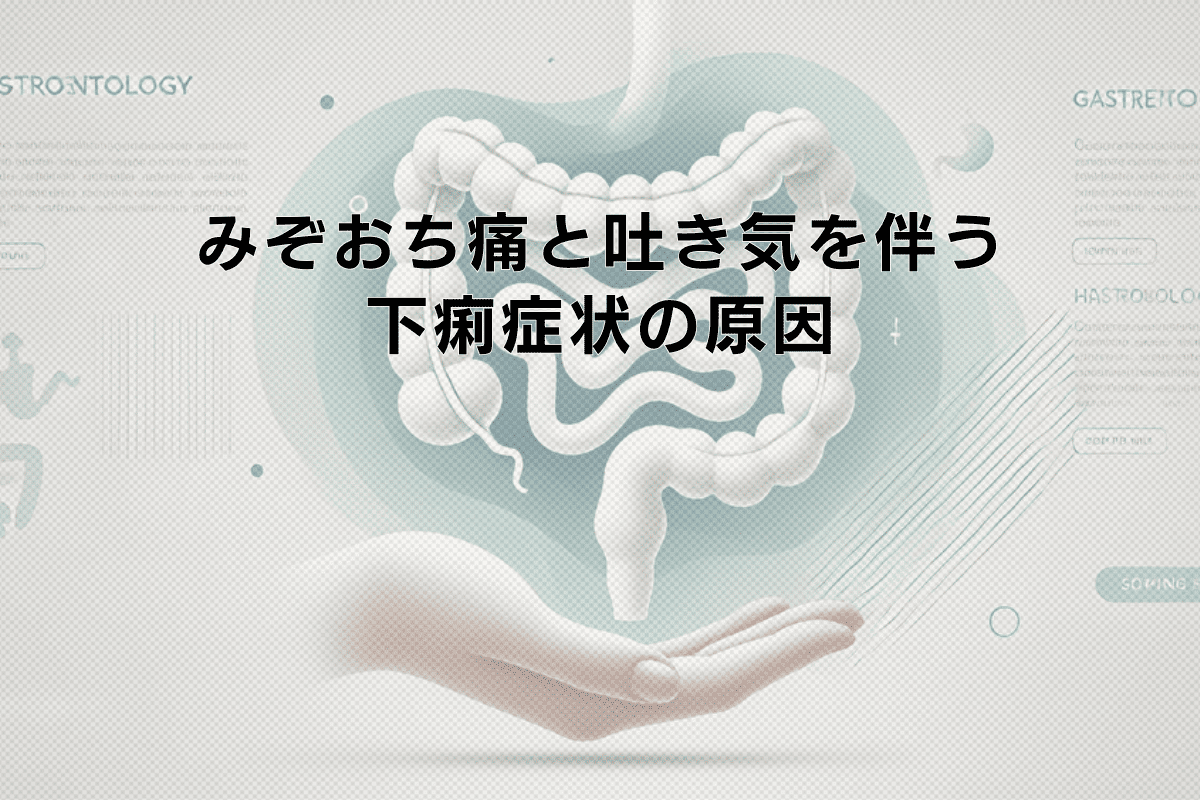
診断に役立つ主な検査
| 検査の種類 | 主な検査項目 | わかること |
|---|---|---|
| 血液検査 | アミラーゼ、リパーゼ、肝胆道系酵素、腫瘍マーカー | 膵臓や肝臓、胆管の異常の有無、栄養状態 |
| 便検査 | 便中脂肪染色、便中エラスターゼ | 脂肪の消化吸収不良の客観的評価、膵機能の評価 |
腹部超音波(エコー)検査
腹部超音波検査は、体に負担なく簡便に行える画像検査の第一選択です。プローブと呼ばれる装置を腹部に当て、超音波を用いて膵臓の形や大きさ、膵管の拡張、膵石の有無、肝臓や胆のう、胆管の状態をリアルタイムに観察します。
慢性膵炎に特徴的な所見や、胆石、腫瘍の存在がわかることがありますが、超音波は空気や骨を透過しにくいため、体格や腸内ガスの影響で膵臓全体を明瞭に観察できない場合もあります。
精密画像検査(CT・MRI・超音波内視鏡)
腹部超音波検査で異常が疑われたり、より詳しい情報が必要だったりする場合には、CTやMRIといった精密な画像検査を行い、検査では、体を輪切りにしたような詳細な画像が得られ、膵臓の内部構造をより客観的に評価できます。
小さな腫瘍や初期の慢性膵炎の変化を描出することが可能です。
特に超音波内視鏡(EUS)は、内視鏡の先端についた超音波装置を胃や十二指腸の中から膵臓に当てるため、体外からの超音波検査よりもはるかに解像度の高い画像が得られ、微細な病変の発見に極めて有用です。
脂肪便と下痢に対する治療方針
治療は、脂肪便と下痢を引き起こしている根本的な原因に対して行います。原因によって治療法は大きく異なりますが、多くの場合、原因疾患の治療、食事療法、薬物療法を組み合わせて症状の改善と栄養状態の維持を目指します。
原因疾患の特定と治療
まず最も重要なのは、背景にある病気を正確に診断し、治療を優先することです。慢性膵炎であれば、病気の進行を抑えるために禁酒が絶対であり、腹痛などの症状をコントロールする薬物療法を行います。
胆石が胆管を塞いでいるのが原因であれば、内視鏡や手術による胆石の除去を検討し、クローン病などの炎症性腸疾患であれば、腸の炎症を抑えるための免疫抑制薬や生物学的製剤による治療が中心となります。
原因となっている病気の活動性をコントロールすることが、脂肪便と下痢を改善させるための大前提です。
食事療法による脂肪摂取量の調整
原因が何であれ、脂肪の消化吸収能力が落ちているため、食事からの脂肪摂取量を制限することが症状緩和の基本となり、1日の脂肪摂取量を20〜30グラム程度に抑えるよう指導することが多いです。
調理法を揚げる・炒めるから、蒸す・茹でる・煮るに変える、肉は脂身の少ない部位を選ぶ、ドレッシングはノンオイルタイプにする、などの工夫が求められます。
ただし、過度な脂肪制限はエネルギー不足や脂溶性ビタミン欠乏を招くため、注意が必要です。
エネルギーを補うために、消化吸収されやすい中鎖脂肪酸(MCTオイル)を食事に取り入れたり、栄養士による専門的な食事指導を受けたりすることも重要になります。
食事療法のポイント
| 項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 脂肪制限 | 1日の脂肪摂取量を20〜30g程度に抑える | 消化管への負担を軽減し、症状を緩和する |
| MCTオイルの活用 | 中鎖脂肪酸をエネルギー源として利用する | 胆汁やリパーゼをあまり必要とせず吸収されやすい |
| 分割食 | 1回の食事量を減らし、食事回数を増やす | 一度に消化する負担を軽くする |
薬物療法による消化吸収の補助
膵臓の機能低下(膵外分泌機能不全)が原因の場合、不足している消化酵素を薬で補う治療(消化酵素補充療法)が非常に有効です。
リパーゼなどの消化酵素を豊富に含む高力価の膵消化酵素薬を、毎食直後に十分な量で服用することで、食物の消化を助け、脂肪便や下痢、腹部膨満感などの症状を劇的に改善させます。
薬を飲むタイミング(食直後)と量を守ることが、効果を最大限に引き出す上でとても大事です。また、胆汁の分泌が不足している場合には、胆汁酸製剤を用いて脂肪の乳化を助けることもあります。
さらに、検査で判明した脂溶性ビタミンなどの栄養素の欠乏に対しては、サプリメントや注射で適切に補充することも大切な治療の一環です。
主な補助的薬物療法
| 薬剤の種類 | 主な働き | 対象となる状態 |
|---|---|---|
| 膵消化酵素薬 | 脂肪、タンパク質、炭水化物の消化を助ける | 膵外分泌機能不全 |
| 胆汁酸製剤 | 脂肪の乳化を助け、吸収を促進する | 胆汁分泌不全 |
| ビタミン製剤 | 不足している脂溶性ビタミンを補充する | 脂溶性ビタミン欠乏症 |
脂肪便と下痢が続くことに関するよくある質問
- 脂肪便は食事を変えれば自力で治せますか。
-
脂っこいものを食べ過ぎた後の一時的な脂肪便であれば、数日間、消化の良い食事を心がけることで自然に改善することがほとんどです。
しかし、食事内容に関わらず脂肪便や下痢が慢性的に続く場合は、膵臓や肝臓、小腸などに何らかの病気が隠れている可能性があり、この場合、食事療法だけで根本的な原因を治すことはできません。
食事の工夫は症状を和らげる上で大切ですが、まずは最寄りの医療機関を受診して原因を正確に診断してもらい、治療を受けることが重要です。
- アルコールを飲まなくても膵臓の病気になりますか。
-
慢性膵炎の最も多い原因は長年のアルコール多飲ですが、アルコールを全く飲まない人でも発症することがあります。
胆石が原因となる場合や、原因がはっきりしない特発性、遺伝的な要因、自己免疫の異常によって起こる自己免疫性膵炎などがあります。また、膵臓がんは飲酒習慣の有無にかかわらず誰にでも起こりうる病気です。
脂肪便や下痢、背中の痛みといった症状がある場合は、飲酒習慣がないからといって膵臓の病気を否定せず、専門医に相談してください。
- 検査には入院が必要ですか。
-
ほとんどの検査は外来で行うことが可能で、問診や身体診察、血液検査、便検査、腹部超音波検査はすべて外来で実施します。CTやMRIといった精密画像検査も通常は入院の必要はありません。
超音波内視鏡や内視鏡的逆行性胆管膵管造影のような、体への負担が少し大きい内視鏡検査の場合は、鎮静剤を使用することや検査後の偶発症のリスクを考慮して、日帰り入院や一泊程度の短期入院を勧める施設もあります。
- 治療を始めたら食事の制限はずっと続きますか。
-
膵外分泌機能不全に対して消化酵素補充療法が非常に効果的であった場合、症状が改善すれば、脂肪制限をある程度緩和できる可能性があります。
しかし、慢性膵炎のように病気自体が進行性で、膵臓の機能が元に戻らない場合、膵臓を休ませて病気の進行を抑えるために、ある程度の食事制限や禁酒は生涯にわたって必要になることが多いです。
治療の目標は、症状をコントロールし、良好な栄養状態を維持しながら、可能な限り生活の質を高めることで、治療方針については、定期的に医師と相談しながら、ご自身の状態に合わせて調整していくことになります。
次に読むことをお勧めする記事
【下痢と栄養吸収障害の関係|内視鏡検査による腸管機能の評価】
脂肪便と下痢について読んで、『栄養がうまく吸収されていないとどうなるのか』と思った方もいらっしゃるのでは?栄養吸収障害の詳しいメカニズムと、内視鏡検査による腸管機能の評価方法について分かりやすく解説しています。
【黄色い下痢が続くときに必要な消化管内視鏡検査】
便色の変化は胆道・膵の病気と関係することがあります。色の手がかりと検査の選び方を合わせて知ると、全体像がつながります。
以上
参考文献
Nakamura T, Takebe K, Kudoh K, Ishii M, Imamura KI, Kikuchi H, Kasai F, Tandoh Y, Yamada N, Arai Y, Terada A. Steatorrhea in Japanese patients with chronic pancreatitis. Journal of gastroenterology. 1995 Jan;30(1):79-83.
Nakamura T, Takeuchi T. Pancreatic steatorrhea, malabsorption, and nutrition biochemistry: a comparison of Japanese, European, and American patients with chronic pancreatitis. Pancreas. 1997 May 1;14(4):323-33.
Nakamura T, Tando Y, Yamada N, Watanabe T, Ogawa Y, Kaji A, Imamura KI, Kikuchi H, Suda T. Study on pancreatic insufficiency (chronic pancreatitis) and steatorrhea in Japanese patients with low fat intake. Digestion. 1999 Feb 1;60(Suppl. 1):93-6.
NAKAMURA T, SUDA T, KON M. Pathophysiology and treatment of diabetic diarrhea. Journal of Smooth Muscle Research. 1996;32(2):27-42.
Ihana-Sugiyama N, Nagata N, Yamamoto-Honda R, Izawa E, Kajio H, Shimbo T, Kakei M, Uemura N, Akiyama J, Noda M. Constipation, hard stools, fecal urgency, and incomplete evacuation, but not diarrhea is associated with diabetes and its related factors. World journal of gastroenterology. 2016 Mar 21;22(11):3252.
Nakamura T, Tando Y, Terada A, Watanabe T, Kaji A, Yamada N, Suda T. Can pancreatic steatorrhea be diagnosed without chemical analysis?. International journal of pancreatology. 1997 Oct;22(2):121-5.
GOLDSTEIN F, Wirts CW, KOWLESSAR OD. Diabetic diarrhea and steatorrhea: Microbiologic and clinical observations. Annals of Internal Medicine. 1970 Feb 1;72(2):215-8.
Hofmann AF, Poley JR. Role of bile acid malabsorption in pathogenesis of diarrhea and steatorrhea in patients with ileal resection: I. Response to cholestyramine or replacement of dietary long chain triglyceride by medium chain triglyceride. Gastroenterology. 1972 May 1;62(5):918-34.
Ulshen MH. Diarrhea and steatorrhea. Primary pediatric care (4th ed., pp. 1020-1033). St. Louis, MO: Mosby. 2001.
Goldstein F, Cozzolino HJ, Wirts CW. Diarrhea and steatorrhea due to a large solitary duodenal diverticulum: Report of a case. The American Journal of Digestive Diseases. 1963 Nov;8(11):937-43.