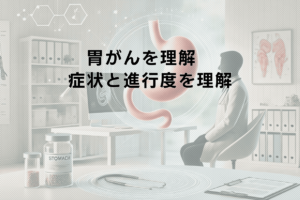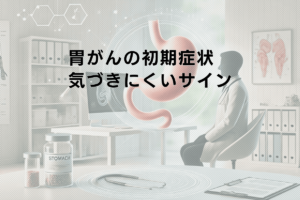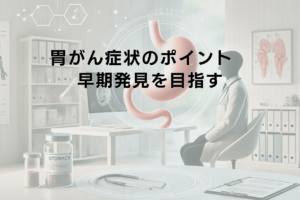胃がんは日本で比較的多くみられる病気の1つであり、発生にはピロリ菌感染や生活習慣が深く関わるといわれています。
近年は内視鏡検査(胃カメラ)による早期発見や定期的な検診の受診が呼びかけられ、治療成績の向上が期待されていますが、初期段階では自覚症状が乏しいことが多いです。
そのため、胃がんの原因やリスク、検査方法、治療法、そして予防策について理解を深めることは、胃やほかの消化器の健康を考えるうえで非常に重要です。
ここでは、胃がんの原因とされるピロリ菌や生活習慣の影響、検査や治療、さらに日常生活でできる予防の取り組みなどを詳しく紹介しながら、大腸や食道を含めた消化器全体との関係についても触れていきます。

胃がんとは
胃がんは、胃の粘膜を構成する細胞が変化し、異常な増殖を続けることで発生する病気です。日本を含むアジア諸国では患者数が比較的多く、喫煙や塩分を多く摂る食事、そしてピロリ菌感染などが大きな要因と考えられています。
多くの場合、粘膜の表面からゆっくりとがんが進行し、治療を行わないまま放置すると、リンパ節やほかの臓器(肝臓や肺など)への転移につながるリスクが高まります。
胃がんの基本的な特徴
胃がんは、早期段階では自覚症状が目立たないことが多いので、健康診断や検診での胃カメラやバリウム検査を受けないと、知らないうちに進行している場合があります。
初期の段階では痛みや不快感がなくても粘膜に変化が起こっていることがあるため、「まだ症状がない=大丈夫」と決めつけてしまうのは危険です。
粘膜から始まる異常な細胞増殖
胃がんは胃の粘膜細胞ががん化して発生し、そこから深い層へと浸潤していきます。
粘膜は胃酸などの刺激から胃を守る組織ですが、ピロリ菌などによる慢性的な炎症や塩分の過剰摂取、喫煙などが粘膜にダメージを与え、異常な細胞増殖のきっかけになりやすいです。
粘膜内にとどまっている段階を早期胃がんと呼びます。発生箇所がある程度限局していることで内視鏡治療による切除が期待できますが、進行すると治療も難しくなります。
感染・遺伝・生活習慣の影響
胃がんの原因にはピロリ菌感染が代表的ですが、ほかにも塩分の摂りすぎや喫煙、飲酒をはじめとする生活習慣の乱れ、また家族内に胃がんの罹患者が多い場合は遺伝的な影響が疑われることもあります。
食道や大腸などの消化器系にがんが発生した経験がある方も、胃がんリスクが一般より高い可能性が指摘されています。
胃がんに関する主なデータ
下の表では、日本における胃がんの特徴的な統計情報を紹介します。
日本における胃がん
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 罹患者数 | 男性のほうがやや多いが、女性も決して少なくない |
| 好発年齢 | 50歳以上で増加傾向 |
| 主な原因 | ピロリ菌、塩分過多、喫煙など |
| 早期発見の重要性 | 転移を防ぎ、内視鏡治療の可能性を高める |
| 定期的な検診 | 胃カメラやバリウム検査などを定期的に受ける |
胃がんが発生する原因
胃がんは特定の原因だけで起こるわけではなく、複数の要因が絡み合って発生し、ピロリ菌が大きく関わることは有名ですが、日常の生活習慣が複合的に影響することも無視できません。
ピロリ菌感染の役割
ピロリ菌は胃の粘膜に感染し、慢性胃炎や胃潰瘍を引き起こすことで知られています。長期間にわたって粘膜に炎症を起こすと細胞に異常が生じやすく、がんが発生する確率が高まります。
ピロリ菌の除菌治療を受けることで胃がん発生リスクを低減できるとされており、特に早期の段階で予防を考える人は検査で感染の有無を調べることが大切です。
塩分過多や喫煙、飲酒
食事の塩分量が高い食文化を持つ日本では、塩辛い食品を好んで食べる人が少なくありません。
塩分の過剰摂取は胃の粘膜を弱らせ、炎症を起こしやすくします。また、喫煙や過度の飲酒も粘膜を傷つけ、細胞の異常を誘発しやすくなります。
こうした生活習慣が日常的に続くと、胃がんをはじめ大腸がんや食道がんのリスクも高まるため注意が必要です。
遺伝的素因と環境因子
家族に胃がんの患者が多いと、同じような食生活を送っていることに加え、遺伝的な要因が重なることで罹患リスクが高くなる場合があります。
ただし、影響は個人差が大きいため、環境因子(食生活やストレスなど)の改善が罹患率低減につながることもあります。
ストレスとの関係
ストレスが直接的に胃がんの原因になるわけではありませんが、強いストレス状態は胃酸分泌の乱れや食欲不振などを招きやすく、粘膜が傷つく一因です。ストレスが原因で生活習慣が乱れれば、結果的にがんリスクが高まる可能性があります。
胃がんの主な原因
| 原因・要因 | 内容 |
|---|---|
| ピロリ菌感染 | 慢性胃炎を起こし、細胞異常を誘発しやすくする |
| 塩分過多 | 胃粘膜へのダメージを増やしがんの発生を促進 |
| 喫煙・飲酒 | 粘膜細胞への負荷が高まり変異が起こりやすくなる |
| 遺伝的素因 | 家族内で同一疾患が多い場合は発症リスクが高い場合がある |
| ストレスや生活習慣 | 胃酸過多や食欲不振を引き起こし、間接的に粘膜を傷つける可能性がある |
| 加齢 | 年齢が上がると細胞の修復能力が低下し、がん化リスクが増える |
胃がんのリスク因子
胃がんを引き起こす原因と密接に関わるものとして、「リスク因子」が挙げられます。この「リスク因子」を把握することにより、自身の生活習慣をどのように見直すべきか明確になります。
加齢と性差
加齢は胃がんのリスクを高める要素の1つで、特に50歳以上で発症率が上がるため、この年代以降は定期的な検診を受ける意義が増します。
また、男性のほうが胃がんの発症率は高めですが、女性だからといって油断できるわけではありません。女性でも塩分の多い食事や喫煙、飲酒などの習慣がある場合はリスクが上がります。
食事と環境
大腸がんや食道がんをはじめとする消化器系のがん全般にいえることですが、脂質や塩分に偏った食生活は細胞に負担をかけやすく、野菜や果物の摂取が少なく、加工食品を多く摂る人は注意が必要です。
また、ピロリ菌感染は、幼少期にピロリ菌に汚染された井戸水の摂取などで感染することが多く、環境の要因も大きいです。
胃がん以外のがん歴
過去に他の臓器(大腸、食道、肺など)でがんを発症したことがある人は、全身的にがんが発生しやすい体質になっている可能性があります。
そのため、胃がんに限らず新たながんの発見につながるよう、定期的な検査を行うことが望ましいです。
リスク因子の重なり
ピロリ菌感染があるうえに喫煙習慣が長い、あるいは塩分の高い食生活を何十年も続けてきたなど、複数のリスク因子が重なるほど胃がんになる可能性が増します。特に高齢者でリスク因子が多い場合は、治療や予後にも影響が出やすいです。
胃がんリスク因子の重なり具合
| リスク因子(例) | 重複数が少ない場合 | 重複数が多い場合 |
|---|---|---|
| ピロリ菌のみ | リスクがある | 他の因子との重複でより高まる |
| ピロリ菌 + 塩分過多 | リスク増大 | 大きなダメージを受けやすい |
| 喫煙 + 飲酒 | 胃だけでなく他のがんリスクも上昇 | |
| 年齢 + ピロリ菌 + 喫煙 | 非常にリスク高 | 早期発見が極めて重要 |
胃がんの症状と進行度の特徴
胃がんの症状は進行度によって大きく異なります。初期段階ではほぼ自覚症状がありませんが、進行してくると胃痛や体重減少、吐き気、黒色便(血便)、みぞおちの痛みなどが現れることがあります。
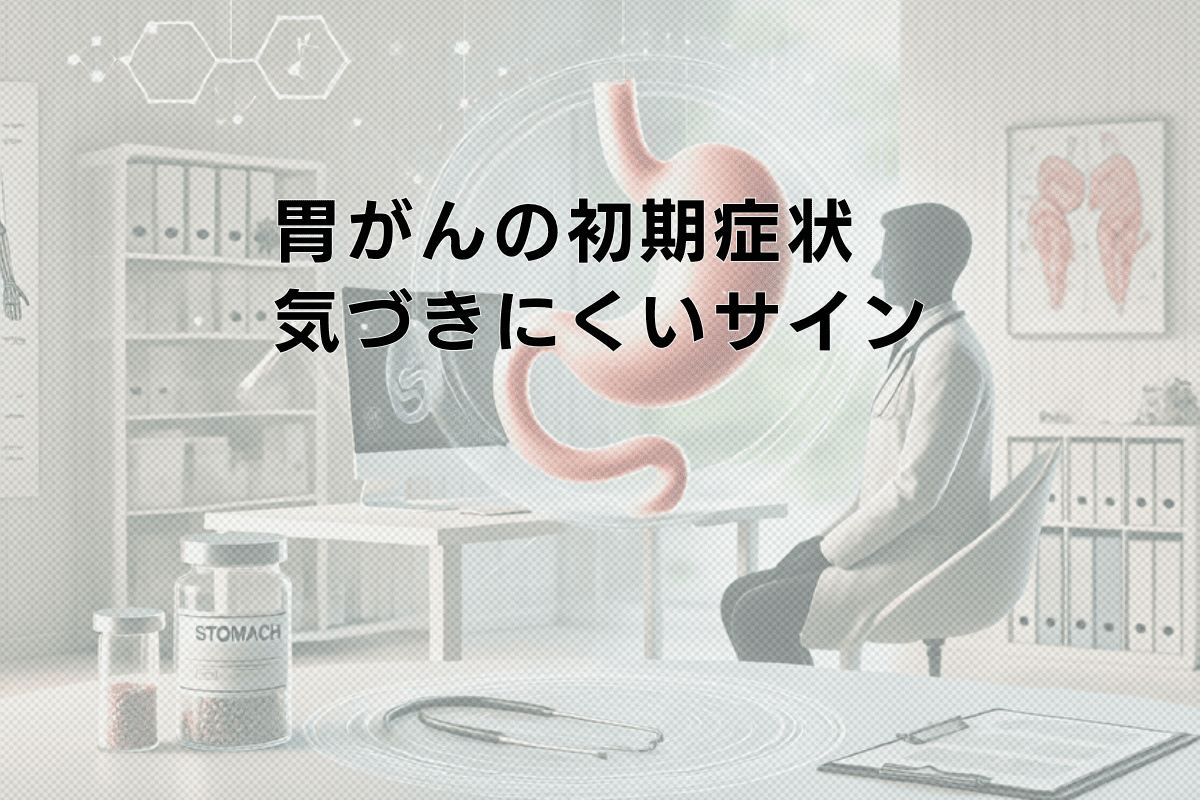
初期症状
初期の胃がんは、体の異常を感じにくいことが特徴で、多少の胃もたれや軽いむかつき程度であることが多く、普段から慢性胃炎などに慣れている人ほど見過ごしやすいです。
進行した場合に起こりやすい症状
がんが進行してくると、以下の症状が目立つようになります。
- 食欲不振や体重減少
- みぞおち周辺の痛みや不快感
- 吐き気や嘔吐、胸焼け
- 血便や黒色便
これらはほかの病気でもみられる症状ですが、長期間続く場合は胃がんを念頭に置いて受診する必要があります。
スキルス胃がんの特徴
スキルス胃がんは、粘膜の下層でがんが増殖し、全体的に広がりやすいタイプの胃がんです。浸潤性が高く、進行速度が速い傾向があり、典型的な初期症状が出にくいため、気づいたときにはかなり進行していることも珍しくありません。
症状進行度と体への影響
がんが深い層へ浸潤すると、リンパ節や血流、さらには腹腔内へ転移するリスクが高まり、転移が起きると治療範囲が大きくなり、外科手術だけで完治を目指すのは難しくなります。
進行度による症状の目安
| 進行度 | 症状の傾向 | 主な影響 |
|---|---|---|
| 早期 | 自覚症状がほぼない | 内視鏡切除の可能性が高い |
| 中期 | 体重減少、胃痛、食欲不振、胸焼け | リンパ節転移のリスク上昇 |
| 進行期 | 強い痛み、嘔吐、黒色便、貧血、倦怠感 | 腹腔内・他臓器へ転移しやすい |
| 末期 | 全身衰弱、継続的な出血や激痛 | 治療は化学療法や緩和ケアが中心になる |
胃がんの検査と診断方法
胃がんが疑われる場合や早期発見を目的とする場合には、内視鏡検査やバリウム検査などさまざまな手法があります。
検査手段ごとに特徴があるため、自分に合った方法を選択することが大切ですが、一般的には「精度の高さ」や「組織採取の可否」を考慮すると内視鏡検査が選ばれることが多いです。
内視鏡検査(胃カメラ)
胃カメラとも呼ばれる内視鏡検査では、口または鼻から細いカメラを挿入し、直接胃の粘膜を観察し、必要に応じて組織を一部採取し、生検を行うことで確定診断することができます。微小な病変を見逃しにくく、早期発見の面で非常に有用です。

バリウム検査
X線検査の一種で、バリウムと発泡剤を飲んで胃の形態を調べ、がんの凹凸や潰瘍の有無を全体像として確認しやすい一方、微細な変化を見落とす可能性は内視鏡検査より高いです。
胃カメラに抵抗がある場合や、健康診断の簡易的なチェックとしてよく用いられます。
超音波検査・CT検査など
超音波検査やCT検査、さらにはPET検査などで胃周辺組織の状態を詳しく評価します。また、CT検査、PET検査は広い範囲を撮影できるため、転移の有無を調べる際に有用です。
検査を受ける頻度と注意点
胃がんに限らずがん検診の受診は継続が大切です。ピロリ菌感染がある場合や、過去に胃炎・胃潰瘍を繰り返した経験がある方、喫煙や塩分過多の食生活を続けている方は、主治医と相談しながら受診間隔を決めてください。

主な検査方法と特徴
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検査 | カメラで直接粘膜を観察し、生検が可能 | 早期発見に優れる、生検で確定診断可 | 不快感や痛みがある、時間がかかる場合もある |
| バリウム検査 | 胃全体の形状や大きな潰瘍・腫瘍の有無をX線で確認 | 検診で受けやすい、費用が比較的安い | 微小病変を見落としやすい、生検ができない |
| 超音波検査 | 胃周囲やリンパ節の状態を音波で観察 | 体への負担が少ない | 胃内部の詳細把握には不向き |
| CT検査 | 広範囲にわたる撮影が可能 | 転移の確認などに役立つ | 被ばくがある、造影剤使用時はアレルギーリスクあり |
| PET検査 | がん細胞の活動性をチェック | 全身のがんを調べられることがある | 施設が限られ、費用が高め |
胃がんの治療と予防
胃がんの治療は、内視鏡治療から外科手術、化学療法など多岐にわたり、胃がんが発見されたタイミング、ステージ(病期)、がんの型などによって最適な治療法は異なります。
内視鏡治療
早期発見によってがんが粘膜内や粘膜下層にとどまっている場合、内視鏡を使った切除が有力な選択肢になります。
リンパ節への転移がないと考えられる段階であれば、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などでがん病変を除去でき、入院期間や体への負担も比較的軽めです。

外科手術
進行がんで内視鏡治療が難しい場合は、腹腔鏡や開腹による部分切除や胃全摘といった外科的治療が検討され、リンパ節の郭清(切除)も同時に行い、転移を最小限にとどめることを目指します。
手術範囲が大きいほど術後の体力低下や食事制限が必要になるため、早期の段階での発見が重要です。
化学療法
進行がんや手術後の再発予防などを目的として、抗がん剤などの化学療法を行うことがあり、併用療法によってがん細胞の増殖を抑え、延命効果や再発率低下を期待します。
予防策と検診の大切さ
胃がんを予防するには、まずピロリ菌の有無を確認して感染していれば除菌することが挙げられます。さらに、塩分を控えめにし、野菜や果物をバランスよく摂る食生活に加え、喫煙や過度の飲酒を避けることが大切です。
また、定期的な内視鏡検査やバリウム検査を受けることで、早期発見につなげることを目指します。
胃がん治療法
| 治療法 | 適応段階 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 早期がん、転移が疑われない | 体への負担が少ない |
| 外科手術 | 進行がん | がん部分とリンパ節を切除して根治を図る |
| 化学療法 | 進行がん、再発予防 | 薬剤でがん細胞の増殖を抑える |
| 放射線治療 | 状況に応じて併用 | 局所的にがん細胞へダメージを与える |
| 緩和ケア | 痛みや症状の軽減 | 末期がんで患者のQOL向上を重視 |
日常生活で気をつけたいこと
胃がんを予防し、再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが必要です。あらゆる消化器系がんは生活習慣と深くかかわるため、食事やストレス管理など総合的な取り組みが求められます。
食事のポイント
- 塩分控えめの食事(漬物、塩辛、干物などに注意する)
- 野菜や果物を多く摂取し、ビタミンや食物繊維を補給する
- 偏りのない栄養バランスを心がけ、加工食品ばかりに頼らない
禁煙・節酒
喫煙は胃だけでなく大腸がんや肺がんなど、多くのがんリスクを高める要因です。過度の飲酒も同様に注意が必要で、連日の大量飲酒は胃や食道の粘膜に大きな負担をかけます。
ストレスと上手につきあう
強いストレス状態は食欲や消化機能に影響を与え、胃の粘膜にダメージを与えやすくなります。適度に運動し、十分な睡眠を確保しながら、休息をとることを意識するのが大切です。
定期的な検査の受診
自覚症状がなくても定期的に検診や健康診断を受ける習慣が大切です。特にピロリ菌感染が疑われる方や、家族歴のある方、過去に胃炎や大腸がんを経験した方は積極的な受診を心がけましょう。
日常生活で取り入れたい習慣
| 項目 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 食事 | 野菜中心のメニュー、塩分を少なめに調理 |
| 喫煙習慣 | 禁煙外来やサポートを利用し、できるだけ禁煙を目指す |
| 飲酒 | 飲む量と頻度をコントロールし、節酒を習慣に |
| ストレス | 運動や趣味を取り入れ、適度に発散する |
| 検診 | 胃カメラやバリウム検査、血液検査を定期的に受ける |
大腸・食道など他の消化器との関連
胃は単独の臓器として働くわけではなく、食道から大腸までつながる消化管の中の1部です。胃がんをはじめとする病気が進行しているときは、ほかの臓器への影響や合併症にも目を向けることが必要です。
食道がんとの関わり
飲酒や喫煙、塩分の高い食生活は胃がんだけでなく食道がんにも影響し、さらに、バレット食道と呼ばれる状態がある方は、食道にがんが発生するリスクが上がることが報告されています。
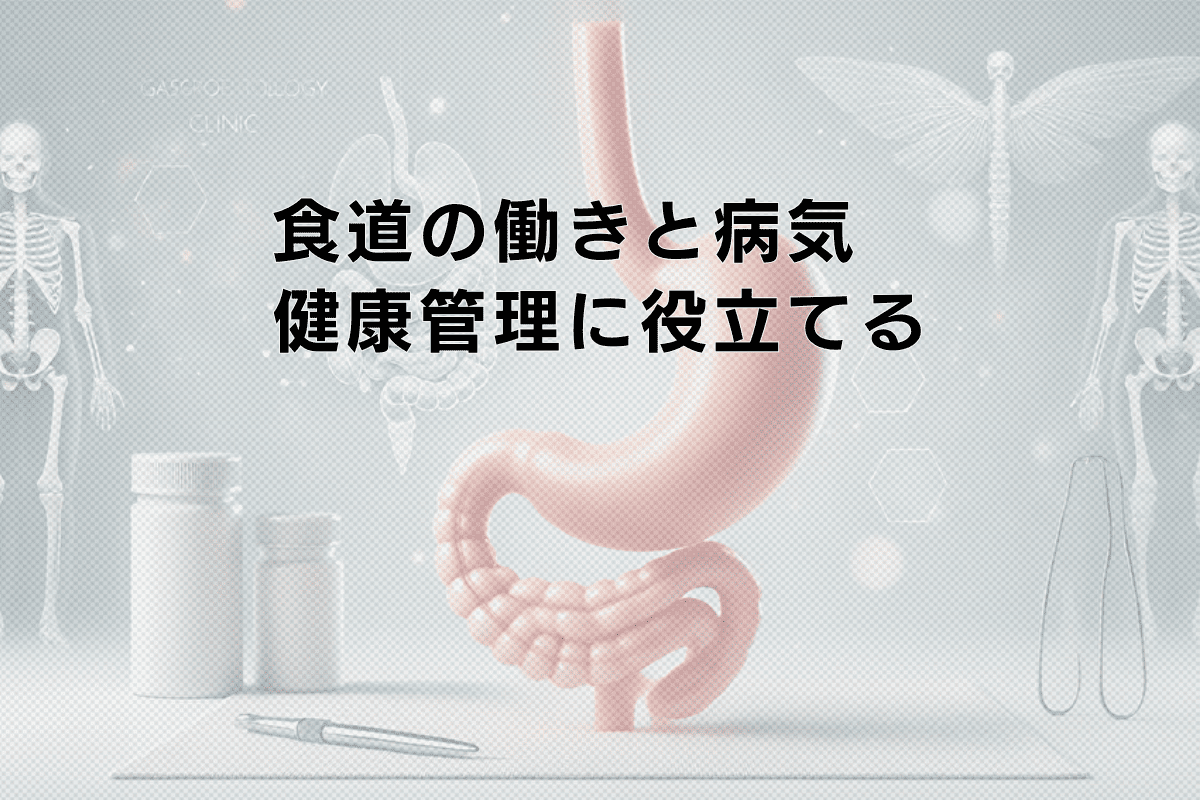
大腸がんのリスク
大腸がんも日本で発症率が高いがんの1つで、高脂肪・高塩分の食事や喫煙、肥満などが大腸がんのリスクを高めるとされており、胃がんと共通する生活習慣が多くあります。
胃や腸は連動して栄養吸収に関わるため、どちらかにトラブルを抱えていると全身の健康状態が影響を受けやすいです。

胃がん治療の影響
胃を部分的に切除した場合、その後の消化機能が低下しやすくなり、食道や大腸などほかの消化器にも負担がかかりやすく、栄養バランスが崩れたり便通に影響が出たりする可能性があります。
早期発見の重要性と検診のすすめ
胃がんに限らず、がんは早期発見ができれば治療の選択肢が広がり、完治を目指せる可能性が高まります。自覚症状に頼るのではなく、定期的な検診を受けることが何よりも大切です。
早期発見がもたらす利点
- 内視鏡による切除など比較的負担の軽い治療で済む
- リンパ節転移の可能性が低く、再発リスクを下げられる
- 体力的・経済的負担が少なく、社会復帰が早い
がん検診の種類
自治体や職場で行う健康診断の中には、胃カメラやバリウム検査が含まれていることがあります。人間ドックではさらに詳細な検査を受けられる場合もあり、リスク因子が高い人ほど積極的に検査メニューを追加することをおすすめします。
健診を受ける頻度
ピロリ菌感染が確認されている人や、胃潰瘍・胃ポリープがある人、または家族歴がある人などは、医師と相談して定期的な健診計画を立てると良いです。
通常は年1回~2年に1回程度の内視鏡検査が理想とされますが、個々のリスクに応じて調整します。
受診時のポイント
検査に際しては空腹の時間や生活習慣の制限があることが多く、指示に従わなければ検査結果に影響が出てしまうため、事前の準備をきちんと行うことが重要です。
胃がん検診を受けるタイミング
| 対象者 | 推奨頻度 | 理由 |
|---|---|---|
| ピロリ菌感染が確認された方 | 年1回 | リスクが高く、早期発見が特に重要 |
| 家族に胃がん患者がいる方 | 年1回~2年に1回 | 遺伝的・環境的な影響を考慮 |
| 過去に胃炎やポリープがある方 | 年1回 | 新たな病変の発生リスクが上昇 |
| 胃痛や胸焼けが慢性的な方 | 症状に応じて医師と相談 | 現在の症状ががん以外の異常かも判断必要 |
| 特に自覚症状がない健康な方 | 2年に1回程度 | 早期発見や予防のため |
まとめ
胃がんは原因が多岐にわたり、ピロリ菌の感染、塩分の過剰摂取、喫煙や飲酒などの生活習慣、さらには遺伝的要因が複雑に絡み合って発生します。
初期段階でははっきりした症状がなく、気づいたときには進行している例も珍しくありません。胃カメラやバリウム検査などの検査手段を上手に活用し、定期的な受診を習慣化することが早期発見につながります。
治療は内視鏡治療から外科手術、化学療法まで幅広く、病期やがんの特徴によって選択肢は異なりますが、どの治療でも早い段階でがんを見つけるほど体への負担が軽くなり、予後も良好になる可能性が高まります。
予防の面では、ピロリ菌除菌や塩分控えめの食生活、禁煙、適度な飲酒にとどめるなどの対策が大切です。
大腸や食道を含む他の消化器官のがんにも通じる話ですが、結局のところ、胃がんも「生活習慣」と「定期的な検診」が大きな鍵になります。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
胃がんについて理解が深まったところで、同じように生活習慣が関わる大腸がんの検査についても知っておくと、より包括的な健康管理ができます。
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
胃がんについて学んだ方には、消化器官全体の働きと内視鏡検査の知識も合わせて持っていただくと、より総合的な理解ができます。
参考文献
Van Cutsem E, Sagaert X, Topal B, Haustermans K, Prenen H. Gastric cancer. The Lancet. 2016 Nov 26;388(10060):2654-64.
Hartgrink HH, Jansen EP, van Grieken NC, van de Velde CJ. Gastric cancer. The Lancet. 2009 Aug 8;374(9688):477-90.
Crew KD, Neugut AI. Epidemiology of gastric cancer. World journal of gastroenterology: WJG. 2006 Jan 1;12(3):354.
Cheng XJ, Lin JC, Tu SP. Etiology and prevention of gastric cancer. Gastrointestinal tumors. 2016 Feb 12;3(1):25-36.
Rugge M, Fassan M, Graham DY. Epidemiology of gastric cancer. Gastric cancer: principles and practice. 2015:23-34.
Correa P. Gastric cancer: overview. Gastroenterology Clinics of North America. 2013 Jun;42(2):211.
Smyth EC, Nilsson M, Grabsch HI, van Grieken NC, Lordick F. Gastric cancer. The Lancet. 2020 Aug 29;396(10251):635-48.
Roder DM. The epidemiology of gastric cancer. Gastric cancer. 2002 Dec;5:5-11.
Thrift AP, El-Serag HB. Burden of gastric cancer. Clinical gastroenterology and hepatology. 2020 Mar 1;18(3):534-42.
Strong VE. Progress in gastric cancer. Updates in surgery. 2018 Jun;70:157-9.