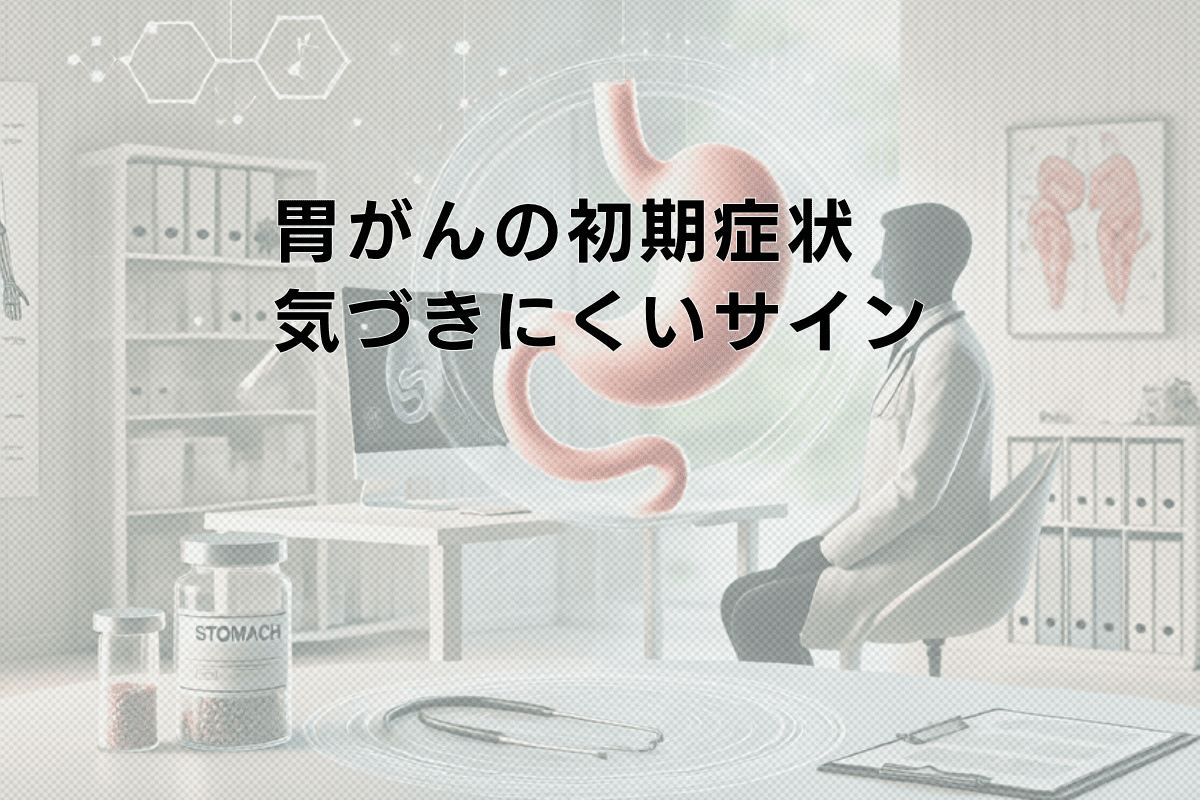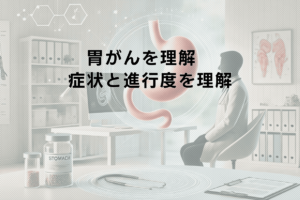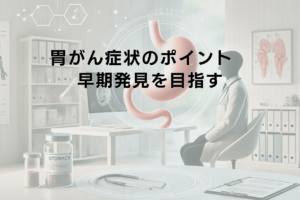胃がんは日本人に多い病気の1つであり、特に初期の段階でははっきりとした症状が現れにくいです。
みぞおちの不快感や軽い食欲不振が続いていても、日常生活のストレスや胃炎と勘違いして放置してしまうケースが少なくありません。
しかし、早い段階で異変に気づいて適切な検査を受ければ、内視鏡による切除など体への負担が軽減される治療を選べる可能性も高まります。
この記事では、胃がん初期の特徴的な症状や原因、検査の種類、そして日々の生活の中で留意しておきたいポイントを詳しく説明します。
胃がんとはどのような病気なのか
胃がんとは、胃の内側を覆う粘膜の細胞が異常増殖し、悪性腫瘍を形成した状態のことです。
胃は食物を受け取り消化を進める臓器であり、その粘膜は外部からの刺激を日々受け続けるため、がんを含むさまざまな疾患が発生しやすいといわれています。
なぜ日本人に多いのか
日本は世界的にも胃がんの罹患率が高い国として知られていますが、ヘリコバクター・ピロリ菌(ピロリ菌)感染率の高さやピロリ菌の東アジア型CagAというたんぱく質が深く関係しています。
また、塩分を多く含む食べ物の過度の摂取、喫煙や飲酒、ストレスが蓄積する生活も原因です。
胃がんができる仕組み
胃粘膜の細胞に何らかの異常が生じて分裂が活発化し、周囲の正常組織を浸潤したり、リンパ節や遠隔臓器に転移したりして広がるのががんの一般的なメカニズムです。
初期段階では粘膜層にとどまり、症状がほとんど出ないケースが多いですが、進行すると他の臓器に転移する可能性が高まります。
大腸がんや食道がんとの違い
同じ消化器系のがんとして大腸がんや食道がんがありますが、部位によって症状やリスク因子、治療法も異なります。例えば大腸がんでは便秘や血便が初期症状になりやすいのに対し、胃がんは吐き気やみぞおちの痛みなどが中心になります。
疑わしい症状がある場合には自己判断せず、医療機関の消化器内科や内視鏡検査を行うクリニックを受診すると安心です。
胃がんと大腸がん・食道がんの一般的な初期症状
| 種類 | 初期症状の例 | 主な検査方法 |
|---|---|---|
| 胃がん | 食欲不振、軽いみぞおちの痛み、吐き気 | 胃カメラ(内視鏡検査)、バリウム検査 |
| 大腸がん | 血便、便秘・下痢、腹痛 | 大腸内視鏡検査、便潜血検査 |
| 食道がん | 食べ物がつかえる感覚、胸やけ | 内視鏡検査 |
初期の胃がん症状とはどのようなものか
胃がんの初期症状は、はっきりした痛みや吐血といった明確な異変が少なく、さりげない体調不良として表れることが多いため、「大したことはない」「疲れているだけ」と判断してしまう人がいますが、症状が続く場合は注意が必要です。
みぞおちの違和感や痛み
みぞおち付近に不快感があったり、食事の量が減っているにもかかわらず胃が張った感じがあるケースは少なくありません。
胃の粘膜に小さながん細胞ができたとしても、最初のうちは痛みがさほど強く出ないこともあり、実際に内視鏡検査を受けないとわからない場合が多いです。
食欲不振や吐き気
食欲不振や吐き気が数日から1週間程度で治まるなら、一過性の体調不良かもしれませんが、2週間以上続くようであれば、消化器の病気や胃がんを疑い、早めに診療を受けることが賢明です。
特有の初期症状はないといわれることが多いですが、ささいな体調の変化を見逃さないよう心がけると早期発見につながります。
黒色便や貧血
胃がんの初期段階でも、粘膜がただれたり血管に近い部分にがんができたりすると、少量の出血が起こることがあり、出血した血液は胃酸によって黒く変色し、便として排泄される際に黒色便(タール便)が見られます。
ただし、黒色便は鉄分の多い食べ物を食べても起こる場合があり、自己判断は禁物です。
体重減少や倦怠感
体重が徐々に減ってきたり、全身の倦怠感が続いたりするのは胃がんだけに限りませんが、いくつもの症状が重なる場合はリスクを考えたほうがいいでしょう。
胃の働きが低下して食事量が減るほか、がんが進行して栄養をとられてしまう結果としても体重が落ちることがあります。
初期に見られることがあるサイン
- みぞおちの違和感・重い感じ
- 胃もたれや少量の食事で満腹感がある
- なんとなく食欲がわかない
- 微妙な吐き気や胸やけが持続する
- 便が黒くなる
- 体重が意識せずに減少している
胃がんの原因やリスク因子を理解する
胃がんの原因は、複数の要素が重なり合って発生します。リスクを減らすには生活習慣の見直しやピロリ菌の検査など、さまざまな対策を行うことが重要です。
ピロリ菌感染の影響
ピロリ菌に感染していると、慢性胃炎を引き起こし、がん細胞が発生しやすくなります。
ピロリ菌感染は経口摂取により起こり、特に幼少期の生活環境(家族からの口移し、水道関連の衛生面)が関係しています。
塩分や喫煙の悪影響
塩分の過剰摂取は胃粘膜への刺激を強め、炎症や潰瘍を起こしやすくします。さらに喫煙は胃粘膜の血流を悪化させ、粘膜修復力を下げるとともに発がん性物質を体内に取り込む行為でもあるため、胃がんリスクを高める要因の1つです。
胃がんに影響を与える主な要因
| 要因 | 具体例 | 影響度合い |
|---|---|---|
| ピロリ菌 | 幼少期の感染、胃への長期的な定着 | 強いリスク要因。除菌で一定の予防効果 |
| 塩分過多 | 漬物、塩辛、インスタント食品の過度摂取 | 粘膜に刺激を与えて胃炎になりやすくする |
| 喫煙 | 長年のタバコ習慣 | 発がん物質が胃を含む全身に悪影響 |
| アルコール | 過度の飲酒 | 胃粘膜の炎症や組織ダメージ |
| ストレス | 生活習慣の乱れ、睡眠不足 | 胃酸過多や免疫力低下に繋がる場合がある |
家族歴や遺伝性
家族に胃がんの人が多いと、ピロリ菌感染が起こりやすいことや生活習慣が似ていることなどから、リスクが高まると指摘される場合があります。
また、遺伝性びまん性胃がんといわれる、遺伝性の胃がんもあります。若い時に胃がんになった近親者が複数人いらっしゃる場合は、定期的に検査を受けることが大切です。
胃がんリスクを高める主な習慣
- 漬物や塩辛など塩分が多い食品を頻繁に食べる
- 毎日のように喫煙を続けている
- アルコールを多量に摂取する
- 不規則な食事時間や早食い
- 長引くストレスを放置している
- 家族に胃がんや大腸がんの既往歴が複数ある
初期の胃がんを発見するための検査方法
初期段階の胃がんは自覚症状がほとんどない場合が多いため、無症状でも定期的に検査を受けることが早期発見のカギです。危険因子が多い人や、生活習慣に不安がある人は、積極的に医療機関を訪れてください。
胃カメラ(内視鏡検査)
口や鼻から内視鏡を挿入し、直接胃の内部を観察する方法です。
小さながんを見逃しにくく、必要に応じて組織を採取して詳しく調べる(生検)こともでき、バリウム検査よりも精度が高く、内視鏡専門のクリニックが対応しています。
痛みや嘔吐反射が怖いという人も、麻酔や鎮静剤を使うことで苦痛を軽減できる場合があります。
バリウム検査
バリウムを飲んで胃の形状や粘膜の状態をX線画像で確認する方法で、自治体の健康診断や大規模な会社の検診で取り入れられることが多く、手軽に受けやすいということが利点です。
しかし、微細な病変を見落としやすいという欠点があり、バリウム検査で異常を示唆された場合には、さらに胃カメラで精密検査を行う必要があります。
ピロリ菌検査
血液や尿、呼気を調べてピロリ菌の抗体や分解産物を測定する検査で、ピロリ菌が陽性の場合、医師の判断のもと除菌療法を受けることで胃がんのリスクを一定程度抑えられ、胃カメラと同時に行われることもあります。
血液検査やCT検査
腫瘍マーカー(例えばペプシノゲン検査など)を測定したり、CT検査で胃周囲の臓器やリンパ節転移の有無をチェックすることもあります。
初期段階の胃がん発見には胃カメラが最も有効とされますが、転移の確認や手術方針の決定には画像検査が有用です。
主な胃がん検査方法と特徴
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 胃カメラ | 内視鏡で直接観察、生検も可能 | 小さな病変を発見しやすい | 検査に苦痛を感じる場合がある |
| バリウム検査 | X線画像で胃の形状を確認 | 集団検診で受けやすい | 微小病変の見落としリスク |
| ピロリ菌検査 | 血液、尿、呼気を用いて菌の有無を判定 | 除菌治療の適否を検討可能 | 胃がんの有無を直接判断するわけではない |
| 血液検査 | 腫瘍マーカーなどを測定 | 全身の状態を簡単に把握できる | 精度が低いので補助的な役割にとどまる |
| CT検査 | 胃周囲臓器や転移を画像で確認 | リンパ節など他臓器への転移を見つけやすい | 放射線被ばく、費用が高め |
初期の胃がんに対する治療とその後の生活
もし初期の胃がんが見つかっても、近年は内視鏡治療が広く普及し、体への負担が比較的小さい方法が選択される場合が多くなっています。早期発見に成功すれば、治癒率も高く、社会復帰もスムーズに行いやすいです。
内視鏡治療の概要
内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)によって、粘膜層にとどまっている小さいがんを切除する方法です。
ただし、開腹手術を回避でき入院期間が短く済む利点もありますが、病変が粘膜下層を越えて深く進んでいる場合は適応外となることもあります。
外科手術や化学療法
がんが進行していたり、内視鏡治療が難しいサイズや浸潤度の場合は、胃の一部または全体を切除する手術が行われます。必要に応じて周囲のリンパ節も切除し、術後は状態に合わせて化学療法や放射線療法を組み合わせます。
進行度によっては術後の食事管理やリハビリが大切です。
初期の胃がん治療後のポイント
- 定期的に胃カメラやCTなどの再検査を受ける
- 食事量や塩分摂取量に注意し、胃への負担を減らす
- 無理な喫煙や飲酒を避け、生活習慣を改善する
- 違和感があれば早めに医師に相談する
再発リスクとフォローアップ
胃がんの治療後も、まったく別の部位に新たながんが発生したり、残った組織で再発するリスクはゼロにはなりません。そのため、定期的に検査を行い、症状が出る前に異変をキャッチすることが重要です。
特にピロリ菌に感染している人は除菌治療後も、継続的なフォローアップが推奨されます。
胃がん予防と生活習慣の見直し
胃がんのリスクを下げるためには、原因となる要素を減らし、体の免疫力を高めるような生活を送ることが大切です。定期検診とあわせて、生活習慣病の予防も視野に入れると相乗効果が期待できます。
食習慣の改善
塩分や脂肪分が多い食べ物を頻繁に摂取すると、胃を含む消化器官に負担がかかりやすいです。
野菜や果物などビタミンや食物繊維をバランスよく取り入れ、水分をしっかり補給することが基本で、暴飲暴食や間食も胃が休む時間を奪い、粘膜が荒れやすくなるので避けてください。
禁煙や節酒
タバコには多くの発がん性物質が含まれており、胃だけでなく全身のがんリスクを高めます。喫煙している人は禁煙を検討し、受動喫煙にも気をつけましょう。
またアルコールも適度なら問題ありませんが、過度の飲酒は胃粘膜を傷つけ、他の病気にもつながりやすいです。
胃がん予防のために気をつけたい習慣
- 塩分を抑えた食事(漬物や塩辛などを控えめに)
- 野菜や果物を毎日の食事に加える
- 喫煙者は禁煙を意識し、必要なら専門外来を利用
- アルコール摂取は適量を心がける
- 食事のスピードをゆっくりにし、よく噛んで食べる
- 十分な睡眠とストレス解消を図る
定期的な健康診断と早期発見の意義
体の不調がなくても、40歳以上やリスク因子を複数持つ人は定期的な健康診断や胃カメラ検査を受けると安心で、自治体や企業で行われる検診がある場合は積極的に活用してください。
早期発見によって治療の選択肢が広がり、治療後の負担も軽減しやすいです。
健康診断で行われる主な検査項目と役割
| 検査項目 | 役割 | 胃がんとの関連性 |
|---|---|---|
| 胃部X線検査 | バリウム造影で胃の形状を確認 | 初期の胃がんを見落とす可能性あり |
| 血液検査 | 貧血や腫瘍マーカーなどをチェック | 間接的に胃がんリスクを示唆 |
| 上部消化管内視鏡 | 直接粘膜を観察し生検も可能 | 微小病変や早期がんを発見しやすい |
| 尿検査 | 全身状態を把握(糖尿病など他の病気の発見) | 胃がんそのものには大きく関与しない |
胃がん初期に備えたクリニック受診の流れ
症状がある、またはリスクが高いと感じたら、できるだけ早く医療機関を受診して具体的な検査を受けることが望ましく、消化器内科を看板に掲げるクリニックで胃カメラ検査の予約をするのがスムーズです。
受診から検査までのステップ
多くのクリニックでは、問診や血圧測定などの基本チェックを行い、その後、患者さんの希望や医師の判断に基づいてバリウム検査や胃カメラなどを選択します。
初期症状がある場合は、胃カメラを推奨されることが多いです。
検査結果の確認と診断
胃カメラ検査で異常が見つかった場合、組織の一部を採取して病理検査を行い、がんであるかどうかを確定診断します。
結果が出るまでには数日から1週間程度かかる場合があり、その間、医師から食事や生活習慣についての指導を受けるケースもあります。
クリニック受診時に気をつける点
- 事前に症状をメモしておき、医師に伝える
- 家族の既往歴や自分の既往歴も整理しておく
- 検査後の注意点や当日の食事制限を把握しておく
- 検査結果の報告日やフォローアップを確認しておく
費用や保険適用
胃がん検査にかかる費用は、保険の種類や検査内容、施設によって異なりますが、多くの検査は健康保険が適用される場合が多いです。
自治体の特定健診やがん検診を活用すると安く検査を受けられることがあります。
ただし、公的検診のバリウム検査だけでは初期の胃がんを完全に除外できないため、心配なときは医療機関で追加の胃カメラを受けるのがおすすめです。
受診・検査にかかる費用の目安
| 検査内容 | 保険適用の有無 | 費用の目安(自己負担) |
|---|---|---|
| 胃カメラ(内視鏡検査) | 症状がある場合は適用 | 数千円~1万円程度(3割負担の場合) |
| バリウム検査 | 集団検診は公費補助 | 無料~2千円程度(自治体による) |
| ピロリ菌検査(尿・呼気) | 胃炎、胃潰瘍がある場合は適用 | 数百円~1千円程度(3割負担) |
| 腫瘍マーカー | がんを疑う所見があれば適用 | 数百円~1千円程度(3割負担) |
まとめ
胃がんの初期症状ははっきりとした特徴がなく、みぞおちの違和感や食欲不振、黒色便などに気づいても「軽い胃炎だろう」と思い込み、医療機関を受診せずに放置してしまいがちです。
しかし、ほんの小さな兆候でも長く続く場合には、内科や消化器クリニックで胃カメラなどの検査を受けましょう。
ピロリ菌の感染や塩分過多の食事、喫煙習慣などがリスクを高める要因として挙げられ、注意して生活習慣を見直すことで胃がん発生率を下げる一助になります。
初期段階の胃がんは内視鏡治療で対応できる場合が多いです。身体への負担を軽減しながら治療できる可能性が高まるので、定期的な健康診断を受け、少しでも気になる症状があれば医師に相談することが大切です。
参考文献
Murakami T. Early cancer of the stomach. World journal of surgery. 1979 Nov;3(6):685-91.
Axon A. Symptoms and diagnosis of gastric cancer at early curable stage. Best practice & research Clinical gastroenterology. 2006 Jan 1;20(4):697-708.
Maconi G, Manes G, Porro GB. Role of symptoms in diagnosis and outcome of gastric cancer. World journal of gastroenterology: WJG. 2008 Feb 2;14(8):1149.
Ogilvie H. Early diagnosis of cancer of the oesophagus and stomach. British Medical Journal. 1947 Sep 9;2(4523):405.
Moynihan BG. The Early Diagnosis And Treatment Of Cancer Of The Stomach. British Medical Journal. 1909 Apr 4;1(2518):830.
Paterson HJ. The Early Diagnosis and Treatment of Cancer of the Stomach. The British Medical Journal. 1910 Oct 1:953-5.
Cassell P, Robinson JO. Cancer of the stomach: a review of 854 patients. British Journal of Surgery. 1976 Aug;63(8):603-7.
Tan YK, Fielding JW. Early diagnosis of early gastric cancer. European journal of gastroenterology & hepatology. 2006 Aug 1;18(8):821-9.
Ilic M, Ilic I. Epidemiology of stomach cancer. World journal of gastroenterology. 2022 Mar 3;28(12):1187.
Lahey FH, Jordan SM. Cancer of the Stomach. New England Journal of Medicine. 1934 Jan 11;210(2):59-66.