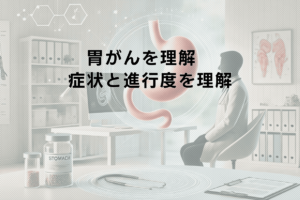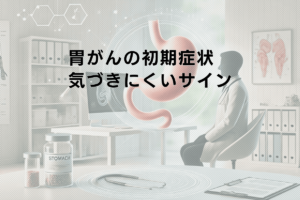胃は食べ物を一時的に蓄え、消化を進める大切な臓器です。胃に発生するがんは、初期の段階でははっきりとした症状がないことが多く、進行してから気づくケースも珍しくありません。
食欲低下や吐き気、みぞおち付近の違和感などは胃がんの兆候のひとつかもしれませんが、別の胃腸の病気や一時的な体調不良とも区別がつきにくいことがあります。
この記事では、胃がんの特徴や原因、検査方法、そして治療の流れまでをわかりやすく解説し、早期発見と予防の観点から役立つ情報をお伝えします。
胃がんとはどのような病気か
胃がんとは、胃の粘膜を構成する細胞が異常増殖を起こして形成される悪性腫瘍のことで、日本人が発症しやすいがんの1つとして長年知られてきました。
食事や生活習慣の変化によって罹患数は減少傾向にあるともいわれますが、まだ多くの人が注意したい病気です。
胃の構造と胃がん発生の仕組み
胃は上部の噴門部、中間の体部、下部の前庭部や幽門部などに分けられ、食物を受け取って消化液と混ぜ合わせる役割を担います。
胃がんは、これらの部位にある粘膜細胞ががん化し、周囲の組織へ侵潤したり、血液やリンパ液を通じて転移したりして広がります。粘膜にとどまっている段階(早期)で治療できるとその後の成績が良い場合が多いです。

胃がんが多い背景
日本人はピロリ菌の感染率が高いことが胃がんの発生に関わる大きな要因です。まだピロリ菌の中でも東アジア型タイプは発がん率が高いことが知られています。
また日本人は塩分を多く含む食事をとりがちで、これが胃の粘膜に負担をかけるとともに、喫煙や過度の飲酒などのリスク因子が複合的に働き、胃がん発生を助長する場合があります。
スキルス胃がんと一般的ながんの違い
スキルス胃がんは、胃壁にしみ込むように広がる特殊な形態の胃がんで、症状が出にくく、進行が速いのが特徴です。
通常の胃がんよりもみぞおち付近の痛みや食欲不振が出る時期が遅れることがあるため、検査を受けるまで発見が遅れやすいケースがみられます。
胃がんと食道がん・大腸がんの違い
消化器系には胃以外にも食道や大腸などがあり、同じようにがんが発生する可能性があります。部位によって症状や治療法が異なるため、自己判断せず、専門医の診断を受けることが望まれます。
特に胃がんと食道がんは初期症状が似通うことがあるため、早めの胃カメラ検査が大切です。
胃がんが疑われる症状
胃がんは初期のうちに明確な自覚症状が出にくいといわれますが、進行してくるといくつかの特徴的なサインが現れます。
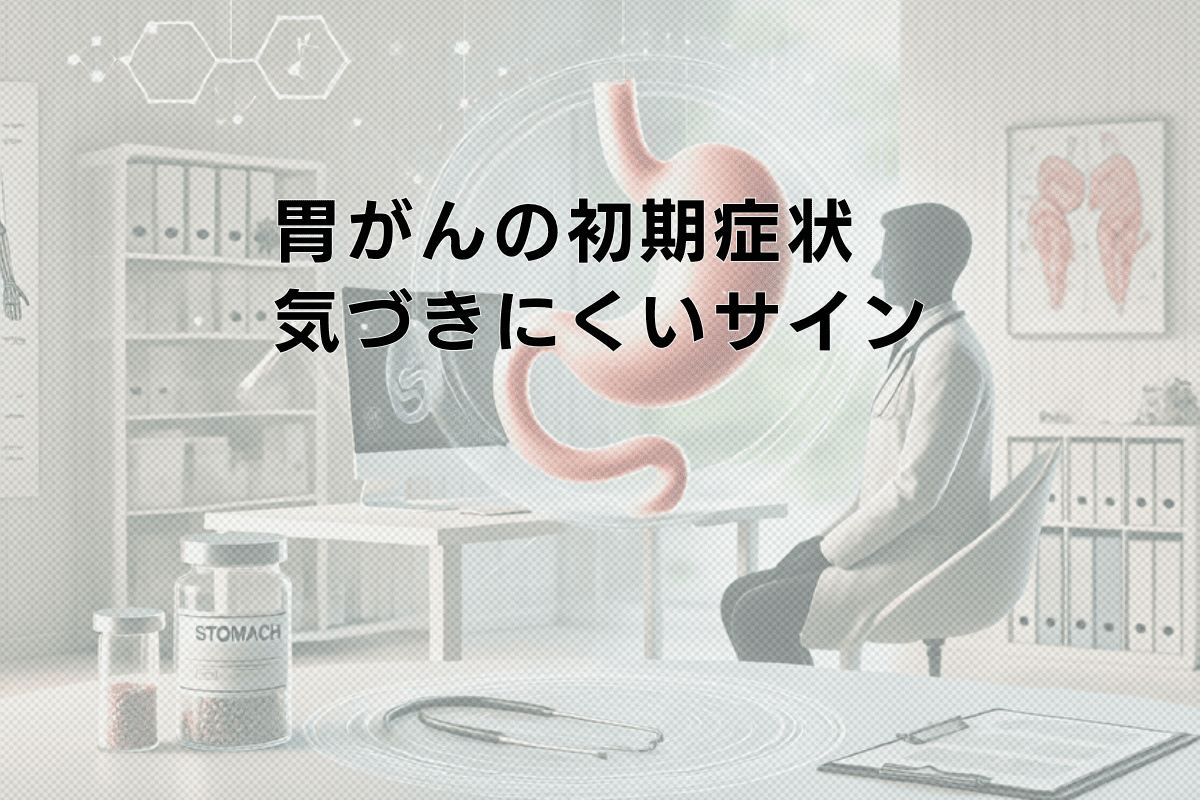
食欲不振や吐き気
胃がんが進行してくると胃の機能が落ちて、食欲不振や吐き気などが続くことがあります。一時的なストレスや軽い胃炎でも同様の症状が起きるため見過ごされがちですが、数日から数週間続く場合は専門機関で検査を受けたほうが安心です。
みぞおち付近の痛みや不快感
みぞおちのあたりが重く感じたり、鈍い痛みが続いたりするのは胃がんを疑うきっかけにもなります。
胃潰瘍や慢性胃炎などのほかの病気でも起こる症状ですが、痛みの程度やタイミングがいつもと違う、長期間に及ぶといった場合は注意が必要です。

胃がんが疑われる症状
| 症状名 | 具体的な状態 | 他の可能性のある病気 |
|---|---|---|
| 食欲不振 | 食べる量が極端に減る | 風邪、胃炎、精神的ストレス |
| 吐き気・嘔吐 | 特に食後にムカムカする | 逆流性食道炎、胃潰瘍、妊娠 |
| みぞおちの痛み | 鈍痛や不快感が断続的に現れる | 胃潰瘍、慢性胃炎、十二指腸潰瘍、膵炎、膵がんなど |
| 胸やけ | 胸やけ感、胃酸が上がる感じ | 食道炎、胃酸過多 |
| 体重減少 | 食事量が減る、栄養をうまく吸収できない | 糖尿病、甲状腺機能亢進症など |
黒色便や出血を伴うケース
胃の内部で出血が続くと、便が黒くなる「黒色便」が出現することがあり、出血量が多い場合は吐血につながることもあり、健康的な状態ではないのは明らかです。
ただし、黒色便は消化器内での出血だけでなく、一部の医薬品や食品によって起こることもあるため、原因の特定には検査が欠かせません。
体重減少や全身の倦怠感
がん細胞にエネルギーや栄養を奪われることで、体重が減少したり、慢性的な疲労感が生じたりしますが、特有の症状ではなく、他の病気でも起こりうるため、複数の症状を総合的に見て判断することが大切です。
気になるげっぷやおならとの関係
げっぷやおならが増えると胃や腸の病気を心配するケースもありますが、胃がんに特化した初期症状としては必ずしも関連が強くありません。
むしろ長引く胸やけや慢性的なみぞおちの不快感などのほうが、胃がんへの注意を促すサインになりやすいです。
胃がんの原因とリスク因子
胃がんの発症にはさまざまな要因が関わっています。ここでは、代表的な原因やリスク因子、そして注意すべき生活習慣などを確認します。
ピロリ菌の感染
ヘリコバクター・ピロリ菌(ピロリ菌)は、胃の粘膜に長期間生息すると慢性胃炎を引き起こし、胃がんのリスクを高めることが知られています。
多くは子どもの時期に、家族内での接触(口移しなど)や感染した水の摂取で感染します。感染していても症状がない場合があるため、感染の有無を調べる検査が広く行われています。
ピロリ菌関連の検査・除菌治療
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査方法 | 血液検査、尿検査、呼気試験、PCR検査などでピロリ菌を検出 |
| 除菌治療の目的 | ピロリ菌を抗生剤で排除して胃炎の進行を抑え、発がんリスクを下げる |
| 除菌後のフォロー | 除菌後も発がんリスクは残るため、定期的に胃内視鏡検査を実施 |
塩分過多や喫煙
食塩や塩蔵食品の過剰摂取は胃に負担をかけ、胃がんを招く可能性が高くなります。さらに喫煙は胃がんだけでなく、肺がんや大腸がんなど多様ながんのリスク要因であり、喫煙者であるほど発症率が高いです。
禁煙や減塩を心がけることで、一定の予防効果が期待できると考えられています。
遺伝的要因や慢性胃炎
一部の遺伝性疾患や家族性の要因で、若い年代でも胃がんのリスクが高い場合がり、また、慢性的な胃炎(萎縮性胃炎など)が持続すると、胃の粘膜細胞が変化を起こしやすくなることも指摘されています。
ピロリ菌感染が継続していると、萎縮性胃炎を起こしやすいです。
高塩分食以外の食習慣
刺激物やアルコールの過剰摂取、野菜や果物の摂取不足なども胃がんを含む消化器がんのリスクを上げる要素です。
また過度に熱い飲食物は食道がんのリスクになりますので気を付けてください。
主な胃がんリスク因子
| リスク因子 | 胃がん発症への影響 | 主な対策 |
|---|---|---|
| ピロリ菌感染 | 慢性胃炎→粘膜異常→がんの可能性 | ピロリ検査、除菌治療 |
| 塩分過多 | 胃粘膜へのダメージ | 減塩、塩蔵食品の摂取を控える |
| 喫煙 | 有害物質が全身に悪影響を及ぼす | 禁煙、受動喫煙を避ける |
| 慢性胃炎 | 粘膜の萎縮や構造変化が起こりやすい | 定期的な胃カメラ検査 |
| アルコール過剰摂取 | 胃壁を荒らし、消化器系全般に負担をかける | 節度ある飲酒 |
胃がんを早期発見する検査
胃がんはできるだけ早い段階で発見することが治療成功のカギなので、症状が軽微であっても検査を受ける意義は大きく、特にピロリ菌感染が疑われる場合は積極的に受診を検討してください。
胃カメラ(内視鏡検査)
胃カメラは、胃の内部を直接観察できる検査で、腫瘍や潰瘍、ポリープなどの異常を細かく把握でき、小さな病変でも見逃しにくく、組織を一部採取して病理検査を行うことも可能です。
少しの痛みや不快感を伴うことがありますが、鎮静剤を用いて負担を軽減する方法もあります。

胃カメラ検査のメリットとデメリット
| 視点 | 胃カメラ(内視鏡検査)のメリット | デメリット |
|---|---|---|
| 精度 | 高い精度で小さい病変も発見しやすい | 専門医の技術に依存しやすい |
| 痛み・負担 | 鎮静剤で軽減可能 | 多少の不快感や麻酔リスクがある |
| 追加検査 | その場で組織採取が行える | 準備や器具の費用がかかる可能性あり |
胃透視検査(バリウム検査)
バリウムを飲んで胃の造影写真を撮影する方法で、簡便に行いやすい一方で、小さな病変を見落とすリスクが胃カメラより高いです。
健診ではバリウム検査が広く採用されていますが、異常が見つかった場合には、精密検査として胃カメラを受けることが推奨されます。
腹部超音波検査やCT検査
胃カメラが主流ですが、腹部超音波(エコー)検査やCT検査も補助的に用いられ、転移の有無や周囲の臓器との関係を調べる際にCT検査が有効です。
ただし、胃内部の粘膜状況までは詳細に把握しにくいため、最終的な診断には胃カメラが中心となります。
ピロリ菌の検査
胃炎や胃潰瘍の既往がある場合や、家族に胃がん経験者が多い場合などに勧められることがあります。ピロリ菌が陽性の場合、除菌治療を受けて胃がんリスクを減らす手段が選択できるため、将来的ながん予防においても大切です。

胃がんの進行度と治療の流れ
胃がんの治療方針は、がんの進行度(ステージ)や患者さんの状態によって変わり、主なステージ区分と、それに応じた治療の流れを紹介します。
ステージごとの特徴
胃がんは腫瘍がどの程度深く浸潤しているか、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無によってStage0からStageⅣまで分類されます。
Stage0やⅠであれば内視鏡治療のみで完結する場合もありますが、ⅢやⅣになると外科手術や化学療法、放射線療法などを組み合わせることが必要です。
胃がんのステージの概要
| ステージ | 腫瘍の深達度 | リンパ節転移・遠隔転移の有無 |
|---|---|---|
| 0期 | 粘膜内だけ | なし |
| Ⅰ期 | 粘膜下層まで | なし、またはリンパ節転移わずか |
| Ⅱ期 | 筋層や漿膜に達する可能性あり | あり(リンパ節転移) |
| Ⅲ期 | がんが深く進行し漿膜を越える | あり(リンパ節転移) |
| Ⅳ期 | 他臓器への転移あり | あり(遠隔転移、肝臓など) |
内視鏡治療
早期胃がんや、病変が小さい場合には、内視鏡的粘膜切除術(EMR)や粘膜下層剥離術(ESD)などが行われ、開腹手術と比べて体への負担が少なく、治癒の見込みも高いケースが多いです。ただし、進行度が高い場合には適応外となります。

外科手術
胃の一部、または全体を切除し、周囲のリンパ節を同時に取り除くのが一般的な胃がん手術です。
病変の大きさや部位によって、胃の上部だけを切除する場合もあれば、幽門側や噴門側を中心に切除する場合もあります。近年は腹腔鏡下手術など、開腹を最小限にして回復を早める手法も広がっています。
化学療法・放射線療法
進行した胃がんの場合、手術と併用して化学療法を行ったり、再発リスクが高い場合に術後の補助療法として化学療法を組み合わせたりします。
放射線療法は胃がんではあまり主流ではありませんが、症状緩和や特定のケースで検討されることもあります。副作用のコントロールが重要なため、医師とのコミュニケーションが欠かせません。
主な治療法と特徴
| 治療法 | 適応状況 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内視鏡治療 (EMR,ESD) | 早期胃がん、小さな病変 | 体への負担が小さい |
| 外科手術 | 進行がん、リンパ節転移あり | 根治を目指すが大がかりな治療 |
| 化学療法 | Ⅲ期以上や再発、転移がある場合 | 複数の薬剤を組み合わせてがんを抑制 |
| 放射線療法 | 限定的な症状緩和など | 単独治療というより補助的に用いられる |
胃がんを予防する生活習慣と検診
胃がんのリスクを下げるためには、日常的な食事や生活習慣の見直しが大切です。また、定期的な胃がん検診の受診も早期発見に大きく寄与します。
塩分や喫煙への配慮
食事の塩分を控えめにし、加工食品や塩辛い食べ物の摂取を減らすことが胃の粘膜への刺激を少なくする一歩です。さらに、喫煙は全身に有害な影響をもたらすため、禁煙を心がけましょう。
ピロリ菌除菌
ピロリ菌に感染していると診断された場合、医師が勧める除菌治療を行います。除菌によって胃の炎症が改善し、胃がん発生の確率が下がると考えられています。ただしがんの発生率が完全にゼロになるわけではないため、定期的な検査を続けることが必要です。
適度な飲酒とバランスの良い食事
アルコールを過剰に摂取すると胃や肝臓に負担がかかり、がんリスクを高める可能性があります。緑黄色野菜や果物、食物繊維を含む食品をバランス良く取り入れ、タンパク質や脂質、炭水化物も適度に摂取することが健康維持に寄与します。
胃がん予防に役立つ食品や習慣
| 食品・習慣 | 期待される効果 |
|---|---|
| 野菜・果物 | 抗酸化ビタミンや食物繊維が豊富 |
| 乳酸菌を含む食品 | 腸内環境の改善や免疫機能の補助 |
| 適度な運動 | 体力維持、消化器官の働きを活性化 |
| 十分な睡眠 | 免疫力の向上、ストレスの緩和 |
定期的な健康診断・胃がん検診
40歳を過ぎたら、年1回程度の定期的な健康診断を意識する方が増えていますが、特に胃がんのリスクが高いと判断された場合は、胃カメラなどの検診を受けることが勧められます。
自治体が実施している胃がん検診は、バリウム検査が中心ですが、最近は胃カメラ検査を選択できる市区町村も増えてきています。より詳しく調べたいときは、胃カメラ検査を受けることをお勧めします。
胃がん検診の種類
| 検診名 | 主な方法 | 発見精度 |
|---|---|---|
| 市区町村の集団検診 | バリウム検査が一般的。最近は胃カメラも多い。 | 中程度 |
| 企業の健康診断 | バリウム検査、胃カメラなど | 胃カメラなら高精度 |
| 人間ドック | 胃カメラの選択が可能 | 高精度 |
胃がんと上手につきあうための心構え
胃がんが見つかっても、早期であれば治る可能性が高く、進行していても医療技術の進歩によって治療選択肢は広がっています。
病院やクリニックでの相談
胃痛や食欲不振が続く場合、または健康診断で異常が見つかった場合には、早めに消化器内科や内視鏡専門医に相談してください。医師の判断で胃カメラ検査やピロリ菌検査を行い、必要に応じて治療方針が検討されます。
セカンドオピニオンの活用
進行した胃がんや、治療方針が複数考えられる場合には、他の医療機関でセカンドオピニオンをとるという方法もあります。病状や治療内容を客観的に整理して自分に合う方法を選ぶため、心理的なサポートを得られる点でも大切です。
医療機関を受診するときに意識したい点
- 症状を具体的に記録して伝える
- 飲んでいる薬やサプリメント、既往症の情報を持参する
- 心配な点や疑問点をメモしておき、医師に尋ねる
- 家族や知人と一緒に受診することで情報を共有する
家族や周囲のサポート
胃がんは心身の負担が大きい病気ですが、家族や周囲の人々の理解とサポートがあると治療や生活の質が向上し、食事の工夫や休息のタイミングなど、日々の生活面で協力し合える体制を整えると、治療に専念しやすくなります。
将来にわたって健康を守るために
1度胃がんを治療しても、胃の中の別の部位でがんが発生するリスクがゼロになるわけではありません。定期的なフォローアップ検査を受け、医師の指示に従った生活習慣を継続すると、再発を早期に見つけたり、予防につなげられます。
まとめ
胃がんは日本で多く見られるがんの1つであり、初期のうちに自覚症状がないため気づきにくく、食欲不振やみぞおちの痛み、黒色便などの症状があれば、専門医に相談することが重要です。
ピロリ菌感染や塩分の取りすぎ、喫煙といったリスク因子が関わるため、生活習慣の改善やピロリ菌の除菌が役立つ可能性があります。
定期的な健康診断や胃がん検診で早期発見をめざし、もし胃がんが見つかった場合でも、内視鏡治療や手術、化学療法などを組み合わせて治療に取り組めます。
次に読むことをお勧めする記事
【胃カメラで分かる症状 検査の流れ】
胃がんの症状や原因について理解できたら、次は実際の検査方法について、以下の記事で一緒に勉強してまいりましょう。胃カメラ検査を検討されている方や、検査への不安をお持ちの方に特におすすめです。
【胃がんの初期症状 気づきにくいサインと生活習慣の注意点】
胃がんの早期発見のためのセルフチェックポイントについても知っておくと、より実践的な健康管理につながります。以下の記事で一緒に学んでまいりましょう。
参考文献
Yang YH. The relationship of symptoms of side effects, fatigue and quality of life in stomach cancer patients receiving chemotherapy. Korean Journal of Adult Nursing. 2002;14(2):205-12.
Cassell P, Robinson JO. Cancer of the stomach: a review of 854 patients. British Journal of Surgery. 1976 Aug;63(8):603-7.
Ilic M, Ilic I. Epidemiology of stomach cancer. World journal of gastroenterology. 2022 Mar 3;28(12):1187.
Maconi G, Manes G, Porro GB. Role of symptoms in diagnosis and outcome of gastric cancer. World journal of gastroenterology: WJG. 2008 Feb 2;14(8):1149.
Brinton W. On the symptoms of cancer of the stomach. The British and Foreign Medico-Chirurgical Review. 1857 Oct;20(40):476.
Nyren OL, Adami HO. Stomach cancer. Textbook of cancer epidemiology. 2008;2:239-74.
Shahon DB, Horowitz S, Kelly WD. Cancer of the stomach: an analysis of 1,152 cases. Surgery. 1956 Feb 1;39(2):204-21.
Torpy JM, Lynm C, Glass RM. Stomach cancer. Jama. 2010 May 5;303(17):1771-.
Murakami T. Early cancer of the stomach. World journal of surgery. 1979 Nov;3(6):685-91.
Lahey FH, Jordan SM. Cancer of the Stomach. New England Journal of Medicine. 1934 Jan 11;210(2):59-66.