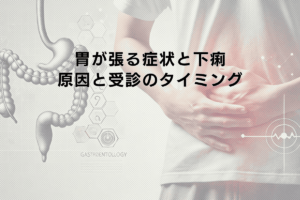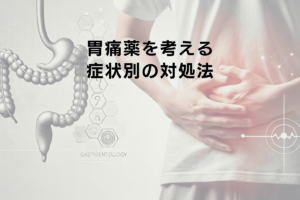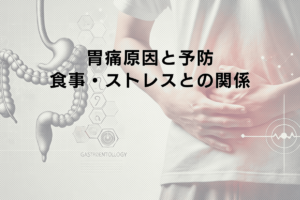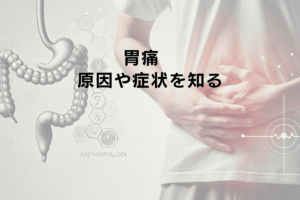空腹時に突然感じる胃痛やみぞおちの違和感は、単なる一時的な刺激だけではなく、胃酸の過剰分泌や胃や十二指腸の粘膜の状態、さらにはストレスなど複合的な要因が絡んでいることがあります。
胃痛の原因は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの病気から、生活習慣の乱れによる胃粘膜への負担まで多岐にわたります。
本記事では、空腹時に起こる胃痛がどのように発生するのかを詳しく解説し、具体的な検査方法や病気の可能性、そして日常生活で気をつけるべき点を紹介します。
空腹時に起こりやすい胃痛のしくみ
空腹のときに胃がキリキリと痛んだり、みぞおちあたりにズキズキする痛みを感じる経験は、決して珍しくありません。まずは空腹時の胃痛がどのような仕組みで起こるのか理解することが大切です。
空腹感と胃酸分泌の関係
私たちの体は食事を摂らなくても、空腹時間が一定以上続くと、次の食事に備えるために胃酸の分泌量をコントロールしようとしますが、バランスが崩れると過剰に胃酸が分泌され、胃の粘膜を刺激して痛みを起こします。
とくに空腹時には食べ物がない状態なので、胃酸が粘膜に直接触れやすく、強い刺激を受けてしまうわけです。
胃と十二指腸の役割
胃は食べ物を受け止めて消化し、適度な形状にしたうえで十二指腸へ送る役割を担っており、十二指腸では胃から送り出された消化物をさらに分解しながら、栄養を吸収しやすい状態へ導きます。
この連携によって食物が体内にうまく取り込まれるのですが、空腹の状態で胃酸が多いと、十二指腸や胃そのものが強い酸性刺激を受けやすくなります。
胃痛が起こる仕組みを理解する利点
胃痛が起こる理由を理解しておけば、普段の生活習慣を見直すきっかけになります。
例えば、食事の間隔が長すぎることや、偏った食習慣によって胃酸の分泌が乱れやすくなっていないかを振り返ることで、症状の軽減や再発防止に役立つ行動を選びやすくなります。
刺激を受けやすいタイミング
空腹時の胃は食べ物がないため、いわば「むき出し」の状態で強い酸に晒される可能性が上がり、このタイミングでお腹がキリキリ痛む場合は、胃酸が粘膜を刺激しているサインと考えられます。
また、朝起きたときや就寝前など、長時間飲食をしなかった後の時間帯に胃痛を感じる方は、胃酸分泌のリズムを見直すことが必要です。
胃の役割と十二指腸の役割の違い
| 器官 | 主な役割 | 空腹時の特徴 |
|---|---|---|
| 胃 | 食物を受け取り、消化液を混ぜる | 胃酸過多になると粘膜を直接刺激しやすい |
| 十二指腸 | 胃から送り出された内容をさらに分解 | 胃酸の影響を受けすぎると潰瘍形成のリスクが上がる |
胃酸と胃の粘膜の関係
空腹時の胃痛と密接な関わりがあるのが、胃酸と胃の粘膜の関係です。胃酸は食物を分解するうえで大切な働きを持ちますが、粘膜への刺激が過度になると潰瘍や炎症の原因になってしまいます。
胃酸がもたらすメリット
胃酸は強酸性(pH1~2ほど)であり、食物中の細菌を殺菌し、タンパク質を分解する役割を担い、適度な胃酸が分泌されることは、胃腸の機能を保つうえで非常に重要です。
殺菌効果によって腸内環境が乱れにくく、栄養を効率的に吸収できる点も見逃せません。
過剰な胃酸分泌のリスク
胃酸の分泌が増えすぎると、胃の粘膜や十二指腸を傷つけてしまい、潰瘍などの病気へと発展する恐れがあります。特に空腹時は保護となる食物がないため、粘膜に直接酸が触れ、強い刺激を受けて痛みを誘発することが多いです。
もし胃痛が慢性的に続くようなら、胃酸が過多になっているかもしれません。
胃粘膜を保護するしくみ
胃には、粘液を分泌して胃酸の攻撃から自分自身を守る仕組みがあり、この粘液の層が保たれ、かつ胃酸の分泌バランスが適正であれば、胃痛は起こりにくくなります。
しかし、ストレスや不規則な食生活、飲酒や喫煙などによって粘液の分泌が乱れると、保護力が低下して空腹時の痛みを引き起こしやすくなります。
空腹時に痛みを感じやすい理由
空腹時は胃の中に食物がないため、粘液層が薄いときや胃酸が多いときにダイレクトに粘膜が刺激を受けます。さらに、生活習慣などが原因で胃粘膜の保護機能が下がっていると、痛みを感じやすい状態になります。
このように、胃酸と粘膜のバランスが崩れたときこそ、空腹時の胃痛が顕著になるのです。
胃酸が増えやすい要因
- 食事の間隔が長くなる
- 極端に脂っこい食事が多い
- ストレスや睡眠不足が続いている
- アルコールや刺激物の摂取が習慣化している
空腹時の胃痛が考えられる病気
単なる胃酸過多や一時的な胃粘膜の刺激だけでなく、空腹時に胃痛を感じるケースの背景には、さまざまな病気が隠れている可能性があり、早期発見につなげるためにも、考えられる病気を知っておくことは重要です。
十二指腸潰瘍と胃潰瘍
十二指腸潰瘍や胃潰瘍は、胃酸と粘膜のバランスが崩れ、組織がただれてできる病変を指します。強い痛みを感じやすいのは、胃酸の刺激が直接潰瘍部に当たることが主な原因です。
胃潰瘍は食後に痛みが強くなるのに対し、十二指腸潰瘍は空腹時に痛みが強くなり食事により症状が和らぐことが特徴的です。
慢性胃炎や急性胃炎
胃酸の分泌異常やピロリ菌感染、ストレスなどにより胃粘膜に炎症が起こる状態が胃炎で、慢性的な胃炎では、症状が軽度でも長期にわたり、空腹時にしみるような痛みを覚えることがあります。
一方、急性胃炎は突発的に起こり、激しい吐き気や、まれに吐血などを伴う場合があるため注意が必要です。

逆流性食道炎
胃の内容物や胃酸が食道へ逆流し、胸やけや胸部の違和感、みぞおち付近の痛みを引き起こす病気で、空腹時に胃酸が増え、少し食道に逆流しただけでも強い刺激となるため、胃痛や胸やけを感じることがあります。
食後にみぞおちが焼けるように痛むことも典型的です。
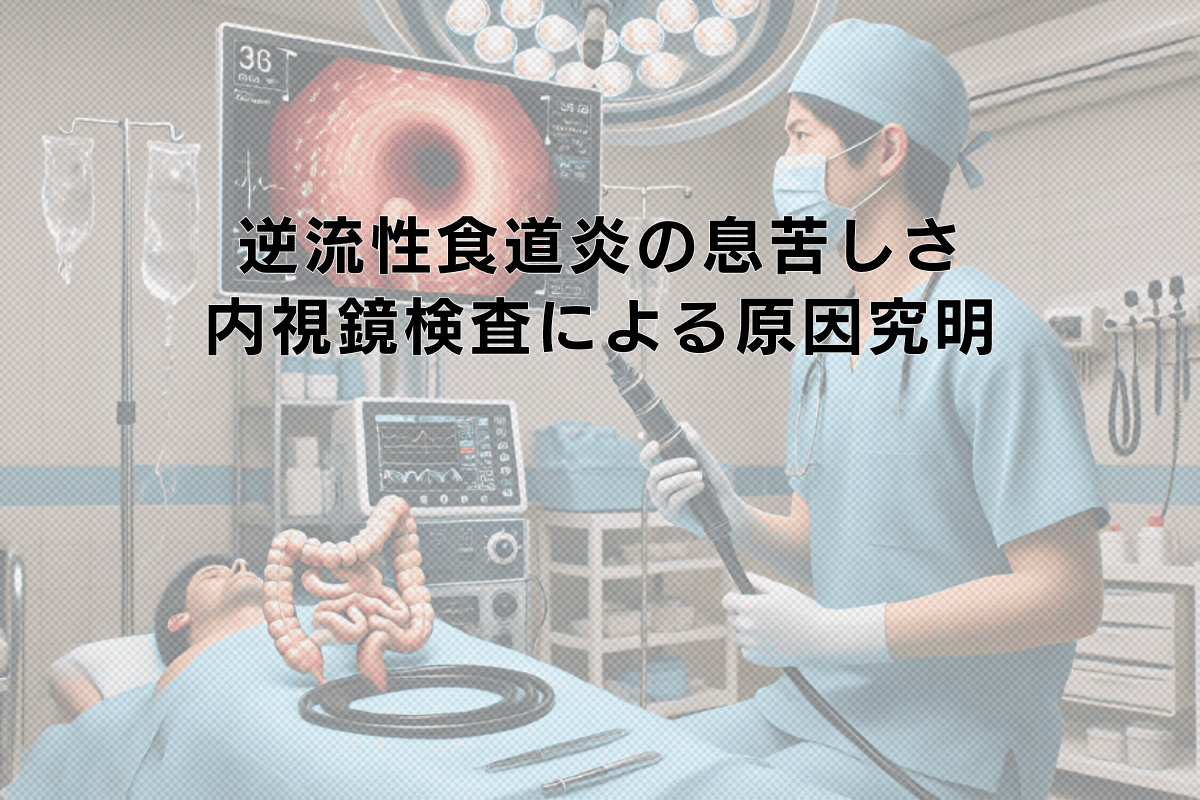
機能性ディスペプシアとストレス
内視鏡検査などで明確な病変が見つからないにもかかわらず、慢性的な胃痛や胸やけ、胃もたれなどの症状を訴える状態を機能性ディスペプシアと呼びます。
ストレスがかかると自律神経のバランスが乱れ、胃腸の働きが不安定になり、空腹時にも痛みを感じるケースが多いです。
空腹時の胃痛が疑われる主な病気と特徴
| 病名 | 主な症状・特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 十二指腸潰瘍 | 空腹時に強い痛み。食べると和らぐことが多い | 放置すると穿孔や出血のリスク |
| 胃潰瘍 | みぞおち付近の強い痛み。食後や夜間に悪化することが多い | シクシク痛む場合は要注意 |
| 慢性胃炎・急性胃炎 | 長期的な胸やけや胃痛、急性だと嘔吐や吐血もある可能性 | ピロリ菌感染の有無を確認する |
| 逆流性食道炎 | 胸やけ、のどの違和感、みぞおちの焼けるような痛み | 空腹時の胃酸逆流が原因となる |
| 機能性ディスペプシア | 検査で異常が見つからないのに慢性的な胃痛や胃もたれを感じる | ストレス管理が大切 |
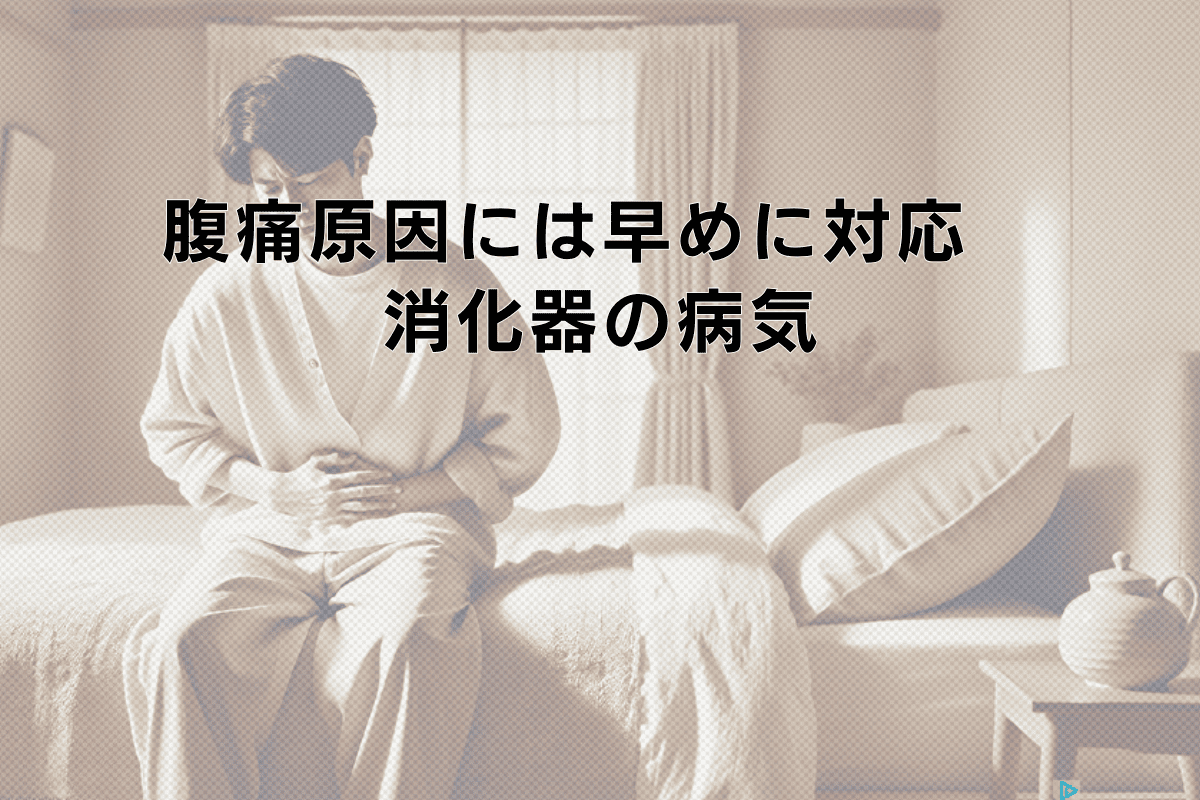
空腹時の胃痛を起こしやすい生活習慣
病気以外にも、私たちの日常生活の中には空腹時の胃痛を悪化させる要因が潜んでいます。食事のとり方やストレス管理などを見直すと、胃痛の頻度を抑えることが期待できます。

食事の取り方と内容
極端なダイエットや忙しい仕事のスケジュールなどで、食事の間隔が大きく開きすぎると空腹時間が長くなり、胃酸が粘膜を刺激しやすくなります。また、脂っこい食事や刺激物を多く摂取する習慣も、胃の負担を増やす原因です。
こまめに軽い食事を摂るなど、胃酸分泌が安定するような工夫を心がけてください。
ストレスや睡眠不足
ストレスが長く続くと、自律神経のバランスが乱れ、胃酸の分泌が異常に増えるケースがあります。また、睡眠不足は胃腸の機能を低下させやすく、胃粘膜の保護も十分に行き届かなくなるため、胃痛を引き起こしやすい状況につながります。
アルコールやカフェイン摂取
アルコールやコーヒー、紅茶などに含まれるカフェインは胃酸の分泌を促しやすい物質で、空腹時に過度に摂取すると、胃に強い刺激が加わり、痛みを感じるリスクが高まります。適量を意識した摂取や、飲むタイミングに配慮することが大切です。
胃に刺激を与える習慣
たばこを吸う習慣や、早食い・大食いなども、胃に大きな負担をかけます。ニコチンは胃粘膜を傷つけ、早食いは大量の空気を胃に送り込むため、痛みや不快感を誘発しやすくなります。
自分自身の日常を見直し、胃に刺激を与えすぎない工夫を取り入れてください。
胃への負担を軽減する工夫
- 食事の回数を増やし、少量をこまめに摂取する
- 就寝前2~3時間は食べ物・飲み物を控える
- 脂っこい料理や濃い味付けの食品を減らす
- ストレス解消の時間を確保して、自律神経を整える
- アルコール、カフェイン、たばこは控えめにする
| 食事・飲み物 | 胃への影響 |
|---|---|
| 揚げ物・高脂肪食 | 消化に時間がかかり、胃酸分泌を増やす原因になりやすい |
| 辛い・濃い味付け | 胃粘膜を刺激し、過剰な胃酸を誘発するケースが多い |
| アルコール | 胃粘膜を直接刺激し、胃酸分泌も活発化させる |
| コーヒー・紅茶 | カフェインが胃酸分泌を促し、空腹時に摂ると胃痛のリスクが上がる |
| 炭酸飲料 | 炭酸ガスによる刺激で胃が張りやすく、痛みや不快感につながる |
受診と検査のすすめ
空腹時の胃痛が何度も繰り返したり、症状が長期間続いたりする場合は、検査を受けて原因を明確にすることが欠かせません。胃や十二指腸に病気が隠れていないかどうかをチェックするために、消化器内科を受診して適切な検査を受けましょう。
受診の目安と注意すべき症状
空腹時の痛みが断続的に起こるだけでなく、吐き気や吐血、黒色便(タール便)などを伴う場合は、十二指腸潰瘍や胃潰瘍、あるいは出血性の病変が疑われ、また、体重の急激な減少や貧血症状があるときも要注意です。
自己判断で放置せず、早めに医師の診察を受けることが重要になります。
消化器内科で行う検査の種類
消化器内科では、空腹時の胃痛やみぞおちの痛みを訴える患者さんに対して、まず問診や触診を行います。加えて、下記のような検査を組み合わせて原因を探るのが一般的です。
- 血液検査:貧血や感染症の有無、炎症の度合いを把握する
- 尿検査・便検査:便潜血反応などで消化管出血の可能性をチェックする
- 画像検査(X線、超音波):消化器の形状や動きを確認し、大きな病変を探す
胃カメラ検査や内視鏡検査の重要性
より詳しい診断には胃カメラ(上部消化管内視鏡)が欠かせません。内視鏡を使って胃や十二指腸の内部を直接観察することで、微細な炎症や潰瘍の有無を確認できます。
ピロリ菌の感染検査も同時に行えるため、検査結果に応じた治療方針を立てやすくなります。

必要に応じた追加の検査
胃カメラの結果や症状によっては、CT検査やMRI検査など、より詳細な画像診断が必要になることもあり、特にがんの疑いがある場合には、組織の一部を採取して病理検査を行うケースもあります。
医師の判断に従い、適切な時期に追加検査を受けてください。
消化器内科で一般的に行う主な検査
| 検査方法 | 主な目的 | メリット |
|---|---|---|
| 血液検査 | 炎症反応、貧血、感染症(ピロリ菌)などの確認 | 全身状態を把握でき、初期評価に適している |
| 便検査 | 潜血、感染症の有無 | 消化管からの出血や感染を推定しやすい |
| 画像検査(X線等) | 消化器の形状や運動機能の確認 | 胃や腸の大まかな状態を把握 |
| 胃カメラ(内視鏡) | 胃や十二指腸を直接観察。組織採取も可能 | 小さな病変の発見と正確な診断が期待できる |
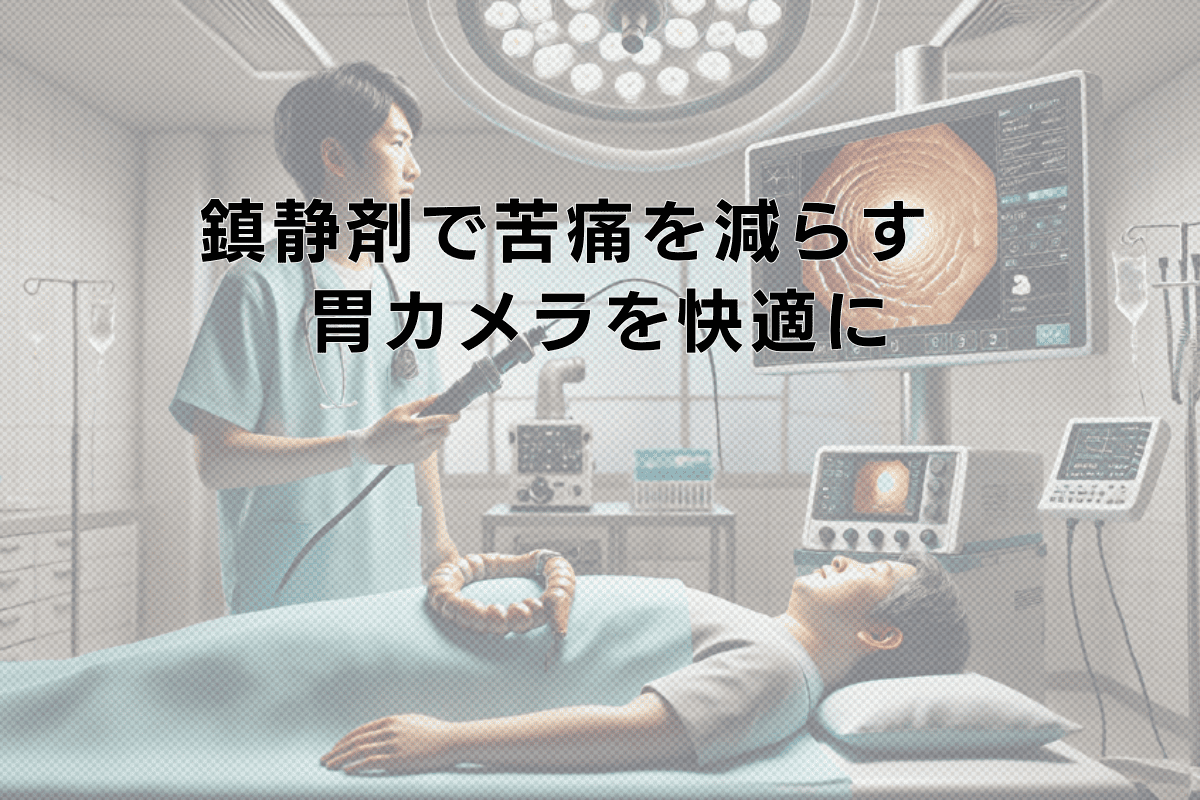
受診前の心がけ
- 痛みの頻度やタイミングをメモしておく
- 吐き気や嘔吐など、ほかの症状があるか確認する
- 食事内容や生活習慣のメモを持参する
- 飲んでいる薬やサプリメントがあればリストを作る

治療方法と日常のケア
治療法は原因となる病気や症状の度合いによって異なりますが、共通して胃の負担を減らす生活習慣の見直しがポイントになります。
薬によるアプローチ
病院で処方される薬には、主に胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)、胃酸を中和する薬(制酸剤)、そして胃粘膜を保護する薬があり、十二指腸潰瘍や胃潰瘍の場合は、薬剤を組み合わせて使用するケースが多いです。
ピロリ菌感染が確認された場合には、除菌治療を行うことも検討されます。

食事指導や生活改善
治療と同時に、医師や栄養士による食事指導を受ける場合があり、空腹時間を極力短くするよう食事回数を増やしたり、脂質やカフェインが多い食品を控えるなどのアドバイスが行われます。
また、ストレスを溜めすぎないように休息を取る、適度な運動を行うなど、ライフスタイル全体の見直しが必要になります。
ピロリ菌感染への対処
ピロリ菌が原因で慢性胃炎や潰瘍が進行している場合、除菌治療が重要です。2種類の抗生剤と、酸を抑える薬を一定期間飲むことで菌を排除し、再発リスクを下げます。
ただし、除菌後も生活習慣が乱れていると胃痛が再発する恐れがあるため、食事やストレス管理などのケアを続けることが必要です。
再発予防と定期的なチェック
治療によって症状が改善しても、体質や食習慣によっては再び胃痛がぶり返す可能性があるので、定期的に内視鏡検査を受け、胃や十二指腸の状態を確認するとともに、体調の変化を見逃さないようにしてください。
特に胃がんのリスクが高い方は、検査の頻度を医師と相談して決めることが大切です。
治療方法と期待される効果
| 治療アプローチ | 主な効果 |
|---|---|
| 制酸剤・胃酸分泌抑制薬の服用 | 胃酸を適度に抑え、粘膜への刺激を減らす |
| 胃粘膜保護薬の服用 | 粘膜に保護膜を作り、空腹時の痛みを軽減 |
| ピロリ菌除菌療法 | 慢性胃炎や潰瘍の再発リスクを低減 |
| 食事・生活習慣の改善 | 胃酸分泌を安定させ、ストレスを軽減する |
| 定期的な内視鏡検査(胃カメラ) | 新たな病変の早期発見や再発確認 |
再発防止につなげる生活習慣
- 治療後もアルコールや刺激物の摂取量に注意する
- 就寝前に食べる習慣を見直して、胃に余計な負担をかけない
- ストレスが溜まる前にこまめにリラックス方法を実践する
- 定期的に医療機関で検査を受け、早期に異常を見つける
まとめと今後の生活で気をつけること
空腹時の胃痛は、日常生活の些細な要因から胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの重篤な病気まで幅広い原因で起こるため、原因を早めに突き止め対処することが重要です。
空腹時胃痛への理解を深める
まずは、空腹時の胃痛がどのように生じるのかを理解すると、自分の体の反応に目を向けるきっかけになり、胃酸の過剰分泌やストレスによる粘膜保護の低下などの仕組みを知ることで、早い段階から改善策を講じられます。
慢性的な痛みへの対応と心構え
胃痛が慢性的に続く場合は、病気の可能性を考慮し、自己流のケアではなく専門家の意見を取り入れることが大切です。
内視鏡検査などで原因がはっきりすれば、安心して効果的な治療を受けられますし、早期発見・早期治療による合併症リスクの軽減にもつながります。
セルフケアと専門的な治療の連携
生活習慣の改善や薬によるケアはどちらか一方だけでなく、両方をうまく組み合わせることでより良い結果が期待できます。
食事の選び方やストレス発散方法など、セルフケアで解決できる部分と、医師による専門的な治療が必要な部分をしっかり切り分け、両者を並行して進めることが長期的な健康維持のコツです。
継続的な観察と早期対策の重要性
一度症状が治まっても、再発する可能性はゼロではありません。定期的に医療機関で検査を受ける、あるいは日々の体調を観察して違和感があれば早めに受診するなど、こまめな対応が何よりも重要です。
空腹時の胃痛は、体からのSOSサインともいえますので、うまく付き合いながら健康的な生活を維持してください。
胃痛の症状と早期対策のまとめ
| 症状の種類 | 対策のポイント |
|---|---|
| 空腹時に強いキリキリした痛み | 胃酸分泌抑制薬の使用、こまめな食事の導入 |
| 食後に胸やけが続く | 逆流性食道炎を疑い、生活習慣の再検討 |
| 長期間にわたるしつこい痛み | 内視鏡検査で原因を特定、ピロリ菌除菌なども検討 |
| 吐血や激しい腹痛を伴う | 至急受診して検査を行い、状態を把握する |
空腹時の胃痛を放置せず、必要に応じて消化器内科を受診し、正確な検査と診断を受けながら、日常生活の改善策を続けることが大切です。
病気が潜んでいる場合でも、早期に発見し早期に治療に入れば、回復や症状改善の可能性は大いに高まります。
自分の体に合った食事やストレス管理法を見つけ、胃腸をいたわりながら健やかな毎日を過ごしてください。
次に読むことをお勧めする記事
【胃カメラで分かる症状 検査の流れ】
空腹時の胃痛について理解が深まったら、実際の胃カメラ検査がどのようなものか気になりませんか?具体的な検査の流れや準備方法を詳しく説明しています。
【胃痛原因と予防のポイント 食事・ストレスとの関係を見直す】
空腹時の胃痛を学んだ皆さんには、予防するための知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
参考文献
Liu Z. Stomachache. Essentials of Chinese Medicine: Essentials of Clinical Specialties in Chinese Medicine. 2009:85-94.
Ye Y, Xu L, Sheng Y. Effects of TCM external scalding therapy on spleen-stomach deficiency cold stomachache and inflammatory indexes. American Journal of Translational Research. 2024;16(5):1769.
Madaminov M. STOMACH PAIN CAUSES, EXAMINATIONS, TREATMENT, RELIEF METHODS. Science and innovation. 2022;1(D7):441-5.
Williams GF. How to Treat a Stomachache (Perspective on the Word Logos). Perspective Digest. 1996;1(3):6.
WANG RX, Zhou Y, Yuan H, QI XL. Symptoms Reduction Using Rough Sets Based Traditional Chinese Medicine Stomachache Diagnosis. InProceedings of the Annual Conference of Biomedical Fuzzy Systems Association 28 2015 Nov 21 (pp. 351-354). Biomedical Fuzzy Systems Association.
Mrouf A, Albatish I, Mosa MJ, Abu-Naser SS. Knowledge Based System for Long-term Abdominal Pain (Stomach Pain) Diagnosis and Treatment.
Kristjánsdóttir G. Prevalence of pain combinations and overall pain: a study of headache, stomach pain and back pain among school-children. Scandinavian journal of social medicine. 1997 Mar;25(1):58-63.
Drewes AM, Arendt-Nielsen L, Jensen JH, Hansen JB, Krarup HB, Tage-Jensen U. Experimental pain in the stomach: a model based on electrical stimulation guided by gastroscopy. Gut. 1997 Dec 1;41(6):753-7.
Rabbets W. Stomach aches and pains. Professional Nursing Today. 2024 Jan 1;28(1):24-5.
Egger HL, Costello EJ, Erkanli A, Angold A. Somatic complaints and psychopathology in children and adolescents: stomach aches, musculoskeletal pains, and headaches. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1999 Jul 1;38(7):852-60.