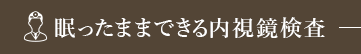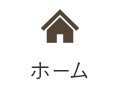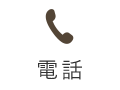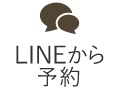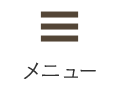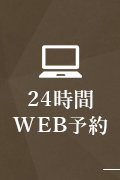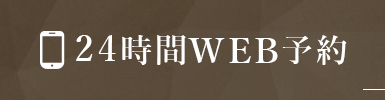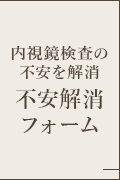健康診断でコレステロール値や中性脂肪が高いと指摘されて、不安を感じていらっしゃいませんか。「このまま放っておいて大丈夫だろうか」「薬を飲まなければいけないのだろうか」と気になっている方も多いと思います。
高脂血症(脂質異常症)は、血液中の脂質バランスが乱れている状態で、放置すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気につながる可能性があります。しかし、早い段階で適切な対応を始めれば、食事療法や運動療法といった生活習慣の改善で十分にコントロールできることも多いのです。
この記事では、高脂血症のリスクから具体的な食事療法・運動療法まで、エビデンスに基づいた情報を分かりやすくお伝えします。金沢駅前にある当院では、管理栄養士が常駐し、お一人おひとりに合わせた食事指導を行っていますので、安心してご相談ください。
この記事のポイント
- 高脂血症は動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めます
- 食事療法では、飽和脂肪酸を減らし、食物繊維を積極的に摂ることが重要です
- 週に150分以上の有酸素運動が、脂質改善に効果的です
- 当院では管理栄養士が常駐し、個別の食事指導を行っています
目次
高脂血症(脂質異常症)とは
高脂血症は、血液中の脂質濃度が基準値から外れている状態を指します。2007年に日本動脈硬化学会が診断基準を見直してから、正式には「脂質異常症」と呼ばれるようになりましたが、高脂血症という名称も広く使われています。
脂質異常症の診断は、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、中性脂肪(トリグリセライド)の3つの数値によって行われます。これらの脂質バランスが乱れると、血管の壁に脂質が沈着し、動脈硬化を引き起こす原因となるのです。
脂質異常症の診断基準
日本動脈硬化学会が定める診断基準では、以下のいずれかに該当する場合に脂質異常症と診断されます。
- LDLコレステロール:140mg/dL以上(高LDLコレステロール血症)
- HDLコレステロール:40mg/dL未満(低HDLコレステロール血症)
- 中性脂肪:空腹時150mg/dL以上、または随時175mg/dL以上(高トリグリセライド血症)
- non-HDLコレステロール:170mg/dL以上
これらの数値は、10時間以上の絶食後に測定した空腹時の値を基本としています。ただし、中性脂肪については、2022年版のガイドラインで随時(非空腹時)の基準値も新たに設定されました。
原発性と続発性の脂質異常症
脂質異常症には、遺伝的要因や生活習慣が主な原因となる「原発性脂質異常症」と、他の疾患(糖尿病、甲状腺機能低下症、腎疾患など)や薬物使用に起因する「続発性脂質異常症」があります。続発性の場合は、基礎疾患の治療も並行して行う必要があります。
高脂血症を放置する3つのリスク
高脂血症そのものには、ほとんど自覚症状がありません。そのため「数値が少し高いだけ」と軽く考えてしまいがちですが、実は静かに進行する危険な状態なのです。放置することで起こりうる主なリスクを3つご説明します。
1. 動脈硬化の進行
血液中のLDLコレステロールが増えすぎると、血管の壁に入り込んで酸化し、動脈硬化を引き起こします。動脈硬化とは、血管が硬く狭くなり、弾力性を失った状態です。この状態が続くと、血液の流れが悪くなり、血管が詰まりやすくなります。
動脈硬化は全身の血管で起こる可能性があり、どの血管で進行するかによって、引き起こされる病気も異なります。心臓の血管で起これば心筋梗塞、脳の血管で起これば脳梗塞、足の血管で起これば閉塞性動脈硬化症といった具合です。
2. 心筋梗塞・狭心症のリスク上昇
心臓に血液を送る冠動脈に動脈硬化が起こると、狭心症や心筋梗塞を発症するリスクが高まります。心筋梗塞は、冠動脈が完全に詰まってしまい、心臓の筋肉に血液が届かなくなる状態で、命に関わる重大な病気です。
LDLコレステロールが高いほど、将来的に冠動脈疾患を発症するリスクが上昇することは、多くの研究で証明されています。特に、糖尿病や高血圧、喫煙などの他のリスク因子がある場合は、さらに注意が必要です。
3. 脳梗塞のリスク上昇
脳の血管に動脈硬化が起こると、脳梗塞のリスクが高まります。特にアテローム血栓性脳梗塞という種類の脳梗塞は、動脈硬化が主な原因となって発症します。
2022年版の動脈硬化性疾患予防ガイドラインでは、脂質管理目標値の設定において、冠動脈疾患だけでなくアテローム血栓性脳梗塞も含めた「動脈硬化性疾患」全体のリスク評価が採用されました。これは、脳梗塞予防においても脂質管理が極めて重要であることを示しています。
高脂血症の食事療法|具体的な実践方法
高脂血症の治療において、食事療法は最も基本的で重要な取り組みです。薬物療法が必要な場合でも、食事療法は並行して続ける必要があります。ここでは、エビデンスに基づいた具体的な食事療法の方法をご紹介します。
適正体重の維持とエネルギー調整
まず大切なのは、適正体重を維持することです。肥満がある場合は、体に溜まった余分な脂肪を減らすことが、脂質改善の第一歩となります。
適正体重の目安は、「身長(m)×身長(m)×BMI目標値」で計算できます。BMI目標値は年齢によって異なり、18~49歳では18.5~24.9、50~64歳では20.0~24.9、65歳以上では21.5~24.9が推奨されています。
1日に必要なエネルギー量は、標準体重に25~30kcalを掛けた値が目安となります。例えば、身長165cmで標準体重が約60kgの方なら、1日1,500~1,800kcal程度が適切です。ただし、活動量や体格によって個人差がありますので、詳しくは医師や管理栄養士にご相談ください。
飽和脂肪酸を減らし不飽和脂肪酸を増やす
LDLコレステロールを下げるために最も効果的なのが、飽和脂肪酸の摂取を減らし、不飽和脂肪酸に置き換えることです。
飽和脂肪酸は、バター、ラード、牛脂、パーム油などの動物性脂肪や一部の植物油に多く含まれており、LDLコレステロールを上昇させます。一方、オリーブオイルに含まれる一価不飽和脂肪酸(MUFA)や、魚油・えごま油に含まれる多価不飽和脂肪酸(PUFA)は、LDLコレステロールを下げる働きがあります。
具体的には以下のような工夫が有効です。
- 肉類は脂身の少ない部位を選び、皮は取り除く
- 調理油はオリーブオイルやキャノーラ油を使用する
- 週に2回以上、魚(特に青魚)を食べる
- バターやマーガリンの使用を控える
- 洋菓子や菓子パンなどの加工食品を減らす
食物繊維を積極的に摂取する
食物繊維は、LDLコレステロールを下げる効果が認められています。2022年版のガイドラインでは、食物繊維の摂取推奨量が1日25g以上に設定されました。
食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、どちらもコレステロール改善に役立ちますが、特に水溶性食物繊維は腸内でコレステロールの吸収を抑える働きがあります。
食物繊維が豊富な食品には以下のようなものがあります。
- 野菜類:ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草、にんじん
- 海藻類:わかめ、昆布、ひじき、もずく
- きのこ類:しいたけ、えのき、しめじ
- 豆類:大豆、納豆、枝豆
- 穀物:玄米、大麦、オートミール
- 果物:りんご、みかん、バナナ(ただし適量に)
果糖を含む加工食品を減らす
中性脂肪が高い方は、特に砂糖や果糖を含む加工食品の摂取を控えることが重要です。清涼飲料水、菓子類、果糖ぶどう糖液糖を含む加工食品は、中性脂肪を上昇させる原因となります。
果物自体は食物繊維やビタミンが豊富で健康的な食品ですが、食べ過ぎは果糖の過剰摂取につながりますので、1日200g程度(みかん2個分、りんご1個分など)を目安にしましょう。
塩分を控え、和食を取り入れる
高脂血症の方の多くは、高血圧も併発しています。塩分の過剰摂取は血圧上昇を招き、動脈硬化性疾患のリスクを高めますので、1日6g未満を目標に減塩を心がけましょう。
米、大豆製品、魚、野菜、海藻、きのこを中心とした和食は、血中脂質を改善し、動脈硬化性疾患の予防に効果的です。さらに低脂肪乳製品を毎日摂取する食生活は、脂質異常症の改善に理想的とされています。
アルコール摂取量の管理
2022年版のガイドラインでは、生活習慣改善の項目に「飲酒」が新たに追加されました。多量飲酒は動脈硬化性疾患の危険因子であり、特に中性脂肪を上昇させます。
アルコールの摂取量は、1日あたり25g以下(日本酒なら1合、ビールなら500ml、ワインならグラス2杯程度)にとどめることが推奨されています。また、週に2日程度の休肝日を設けることも大切です。
高脂血症の運動療法|効果的な取り組み方
運動療法は、食事療法と並んで高脂血症治療の柱となります。適度な運動は、中性脂肪を下げ、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を上げる効果があります。また、体重減少や血圧低下にもつながり、総合的な心血管リスクの改善が期待できます。
有酸素運動が基本
高脂血症の改善には、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動が最も効果的です。中強度以上の有酸素運動を定期的に行うことが推奨されており、具体的には以下のような目標が示されています。
- 週に150分以上の中強度の運動(1日30分×5日以上)
- または週に75分以上の高強度の運動
- できれば毎日、少なくとも週5日以上実施する
中強度の運動とは、「ややきつい」と感じる程度の運動で、会話ができるくらいの速さで歩いたり、軽いジョギングをしたりする程度です。心拍数でいえば、最大心拍数(220-年齢)の50~70%程度が目安となります。
無理なく続けられる運動を選ぶ
運動療法で最も大切なのは、継続することです。いきなり激しい運動を始めても、体に負担がかかり長続きしません。まずは、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めましょう。
- エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う
- 一駅分歩く、または遠回りして歩く
- 家事や庭仕事を積極的に行う
- 休日に散歩や軽いハイキングを楽しむ
運動習慣がない方は、まず1日10分のウォーキングから始めて、徐々に時間を延ばしていくのが良いでしょう。10分の運動を3回に分けて行っても効果は期待できます。
筋力トレーニングも組み合わせる
有酸素運動に加えて、週に2~3回の筋力トレーニングを組み合わせると、より効果的です。筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、体重管理がしやすくなります。
自宅でできる簡単な筋力トレーニングとしては、スクワット、腕立て伏せ(膝をついた状態でも可)、腹筋運動などがあります。無理のない範囲で、10~15回を2~3セット行うことから始めましょう。
運動時の注意点
運動療法を始める前に、特に以下のような方は必ず医師に相談してください。
- 心臓病や不整脈がある方
- 高血圧が十分にコントロールされていない方
- 糖尿病で合併症がある方
- 関節や腰に痛みがある方
- 運動中に胸痛や息切れがひどくなる方
また、運動中は水分補給を忘れずに行い、体調が悪いときは無理をしないことが大切です。
金沢駅前院での高脂血症治療
金沢駅前にある当院では、高脂血症の治療に力を入れており、患者さま一人ひとりに寄り添った丁寧な診療を心がけています。特に、管理栄養士が常駐している点が当院の大きな特徴です。
管理栄養士による個別栄養指導
高脂血症の改善には、食事療法が欠かせません。しかし、「何をどう食べればいいのか分からない」「外食が多くて難しい」といったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
当院では、管理栄養士が常駐しており、お一人おひとりのライフスタイルや食習慣に合わせた、実践的な栄養指導を行っています。ご家族の食事と別に作るのではなく、家族みんなで健康的な食事を楽しめるようなアドバイスも得意としています。
栄養指導では以下のようなサポートを行っています。
- 現在の食生活の詳しい聞き取りと問題点の洗い出し
- 具体的な献立例や調理方法のご提案
- 外食時の選び方、コンビニ食の活用法
- 無理なく続けられる食事改善のステップ作り
- 定期的なフォローアップと進捗確認
総合的な生活習慣改善のサポート
当院では、食事療法だけでなく、運動療法や禁煙支援など、総合的な生活習慣改善をサポートしています。医師、看護師、管理栄養士がチームとなって、患者さまの健康づくりをお手伝いします。
また、定期的な血液検査で脂質の数値を確認し、食事療法や運動療法の効果を評価します。生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合は、薬物療法も検討しますが、その際も生活習慣改善は継続して行います。
金沢駅前で通いやすい立地
当院は金沢駅から徒歩圏内にあり、お仕事帰りやお買い物のついでにも通いやすい立地です。予約制ですので、待ち時間も少なく、忙しい方でも無理なく通院を続けていただけます。
高脂血症は、長期的な管理が必要な病気です。だからこそ、通いやすく、相談しやすいクリニックであることが大切だと考えています。
よくあるご質問
Q1. コレステロール値が少し高いだけですが、治療は必要ですか?
A. コレステロール値が基準値を少し超えているだけでも、他のリスク因子(糖尿病、高血圧、喫煙、家族歴など)がある場合は、早めに治療を始めることが推奨されます。逆に、他のリスク因子がなく、数値も軽度の上昇であれば、まずは生活習慣の改善から始めることができます。ご自身の状態に応じた判断が必要ですので、ぜひ一度ご相談ください。
Q2. 食事療法だけでどのくらい数値は下がりますか?
A. 個人差がありますが、適切な食事療法を3~6ヶ月続けることで、LDLコレステロールは10~15%程度低下することが期待できます。特に、飽和脂肪酸を減らし不飽和脂肪酸に置き換えることや、食物繊維を十分に摂取することが効果的です。当院の管理栄養士が、具体的な目標設定と実践方法をご提案いたします。
Q3. 卵はコレステロールが高いので食べない方がいいですか?
A. 以前は卵の摂取が制限されていましたが、現在の研究では、健康な方が1日1個程度の卵を食べても血中コレステロール値への影響は限定的とされています。むしろ、バターやラードなどの飽和脂肪酸を多く含む食品の方が、血中コレステロールを上げやすいことが分かっています。卵は良質なたんぱく質源ですので、極端に避ける必要はありませんが、バランスよく食べることが大切です。
Q4. 運動はどのくらいの期間続ければ効果が出ますか?
A. 運動療法の効果は、早ければ2~3ヶ月で現れ始めます。特に中性脂肪やHDLコレステロールは、比較的早く改善が見られることが多いです。ただし、継続することが何より重要で、運動をやめてしまうと数値は元に戻ってしまいます。無理のない範囲で、生活の一部として運動習慣を定着させることを目指しましょう。
Q5. 薬を飲み始めたら一生飲み続けなければいけませんか?
A. 必ずしもそうとは限りません。薬物療法を開始した後も、食事療法や運動療法を継続することで、数値が改善し、薬の量を減らしたり、場合によっては中止できたりすることもあります。ただし、家族性高コレステロール血症など遺伝的な要因が強い場合は、長期的な薬物療法が必要になることが多いです。いずれにしても、医師と相談しながら治療方針を決めていきます。
次に読むことをおすすめする記事
脂肪肝に要注意 肥満・飲酒を見直して肝臓をいたわりましょう
高脂血症と脂肪肝は密接に関連しています。特に糖尿病や脂質異常症を合併している方は、脂肪肝から肝硬変や肝がんへ進行するリスクが高まります。この記事では、脂肪肝の原因から予防・改善方法まで、詳しく解説しています。生活習慣の見直しを総合的に進めたい方におすすめです。
脂肪肝改善を目指す 食事と運動で体重管理
脂肪肝と高脂血症は、どちらも生活習慣の改善で大きく改善できる疾患です。この記事では、具体的な食事療法と運動療法のポイントを分かりやすく解説しています。体重管理に悩んでいる方や、より詳しい実践方法を知りたい方にぜひお読みいただきたい内容です。
参考文献
著者・監修者情報
中村 文保|医療法人社団心匡会 理事長
総合内科専門医/消化器内視鏡専門医/消化器病専門医/肝臓専門医。内視鏡を核に苦痛の少ない検査と分かりやすい診療を実践、金沢駅前で地域医療に注力。
公開日:2025-10-30 / 最終更新日:2025-10-30